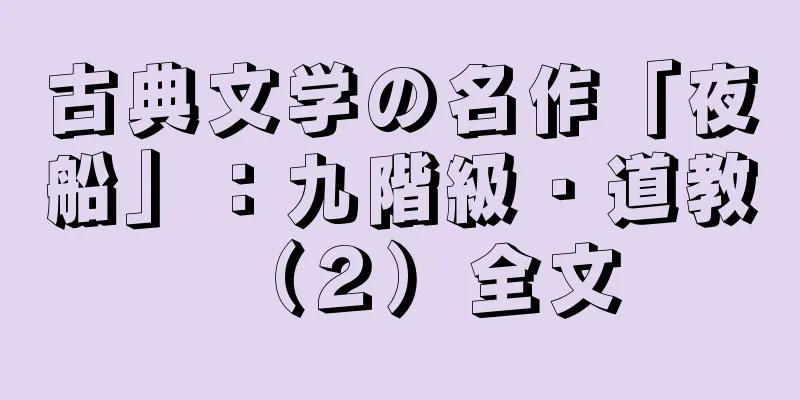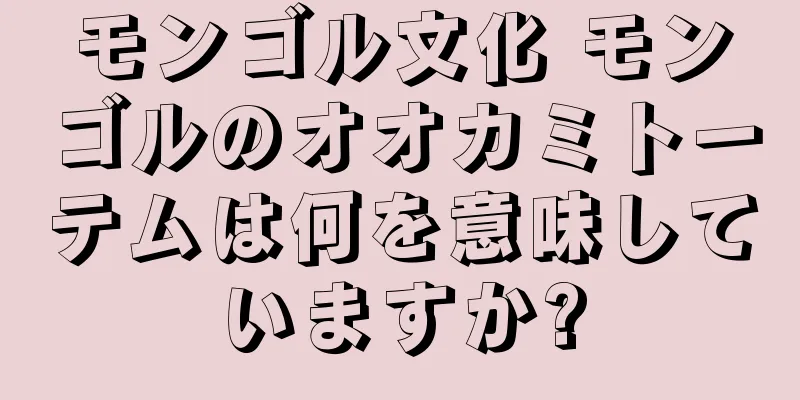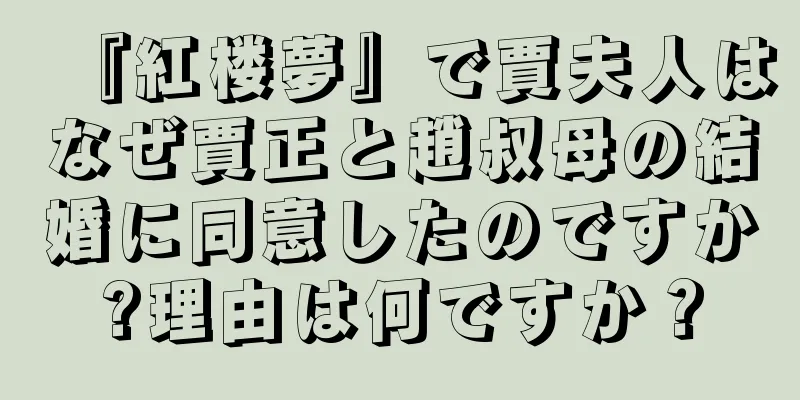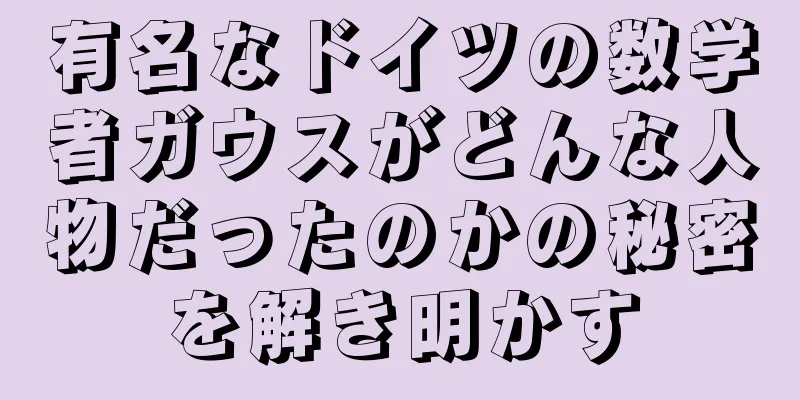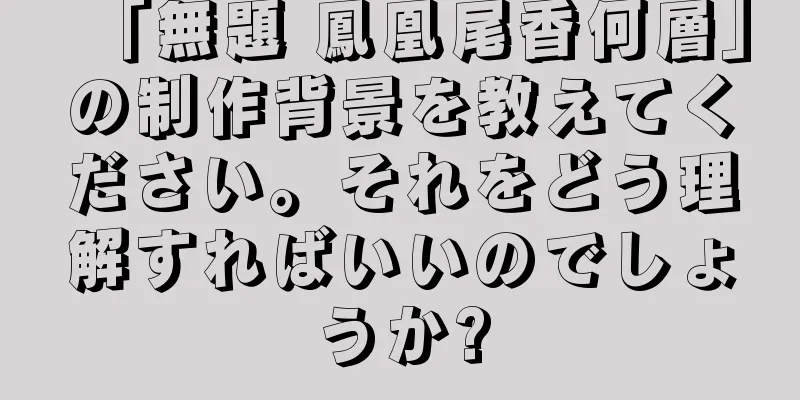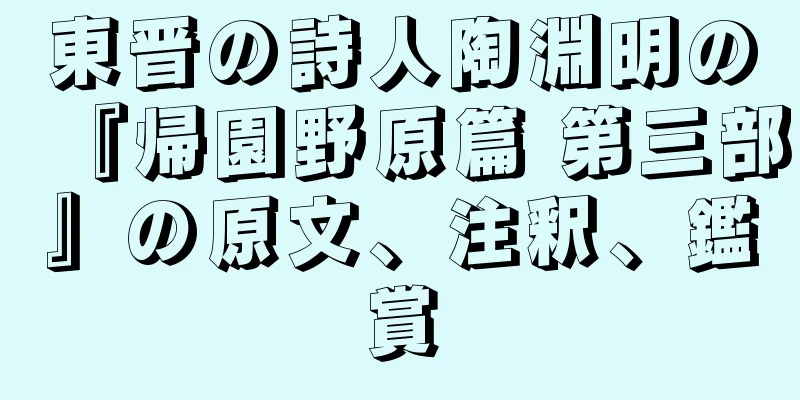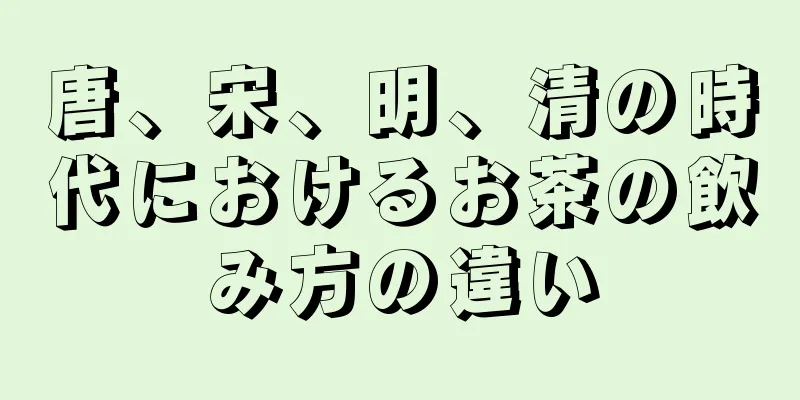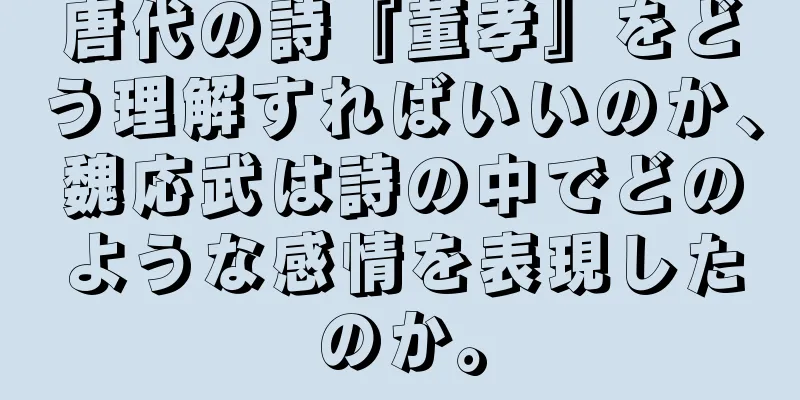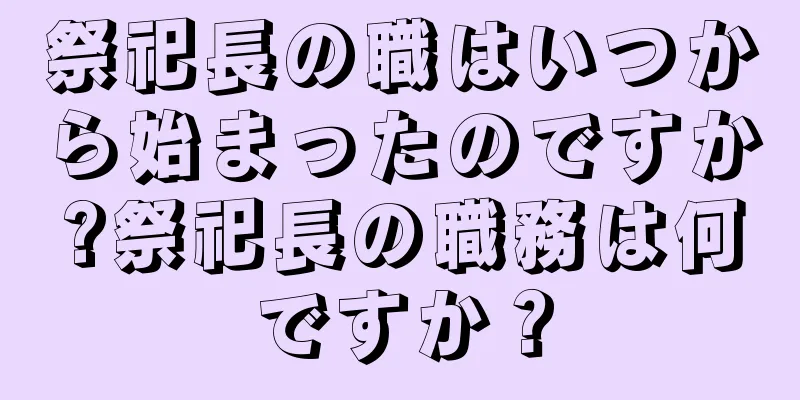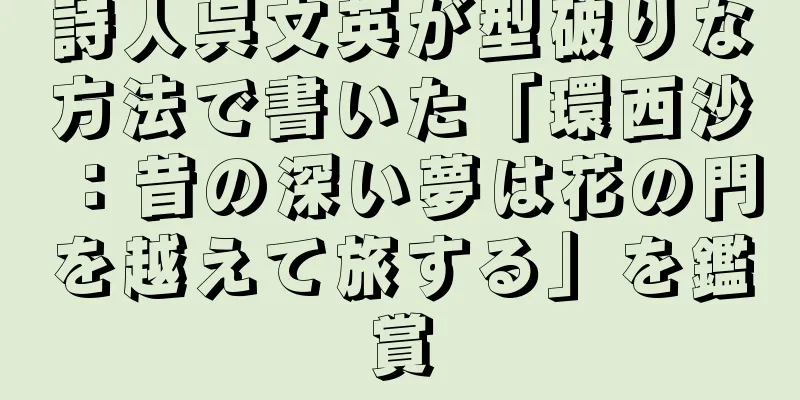「Li Sao」とはどういう意味ですか?屈原はなぜ『李索』を書いたのでしょうか?
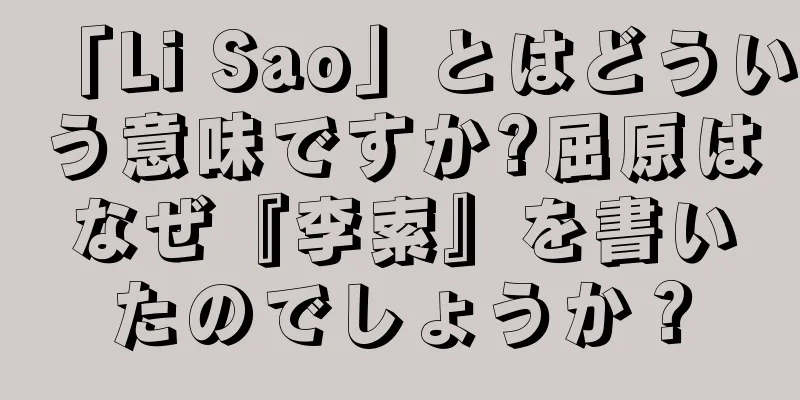
|
『李闕』は『楚辞』の重鎮として、多くの人に衝撃を与えました。『李闕』の意味については意見が大きく分かれています。記事のタイトルは記事の要点と言えます。記事のタイトルの意味を研究する必要があります。それでは、『李闕』の意味についてお話ししましょう。 まず、『李鈞』は戦国時代に書かれたもので、作者は屈原である。『李鈞』の作者はかつて論争を呼び、「屈原否定論」が起こり、淮南王劉安が書いたとされた。もし『李鈞』の作者が屈原でなければ、『李鈞』という題名の持つ意味も変わってくる。しかし、1977年、安徽省阜陽市双谷台漢代一号墓から一組の古書の竹簡が出土し、その中に楚辞の作品の中に『李鈞』の4字と『社江』の5字が含まれていた。この状況は、『楚辞』が西漢初期には完成し、社会に普及していたはずであったことを示している。漢の武帝が劉安にその伝記を書くよう命じるずっと前から、『李鈞』はすでに存在し、広く流布していた。したがって、「李鈞」の作者が屈原であることは正しい。このようにして、作者自身、作者の経験、作者が生きた時代から、「李鈞」の意味をより簡単に理解することができます。 第二に、「李去」は戦国時代の作品です。「李去」の意味に関する最も古い説明は、司馬遷の『史記』の「屈原・賈義伝」にあります。「李去とは悲しみを残すという意味です。」この時代には、体系的な解釈書や偉大な学者はいませんでした。一部の文人や歴史家は、執筆の必要性に応じて、無意識のうちに文章の中で言葉の意味を説明していました。司馬遷の説明が出るとすぐに、後世の人々は興味を持ち、新しい解釈をしたいと考えました。しかし、司馬遷は「李」の意味を説明せず、「去」の意味のみを説明しました。したがって、後世の人たちによる「李匡」という二つの単語の解釈の主な違いは、「李」という単語にあります。 司馬遷より少し後に生きたもう一人の偉大な歴史家、班固は著書『礼察讃』の中でこう述べている。「礼とは苦しむこと、察とは悲しみを意味する。彼が悲しみを味わったからこそこの詩を書いたことは明らかだ」。ここで班固は「礼」を「苦しむ」という意味に解釈しており、これは基本的に司馬遷の意味と同じである。その後、王毅は著書『楚辞章集』の中で、この二つの言葉の意味を力強く解説した。「離とは別れ、悲しみとは悲しみ」。ここまで、「離」の偉大な解釈者として司馬遷、班固、王毅の3人を挙げてきたが、ここから班固の「悲しみ」の解釈は司馬遷の「悲しみ」と同じであり、王毅の観点は司馬遷や班固の解釈とは異なることがわかる。つまり、王毅の新しい解釈は彼自身のものだ。王毅の新しい解釈が発表されて以来、さまざまな学者が独自の考えを出し、先人たちが表現できなかった考えを表現し始めた。考えてみれば、清代の蒋済はこう言っています。「楚辞を論じる人は、かつては学者が72人いると言っていたが、顧語堂はさらに14人いると付け加えた。」『李鈞』は『楚辞』の中で最も重要な章であるため、後代の学者たちは「李鈞」という2つの単語が何を意味するのかに非常に興味を持っていました。中国屈原学会副会長の周建中氏のような現代の学者の中には、研究論文「『李鈞』の題名とその意味の解釈に関する分類と考察」の中で27の解釈をまとめた人もいます。27の解釈があることは、各解釈に複数の代表者がいることを意味しています。したがって、「李鈞」の題名が引き起こした論争がいかに大きいかがわかります。 それでは、いくつかの観点を例に挙げて議論してみましょう。まず、前世紀の偉大な楚辞学者である于国恩氏は、彼の有名な著書『楚辞入門』で130冊以上の本を引用し、それらを3つの主要なタイプにまとめましたが、最終的に彼は独自の新しい解釈「宋論」を提唱しました。その本には、「『老商』と『里察』はもともと二重音の単語です。古代の発音は、シャオ、ゲ、ヤン、ヨウで、他の2つは赤です。『老商』は『里察』の音訳であると思われます。同じものですが、名前が異なります。『楚辞』のタイトルは、主に『九歌』や『九編』などの古代の音楽歌に基づいています。したがって、『里察』にも、邵中の『楊阿』、『延禄』、『陽春』、『百雪』、後期の岳府の『旗欧』などの独自の音楽がある可能性があります( 「大昭」の作者は次第に屈原の時代から離れ、音も次第に変化した。王毅は「老商」が「李索」であり、これもまた宮廷の古歌であることを知らなかったので、別の歌名だと思っていたが、実は同じものだった。この見解は発表されるとすぐに騒動を引き起こし、さまざまな学者が疑問を投げかけた。馬茂元氏は「楚辞選」の中で、「その名前には二重の意味がある。音楽の観点から言えば、「李索」は楚で流行していた歌の名前かもしれない」と述べている。彼は游国恩を引用している。「『楚辞大昭』には「伏羲家編、楚老商志」という文章がある。王毅の注釈には「家編、老商はすべて歌名である。「老商」と「李索曦」は二重音語、または同じものだが異なる名前である」とある。 幽果恩と馬茂源の音楽理論は根拠のないものではなく、音声と韻の観点からの視点を提供しており、注目に値する。第二に、中国の研究の偉大な学者であるQian Zhongsuの見解があります。彼は「Guan Zhui Pian」で彼自身の意見を提出しました。ハート・スートラは「逆さまの夢から離れてください」と言います。または、ザ・トーアストは、「33日以上の「西への5番目の章」(西への5番目の章)に居住していると言います。 Uの見解では、「Li Sao」の意味は、「悲しみを取り除き、悲しみに別れを告げることです」。 上に挙げた幽国恩と銭仲書の見解はいずれも専門家の意見であり、それが正しいか間違っているかは、現代の学者である尹翔が論文「『里察』は『老商』と同じか?」で説明している。 「『里索』の題名の解説について」という記事では、魏炯若氏の「通用する意味は説明不要」という見解を引用し、「里」の通用する意味について探究している。記事では、『詩経』の「里」は「苦しむ」という意味であるという見解を引用して銭仲書の見解を反駁し、同古音、語形成法、屈原の創作命題、古代文化の発展など4つの観点から、游国恩の「里索」は「手間がかかる」という見解を反駁している。ここまで述べてきましたが、まとめると、「李嗣」という言葉の意味について私なりの意見があります。まず、「李嗣」が戦国時代の楚の時代には2音節の言葉であったと信じるならば、幽国恩と馬茂源の「歌説」は注目に値します。 第二に。当時の「李劫」は二音節語ではなく、単音節語だったと考えるなら、それぞれを解釈すべきです。この解釈は最も意見の相違を招きます。その中でも「李」という語は最も議論を呼んでいます。後世の人々は「劫」についてさまざまな解釈をし始めました。私は淮南王劉安に基づく司馬遷の解釈が最も信頼できると思うので、司馬遷の「劫」の解釈を採用すべきです。「李」という語については、班固の「周」の解釈に賛成です。時代やテキストの内容や意味に関係なく、「李劫」が単音節語であるならば、「周有」が最良の説明だと思います。屈原の長大な政治的叙情詩とその題名「李索」は、歴史の歳月による沈殿と洗礼を経て、次第に象徴的存在となった。屈原は死とともに、文人の独立した個性への激しい執着という精神の誕生を宣言し、流れに身を任せ、群衆に同調する者たちを激しく攻撃した。タイトルを理解する理由は、当時の屈原の心境をさらに理解し、祖国に奉仕する術もなく、死ぬまで粘り強く生き抜いた文人の揺るぎない執念を評価するためだけです。これらを理解した後、「李孟」という2つの文字をもう一度見つめると、より深い理解が得られ、それが内なる動機となり、人生の選択において次の重要な一歩を踏み出すのに役立つと私は信じています。 |
<<: 吉夏アカデミーとは何ですか?薊下書院はどの国に最初に建てられましたか?
>>: 清朝の皇帝は関に入った後、どのように亡くなったのでしょうか?清朝皇帝の死因
推薦する
もし賈靖が毎日仙人を修行することに夢中になっていなかったら、秦克清の運命はどうなっていたでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つです。普及版は全部で120章か...
「Shi Ziyou」が誕生した背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
ショー・ジユ陸游(宋代)私が初めて詩を学んだとき、私はただ文章を書くことと絵を描くことに秀でたいと思...
唐王朝はどのようにして分離独立政権の状況に陥ったのでしょうか?安史の乱は何年続きましたか?
安史の乱は中国史上重要な出来事であり、唐王朝衰退の転換点となった。安は安禄山、史は史思明を指します。...
秦瓊は非常に強力であるという印象を人々に与えていますが、なぜ霊岩閣では最下位にランクされているのでしょうか?
古代では、多くの皇帝が功績のあった官僚をランク付けしていました。このようにしてのみ、功績のあった官僚...
『西江月:息子姉妹に家庭の事を任せるように教える』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
西江月:息子に家事を任せるように言う新奇集(宋代)すべてのものははかないものであり、葦や柳のように枯...
紫禁城には井戸がいくつありますか?紫禁城の井戸は何に使われていますか?
故宮には井戸がいくつあるのでしょうか? 故宮の井戸は何に使われているのでしょうか? 一緒に学んで参考...
李白の古詩「金陵三号」の本来の意味を鑑賞
古詩「金陵第3号」時代: 唐代著者: 李白六つの王朝の興亡。ワインを3杯お出しします。元芳と秦には土...
王希峰の「一人は服従、二人は命令、三人は木偶の坊」という判決の深い意味は何でしょうか?
『紅楼夢』第五章で、賈宝玉が太虚の幻界で金陵十二美女の「生涯帳」を見ているとき、王希峰を暗示する「氷...
欧陽秀の「草踏図」:春分の日の美しい風景が紙の上に鮮やかに描かれている
欧陽秀(おうようしゅう、1007年8月1日 - 1072年9月22日)、字は永叔、晩年は随翁、劉義居...
太平広記・巻73・道教・世民をどのように翻訳しますか?原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
『晋史記』第31巻第一伝原文の鑑賞
◎皇后と妾(前編)張玄穆皇后 夏侯景淮皇后 楊景賢皇后 王文明皇后 楊武元皇后 楊武道皇后(諸葛左貴...
西の海第87章:宝船が鳳都王国に墜落し、王明は前世の妻と出会う
『西遊記』は、正式名称を『三宝西遊記』といい、『三宝西遊記』、『三宝西遊記』とも呼ばれ、明代の羅茂登...
「大混乱のあと村の老人と出会う」が生まれた背景とは?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
混乱の後で村の老人と出会う杜荀和(唐代)混乱の後、老人は廃墟となった村に住んでいます。村のすべてが悲...
『紅楼夢』では、薛宝才は本当に賈宝玉が好きなのか、それとも利用しているのか?
ご存知のとおり、「紅楼夢」の金婚は詐欺です。薛宝才は本当に賈宝玉に恋をしたのでしょうか、それともただ...
皇帝の物語:宋の徽宗趙徽はどのようにして皇帝になったのでしょうか?
中国の歴史では、秦の始皇帝が皇帝制度を創設し、「始皇帝」として知られる最初の皇帝となった。それ以来、...