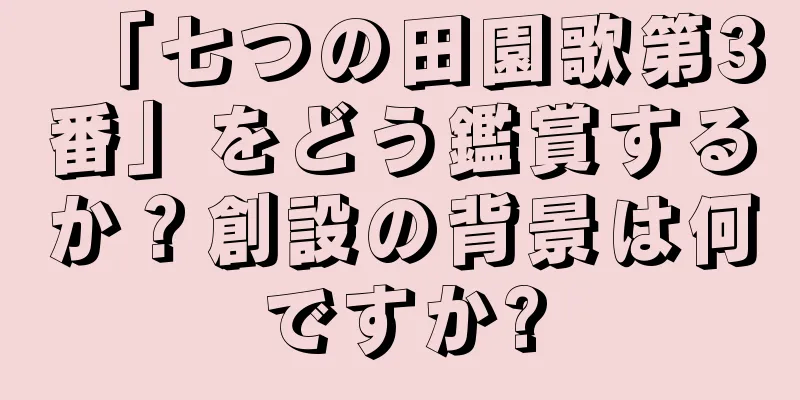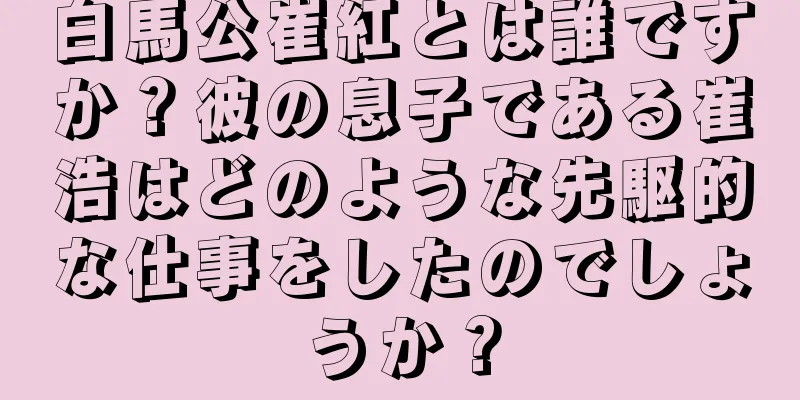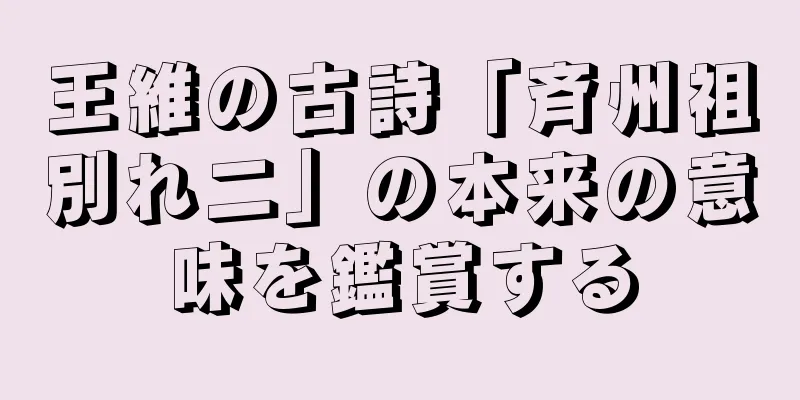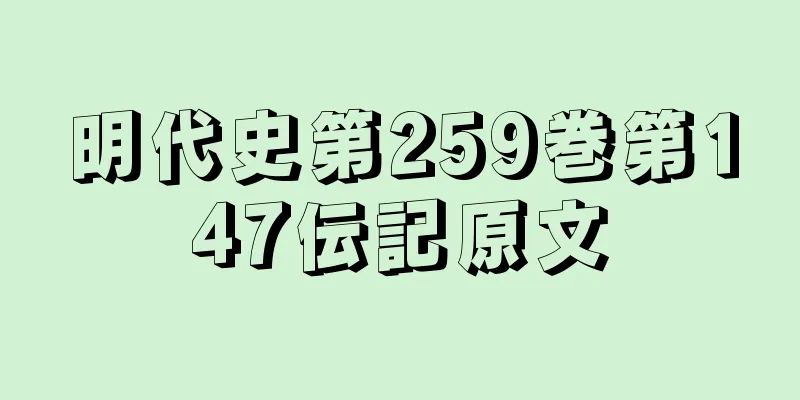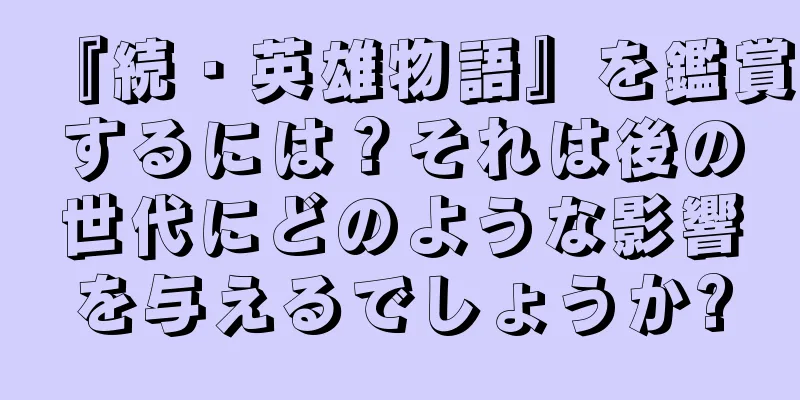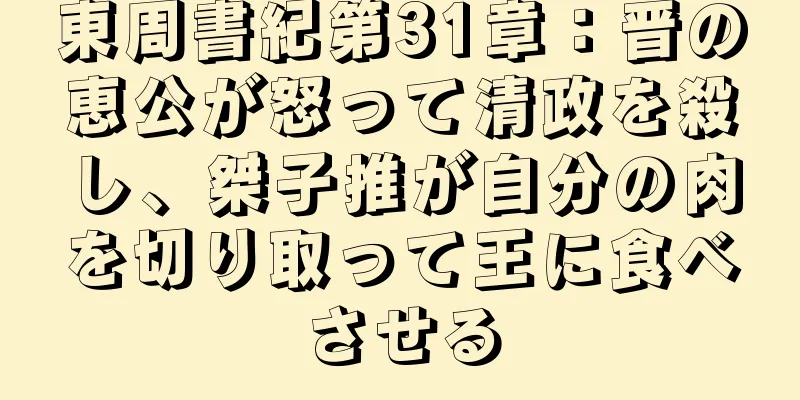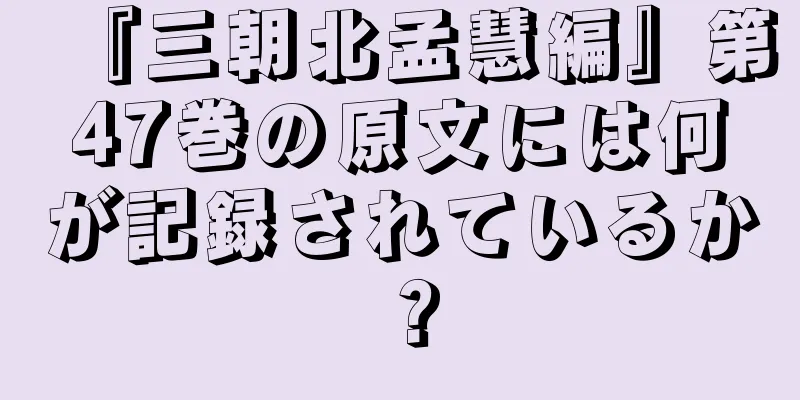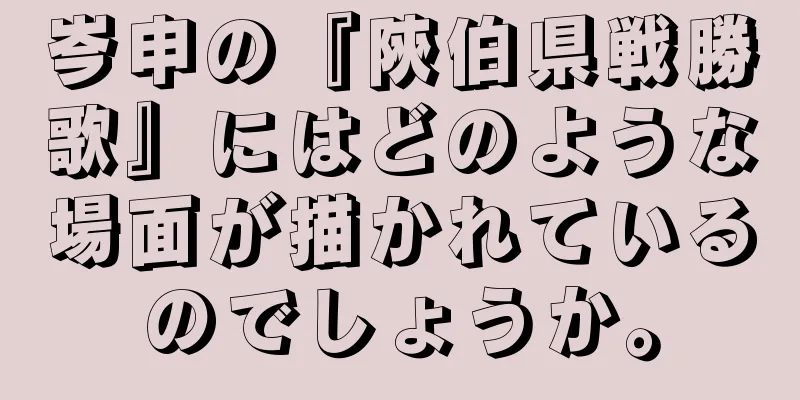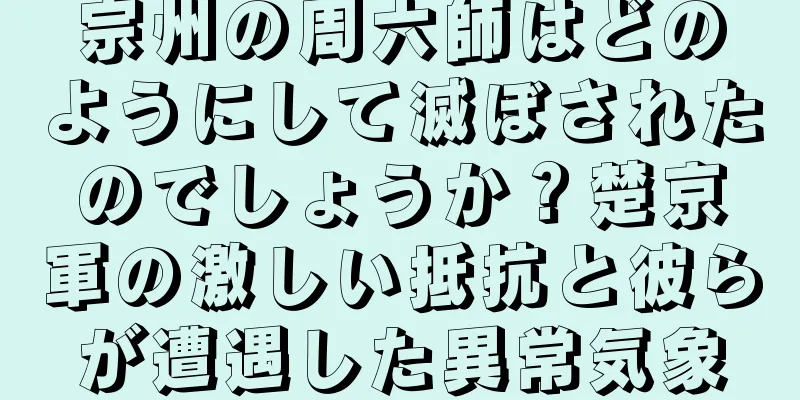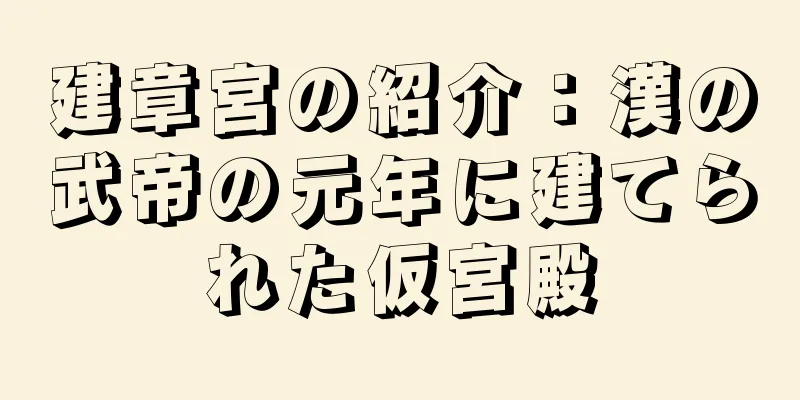楊年群:科挙は本当に無駄なのか?
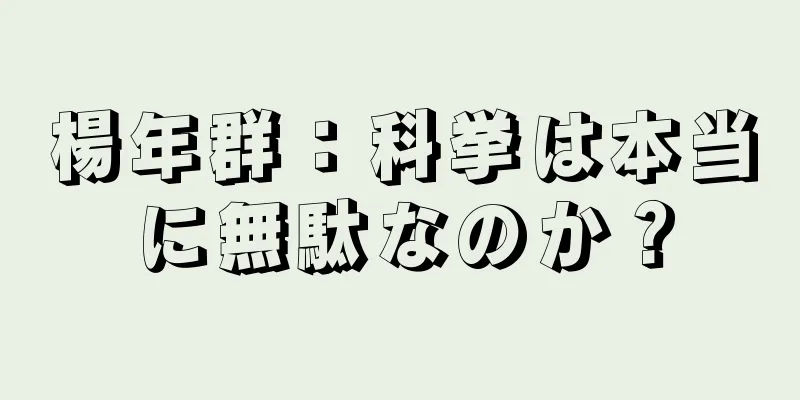
|
(編集者注:本稿の著者である楊念群氏は、中国人民大学清史研究所の教授である。同氏は「科挙制度と新教育制度を比較した場合、科挙制度の3つの試験は、道徳、人文科学、実用性のバランスが取れており、その学問的方向性は極めて適切であると思う。現代教育は実用性のみを追求し、人文科学の基礎がなければ、生み出される人材は必然的に偏ってしまう」と考えている。) 科挙と新学問の葛藤 清朝末期には数々の改革が行われ、科挙制度の廃止はおそらく老若男女にとって最も衝撃的な出来事だった。田舎に残った無知で愚かな老学生は、尊敬される人々から解雇や失業の標的に変わった。それらは近代国家の身体に増殖する化膿性の腫瘍のようなもので、誰もが外科医に変身してそれをメスで切り取る役割を担っているようだ。今の人は科挙制度を軽蔑し、ほくそ笑んでいるようだ。しかし、科挙制度の最終列車に乗った人たちは非常に現実的で、科挙制度は貧しい人々が生活するための手段であると常に感じている。名誉と富を追求する道を選ばなければ、必ず軽蔑される。貧しい家庭にとって科挙制度に合格することは、その家庭に名誉をもたらす一大イベントである。文盲の父親の子供は上流階級に入るチャンスがある。したがって、科挙制度が人々に害を及ぼすと簡単に唾を吐くべきではない。 『科挙』が批判されるもう一つの理由は、現代の人々が科挙の規則を理解しておらず、誤って『八足文』を科挙の全体とみなして批判していることである。私は、せむしで頬が痩せて醜い顔をした候補者たちは、古典からしか引用できない、ただの衒学的な本の虫の集団だと思っていた。ここで明確にしておきたいのは、明清時代以降、少なくとも3回の科挙があったということだ。第1回と第2回の科挙では、間違いなく『四書』と『五経』が試された。家庭教師に殴られて皮膚が何層も剥がれなければ、勇敢だとみなされた。毎年科挙を受け、一生学生の輪の中にいれば、簡単に馬鹿になり、気が狂って自傷行為をすることも珍しくなかった。しかし、忘れてはならないのは、科挙には「兵法問題」と呼ばれる、軍事、農業、刑罰、礼儀、民政、河川防衛、産業救済などに関する科目が3回あるということであり、これは完全に頭のいい人が取り組むべき科目である。細かく見ていくと、現在の大学入試で出題される「経済史」「法制史」「開拓民族史」「思想史」などの科目とよく似ている。 暗記が求められる第1ラウンド、第2ラウンドに比べ、このラウンドの問題は体操競技のオプション動作のようなもので、決まりきった真似技だけで合格するのは容易ではないだろう。皇帝は宮廷の試験段階においても、古人の書物を推測しようとしてはならないことを強調し、自分の考えを述べるよう奨励した。順治年間、皇帝の面談段階になると、政策論文の長さに制限はなく、故意に古いやり方に固執したり、決まり文句や官語を使っておざなりにしたりしてはならないと規定された。何も隠さずに自分の考えを述べることが求められた。乾隆帝以前の第二ラウンドには、いわゆる「陳状」「勅状」「判決」も含まれていた。陳状と勅状は、臣下が皇帝に手紙を書いたり、皇帝が勅状を出して問題を議論する様子を模倣したもので、候補者がさまざまな立場から政治問題を処理するのにふさわしいかどうかをテストする意味があった。「判決」は、今日の法廷事件の解釈のようなもので、いくつかの事件を列挙して、法律知識と事件解決能力をテストした。ほとんどすべての回答は、空論ではなく実際的なものであることが求められた。政策論文が加われば、候補者は地方公務員の立場に立って公務をこなすことになる。現場の状況に応じた機敏な対応が求められるのは、現在の候補者の想像を超える。乾隆帝以降、勅令、勅旨、判決に関する試験は廃止されたが、政策論文の部分は依然として非常に難しく、飾り言葉や決まり文句を使って難関を突破することは不可能であった。 人々が「科挙」を八つ足のエッセイと直接結び付けるのは、理由がないわけではありません。これは、八つ足のエッセイの執筆が第1ラウンドと第2ラウンドに設定されているためです。第1ラウンドと第2ラウンドで失敗すれば、世界を統治するための素晴らしいアイデアをたくさん書いても無駄になります。そのため、誰もが八つ足のエッセイで互いに競い合いました。しかし、賢い人々に会うと、人を罠に誘い込むようなこのような八つ足のエッセイの勉強は、すぐに心を縛る無駄なものになります。彼らを惨めにしたのは、試験を受ける前に、厳格で堅苦しく時代遅れの形式で経典の一節を暗記し、気取った試験詩を書かなければならなかったことです。これが最も悲惨で有害なことでした。この部分は通常、現代文学の芸術と呼ばれています。しかし、科挙を批判する人の中で、「政策論文」の重要性を疑問視する人はほとんどいない。 「策闻」の構成は、一般的に4~5問です。第1問は主に「古典」の歴史に関するもので、現在の「基礎科目」のテストに相当します。「古典」は人生の基礎であることを強調しています。この部分では、依然として暗記の死活的なスキルがテストされており、第1ラウンドと第2ラウンドの内容と重複しています。目的は、受験者の文献学の基礎を探ることです。 2 番目の質問以降では、応募者は自由に自己表現する余地が広がります。質問のほとんどは、中央政府制度の発展や役人の選考・審査方法など、制度史の発展に関するものでした。 「『荀麗』とは何か?」のように、一言で答えるのが難しい質問もあります。 3 番目の質問は、地方自治の問題についてであることが多く、この部分では水利護岸をどのように規制するかについても言及されます。 4番目の質問には、歴史的、地理的な進化を分析したり、穀物のさまざまな貯蔵方法について議論したりすることが含まれています。私はかつて、古代の農業書である『其民要書』と『農桑集要』を現実に照らして分析することを要求する質問を見たことがありますが、それは少し経済学の知識のテストのようでした。試験問題に5番目の質問がある場合、軍事や沿岸防衛などのトピックが含まれます。質問では地域の状況も考慮されます。たとえば、江南での質問では、防波堤プロジェクトの歴史や水上輸送の長所と短所に焦点が当てられます。道光年間、海寧県の試験問題では、明代の有名な河川管理専門家である潘継勲の水利著作『河川防御略論』が具体的に論じられ、関連する多くの河川管理戦略についても論じられました。 「通貨制度」に関する試験問題で、唐代の官文・篆書から宋代の草書・行書に変わった後、「貨幣」という文字をどう変換するかという専門的な内容について詳しく問われているのを見たことがあります。 「策问」の質問の単語は、現在の大学入試問題が1行か2行であるのとは異なり、一般的に長くなっています。試験官が意見を述べることが多く、受験者がそれを検証または反論します。道光元年、海寧の省試問題に「保家」を論じる問題が出題された。周代に保家が設立されたことから始まり、明代に保家制度がどのように発展してきたかを論じており、まるで「保家の歴史」のようであった。試験官の質問も非常に鋭いものだった。一つは、宋代の王安石が、多くの人々が不便だと感じた保家制度を積極的に実施し、司馬光が廃止を嘆願したのに、明代の王守仁が江西省で実施したときにはなぜそれほど効果的だったのか、というものだ。 2 番目の質問は、都市や町は人口密度が高く、検査は簡単ですが、谷間や密林に点在する土地、人里離れた隠れた寺院や住居をどのように巡回すればよいかということです。客家人のスラム街に住む人々が住む人口の少ない地域や、行き来の激しい商船や漁師が住む地域を統括し、監視する上で、保家制度はどのように役割を果たすことができるのでしょうか。質問の最後には、受験者は現場から来たので、実務経験に基づいて冷静に回答できることを思い出しました。 政策論文の質問に正確に答えるには、幅広い知識と人生経験が必要です。ただ単に暗記するだけではだめです。暗記や真似に慣れている受験者は、当然、それをやろうとはしません。この考え方に応えるために、科挙では政策に関する質問を回避するための怠惰な方法がいくつか考案され、試験の難易度が下げられました。かつて安徽大学の学長を務めた姚永蓋の『沈易軒日記』には、彼の弟が科挙を受けた際、試験問題に詩文と散文の問題が1問しかなく、政策に関する論述問題がなかったという記録がある。さらに奇妙なのは、政策エッセイを自由に詩に変えることができることです。それでも詩が書けないなら、詩に変えて提出すればいいのです。姚永蓋は、政策論文は役に立つ文章だが、詩や散文は役に立たない文章だと悪態をつかずにはいられなかった。彼は政策論文を軽蔑し、詩や散文を重んじていた。世の中がこのように卑劣で下品なため、学者の道徳が低下し、知識が浅くなるのも無理はない。 政策に関する質問に答えるには相当の知識が必要なので、受験者は、8本足のエッセイの訓練以外に、どこでこの知識を得るのでしょうか?当事者の経験から判断すると、一つの方法は、家庭教育の早い段階で意図的に子供に知識を植え付けることです。姚永蓋の父は、農地と水利に留意する必要性を強調し、彼が規定した参考文献を地理(天文学を添付)、軍事と塩、水運、水利、農地、金融、祭祀と音楽、西洋事情に分け、それぞれを詳しく学ぶように促しました。実際、儒学者は日常の俗事を学ぶことを決して避けませんでした。「農を学んでも農の心がない」という言葉があります。真の君子とは、日々の俗事に忙しくても、心の中では清らかで穏やかな道徳心を保つことができる人です。 政策問題が実務に役立ったからこそ、清末期の科挙制度は、まず試験会場の順序を逆転させる改革から始まった。最も有名な動きの一つは、1901年(光緒27年)に両江総督の劉坤義と湖広総督の張之洞が共同で出した「江楚合同委員会三箇条」である。第一願書は、第一ラウンドの試験では中国の政治と歴史を試験し、博学と呼び、第二ラウンドでは各国の政治、地理、農業、工業、軍事準備、数学を試験し、総合と呼んだ。この2つの試験の内容は、通常第三ラウンドに配置されていた科挙の「政策問題」に相当するが、願書ではそれらを第一ラウンドと第二ラウンドに配置することを要求し、最も伝統的な四書五経の基礎研究を第三ラウンドに移し、清浄と呼んだ。道徳的根源の研究と世俗的な事柄の研究は完全に逆転し、時間の経過とともに徐々に不要になっていった。 蒋楚の三通の嘆願書が発布されると、すぐに下層階級から反応があり、何らかの行動がとられた。例えば、日記には、その年の8月に湖北省黄安市出身の朱志三さんが私立学校に通っていたことが記されている。先生が突然、もう八本足のエッセイは書かない、代わりに時事問題に焦点を当てた「道徳エッセイ」を書くと発表。先生が言っていた「道徳エッセイ」は、おおよそ「政策に関する質問」のようなタイプの質問に相当するのだろう。その日、講師が与えたテーマは「軍事訓練について」でした。この人は新しい本を読むのが好きで、最先端の考えを持っていると言われている。つい数日前には、「中国は簡単に富国強国になれる」といった流行のタイトルの記事を発表したばかりだ。次のような新たな疑問もあります。中国は西側諸国に、返済に40年かかる負債を抱えています。何ができるでしょうか?この質問は、テレビシリーズで狄仁傑が助手の袁芳に「どう思いますか?」と尋ねた質問に少し似ています。この草の根レベルの教師が実際に次のような前衛的な疑問を提起できたことは、いくぶん驚くべきことである。君主制、民主主義、そして君主と国民が共同で統治する国の違いは何か?五穀改革の六君子が殺害されてからまだ6年しか経っていないが、当時の君主民主主義の議論は、すでに草の根の私立学校の教師たちの心の中に、隠れた地下火のように広がっていたことが分かる。しかし、地方の人々の間では、時事問題の試験に対して常に抵抗があり、県レベルの試験で時事問題が問題となると、多くの学生が試験をボイコットすることが多い。 現代の知識で問題を埋めるためには、科挙制度の柔軟な改革だけに頼るだけでは明らかに不十分であり、日本から学ぶことがさらなる研究への流行の近道となった。当時、清朝政府はまだ学校開設の明確な命令を出していなかったため、各省が独自に主導権を握り、地方の役人はそれを黙認して放置していた。私立学校がアカデミーに変わったときに最も不足していたのは教師でした。教師の知識構造は古すぎ、数学、科学、工学、政治、法律などの新しい科目について無知でした。最も簡単な方法は、外国人教師を雇うか、若者を直接隣国の日本に留学させ、帰国後に学校で教えることでした。この時期、ほとんどの小学校は日本人教師を雇うことを好み、もともと科挙に熱心だった家庭は、子供たちを日本に短期研修に送ることにも積極的でした。その多くは、すぐに成功するための実利的な配慮でした。短期教員養成コースや法律・政治学コースを学ぶために日本に行く学生のほとんどは、通常、公的資金援助と私費留学のどちらかを選択します。例えば、安徽省から日本に留学する留学生は、学業を終えて中国に帰国後、3年間故郷に貢献するという条件で、公的寄付20%、私費10%の割合で資金援助を受けます。 日本に留学する学生が多すぎたため、日本人は次第に人を騙すビジネスを始めた。鮑天霄の回想によると、速成師範学校では学力に関係なく卒業証書が発行され、学生は1年で卒業できた。中国に帰国後、小学校教師の資格を得て贅沢な生活を送ることができた。もっと極端な例もある。日本語が分からない中国人に対しては、日本人は通訳を雇うだけで対応し、教師が説明している間、通訳は傍らで説明する。さらにひどいのは、留学生が読めるように、日本語の教科書を中国語に直訳する日本人教師もいるということだ。帰国後の日本語がどれだけ下手になるかは想像に難くない。 日本から帰国した師範学校の早熟な生徒は、冗談を言うのが得意で、知識は半分しかないのに、わざわざ台東に行って、日本から盗んだ逸話に頼って、自慢したり、世間を喜ばせたりして、でたらめを言う。県級師範学校の教師はカタカナとひらがなしか分からないし、日本語のレベルも驚くほど低い。東京に半年留学しただけの校長が、舞台に立って意味不明なことを言うこともあった。当時の人々は、日本の近代文化はもともと欧米から輸入されたもので、さらに移入が進むと中国人はすべて第三者の販売業者となり、販売されている商品の純度に疑問を抱き始めたと感じていました。当時の試験問題にそのような疑問が浮かんだのも無理はない。日本や上海で勉強する学生はみな、乱暴で、模範となるような行動をせず、勉強にも熱心ではない。そのような学生を信頼できるのだろうか?科挙制度を廃止しなければ、自己啓発の望みはないかもしれない。学生を罰しなければ、放任主義の弊害が残る。我々はどうしたらよいのか。 科挙制度は廃止され、私立学校の教師も多すぎたため、簡単に解雇するわけにはいかなかった。その結果、各地に「教員養成学校」が設立され、日本に留学した学生を雇って、こうした旧式の教師を指導することになり、短期間の再研修の後、旧私立学校の教師が急遽小学校の教師に採用され、一時的に生計を立てることが可能になったため、多くの笑い話となった。観客席には白髪の老人が数人座っていることが多く、舞台上には20代の若者が立っている。彼らの中には、海外に行く前は観客席の老いた私立学校の先生の教え子だった人もいて、帰国後、あっという間に先生の師匠になった人もいる。これらの「生徒」は、これらの若い教師よりも 1 世代、あるいは 2 世代年上です。村では彼を義父と呼ばなければなりませんが、彼の義理の家族の中には年長者がいたり、彼の下には家族の中に父親がいたりするかもしれません。教師と生徒の間でこのような序列の逆転の例は多すぎます。鮑天暁さんは、ある若者がトレーニングセンターの登録用紙を見て首を横に振り、「教えることはできません」と言ったことを思い出した。理由を聞くと、リストに載っていた教師の一人が彼の元教師だったことがわかった。その若者はあまりにもいたずらっ子で、その老教師に手を叩かれたことがあった。今、その老教師が彼に教えているが、彼は老教師と顔を合わせるのがとても恥ずかしかった。その老人を別の訓練施設に移す以外に選択肢はなかった。最も興味深いのは、これらの古い生徒たちが小さなティーポットと水ギセルも教室に持ち込んでいたことです。彼らは興奮すると、時々喉を潤すためにお茶を飲んだり、首を振ったり、同意してうなずいたり、あるいは単にマッチを擦って水ギセルを吸い始めたりしていました。 科挙制度の廃止により、初等教育は必然的に新旧混交のジレンマに陥った。安徽省で学校を経営していた姚永蓋はこの問題をよく理解しており、異なる流派の学校を運営するというアイデアを提案した。彼は、一部の高等学校では伝統的な中国学の基礎を持つ人材を採用し、西洋の言語や一般科学をできるだけ多く学ばせることを提唱した。伝統的な中国学の基礎が弱く、良い人と悪い人の区別がつかないことを心配する必要はないからだ。啓蒙段階にある小学校は若い生徒を募集し、数学、体操、音楽の勉強も考慮に入れながら、倫理的および道徳的基礎の育成に重点を置く必要があります。しかし、この考えは、現代中国の人文科学教育の衰退の最終的な運命を変えることはできません。各県、州、郡の中学校は西洋の科学と工学に偏りすぎており、中国語のリテラシーは低下し続けており、大学で中国語が得意な学生は非常に少ないです。学生は中国語の試験中にカンニングをしていることがしばしば発覚するが、それを恥ずかしく思っていない。姚永蓋は、すでに学校の生徒の心理的変化を見抜いていた。生徒は傲慢で暴力的であり、教師を軽視する態度がいたるところに見受けられ、ついには怒りのあまり辞職に至った。彼は甥に宛てた手紙の中でこう書いている。「学者や官吏は古い知識を学ぶときは偏見を持たず、新しい知識を学ぶときは法律を遵守すべきである。」一般的な意味は、新しい学者の表面的な性質や衝動性にとらわれていると、彼らが研究においてしっかりとした基礎を築くことが難しくなるということです。 科挙制度と新教育を比べると、科挙制度の3つの試験は、道徳、人文、実用のバランスが取れており、学問の方向性は適切であると感じます。一方、現代教育は実用性のみを追求し、人文を基盤としなければ、育成される人材が偏った方向に行かざるを得ないのは当然です。 |
<<: 古代人は科挙に失敗したあとどうやって生計を立てたのでしょうか?
>>: 古代において最高の学者になることはどれほど困難だったのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』の宝玉と王夫人の関係は何ですか?なぜ私たちは離れていくのでしょうか?
『紅楼夢』の宝玉と王夫人の関係を知らない読者のために、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。読み...
古典文学の傑作『太平天国』:陸軍省第84巻
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』で王希峰はなぜ寧国屋敷であんなに騒ぎ立てたのでしょうか?
王禧峰は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人です。以下の記事は『Interest...
二十四史第115巻「明代史」第三伝
興宗孝康帝(孝康皇后、呂太后) 睿宗献帝(献皇后)興宗皇帝孝康表は太祖の長男であった。母:高王妃。彼...
唐代の詩人、王維の『観狩』の原訳、注釈、鑑賞
「観狩」は唐代の有名な詩人、王維が書いた五字の詩です。 Interesting Historyの編集...
「大連花・春景色」を鑑賞、詩人蘇軾は現実世界を忘れていない
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
劉備が即位した後に張飛と馬超にのみ貴族の称号を与えたのはなぜですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
五十肩は一般的に肩関節周囲炎を指します。現代の医学用語ではこれをどのように説明するのでしょうか?
五十肩は一般的に肩関節周囲炎を指し、肩甲上腕関節周囲炎と略され、五十肩や五十肩とも呼ばれます。肩関節...
李克はもともと王位を継承する希望を持っていたのに、なぜ反逆罪で死んだのでしょうか?
李世民には全部で14人の息子がいて、李可は3番目でした。李世民は生前、李可に帝位を譲るつもりでしたが...
「秀雲閣」銀索閣は陣形を整え、古仏寺は徐武に出会った
殷索閣は徐武に会うために古代仏寺の形成を手配した三堅が寺に戻ると、弟子たちは皆、彼に敬意を表した。彼...
劉晨翁の「秦娥を偲ぶ-元宵節」:詩全体が悲しみと悲哀に満ちており、『徐西慈』の有名な詩である。
劉晨翁(1232-1297)、雅号は慧夢、号は許熙としても知られる。彼はまた、徐喜居士、徐喜農、小娜...
『紅楼夢』で賈宝玉はなぜ科挙を受けようとしなかったのですか?理由は何ですか?
中国の古典『紅楼夢』の主人公である賈宝玉は、栄果屋敷の賈正と王傅仁の次男である。本日は、Intere...
『韓湘子全伝』第21章:寺で吉凶を尋ね、占いを求め、飢えと渇きを癒し、茅葺き小屋に住む
『韓湘子全伝』は、韓湘子が仙人となり、韓愈を導いて天に昇るまでの物語です。本書は、明代天啓三年(16...
『紅楼夢』の西人(シーレン)と黛玉(ダイユウ)の関係は何ですか?
希仁は『紅楼夢』の登場人物です。彼女は金陵十二美女の一人で、宝玉の部屋の四人の侍女の長です。次回はI...
『女仙秘史』第36章:唐月君が済南城を創設し、陸時珍が建文帝の訪問について議論した
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...