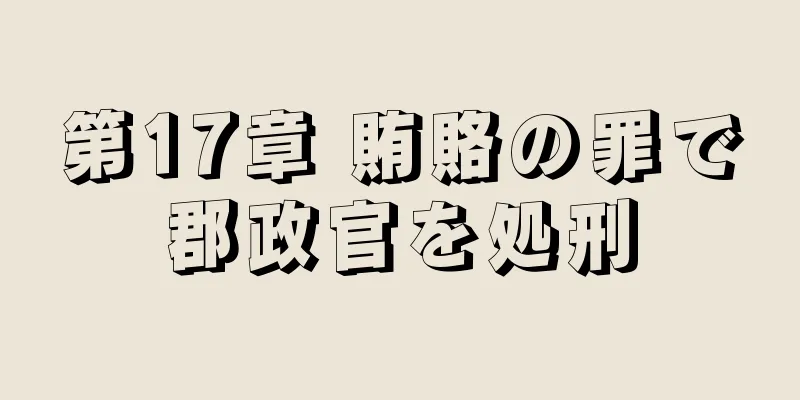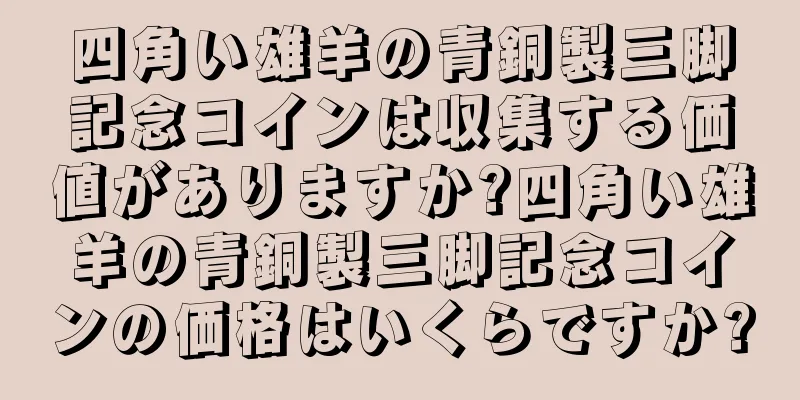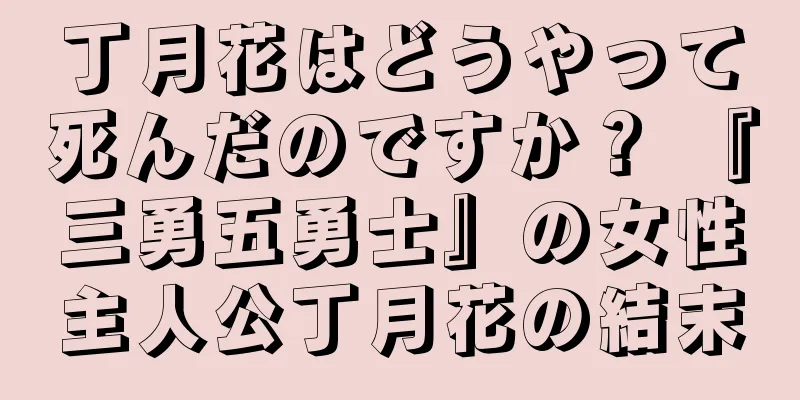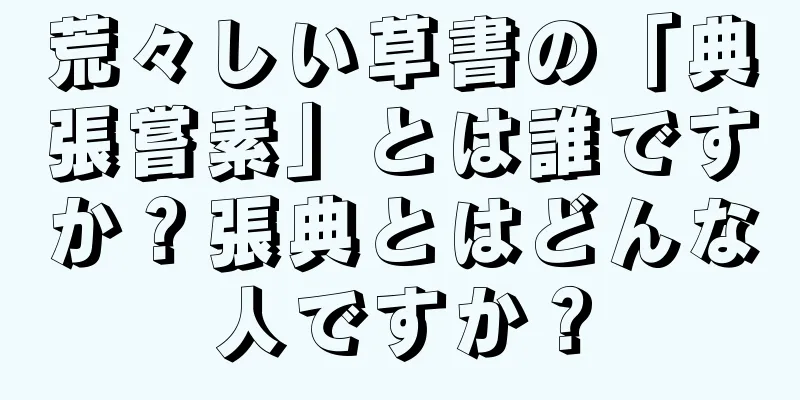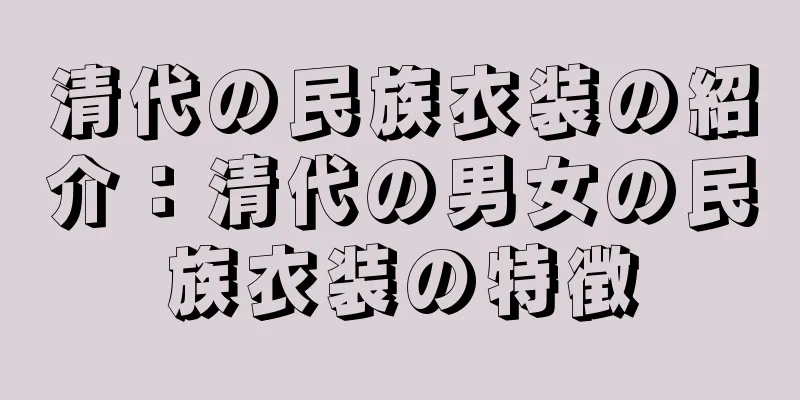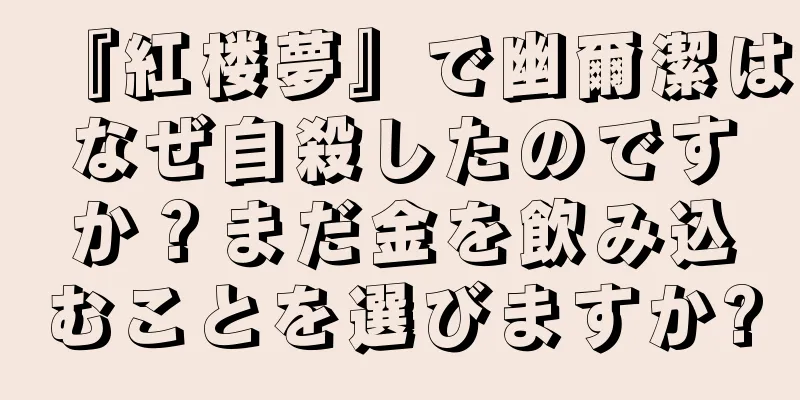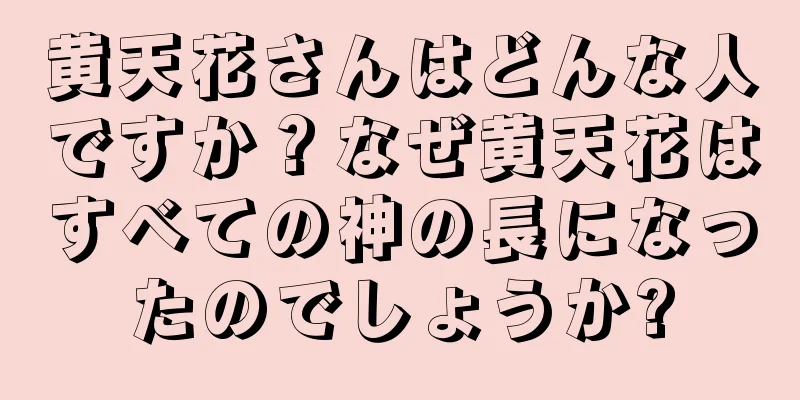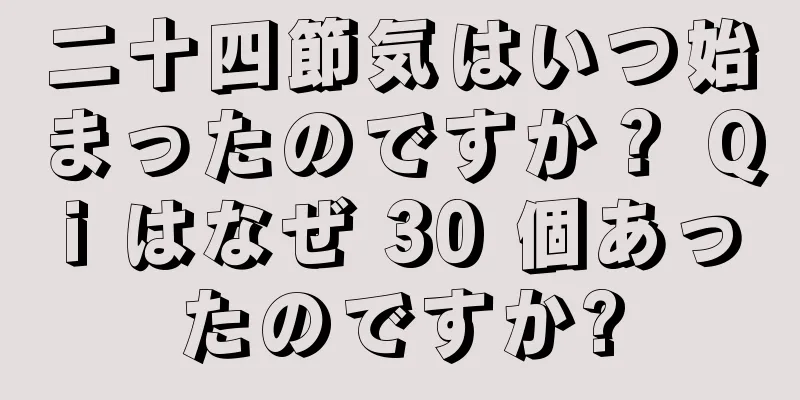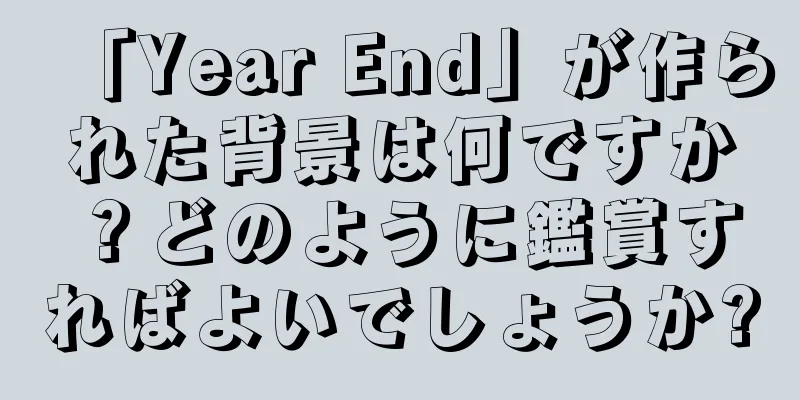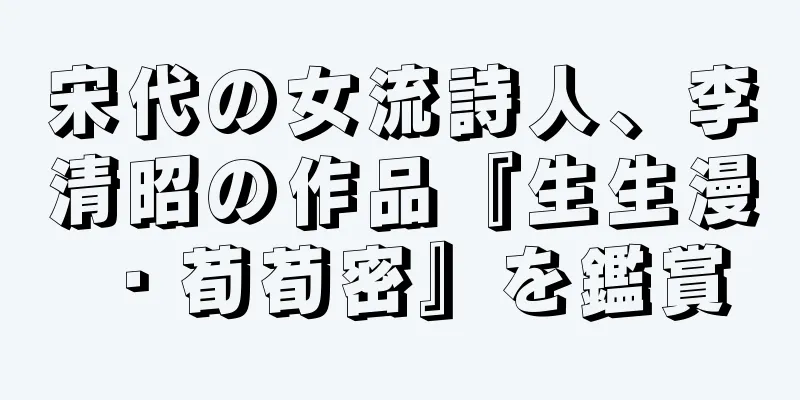なぜ日本人は復讐物語が好きなのでしょうか?
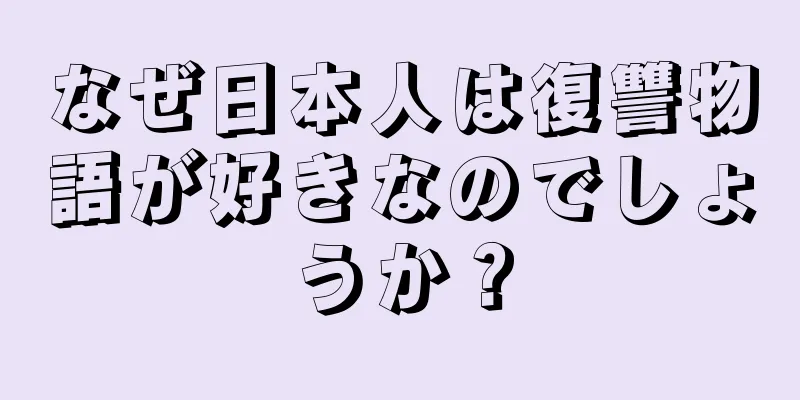
|
中国では復讐よりも恩返しが重視されている。司馬遷の『刺史記』の主題は復讐ではなく恩返しである。例えば、荊軻が秦王を暗殺したのは、深い憎しみからではなく、友人のために命を捨てる覚悟があったからである。中国は古来より日本に対して恩義を感じていますが、日本はそう思っていません。両国が同じ考えを持つことは難しいでしょう。 日本人は復讐物語が大好きです。復讐は魅力的に聞こえるが、恋愛をはるかに超える、侍小説の伝統的なテーマである。 井上和氏は小説家、劇作家、日本ペンクラブ会長であった。2010年に亡くなった。彼はかつてこう言った。「復讐、この種の物語は世界中で一般的だが、日本人は特にそれを好む。」彼自身も復讐劇を書いており、彼の小説『吉里吉里の人々』も復讐の幻想を描いている。先代の菊池寛(小説家、出版者)は大衆の好みに応えて、『復讐の禁』『怨念の彼方に』『復讐の三態』など復讐小説を得意とした。現代小説でも、垣根涼介の小説『ワイルドソウル』のように復讐をテーマとするものが多い。 復讐は、日本語では通常「仇搜」または「敌搜」と呼ばれ、命の代わりに人を殺すことを意味します。殺しはしないが、目には目を、歯には歯を、それがせいぜい復讐だ。 日本の歴史には復讐の物語は多いが、感謝の物語は少ない。亀が恩返しをし、鶴が恩返しをする、という民間の伝説があるが、人間はいつも信用できず、いつも覗き見したがるので、結局二人は険悪なまま別れてしまう。人間は他の動物のように一人では生きていけないので、育ててくれた親の優しさ、先生や友達の優しさ、その他にも山よりも高く海よりも深いほどの不当な恩恵など、たくさんの恩恵を受けてきました。 中国では復讐よりも恩返しが重視されている。司馬遷の『刺史記』の主題は復讐ではなく恩返しである。例えば、荊軻が秦王を暗殺したのは、深い憎しみからではなく、友人のために命を捨てる覚悟があったからである。中国は古来より日本に対して恩義を感じていますが、日本はそう思っていません。両国が同じ考えを持つことは難しいでしょう。 唐代、張神粛が賄賂を受け取っていたことが発覚。楊万卿がこの事件を処理し、神粛は処刑され、家族は国境に流刑となった。開元22年(734年)、沈粛の子張秀は赦免されて北京に戻り、まだ成人していなかったが、弟の張炎とともに楊万卿を暗殺した。李龍基皇帝は彼の孝行を称賛し、彼を起訴しないことを決定したが、司法部門はこれに同意せず、法律の執行を主張した。張秀が処刑されたとき、ある人が彼の弔辞にこう書いた。「彼は復讐のために法を無視し、刑法から逃れることは本当に困難だった。彼は孝行のために自分の命を忘れ、まさに礼記に従った。」 その年、長安で日本人留学生の荊真成が亡くなり、皇帝は彼の死を悼んだ。前年(733年)、日本は10回目の遣唐使を派遣した。唐に18年間滞在していた玄芳と吉備真備は船で帰国した。張兄弟の仇討ちの話も日本に伝わったのかもしれない。法に逆らって復讐することと、孝のために自分を忘れることは、復讐の永遠の矛盾である。復讐は感情を伴うため、人の心を動かしやすい。さらに、人々は復讐を利用して悪や権力者に対する恨みをはらすこともできる。これが、侍小説が読者層を持つ理由である。 復讐は、人間が血縁意識を発達させてから形成された本能なのかもしれない。倫理観として、日本の復讐観念は中国に遡ることができ、『礼記』には「父の敵は和解できない」と書かれている。江戸時代になると、朱熹の思想はさらに尊敬されるようになった。敵は父親だけではなく、皇帝と父親の間の敵は和解できないものだった。 盗賊が侍になる 1603年、徳川家康が将軍に就任し、江戸(現在の東京)に幕府を開き、天下を制覇しました。それから15代将軍が天皇家に大政奉還した1867年までの260年間を江戸時代といいます。いわゆる「時代小説」の多くはこの時代を舞台とし、侍小説として翻訳されている。 江戸時代、人々は武士、農民、商人、職人の4つの階級に分かれていました。武士は最上位の階級であり、市場について書くときも必ず武士が登場します。侍には、腰に大小2本の刀を携行できる特権があり、これらは「大小」と呼ばれます。特権には、護身用に刀を使用するという義務が伴います。世の中は平和で、王子様が世界のために戦っていた時代の戦士はもういません。平凡な日々では、武力を使うことは戦うこと、殺すこと、復讐することの3つに過ぎません。戦うことは勇気の象徴であり、一歩も前に出ないことは臆病の表れです。火と喧嘩は江戸の二つの花となった。 一般の人々(農民、ビジネスマン、実業家)が無礼であったり攻撃的であったりした場合、武士は指導層の地位と評判が侵害されないことを示し、武士としての勇気を保つために刀を抜いて彼らを殺すことができました。家康の遺訓百選の中に、親の仇討ちをしたいなら、記録に残す限りはしても良いが、際限なく仇討ちをすることは許されない、という訓戒がある。父親の復讐は息子だけが許され、弟は兄の復讐を許されるが、その逆は許されない。屈辱による自殺は復讐にはならない。 復讐は流行であり、幕府は復讐の範囲を最小限に留める意図から、復讐を容認した。京都の朝廷事務を管理するために幕府から派遣された役人、板倉重宗はかつて、父の仇討ちは京都市内およびその近郊で行ってよいが、宮殿の立入禁止区域や神社仏閣内では行ってはならないと命じた。家康の遺訓は江戸時代初期に登場したものであり、真偽のほどは定かではないが、仇討ちの制度化に関する規定は板倉重宗の遺訓のみ現存する。 日本の歴史上、中国語を使って日本人の考え方を変えることに成功した二人の君主がいました。聖徳太子と徳川家康です。徳川家康は学問を好まなかったが、天下を取ったとしてもすぐには国を治めることができないことを知っていた。天下を取った後、藤原惺窩や林羅山などの儒学者を雇い、義と格を重んじる朱子の思想を国学とした。 武士はもともと財産目当てで人を殺める盗賊でしたが、学問を修め、自己を磨くことが奨励され、「学者官階級」へと変貌を遂げ、次第に武士の倫理規範である「武士道」が確立していきました。話し方、服装、髪型、飲酒などにも一定のルールがあり、常に武士としての威厳を保たなければなりません。諺にもあるように、飢えた戦士は口に爪楊枝をくわえていますが、これはまさにその通りの意味です。戦時における問題はいかに生き残るかであり、一方、平時における生命の問題は生ではなく死である。平和な時代には滅多に起こらない死は、名誉を守る機会を与えてくれる。 評判は面子にも関係します。面子を保つ必要性は、いつでも、さまざまな場所で常に発生します。武士は、他人を殺したり、自殺したりすることで、死を望みました。名誉を守ることは倒錯したレベルにまで達している。例えば、新渡戸稲造は『武士道』の中で、ある都市の住人が侍に背中にノミが飛び回っていることを親切に指摘したところ、その侍はたちまち真っ二つに裂かれたという例を挙げている。その理由は単純で奇妙である。ノミに覆われているのは動物だけであり、高貴な侍は動物とみなされ、そのような侮辱は許されないということである。名誉の名の下に、復讐は友情から道徳へと高められます。 1817年、新発田藩(現在の新潟県北東部)で、久屋小太郎が7歳の時、父が宴会で滝沢久右衛門と口論になり殺害された。小太郎が18歳のとき、藩主は彼に刀と金20両を与え、復讐の旅に出発した。光太郎は敵が誰なのかわからず、叔父に付き添われて重労働をしながら全国を旅した。最終的に石巻(宮城県)近郊の滝沢にたどり着き、出家したが、杖にナイフを隠し持っていた。 滝沢は小太郎に切り倒され、息を切らして言った。「有名な学者を見つけて、私たちの物語を詩にしてくれ。」光太郎は漢学者の潘渓王介の家を訪ねて、「あなたが書かなければ、滝沢は安らかに眠ることができない」と頼んだ。大卓の作だが、詩集には収録されていない。一説には、光太郎が満足できず破り捨てたとも言われている。滝沢は82歳、光太郎は41年前に復讐を果たした。菊池寛と長谷川伸はともにこの事件を題材にした小説を書いている。石巻市の海岸には「久米光太郎仇討ちの地」と書かれた四角い柱がある。2011年3月11日の地震による津波で流されたと思われる。 赤穂事件 江戸時代には15人の将軍がいましたが、その中でも5代将軍の徳川綱吉(1646年 - 1709年)は最も優れた儒学者であり、文治政治を推進しました。彼は諸侯のために勉強会を招集し、自ら儒教を教えた。忠孝を促進するために各領地に忠孝碑が建てられた。戦国時代から残る殺意を一掃するため、衆生を慈悲深くせよという命令を出したが、度が過ぎ、吠える犬を殴れば左腕に「犬」の文字の刺青を入れられ、顔を刺した蚊を殺せば流罪にされた。人命を軽んじたため「犬将軍」と呼ばれ、悪名が今も残っている。しかし、47人もの者が公然と彼を非難し、幕府は難問に直面した。これが日本史上最大の仇討ち事件、赤穂事件である。 清の康熙帝の治世40年目となる元禄14年、すなわち西暦1701年に、幕府は天皇から派遣された勅使を迎えるために浅野長規を派遣しました。浅野氏は赤穂藩主で、藩内の職人を統括する将軍内匠頭を務めた。江戸城(将軍の居城、現在の皇居)の廊下で、浅野は吉良義雄を背後から刺した。 吉良は幕府の礼法を司っていた。浅野は吉良に助言を求めたが、吉良は礼法を卑しいものとみなし、指導もしないどころか、厳しい言葉を投げかけ、浅野を憤慨させた。復讐物語は殺人から始まり、殺人を使って問題を解決します。敵は悪人として設定され、人間と神の両方から嫌われ、悪を罰し善を促進するという基本的な価値観が形成されます。敵役の吉良吉雄は舞台上では悪役として描かれる。菊池寛の『吉良の立場』や森村誠一の『吉良忠臣蔵』など吉良を賞賛する者もいた。 将軍邸での公務中は、たとえ怒っていても刀を抜いて殺人を犯すわけにはいかないので、浅野の行動はちょっと信じがたいものがありました。当時の武士がいかに名誉を重んじ、刀を抜いて犯罪を犯す風潮が深刻であったかを示しているのかもしれません。綱吉はこれを知り激怒し、その日のうちに浅野に切腹を命じた。浅野の家財は没収され、家臣は皆浪人となった。武士は刀を所持しており、乱闘は武力闘争に発展する可能性があったため、幕府は口論や争いがあった場合、理由の如何を問わず双方に鞭打ち50回という規則を設けた。綱吉は、悪徳官僚を罷免し、悪政を改め、規律を正した。徳と罰を区別し、すべての人を平等に扱うのが政治の原則の一つである。しかし、浅野に自害を命じ、吉良は何もなかったかのように振舞った。このような扱いは、どうしても一方に偏ってしまう。 赤穂浪士の仇討ち状では、当時口論があり浅野は衝動的に刀を抜いたため、幕府が吉良を処罰しなかったのは不当であると主張している。元禄15年12月15日、いつの間にか大石良雄(通称内蔵助、『忠臣蔵』の「蔵」もこの人のことかもしれない)が46人の浪人を引き連れて吉良邸に入り、吉良を殺害して首を切り、浅野に供物として捧げた。彼の墓は東京の泉岳寺にある。すると、彼らは喜んで切腹するのではなく、説明を求めて官庁に嘆願書を提出した。 忠義は封建制度の精神的基礎です。綱吉は特に主君への忠誠と親への孝行を説いています。浪士たちが主君の仇討ちを敢行するのは、「天皇の恩は山の千倍」の具体化です。もし彼らが死刑に処せられたら、それは忠義の露骨な否定ではないでしょうか。群衆を集めて騒ぎを起こしたり、夜間に民家に侵入したりすることは、治安を乱す違法行為です。このようなことを許せば、国は国でなくなります。赤穂事件の正当性を認めるということは、幕府が誤りを犯したことを意味し、浅野氏の名誉回復が必要であることを意味する。決断力のある綱吉ですら躊躇し、儒学者の間で大論争が勃発した。テーマは唐代に議論された「復讐のために法を破れば必ず刑法を逃れられる」「孝のために身を捨てることはまさに礼記に則っている」といった内容に他なりません。 偉大な学者である荻生徂徠は、その行為は正義ではあるが、法律上許されるものではなく、武士の礼儀に従って罰し、切腹させるのが最善の方法であると主張しました。 1 か月以上経って、将軍は 46 人の侍に切腹を命じました。そのうちの 1 人が行方不明になり、これによって文学や芸術の創造に想像力を働かせる余地も生まれました。実際、赤穂浪士たちは単に主君のために復讐したのではなく、名誉心のために、自分たちの名を上げ、家族の栄光をもたらそうとしたのです。予想通り、社会からは拍手喝采が起こり、彼らを正義の人として称賛したが、一方、済剛は暴君で悪名高い統治者として固定観念にとらわれていた。 赤穂事件の直後に『仮名手本忠臣蔵』として舞台化されました。 「かな」は日本語のアルファベット、「てべん」はテンプレート、「くあん」は倉庫を意味します。ここでのいわゆる宝は忠臣の宝物を指すため、「ちゅうちぇんく」と翻訳した人もいます。1つの倉庫にある忠臣の数は、忠臣が何人いるかを示しています。模倣が生まれて忠臣蔵型が形成され、日本文化を表現するキーワードにまでなった。 『仮名手本忠臣蔵』は義と人情に満ち、庶民に愛され、また世界が大きな舞台であるにもかかわらず、舞台を世界とみなす『菊と刀』などの作品で日本に対する誤った観察につながったようです。今でも『忠臣蔵』は書店でよく見かけますし、テレビでもよく放映されていますが、生徒にその問いに答えさせると、半数の生徒は「浅野内匠頭の宣」の読み方を答えられません。 復讐の手紙 江戸時代、全国の大名が将軍に参勤交代するため定期的に江戸に参勤し、主従関係を明確化して権力を集中させるために、人質同然で江戸に留まりました。封建領主たちは都(江戸)に上陸し、まるでパレードのように道中を練り歩きました。そのため、日本人は今でも街中で長距離走などの競技を見るのが好きです。このような浪費があれば、分離主義の属国には反乱を起こす資金がなくなるだろう。藩主たちは多数の武士を連れてきて、江戸の街は独身者で溢れ、吉原などの遊郭は栄えました。故郷に残った妻は、一瞬でも自分をコントロールできずに夫を裏切り、それが自らの死につながるかもしれない。 姦通した女性だけでなく、姦通した男性も殺されなければなりません。もし彼が逃げたなら、追い詰められて殺されなければなりません。これはおそらく、不倫に対する日本独特で無知な対処法です。私たちの武松は虎を殺し、兄の仇討ちのために姦夫と姦女を殺した英雄ですが、結局は法律を犯してしまいました。もし日本人が追って殺さなければ、面目を失い、笑われるだけだった。侍にとって、それは倫理的な問題ではなく、名誉の問題だった。 近松門左衛門の浄瑠璃『堀河橋太鼓』は、江戸に滞在中の彦九郎と、酒好きで酒に酔いしれて太鼓の名人と情事に及ぶ妻あたねの物語である。彦次郎が領主の大行進を追って故郷に帰ると、ある人が彦次郎の妻が姦通して妊娠しているとほのめかした。阿忠の妹の阿騰は妹を救うために、顔九朗に妻と離婚して再婚するよう頼んだ。厳九郎の妹の玉羅も関与が疑われ、離婚して実家に送り返された。彼女は義妹の不倫の証拠を提示し、阿忠は自殺した。彦九郎は息子の由良と阿天とともに京都まで追いかけ、太鼓打ちを殺した。 復讐を私的に解決することを許しているのは、おそらく警察力の不足に関係しているのだろう。江戸は人口100万人の大都市で、北町と南町に分かれていました。町奉行(教場院)は行政、司法、警察を担当し、それぞれに100人以上の巡査や警察官がいましたが、明らかに人数が足りず、法の執行は個人で行う必要がありました。また、各藩は独立しており、ある藩で殺人事件が起きても、警察は他の藩まで越境して犯人を追うことはできませんでしたが、個人は復讐のためなら全国を自由に旅することができました。 侍はサラリーマンです。復讐しようと決心したら、事前に幕府に許可を申請しなければなりません。父親や兄弟が殺されれば、侍の面目が損なわれるので、敵を殺すために地の果てまで追いかけるのです。幕府は、その資料を幕府の役人に提出して保管させ、その後、申請者を無給で停職処分にしたり、申請者に金銭を与えて紹介状を渡し、復讐に出かけることを許可したりした。 敵を殺してしまうと、捜査すべき事件となり、江戸であろうと他の領地であろうと、普通の殺人事件として扱われることはありません。ただし、申請は義務ではありません。登録されていない場合は、その後の審査が必要になります。復讐であれば無罪です。復讐が成功し、故郷に戻って職務に復帰すれば、賞賛されてさらに数石の米が給料として支給されることもある。父親が殺された場合、嫡子は復讐しない限り、地位と家業を継承することはできない。復讐する前に、敵は死んでしまいました。これは悪行が罰せられたからでも、神が助けてくれたからでもなく、復讐心が満たされず、領地に戻っても職務を再開できず、別の方法を探さなければならなかったからです。 復讐は正当な行為だが、簡単なことではなく、成功率も低い。 『日本書紀』は720年に書かれ、それ以降明治政府が禁書とするまでの1000年にわたる仇討ちの歴史を約140項目にわたって記している。記録された事件はまさに彼らが望んでいたものだった。成功率1%で計算すると、実際にはかなりの数の復讐行為があり、そのほとんどは江戸時代に起こった。 武家社会における仇討ちにも一定のルールや形式があり、それは小説以上に奇抜なものです。古代からあった仇討ちや切腹も、江戸時代特有の風習のようです。復讐は民俗的な習慣のようなもので、日本は復讐心に満ちた国だという印象を与えます。 1941年の日本による真珠湾攻撃は、1853年にアメリカが日本の鎖国政策を打開するために砲艦を使用したことに対する報復だったと一部のアメリカ人は考えている。 1945年に日本が敗戦すると、占領軍は報復を恐れて日本刀を没収し、復讐劇を禁止した。吉川英治の『宮本武蔵』などの侍小説も禁止された。 憎しみをありがとう 敵を作って殺されれば面目を失う。たとえ卑怯者と思われても、どんな手段を使ってでも逃げろと山鹿宗喬の『武術全書』は説いている。敵は逃げてしまい、今日のようにインターネットで人肉検索を行うことができなければ、復讐することは非常に困難です。かつて誰かが、復讐に必要な平均時間は約 10 年 3 か月だと計算しました。紳士が復讐をするのに遅すぎるということはないというのは本当です。 最も古い記録は、東北に7歳の時に同じ村の源八郎に母親を殺された少女がいたというものである。彼女は結婚して女性になったが、事件を知り、復讐を決意した。敵を知る従兄に付き添われて、彼女はあちこち捜索し、偶然にも源八郎が近くの寺の住職であることを発見した。彼女は、彼がお茶を飲んでいるところを背後から刺した。彼女はその時すでに60歳であった。領主は彼女を褒め、銀貨十枚を授け、こう尋ねました。「ようやく願いが叶いましたが、どう思いますか?」答えは、「私は憎しみにのみ感謝している」です。 復讐のために地の果てや空の果てまで旅をする苦難は、感情だけでは耐えられない。民俗学者の折口信夫はかつて「愛する者への復讐のためだけに復讐を続けるのは不可能だ」と言った。たとえ父親が間違っていたとしても、復讐はしなければならない。それは義務なのだ。仇討ちは本来個人的な事柄であるが、幕府の認可を得て江戸幕府に報告されると、その性質は私的なものから公的なものへと変わり、この仇討ちは必ず遂行されなければならない。 武士は家臣であり、臣下です。名誉は武士にとって個人的な問題であるだけでなく、彼が属する「家」、つまり封建領地の名誉と秩序にも関係します。復讐は美徳であると同時に責任でもあり、復讐者の運命は変わります。早く勝利を収めて帰還し、偉大な栄光を享受してください。さもなければ、復讐と放浪の人生を送ることになるでしょう。時間がすべてをすり減らし、当初の情熱は徐々に薄れ、代わりに私は復讐の義務に苦しめられ、孤独と痛みに苦しんでいます。並外れた意志の力がなければ、途中で諦めてしまうのは避けられません。 1833年、酒井家の家臣山本三右衛門が任務中に盗賊亀蔵に殺され、その娘礼弥は復讐を決意した。叔父の山本九郎右衛門は喜んで協力したが、李堯に同行を思いとどまらせた。彼は、弟の宇兵衛と自分、家臣の文吉が復讐に出かけ、敵を見つけたら李堯を呼ぶことに同意した。何年もかけていろいろな場所を旅した後、ようやく亀蔵が江戸に戻ってきたという知らせが届きました。九郎右衛門は神田橋の外の五字院原で亀蔵を捕らえた。九郎右衛門は李耀を呼び、亀蔵の縛めを解いた。李耀は「父の仇を討て」と叫び、亀蔵を三度切りつけた。亀は血を隠して夏草を汚す。 酒井家は輿を出して彼女を出迎え、彼女の正しい行いを讃えた。また、宇兵衛が途中で脱走し、遊郭にふけり、仇討ちに参加しなかったことなどを考慮し、李瑶が山本家を継ぐこととなった。九郎右衛門も米給が100石増された。森鴎外はこの事件を題材にした小説『五臓六腑の仇討ち』を著した。小説の中の弟は、復讐に燃える辛い時期に、こんなふうに人生を無駄にすることに何の意味があるのか、この苦難を乗り越えるために何に頼ればいいのか、神仏は本当に助けてくれるのか、と自問自答する。 復讐への道には多くの物語がある。復讐物語を好んで書く侍小説家の池場正太郎はこう言っている。「復讐者も敵も常に命の崖っぷちにいて、逃げたり、追いかけたり、死ぬ運命にある人生の局面を繰り広げており、その様相も多彩である。」二人だけではなく、彼らの家族、そして彼らを取り巻く社会的、経済的状況も関係しています。時には政治でも大きな問題が起こり、単なる復讐の描写ではなく、さまざまな環境で起こる人間ドラマの共通テーマとなっています。 武士小説には「命令に従って敵と戦う」ことや、主君の命令を実行すること、あるいは姦夫や姦女を殺すことなどが頻繁に登場し、復讐は許されない。殺人者は罪を逃れたかったため、その場で殺害することが身代わりの罰とみなされ、親族は復讐することができなかった。一度復讐をしたら、相手は復讐し返すことはできません。江戸時代初期、山形に阿倍波市左衛門という軽薄な男がいたが、松井三治に殺された。弥一左衛門の弟と右衛門は兄の仇討ちをし、三千を殺した。事態はそこで終わるはずだったが、三智の弟・権三郎が再び与右衛門を殺害した。彼と右衛門の甥の茂太郎は叔父の仇討ちをし、権三郎を殺した。権三郎の従弟である源八は再び繁太郎を追いかけたが、その後どうなったかは不明である。幕府は山形藩主を叱責した。「このまま殺人を続ければ、山形の男たちは皆死んでしまうのではないか?」 助田 誰かが復讐しようとしているのを見た場合、たとえ要請があっても、ヤメンランナーは助けることは許されず、現場を整備して事後の処理しかできない。復讐者も敵も、「助太刀」と呼ばれる助っ人を求めることができます。特に女性や子供が復讐を望む場合、通常は他人、もちろん亡くなった人と親しい関係にあり、敵に対して同じ憎しみを共有する人々に助けを求めなければなりません。あくまでも支援活動ですので、絶対に必要な場合以外は行動を起こしません。 津本陽は、歴史上有名な高田馬場決闘についての短編小説を書いています。1694年、村上庄左衛門はだらしなく、60歳の菅野六郎左衛門に叱責されました。村上庄左衛門は菅野に恨みを持ち、決闘を強要しました。武士である菅野には戦うしか選択肢がなかった。翌朝、高田馬場の決闘に行く前に、家来の市助に堀部安兵衛に手紙を届けさせ、最後の準備を託した。彼らは同じ武道学校出身の仲良しの友達です。 安秉衛はすぐに主人に休暇を願い出て、助けに駆けつけた。彼はすでにナイフの腕前で有名だったが、ナイフを使うのはこれが初めてだった。勇気を出すために途中でワインを数杯飲んだ。私たちが到着したとき、決闘はすでに始まっていました。村上は弟の三郎右衛門と槍術の師範である中津川由美に助けられた。村上と中津川は菅野と戦い、三郎右衛門は市助と戦う。菅野は複数の負傷を負っていた。安兵衛は怒りながら前に出て、三人の敵を次々に切り倒した。菅野さんは運ばれ、死亡した。その後、安兵衛は赤穂事件に参戦。47人の侍の中で唯一、事件前に人を殺した経験を持つ人物で、切腹したときまだ34歳だった。 彼らは酒を飲んだりチェスをしたりして仲たがいし、不倫のせいで敵対するようになった。最初からすべては愚かで、復讐も愚かな行為だった。この行為は個人の面子と孝行に支えられており、国家憎悪や民族憎悪にまで高めることはできず、私的憎悪に逃げ道を与えるため、解決のしようがない。私たちは時々正義について語りますが、それは本当に公平、つまり命には命をということを意味します。赤穂事件は結局、公平を求める行為だった。芥川賞を受賞した五味康雄の短編小説「失われた神」は、玄雲斎との決闘で父を殺され、玄雲斎の弟子となった鉄郎太が技を極め、下山の際、見送りに来た玄雲斎を撃退し殺害するという内容。愛や義理で常に揺れ動く、苦悩する中国武侠小説とは全く異なり、争いを生むより解決する方がよいという考えで思想を昇華させている。 福翁の二人の息子と家臣は森脇新右衛門への復讐を企てた。家臣はまず森脇家に潜入し、銃を扱う従者となり、森脇家の厚い信頼を得た。ある日、二人の息子が家臣に連れられて刃物商の格好でやって来ました。しかし、盛別は大柄で力も強い男だったので、二人の息子は攻めるのに苦労し、がっかりして立ち去った。家臣は告白した。「あなたは私の元主人の敵であり、あの二人の刃物商人は主人の息子です。彼らは長年復讐を企んでいましたが、昨日ようやくその機会が訪れたのに、実行に移せなかったのです。」私を殺してください。森脇は言った。「あなたは忠実な大臣だ。私はこれからもあなたを利用する。あなたは私を殺す機会を待つがいい。」機会があったにもかかわらず、家臣は復讐の気持ちを決して奮い起こすことができなかった。 3年後、森脇は言った。「これからは忠誠を捨てて、私の忠臣とならねばならない。」家臣は言った。「しかし、私はまだ昔の主君の子供たちの面倒を見たいのです。」辞任して出発してください。次の話は流通しておらず、召使が彼の主人のgrみを解決したかのように、問題は解決されていないようです。 フィールドの雑草 江戸将軍が衰退していたので、Conf教の学者Sakai Torazanは、復venのジレンマについての彼の感情を表現する詩を作曲しました。王の法律は廃止されず、大臣の忠誠心を失うことはできません。 1873年2月、明治政府法務大臣は、「敵の復venに関する禁止命令」を発行し、厳密に復venを禁止しました。命令は次のように述べています。殺害は国家のタブーであり、殺人者を罰することは政府の公的権力です。古代から父親と兄弟が子どもの義務であるという古い習慣がありました。彼は深い感情からそうするしかありませんでしたが、彼は個人的な怒りのために禁止を破り、私的な問題で公共の力を侵害したため、arbitrary意的な殺害の犯罪は避けることはできません。 啓蒙思想家の福沢裕辺は、1872年から1876年まで「学習への勧め」を書きました。そこでは、彼は復venの行為を断固として否定し、国家法の重要性について人々を真剣に啓発しました。当時、日本政府は徳川将軍、キラとアサノ家の家臣でした。保持者が判決が不公平だと思った場合、なぜ彼らは政府に苦情を申し立てなかったのですか?これは真のヒーローと呼ばれるものです。 過去には、私たちはこの原則として、私たちは国家法の深刻さを無視し、これは市民の義務の誤解であり、政府の権威を侵害しました。幸いなことに、当時の徳川政府はこれらの凶悪犯を罰し、問題はうまく終わった。もし彼らが赦された場合、キラ家は確かに復venをして、アコの家臣を殺すでしょう。家臣の家族は復venを取り、キラ家を攻撃しました。復venのサイクルは、両側のすべての家族や友人が一掃されるまで終わることはありません。これは、政治や法律のない社会がどのようなものであるかです。個人的に決定を下し、国に害を及ぼす人々はこのようなものであり、私たちは注意しなければなりません。 しかし、古い習慣は一生懸命死にます。刑法と刑法は1880年7月に公布されましたが、敵に対する復venはまだ良いことと見なされていました。その年の11月、川上Yukiyoshiという名前の27歳の兵士は、父親が殺されたことを知ったので、彼は許可なしにキャンプを去り、敵の頭を切り取り、亡くなった父親の墓の前に置き、彼は翌日に自分自身を降伏させました。物語は新聞で広く報告され、すぐに小説に変わり、舞台に立てられました。しかし、国の法律は彼を容認しませんでした。彼は刑務所で15年の刑を宣告され、釈放後さらに6年間住んでいて、老年で亡くなりました。 シン・ハセガワは1963年に亡くなりました。彼は小説家であり、劇作家のトレーニングクラス「shintakai」を設立しました。彼の晩年に書かれた日本の復venの奇妙な事例は、復venの特別な事例を説明しています。一部の人々は、復venは正義の分野で成長する雑草のようなものであると言います。サムライの小説はもともと日本の近代化に対する抵抗に基づいていたが、彼らはいわゆる正義や人間の感情を使ってこの雑草を支持するように、法律に反するようなものだった。 |
<<: 義和団の乱の解明:義和団の乱とはどのような組織だったのか?
>>: 清朝後期の権力の詳細な説明: 中国に最も大きな損害を与えたのは誰か?
推薦する
『紅楼夢』で賈震と秦克清はどんな役を演じますか?
今日、『Interesting History』の編集者は、曹雪芹によって恥の柱に釘付けにされた不運...
哲学書『春秋凡録』第12巻原文の鑑賞
陰陽の始まりと終わり 第48章天の道は終わり、また始まるので、北は天が終わり、始まる場所であり、陰陽...
敦煌の壁画にはどのような装飾模様がありますか?
敦煌の壁画にはどのような装飾模様があるか知りたいですか?実は、装飾模様は時代によって異なり、常に変化...
第58章:紀勝は天命を偽造して災いを起こそうとした裏切り者を弾劾した
『海公大紅袍全伝』は、清代の中国語で書かれた全60章からなる長編歴史ロマンス小説です。題名は「金一寨...
王維の古詩「肖禅師の宋丘寺を通り過ぎる」の本来の意味を鑑賞する
古詩「松丘庵の蕭禅師の傍を通り過ぎる」時代: 唐代著者 王維弟のアサンガと兄のアサンガとアサンガ、宋...
時代や場所が適切であることは言うまでもなく、なぜ項羽は人として劉邦と同じレベルではないのでしょうか?
古代では通信手段が未発達で、現代のハイテク電子機器も存在しなかったため、文字が情報を広める主な手段と...
『学者』ではファン・ジンはどのように描写されていますか?そしてなぜ彼は狂ってしまったのですか?
このプロットは原作の第 3 章に由来しており、科挙に合格した喜びのあまり范錦が狂ってしまうという話で...
『山行記 カッコウが飛び、早めの耕作を勧める』をどう評価するか?創作の背景は何ですか?
山の旅:カッコウが飛んで早めの耕作を勧める姚娜(清朝)カッコウが飛んで早めの耕作を促し、春の晴れたう...
『紅楼夢』の賈家では大晦日にどのような行事が行われましたか?
『紅楼夢』に登場する賈家は、百年の歴史を持つ名門貴族の家系です。知らなくても大丈夫です。『Inter...
『紅楼夢』の中で賈徴は子供たちをどのように教育したのでしょうか?なぜ学ぶ価値がないのでしょうか?
賈正は賈宝玉の父であり、賈正の母の次男であり、栄果屋敷の二代目主人です。今日は、興味深い歴史の編集者...
水滴拷問とはどのようなものですか?水滴拷問は本当に存在するのか?
水滴拷問といえば、何を思い浮かべますか?次にInteresting Historyの編集者が、関連す...
秦観の「良いことがやってくる - 夢の中で書いたもの」:この詩は詩人が滁州の酒税監督官に降格されたときに書かれたものである。
秦観(1049年 - 1100年9月17日)、字は少邑、別名は太虚、別名は淮海居士、漢口居士とも呼ば...
陸占元の妻は誰ですか?陸占元の妻何元軍のプロフィール
何元君(別名阿歓)は、金庸の武侠小説『射雁英雄の帰還』の登場人物。南帝の易登師の弟子である武三童の養...
四季:冬至はいつですか?冬至の紹介
冬至の由来と風習では、冬至の時期、由来、風習、冬至にまつわる詩などを掲載しています。以下は冬至の日付...
牛魔王は孫悟空と同等だと言えるのに、なぜ哪吒に勝てないのでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...