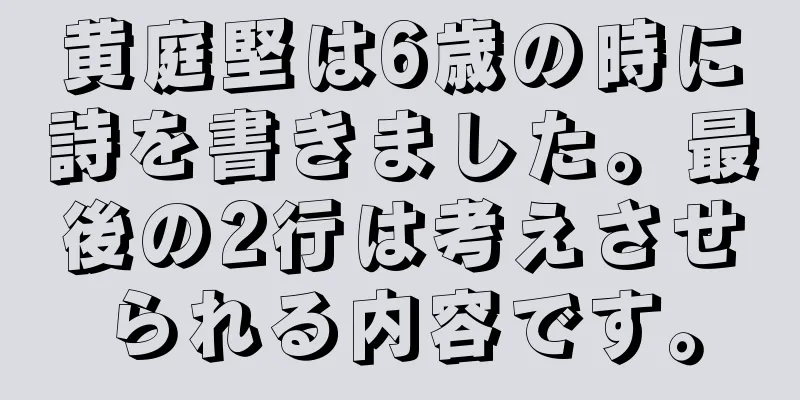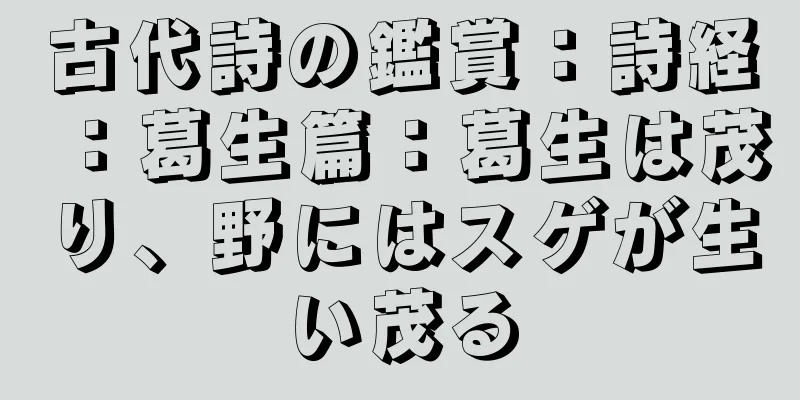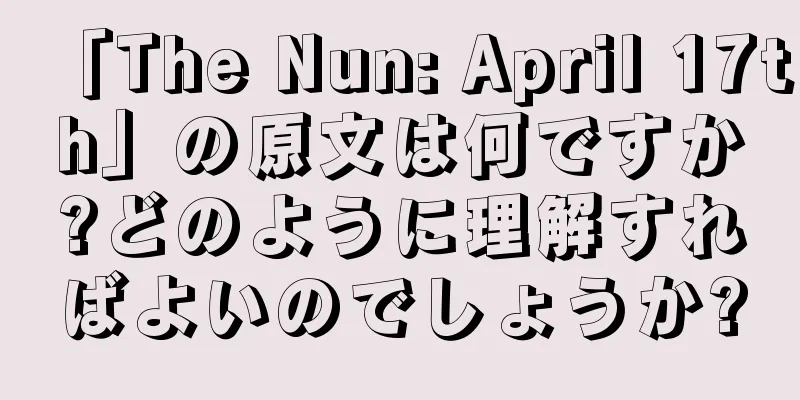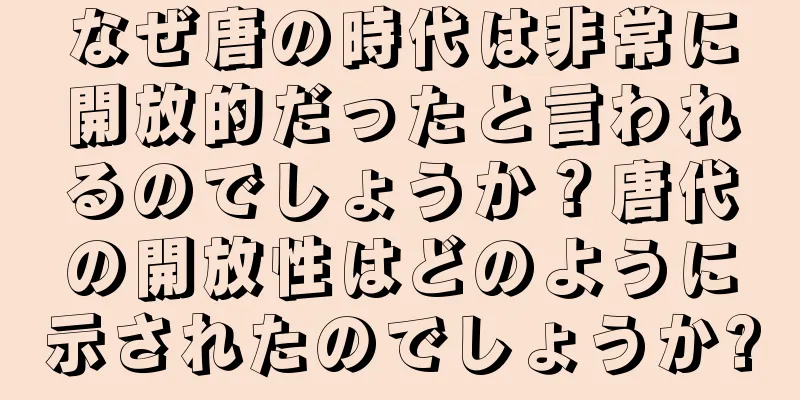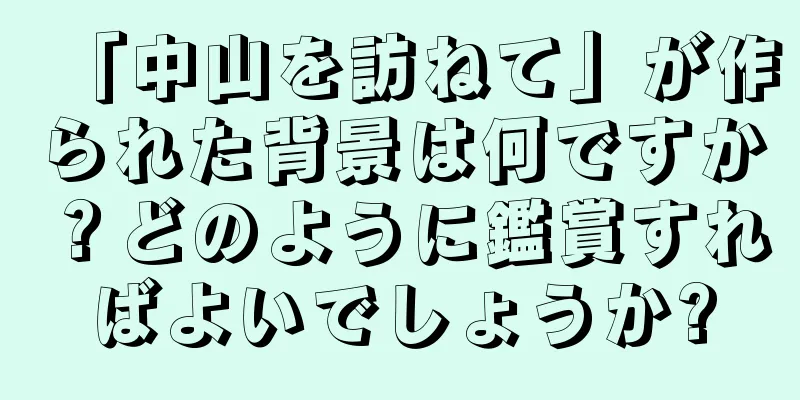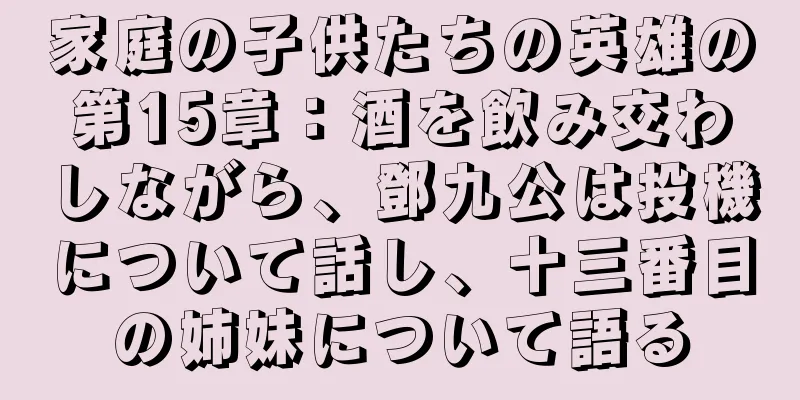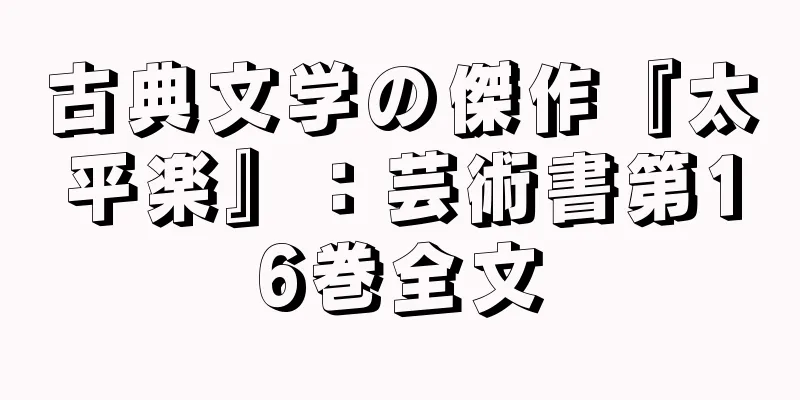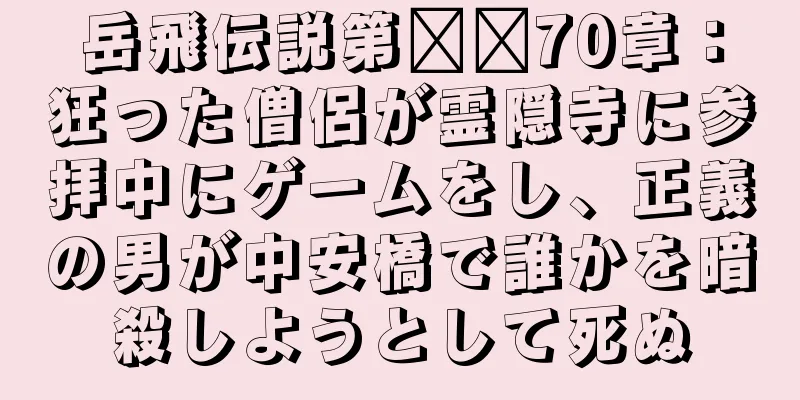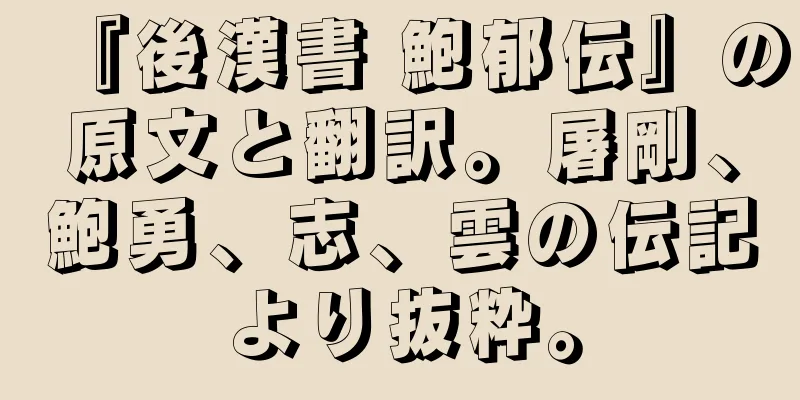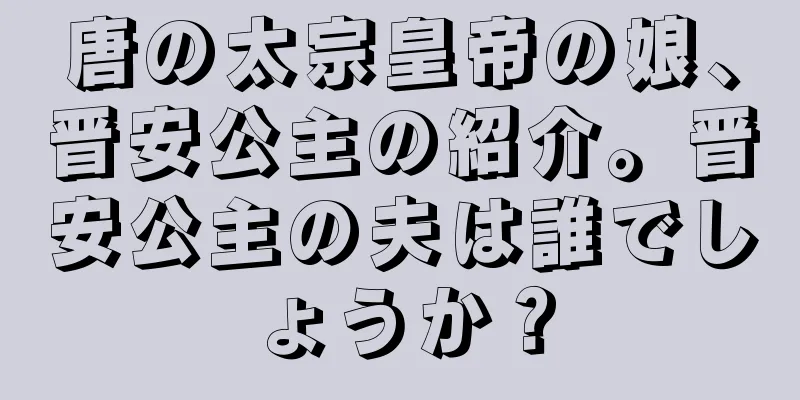宦官と公務員の違い:異なる貪欲さ
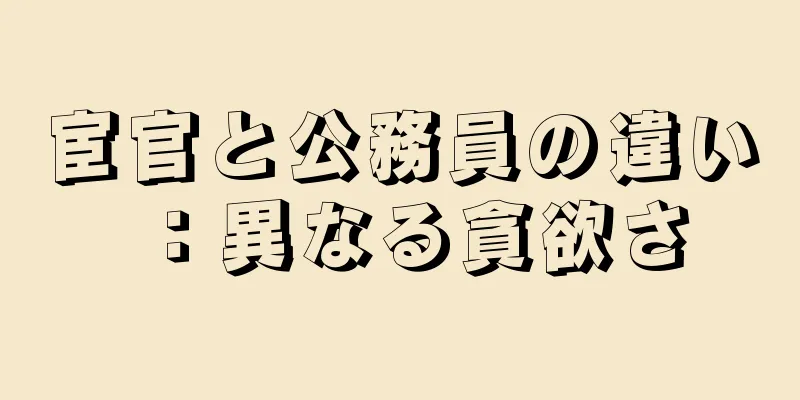
|
明朝の宦官による税務行政が政府を混乱させた 明代の宦官は一般的に質素な背景を持つ小さな家庭の出身であり、後継者がいなければ、その影響力と背景は官僚のそれとは比べものにならないほどでした。彼らの腐敗の手法は、往々にして単純かつ粗雑である。一般的には、賄賂など簡単に見破れるものばかりです。事件後、国(皇帝)は財産を没収し、指導者を処刑することで、多くの損失を回復することができました。 公務員は制度的腐敗に関与しており、海上禁止の推進はその最たる例である。宦官は海関を支配し、賄賂を受け取っていたため、国の税収が半分失われることも珍しくなかった。しかし、少なくとも収入の半分はまだ残っています。公務員はどうやってやるのでしょうか?海禁! まず第一に、公務員のほとんどは大地主であり、自らも製品の生産者です。次に、貿易を行う海上商人を支援します。しかし、これには 2 つの問題があります。 一つは海上税関が課す税金です。 第二に、他の民間商人との競争により利益が減少しました。 当時の文人の記録によれば、双嶼と月岡の人々の間では海外貿易がまだ非常に盛んであった。中小企業は、鉄の針などの商品を輸入し、港に到着すると、特別な船が輸送を提供していました。金額は、人数と商品の重量に基づいて計算されました(計算方法は、重量、種類、容積を考慮する非常に複雑なものでした)。日本への往復で、中小企業の利益は少なくとも2倍になりました。 公務員はどうやってそれをやったのでしょうか?海上禁止。 一つ目は脱税です。海上を禁じれば理論上は海外貿易はなくなり、海上関税局も廃止できます。公務員の船舶は税金を支払う必要がなくなる。 2つ目は、競合する個人投資家を取り締まることです。海上禁止令により個人投資家の取引が禁止されるため、大口投資家のキャラバンは自由に移動でき、ほぼ独占的な取引の利益は自然に倍増します。 実際、日本の海賊のその後の台頭も、文官や文人によって課された海上禁制と直接関係していた。大まかに言えば、海商が次第に大きくなり団結し始めたため、文官による統制が難しくなり、衝突の末に両者が戦うようになったと理解できます。倭寇の本当の始まりは、倭寇のリーダーである王志(安徽省出身の漢民族の男性)が数人の大海商(ほとんどが漢民族の男性)とグループを結成し、学者官僚の支配から脱却しようとしたときでした。その後、江南の朱という愚かな知事が月岡を占領して平定し、数人の日本海賊のリーダーを捕らえて殺害し、両者の対立は激化した。 彼が愚か者と呼ばれる理由は、学者官僚でさえ金の卵を産む鶏を飼い慣らそうとしただけなのに、愚か者は鶏を殺してしまったからです。自殺に追い込まれる結末も普通です。ちなみに、歴史上、日本の海賊のリーダーは数十人記録されています。名前だけから判断すると、彼らは全員中国人です。山田一郎なんて存在しない。したがって、日本の侵略者との戦いは、基本的に反侵略とは関係がありません。 このことから、宦官と公務員の違いが分かります。宦官がどんなに貪欲であっても、最大の分け前は皇帝のものとなります。宦官が職務をきちんと果たせず、皇帝が不満を抱くと、宦官は必ず死ぬでしょう。官僚たちは良心の呵責を全く感じず、皇帝はほとんど一銭も受け取らなかった。崇禎年間、北部では大災害が起こり人々が餓死する中、南部では農地を破壊して桑や茶を植え、ある年には茶税が一桁になったこともあった。これは制約のない公務員制度の必然的な結果です。 歴史書は官僚によって書かれ、国家の問題や政策の誤りは宦官のせいにされることが多かったが、時には皇帝のせいにされた。したがって、明朝の皇帝のほとんどは当然ながら良い皇帝ではなく、もちろん宦官はさらに悪かった。 追伸:明朝の皇帝の権力について話しましょう。重大な勅令には皇帝の印璽と内閣の承認が不可欠でした。内閣の承認なしに皇帝自らが発布した勅令は「中治」と呼ばれた。理論上は、明朝の役人はそれを違法な命令とみなして(例えば、宦官や皇帝の妻の親戚、その他の裏切り者によって発布されたと信じて)、執行を拒否する権利があった。歴史的に、明朝の役人たちはかつて皇帝の勅令を拒否することを良いことだと考えていた。逆に言えば、皇帝の印がなければ、内閣が発した命令に抵抗する者はほとんどいなかった。わかりやすい例は、内閣の命令により首都の守備隊が国王の防衛を拒否した宮殿移転のケースである。文官は「江斌の話には気をつけろ」という一言で軍将軍を完全に黙らせた。 |
<<: 食料は人民の第一の必需品である。中国の歴史は穀倉を守るための3000年の戦いである。
推薦する
古典文学の傑作「東遊記」第49話:東嬪が二度目の太子討伐を果たす
『東遊記』は、『山東八仙伝』や『山東八仙伝』としても知られ、全2巻、全56章から構成されています。作...
軍事著作「百戦百策」第3巻 昼戦全文と翻訳注
『百戦奇略』(原題『百戦奇法』)は、主に戦闘の原理と方法について論じた古代の軍事理論書であり、宋代以...
古代の恋愛物語の一つ:なぜ神福と雲娘の愛は不完全だったのか?
乾隆40年、沈福はまだ幼かった。ある日、彼は母親と一緒に家に帰り、祖母の家で生涯愛していた女性に初め...
「シックス・フット・レーン」はどうやって生まれたのですか? 「シックス・フット・レーン」はどんな物語から生まれたのですか?
今日は、Interesting Historyの編集者がLiuchifangについての記事をお届けし...
トゥ族の習慣 トゥ族の人々は日常生活でどのような習慣を持っていますか?
全国には192,573人のトゥ族がおり、虎竹トゥ族自治県、民和回族・トゥ族自治県、大同回族・トゥ族自...
なぜ劉邦は蕭何に殺されなかったのか?蕭何は劉邦の疑惑を呼ぶために何をしたのでしょうか?
劉邦が蕭何に殺されなかった理由は何だったのでしょうか?次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、...
道教における皇帝羌瘣とは誰ですか?雷震子ですか?
皆さんご存知の通り、道教は我が国の長い歴史を持つ土着の宗教です。では、道教における皇帝羌瘣とは誰でし...
『紅楼夢』では、賈家は裕福な家庭です。彼らの生活はどれほど優雅なのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
水滸伝では、胡三娘は戦闘のたびに敵を生きたまま捕らえていました。それはなぜでしょうか?
胡三娘は古典小説『水滸伝』の登場人物で、通称は「易章青」です。今日は、Interesting His...
紅楼夢第16章:賈元春が鳳凰宮の女王に選ばれ、秦景卿が若くして亡くなる
宝玉は外書院が片付いているのを見て、秦忠と夜に勉強することに同意したと伝えられている。残念ながら、秦...
本草綱目・第1巻・順序・五味優勢の具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
『紅楼夢』では、賈家の女性メイドは年間いくら稼いでいますか?
ご存知のように、「紅楼夢」の賈家は裕福な家庭です。では、このような裕福な家庭の女中は、1年間にどれく...
三国志の最後の三つの国が晋王朝に復帰したきっかけは何ですか?三国志の歴史における貴族政治!
三国志の最後の三家が晋に復帰したきっかけは?三国志の歴史における貴族政治!興味のある読者は編集者をフ...
唐寅の「鶏図」:鶏の態度と夜明けを告げる本能が十分に表現されている
唐寅(1470年3月6日 - 1524年1月7日)、号は伯虎、号は子維、別名は六如居士。蘇州府呉県南...
『紅楼夢』で、南安妃はなぜ賈夫人の80歳の誕生日に出席したのですか?
南安妃は小説『紅楼夢』にはあまり登場しないが、賈家の三女である丹春の運命を決定づける人物である。今日...