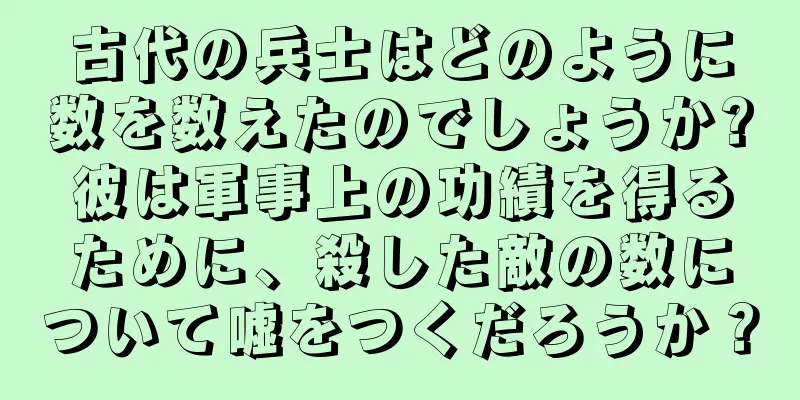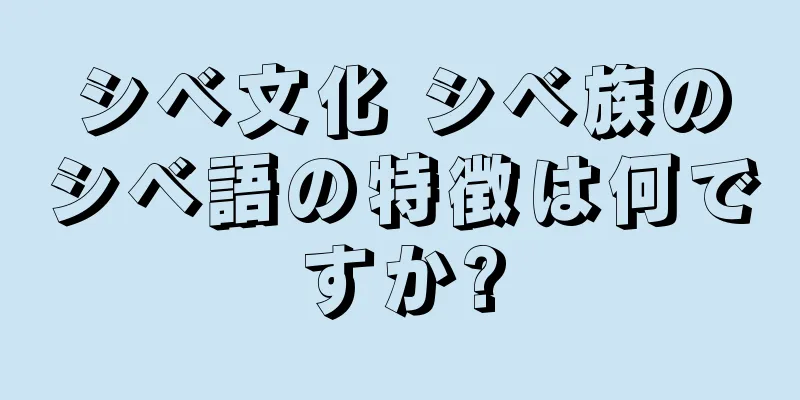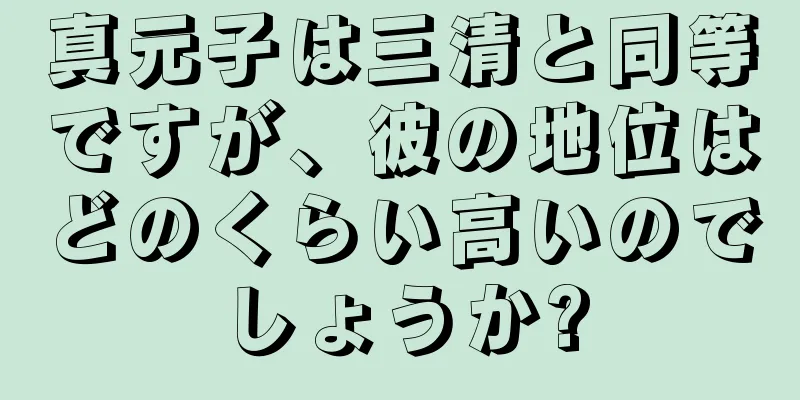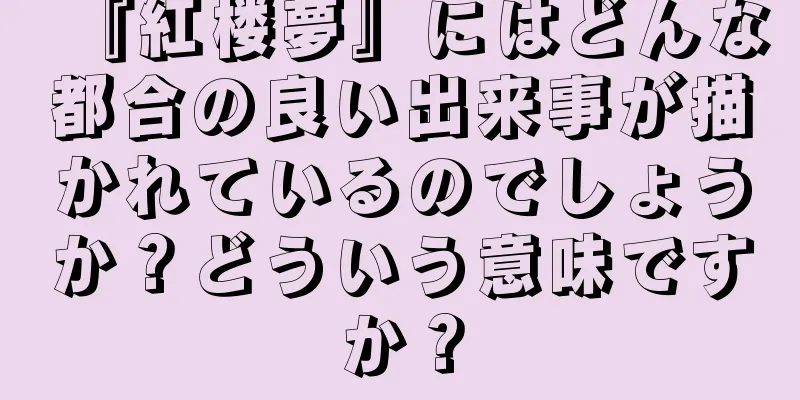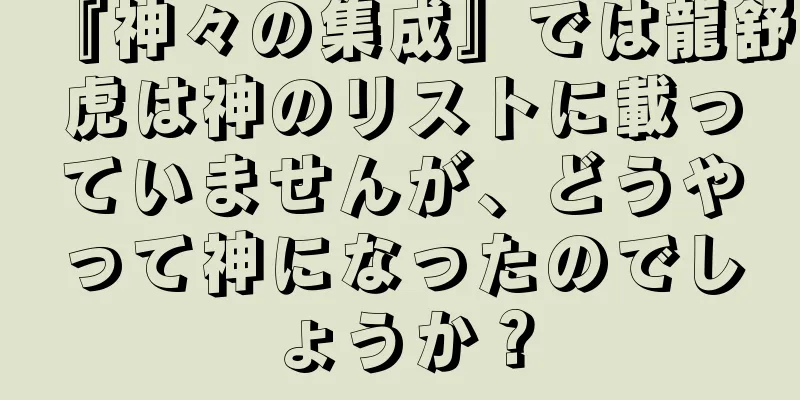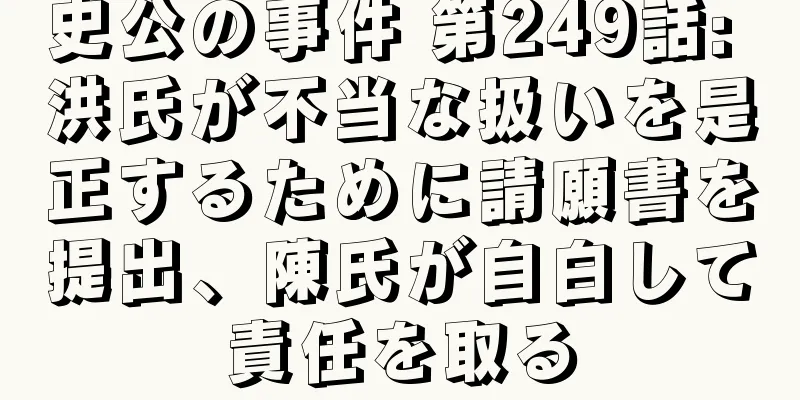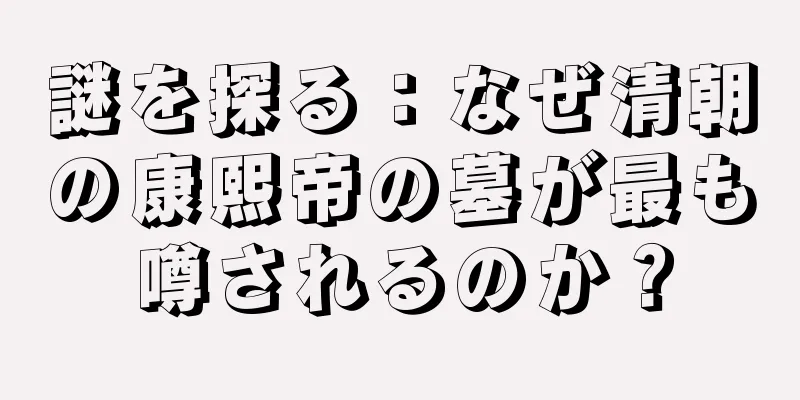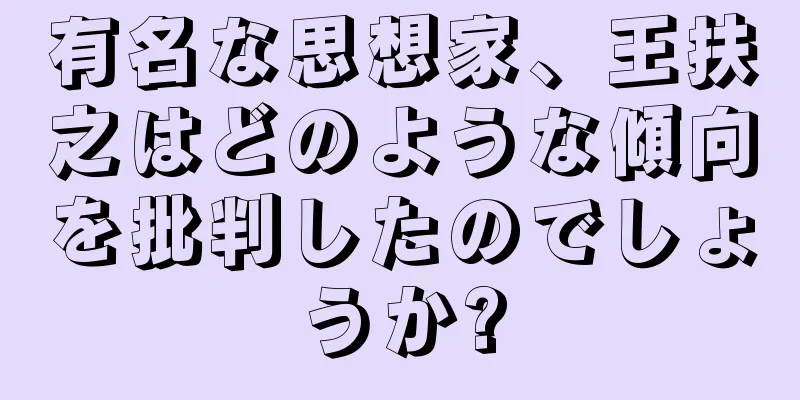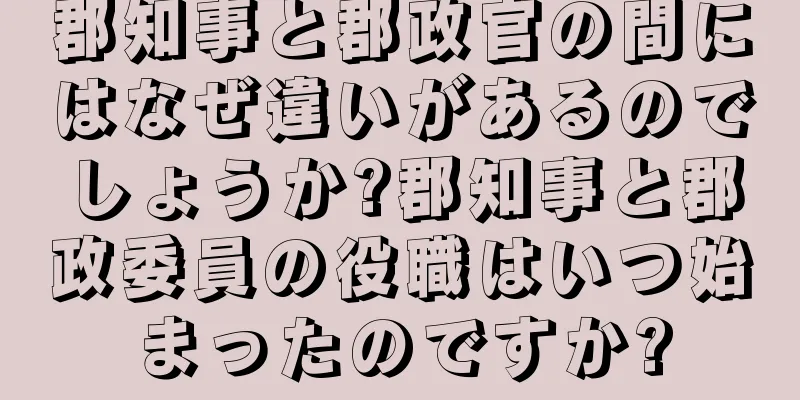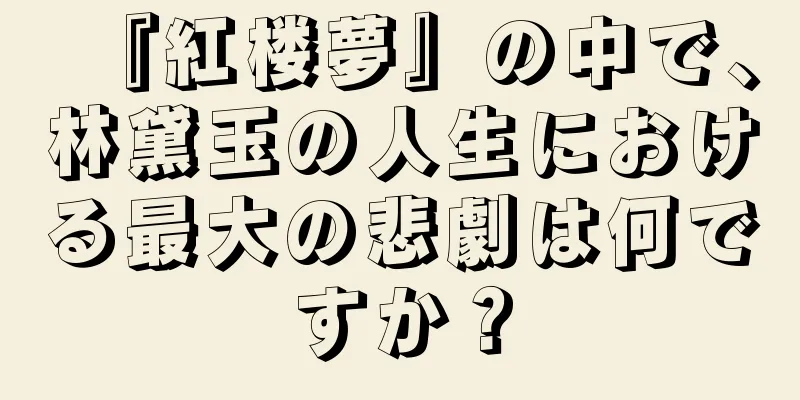明らかに:ベトナムはいかにして漢字を放棄したのか?
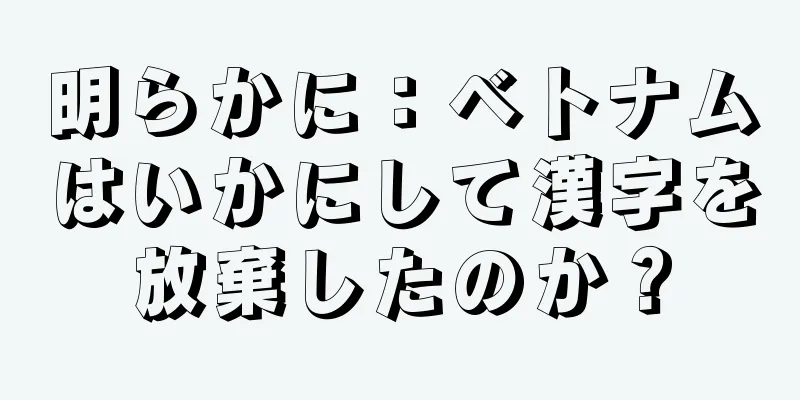
|
周知のとおり、歴史上、中国文化の広がりとともに、漢字もベトナム、朝鮮半島、日本などの周辺地域に広がり、「漢字文化圏」で流通する超民族的な表記体系となりました。しかし厳密に言えば、現在漢字を使用している国は中国と日本だけであり、ベトナムと朝鮮半島は漢字文化圏から撤退したようです。特にベトナムでは漢字が廃止されて100年近く経ち、ラテン語が公用語となっているなど、時代が変わってしまったのは残念です。 「儒教」の広がり 紀元前111年、漢軍は3度の遠征を行い、秦末期の戦争で嶺南から分離した南越王国を滅ぼした。その旧領土には7つの県が設けられ、そのうちの交趾県、九鎮県、日南県は現在のベトナムに位置している。当初、ここの住民は中原の文化に全く馴染みがなかった。 「交趾にはすべての県と州が設けられたが、それぞれの言語が異なり、何度も翻訳してやっと理解できた」と言われている。前漢時代に設置された県名からも、その様子がうかがえる。交趾県と九鎮県の17県のうち、「安定」だけが「名を賜った」漢名である。「北戴、西嶼、徐浦、五裂、五辺」などは、明らかに現地の方言の漢字を音訳したものに過ぎない。 しかし、長い「郡時代」(紀元前111年から紀元後939年、ベトナムでは「北方支配時代」として知られる)の間に、領主、役人、商人、職人、権力を失った老大臣、犯罪者を含む漢民族の集団がベトナムに移住した...「(ベトナム原住民の)フン王文化の発展は紀元前初期に突然停滞したようだった。考古学者が鍬でどこを掘っても、古代漢風のレンガ造りの墓があちこちに散らばっており、副葬品も漢風だった...」三国時代、有名な学者徐静は戦火から逃れるために会稽(現在の浙江省紹興市)から船に乗ることを選んだ。彼は途中で現在の広東省と福建省を通過したが、彼の目にはそこは荒野だった。「広大で人口の多い」交趾に到着して初めて、彼は再び「漢の地」を見た。 漢民族が南下し、徐々に中国文化が生まれました。漢代の任厳と西光はそれぞれ九鎮と交趾に「古典を教える学校を設立」し、漢字がベトナムに伝わった。当初、ベトナムでは儒教文化の普及の必要に応じて漢字が普及したため、ベトナムでは漢字は「儒教文字」とも呼ばれています。 隋代に科挙制度が先駆けて導入された後、唐代は隋の制度を継承し、進士や明経などの科挙を通じて広く人材を採用しました。安南では、各郡・各県に朝廷が運営する官立学校のほか、各種私立学校や農村学校も大きく発展した。これは、アンナンにおける漢字の普及に重要な役割を果たし、ベトナム語における「シナベトナム語発音」の形成につながりました。各漢字には対応する「シナベトナム語発音」があり、もちろん唐代の中原中国語の発音を受け継いでいます。例えば、『五代旧史』には「開平元年(後梁)天文台が太陽と日付を報告し、『戊』の字を『武』に改めるよう要請した」という記録があり、当時の中原での発音が変化していたことがわかります。タブーにより、「戊」は「武」と読まれるようになり、シナベトナム語の発音では「戊(mau)」と「武(vu)」の発音が今でも完全に異なります。 「永遠の安南文学の巨匠」江公福 唐代には、安南学者の漢字能力は非常に高いレベルに達していました。愛州臨南県(現在のベトナム、タンホア省アンディン県)出身の蒋公福は、中原で科挙に参加し最高の成績を収めた安南学者の代表的な人物でした。この男は科挙に合格して進士となり、唐の徳宗皇帝の時代には副長官、副宰相を務めた。 『全唐詩集』には『直言極論』と未完の『白雲春海歌』が含まれている。蒋公夫の中国文化レベルは非常に高く、中原の多くの知識人や政治家を凌駕している。ベトナムの学者は彼を「安南の永遠の文豪」とさえ尊敬している。 「子南」への挑戦 10 世紀にベトナムは属国としての地位を確立しました。しかし、現在では、中国文化の影響を1000年以上受け、漢字はベトナム社会のあらゆる分野に深く根付いています。 1070年、ベトナムの李朝はタンロン市に文廟を建立した。 1076年、李朝は孔子廟の隣に皇族や高官の子弟に漢字や文化の教育を施すための帝国書院を建設しました。その後、教育の範囲は徐々に拡大され、一般の優秀な子弟も受け入れるようになりました。 1075年、ベトナムは初の科挙を実施しました。科挙はその後、各王朝の官僚採用の重要な手段となりました。科挙の内容、形式、実施方法はすべて中国を参考にしたものです。ベトナムの科挙の800年の歴史の中で、科挙に合格した人は2,818人に上ります。 ベトナムの封建国家の正統な表記体系として、漢字はベトナムの学術と文学の伝統を徐々に育み、向上させていきました。リー・タイ・トーの『遷都令』はベトナムに現存する最古の歴史文書と文学作品とされ、レ・ヴァン・シウの『大越史』、ファン・フー・ティエンの『続大越史』、ウー・シーリャンの『大越全史』などの有名な歴史書はすべて漢字で書かれており、ベトナムの歴史は漢字の助けを借りて記録され、伝えられてきたと言えます。 しかし、日本や朝鮮半島と同様に、ベトナムでも漢字の使用において「自国の言語が中国の言語と異なる」という問題に直面していました。つまり、漢字では自国の言語を十分かつ正確に表現できないのです。日本と韓国にとっての解決策は、それぞれ「万葉仮名」と「伊読」を開発することでした。これは、漢字を表音記号として使用し、最終的にひらがな/カタカナと「訓民音」という独自の表音表記体系を形成しました。ベトナムは「南の言葉」を意味する「ノム」という異なるアプローチをとっている。 ダイ・ヴィエットの全歴史 13 世紀までに、ノム語は体系化され、文学作品で使用されるようになりました。ホー朝(1400-1407)の胡溪礼帝は『史記』をノム語に翻訳して宮廷女官に教え、大善朝(1771-1792)の阮慧帝は第三試験でノム語での解答を受験者に要求した。18世紀前半から19世紀前半にかけて、『徴兵女の歌』『宮中恨歌』『金恩允物語』などの古典名作が出版され、ノム語文学は最盛期を迎えた。 しかし、Nom は漢字をベースとしており、漢字全体または漢字の部首を借用し、音韻・意味・表意・借用文字の漢字作成方法を採用しています。各ノム文字は、その構成に 1 つ以上の漢字を必要とし、音韻意味文字、表意文字、借用語のいずれで構成されていても、そのほとんどは漢字の発音に従って読み取られます。たとえば、「五」という文字はノム語で「南五」と書かれ、「南 (nam)」は発音を表し、「五」は意味を表します。これは実は、初期の中国語で作られた「很」や広東語で作られた「丶」(的)と何ら変わりはなく、本質的には漢字の補足です。漢字とノム文字は、文字の構造的構成要素がまったく同じであるため、実際には同じ種類の文字であるとも言えます。 したがって、ノム文字を学ぶには、まず漢字を学ぶ必要があります。しかし、ノム文字は漢字よりも読み書きが難しく、覚えるのも難しいため、この「南方言語」は漢字に馴染みのない一般大衆には受け入れられない。科挙制度を経て漢字を習得したエリート層も、賢人の教えを伝える「儒教文字」を好んで使用したため、儒教文字が漢字の地位に取って代わることはなかった。 偶然に生まれた中国語の文字 実際、タイソン王朝がノム文字の普及を試みたのは1世紀も前のことであり、すでに漢字(およびノム文字)とはまったく異なる別の種類の文字が登場していました。 1615年1月18日、イタリアとポルトガルからの2人のカトリック宣教師がダナンにやって来て教会を建て、西洋の宣教師がベトナムで説教する先例を築いた。これらの宣教師は、西洋の先進的な知識と斬新な製品を持ち込み、病気を治したり悪霊を追い払う魔法の西洋医学の使い方を知っていたため、非常に魅力的で、信者をどんどん増やしていきました。 初期の西洋の宣教師たちは、できるだけ早く東アジアに神の「福音」を広めるために、有名なマテオ・リッチの先例に倣い、現地の文化を積極的に学びました。しかし、学者や官僚といった上流階級の道を歩んだマテオ・リッチとは異なり、後の宣教師たちは基本的に文盲の下層階級の人々をターゲットにしていたため、自分たちが作ったラテンアルファベットでベトナム語を記録し始めた。 1651年にフランスの宣教師アレクサンドル・ド・ロードによって編纂されたベトナム語・ポルトガル語・ラテン語辞書は、「国語」(Ch? Qu?c Ng?)の出現の重要な象徴と見なされています。ベトナムの司祭である杜光正は、慎重な調査と研究を経て、次のように結論づけた。「現在の国語は、17世紀にベトナムで活動していた多くのカトリック司祭(一部のベトナム人信者の黙認のもと)が共同で作り上げたものである。彼らは一般的にラテン文字を使用し、ポルトガル語、イタリア語、ギリシャ語の音と音調をある程度借用し、それらを組み合わせて私たちが使用する文字を作った。」 アヘン戦争後、中国南東部沿岸でも同様の事態が起こりました。当時の宣教師たちは、庶民に布教するために、現地の方言に基づいたローマ字をいくつか作りました。その中で最も影響力があったのは、20世紀まで使われていた閩南語の方言「百花子(Pe?h-oē-jī)」でした。中国南東部の沿岸地域と同様に、北京語の文字は当初、聖書の翻訳や教義資料の編集など、宗教的な場面でのみ使用されていました。その地位を大きく変えたのは、フランスの侵略でした。 1858年、フランス軍はダナンを砲撃し、ベトナムの扉を開き、ベトナム全土をフランスの植民地にするのに30年近くかかりました。侵略者は、漢字を中国とベトナムの歴史的、文化的絆であり、フランスの植民地支配の障害であるとみなしていたため、クオック・グエンの使用を強制し、「進歩と相容れない漢字が依然として思想を伝える唯一の手段である限り、変革を促進する最も効果的な方法は、フランス・安南派の学校を発展させ、漢字をラテン文字に置き換えることだ」と脅した。 1917年、フランス植民地当局は学校での漢字教育の完全廃止を大胆に命じ、1919年7月にはフエの傀儡宮廷が科挙制度の廃止を告げる「勅令」を発布し、漢字(およびそれに付随するノム文字)はベトナムの歴史舞台から退場を余儀なくされた。 ノム文学作品 しかし、フランス側の目的は「まず(漢字を)『国語』と呼ばれるヨーロッパ文字で書かれたアンナン語に置き換え、その後フランス語に置き換える」ことだけだった。国語文字の使用は、小学校低学年におけるベトナム語とフランス語のバイリンガル教育に限られています。小学校高学年以上では、フランス語が主要言語となります。 「長い年月を経て、遠い将来、ベトナム語は消滅し、この国の将来のフランス語にいくつかの言葉が残るかもしれない。ちょうどグアラニー語がブラジルのポルトガル語に多くの言葉を与えたのと同じように」と植民者たちはすでに騒ぎ立てている。 侵略者たちの北京語の文字に対する態度には裏の目的があり、北京語の文字自体にも欠点がないわけではなかった。例えば、f はなく ph が使われ、z を表すのに d が使われ、北京語の文字では一般的な d は ? で表されるなどである。しかし、北京語は習得しやすく理解しやすいため、国家の愛国者たちが革命思想を広め、国家の独立のために戦うための有用なツールとなった。 1945年9月2日、ハノイのバーディン広場で、ホー・チ・ミンは自ら国語で書いた独立宣言を読み上げ、ベトナム民主共和国の誕生を厳粛に宣言した。 その後すぐに、クオックグー語はベトナムの公用語となりました。 1946年に公布された憲法第18条には、「候補者は選挙権を持つ国民で、21歳以上で、中国語の読み書きができなければならない」とさえ規定されている。これは、ナショナリズムによる「脱中国化」に完全に起因しているわけではないようだ。ホー・チミンは中国語と漢字に精通していたし、もう一人の指導者である張正の名前もこの二つの漢字から直接来ている。さらに、毛沢東主席でさえかつては「ピンインはより便利な表記法だ。漢字は複雑で難解すぎる。現在は簡略化された改革しか行っていないが、将来的には根本的な改革を行わなければならないだろう」と考えていた。 (毛沢東書簡選集、454ページ) 現在ベトナムでは、クオックグー語の公用語としての地位は揺るぎないものとなっているが、ノム語は一握りの専門家しか読めない死語となっている。漢字については、意外にもベトナムの僧侶や尼僧の書斎にまだ残っている。中国仏教の経典はすべて中国語で書かれているからだ。かつてベトナムには宗教の力を借りて国語が入り、現在も漢字が宗教の力を借りてベトナムで生き残っている。これが歴史の不思議さなのかもしれない。 参考文献: 蘇才瓊:「ベトナム語の表記の変化と国民意識の発展」、済南大学修士論文、2010年 梁茂華:「ベトナム語の文字の発展史に関する研究」、鄭州大学博士論文、2014年 |
>>: 阿子の師匠は誰ですか?阿子の師匠、丁春秋のプロフィール
推薦する
「彭氏の事件」第1章:彭氏は三河県に赴任し、途中で麗江寺を個人的に訪問した。
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
嘉慶自身は重い歴史的負担を負っているのだろうか? 『明鑑』を編纂した経緯は?
清朝の国力の絶頂期は「康熙・雍正・乾隆の盛期」であると一般に認識されています。しかし、乾隆帝が亡くな...
『二十四史』第77巻『明代史』原文
◎食べ物1 『記録』には「富は地から、法は天から採る。富国の基礎は農業と養蚕にある」とある。明代初期...
万里の長城の歴史的意義:それは中国国家の強大な力を象徴しています!
秦漢時代から明清時代にかけて、万里の長城沿いの多くの関所は、農業と畜産という2大経済・文化システムに...
『紅楼夢』で西仁はどのようにして賈家の一流メイドになったのでしょうか?
希仁は『紅楼夢』の重要キャラクターです。彼女は『金陵十二美女』第二巻の二人目であり、宝玉の部屋のメイ...
『西遊記』で孫悟空のクラスメイトだった方村山の人たちは結局どこへ行ったのでしょうか?
『西遊記』で孫悟空の同級生だった方村山の人たちは結局どこへ行ったのか知りたいですか?次の興味深い歴史...
『南湘子 秋の夕暮れの村の暮らし』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
南郷子:秋の村那蘭興徳(清朝)冷たい小川は赤い葉で満たされ、空っぽの山々に沿ってすべての木々は高く成...
明代志農(選集):陳翔著全文と翻訳注、情報部
『シンクタンク全集』は、明の天啓6年(1626年)に初めて編纂された。この本には、秦以前の時代から明...
『呉越春秋』第9巻の郭建の陰謀の主なストーリーは何ですか?
郭堅の治世10年2月、越王は将来について深く考えていました。呉に辱められた後、天の祝福を受けて越国を...
王さんの経歴は何ですか?なぜ彼女は側室ほど寵愛されないのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が王夫人についての記事をお届けします。ぜひお読...
「姪の陸倫が一緒に居てくれて嬉しい」は、司空書が書いたものです。二人とも大理時代の十傑の学者の一人です。
司空書(720-790)、号文初(『唐人伝』では文明と表記、ここでは『新唐書』による)、広平(現在の...
呂桂孟の「西梅と春の晩に酔い覚める」:この詩は酔うことの喜びについて書かれており、気楽で奔放です。
呂帰孟(? - 881年頃)、号は呂王、号は天水子、江湖三人、伏里献生。常熟(現在の江蘇省蘇州)の人...
太平広記・第35巻・仙人・馮大良をどのように翻訳しますか?原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...
『紅楼夢』で、賈大如は寧国公の息子ですか?なぜ彼はそんなに貧しいのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
冷香丸とは何ですか?薛宝柴はなぜこれを食べたいのでしょうか?
みなさんこんにちは。Interesting Historyの編集者です。今日は薛宝柴の物語をお話しし...