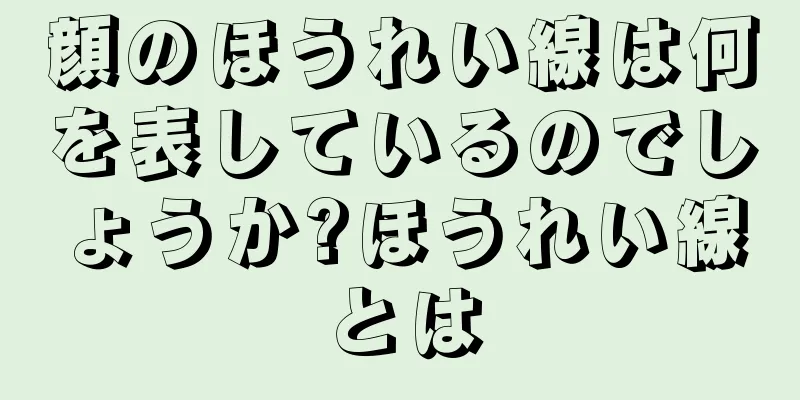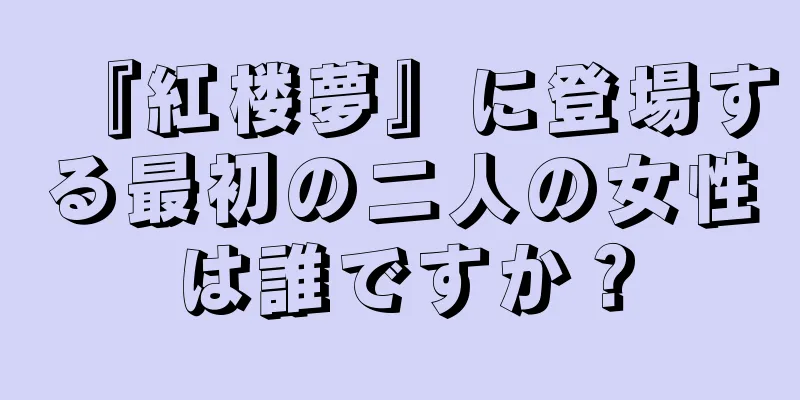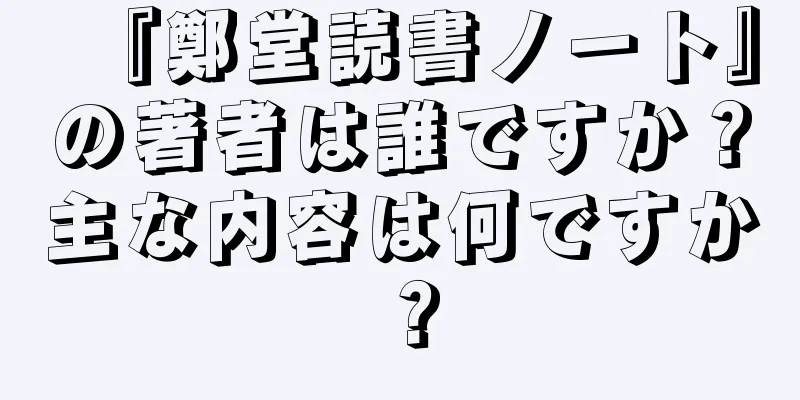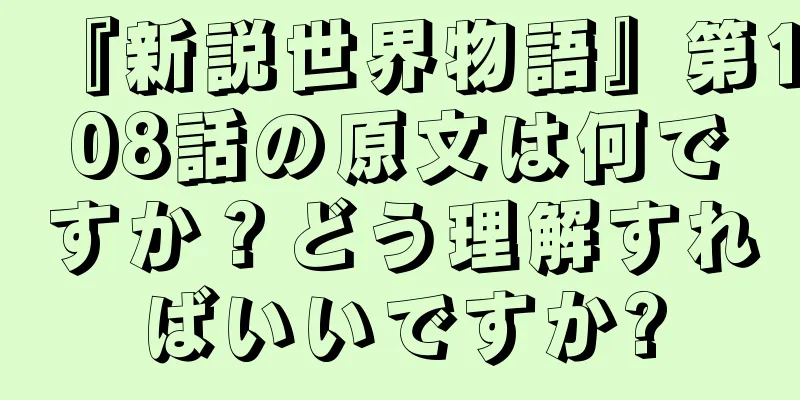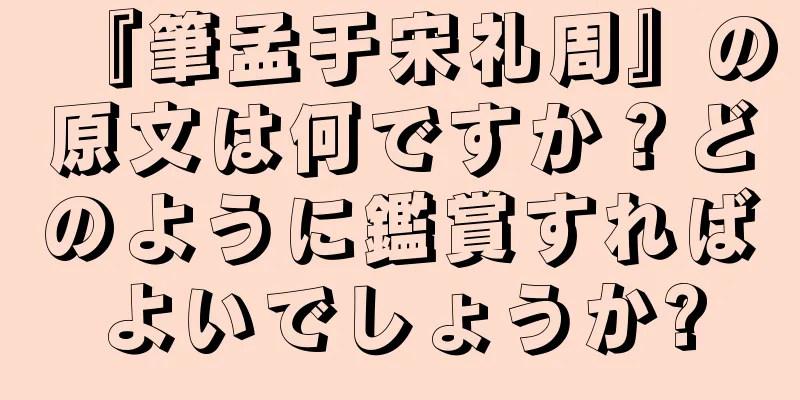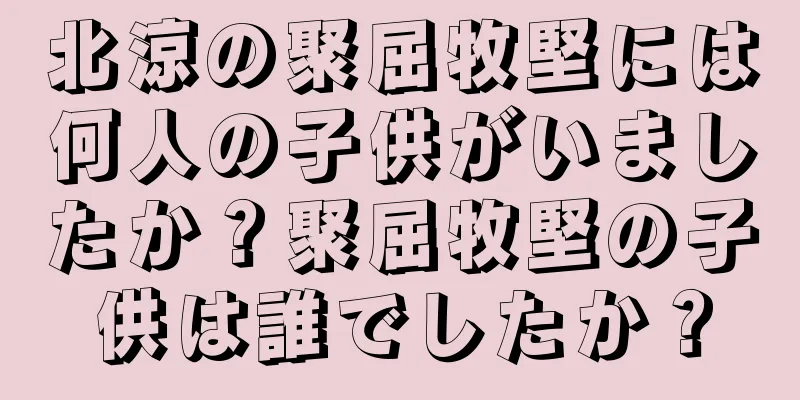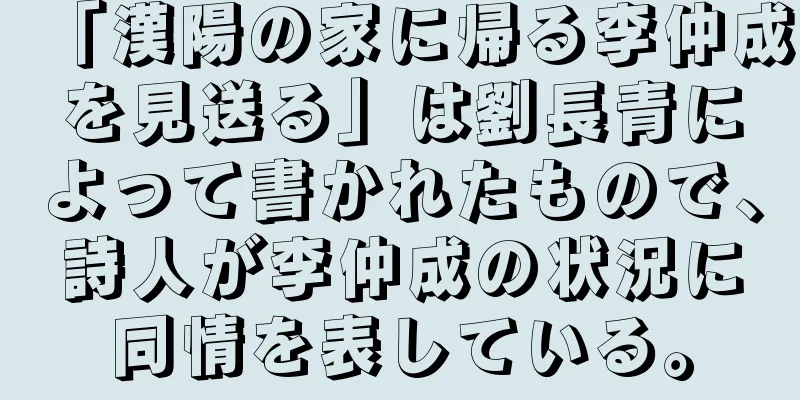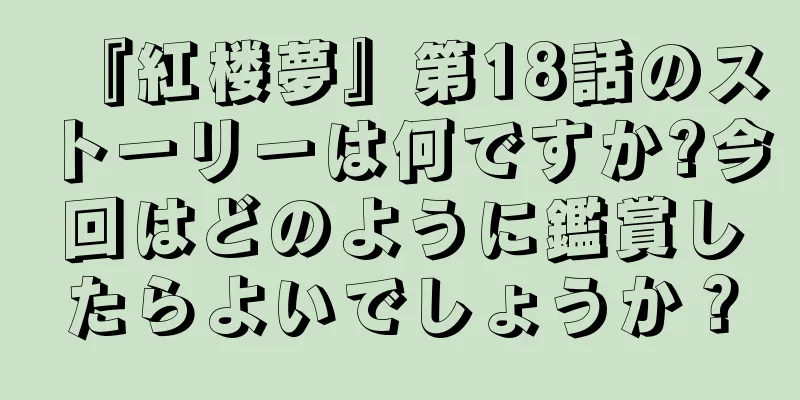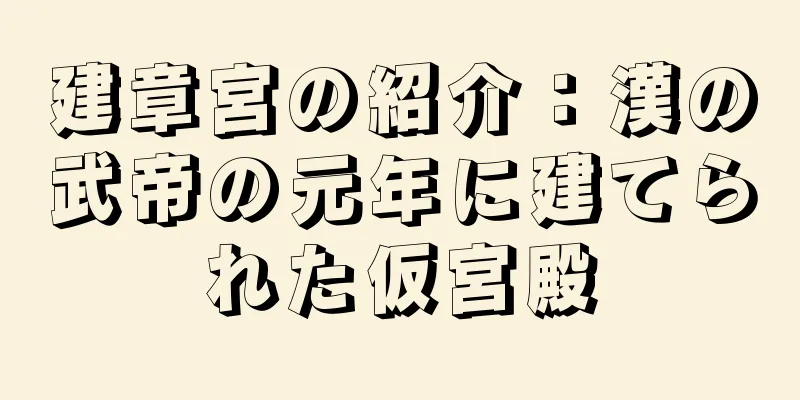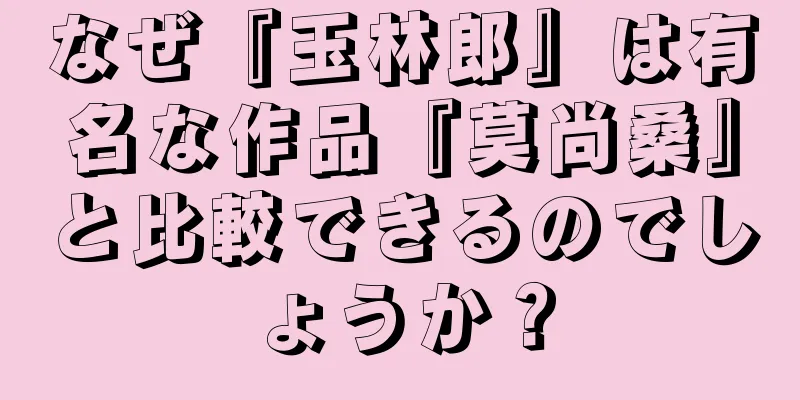古代における「教師」の称号は何でしたか?すでにあまり馴染みのないものもあります
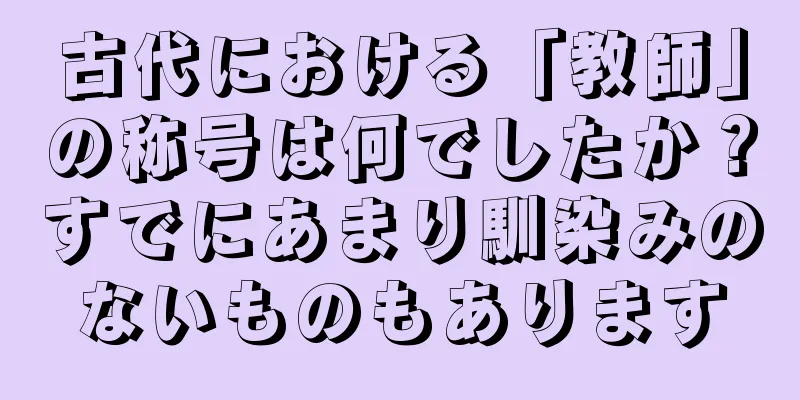
|
「教師」という言葉は学校で教える人の肩書きであり、「教えること、知識を伝えること、疑問を解決すること」が教師の基本的な職務です。 「先生」とは、もともとは年老いて経験を積んだ学者や学問を教える人を指し、例えば『史記』には「斉の襄王の治世中、荀子は最も有名な先生であった」とある。後には、生徒を教える人も「先生」と呼ばれるようになった。例えば、晋の袁浩文の『甥の孫伯安に捧ぐ』には「伯安は小学校に入学したが、とても頭が良く聡明であった。文章を組み立てる天賦の才があり、その言葉は先生を驚かせた」とある。明清時代以降、教師は一般的に「先生」と呼ばれるようになった。 19世紀末、中国近代教育の創始者とされる何子遠氏と1911年革命の功労者たちは「西洋の学問」を中国に導入し、新式の学校を設立した後、「学生行動規範」で教師の呼称を「先生」と明確に定義し始めた。しかし、中華民国時代には大多数の学生が「先生」を「先生」に変更することに同意し始め、今日まで使用されている。 実際、「先生」以外にも、古代には先生を表す呼び名がたくさんあり、その中にはかなり馴染みのないものもあります。 1. 教師:教師を尊敬される年長者としてみなすことを意味し、古代では教師に対する尊敬称号の 1 つでした。 『韓非子・五蘊』:「今、才能のない子供がいます。両親は怒っていますが、彼は変わりません。村人たちは彼を叱っていますが、彼は動きません。先生は彼に教えていますが、彼は変わりません。もし彼に両親の愛情、村人たちの振る舞い、先生の知恵があり、この3つの美徳が彼に加われば、彼はまったく動かず、足の毛も変わりません。」 2. 師匠:もともとは弟子たちが孔子に敬意を表して使った呼び名です。後に師匠は教師に対する敬意を表す呼び名となりました。論語:子章:「師は常に学ぶことを怠らない。それでは、永遠の師はなぜ必要か?」 3. 山章:歴代の山学院の主任教師の称号で、その由来は「景祥進師」に由来する。五代十国時代、蒋衛東は衡山に隠棲して教師を務め、多くの弟子がいたため「山章」と呼ばれ尊敬されていた。それ以来、「山章」は教師に対する尊敬の称号となった。元代には、各道・州・県に校長を置く学院が設けられていた。明・清の時代は元制を踏襲し、乾隆年間に「院」に改称され、清末期でも「山章」と呼ばれていた。科挙制度の廃止後、学問所は学校と改名され、校長という称号も廃止された。 4. 師匠:古代における教師の総称。 「師」という言葉は、もともと太師、太夫、少師、少夫などの官職の総称でした。これらの役職は王子の教育を担当していたため、師は教師の同義語にもなりました。 『古梁伝・昭公19年』:「子供が縛られて先生のところに行かないのは、父親のせいだ。」先生という称号は今でも使われているが、一般的にはビジネス、オペラ、演劇などの業界の教師を指す。 5. 師匠: 昔から「師匠は必ず父となる」ということわざがあり、師匠は敬意を込めて師匠とも呼ばれます。 「呂氏春秋・勉学の奨励」:「先生に仕えることは、父に仕えることと同じである。」 6. 先生: 西賓とも呼ばれ、教師に対する尊敬の称号です。その由来は次のような暗喩です。漢の明帝、劉荘が皇太子だったとき、彼は桓容を師と崇めていました。彼は即位した後も桓容を非常に尊敬し、桓容が住んでいた太昌邸によく行き、桓容の講義を聞きました。漢の時代、人々は床に座り、最も名誉ある席は西と東を向いた席でした。漢の明帝は皇帝であったが、悟りを開いた師に対する敬意を示すため、桓容のために西と東を向いた席を設けた。それ以来、「西熙」または「西斌」は師に対する敬称となった。 7. 司宝: もともとは古代の皇帝を補佐し、皇室の子供たちを教育する役人でした。彼は教師であり保護者でもあり、総称して「司宝」と呼ばれていました。 『易経・西辞・下』には「師がいないと、父母の前にいるようなものだ」とある。後に、この表現は師全般を指すようになった。清朝の龔子真は『包小』の中で次のように書いている。「小学とは子どもにとっての学問である。学問とは父、兄、教師、保護者の傍らに仕え、彼らの助言者となることである。」 8. グランドマスター:元々は王族の教育を担当する役人。 『漢書・平帝記』には「上皇以来の王族には、氏族名と郡に応じて師匠がいて、彼らを矯正し、教育した」と記されている。その後、彼は次第に誰からも尊敬され、模範とされる人物へと成長していった。北宋時代の孔平忠の『譚園』第3巻には、「石潔は、号を寿道といい、崔来山の隠者であった。文学と学問の達人で、民衆からは崔来先生と呼ばれていた」と記されている。 9. 教授: 今日、教授という言葉は高等教育システムにおける称号ですが、古代帝国アカデミーでは講義を行うのは博士課程の学生でした。中国では、漢代と唐代の両時代に、皇室学院に博士課程の学生がいた。宋代には、中央学校と地方学校に教授が置かれるようになった。元代には、各省、州、県の儒学の学院や、明代と清代の県立学校にも教授がいた。 10. ティーチングアシスタント: インペリアルカレッジで教える教師。西晋の咸寧2年に、帝国書院が設立され、書院の学長と博士を調整して儒教の古典を教える助教授が任命されました。それ以来、いくつかの王朝を除いて、帝室には必ず国子助教授、太学助教授、思門助教授、光文助教授などと呼ばれる古典の助教授がいた。 11. 薛伯:もともとは唐代の県郡の官吏。唐代には、各県と各郡に1人の儒学者がおり、学生に五経を教える責任がありました。後に、学官は一般に学博士と呼ばれるようになりました。清代の小説家、呉敬子の『士人記』第36章には、「この男は他とは全く違う。学問の精神が欠けているだけでなく、学者としての精神も欠けている」とある。 12. 講師:もともとは経典を教える役人。 『後漢書 儒学者伝』には、「彼はまた、非常に才能のある学生に『古文文献』、『毛詩』、『古梁』、『左伝』を学ぶよう命じた。彼は学官を置かなかったが、優秀な学生を講師に昇進させた」と記されている。 13. 教養:もともとは宋代の都の小学校や武術学校の役人の名。明・清の時代に、この県は県内最高位の教育機関として「県書院」を設立し、1人の教師と数人の講師を擁した。メンターとは教師を補助するアシスタントです。地方学校の教師のほとんどは進士出身者であり、朝廷から直接任命された。 『明代史官録四』には「儒教:州には教授1人、講師4人。州には校長1人、講師3人。県には講師1人、講師2人。教授、校長、講師は管轄下の学生の教育に責任を持ち、講師は彼らを補佐する」とある。 14. サー: 「サー」という言葉の本来の意味は、最初に生まれた人であり、年長者や知識のある人を指すようになりました。 『孟子』の「先生、なぜこうおっしゃるのですか」や『国策』の「先生、どうぞお座りください。なぜこうしなければならないのですか」という文章では、「先生」は知識と徳を備えた年長者に対して使われています。その後、「Sir」という言葉は教育に携わる人を意味するようになりました。 『礼記:屈礼尚』:「師に従うときは、道を渡って他の人と話をしてはならない。」 鄭玄の注釈:「師とは教える老人である。」 |
<<: イヤリングの起源:もともとは古代の女性が逃げないようにするために身に着けていた「拷問器具」だった
>>: 文学と歴史事典:「浮大白」は古代ではどういう意味ですか?
推薦する
「Dziビーズ」の価格が急騰しているのはなぜですか?本物のDziビーズと偽物のDziビーズを見分けるにはどうすればいいですか?
「Dziビーズ」の価格はなぜ急騰したのでしょうか?本物のDziビーズと偽物のDziビーズを見分けるに...
それぞれ異なる状況と感情を持つ李清昭の蓮に関する3つの詩のレビュー
みなさんこんにちは。私は『Interesting History』の編集者です。李清昭については、み...
星堂伝第57章:噂を広めて四将軍を追い払い、高山王を威嚇する力を見せつける
小説『大唐興隆』は『大隋唐』『大唐興隆全物語』とも呼ばれています。関連する古典小説には、清代乾隆年間...
英雄伝第21章:燕王は弱いふりをして敵を欺き、張羽は勇敢さを頼りに戦いで死ぬ
『続英雄譚』は、明代の無名の作者(紀真倫という説もある)によって書かれた長編小説で、明代の万暦年間に...
「北の鳥」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
ノーザンバード李尚閔(唐代)私は巴河が大好きなので、瘴気は気になりません。カッコウに会えるなら、オオ...
于玄吉の「江陵より子安に哀悼の手紙を送る」:この詩は簡単に5字の四行詩に短縮できる。
于玄姫は唐代末期の女性詩人で、長安(現在の陝西省西安市)に生まれた。彼女の本名は于有為、雅号は慧蘭。...
『清明』の中で杜牧はどのような感情を表現しているのでしょうか?清明節の詩の鑑賞
杜牧の「清明」はどのような感情を表現しているのでしょうか?芸術の面から見ると、この詩は低いところから...
『詩経・国風・全語』の原文は何ですか?どうやって鑑賞すればいいのでしょうか?
力匿名(秦以前)私の場合、別荘が忙しすぎて、残り物がありません。ああ、私はその権威を受け入れません!...
易軒志全文、第20巻、南宋奇談集
『易軒志』は、南宋時代の洪邁が漢文で書いた奇談集である。本のタイトルは『列子唐文』から来ている。『山...
エウェンキ族の礼儀作法の紹介 エウェンキ族の礼儀作法の誕生の儀式
トナカイ飼育を行うエウェンキ族の女性が出産を控えると、分娩室として一時的な「不死の柱」を建てる。分娩...
前漢時代の五朱銭の特徴は何ですか?前漢時代の五朱銭の特徴の詳細な説明
西漢の五斤銭にはどんな特徴があるか知りたいですか?貨幣の乱造による貨幣制度の混乱と呉楚の乱を考慮して...
諸葛亮は優れた戦略で有名ですよね?なぜ関羽を救出するために軍隊を派遣しなかったのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
魏延の「紫霧谷戦略」には5,000人の精鋭兵士しか必要ありませんでした。なぜ諸葛亮はそれを試そうとしなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
唐代の詩「奉済郵便局の燕氏を再び送る」の四韻をどのように鑑賞すればよいでしょうか。杜甫はこの詩の中でどのような比喩を用いているのでしょうか。
鳳輦宿場が唐代の杜甫の『延公四韻』を再送、以下興味深い歴史編集者が詳しい紹介を持ってきますので、見て...
宋代の詩「青春の旅・端午節に黄寿虚君有に贈る」を鑑賞します。この詩はどのような場面を描いていますか?
若い旅人 - 端午節の贈り物、黄寿虚君有 [宋代] 蘇軾、次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介を持って...