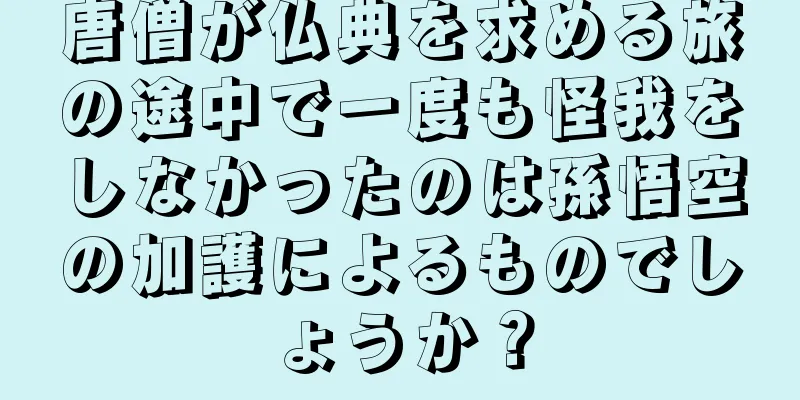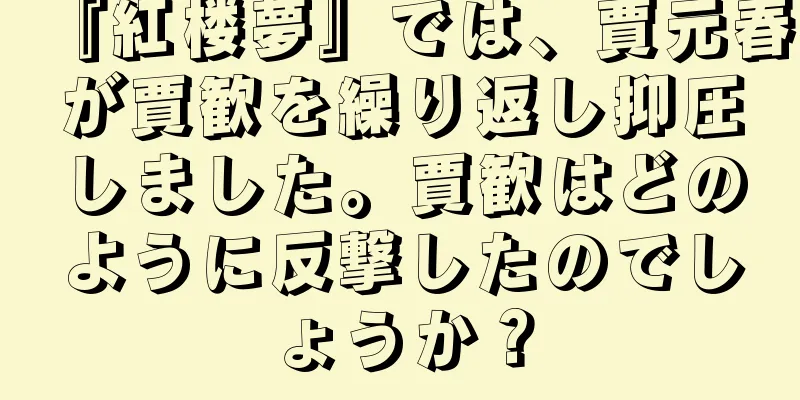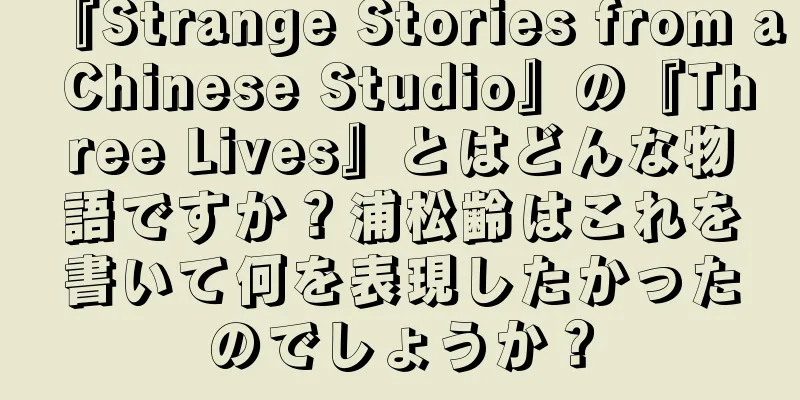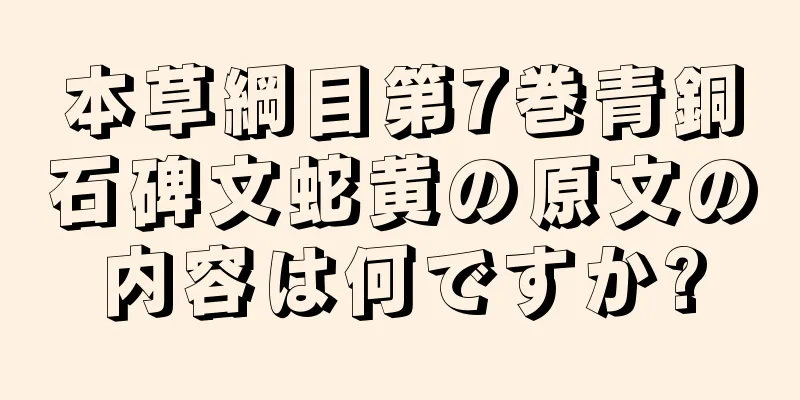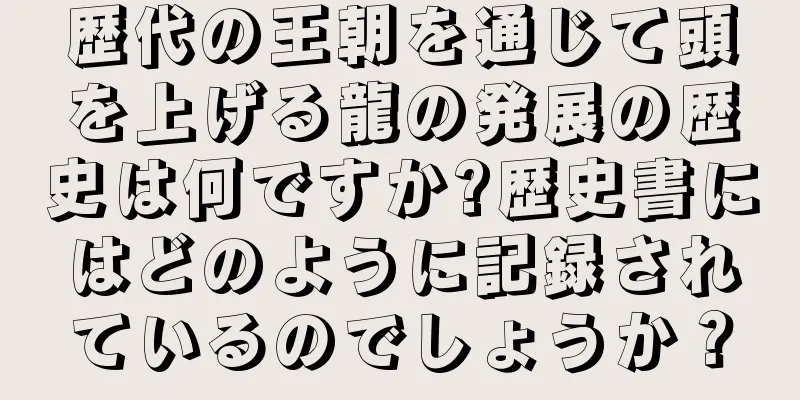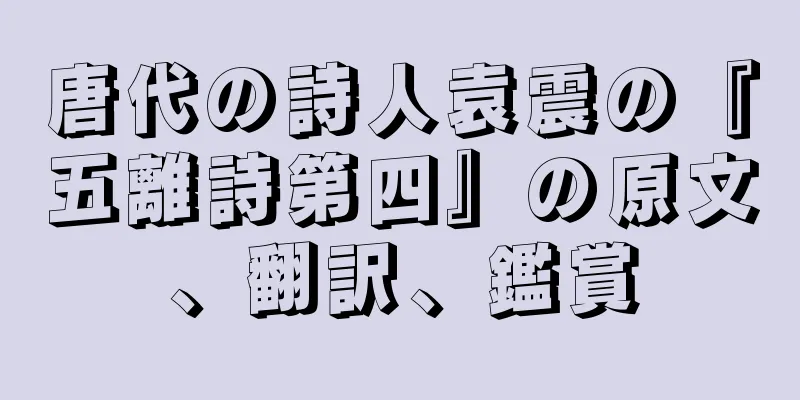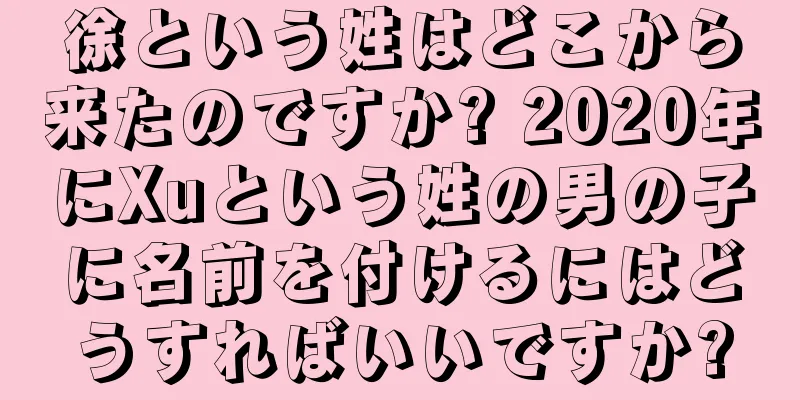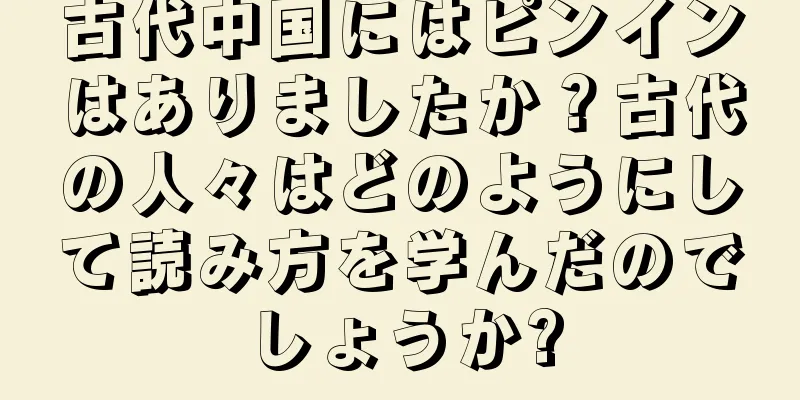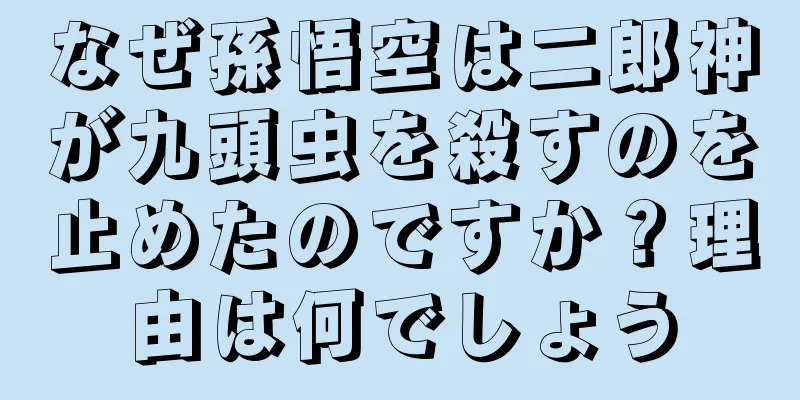明代における通貨の進化: 明代に紙幣が崩壊したのはなぜか?
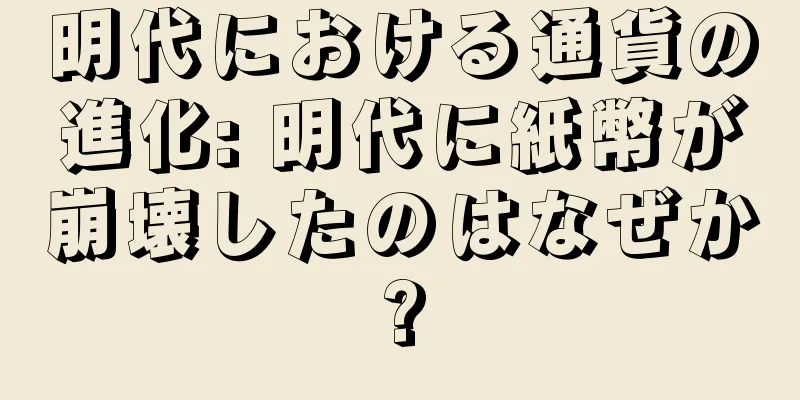
|
明代に紙幣が暴落したのはなぜか。宋代、金代、元の三代がいずれも王朝末期に紙幣暴落を経験したのに比べ、明代の紙幣暴落は王朝経済が安定し、国力が強かった時代に起きた。この事実は不可解である。私は読者と協力してより可能性の高い理由を見つけたいと願い、この問題を再検討するためにここで提起します。 写真はインターネットから 1. 明代の紙幣 明代の紙幣は洪武帝の時代に発行されてから正統帝の崩壊まで、わずか60年以上流通していた。紙幣を使用していた宋、金、元の3つの王朝と比較すると、明王朝の紙幣の寿命は最も短かった。朱元璋(1328-1398)は明王朝(1368-1644)を建国した。彼は歴代王朝の紙幣の経験を参考にして、即位後7年で紙幣の発行を決定し、翌年、正式に明宝札を印刷した。意外にも、彼の死後30年以上経って、宝札の流通はひっそりと終了した。また、明王朝が終わったときの政治経済状況は穏やかで、当時の人々は何も知らなかったようで、この現象は本当に興味深い。 洪武元年(1368年)、朱元璋は洪武通宝と呼ばれる王朝の銅貨を鋳造しました。これは、一銭(10銭)、二銭、三銭、五銭、一両(10銭、つまり100銭)の5種類に分かれていました。洪武8年に大明宝超という紙幣が発行され、洪武の年号が付けられ、一連、五百銭、四百銭、三百銭、二百銭、百銭の6種類に分かれていた。彼は、宝鐘1本は銀1オンスと銅貨1,000枚に相当し、金1オンスは宝鐘4本に相当すると規定した。国民は金銀を使って政府の宝札と交換することができますが、政府は金銀を使って国民と宝札を交換することはありません。市場取引では紙幣と銅貨のみが使用可能であり、金や銀は使用できません。 洪武22年4月、朱元璋は銅貨の不足を補うために、10セントから50セントまでの小額紙幣の印刷を命じた。洪武27年8月、彼は銅銭の使用を禁止し、半月以内に人々に銅銭を政府に引き渡して小額紙幣と交換するよう強制し、通貨を完全に紙幣に交換しようとした。この命令は長くは続かず、実行することもできません。明宝潮が通貨市場から撤退した正統年間まで、明政府は明宝潮を主要通貨、銅貨を補助通貨とする通貨制度を実施し、この2つの通貨が市場取引に供給された。 2. 紙幣崩壊の理由 宋代、金代、元代の紙幣が崩壊した原因は、各王朝が財政収支の困難に直面し、政府が財政赤字を埋めるために紙幣を無差別に発行し、ハイパーインフレと紙幣制度の崩壊を招いたためだと人々はずっと信じてきた。こうした見解は歴史的事実と一致するはずだ。しかし、この見解を明代の紙幣崩壊に当てはめるのは事実と矛盾する。 写真はインターネットから 紙幣の発行量と価格を機械的に結び付けるのこそが貨幣数量説の基本的な精神である。今日の理論の複雑な意味合いに立ち入ることなく、最も単純な貨幣数量説に戻りましょう。これはデイヴィッド・ヒュームが提唱し、アーヴィング・フィッシャーが要約した単純な方程式です。 MV=PT M(貨幣)は明代に発行された宝札の量、V(流通速度)は宝札の流通速度、P(価格)は商品の価格、T(取引)は商品の総取引量を表します。上記の式によれば、V と T が変化しない場合、M が増加すると P も増加します。明代の官僚たちは、MとPの機械的な関係に固執し、他の可能性のある要因を無視して、紙幣に対してこのような態度をとっていました。紙幣の価値を安定させる唯一の方法は、M、つまり発行される宝札の量を減らすことでした。明朝は、一方では宝銭の発行を減らし、さらには印刷も中止したが、他方では、宝銭の発行を厳しくするために、家賃や税金の支払いに宝銭の使用を拡大した。不思議なことに、政府が宝貨の発行量を制限し削減しようと努力したにもかかわらず、宝貨の価値は下がり続け、回復不能な状態となった。明らかに、ここではさらに調査する必要がある何か他のことが起こっています。 上記の簡単な方程式に戻りましょう。まず、宝札の流通率であるVに注目してみましょう。一定期間において、発行された明宝貨幣の総量Mが不変であり、商品取引総量Tが不変であると仮定すると、明宝貨幣の流通率Vが増加すると、価格Pも増加します。明代の倹約家で慎重な太祖朱元璋は洪武8年に明宝札を発行して以来、紙幣価格の安定に細心の注意を払った。違法取引を取り締まるために厳しい刑罰を課したほか、宝札の発行管理にも力を入れた。しかし、宝潮の価格は下落し続け、安定することはできなかった。朱元璋と洪武帝の官僚たちが、発行された宝札の量と価格の間には正の相関関係があることに気づいたのは間違いではなかった。 しかし、このような配慮だけでは不十分です。なぜなら、発行量に加えて、宝潮の市場流通量は流通率にも影響を受けるからです。総発行量 M は総流通量 MV と等しくないため、M のみを考慮するだけでは不十分であり、V も考慮する必要があります。この点は洪武帝とその後の政府、そして今日に至るまで学界によっても無視されてきました。明宝超の下落の鍵は、Vが大きすぎること、つまり流通率が高すぎることです。他の王朝と比べると、明代の宝札の流通率は非常に高かった。ある期間において、商品取引の総量は変わらず、通貨発行量も変わらないが、流通率が上昇したため、流通する通貨の総量 MV もそれに応じて増加すると仮定します。その結果、価格 P が上昇し、通貨単位 M の購買力がそれに応じて低下します。このV字増加効果により、政府は宝貨の発行量を抑制しようと努力しているにもかかわらず、実際の宝貨の流通量は依然として非常に多く、その結果、物価が上昇し、紙幣の価格が下落しているのです。 写真はインターネットから 宝貨の価値が継続的に下落する状況に直面して、洪武朝から正統朝までの各王朝の政府は、宝貨の発行を統制し、宝貨への課税を引き上げることで、市場での流通量を減らし、紙幣の価格を安定させるか引き上げる効果を達成しようとした。現実は全く逆で、紙幣の価格は下がり続け、宝貨が市場に流通しにくくなっても紙幣の価値は回復しない。宣徳・正統両朝の時代、政府は新紙幣の鋳造を中止し、宝札で納めた税金や各種犯罪の罰金を宝札に替える規制を拡大し、公務員の給料や各種費用の支払いに宝札を使用することを減らすなど、あらゆる手段を講じました。しかし、最終的に宝札はハイパーインフレを引き起こし、市場流通から撤退せざるを得ませんでした。ここで何が起こっているのですか? 明らかに、貨幣数量説の上記の式は、数量の減少と価格の下落が同時に起こるという矛盾した現象には適用できません。この矛盾を解決するには、おそらく別の視点から問題を見る必要があるでしょう。ここでは通貨競争と通貨代替の考え方を使って説明してみたいと思います。 明代の貨幣制度では、宝銭が主要通貨として使用され、銅貨が補助通貨として市場で流通していました。市場に宝貨以外に取引手段として使用できる通貨がない場合、人々は非兌換宝貨の価値に疑問を抱いていても、依然としてそれを使用して取引を行うでしょう。宝貨が支払い手段としての使用価値を保持している限り、紙幣の価格は誰もが受け入れられる信用価値の範囲内に維持することができます。さらに、それは政府と国民の間の取引の法的手段であり、税金の支払い手段でもあります。問題は、他の通貨が市場流通に加わると、通貨間の競争と代替が生じることです。 布や穀物に加えて、流通していた最も重要な通貨は銀でした。明朝政府は銀貨を鋳造しませんでした。銀は支払い手段としても機能する金属商品であり、長い間民間市場で流通していました。銀は金属通貨であるため、その価値は銀の商品価格に基づいており、名目価値は大きく逸脱することはなく、人々の受け入れも比較的安定しています。銀と宝貨幣が通貨競争に参入すると、銀の金銭的優位性がすぐに明らかになりました。持ち運びに不便な点を除けば、銀は支払い手段としても、計算単位としても、あるいは価値あるものとしても、宝物紙幣よりも信頼性が高い。国民が保有する銀が通貨に転換され、市場取引に投入されれば、宝超の通貨としての地位は必然的に危うくなり、それに対抗することは困難となるだろう。明政府が繰り返し厳しい刑罰を用いて、人々が市場取引で銀を使用することを禁じたのは全く当然のことでした。 残念ながら、政府の禁止措置はほとんど効果がなく、その政治的意図は経済的合理性ほど強力ではない。銀の侵略に直面して、宝超の価値は下がり続け、ついには市場流通から撤退せざるを得なくなった。明政府は貨幣数量説という厳格な概念の下、宝銭の価値が下がるのを見ると、それは宝銭の発行量が多すぎるためだと考え、宝銭の回収を試み、宝銭のインフレ傾向と逆の、いわゆる逆風金融政策を採用した。宝超と銀が競合する通貨市場において、この政策は宝超のバブルと崩壊を加速させるのに十分であった。 理由は簡単です。特定の期間において、貨幣需要は変化せず、宝貨と銀の交換レートは 1:1 であると仮定します。つまり、1 宝貨の価格は、公定価格で設定された 1 両の銀に等しいということです。 写真はインターネットから 当時流通していた宝札の総額が100束、銀の総額が100両だったと仮定します。宝銭と銀貨の名目上の金額はそれぞれ100であり、実質的な金額もそれぞれ100である。総貨幣需要は200で、Baochaoの市場シェアは50%です。宝銭の価値が半分に下落し、2匁が1両の銀に交換されると、宝銭の名目上の貨幣量が100匁のままであれば、実質的な貨幣量は25%に減少することになる。 市場が要求するのは名目上の金額ではなく、実際の価値です。宝潮の実質通貨シェアは、当初の50%から25%へと半分に減少しました。銀貨の供給が非常に弾力的であるという前提(人々はいつでも通貨に交換できる十分な銀を持っている)の下、減少した宝潮のシェアはすぐに銀に置き換えられました。その結果、宝潮と銀の実質通貨市場シェアは25%:75%となり、つまり、両者の市場シェアは1/4:3/4となりました。もし宝超の価値がさらに半分に下落し、つまり4匁が1両の銀と交換可能となり、名目通貨額が100匁のまま変わらない場合、宝超の実質通貨の市場シェアは12.5%に縮小し、銀は87.5%に拡大し、つまり両者の市場シェアは1/8:7/8となる。名目上の金額が変わらないまま宝貨幣の価値が下がり続けると、貨幣市場における宝貨幣のシェアは縮小し続け、最終的には市場流通から完全に撤退し、銀に完全に置き換えられることになる。お金は言語のようなものです。使う人が増えれば増えるほど、より便利になります。使う人が減れば減るほど、あまり役に立ちません。使用率は通貨の流動性を反映し、流動性によって通貨の価値が決まります。 通貨市場における宝潮のシェアが減少すると、その流動性が低下し、価値の下落は避けられない結果となります。明政府は常に後退する宝潮政策を堅持し、切り下げの圧力に直面して、新しい紙幣への投資を避けようとした。さらに、明政府は宝潮の回収も強化したため、宝潮の市場シェアはさらに縮小し、宝潮の流動性は急速に低下し、宝潮の価値の下落は加速しました。宣徳朝から明朝は前王朝よりも積極的に宝銭の回収に取り組み、宝銭の下落傾向はより急速で、その崩壊は加速し、最終的に正統朝の時代には完全に銀に取って代わられました。 簡単に言えば、明宝札が発行されたとき、それは純粋に信用に基づいた非兌換紙幣として設定されていたため、人々にとって受け入れがたいものであり、その価値が下がる運命は避けられませんでした。明朝政府は通貨価値の下落に直面し、逆周期的な政策として宝銭の発行量を減らしていた。その結果、通貨価値の下落傾向が加速し、銀が継続的に金融市場に流入し、宝銭の通貨機能を代替するようになった。明宝札は発行後約60年で廃れ、宋・金・元の紙幣よりも短命であった。中国紙幣史上の特例といえる。王朝の経済力が高まりつつあった時期に王朝が崩壊したのは例外的なケースだった。 中国の最初の紙幣のサイクルは、明王朝の全盛期に終了しました。明朝の紙幣の崩壊は、政府の政策における二つの誤りによって引き起こされた。最初の誤りは非兌換紙幣政策であり、2番目の誤りは保守的かつ後退的な紙幣発行政策であった。紙幣を兌換しないという政策により、明宝貨の価値は疑われ、時間の経過とともに価値が下がる運命にあった。紙幣発行の保守的かつ後退的な政策は、宝貨の価値の下落を加速させました。銀との競争に直面して、明宝貨は通貨市場での実際のシェアを継続的に減らし、最終的に完全に銀に取って代わられました。鄭統王朝以来、中国経済は二重金属通貨の道を歩み始め、4世紀以上にわたって銀貨と銅貨が並行して流通してきた。 中国の伝統的な経済の発展において、明代における紙幣の崩壊は、私たちに反省する価値のある経済的影響をもたらしました。 写真はインターネットから (1)明・清時代の銀と銅の二重通貨制度では、銅貨は政府が発行し、銀は一般大衆が発行・流通することができた。この通貨制度は、いつでもどこでも両通貨間の為替レートを調整することができ、両通貨の量を混合し、市場の需要に応じて自動的に拡大縮小することができるため、明清時代の中国各地の経済発展の差という現実に効果的に適応し、そのような差が長期にわたって安定的に継続することを可能にする。例えば、先進地域では主に銀貨が使用され、後進地域では主に銅貨が使用され、この現象は清朝末期まで続きました。銀と銅の二重通貨制度の運用は、スペクトルのように多様であった中国各地の伝統的な経済の安定に役立ったが、国全体の経済統合には役立たなかった。 (2)銀銅二重通貨制度は金属通貨制度であり、通貨材料の供給は原材料の採掘や輸出入に左右され、不確実性に満ちている。一方、銀と銅は商品であり、商品市場の需給状況は通貨市場の需給状況とは異なります。商品価格と通貨価格が同期できない結果、銀と銅の通貨価格の安定性が損なわれ、両者の為替レートの不確実性が増幅されます。こうした不確実性は市場経済の発展に悪影響を及ぼします。明清時代の経済は長期にわたってデフレ状態にあったと一般的に言われています。デフレは市場経済の発展に決して有利ではなく、ひどい場合には不況や後退を引き起こすこともあります。 (3)歴史的経験は、人類の経済発展の道筋は、市場経済部門が徐々に非市場経済部門に浸透し、侵食し、そして取って代わるプロセスであることを物語っている。信用通貨は活況を呈する市場経済の産物です。中国の紙幣は、市場経済がまだ補助的、補足的な経済部門であった時代に登場し、さらなる強化と発展ができず、代わりに銀銅の二重金属通貨に取って代わられました。これは、伝統的な市場経済部門が長い間狭い補助的分野にあり、非市場経済部門をさらに浸透、浸食、置き換えて、経済運営の支配的なモードに発展できなかったことを反映しています。つまり、1950年代に中国の学者が提唱した資本主義の萌芽期からすでに長いこと経っており、紙幣の出現は異常事態であると思われる。しかし、存在するものは合理的であり、そのような考え方が現在や未来を見るのに適していないとしても、過去を見るのに適しています。紙幣が出現したという事実は、中国の伝統的な貨幣経済にはまだ解明されていない発展の論理があることを意味し、また、現在主流となっている貨幣経済史観を再検討する必要があることも意味している。 中国の最初の紙幣サイクルは、伝統的な経済環境の中で行われ、完了したユニークな通貨実験でした。マルコ・ポーロ(1254-1324)の時代のヨーロッパの人々に衝撃を与え、信じ難いものにしたが、明王朝が最盛期を迎えた頃にそれが終焉を迎えたとは、今日でも信じ難いことである。それは、暖かい春の到来と長い冬の到来の前に咲く小さな花のように、統制と慣習を重視する経済を震えさせ、装飾するだけで、中国の伝統的な市場経済の発展に多くの活力と輝きを加えていない。傅一齢はかつて、中国の伝統的な経済資本主義の発展の特徴は早熟かつ未熟であると鋭く指摘しており、宋代初期から明代初期にかけての紙幣の経験はまさにこれを裏付けるものであった。 |
推薦する
『紅楼夢』のFang Guanとは誰ですか?方観の伝記
『紅楼夢』のFang Guanとは誰ですか?方観は清代の小説『紅楼夢』に登場する女性キャラクターです...
崇禎帝は崇禎11年に明王朝を再興する機会をなぜ逃したのでしょうか?
崇禎が即位したのは、明朝が内外ともに苦境に陥っていた時だった。多くの人は崇禎が魏忠賢を殺害したのは誤...
『春の田舎雑感』をどう理解したらいいのでしょうか?創作の背景は何ですか?
春の田園范成大(宋代)柳の花が咲き誇る奥の路地では、昼に鶏が鳴き、桑の葉の先はまだ青くない。寝てから...
林黛玉と賈宝玉は交際していたのか詳細に分析
古典の名作『紅楼夢』は『金瓶梅』の影響を強く受けています。性的な描写は当然その構成要素の一つですが、...
李定果はどのようにして有名な王になったのでしょうか? 李定果の墓はどこにありますか?
李定国は名王を二度破った『李定国二名君破』は、李定国将軍が清朝の二人の王子を倒した物語です。この二人...
皇太子劉菊の家族全員が殺害された。漢の武帝はどのようにして劉炳義が自分の曾孫であると判断されたのだろうか?
漢の武帝は伝説的な人物であり、常に史上最高の皇帝と呼ばれてきました。主な理由は、「強大な漢を怒らせる...
ヤン・ジダオの「雨美人:曲がった柵の外の空は水のようだ」:それは人々を酔わせ、魅了し、考えずにはいられない。
顔継道(1038年5月29日 - 1110年)は北宋時代の有名な詩人である。名は書源、号は蕭山。福州...
南宋代宋慈著『西源義録』全文:巻一:総説
『西元集録』は法医学書で、『西元録』、『宋特星西元集録』とも呼ばれ、全4巻である。南宋の宋慈(恵夫)...
唐の太宗皇帝はなぜ安西保護国を設立したのですか?安西保護国は何をしたのですか?
唐の太宗皇帝はなぜ安西保護国を設立したのか?安西保護国は何をしたのか?Interesting His...
「水の転換」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
水の転用李群宇(唐代)秋の泉から冷たい玉の小川が流れ、深い洞窟の入り口から煙が上がっています。底流の...
七剣士と十三英雄の第138章:焦大鵬が初めて王元帥と会う、玄真子が泥棒を送って良渚を捕まえる
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
なぜ劉老老は別荘を玉皇大帝の宮殿と間違えたのでしょうか?
周知のように、「紅楼夢」は虚実、虚偽と真実が入り混じった物語です。では、なぜ劉老老は別荘を玉皇宮と間...
「補償の弱体化」とはどういう意味ですか? 「弱体化補償」の原則は正しいのか?
「弱体化補償」の原理は正しいのか?次のInteresting History編集者が詳細な記事紹介を...
エウェンキ民族の歴史 エウェンキ民族の民俗神話
エウェンキ族には、世界の創造、人類の起源、自然現象、古代の英雄に関する多くの神話があります。これは、...
朱元璋はなぜ金義衛を創設したのでしょうか?英雄を殺すための王室の道具
金一味は朱元璋によって発明された。刺繍制服衛兵は朱元璋の偉大な発明でした。 『明史刑法』には、「刑法...