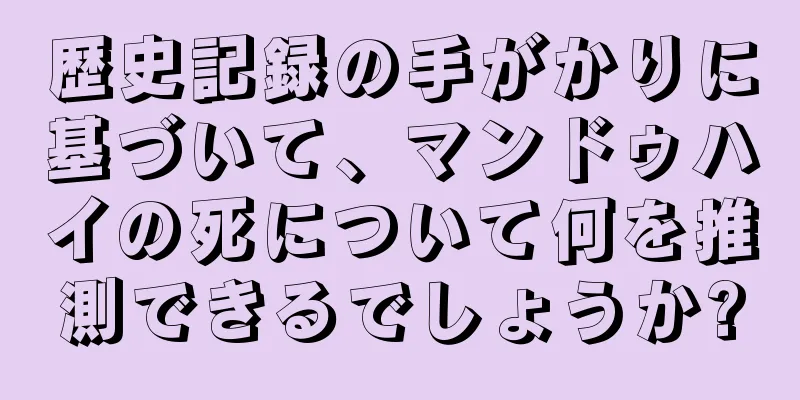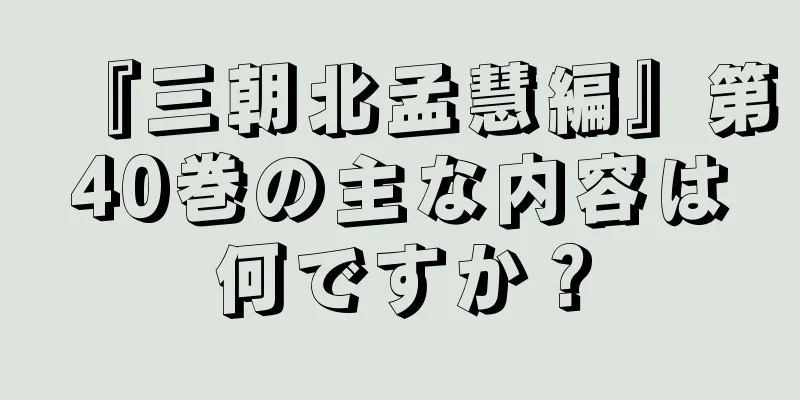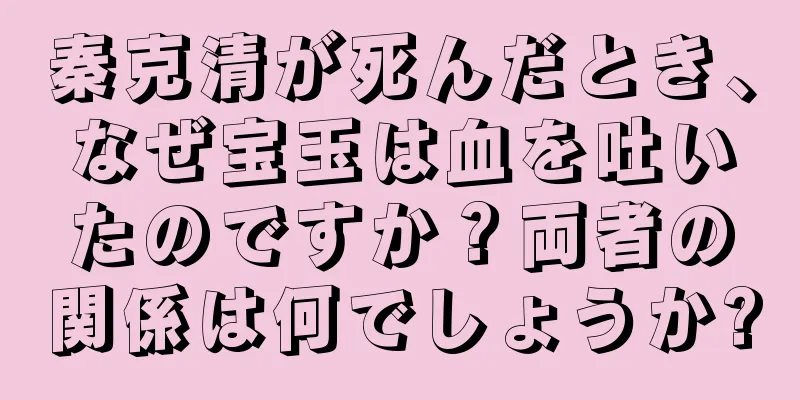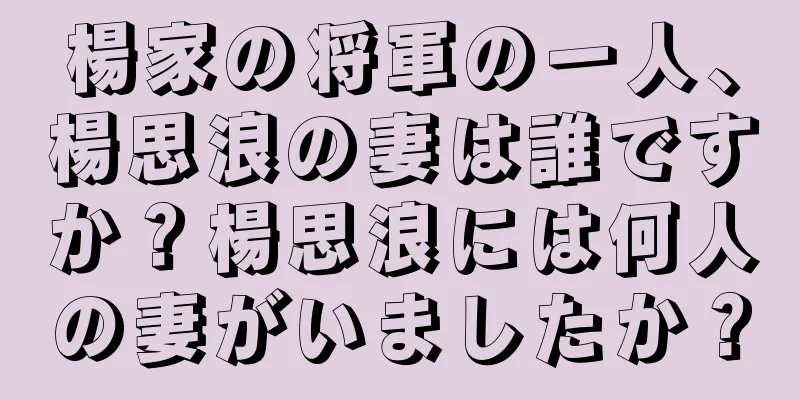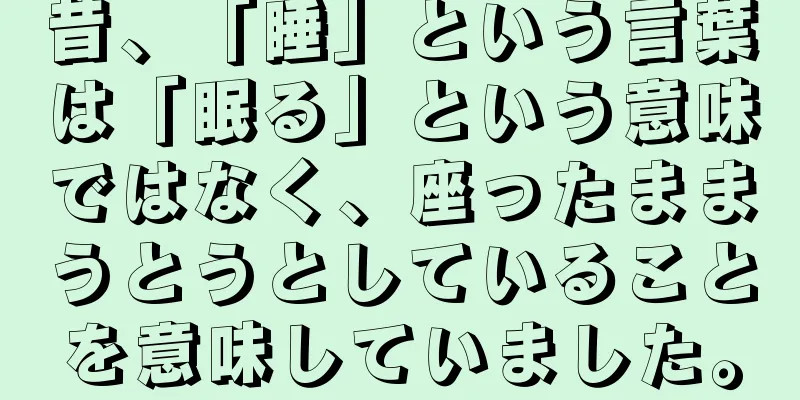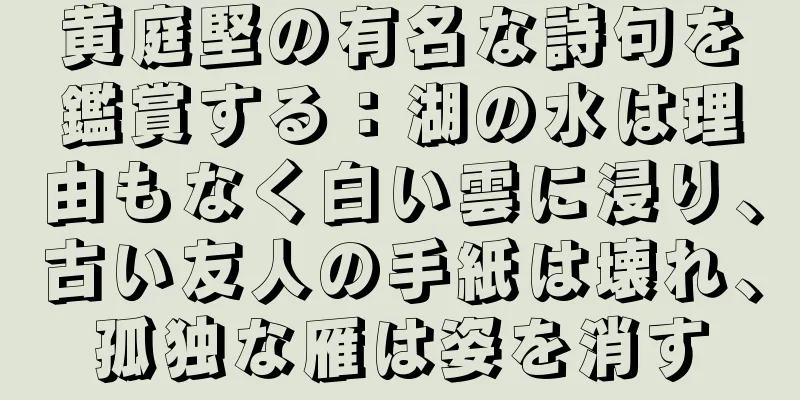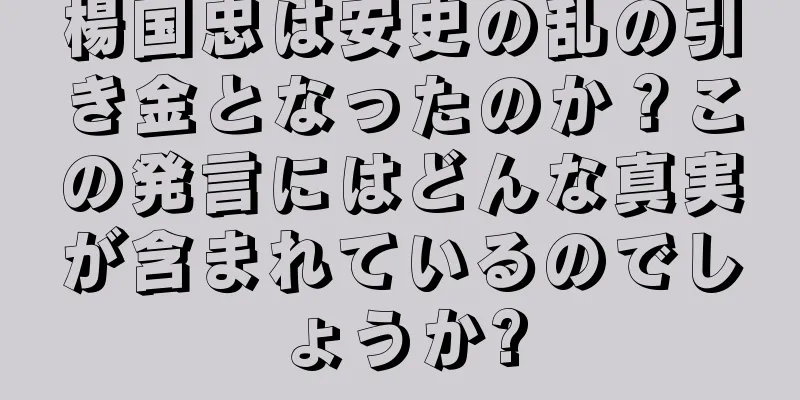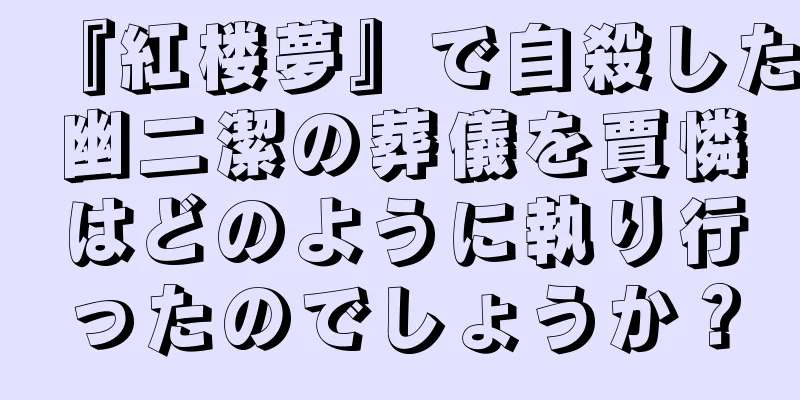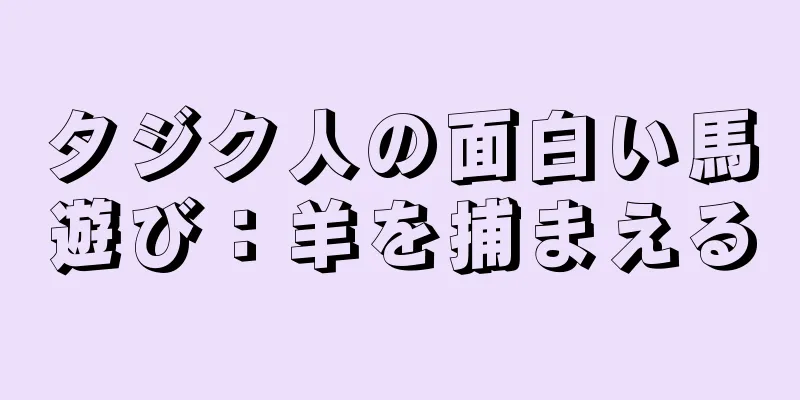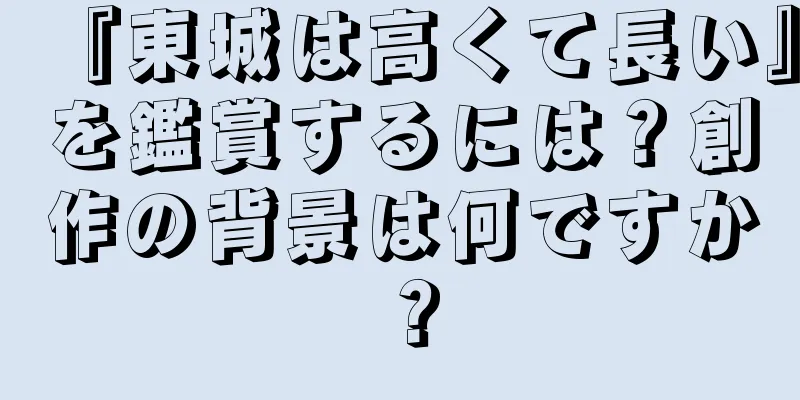春秋戦国時代の刀銭:春秋戦国時代の各国の貨幣の分類は?
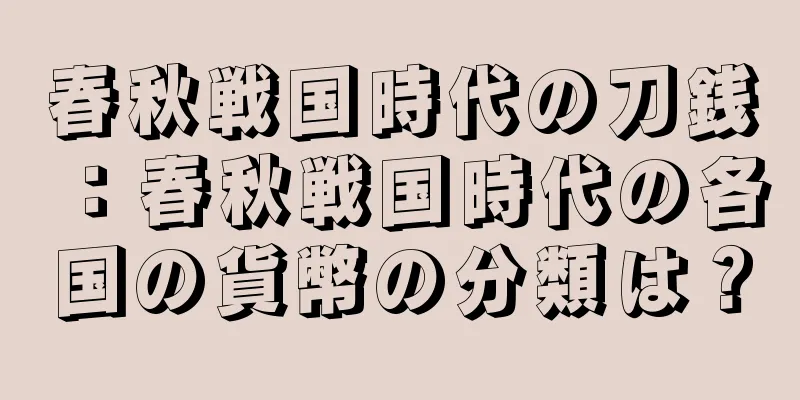
|
春秋戦国時代の貨幣入門 春秋時代は、中国の歴史において奴隷制から封建制へと大きく転換した時代でした。商品経済のさらなる発展により、流通通貨の需要が急増し、金属鋳造技術も成熟し、大規模な金属通貨鋳造の必要性と可能性が生まれました。この時期の通貨の最大の特徴は、鋳造された硬貨の種類の多さと通貨制度の混乱であった。当時、周王朝の勢力が徐々に弱まるにつれ、各国は独立し、独自の経済体制を持っていたため、各国が独自の通貨を鋳造し、相互に流通させ、複数の通貨と複数の通貨の種類が共存し、長期間使用されるという特殊な状況が形成されました。 春秋戦国時代の貨幣分類 この時代の貨幣は、形状や流通の仕方から、布銭、刀銭、丸銭、蟻鼻銭(鬼面銭)の4種類に分けられます。 布製コイン 鍾貨は中国の古代貨幣で、その形状がシャベルに似ていることから、鍾布とも呼ばれています。春秋時代初期に登場し、戦国時代後期まで鋳造・流通されていました。 「布」は「镈」と同音異義語で、古代ではよく使われていました。布貨は青銅製の農具ハンマーから発展したもので、主に三晋と西周の地域で流通していました。布貨幣の形状によって、中空布貨幣と平頭布貨幣の2種類に分けられます。 初期の布貨は道具としての外観を保っており、持ち手用のソケットがあり、原始的で重いため、頭なし布貨と呼ばれていました。その後、布貨は徐々に軽くなり、薄く、小さくなり、貨幣本体が完全にシート状になったため、頭なし布貨と呼ばれました。平布には通常、地名や重さを記録する言葉が刻まれています。その後、王莽の新王朝でも布貨幣が鋳造されました。 中国東周時代のシャベル型の青銅貨幣。春秋時代後期に出現し、戦国時代中期以降に広く流布した。主に三晋と両周の地域で使用されました。鎛は青銅製の農具で、「布」と発音され、形がシャベルに似ていることから「鎛布」とも呼ばれていました。 最も初期の布製コインは、道具として使用する際にハンドル用のソケットが残る中空の頭部を備えており、中空頭部布製コインと呼ばれていました。その後、ソケットのない平らな上部のコインになり、コイン本体は完全にシート状になり、鋳造や持ち運びが容易になりました。平布には「安邑」や「晋陽」といった地名や、「一釿」や「十二朱」といった通貨単位などの文字が鋳造されていることが多い。貨幣がハンマーの形に作られているという事実は、この農具がかつてこの地域で交換手段として使われていたことを示しています。その後、王莽は古い方法を復活させ、再び布製の貨幣を鋳造した。 鉤銭(ぶせん)は、春秋時代から戦国時代に鋳造された鉤銭や平鉤銭などの鍬形貨幣の総称である。その形状からその名前が付けられました。 ナイフコイン 刀銭は商周時代に使われていた青銅器から発展したもので、刀銭の柄の端には輪があり、柄には亀裂があります。形状は針先刀、尖頭刀、丸頭刀、弧状刀などがあり、主に斉、燕などの東方で流通し、後に趙、中山などの国に発展し、布銭と共存しました。斉刀、即墨刀、安陽刀、針頭刀、尖頭刀、丸頭刀、明刀など多くの種類があります。秦の始皇帝が中国を統一した後、貨幣制度を統一し、貝や刀、布などの貨幣を廃止したという文字が刻まれています。後に王莽が鋳造した貨幣の中には、金をちりばめたナイフもあった。 東の斉国と北の燕国では主に刀銭が使われていました。刀貨は「延明刀貨」と「斉刀貨」の2種類に分かれています。ナイフコインの形状は、山容族や北陂族などの北方遊牧民が釣りや狩猟に使用していたナイフツールにインスピレーションを得ています。刃の表面に「華」の文字があることから「道華」と呼ばれています。刀身の形状は、弧状、折れ状、直状などがあり、刀身の頭部は平頭、尖頭などがあり、我が国の初期の青銅貨幣の一種でもあります。 元前 元銭は、元金や環銭とも呼ばれ、古代中国の銅貨です。戦国時代には秦・魏両国で主に流通していた。中央に丸い穴がある丸い形。コインには文字が刻まれています。一説では糸車から進化したものとされ、別の説ではバイリングから進化したものとされる。四角い穴の開いた硬貨の前身です。 「元銭」は、戦国時代に中国で鋳造された円形の銅貨の一種です。略して「元花」や「環銭」とも呼ばれています。秦以前の時代の我が国の4大銅貨制度の一つであり、秦代の主な貨幣形態でもあります。円形コインには、主に 2 つの種類があります。1 つは、より原始的な丸い穴の開いた円形コインで、もう 1 つは、丸い穴の開いた四角いコインです (これは、円形コインから徐々に進化したものです)。初期の円形硬貨の穴は比較的狭かったが、次第に大きくなっていった。丸いコインの表面に刻印がありますが、裏面には文字がありません。 アリの鼻のお金 易比銭は、揚子江と淮河流域の楚国で流通していた通貨で、模造貝から作られました。楚国は他の中原諸国に比べて経済や文化が未発達であったため、鐘や刀、糸車の使用も比較的遅く、銅銭も模造貝殻の形をそのまま使用し続けました。アリの鼻コインは楕円形で、前面は凸型、背面は平らです。貝殻のような形をしていますが、サイズは小さめです。 中華人民共和国の建国以来、蟻鼻貨幣のほとんどは河南省と江蘇省で発掘されている。鬼面貨幣は湖北省、湖南省、河南省、江蘇省、安徽省などで発見されている。1963年、湖北省孝感市の野竹湖で鬼面貨幣5000枚が発掘された。表面には「朱」の文字が書かれており、平均重量は約4.37グラムだった。発掘された墓の位置と数から判断すると。蟻鼻銭は戦国時代初期(紀元前5世紀)に鋳造され、鬼面銭は戦国時代中期から後期(紀元前4世紀から3世紀頃)に鋳造されました。楚の国の領土は当初はそれほど大きくなかったが、後に徐々に領土が拡大するにつれて、蟻鼻銭や鬼面銭の流通範囲も拡大し、次第に長江中下流域に独自の貨幣制度が形成されていった。 |
>>: 春秋戦国時代の蟻銭:春秋戦国時代の各国の貨幣の分類は?
推薦する
張秀はなぜ槍の神と呼ばれているのでしょうか?彼は本当にそんなに強いのでしょうか?
張秀:「万城侯」の称号を授かり、「北の槍王」として知られた。虎の頭を持つ金の槍を振るう。張秀は有名な...
どのような戦略が「優れた戦略」と言えるのでしょうか?歴史上、どのような独創的な戦略が登場したかを見てみましょう。
今日は、おもしろ歴史編集長が「奇妙な戦略」と呼べる戦略とはどのようなものなのかをご紹介します。皆様の...
明代の技術:封建王朝における技術発展のピーク期
天文学と気象学 14 世紀半ばの「白猿三灯図」には、天候の変化と関連した 132 枚の雲図が掲載され...
『紅楼夢』の邢秀燕の正体は何ですか?彼の父親は誰ですか?
邢秀燕は『紅楼夢』に登場する邢忠とその妻の娘であり、邢夫人の姪である。 Interesting Hi...
『紅楼夢』で、薛宝才はなぜ金婚式を公に放棄したのですか?
薛宝柴は、曹雪芹の小説『紅楼夢』およびその派生作品のヒロインの一人である。まだ知らない読者のために、...
如来仏はなぜ一角犀王を恐れるのでしょうか?理由は何でしょう
『西遊記』では、如来仏は五方の五大老であり、霊山のリーダーでもあります。彼の身分と地位は頂点にありま...
『紅楼夢』で少女と呼べるのは誰でしょうか?できない人がいるでしょうか?
『紅楼夢』は中国古代の章立て形式の長編小説であり、四大古典傑作の第一作です。上記の疑問は、次の文章で...
光緒年間の「定武飢饉」はどれほど残酷だったのでしょうか?何百万人もの人々が亡くなり、役人は金持ちになりました!
本日は、Interesting Historyの編集者が光緒年間の「定武飢饉」についてお伝えし、皆様...
『紅楼夢』の王禧峰はなぜいつも大観園を丁寧に管理していたのでしょうか?
王希峰は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人です。以下の記事はInteresti...
「氷の卵」はどうやって形成されるのでしょうか?フィンランドのビーチに氷の卵が現れる理由は何ですか?
「氷の卵」はどうやってできるのかご存知ですか?次は、Interesting History編集長が解...
宋・遼時代の奠堂はどのような場所だったのでしょうか?市場で取引される商品に対する規制は何ですか?
「衢場」は宋、遼、金、元の時代に民族政権の国境地帯に設けられた貿易市場であった。次は興味深い歴史エデ...
「漁師の誇り ―花の下でふと二つの櫂の音が聞こえる―」という詩をどう鑑賞したらよいのでしょうか。創作の背景は何ですか?
漁師の誇り - 突然、花の下で2つのオールの音が聞こえた欧陽秀(宋代)突然、花の下から2つのオールの...
大唐西域記史第四巻原文
大唐西域記 第四巻(十五国)玄奘三蔵訳大宗志寺の僧侶汾済が書いた浙江からナブティへジャランダラ王国、...
『秋季折々詩』は北宋時代の儒教哲学者、程昊によって書かれたものです。この詩から私たちはどのような四つの世界を理解できるでしょうか?
程昊は、号を伯春、号を明道といい、通称は明道氏。北宋代に朱子学を創始した。弟の程毅とともに「二人の程...
西遊記 第23章:三蔵法師は根源を忘れず、四聖人は禅の心を試す
『西遊記』は古代中国における神と魔を題材にした最初のロマンチックな章立ての小説で、『三国志演義』、『...