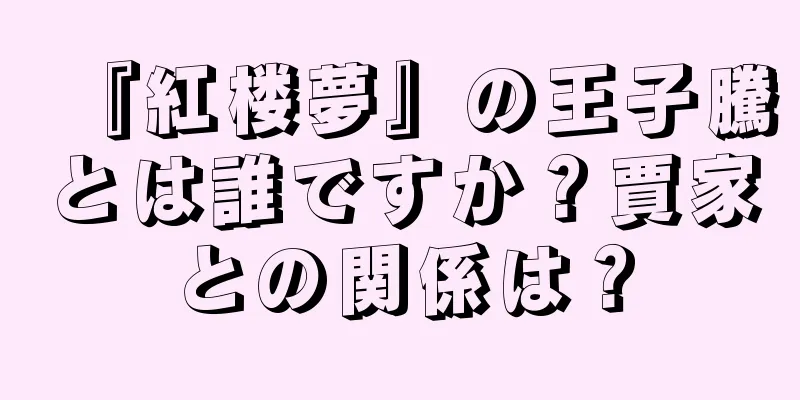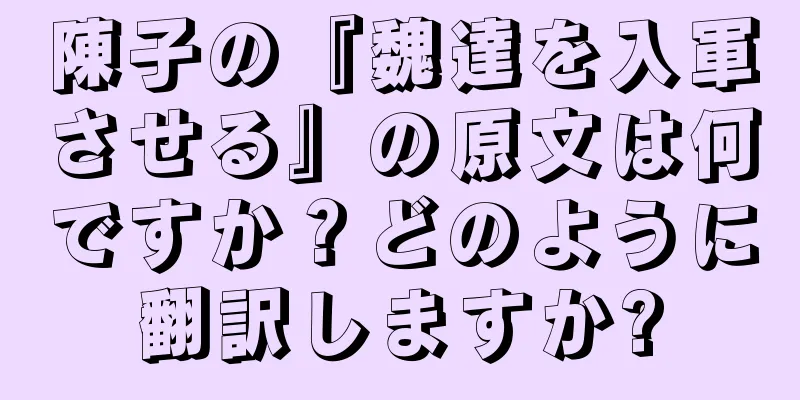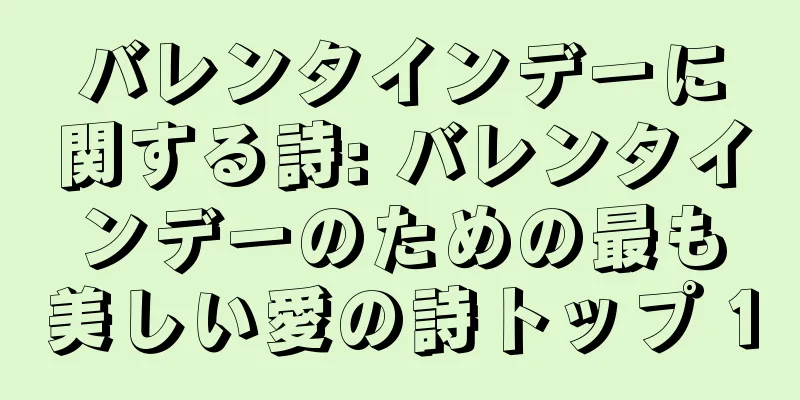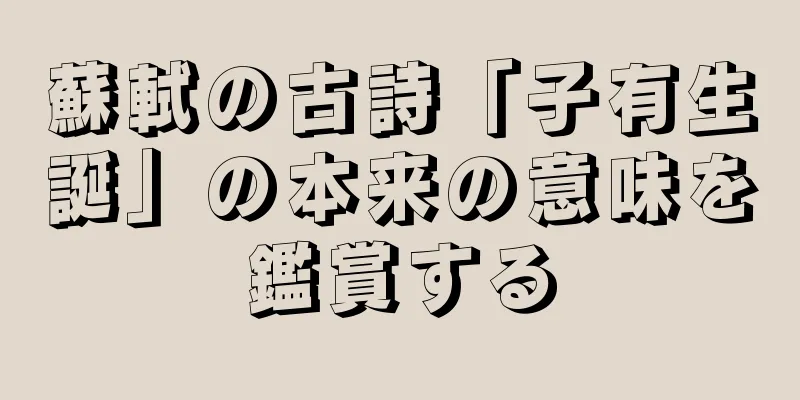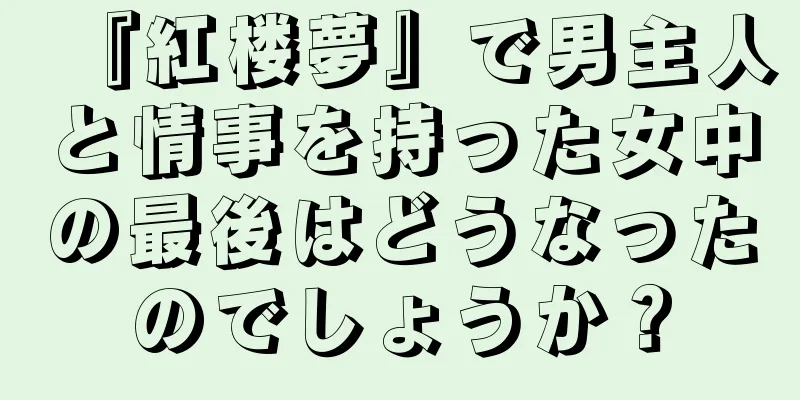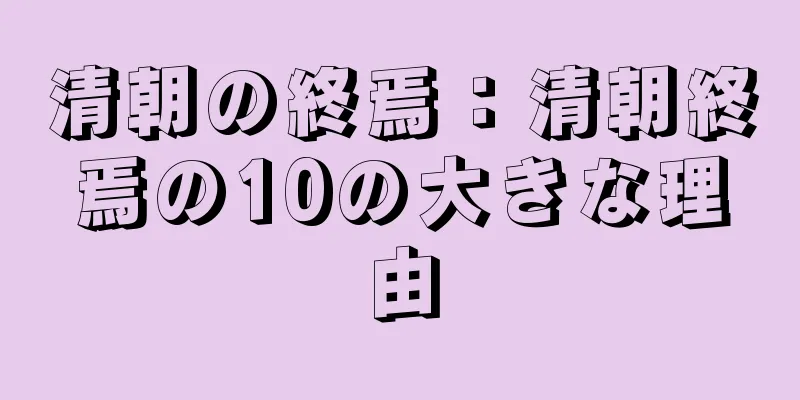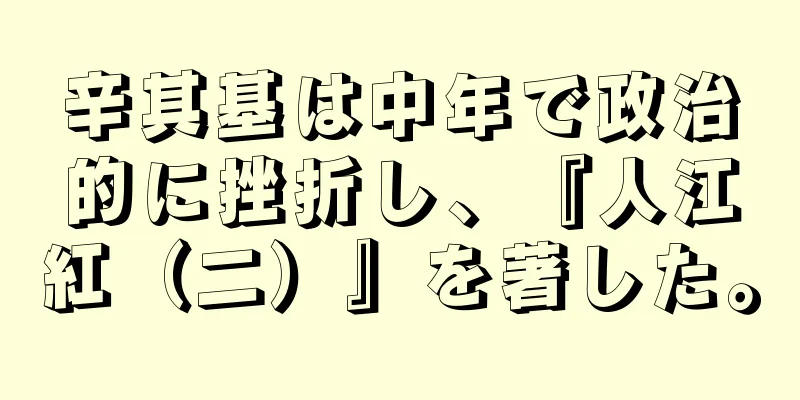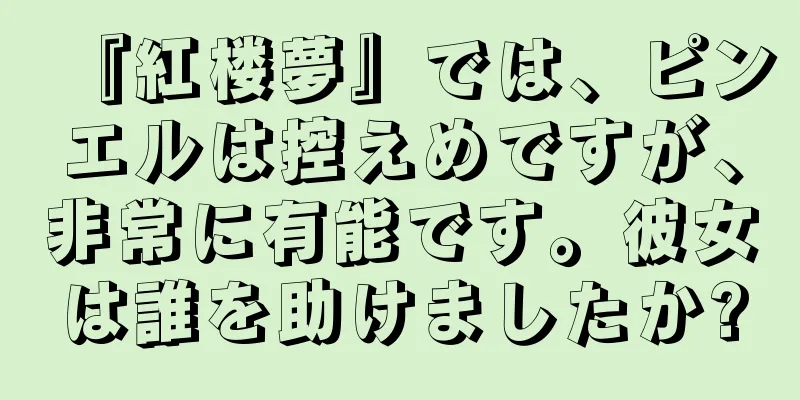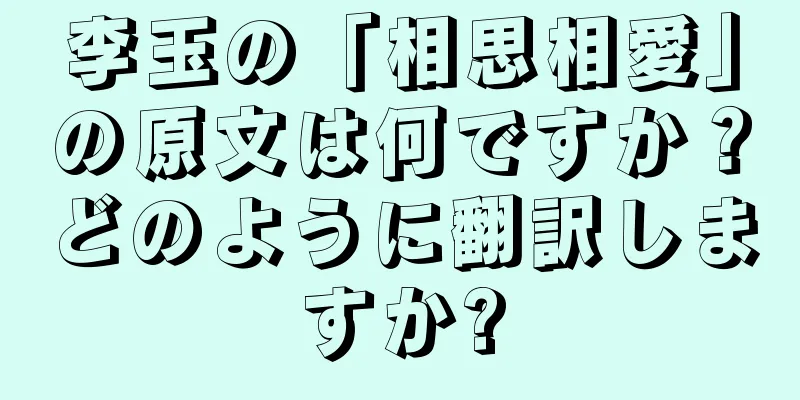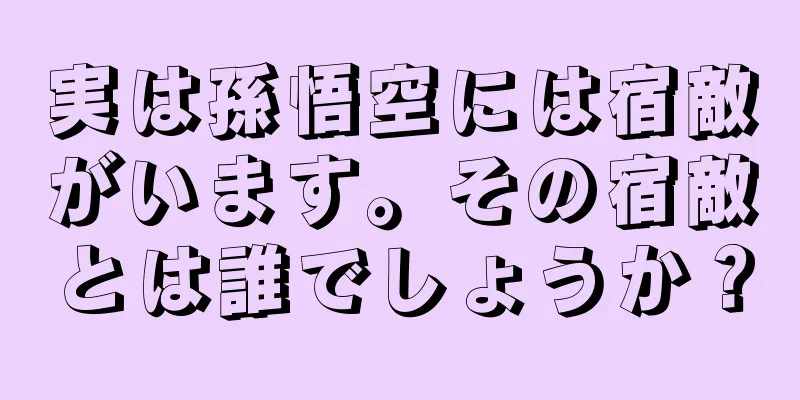古代の事務局は今日のどの部門に相当しますか?事務局の機能の詳細な説明
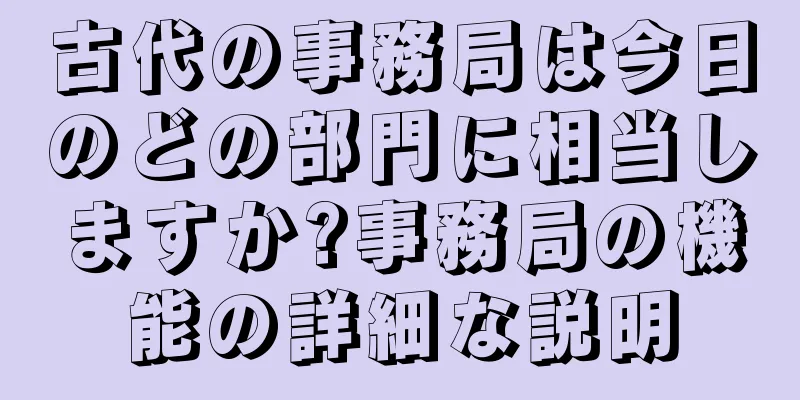
|
中書聖は古代の皇帝直属の中央官庁の名称である。封建政権の中央統治部門は、漢の時代に初めて設置されました。魏では総監と書記の役職を持つ事務総長が設立されました。魏の曹丕は、その名称を事務総長と書記に改めました。晋の時代以降は、官吏と呼ばれ、君主の意志に従い、機密事項を扱い、勅令や中央政府の布告を発布する最高機関となった。それは隋・唐の時代まで続き、国家の政治の中心(三省六部制)となった。宋代と元代には、書記局に中書令と中書成祥の役職があった。これらの役職は明代と清代に廃止された。 元朝の政務局には遠隔地にいくつかの支局(地方最高政府)があり、それぞれ興中州省(略称は興盛)と呼ばれ、後にその管轄区域を指し、さらに地方省に短縮された(ただし政務局自体は直接の管轄区域を「腹」とは呼んでいない)。 国の中央統治機関の名称の変遷:漢の武帝以前には、比較的独立した宰相府があった。漢の武帝は、皇帝の権力を強化し、宰相府の行政権力を弱めるために、官房と内廷の役人を設置した。西晋の官房の設置により、宰相の伝統的な権力は皇帝の権力にさらに依存するようになったが、実際の権力関係は名目上の関係よりも高かった。その後、官房は比較的独立し、元の時代にも地方に支官房が設置された。明代の洪武13年、朱元璋は宰相胡衛庸を殺害し、これを機に明朝の書記局を廃止し、書記局舎人のみを残した。清朝には中書科という低い地位で監督機能のみを持つ官職があった。 導入 漢の武帝の治世中 皇帝の権力を強化するため、文書を担当する尚書が重要な機密事項を担当した。後宮への出入りを容易にするため、宦官がその職に就き、中尚書、略して中書と呼ばれた。また、夜娼も務めたため、中書夜娼とも呼ばれた。その最高責任者には霊氏と普社氏が含まれる。漢の宣帝の末期、洪公は中書の丞相、石仙は普社丞相であった。元帝の治世には、石仙は中書の丞相、老良は普社丞相であった。二人とも独裁的で、朝廷の役人たちに嫌われていた。成帝の時代には、宦官が中書を務める制度が廃止され、その後、後漢末期まで、学者が上書に任命されました。尚書泰は重要な地位を占め、その地位はますます重要になっていった。しかし、独裁的な封建領主は、自らを脅かさないように、臣民が権力を持ちすぎないように常に注意しなければなりません。 後漢末期、曹操が魏王の位を授けられた後、魏国の官僚を設置する際に、商書の事務を監督する秘書長を設置した。魏の文帝、曹丕が即位すると、書記を中書に改め、監と令をそれぞれ1つずつ任命した。監と令の下には数人の中書郎が置かれた。こうして中書州が正式に設置され、その官吏は学者であり、前漢の宦官であった中書とは異なっていた。それ以来、事務局と首相官邸は並んで存在するようになった。もともと尚書郎が行っていた勅令の起草の責任は、中書省の役人に移管されました。中書簡・霊の位は上書霊・普社より低いが、上書よりも皇帝に近い立場にあったため、内政権は次第に中書州に移り、上書台もそれに応じて地位が弱まっていった。三国時代には曹魏のほか孫武も中書を設置し、霊・朗を任命したが、その制度は魏のものと若干異なっていた。蜀漢は不明。 西晋の時代以降、北周の時代を除いて、すべての王朝は曹魏の官房設置の慣例に従ったが、北周の時代は官房という名称を使わずに六官制を実施した。しかし、春官政権には、内史中大夫、夏大夫といった、中書霊や士朗に相当する役職が存在した。隋の時代には六官制が廃止され、現在の中州州として知られる內氏州が設立されました。煬帝の治世の終わりに、内州聖と改名されました。唐代初期には内氏州とも呼ばれていたが、武徳三年(620年)に中州州に改名された。高宗龍朔2年(662年)、西台と改名され、咸衡(670-674年)の初めに元の名に戻されました。武帝光寨元年(684年)、鳳閣と改名され、中宗神龍(705-707年)の初めに元の名に戻りました。玄宗開元元年(713年)、紫微県と改名され、5年後に元の名に戻りました。魏晋の時代から、書記局は尚書省、孟下省とともに三省の一つとなっていた。 宋代には最高行政機関として中書門舎が設立され、最高官吏が宰相の権限を行使した。 元朝では、書記局がすべての役人を統括し、枢密院と監察院と政治、軍事、監督の権力を共有していました。孟夏省と尚書省は両方とも廃止されたため、中書省は以前の王朝よりも重要になりました。地方行政の一部も事務局によって管理されていました。遠隔地では、その地域を統治するために 11 の州が設立されました。 明代初期にも使われていたが、洪武13年(1380年)、官房は廃止され、6つの省は皇帝が直接指揮することになった。また、朝廷はもはや宰相を任命できないと規定され、権力の集中化はさらに強化された。明代の永楽帝の時代には内閣が設立され、機密事項は「内閣」に移管され始めた。その後、中書生という機関は存在しなくなった。 歴史 起源 古代中国における最高中央政府機関の一つ。漢代の尚書と関係がある。漢の武帝の時代には、皇帝の権力がさらに強化され、文書を担当する中書令と四尚書が機密事項を担当しました。司馬遷は初代中書令であり、尚書を率いて計画を検討し、中書令は封印事項を担当しました。後宮への出入りを容易にするため、宦官がその地位に就き、中尚書、略して中書と呼ばれた。彼は夜娼の地位も兼ねていたため、中書夜娼霊と呼ばれた。事務局の最高責任者にはリン氏とプーシェ氏が含まれる。宣帝の末期には洪公が中書丞相、石仙が普社丞相であった。元帝の時代には石仙が中書丞相、老良が普社丞相であった。二人とも独裁的で、朝廷の役人から嫌われていた。成帝の時代には、尚書の数が5人に増え、宦官の中書の制度は廃止され、以後、東漢末期まで、学者が尚書に任命された。尚書台は重要な地位を占め、その地位はますます重要になっていった。しかし、独裁的な封建領主は、自らを脅かさないように、臣民が権力を握りすぎないように常に注意しなければなりません。 魏晋時代 事務局の組織は王朝ごとに変化してきました。魏晋時代から隋初期にかけて、最高官吏として監察官と知事がそれぞれ1人ずついた。その後、隋代には監察官が廃止され、二人の官吏が任命された。唐代は隋の制度を継承し、中州嶺は有祥嶺、内士嶺、紫微嶺などに改名されたが、すぐにすべて元の名前に戻った。監察と令の下には、監察と令の代理である書記官(魏晋代には単に郎または同氏郎とも呼ばれ、金宋代以降は一般に士郎と呼ばれた)がいた。彼の職務は、監察と令と同様に、皇帝の質問に答え、勅書を起草し、臣下の嘆願書を読み上げることであった。晋代から隋代初期にかけては、副大臣の数は4人であったが、後に2人に減らされ、唐代もそれに倣った。副大臣の下には秘書局長がおり、当初は秘書局通師長と呼ばれていたが、後に通師の称号は廃止された。中書社人は当初、皇帝に弔辞を奉呈する役目を務め、後に勅書の起草、外交使節の勅令受理、皇帝の勅令の宣布、訴訟の審理などを担当した。職員の数は王朝によって異なり、唐代には 6 人がいました。中書社人の下には、皇帝を案内し、宮殿に報告する役割を担う通氏社人(かつて通氏夜哲と改名)が数人いた。また、唐代に設立された、助言や批評を担当する有不闊と有世易、隋代に設立された日誌の編纂を担当する九九社人がいた。 事務局の最も重要な任務は勅令を起草することであった。魏晋の初めには、主に長官、大臣、副長官が自ら勅令を起草しました。例えば、曹魏の時代には、劉芳が長官を務め、勅令の作成に長けていました。三祖(魏武、魏文、魏明)の勅令のほとんどは、劉芳が書いたものです。張華は西晋の中央書記長であった。当時のすべての勅令は張華によって起草された。その後、監督や奉行を務めた貴族たちは、清談を重んじ、雑事を嫌ったため、勅旨や文書の起草を奉公人に委ねることが多くなり、機密事項に関する権限は次第に下層に移っていった。南朝時代、勅令の起草は中書社人の専任業務となった。皇帝が勅令を使いやすくするため、下級貴族や庶民を社人に任命することが多かった。「彼らは内閣に入り、勅令を発表し、すべての勅令は社人によって持ち込まれた」。このようにして、彼らは意思決定に参加する機会を得た。南斉の永明年間(483-493年)、中州同氏世人は全国に大きな権力を握っていました。梁の武帝は、周奢と朱懿に機密情報を託し、中書社人として歴任した。二人は官職を何度も昇進したが、社人のままであった。陳朝では、「国事はすべて秘書局が管理していた。秘書局には秘書局長が5人おり、それぞれが21の部署を担当し、それぞれが尚書の各部の上司として国内のあらゆる機密を管理し、尚書は彼らに従わなければならなかった」。これにより秘書局長による独裁状態が生まれ、監察、大臣、副大臣の役職は空虚な肩書となった。この状況は陳の没落後に初めて変化した。北朝時代の中書簡と中書霊は、依然として勅書を起草する権限を握っていた。例えば、北魏の高雲と高陸は、文才があったため中書簡と中書霊を兼ねており、勅書や書状のほとんどはこの二人によって書かれた。北斉の邢紹と衛寿も中書簡と中書霊を兼ねており、勅書を自ら執筆していた。これは、勅書が召使によって起草されていた南朝の状況とは異なっていた。 隋と唐 事務局 官府には中書陵が二人おり、三位であった(代宗の時代に二位に昇格)。高宗の龍朔元年(661年)、官府は西台に改められ、中書陵は有祥と改められた。光寨元年(684年)、書記局は奉閣に改められ、書記長は内氏と称された。開元元年(713年)、書記局は紫微州に改められ、書記長は紫微霊と称された。その後、古い名前に戻されました。中書霊は省の最高官吏であった。『新唐書 官吏伝』には、「中書霊は…皇帝を補佐して主要な政務を扱い、省の政務を総括する責任を負っている」と記されている。 さらに2人の副大臣が任命され、第4位(代宗皇帝の治世中に第2位に昇格)は、中書大臣の代理を務めた。彼らは朝廷の主要な政務の審議に参加し、自ら役人を任命した。蛮族が朝廷に来た場合は、彼らはその嘆願書を受け取り、報告した。また、中書社人は6人おり、第5位で中書省の中核官僚であった。彼らは、勅書の審議に参加し、勅旨や勅令、勅印や勅令を起草する役割を担っていた。重要な機械事務を司るため、漏らさない、遅らせない、違反しない、忘れないという4つの禁止事項が特に定められています。彼らは省内で討議された軍事や国家の重大な事柄や新聞で報道された記念碑に対して予備的な意見を述べ、署名することができた。彼らは「五華班士」と呼ばれた。 省内の意見は、省長と副省長によって集められた後、省長のシェレンに引き渡され、シェレンは皇帝の意向に従って勅旨を起草した。勅旨の起草に特に責任を持つシェレンは「志志高」と呼ばれ、他のシェレンも勅旨に署名しなければならなかった。役人の中で最も年長の人物は「葛老」と呼ばれ、省の雑務を処理する責任を負いました。 6 人のシェレンは官房の 6 つの省庁に配属され、事件の裁定において首相を補佐した。 首相の会議室である政務室には官房に通じる扉があり、首相は国政について官房に相談するためによくこの扉を通った。 『旧唐書』によれば、張雁は代宗大理の治世中に宰相を務めていたとき、「皇帝に敬意を表し、皇帝と接触しないように」扉を塞いだという。粛宗の治世には、他の官吏が中書社人事務を担当することが多かった。『新唐書 官吏伝』には、当時「戦乱が勃発すると、人々は慌てて政府から抜け出す方法を探したため、荘を宰相に任命することにした。それ以来、社人はもはや六省の報告を監督しなくなった」と記されている。武宗の徽昌の終わりまで、宰相の李徳裕は再び「太閣の通常の事務と県郡からの請願は、再び社人によって処理されるべきである」と提案した。しかし、この制度は当時は真剣に実施されなかったようだ。 唐代、中書社人は学者や文人が憧れる重要な地位でした。「学者にとって最高の地位であり、朝廷にとって最良の選択」と言われ、州知事や宰相になるための重要な足がかりでした。 さらに、官吏には6等級の官吏が2人いた。『新唐書官吏伝』には、「彼らは歴史記録の編纂、勅旨や皇帝の慈悲の記録、記録制度などの責任を負う。四半期末には国史官の称号が与えられる」と記されている。通司社人は6位以上の16人で、謁見の案内や朝廷への報告を担当していた。出仕に来た側近や、列をなして座る文武の官吏は通司社人によって指導され、お辞儀、起立、入退場の作法を指導された。四方八方の蛮族からの貢物も同氏社人によって受け取られ、奉納された。兵士たちは戦争に行くと、重労働をし、毎月家族を訪ねるよう命じられました。また、第七位の番頭が四人いる。責任者は4名おり、いずれも第8位である。右侍従は三位二名、右納言は五位四名で、朝廷で重要な事柄について助言や批判をしたり、重要な事柄を議論したり、皇帝に秘密裏に報告したりする役割を担っていた。 宋代 宋代には尚書、門下、中書の三つの省が設けられたが、中書の省が最も権力を握っていた。 『宋史官録』には「三部の長は宰相だけではなく、外に尚書と門下があり、さらに中書晋中という政務庁があり、枢密院とともに主要な政務を司る」とある。宋代の中書省の職務は「雑務を提案し、命令を発布し、検閲の告示を執行し、大臣から改革の設立の要請を受け、省、局、寺院、監督、随員、知事、軍知事などの役人を任命すること」であった。中書省は行政権を握っており、軍事権を握る枢密院とともに「両部」と呼ばれていた。 北宋初期、官房は名ばかりで、宮部省とともに皇城外の両翼に置かれ、勅令、請願への返答、試験などの日常的な事務のみを担当していました。宰相府は中書門舎と呼ばれ、略して中書(通称正時堂)と呼ばれ、皇城内にあり、中書省内にはなかった。事務局長は実際には任命されていなかった。中書社人も給与制の官吏であり、勅令を起草することはなかった。その代わりに社人院が設けられ、その中の直司高または直社人院が対外的な勅令を担当した。元豊の官制改革では、官房と人事部の権限を3つの部署に分割し、「官房が命令し、人事部が報告し、商部が実行する」という唐の制度を復活させ、実際の役職に地方官を任命した。同時に社人院は廃止され、中州省が設置された。中書霊の地位は空席のままであったが、右普社(中書世朗)が中書霊の職務を代行し、左普社(孟夏世朗)とともに宰相を務めた。もう一人の中書世朗が副官に任命され、孟夏世朗、尚書左、有成とともに摂政を務めた。しかし、三省の権限分担制は行政上の意思決定の効率性に影響するため、事前に首相と大臣が政務会議で協議し、承認を得た上で「三省共同の勅令遵守」として実施することとした。 南宋代には、官房と人事部が統合されて官房と人事部となった。右宰相と官房長官は右宰相に、官房長官は副宰相に改称された。 廖と金 遼王朝は漢民族を統治するために南方の官僚を使い、その南朝の官僚も唐の制度に従い、3つの州の名にちなんで名付けられました。官房はもともと政務官房と呼ばれていましたが、庚宗皇帝の治世中に改名されました。記録に残る官吏には、中書霊、中書世朗、中書世仁などがいるが、必ずしも実際の役職があったわけではなく、漢民族を誘致したり、名誉や恩恵を示すために使われた者が多かった。 晋の冀宗万延譚は官制を改革し、唐宋の制度を模範として三省を設置した。しかし、書記長は尚書有宰相を兼務し、宰相の下位に位置づけられ、実質的な副大臣や書記は存在しなかった。勅令は翰林書院が担当したため、書記長は名ばかりであった。万延梁は中書省と門下省の二つの省を廃止し、上書省のみを最高官庁とした。 元朝 元朝の創始者フビライ・ハーン以前、モンゴル帝国はジャルクフチによって統治され、大ジャルクフチが最高行政官であった。また、ハーンの啓学組織には、勅書の作成や発布、その他朝廷の事務を担当する毗計(びけい、書記の意味)という役職があり、ウイグル語、中国語、ペルシア語などのさまざまな文書を担当する毗計がいた。モンゴルの支配が拡大するにつれ、法令の発布、貢物の徴収、中原と西域の役人の任命と解任には文書の使用が必要となり、行政におけるビジャチ機関の役割はますます重要になった。ビジャチの長は政府運営に参加することができ、大ジャルクチに次ぐ大臣となった。 1231年、オゴデイが南征の途中、雲中(現在の山西省大同)に駐屯していたとき、中原の官号を真似て、ビジャチ族の首領である野呂初才、念河崇山、鎮海をそれぞれ中央書記局の大臣、左宰相、右宰相に任命し、同時にビジャチ族の組織を書記局と名付けた。しかし、これは中原の漢民族地域を統治する必要性を満たすために中原の正式な名称を使用するための一時的な措置に過ぎず、モンゴル国家の慣習とはならなかった。 中統元年(1260年)に即位したフビライ・ハーンは、中原の官制を導入し、最高行政機関として国政を司る官僚機構を設立した。官吏の任命制度は晋の尚書省の制度に倣った。首席官吏の鍾書令は皇太子が兼任し、皇太子が任命されない場合には空席となった。実際の最高官僚は右丞相と左丞相(元の制度では右が重視されていたため、右が左より上であった)が各1人ずつであったが、右丞相のみのこともあり、右丞相は省全体の事務を担当し、すべての部門を指揮した。平昌正氏は宰相の代理として4人おり、有成氏1人、左成氏1人、摂政である滄芝正氏は2人おり、総じて在氏と呼ばれている。さらに4人の評議員が任命され、事務局の業務を監督し、左派事務局と右派事務局の事務作業を担当し、重要な軍事および国家問題の意思決定に参加した。左部と右部にはそれぞれ、朗中、元外朗、都司などの官吏がいた。事務局は6つの省庁を管轄していた。中統元年(1264年)、左三省(礼・胡・礼)と右三省(兵・興・公)が設けられ、智元元年(1264年)に礼と礼胡兵興公の四省に分かれ、七年後に六省が設けられた。国家統一の過程で、各地域は次々と独自の書記局を設立し、それらはすべて書記局の管轄下に置かれました。山東省、山西省、河北省、および内モンゴルの一部は書記局によって直接統治され、「内陸」を意味する「富里」と呼ばれていました。始元7年から8年、24年から29年、始大2年から4年(1309年)にかけて、3回にわたって官吏が置かれ、財政や税金の管理が行われ、また、平章、有成、左成、滄政などの宰相や高官が任命された。この期間中、行政権は事実上事務局に属し、それに応じて事務局の各部門も事務局に変更されました。事務局は廃止され、権力は中央事務局に戻された。 元朝の官府には遠隔地にいくつかの支局(特別な行政機関、政府機関)があり、それぞれ興中州省(略称は興盛)と呼ばれ、後には管轄地域を指すようになった(ただし官府自体は直接管轄する「腹」を指してはいない)。 注: 事務局 (「Fu Li」) の直接の管轄は事務局ではありません。これは、事務局が元々行政区ではなく事務局の支部であったのと同じです。元代の「中書聖」には二つの意味があり、その一つは「腹」の行政区であるという説もあるが、これは誤りである。 明代 明代初期には元の制度が踏襲され、国政を司り六省を監督する官房が設立され、非常に強い権限が与えられました。洪武13年(1380年)、明の太祖朱元璋は宰相胡衛庸を殺害し、これを機に官房を廃止した。政府を6つに分け、皇帝の政治に直接責任を持たせた。権力の集中化は前例のないほど強化され(胡衛庸の件を参照)、官房の舎人のみが存続した。清代には中書科が存在したが、中書生ほどの地位はなく、監督機能のみを有していた。 |
<<: 古代西夏王国を建国したのは誰ですか?西夏王国は何年間続きましたか?
>>: 「明代の四大巨匠」の一人である邱英はどんな絵画を得意としていたのでしょうか?代表作は何ですか?
推薦する
清朝時代に度々禁じられた『連成壁』とはどのような物語でしょうか?
清朝時代に何度も禁じられた『連成秘』とはどのような物語なのでしょうか?実はこの本は主に市井の庶民の人...
曹植といえば、なぜ彼に対する最も有名な評価は「彼の才能は並外れている」なのでしょうか?
曹植といえば、まず思い浮かぶのは七段詩「豆を煮てスープを作り、発酵した黒豆を濾して汁を作る。鍋の下で...
劉長青の詩の有名な一節を鑑賞する: 憧れと悲しみに満ちた砂州の白い蓮を誰が見るだろうか?
劉長清(生没年不詳)、法名は文芳、宣城(現在の安徽省)出身の漢民族で、唐代の詩人。彼は詩作に優れ、特...
「肘の救急処方」第6巻第48号、虫などによる耳の感染を治療するための処方
『肘の応急処方』は古代中国の医学処方書です。これは中国初の臨床応急処置マニュアルです。漢方治療に関す...
艾公4年に古梁邇が著した『春秋古梁伝』には何が記録されていますか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
古代と現代の驚異 第35巻:王教撰の百年の憧れ(第1部)
『今昔奇談』は、明代の鮑翁老人によって書かれた、中国語の俗語による短編小説集です。馮夢龍の『三語』と...
劉宗元の『漁夫』:この詩は芸術的に特に注目に値する。
劉宗元(773年 - 819年11月28日)は、字を子侯といい、河東(現在の山西省運城市永済)出身の...
王維の『衛成の歌』:この詩は「袁児を安渓に送る」とも題されている。
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
『紅楼夢』の王希峰はどうやって宝玉を宝仔と結婚させたのですか?
『紅楼夢』の王禧峰はどのようにして宝玉を宝斎と結婚させたのでしょうか? 『Interesting H...
『紅楼夢』で袁春は林黛玉に対してどう感じているのでしょうか?
『紅楼夢』の端午節に贈られる贈り物には、深い意味が隠されています。以下の記事は、Interestin...
進化論の思想的意味合いは何ですか?当時、進化論はどのような影響を与えたのでしょうか?
「進化と倫理」の主な考え方は何ですか?「進化と倫理」の影響は何ですか?興味深い歴史がそれを紹介します...
陸游の『夜宮遊夢記・伯勲師に送る』:上部と下部が一体化しており、
陸游(1125年11月13日 - 1210年1月26日)は、字は武官、字は方翁、越州山陰(現在の浙江...
黄超は殺されたのか、それとも自殺したのか?公式または帝国の歴史書にはどのような記録が残されていますか?
唐の末期に、黄超の指揮のもと、活発で大規模な農民反乱が勃発した。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹...
慕容超の祖父は誰ですか?慕容超の祖父慕容黄の略歴
慕容超(384年 - 410年)、号は祖明、南燕の献武帝慕容徳の甥、北海王慕容奴容の息子であり、十六...
人物画の技法にはどのようなものがありますか?線画、繊細で色彩豊かな絵画、フリーハンドの絵画
人物画の基本技法: 中国と海外の両方における絵画の発展の初期の歴史では、人物画が主な焦点であり、宗教...