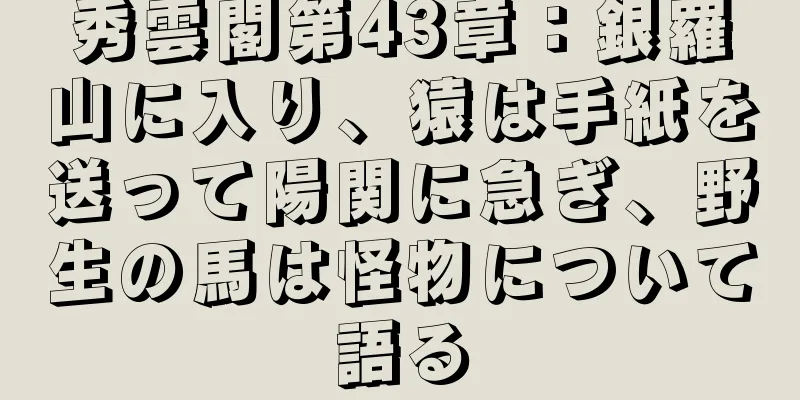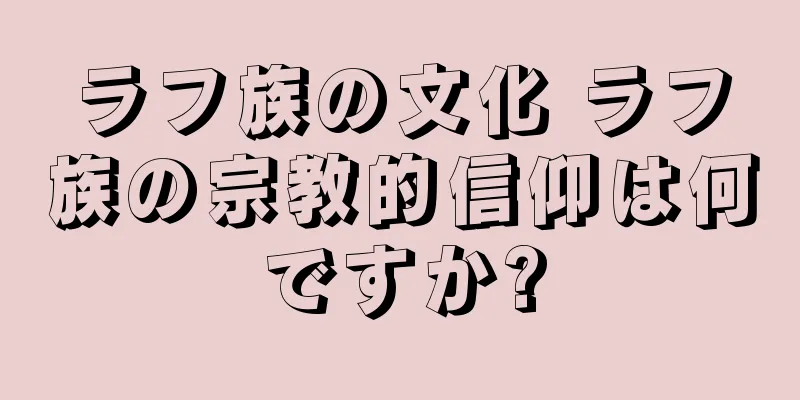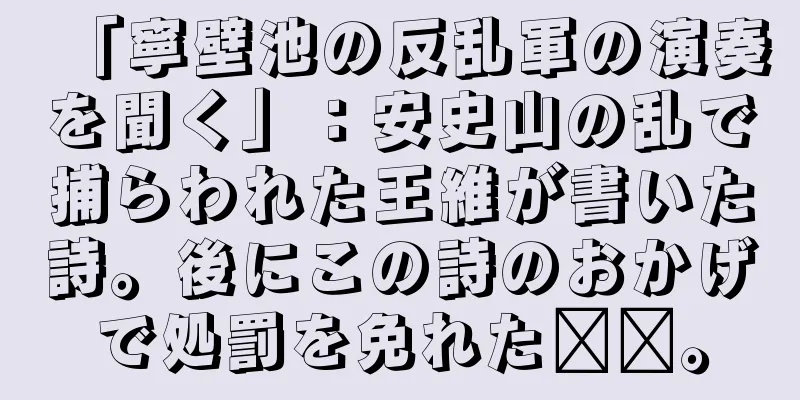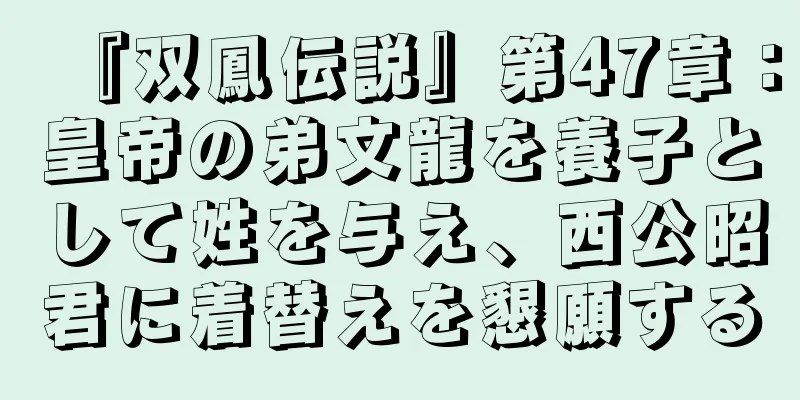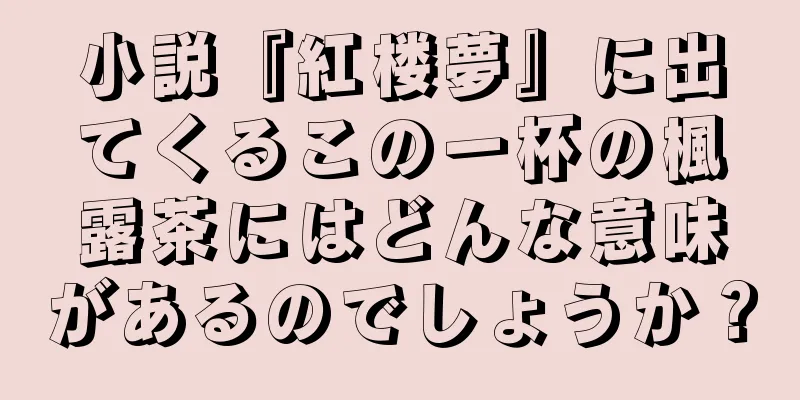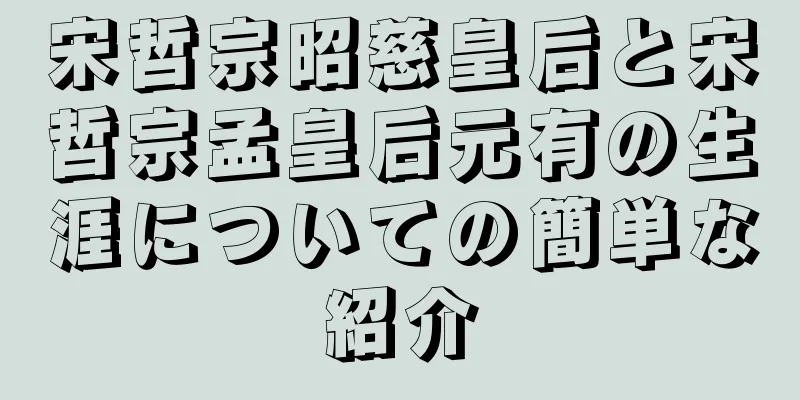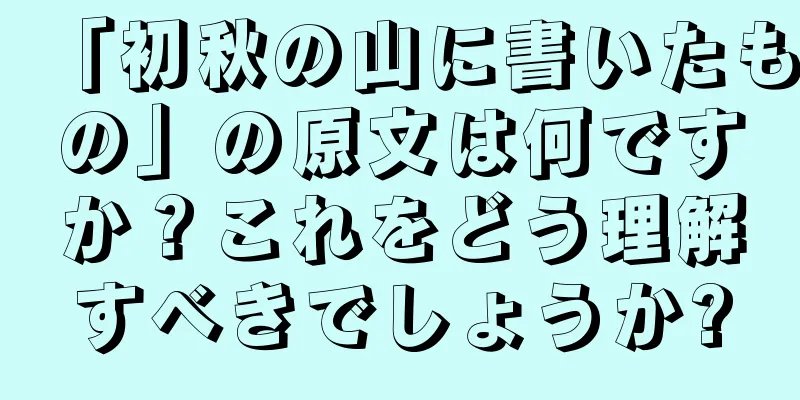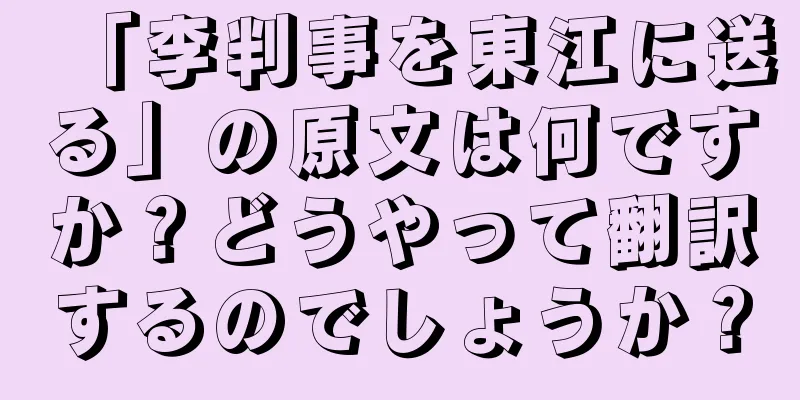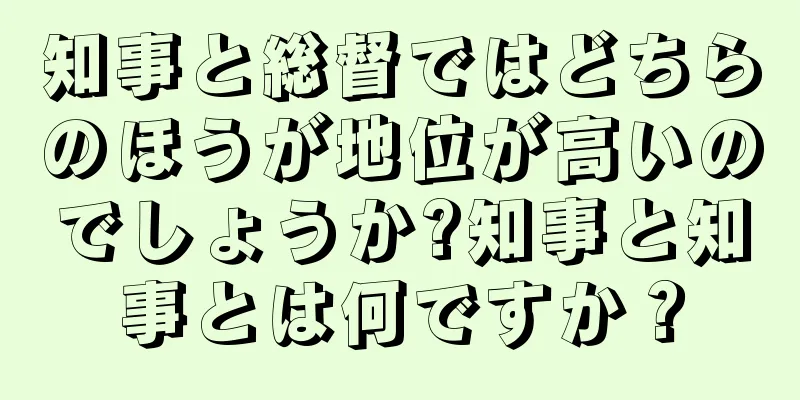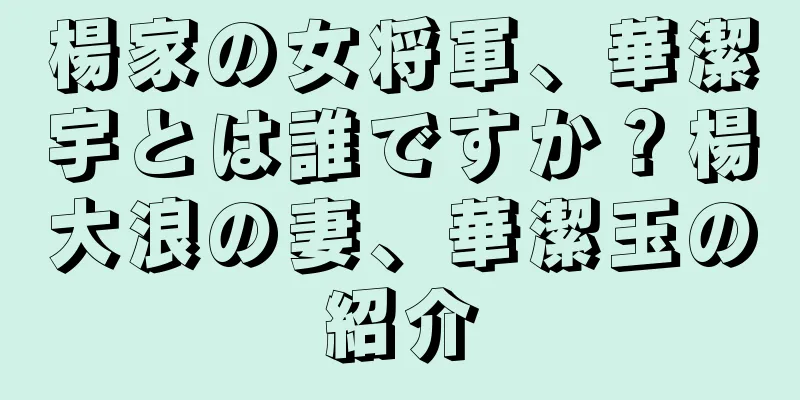古代中国では官職はどのように順位付けされていたのでしょうか?官職の順位と役職名!
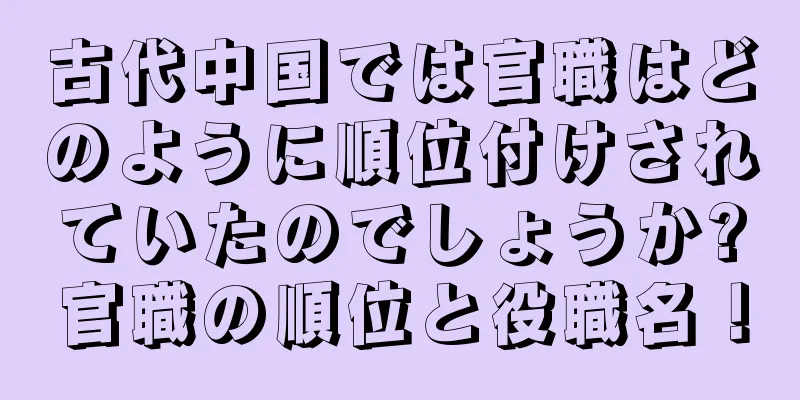
|
古代中国では官職はどのようにランク付けされていたのでしょうか?官職のランクと称号!Interesting Historyの編集者が詳細な関連コンテンツを提供します。 【ジェイド】 爵位は称号や貴族の称号を意味し、古代の皇帝が高貴な親族や功績のある役人に授けたものです。昔、周の時代には公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵の5種類の貴族が存在したと言われています。後世の貴族の称号と貴族制度は、時代によって頻繁に変化しました。例えば、漢代初期、劉邦は太子に王号を授けただけでなく、彭越を梁王、英布を淮南王とするなど、功績のあった7人の官吏にも王号を授けた。魏の曹植はかつて陳王、唐の郭子義は汾陽王の爵位を授けられた。清朝の初代皇帝ヌルハチは、息子の阿爾娥を英王、多多を虞王、郝歌を蘇王に授けた。例えば、宋代には、崔準が莱公、王安石が荊公、司馬光が文公を賜り、明代には、李山昌が漢国公、李文忠が曹公、劉基が承義伯、王陽明が新建伯を賜り、清代には、曽国藩が一級の易容侯、左宗棠が二級の克靖侯、李鴻章が一級の遂義侯を賜った。 【首相】 内閣総理大臣は封建官僚機構の最高責任者であり、君主の意志に従って国政を運営する人物です。彼は首相と呼ばれることもあり、またしばしば首相、略して「首相」と呼ばれることもあります。例えば、『陳社伝』には「広氏には王、王子、将軍、大臣はもういないのか」とあり、『廉頗・林相如伝』には「将軍や大臣はおろか、庶民ですら恥ずかしい」とあり、『蜀宰相』には「宰相の祠はどこにあるか。金官城の外には密生した糸杉がある。 「『ガイドブック』追記」:「私は右宰相兼枢密顧問官、そして全軍の司令官に任命されました。 ” 【グランドマスター】 二種類の官職を指す。まず、古代では太師、太夫、太宝は「三公」と呼ばれていたが、後世では主に高官に与えられた称号で、寵愛は示したものの実際の地位は示さなかった。例えば、宋代の趙普と文延伯はかつて太師の称号を与えられた。第二に、古代では、太子太師、太子太師、太子太守は「東宮三師」とも呼ばれ、彼らは皆太子の師でした。太師は太子太師の略称であり、後に徐々に名誉称号になりました。例えば、『梅花霊記』の「燕太師が戦死」では、燕真卿はかつて太師の称号を与えられたため、そのように呼ばれました。例えば、明代の張居正は8つの尊号を持ち、最終的に太子太傅の称号を与えられた。清代の洪承周も太子太傅の称号を与えられたが、実際には太子を指導することはなかった。 【グランドチューター】 「グランドマスター」の項目を参照してください。古代の「三公爵」の一人。また、「東宮の三師」の一人を指す。例えば、賈懿は長沙王と梁淮王の師を務めていたため、太夫と名付けられた。その後、次第に名誉称号となり、例えば曾国藩、曾国全、左宗棠、李鴻章などは死後、強制的に太夫の称号を授けられた。 【若き守護者】 二種類の官職を指します。まず、古代には、少氏、少傅、少宝の3人が「三孤児」と呼ばれていましたが、次第に尊称となり、『梅花霊記』には「少宝文も大光法を悟って逃れた」とあり、文天祥もかつて少宝を務めていたため、そう呼ばれるようになりました。第二に、古代には太子の侍従、太子の師匠、太子の護衛は「東宮の三童」と呼ばれていましたが、後に徐々に名誉ある称号になりました。 【商書】 もともとは文書や記念碑などを管理する役人だった。六部は隋代に廃止され、唐代に人事、歳入、礼、兵、刑、工の六部が設けられ、各部の長官と副長官として尚書と士朗が置かれた。例えば、『張衡伝』には「皇帝に遺骨の埋葬を懇願する手紙を書き、国務長官に任命された」とある。また、かつて人事部長を務めた書家の顔真卿、かつて司法部長を務めた詩人の白居易、かつて陸軍部長を務めた石克法などもその例である。 【学士】 魏晋の時代には、儀式や諸事の取りまとめを担当する官職であった。唐代以降は、皇帝の秘書官や顧問となり、機密事項に携わった翰林学者を指し、「内大臣」と呼ばれた。明清代においても、勅書、随書、随講師、編集者、学者は翰林学者であったが、その地位や職務は唐宋代のものとは異なっていた。例えば、『後記』には「紫正宮の学者に任命された」とあるが、これは文天祥が宰相を退いた後に与えられた官職であり、『譚思同』には「王は学者徐志静を推薦した」とあるが、徐志静は当時翰林書院の学士であり、皇帝に講義を行うための官職であった。白居易、欧陽秀、蘇軾、司馬光、沈括、宋廉などは皆翰林の学者であった。 【上清】 周王朝の官制では、皇帝と諸侯は皆大臣を擁し、大臣は上・中・下の三階級に分かれていた。最も名誉ある大臣は「尚青」と呼ばれた。例えば、『廉頗・林相如伝』には、「廉頗は趙の将軍であり…宰相に任命された」とある。 【一般的な】 これは先秦時代と前漢時代の将軍の最高の称号であった。例えば、漢の高祖は韓信を将軍に任命し、漢の武帝は衛青を将軍に任命した。魏晋の時代以降、徐々に実質的な職務を伴わない空虚な称号となっていった。将軍の地位は明・清の戦争中に設立され、戦争後に廃止された。 『張衡伝』には「将軍鄧植はその才能に驚いた」とある。鄧植は当時漢の何帝の将軍であった。 【国務参事官】 「政治参加」とも呼ばれます。彼は唐・宋時代の最高政治官僚の一人であり、同平章氏、叔米氏、広密夫氏とともに「在直」と呼ばれていました。宋代には范仲燕、欧陽秀、王安石らがこの地位に就いた。 『倹約養生訓』には「参議呂公が検閲官に任命された」とある。「呂公」とは宋代真宗皇帝の治世中の呂宗道を指す。 「タン・シトン」 「新しい政策に参加する人々は、唐や宋の時代の副大臣、つまり実際には首相のような存在です。」 【軍事大臣】 太政官は清朝時代に皇帝を補佐した行政機関であった。この役職に就く人数は決まっておらず、一般的には王子、大学の学者、大臣、副大臣、都の役人などが兼任し、太政大臣と呼ばれます。大顧問官の数は3~4人から6~7人までで、「枢密大臣」と呼ばれていました。清朝末期には、左宗棠、張之洞、袁世凱らが短期間だけ太政大臣を務めた。 「譚思同」「当時の太政大臣の姜義が処刑を監督した。」 【張静軍事書記】 「大顧問」の項目を参照。彼は大評議会の職員であり、大評議会の部下であり、「小さな大評議会」と呼ばれていました。譚思同:「皇帝は4人の景卿を軍書記に昇進させ、楊睿、林旭、劉光迪とともに新政策に参加した。」 【帝国検閲官】 もともと歴史家であり、『廉頗・林相如伝』には「秦の検閲官が彼の前で書いた」「相如は引き返し、趙の検閲官を呼んで書いた」などとある。秦の時代以降、宰相に次ぐ地位にある検閲官が設立され、官吏の誤りを弾劾し調査する役割を担った。明代の韓愈はかつて検閲総長を務め、海鋭はかつて南京の右検閲総長を務めた。もう一つの例は、『王中粛公敖事記』に「公は検閲官長で、宦官を率いて遼寧を守った」とある。当時、王敖は検閲官長であった。 【枢密顧問官】 枢密院の長。唐代には宦官が務め、宋代以降は大臣が務めるようになった。枢密院は軍事と国政を司る最高国家機関の一つで、枢密顧問官の権力は首相に匹敵する。清代には軍事大臣はしばしば敬意を込めて「枢密顧問官」と呼ばれた。宋代の欧陽秀はかつて枢密使副使を務めた。 『指南録』には「右宰相、枢密顧問官、諸軍の総司令官に任ぜられた」とある。当時、文天祥は重要な軍事問題を担当していた。 【左火】 戦国時代の楚国の官称で、後世の左氏義・右氏義に相当する。主な職務は皇帝に助言し、才能のある人を推薦することであった。 「屈原の伝記」:「屈原は、名前を平といい、楚と同じ姓を持ち、楚の淮王の右腕であった。」 【グランドコマンダー】 元代以前の官職名。彼は皇帝を補佐する最高位の軍事官であり、漢代には大司馬と呼ばれていました。宋代に最高位の武官に定められた。 「雪山寺の林師匠」:「私は高将軍を怒らせたので、彼に罪を着せ、訴訟に巻き込まれた。」高将軍は高秋のことを指している。 【尚大夫】 秦以前の時代の官名で、清より一つ下の位にあった。 『廉頗・林相如伝』には「相如を高官に任ず」と記されている。当時、林相如の官職は高官の廉頗よりも低かった。 【医者】 この用語の内容は王朝によって異なり、時には検閲官や大納言など中央政府機関の重要な役職を指すこともあります。 『屈原伝』には、「上官大夫は彼と同格で、寵愛を競い合ったが、彼の能力に嫉妬していた」とある。「上官大夫」は、一般的に上官金尚のことを指すと考えられている。 「あなたは三長の大臣ではないのですか?」屈原は趙、屈、荊の3つの王家の政務を担当する最高官僚でした。 『指南書の追記』には「左宰相府に集まった諸君、官吏、学者」とある。これは検閲官長、参事官などを指している。 【学者・官僚】 昔は、比較的高い名声と地位を持つ役人や知識人を指していました。 『師論』には「士官一家が互いに師弟と呼び合うと、一同が笑う」とある。『石鐘山記』には「士官たちは夜、崖の下に船を停めようとしなかったため、誰も知らなかった」とある。『倹約養生訓』には「当時の士官一家は皆このようだった」とある。『五人墓誌』には「郡内の賢明な士官たちが当局に助けを求めた」とある。 【太子】 西周から春秋時代にかけて、文書の起草、君主や大臣の任命、歴史の記録、経典、暦、祭祀などの管理を担当した高官の大臣でした。秦漢の時代以降、史官の職が設けられ、その職務範囲は次第に狭まり、地位も低下していった。司馬遷は史官を務めた。 『張衡伝』:「舜帝の治世の初めに、彼は再び転任し、再び太史となった。」 『五人碑文』:「徳の高い学者や官吏は、私に言わせれば武公、太史の文斉は文公、孟昌は堯公である。」 文斉は翰林書院の編纂者であり歴史家であったため、太史と呼ばれていました。 【主な経歴】 秦の時代、彼らは宰相の下で働く役人でした。例えば、李斯は宰相の秘書長に相当する主史を務めたことがあります。漢代以降は将軍の部下となり参謀長となった。 『帝都退去の碑』には、「世忠、尚書、長師、燕鈞は皆忠義に篤く、国のために命を捨てる覚悟のある臣下である」とある。「長師」とは張業のことである。 「赤壁の戦い」:「子豫は梁の弟の金である。彼は混乱を避けるために江東に逃げ、孫権の書記長となった。」 【大臣】 彼は当初、宮廷の侍従として勤務していた。東漢以降、商書の官吏となった。唐代以降、士郎の地位は三部(中書、門下、商書)の各部の宰相(商書)の副となった(詳細は「三部六部」の項を参照)。韓国愈は司法省、陸軍省、人事省の次官を歴任した。 『下都追慕録』には「世忠、世浪、郭有志、費益、董雲等」とあり、董雲は世浪である。 「譚思同」:「8月1日、皇帝は袁世凱を召し出し、特別に副大臣の称号を与えた。」袁世凱は陸軍省の副大臣であった。 【大臣】 もともとは正規の官職以外の付加的な官職のひとつであった。彼は皇帝に仕えたため、次第に地位が上がり、大臣の位を超えた。魏晋の時代以降、彼らは事実上の宰相となることが多かった。 『離都碑』に記されている郭有之と費毅は世忠である。 【医者】 戦国時代の宮廷の衛兵であった。唐代から清代にかけて、彼らは尚書や士郎以下の高官となり、各部署の事務を担当した。たとえば、荊軻の『秦始皇帝暗殺』では、「宮廷の衛兵は皆皇帝に従う」とあります。これは宮廷の衛兵のことを指しています。 『張衡伝』には「皇帝から閔中に任命された」と記されている。「閔中」とは、車両や騎兵を担当する役人の名である。 【軍隊に入る】 「軍務官」の略称で、もともとは『離都追悼文』に登場する軍事顧問の蒋琳のような首相の軍事顧問を指す。晋の時代以降、彼らの地位は次第に低下し、王や将軍の参謀となった。例えば、陶淵明はかつて真君軍の武官を務めたことがあるし、『後漢書』の著者である范業はかつて劉愈の四男である劉易康の武官を務めたことがある。隋唐以降、彼らは次第に地方官吏となり、例えば杜甫は右衛門の武器庫の副武官や華州工部の副武官を務め、白居易は荊昭府の内務部の副武官を務めた。 【リン・イン】 戦国時代、楚の国で軍事と政治の権力を担う最高官吏は宰相に相当し、例えば『屈原伝』には「霊隠子蘭はこれを聞いて激怒した」とある。明清時代には郡長官を指し、例えば『蟋蟀』には「天は親切で寛大な人に報いる。そのため、傅塵と霊隠はともに蟋蟀の祝福を受けた」とある。 【陰】 「Ling Yin」の項目を参照してください。戦国時代、楚の霊隠の補佐役には左隠と有隠がいた。『鴻門の宴』の「楚の左隠、項伯」など。左隠の地位は有隠よりやや高かった。景昭殷、河南殷、周殷、献殷など古代の官僚の総称でもある。 【指揮官】 将軍より下の階級の軍人。 「陳奢伝」:「陳奢は自らを将軍に任命し、呉広を隊長に任命した。」 「鴻門の宴」:「沛公が去った後、襄王は隊長の陳平を派遣して沛公を召喚した。」 【蒋青】 天皇の車、馬、家畜を管理する宮内大臣の別名。五人の墓碑銘:「高徳な学者や官吏の中で、蔣銀之氏は呉墨氏である。」 「銀之」は呉墨の敬称である。 【シマ】 異なる王朝で言及される公式の地位は同じではありませんでした。戦国時代には、軍務と軍事税を担当する副官であり、『鴻門宴会記』には「沛公の左司馬曹無尚が言った」とある。隋・唐時代には、県知事や郡知事(巡査)の下級官吏であり、『琵琶歌』には「元和10年、九江県の司馬に降格した」とある。当時、白居易は九江に降格しており、その地位は県知事や郡長よりも下位であった。 【ジエドゥシ】 唐代には、複数の国の軍事や政治を統括する総督が、もともとは辺境の国にのみ設置されていたが、後に内陸部にも設置され、分離独立の状況が生じたため、「梵鎮」と呼ばれた。 『紅楼夢』第4章:「玉村は急いで賈徴と北京陣営の知事である王子騰に2通の手紙を書いた。」 【天皇】 「Jinglüe」とも呼ばれます。唐代と宋代には、総督と同等の国境防衛の軍事長官であった。例えば、范仲燕はかつて陝西省の副使を務めたことがある。明・清時代には、軍事上の重要な任務がある場合、総督よりも高い官位を持つ特別の軍知事が任命されました。例えば、『梅花嶺記』には「洪承周太守は彼と古い縁があった」とある。洪承周が清朝に降伏した後、彼は7つの省の太守を務め、江寧に駐在していた。 【州知事】 もともとは監察官の名称であったが、後漢以降は県や郡の最高軍事・政治長官となり、知事と呼ばれることもある。唐代には白居易が杭州と蘇州の太守を務め、劉宗元が柳州の太守を務めた。 【グランドマスター】 「州知事」の項目を参照してください。 「郡政官」とも呼ばれ、州または郡の最高行政官。范燁はかつて宣城の知事を務めた。 「桃花春」:「私は郡に着くと、知事のところに行き、このことを話しました。」 「孔雀が南東に飛ぶ」:「知事に、彼の家にそのような若者がいると伝えました。」 「赤壁の戦い」:「私は蒼武の知事である武居と古い関係があり、彼と一緒に避難したいと思っていました。」 【ドゥドゥ】 「Jinglüe Shi」の項目を参照してください。軍司令官または将軍の官職名。一部の王朝では、地方の最高官吏も「杜杜」と呼ばれ、街道使または県級知事に相当した。例えば、『梅花霊記』には「州知事の任敏宇、将軍の劉昭基らは皆死亡した」と記録されている。劉昭基は地方駐屯軍の指揮官であった。 【知事】 明代初期には、北京の役人が地方を視察することを指していた。清代には正式に省の地方長官となり、総督より少し低い地位となった。別名「扶遠」「扶台」「扶鈞」とも呼ばれた。例えば、『五人碑文』には「当時、呉を平定するために太政大臣に任命されたのは、魏の私人であった」とある。呉を平定するということは、呉の知事を務めることを意味する。 【ふじゅん】 「知事」の項目を参照してください。 「コオロギ」:「それで彼は労働者の功績に報いて、それを軍の知事に贈りました。」軍の知事は非常に喜んで、皇帝に金の檻を贈りました。 「皇帝が傅辰に名馬や名服、名繻子を授けたことから『傅辰』とも呼ばれる。」 【キャプテン】 漢代における将軍に次ぐ官職。例えば、『赤壁の戦い』では、「魯粛が軍司令官に任命された」とあります。当時、魯粛は副将軍として、司令官の周瑜を補佐して軍事作戦を計画していました。唐代以降、その地位は徐々に低下していった。 【コーチ】 宋代の軍隊で武術を指導した将校。『水滸伝』の林冲は、都の80万人の近衛兵の槍棍の師範を務めた。 【ティシア】 宋代に県や郡に所属し、軍隊の訓練や盗賊の捕獲などを担当した武官の官称。 『水滸伝』の呂氏の隊長、呂智深など。 【婚約】 中央官僚や地方官僚によって任命された部下も「職員」と呼ばれる。 「赤壁の戦い」:「景の名声と地位は依然として失われていない。」 【知事】 つまり「大正」、別名「支州」です。 『泰山登山記』:「今月25日、州知事朱暁春の紫瑩とともに南斜面から登頂した。」 【郡知事】 郡の最高執行者。「治安判事」とも呼ばれる。 「孔雀は南東へ飛ぶ」:「10日以上家に帰ってから、郡知事は仲人を派遣した。」 【李政】 古代では、郷役人は村の長でした。たとえば、「クリケット」では、「村長に責任を負わせろ」 【李旭】 村の事務を管理する役人。 「コオロギ」:「村役人は狡猾で、この税金を利用して住民から税金を徴収している。」 【3つの州と6つの省】 3つの省とは、官房、故宮博物院、官房の3つです。隋唐の時代、三省は最高政府機関であった。一般的に、官吏部は意思決定を担当し、人事部は審議を担当し、商書部は執行を担当した。三省のトップはいずれも宰相であった。官房長官は官房令と呼ばれ、その下に官房副総裁、官房長官などの官吏がいた。人事省長官は官房侍従と呼ばれ、その下に官房副総裁、官房総長などの官吏がいた。国務省長官は官房令と呼ばれ、その下に左官、右官などの官吏がいた。尚書省には、人事部(官吏の任免を担当、現在の組織部に相当)、歳入部(土地登記、課税、財務などを担当)、礼部(儀式、科挙、学校などを担当)、陸軍部(軍事を担当、現在の国防部に相当する)、懲罰部(司法、監獄などを担当、現在の司法省に相当する)、工務部(土木建築、軍農場、水利などを担当)の6つの部局が置かれていた。各部の長は尚書、副長は士朗と呼ばれ、その下に郎中、元外郎、朱師などの官吏がいた。六部制は隋・唐の時代から実施され、清朝末期まで続いた。 【役員の任命、解任、昇進、降格】 「三省六省」制度の施行後、公務員の昇進や任命は人事省の管轄となった。公務員の任命、解任、昇進においては、次のような用語がよく使用されます。 (1)礼拝。特定の儀式によって特定の公的地位または称号を授与すること。例えば、「手引書後記」には「かくて総理大臣の印を辞退し、その職に就くことを拒絶した」とあり、総理大臣の印を受けず、その職に就かなかったという意味である。 (2)除く。官職を任命する。例えば、「予处右先相兼封密仕仕」(《 (指路錄>后序) ) という文では、「予处」は官職を授与することを意味します。 (3)促進する。官位の昇進。『戦国の戦略 燕の戦略』に次のように記されている。「先王は客人の中から官吏を昇進させ、大臣よりも上に置いた。」 (4)移転官職の異動には、昇進、降格、同格異動の3つのケースがあります。区別しやすくするために、「前」の前後に単語を付けることが多いです。昇進は「前昇」「前手」「前休」、降格は「前暁」「前哲」「左前」、異動は「転前」「前官」「前釣」、退職後に元の職に戻ることは「前復」と呼ばれます。 (5)追放。降格または遠隔地への転勤。 『岳陽塔碑文』の「滕子静は巴陵県に配流された」の「氪」は降格を意味する。 (6)降格「解任」や「解任・削除・奪取」はいずれも公職から解かれることを意味します。例えば、『国語』には「公は皇太子神勝を廃し、西斉を即位させる」とある。 (7)行く。職務の終了には、辞職、転勤、解雇の3種類があります。辞職や転勤は一般的な事情による公職への調整であり、解雇は平民への降格である。 (8)遺骨を乞う。張衡は老齢になると辞職して引退を願い出た。『張衡伝』には「在職三年後、皇帝に退位を願い出る手紙を書き、国務大臣に任命された」とある。 |
<<: 三国志の状況はどのようにして起こったのでしょうか?三国志の理由は何だったのでしょうか?
>>: 北魏はどうやって分裂したのですか?北魏が分裂した理由は何だったのでしょうか?
推薦する
九門総司令官と清朝近衛軍太政大臣のどちらがより権力を持っているでしょうか?彼らの分担はどうなっているのでしょうか?
みなさんこんにちは。Interesting Historyの編集者です。今日は、清朝の九門総司令官と...
三英雄五勇士第75章:倪知事は途中で再び危険に遭遇し、裏切り者は黒狐の牢獄で暗殺された
清朝の貴族の弟子、石宇坤が書いた『三勇五勇士』は、中国古典文学における長編騎士道小説である。中国武侠...
帝王切開は本当に華佗から始まったのでしょうか?華佗に関して学界には二つの派閥があるのでしょうか?
華佗は中国の歴史上有名な医学者であり、彼が「麻妃散」を用いて開腹手術を行ったことは、中国医学の歴史に...
『夜の船 西の都の楽しい日々を思い出す』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
夜の船:西の首都の喜びを思い出す欧陽秀(宋代)西の首都での楽しい日々を思い出します。別れてしまった今...
なぜフランスのルルドへ巡礼するのでしょうか?フランスのルルドの湧き水にはどんな不思議な伝説があるのでしょうか?
フランスのルルドには毎年何百万人もの巡礼者がいます。なぜ人々はルルドに熱心に通うのでしょうか?ルルド...
李白の「四川入友別れ」:この詩は後世に「正真正銘の五字律詩」と賞賛された。
李白(701年 - 762年12月)は、太白、清廉居士、流罪仙とも呼ばれ、唐代の偉大な浪漫詩人です。...
『紅楼夢』で林志霄の家族が王希峰を裏切った最も重要な理由は何ですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
『雲済寺に泊まる』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
雲池寺に泊まる文廷雲(唐代)道は深く、白い雲に覆われており、東峰の弟子たちは遠くから彼を探しています...
梁山が方羅と戦いに行ったとき、石秀、石進、その他 6 人の死の責任は誰が負うべきでしょうか?
『水滸伝』では、陸俊義は武術の達人であるだけでなく、作戦指揮に長けた軍事的才能も持ち合わせており、涼...
宋代の詩にある梅の花を題材にした2つの四行詩のうち最初の詩の鑑賞:陸游はこの詩の中でどのような場面を描写したのでしょうか。
宋代の陸游による『梅花二連歌 第一番』。以下、Interesting History編集部が詳しく紹...
古典文学の傑作「夜の船」:軍事と軍事
『夜船』は、明代末期から清代初期の作家・歴史家である張岱が著した百科事典である。この本は、あらゆる職...
『魏平石送還』の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
魏平石を送る王維(唐代)彼は将軍を追って幽仙を捕らえようと、戦場の固遠に向かって馬を走らせた。漢の使...
清朝の中秋節:庶民は1日祝うが皇帝は3日間祝う
清朝時代の中秋節では、一般の人々は1日だけ祝いましたが、皇帝は通常3日間祝い、西太后の場合は5日間祝...
長孫無忌の息子、長孫充の紹介と、長孫充の結末は?
長孫崇は河南省洛陽出身で、唐代の王妃であり、長孫無忌の息子であった。 633年、当時皇族の少慶であっ...
『紅楼夢』で、薛叔母さんが大観園に入ったとき、なぜ彼女は宝斎の横武園に住んでいなかったのですか?
『紅楼夢』で、薛叔母が大観園に入ったとき、なぜ宝斎の横武院に住まなかったのですか? その代わりに、林...