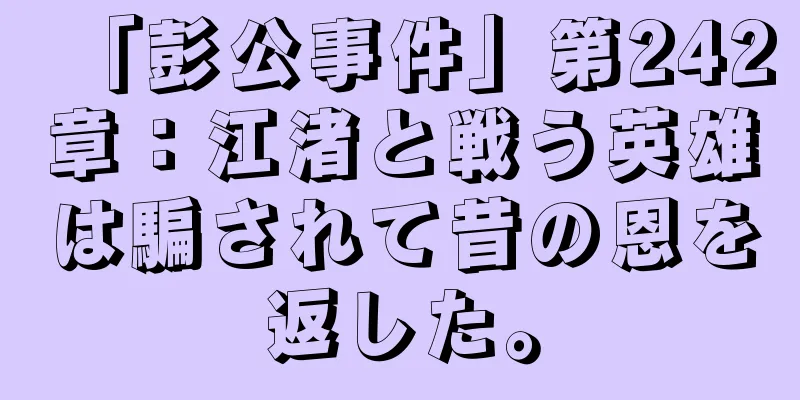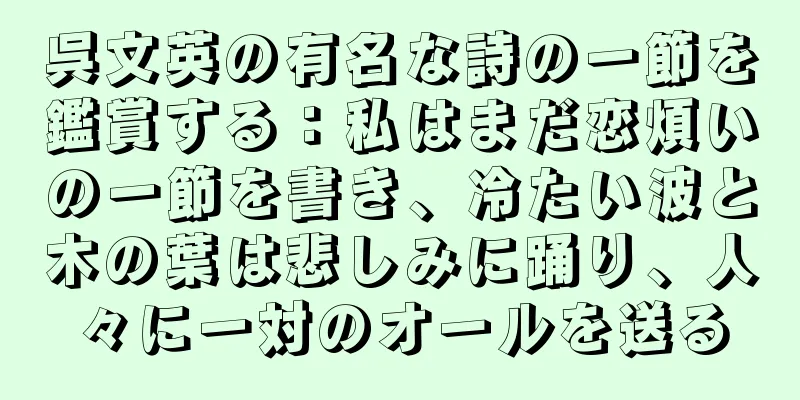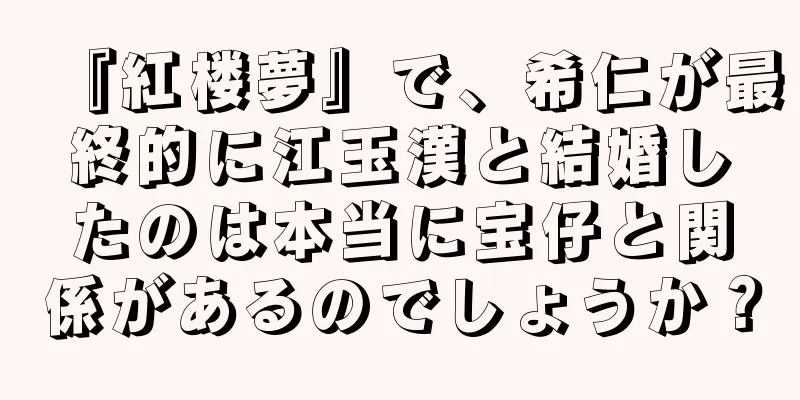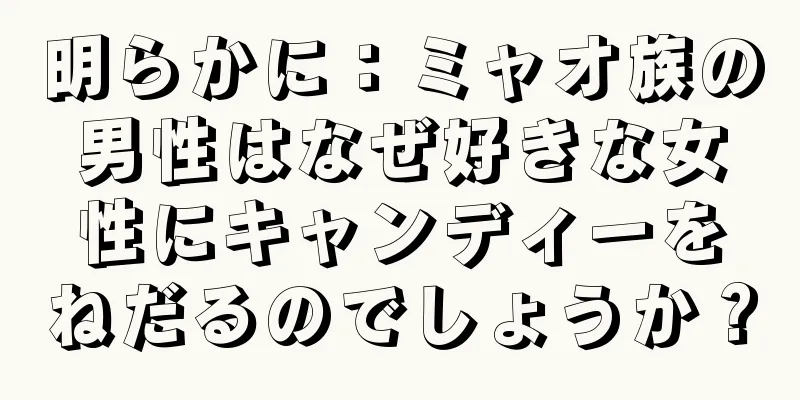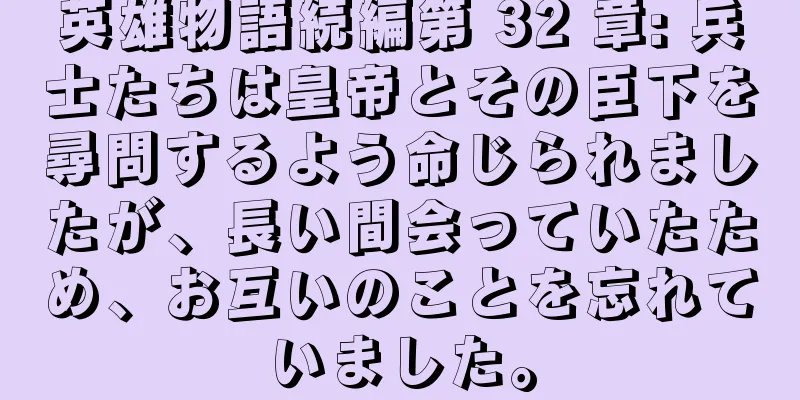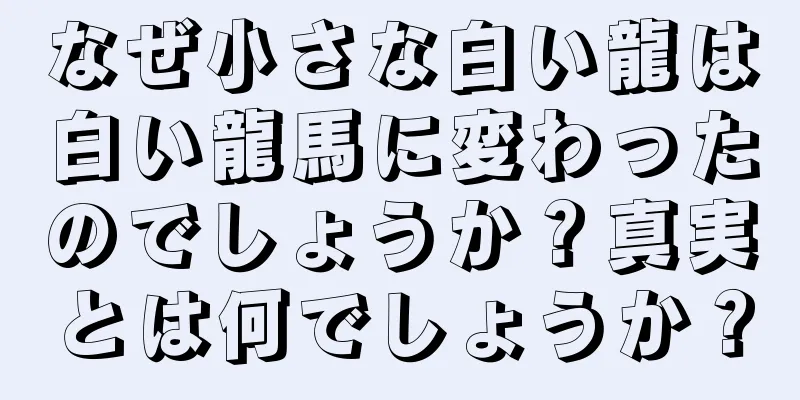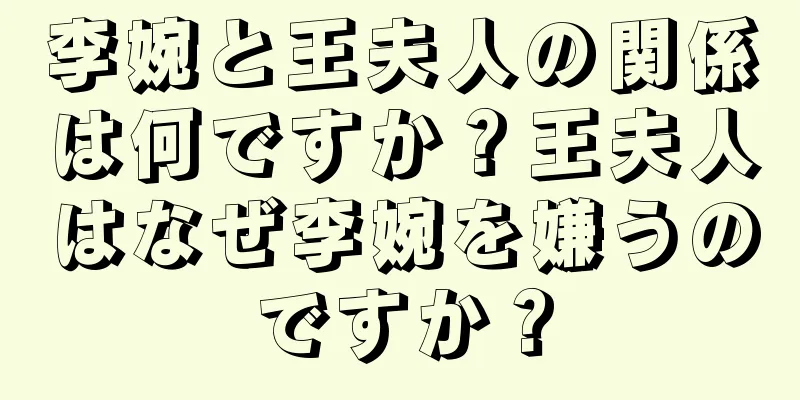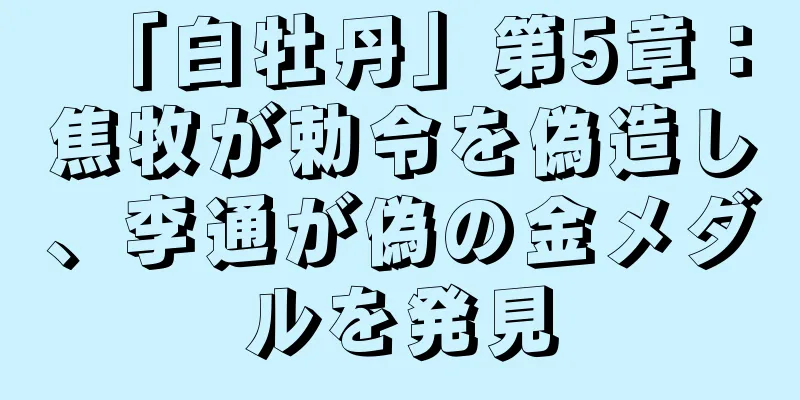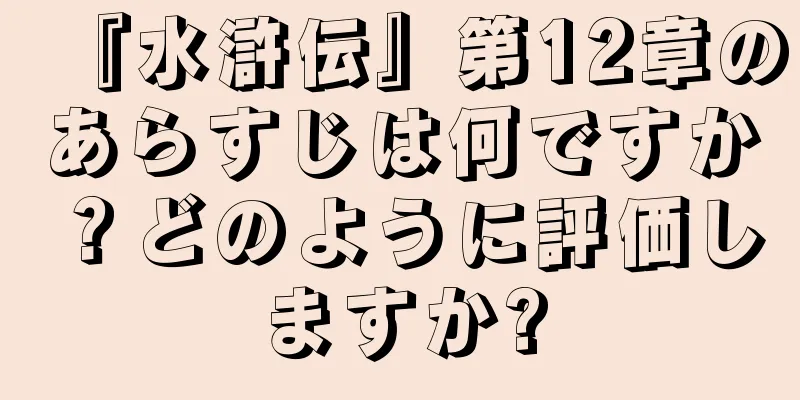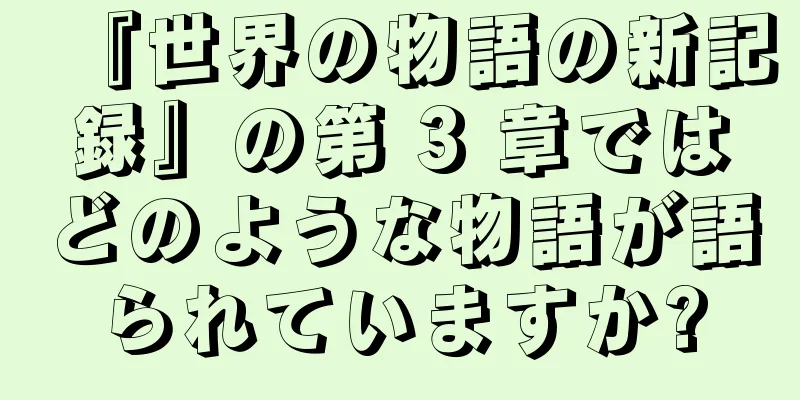孫斌は『兵法』の著者ですか? 『孫子の兵法』はどのようにして生まれたのでしょうか?
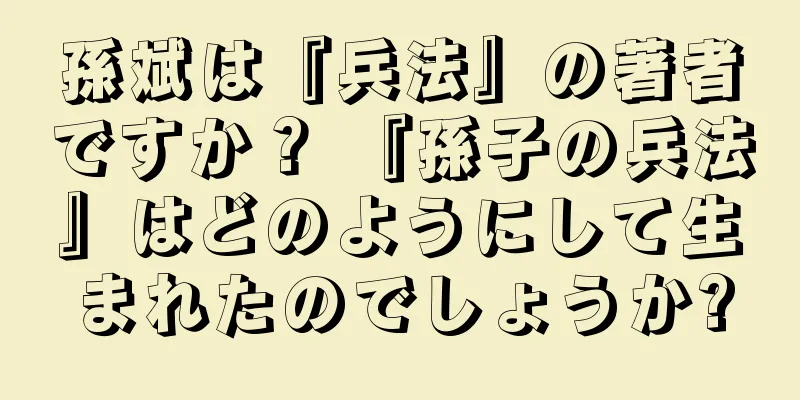
|
孫斌は『兵法』の著者ですか?『兵法』はどのようにして生まれたのでしょうか?次の『Interesting History』編集者が詳しい答えを教えてくれます。 「兵法」といえば、多くの人が知っていると思いますが、その由来をご存知でしょうか。今日は、その由来についてお話しします。兵法に込められた知恵は、現代にも通用します。 伝説によると、『兵法』は春秋時代の呉の将軍孫武によって書かれたと言われています。しかし、当時から現在に至るまで、人類の歴史上の戦争と同様に、孫子の著者が呉の将軍孫武であるかどうかについての議論は絶えませんでした。戦国時代には、『商陽書』や『韓非子』などの書籍に記載されている「呉の孫子書」は、孫子の兵法と呉子の兵法を指しています。 しかし、著者が孫武であるとも明記されていませんでした。漢代になって初めて、司馬遷の『史記』が孫子兵法13章の著作権を孫武に帰しました。数千年にわたって有名だった司馬遷の『史記』の支援により、この本の著作権についてコメントした人は誰もいません。 疑惑は宋代に始まった。宋代の陳真孫は司馬遷の直寨書録の身体検査で直接批判し、兵法は本当に孫武が書いたのか、孫武など本当にいたのかと問うた。その後すぐに宋代の葉石や清代の姚継衡も陳真孫を助けた。もちろん彼らは戯言を言っているのではなく、事実を語り理路整然とした人々である。その根拠は次の通りである。 『史記』には、呉王が楚国を攻撃する際に孫武が協力したことが明確に記されており、また、呉王の二人の側室を殺した宮女についての古典的な物語も言及されているが、これは非常に現実的であるように思われるが、これは小説家の物語なのかもしれない。なぜだろうか? 想像してみて下さい。誰かが君主のもとへ行き、偉業を成し遂げようとしますが、初めて会った時に君主の愛する側室を殺してしまいます。たとえ君主があなたの首をあなたの首に当てたままにしておいても、君主があなたを憎まないのは簡単でしょうか? 君主の信頼を得るのは言うまでもありません。 もう一つの証拠は、『左伝』の呉王の生涯と功績について語るとき、孫武の名が一度も出てこないことです。春秋時代に孫武が本当にいたなら、この人物はこのような大いなる世界に現れたはずであり、『左伝』には孫武について書かれているはずです。 呉の国、特に楚の首都を占領した話は比較的詳しく描かれている。孫武などについては触れられているが、孫武の名前は出てこないので、実在したかどうかは不明である。しかし、呉の国において孫武は脇役のような存在で、決して優れた軍事戦略家ではなかったと言える。 『兵法』が本当に春秋時代に孫武によって書かれたものであれば、その本に欠陥があるはずはない。例えば、春秋時代には富豪が主力として言及されていたが、この本では国軍が主力として繰り返し言及されている。春秋時代に魏徴将軍が国軍を率いて遠征するよう命じられたことはなかった。『兵法』には、将軍が国を留守にしているときは国王の命令に従わなくてもよいと書かれている。 春秋時代の戦争の規模は大きくなく、いくつかの有名な戦いでは数百台の戦車が使われただけだった。このような大規模な戦争は戦国時代にしかできなかった。したがって、『兵法』は戦国時代中期から後期の誰かが書いたものであるはずである。春秋時代の孫武が呉王に献上したのはこの兵法ではなかった。 『兵法書』には10回登場しますが、すべて戦国時代以降の用法です。春秋時代、軍の指揮官は主に君主自身でした。大臣であれば、国の政策を管理する人で、主に君主の近親者または大臣でした。貴族、将軍、宰相はすべて同じ立場でした。将軍と宰相を分けて、軍を管理および指揮する専門の部門はありませんでした。これらはすべて戦国時代のものです。 また、孫子の兵法書には、軍事費について語るときに「千金」という言葉がよく登場し、「百金」という言葉も出てくると書かれています。このことからも、この本が戦国時代に書かれたものであることがわかります。春秋時代には金は通貨ではなく、「金蓮」という数字が一緒に出てくることはありません。 また、『兵法』は孫臏によって書かれたという説や、孫臏は『呂氏春秋』に挙げられている春秋戦国時代の十大名家思想の一つであるという説もある。戦国時代、最も著名な人物は孫臏であり、『戦国の兵法』には孫子の名が何度も登場していることがわかります。例えば、この本には孫子が田済に言ったことが書かれています。孫臏の話に詳しい人なら、孫子が田済に協力した孫臏のことを言っているに違いないと分かります。 同様に、多くの学者がこれらの見解に疑問を抱いており、孫子の著者の謎を完全に解明するには、今後さらなる検証と研究が必要であると思われます。 しかし、『兵法』が我が国の貴重な古代文化遺産であり、中華民族の5000年文明の結晶であることは否定できません。この兵法書は世界でも広く認知されています。例えば、アメリカ人は『兵法』を歴史上最も優れた英知と呼び、アメリカの上級士官学校では必読書となっています。また、日本人は『兵法』をビジネスリーダーの必読書に挙げています。この本には柔軟性についての理解が含まれており、その理論と原則の多くは、人生のあらゆる側面に借用して適用することができます。そのため、軍事戦略は今でも人々によって研究されており、非常に実用的です。そこに含まれる戦略的および戦術的アイデアは、ビジネス環境でビジネス戦略を導くために広く使用できるため、現代の戦争、特にビジネス分野で広く使用されています。 戦争の法則と「道」:秦以前の軍事書では、戦争の一般的な法則を論じる際に、老子の「道」についての考えが散りばめられています。 「道」の意味は、今日私たちが自然法則と呼んでいるもの、あるいは万物の成長の一般原則と同じです。それは人類が従わなければならない法則です。その不変性から、「道」は「チャン」とも呼ばれます。秦以前の軍事書に反映されている戦争の原則はすべて、その思想的起源にまで遡ることができます。軍事戦略家たちは道教独特の哲学思想を自らの軍事理論と融合させ、古代中国の軍事思想に多大な貢献をしました。 『孫子』を注意深く読むと、その中心となる議論は戦略であることがわかります。戦略とは人類の知恵の結晶です。競争は力と知恵の競争です。ビジネス戦争は軍事戦争と同じで、戦略をうまく使う人が勝利するでしょう。 『孫子』という本は私たちに知恵と戦略の啓蒙を残してくれます。現代のビジネスにおける競争は軍事戦争のようなものです。剣術や煙幕はありませんが、戦争と同じくらい危険です。企業の上級意思決定者は軍事戦略家のような存在です。競争に生き残るためには、勇気と機知に富んだ能力が求められます。特に、非常に厳しい競争環境に直面している中で、事業者が判断を誤れば、競争から淘汰され、企業の衰退につながるリスクに直面する可能性があります。したがって、企業のトップ意思決定者は、状況を評価し、現実に基づいて将来を予測し、戦略を立て、予想外の手段で勝利を達成する必要があります。 孫子の兵法における戦略的思考には 2 つの意味があります。1 つは先見性、いわゆる「戦いが始まる前に勝つ」ことであり、もう 1 つは知恵、いわゆる「状況を利用して他者に勝つ」ことです。孫子の素晴らしさは、どんなに優れた戦略や戦術、龍の戦術や虎の鈴があっても、それを発砲せずに発砲させるような語り方を常に採用している点にあります。 同時に、『兵法』は「知識」という概念の説明に重点を置いており、これは他の理論の具体的な議論の重要な基礎となっています。本にこう書いてある。「自分を知り、敵を知れば、百戦危うくなく戦える。」これは理解するのが難しいことではありません。預言者たちはお互いを知っていて、計画を立て、最終的に行動を起こします。したがって、知識はすべての基礎です。 では、知識とは何でしょうか? 『兵法』における「知識」には 3 つの意味があります。第一に、物事の基本的な状態に関する洞察です。最も重要な考え方は、常に現状を冷静かつ科学的に分析することです。第二に、自分の領域を改善し、さらに先を見据え、状況の微妙な変化に十分注意を払います。これには、他の人が見ることができないものを見る能力が必要であり、それがまさに勝利への鍵となります。第三に、物事の発展を支配する法則、いわゆる「道」を理解し、物事がどのように発展するかを予見します。物事がどのように展開するかを知ることによってのみ、緊急事態を回避することができます。 『兵法』では、将軍の判断力と戦場の変化に適応する能力を重視し、将軍は戦場の実際の状況に基づいて選択をしなければならないこと、一部の道は通れないこと、一部の目標は攻撃できないことを指摘しています。戦い方は水に似ています。水の流れの法則は、高いところを避けて低いところに流れることです。戦いの法則は、敵の強いところを避けて、敵の弱点を攻撃することです。水の流れの方向は地形の高さによって制限されます。戦いで勝つための戦略は、敵の状況に応じて決定されます。したがって、水の流れに決まった形がないのと同じように、戦いにも決まった方法や手法はありません。敵の状況の変化に適応して勝利できる者を軍事の天才と呼ぶことができる。 人生においても同じことが言えます。人生の選択に直面したときは、慎重に考える必要があります。 「状況の章」には、「有利な状況で敵を動かし、兵士で敵を待ち受ける」とあります。この戦闘原則は、別の観点から、トレードオフや損得を正しく処理する方法を学ぶことも思い出させてくれます。物事の外見に惑わされないでください。 「賢者の考えには常に利益と害が混じっている。」長所と短所を比較検討し、利益を追求し害を避け、複雑な状況で正しい選択を行うことによってのみ、価値を最大化することができます。この考えは後の世代の多くの人々に影響を与えました。 次に、知恵に満ち、現代にも当てはまる古典的な名言を 10 個紹介します。 最初の文: 「将軍は賢く、信頼でき、慈悲深く、勇敢で、厳格でなければならない。」 - 孫子の兵法 真の将軍は、機転が利き、賞罰が公平で、部下を心から思いやり、勇敢で決断力があり、軍規が厳格でなければなりません。そうして初めて、将軍は重要な任務を引き受けることができ、これは今日でも重要な基準です。 2 番目の文: 「勢いとは、有利な状況に応じて制御する力である。」 - 『孫子の兵法』、第 11 章。 「利」の原則に基づいて緊急措置を講じ、敵を抑制し、より優秀で有能な人々にあなたのために働かせ、より賢い人々にあなたに助言を与えさせる、これが現在の「状況を利用する」ことです。 3 番目の文: 「敵が最も準備できていないときに攻撃し、不意を突く。」 - 孫子の兵法、戦略の始まり 敵が最も備えていない場所に軍隊を派遣して攻撃すること、つまり、とられる行動は人々の予想を超えるものでなければならない。現在では、主に機会を捉える必要性を表現するために使用されている。 4 番目の文: 「水は地形に応じて流れ、兵士は敵に応じて勝利する。」 - 『孫子の兵法』 戦い方は水に似ています。水の流れの法則は、高いところを避けて下に流れることです。戦いの法則は、敵の強いところを避けて、敵の弱点を攻撃することです。水の流れの方向は地形によって制限されており、敵の状況に応じて勝利の戦略が決まります。したがって、水に決まった形がないのと同じように、戦い方にも決まった形はありません。敵の状況の変化に適応して勝利できる人を軍事の天才と呼びます。現代では物事の変化に応じて変化することを表すときに使われます。 5 番目の文: 「将軍が戦場にいるときは、君主の命令に従ってはならない。」 - 『孫子の兵法』第 9 章 変化 これは原則であると同時に戦略でもあります。賢明な統治者であれば、冷静な判断力があれば、事の大小にかかわらず、前線の軍事問題に自ら介入するのではなく、戦場で戦う将軍たちを遠隔操作し、完全な自治権を与えるだろう。その結果、前者が勝ち、後者が負けることが多いです。 6 番目の文: 「3 つの軍の事情を知らずに、その管理に参加すれば、兵士は混乱するだろう。」 - 孫子の「兵法」 軍の内部事情を知らずに軍の運営に干渉すれば将兵を混乱させる。軍事上の配慮を知らずに軍の指揮に干渉すれば将兵に疑念を抱かせる。これは、このような間違いを犯すことが多い今日の経営陣に特に当てはまります。 第 7 文: 「絶望的な状況に追い込めば生き残るだろう。致命的な状況に追い込めば生きるだろう。」 - 『孫子の兵法』、第 9 章「地形」 戦闘の際には、軍隊が退却できず、戦闘中に死ぬしかない状況に置きます。すると兵士たちは勇敢に前進し、敵を殺して勝利します。今は、決心して成功できるように、退路をあらかじめ断つことを意味します。 文 8: 「最善の軍事作戦は敵の計画を攻撃することであり、次に最善は敵の同盟を攻撃することであり、次に最善は敵の軍隊を攻撃することであり、最悪は敵の都市を攻撃することである。」 - 孫子の兵法、攻勢戦略の章 最善の軍事行動は戦略を用いて敵の戦略的意図や戦争行為を阻止することであり、次に最善なのは外交を用いて敵を倒すことであり、3番目に最善なのは武力を用いて敵軍を倒すことである。最悪の戦略は敵の都市を攻撃し、最小の損失で最大の利益を得ることである。 第 9 文: 「熟練した戦士の勝利は、その知恵や勇気によるものではない。」 - 孫子の「兵法」 戦いに勝つのが得意な人は、奇跡的な勝利を挙げたわけでもなく、知恵に恵まれたわけでもなく、戦いにおける勇敢さで知られているわけでもない。本当に賢い人は、決して自分を絶望的な状況に置くことはありません。自分の言動に慎重であり、自分のキャリアをギャンブルのようには考えません。 第 10 文: 「退却する軍を止めてはならない。包囲された軍に隙間を空けてはならない。必死の敵を追撃してはならない。」 - 孫子の「兵法」 敵が自国に退却するときには迎撃せず、包囲するときには隙を空けましょう。敵は窮地に陥ると必死に戦うこともあるので、やみくもに近づかないでください。 |
<<: 宋の太祖皇帝が建国後に最初にしたことは何ですか?帝国の権力の重要性について簡単に説明します。
>>: 元朝において社会的矛盾がなぜそれほど深刻だったのでしょうか?これらの矛盾の原因は何でしょうか?
推薦する
西遊記 第58章: 二つの心は宇宙を乱し、一つの心は涅槃に達することを困難にする
『西遊記』は古代中国における神と魔を題材にした最初のロマンチックな章立ての小説で、『三国志演義』、『...
劉玉熙の『江南を思い出す:春は去った』:詩人の芸術的特徴は「新鮮さ、流暢さ、繊細な考え」
劉毓熙(772-842)、号は孟徳、河南省鄭州市溪陽に生まれた。本人曰く「私の家はもともと溪山出身で...
水神の原型は誰ですか?神々の任命の中で、紙の上で戦争について語るのが得意な唯一の将軍
神々の入封においては、商周の戦争であろうと神々同士の戦いであろうと、行軍、戦闘、軍隊の配置がすべて重...
「九月九日に山東の兄弟を思い出す」をどのように理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
9月9日に山東省の兄弟たちを思い出す王維(唐代)外国の地ではよそ者なので、休暇中は家族が恋しくなりま...
秦観が憂鬱な気分で書いた詩:「阮朗桂・湘天風雨破冬」
秦観の『阮郎帰郷天風雨破冬始』を鑑賞し、興味深い歴史の編集者が関連コンテンツをお届けします。ご興味の...
『紅楼夢』で袁春が両親を訪ねる場面には、どのような政治的陰謀が隠されているのでしょうか?
元春が実家を訪ねるシーンは、『紅楼夢』の中で最も印象的なシーンです。 Interesting His...
グアルジア族の分布 グアルジア族の主な居住地の紹介
グァエルジア族の分布:グァエルジア族は満州族の姓であり、8つの主要な満州族の姓の1つです。グワルジア...
劉裕が一挙に占領し、東晋の全権力を掌握した場所はどこでしょうか?
荊州は、東晋末期の混乱期はもちろんのこと、古代から軍事上の重要拠点となってきました。司馬秀之の軍勢は...
春秋時代にはどのような政略結婚がありましたか?結婚は中国の歴史にどのような影響を与えたのでしょうか?
本日は、おもしろ歴史編集部が春秋時代の列強間の結婚物語をお届けします!ご興味のある方はぜひご覧くださ...
古典文学の傑作『太平天国』:人材資源編第21巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
『紅楼夢』で王希峰が賈雲の仕事を奪ったことの意味は何ですか?
王希峰は『紅楼夢』の登場人物。賈廉の妻、王夫人の姪であり、金陵十二美女の一人。多くの人が理解していな...
宋代の『詩』鑑賞:星香子の「樹囲村」では、作者はどのような感情を表現しているのでしょうか?
星香子·村の周りの木々 [宋代] 秦貫、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見...
安慶公主が夫のために嘆願したとき、朱元璋はどのように反応しましたか?
朱元璋が最も嫌ったのは汚職官僚であり、容赦なく彼らに接した。彼が汚職官僚をこれほど嫌った理由は、朱元...
『女仙伝』第22章:鉄軍の焦伯は衛兵の景文曲を殺すことができ、曲の腐った皮は依然として燕王と戦った
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...
杜遜和の『自伝』では、詩人は自身の感情を通して現在の政治情勢に対する不満を表現している。
杜遜和は、字を延芝、号を九花山人といい、唐代末期の官僚詩人であり、写実主義の詩人である。彼は詩が優雅...