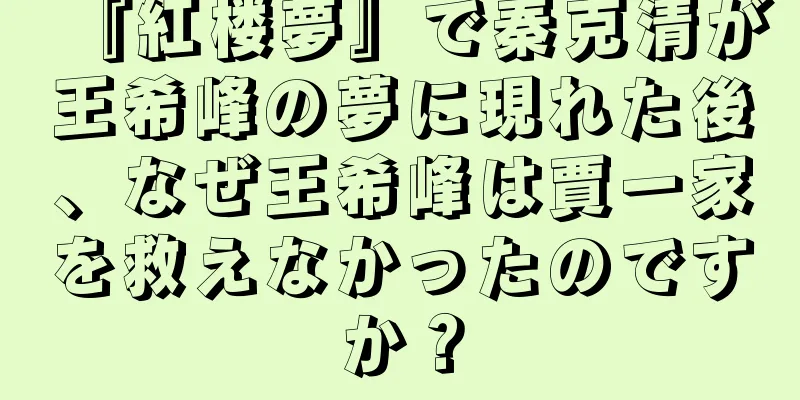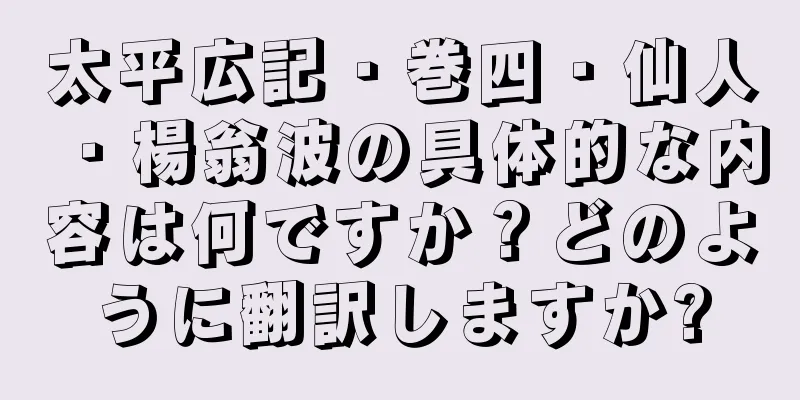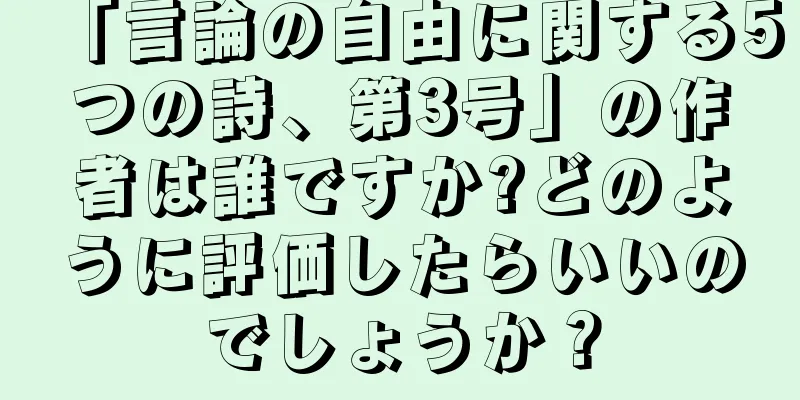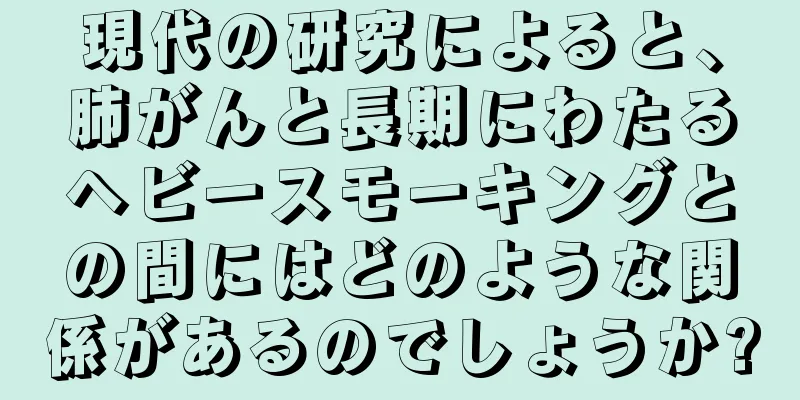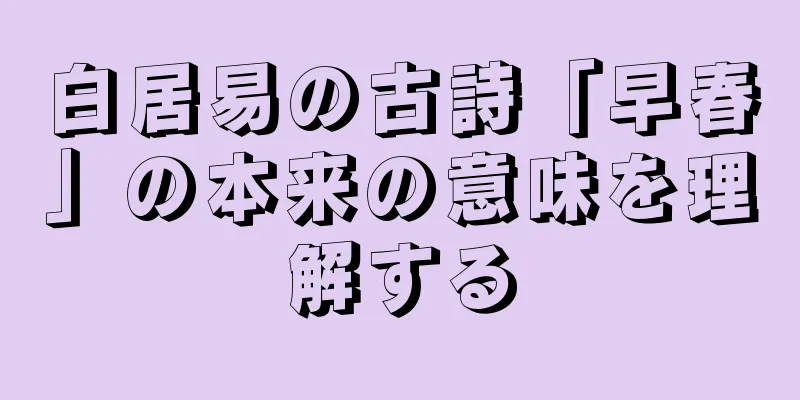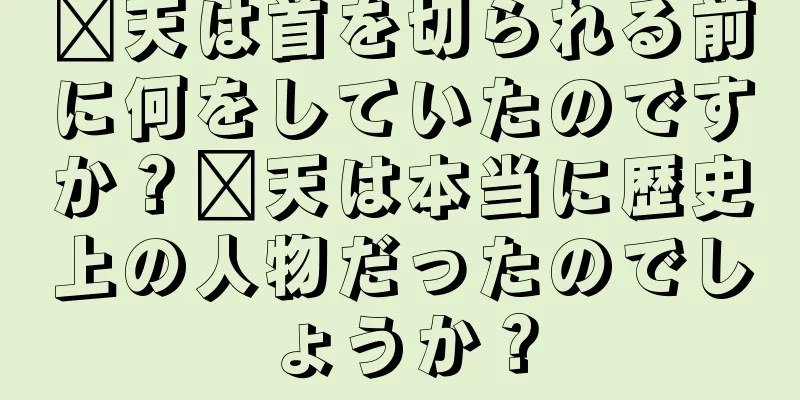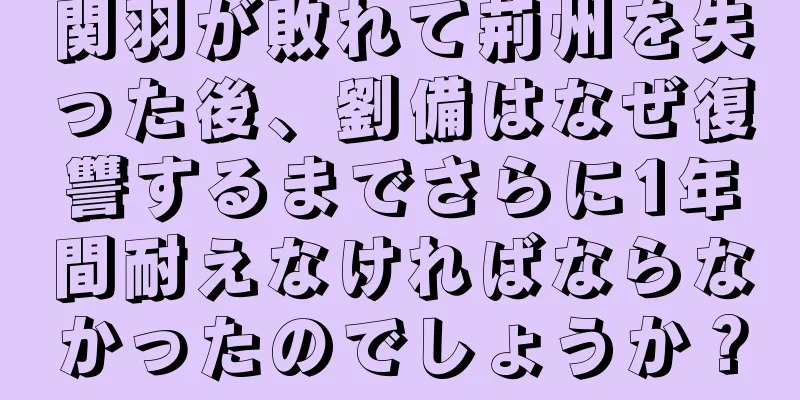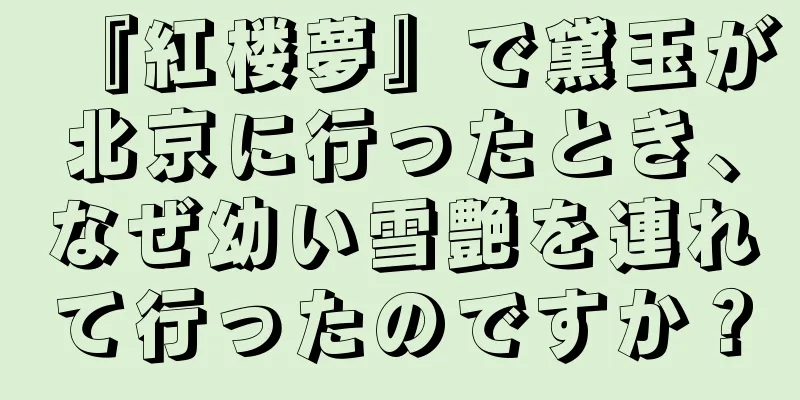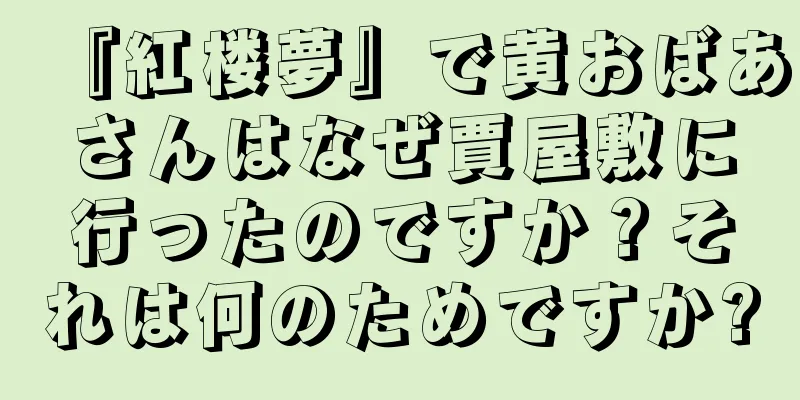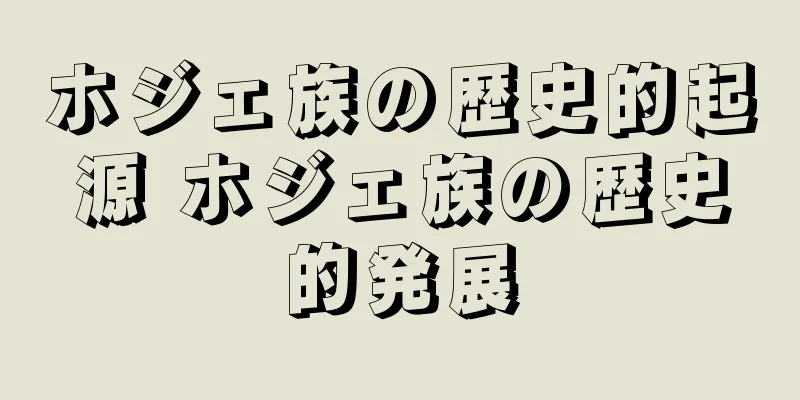「午後以降食べない」ことのメリットは何でしょうか?古代人はなぜ正午以降は食事をしなかったのでしょうか?
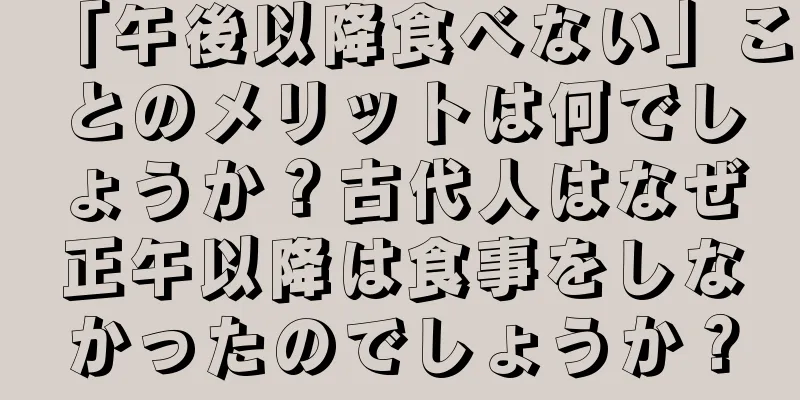
|
「正午以降は食べない」ことのメリットとは?古代人はなぜ「正午以降は食べない」のか?Interesting Historyの編集者が詳細な関連コンテンツを提供します。 実際、ダイエットをしている人の多くは、正午以降は食べないということはよく知っていますが、長年続けてきた一日三食の習慣は口で言うだけでは変えられないこともあるので、多くの人が知っているものの、実際に実行するのは難しいのです。しかし、「正午以降は食べない」という言い伝えはどこから来たのか知っていますか?本当にダイエットに効果があるのでしょうか?正午以降は食べないという食習慣を最初に実践したのはどんな人たちだったのでしょうか?「正午」とは何時のことを指すのでしょうか? 正午以降に食事を摂らないことは、仏陀が僧侶に与えた戒律です。律蔵における正しい用語は「不適切な時に食事をしない」です。つまり、法律で許可されている時間以外に食事をすることはできないということです。正午から翌日の夜明けまでの間、食事は禁止です。 仏教では、早朝は神が食事をする時間、正午は仏陀、つまり三世の仏が食事をする時間、夕暮れは動物が食事をする時間、夜は幽霊と神が食事をする時間であると信じられています。 ルーベン師は著書「仏教に関する質疑応答」の中でこう書いています。「正午以降に食べないことには多くの利点があるので、仏陀はそれを確立したのです。」 1. 食欲が減退すると、男性と女性の性欲も減退する可能性があります。 2. 心身をリラックスさせ、胃腸を休ませることができます。 3. 瞑想(サンスクリット語:ディヤーナ)に入りやすい。 4. 修行して悟りを得るための時間が増える。 5. 解脱(サンスクリット語:vimokso)を得るためには、食欲を浄化しなければなりません。 6. 三世の仏は皆、正午以降は食事をしない。 正午以降の断食には、上記のような利点があります。この原則は誰でも実行でき、継続すれば、正午以降の断食のメリットと利益を無制限に得ることができます。 「八戒」とは、在家の仏教徒が修道生活を体験するための一連の戒律です。 多くの仏弟子が五戒を受けています。五戒の規範は世俗的な道徳に非常に近いものです。したがって、五戒を守ることで人間界と天界で祝福を得ることができるのです。八戒は僧侶の戒律に近いもので、在家の仏教徒が世俗的な解放の種を植えるのを助けるために、慈悲心から仏陀によって制定されました。 その意義は、在家の仏教徒がこれらの戒律を守ることによって僧侶の清浄で禁欲的な生活を体験できるということである。八戒は初心戒に近いため、それを守ることの功徳は大きいです。 仏教の経典によれば、八戒を一昼夜守ることの功徳は、五戒を一生守ることの功徳に等しいとされています。条件が許せば、皆さんがもっと頻繁にお寺に通って「八戒」を守ってくれることを願っています。 八戒は適切な寺院で守られ、僧侶によって教えられるべきです。もし、あなたがいる場所に僧侶や清浄な寺院がない場合は、仏様の前で自ら受けることもできます。近年、蘇州西園街荘仏教寺院では、毎月信者に八戒を説いています。具体的な時間は毎月第一週末です。機会があれば誰でも体験できます。 現在の時刻によると、「正午」は12時です。古代には時計はありませんでした。人々は通常、太陽に棒を立て、影が中心に達したときが正午でした。正午の儀式を守る人は、正午から翌朝の光が現れるまでしか食事をすることができません。いわゆる明香には特定の時間はなく、屋外で手のひらの線が見える時間を基準としています。 八戒では横にならないようにする必要はないので、普通に休むことができます。八戒を守るためには、戒律の特徴を理解して正しく守る必要があります。五戒と比較すると、八戒には二つの重点があります。一つは好色にならないこと、もう一つは不適切な時間に食事をしないことです。五戒は「姦通の禁止」を要求し、夫婦間の合法的な性生活を認めています。 八戒を守る一昼夜の間、あらゆる性行為を厳格に控えなければなりません。第六戒「香りのよい花や蔓を身につけない、体に香水をつけない、歌ったり踊ったりしない、故意に売春を見たり聞いたりしない」、第七戒「高くて広いベッドに座らない」も、「情欲を持たない」という戒律を守るためのものです。 「不適当な時間に食事をしない」という事は五戒には含まれておらず、厳格に守らなければなりません。 そういえば、夕食を食べるのが好きというのは、私たち人間が病気にかかりやすい理由の一つであり、また、多くの病気が長い間治らない理由の一つでもあります。多くの人は、夜にお腹が空いたら食べるべきだと考えていますが、実際にはそれは真実ではありません。夜にお腹が空いたときに食べないのは普通のことです。 1418年、明代の永楽帝朱棣の寵愛を受け、翰林学者でもあった胡広が37歳で亡くなった。胡光は文人であり、口を閉ざすのが彼の特徴であった。彼は朱棣と話し合った内容を決して漏らさなかったので、朱棣は彼をとても気に入っていた。しかし、胡広は夕食を食べるのが大好きだったので、朱棣も彼を嫌っていました。 昔、夕食を食べる人は放蕩者とみなされました。しかし、胡広は長い間病気で体が弱っていたため、一回の食事でたくさん食べることができず、食事を重ねなければならなかったと言います。すると朱棣は彼を許した。 漢方医学も仏教も「正午以降は食べてはいけない」と言っています。いわゆる「正午」は午前11時から午後1時までです。午後1時以降は食事ができません。お腹が空いたらどうすればいいですか?ジュースを飲んだり、フルーツを食べたりできます。 伝統的な中国医学と仏教では、食糧を節約するためではなく、健康を維持するために夕食を食べないことを推奨しています。さらに、中国人には、食べるときに唇を閉じたり、唇を鳴らしたりしないなど、食事に関する多くのルールがあります。たとえば、食べ物を取るときは、線を越えることはできず、お皿の自分の側からのみ食べ物を取ることができます。たとえば、食事中に話すことはできません。 しかし、最大のルールは夕食を食べてはいけないということです。夕食を食べると失礼とみなされます。そうすると、政府は科挙を受けることを許可してくれなくなり、妻を見つけることさえできなくなる可能性があり、ビジネスを行うことも困難になるでしょう。 胡光は翰林になってから初めて夕食を食べ始めました。彼自身が言ったように、彼は長い間病気でとても衰弱しており、一度にたくさん食べることができなかったので、夕食を食べなければならなかった。そして、その夕食は非常に豪華だった。しかし、夕食を食べた後、胡光さんの体は強くなるどころか、ますます問題が増えていった。それで彼は食べ過ぎて死んでしまいました。 |
<<: 武昌魚は武昌産ですか? 「武昌魚」はどうやって生まれたのですか?
>>: 金鉄線GE窯とは?金線・鉄線 Ge 窯の特徴をご紹介!
推薦する
唐代に胡文化はどれほど人気があったのでしょうか?胡族の文化や習慣は何ですか?
今日は、おもしろ歴史編集長が胡族の文化や習慣についてご紹介します。皆さんのお役に立てれば幸いです。唐...
古宇についての古代の詩にはどんなものがありますか?詩の翻訳とはどのようなものですか?
本日は、Interesting History の編集者が、穀物雨に関する古代の詩をご紹介します。ご...
『紅楼夢』における賈夫人と王夫人の家政観の違いは何ですか?
『紅楼夢』では、賈夫人と王夫人はそれぞれ栄果屋敷の二代目と三代目の女主人です。では、彼女たちの家事に...
劉邦は後に漢王朝の皇帝になりました。なぜ彼は蕭何に対して暴力を振るわなかったのでしょうか?
劉邦には多くの臣下がいた。これらの建国の英雄の中には、かつて六国の部下だった者や、革命で共に戦った貧...
漆器は中国独特の工芸品の一つです。揚州漆器の歴史はどのくらい長いのでしょうか?
漆器は中国の特別な芸術工芸品の一つです。揚州は豊かな歴史文化遺産を有し、中国で最初に公布された24の...
荘公十年に古梁邇が著した『春秋古梁伝』には何が記録されていますか?
荘公十年に古梁邇が著した『春秋古梁伝』には何が記されているのでしょうか?これは多くの読者が関心を持っ...
『太平広記』第446巻の「十三獣」にはどんな登場人物がいますか?
猿楚河の漁師王仁宇、猿、翟昭、徐吉之、張玉燕、薛芳の曽祖父ヤンユドゥマカクチンパンジー良いワインは話...
『紅楼夢』では、賈歓、賈珠、賈蘭のうち誰が家業を継ぐのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
瓦崗五虎退の5人の英雄とは誰ですか?この5人の最終的な運命はどうなったのでしょうか?
次に、『Interesting History』の編集者が、歴史上の本当の瓦岡五虎の軌跡を辿り、彼ら...
玉丁真人は『封神演義』でどれくらい強いですか?
冊封禅宗の元師天尊の弟子は十二金仙と呼ばれ、それぞれが偉大な魔力を持ち、三界で名声を博しています。そ...
『水滸伝』に登場する108人の英雄たちは、“採用”された後、どのような結末を迎えたのでしょうか?システムに戻る人もいれば、僧侶になる人もいるのでしょうか?
みなさんこんにちは。おもしろ歴史編集長です。今日は『水滸伝』に登場する108人の英雄たちが「徴兵」さ...
『易軒志』第12巻の主な内容は何ですか?
リン・ジインデ南江の出身の林季は、若いころに都に来た。蔡州に着くと、ある宿に泊まった。背中の股間に何...
蘇軾の有名な詩の一節を鑑賞する:出かける前に袖をまくり、残った菊を摘む
蘇軾は北宋中期の文壇のリーダーであり、詩、作詞、散文、書道、絵画などで大きな業績を残した。彼の文章は...
秦の二代皇帝胡亥とはどんな人物だったのでしょうか?歴史は秦の二代皇帝胡亥をどのように評価しているのでしょうか?
胡亥(紀元前230年 - 紀元前207年)、別名秦二世、二代皇帝とも呼ばれ、姓は英、趙氏、号は胡亥、...
「彭公事件」第169話:解毒剤を盗んだ英雄が友人を救い、盗賊団を追い払い、英雄となって有名になる
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...