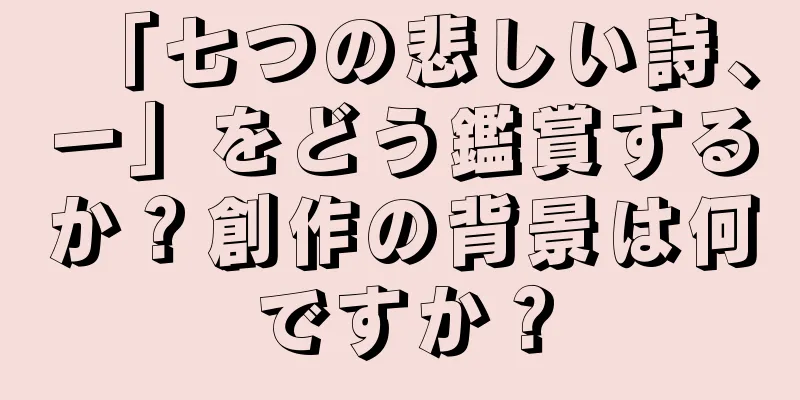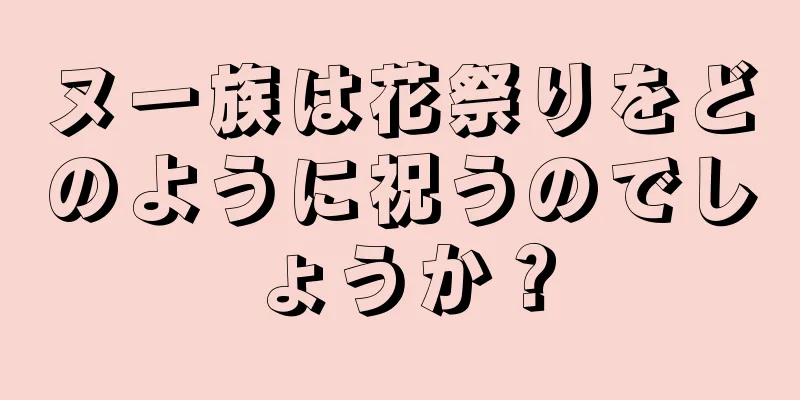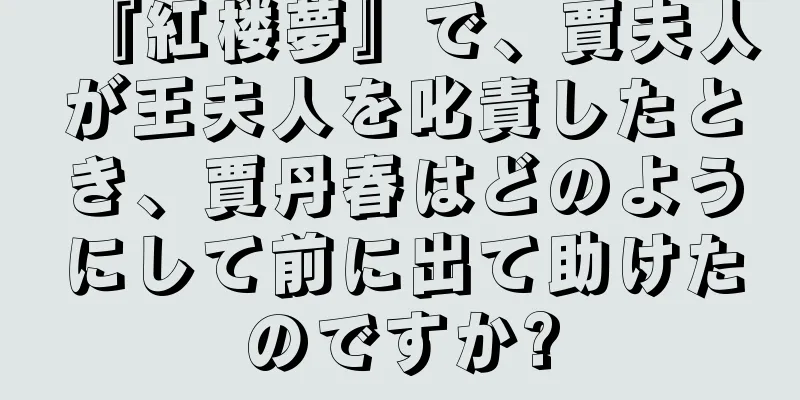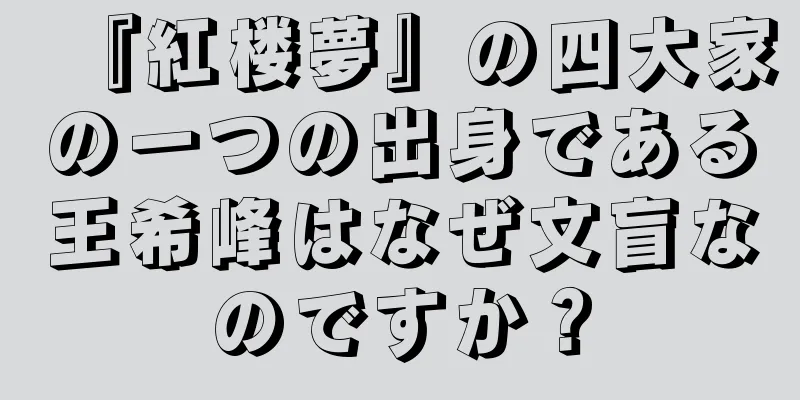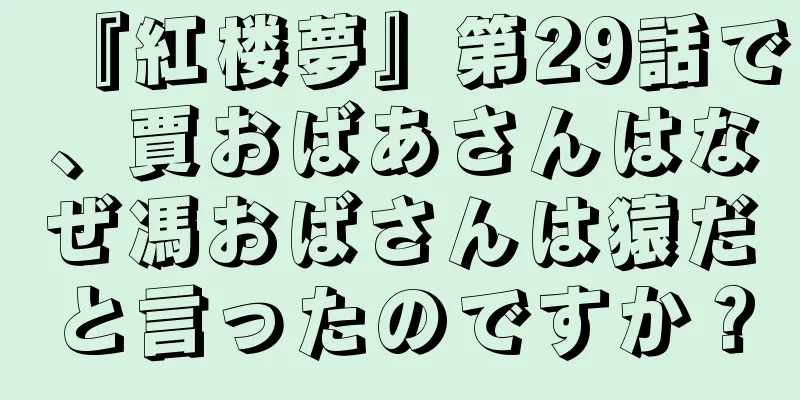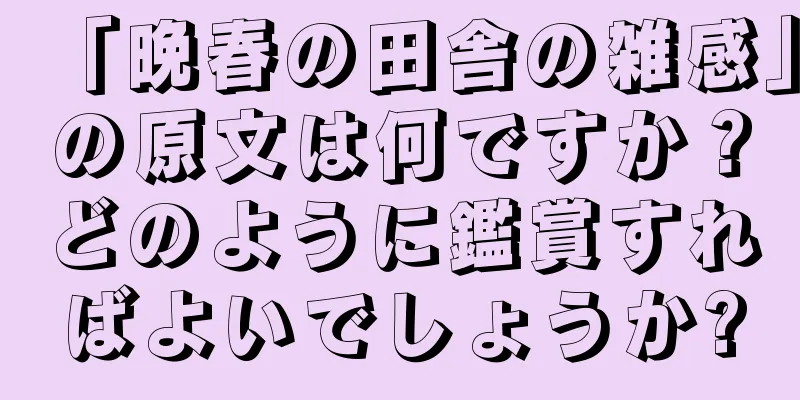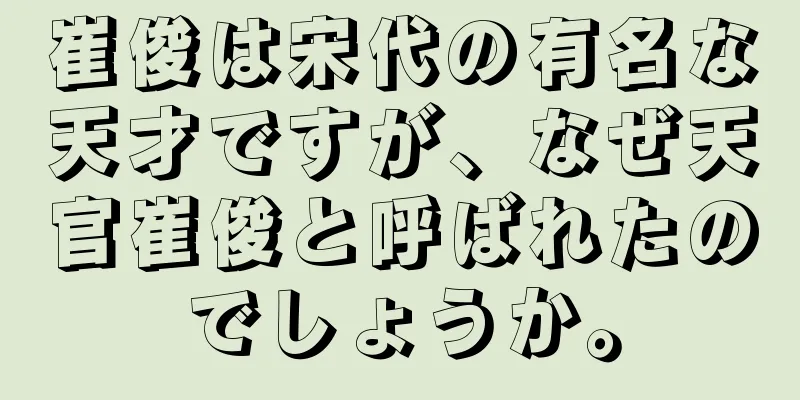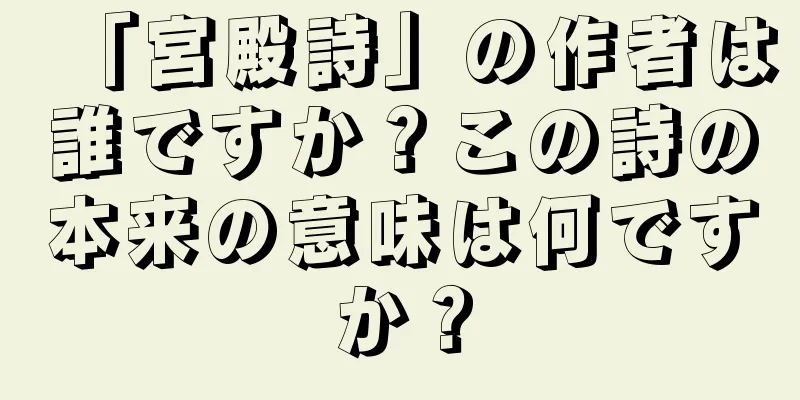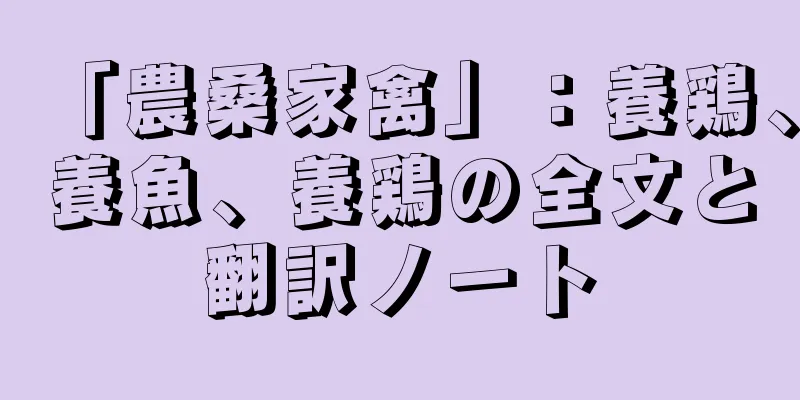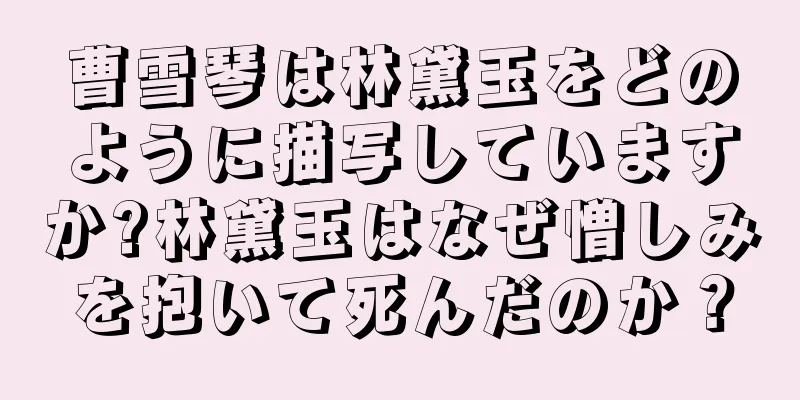槍と銃は非常によく似ていますが、違いは何でしょうか?
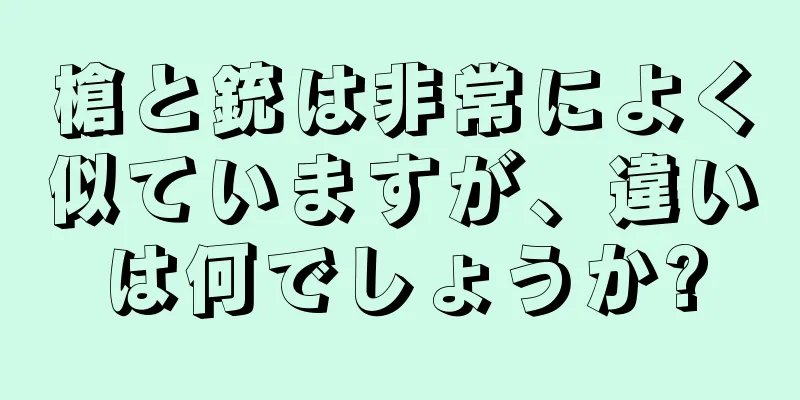
|
古代中国には、剣、槍、戟、斧、鉤、フォークなど、多くの種類の武器がありました。種類は多かったのですが、多くの人が、それらは非常に異なっていることに気付きました。しかし、それほど明白に違いがない武器が 2 種類ありました。それは、銃と槍です。銃と槍は見た目は非常に似ていますが、両者の根本的な違いは何でしょうか? 今日は、Interesting History の編集者がそれについて学びます。 まず、槍は非常に早くから登場しました。原始社会の頃から、私たちの祖先は狩猟に槍を使い始めました。狩猟用の武器として、槍は手に持つだけでなく、決定的な瞬間に力を入れて投げて遠距離にダメージを与えることもできます。その後に作られた槍は、ほとんどがナツメの木や金属で作られ、一般的に重くなりました。槍の中には、柄が鋼鉄で、重さが 70 ~ 80 キログラムに達するものもありました。構造的には槍は非常に単純で、槍の穂先と柄の2つの部分のみで構成されているため、槍の種類は比較的少ないです。 槍と違って、銃には多くの種類があるだけでなく、柄も柔らかいものや硬いものがあり、その長さは腕を上に伸ばした直立した人間の身長とほぼ同じです。銃と槍は見た目は非常に似ていますが、銃は槍などの重い武器よりも軽い武器です。 「一寸長ければ一寸強い」という諺があるように、槍は鋭い刃と棒からなる長い柄の突き刺す武器です。柄は刃より長く、短い武器とは全く逆です。その総合的な威力は非常に大きいため、「武器の王」とも呼ばれています。銃は槍から自然に進化したものであり、槍のアップグレード版です。銃は槍の威力を持つだけでなく、槍の重さがなくなり、武器がはるかに軽くなります。使用時に使用者の負担が減り、戦闘の身体的負担が軽減されます。この銃は軽いだけでなく、非常に頑丈です。この武器は操作が簡単で、武術のスキルを十分に発揮できます。しかし、銃術は18の武術の中でも習得が難しい部類に入ります。 そうは言っても、銃にはもっと明白な利点があることを誰もが発見したに違いありません。このため、後の世代では銃の使用率がはるかに高くなっています。清朝まで、軍隊は依然として「赤房槍」を使用していました。普通の槍との違いは、刃と槍の接合部に赤い房が結ばれていることです。しかし、赤い房は単に美しさのためだけではありません。戦闘中、赤い房は敵の血が槍を伝って流れ落ち、使用者が滑るのを防ぐことができます。また、赤い房は非常に軽く、槍術の練習をするときには、赤い房のひらひらで武器の強さを判断できます。同時に、戦闘中、赤は相手の注意を引きやすく、敵を妨害したり気を散らしたりできるため、相手が欠陥を明らかにして自分の側にチャンスを作りやすくなります。こんなにシンプルな武器にこんなにも知恵が詰まっているなんて、本当にすごいですね! |
<<: 豆腐の起源を探ります。豆腐を発明したのは誰でしょうか?
>>: 玄関に石のライオンを置くという習慣はどこから来たのでしょうか?特別な意味は何ですか?
推薦する
ウイグルの歴史の起源 ウイグル民族の簡単な歴史
ウイグル族は、モンゴルの草原に住む回河族と、新疆南部のオアシスの先住民族という2つの主な起源を持つ多...
『紅楼夢』にはどんな色の赤が登場しますか?それぞれどの章ですか?
古代中国の長編小説『紅楼夢』は、中国古典文学の四大傑作の第一作です。今日は、Interesting ...
易経の丙卦九支にある「野に鳥なし」とはどういう意味ですか?
『易経』の「横卦九字」にある「野に鳥なし」とはどういう意味でしょうか? これは多くの読者が知りたい質...
唐代の詩に出てくる蝉をどのように鑑賞すればよいのでしょうか?この詩の本来の内容は何ですか?
蝉[唐代]李尚胤、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょう!高所では...
『紅楼夢』で小翠堂はどこにいますか?どんな秘密が隠されているのでしょうか?
小翠堂は曹雪芹の『紅楼夢』に登場する大観園にある建物です。今日は、Interesting Histo...
宋代の女流詩人、李清昭の作品『生生漫・荀荀密』を鑑賞
靖康事件の後、李青昭の国は滅び、家族は没落し、夫は亡くなり、彼女は人事によって傷つけられた。この時期...
楊鉄鑫はどうやって死んだのか?楊鉄鑫の武術はどれほど優れていたのか?
楊鉄鑫は金庸の小説『射雁英雄伝』の登場人物の一人です。有名な将軍楊在星の子孫で、牛家村に住んでいます...
西遊記 第1章 精神的な根は生命の源を育み、心は偉大な道を耕す
『西遊記』は古代中国における神と魔を題材にした最初のロマンチックな章立ての小説で、『三国志演義』、『...
『秦鄭を偲ぶ:潼樹への頌歌』をどのように理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
秦夷を偲ぶ - 唐への頌歌李清昭(宋代)高い東屋の上に立つと、混沌とした山々と平原の上で煙が薄れてい...
古代と現代の驚異 第38巻:趙の喬県主が黄みかんを贈呈(第2部)
『今昔奇談』は、明代の鮑翁老人によって書かれた、中国語の俗語による短編小説集です。馮夢龍の『三語』と...
西夏の手工芸産業がなぜこれほど発展したのでしょうか?支配者の贅沢な生活を満たすために
初期のダンシャン・チャン族は遊牧生活を送っており、手工芸品が経済生活に占める割合はわずかでした。彼ら...
なぜ賈正は賈爾よりも地位が高いのでしょうか?長男の賈舎はなぜ別の庭に住んでいたのでしょうか?
賈奢は、名を恩后といい、前公爵容賈岱山の跡継ぎ容賈元公爵の孫であり、賈夫人の母の長男であった。彼は一...
宋仁宗には10人以上の子供がいたのに、趙叔はどうやって皇帝になったのでしょうか?
宋仁宗の側室たちは、楊王昭芳、雍王昭欣、荊王昭熙の3人の息子を含む10数人の子供を産んだ。しかし、こ...
国際女性デーの起源と歴史的経緯
国際女性デーの起源となった要因をご存知ですか?第108回国際女性デーの発展の歴史とは?実は、国際女性...
鄭謝の『山雪のあと』:著者は苦難の人生に対する深い後悔を表明している
鄭板橋(1693-1766)は、本名を鄭謝、別名を科柔、連安、板橋といい、板橋氏とも呼ばれた。江蘇省...