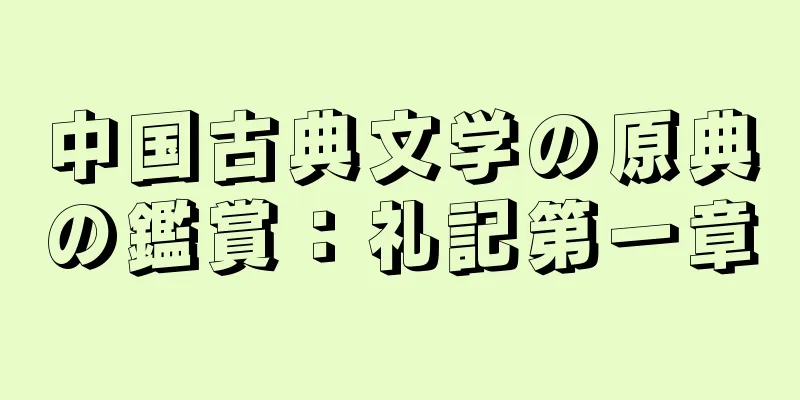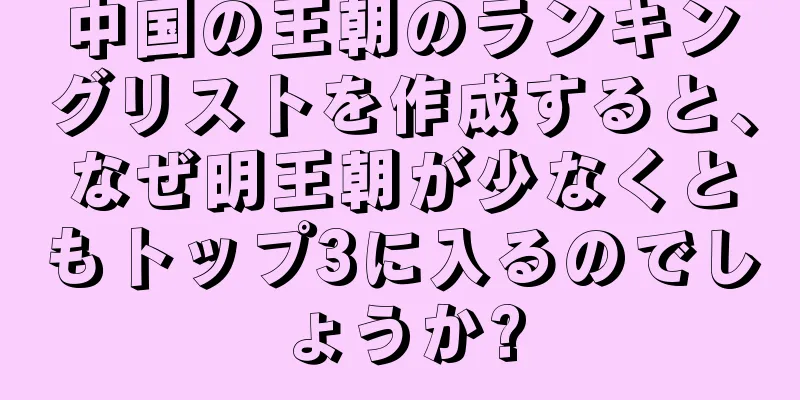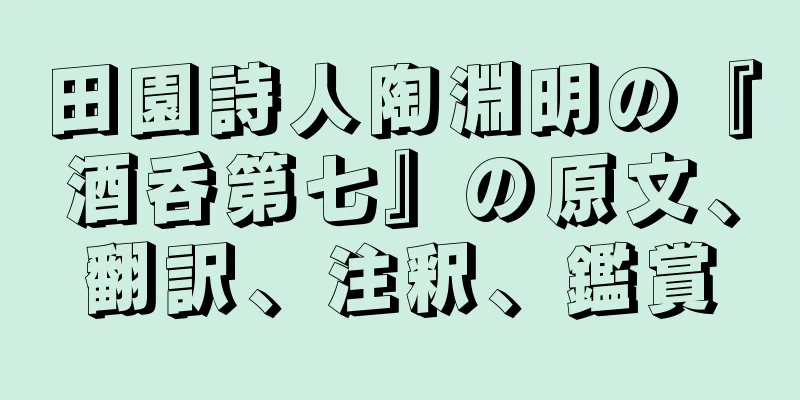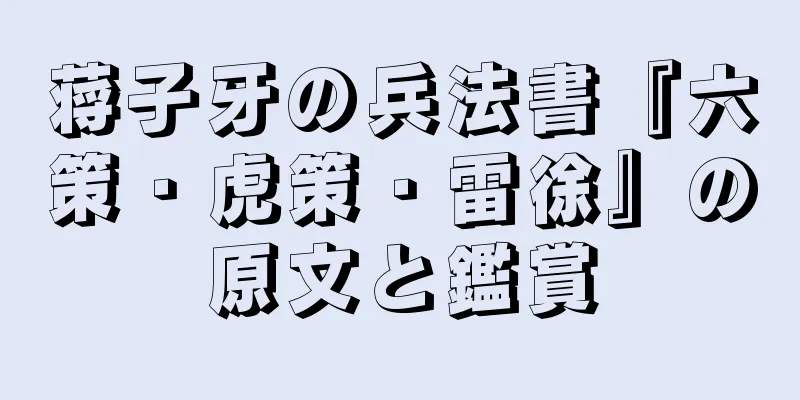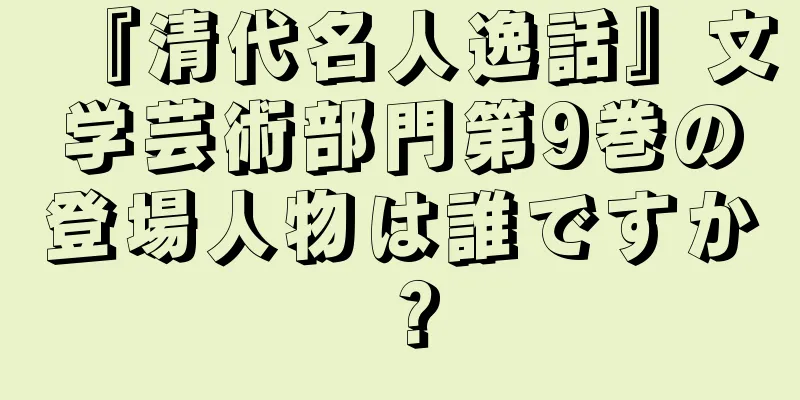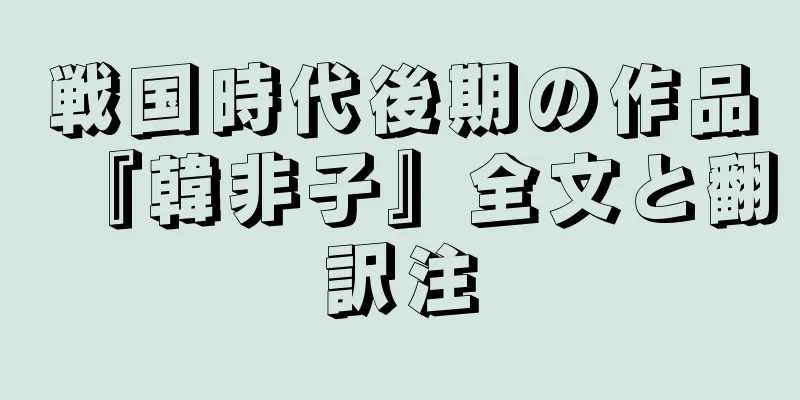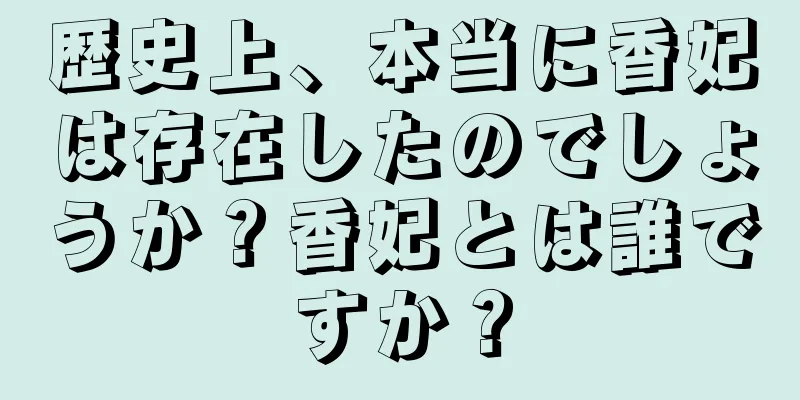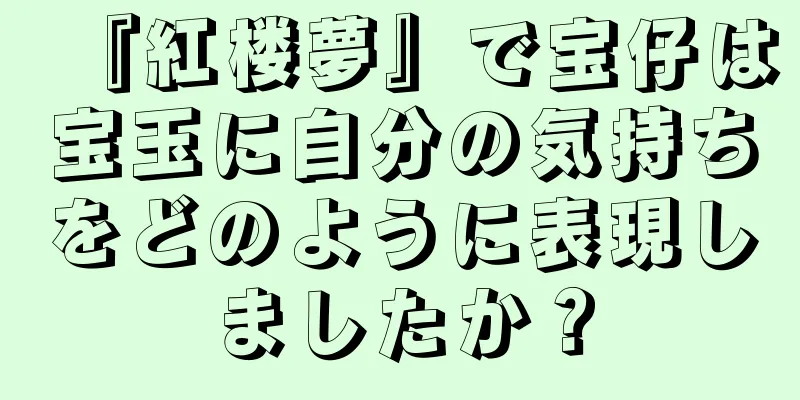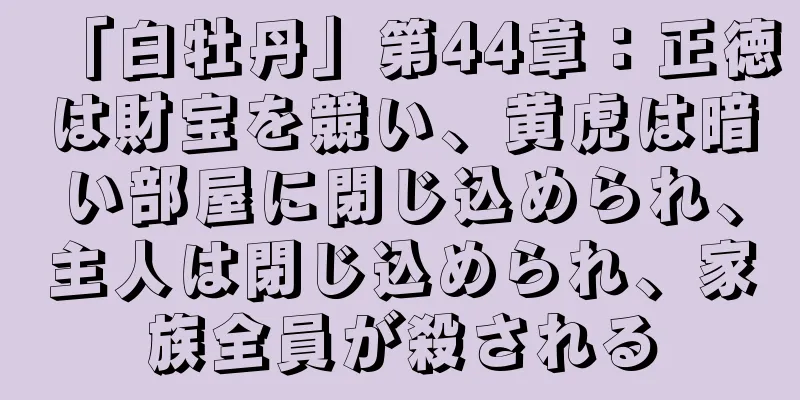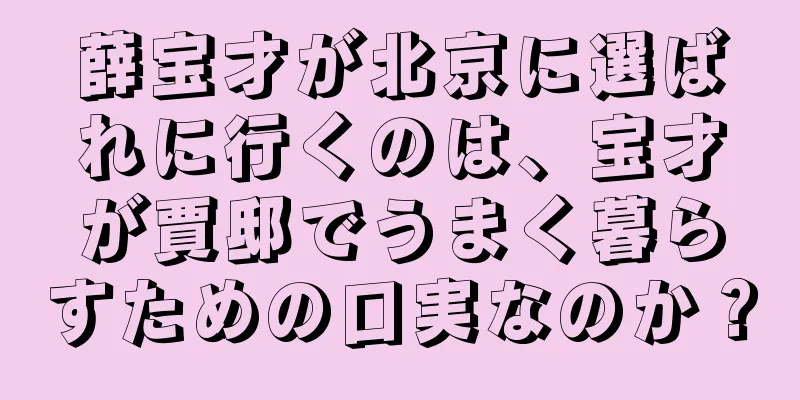「日本の戦国時代」と「中国の三国時代」の類似点は何でしょうか?日本はなぜ「三国志」の歴史にこだわるのでしょうか?
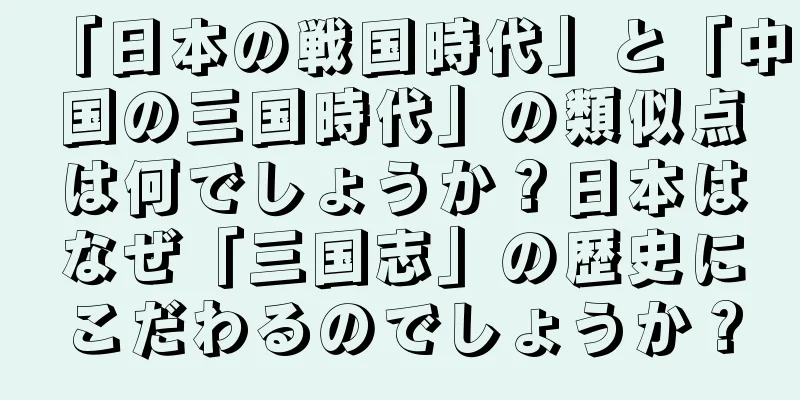
|
「日本の戦国時代」と「中国の三国時代」の共通点とは?なぜ日本は「三国時代」の歴史にこだわるのか?『おもしろ歴史』編集部が詳しい関連コンテンツをお届けします。 現代日本の中国三国志の歴史に対する関心は、執着のレベルに達しています。日本だけでも「三国志クラブ」が数百あり、「三国志英雄」「真・三國無双」など、三国志関連のアニメ、ゲームなども百以上あります。三国志の専門クラスや三国志知識テストもあり、彼らの戦国時代は中国の三国時代とよく比較されます。 中国の三国時代は、大まかに言えば、董卓が都に入った西暦190年から、西晋が呉を滅ぼして国を統一した西暦280年まででした。 日本の戦国時代は、広義には、1467年の応仁の乱の勃発から、1615年に徳川家康が豊臣氏を完全に滅ぼすまでの期間を指します。 では、なぜ 2 つの歴史的時代は何千年も離れており、まったく異なる場所で起こっているのでしょうか? 実は、主な理由は、この二つの歴史的時代には多くの類似点があるからです。また、日本は唐代以来、中国文化の影響を深く受けてきたため、この二つを結びつけるのは自然なことです。 日本の戦国時代は、国内のネットユーザーから「村と郡の争い」と揶揄されることが多いが、客観的に見ると、戦争の規模が小さいことを除けば、日本の戦国時代の歴史は確かに輝かしく、中国の三国時代と多くの類似点がある。 上:戦国時代の日本の地図 上:中国の三国志地図 1. 類似した歴史的背景 東漢末期、朝廷は腐敗し、宦官や皇帝の親族たちは絶えず争い、国全体が深刻な干ばつに見舞われ、黄巾の乱が勃発した。しかし、腐敗し無能な東漢の朝廷は反乱を鎮圧することができず、地方政府が軍隊を徴兵して独自に反乱を鎮圧することを許した。その結果、地方の州や郡は中央の統制から離れ始めた。董卓が北京に入った後、軍閥同士が戦う状況が生まれ、皇帝は権力を失い傀儡となった。その後、曹操は「皇帝を使って君主を指揮する」という政策の下で急速に台頭し、東漢末期の最も強力な君主となった。赤壁の戦いの後、三つ巴の対立が形成された。 日本の戦国時代の始まりも、応仁の乱という内乱から始まりました。しかし、応仁の乱は農民反乱ではなく、当時の日本の実質的な支配者であった室町幕府の支配下における、各守護大名(大名は日本の封建領主の古い呼び名で、古代中国の君主と理解できます。いわゆる守護大名とは、将軍によって守護として任命された封建領主のことで、将軍直属の大名に相当します)間の内紛でした。応仁の乱は将軍や守護大名の衰退に直結し、地方で実力のある大名が台頭し、大名同士が領有権を争う戦国時代へとつながっていきました。 そのため、三国時代も日本の戦国時代も内乱を背景に展開した。国は統一から分裂へ、諸侯は互いに併合し、最高権力者は傀儡となり、中国の皇帝は「諸侯を統率するために人質にされ」、日本の将軍は「皇帝に説得された」(「皇帝に説得された」という日本語は主に京都に行くことを意味し、京都の別名は洛陽である。古代日本では、「皇帝に説得された」は主に、最も有力な大名が軍隊を集めて京都に進軍し、自らの地位を示す過程を表すために使われた)。 上:赤壁の戦い 上:赤壁の戦い 2. 類似したキャラクターの経験 三国時代も日本の戦国時代も、数え切れないほどの優れた政治・軍事戦略家を輩出しており、両時代の多くの人物が同様の経験をしています。最も典型的な例は曹操と織田信長であり、彼らの経験には多くの類似点があります。 二人とも若い頃はボヘミアンな性格で、世間から好かれていませんでした。 『三国志』によれば、曹操は若い頃はわがままで、遊び好きで、手に負えない、規律に欠け、学識がなかった。人々は一般的に曹操に才能がないと信じていた(南陽の許紹だけが曹操を「平時には裏切り者、乱時には英雄」と評した)。 近代日本の歴史家、山岡荘八の著書『織田信長』によれば、織田信長は手に負えない、無礼、怠惰で、よくトラブルを起こし、あちこちで争いを起こした。彼は「尾張の大馬鹿者」というあだ名をつけられていた(織田信長は尾張国、現在の名古屋市で生まれた)。 二人は政治や軍事に非常に才能があり、先進的な政治制度を実施し、小勢力で大勢力を、弱勢力で強勢力を倒すという輝かしい戦果を挙げました。 上:曹操(155-220) 曹操は前漢の駐屯耕作制度を継承し、これを積極的に推進し、兵農を一体化することで戦争中の軍糧の緊急問題を解決した。また、「人材選抜」政策を実施し、型破りに多くの人材を発掘・登用し、「将軍は雲、参謀は雨」に囲まれた。 織田信長は戦争で大規模に火器を使用し、拠点であった尾張と目濃の人口の多さと豊富な資源を利用して、兵農を分離して職業軍を設立し、「検地制度」を実施しました。これは、各勢力の領土を縮小し、各勢力への固定的な支援を通じて地方での優位性を減らし、地方勢力の兵力が多すぎる現象を効果的に防止するというものでした。 建安5年(200年)、曹操は官渡の戦いでわずか2万の兵力で武巣を奇襲し、袁紹の10万以上の軍を破った(官渡の戦いの両軍の兵力は歴史家の間で常に議論の的となっているが、2つの点は確かである。第一に、曹操の兵力は袁紹の兵力よりはるかに少なかったこと、第二に、『三国志演義』の袁紹の軍は70万以上であり、曹操の軍が7万以上というのはまったくあり得ないことであり、まったくのナンセンスである)。こうして曹操は北方統一の基盤を築いた。 1560年、織田信長は大雨に乗じて桶狭間の戦いで奇襲を仕掛け、今川義元の不意を突いた。信長は4千人余りの兵で今川義元の2万余りの軍勢を打ち破り、当時の東海道の覇者であった今川氏を滅ぼして勢力を大きく拡大し、その後の覇権の基礎を築いた。 上_織田信長(1534年6月23日 - 1582年6月21日)は、幼少期には吉伏としても知られ、「戦国時代の三大名匠」の一人でした。 二人とも「皇帝を利用して王子たちを支配する」ことに長けており、二人とも自分たちが支配する傀儡たちから反乱を受けていた。 建安元年(196年)、曹操は漢の献帝劉協を迎え、許昌に遷都し、皇帝の名の下に四方を征服し、政治的に優位に立った。漢の献帝劉協は曹操に支配されることを嫌い、有名な「易岱昭の変」を計画し、董承、傅琬、劉備、鍾基らを結集して曹操を暗殺し、権力を取り戻そうとしたが、残念ながら計画が漏洩したため、実行前に失敗に終わった。 1568年9月、織田信長は室町幕府第12代将軍足利義晴の次男、足利義昭を第15代将軍(第13代将軍は足利義輝、第14代将軍は足利義栄)に擁立し、上洛に成功した。美濃斎藤氏、北近江浅井氏、南近江六角氏などの大名の支援も得て、「武力を全国に広げる」という戦略目標を加速させた。足利義昭は織田信長の横暴に耐えかね、上杉謙信、毛利輝元、本願寺顕如、武田信玄などの大名を集めて織田信長討伐に乗り出した。これが有名な二度の「信長包囲網」である。しかし、さまざまな理由から、どちらも織田信長によって突破され、足利義昭は京都から追放され、彼の領地は織田信長に併合された。 しかし、非常に興味深いのは、曹操が人質にしていた「天子」は古代中国の実権を握っていた皇帝であり、まさに「天子を人質にして諸侯を指揮」していたということである。しかし、日本の「天子」である天皇は、1185年に鎌倉幕府が成立した時点ですでに傀儡となっていた。応仁の乱前夜まで、日本は「天子を人質にして諸侯を統率する」という状況にあり、「天子を人質にしている人」が将軍であった。そのため、織田信長が足利義昭を傀儡として捕らえたことは、魔法のように「二重捕り」、つまり「他の君主を支配するために天皇を人質に取る」ことになってしまった。当時の日本の天皇はあまりにも惨めだったとしか言えない。 上の画像_織田信長の覇権と武将間の権力分割 1549-1582 二人とも全盛期に急激な変化に遭遇し、生涯で志を達成することができませんでした。 曹操は北を統一し、劉聡を討伐し、荊州を占領した後、意気揚々としていたが、赤壁の戦いで大敗を喫した。まだ力は残っており、馬騰、韓遂、張魯など多くの君主を次々と征服し、天下の大部分を統一したが、建安25年(220年)に病死するまで孫権と劉備を排除することができず、天下統一の大業を成し遂げることができなかった。 1582年6月、織田信長は天下をほぼ統一し、順調に進んでいたが、本能寺の変に遭遇。腹心の明智光秀に謀反を起こされ、自害に追い込まれた(織田信長の本能寺での死因や明智光秀の謀反の理由については諸説あるが、この事件で織田信長が死亡したことは間違いない)。織田信長の死後、その家臣団は急速に崩壊し、「武力を全国に広げる」という戦略は終焉を迎えた。しかし、彼の主将である羽柴秀吉(豊臣秀吉)は彼の遺産のほとんどを継承し、それに基づいて日本を統一しました。 曹操と織田信長の類似点を比べてみると、袁紹と今川義元にも多くの類似点があることが分かります。袁紹は先祖の「四代三官」の威信を最大限に利用し、公孫瓚を征服して後漢末期最大の君主となりました。しかし敵を過小評価し、全盛期に曹操に敗れ、その後病死し、河北も曹操に占領されました。今川義元も自らの努力で今川家の勢力を遠江、駿河、三河、南尾張にまで拡大し、当時の日本の東海道の覇者となりましたが、敵を過小評価したために全盛期に織田信長に敗れ、死去し国を滅ぼされました。 上_袁紹(?-202)、号は本初 第三に、結末が似ている。 三国時代の最終的な結末は、数十年にわたって争ってきた魏、蜀、呉の三勢力が統一に失敗したことでした。最も強大な曹魏政権が第4世代の曹芳に引き継がれたとき、高平令の政変の後、数十年にわたって我慢してきた有力な大臣である司馬懿によって政権が奪われました。司馬懿とその子孫は曹魏の強大な国力を基盤として、東呉と蜀漢を滅ぼし、天下を統一して西晋を建国した。 日本の戦国時代は、織田信長の側近で、賤民の出で「猿」と呼ばれた豊臣秀吉が、織田信長の礎の上に日本を統一したことで終わりました。しかし、徳川家康を懐柔したり、朝鮮出兵を開始したりといった一連の愚かな行動により、統治を続けることができず、わずか8年間の統治で亡くなりました。豊臣秀吉の死後、数十年にわたって我慢してきた徳川家康はすぐに蜂起し、1603年に江戸幕府を開き、1615年に豊臣氏を全滅させて戦国時代を終わらせました。 三国時代や日本の戦国時代の最終的な勝者は、すべて忍耐と長寿によって成功したと言え、徳川家康は「亀」というあだ名さえ得ました。 上:徳川幕府時代の日本 上:西晋の領土 しかし、さらに時代を遡れば、三国時代の結末は日本の戦国時代とは全く逆になるはずです。司馬一族が建国した西晋は天下統一からわずか37年で内乱により早々に滅亡し、東晋の十六国南北朝時代が始まり、200年以上の戦乱と分裂が続きました。一方、徳川家康が江戸幕府を開いて戦国時代を終わらせ、日本の江戸時代が始まり、200年以上の平和統一が続きました。 三国時代の歴史は素晴らしく、『三国志演義』の影響を受けて、現代中国、さらには東アジア全体の人々の間でも永続的な話題となっています。日本の戦国時代は、相対的に見ればはるかに劣っていたが、一方で「毛利元就は早生まれだった」「上杉謙信は男か女か」「徳川家康は馬に乗って死ぬほど怖がっていた」「織田信長は仏教を滅ぼした第六天魔王」など、日本の戦国時代にも興味深い話題が数多くあった。興味のある読者はそれについて学ぶことができ、それは日本の歴史、さらには国としての日本を学ぶのに非常に役立ちます。 |
<<: 秦と楚の間にはどんな恨みやしがらみがあるのでしょうか? 「楚に三家あっても、楚が秦を滅ぼす」と言われているのはなぜでしょうか?
>>: 「桂坊人」とはどのような民族ですか? 「桂坊人」はいつ誕生したのでしょうか?
推薦する
李淵は功績に基づいて人々にどのように報酬を与えたのでしょうか?将軍であろうと兵士であろうと、我々はすべての人を平等に扱わなければなりません。
李淵が天下を掌握し皇帝になったという事実は、彼が愚か者ではなかったことを証明している。「大小の区別な...
『紅楼夢』では、薛宝柴が本気を出したら夏金貴に対処できるだろうか?
「紅楼夢」の夏金貴は薛潘と結婚し、薛家の長女、薛家の将来の当主となった。しかし、彼女は気性が荒く、騒...
黄景仁の「秋夜」は荒涼とした秋の情景を描いている
黄景仁は、漢容、仲澤とも呼ばれ、別名は呂非子とも呼ばれ、清朝の詩人であった。彼の詩は有名で、「杭の七...
三国志演義第41章:劉玄徳が民を率いて川を渡り、趙子龍が単独で馬に乗って主君を救う
『三国志演義』は、『三国志演義』とも呼ばれ、正式名称は『三国志演義』で、元代末期から明代初期にかけて...
トゥファ・リルグには何人の甥がいますか?トゥファ・リルの孫は誰ですか?
吐法礼禄固(?-402)は、河西出身の鮮卑人で、十六国時代の南涼の君主であった。吐法五固の弟であり、...
薛将軍第15章:老樊洪は漢江の戦いで敗れ、樊麗華は主君の命令で去る
『薛家の将軍たち』は、主に薛仁貴とその子孫の物語を描いた小説シリーズです。これらは『楊家の将軍』や『...
永遠の謎:秦の始皇帝の兵馬俑はなぜ兜をかぶらなかったのか?
彼らはヘルメットをかぶらないだけでなく、着用している鎧も非常に簡素で、鎧板は最小限に抑えられています...
ジンポ族の結婚習慣の紹介
雲南省龍川県は、景坡族の主な居住地です。ここでは恋人同士が手紙を書くのではなく、物を使ってコミュニケ...
晋の元帝、司馬叡はそんな人物でした。歴史は司馬叡をどのように評価しているのでしょうか?
司馬睿(276年 - 323年)、晋の元帝、愛称は景文、東晋(在位318年 - 323年)の初代皇帝...
周邦厳の『応天長・天鳳部然』:詩全体が激しい悲しみのシンフォニーである
周邦厳(1057-1121)、号は梅成、号は清真居士、銭塘(現在の浙江省杭州市)の人。北宋時代の作家...
『晋書』第23巻第13章の原文は何ですか?
◎レクシア永嘉の乱の際、国は分裂し、劉と石は役者や楽器をすべて失いました。江左に祖廟が初めて建立され...
「ホタル」を鑑賞するには?創設の背景は何ですか?
ホタル杜甫(唐代)幸運にも、腐った草が出てきたので、思い切って太陽の近くまで飛んでみました。勉強は得...
亥年生まれの人の出生仏は阿弥陀仏である。
十二支の豚の守護聖人は、十二支が「豚」である人々の出生仏でもある阿弥陀仏です。次は興味深い歴史エディ...
「秋夜秋文」の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
秋の夜に邱さんに宛てた手紙魏英武(唐代)秋の夜にあなたを思いながら、散歩をしながら涼しい天気について...
『紅楼夢』でタンチュンは黛玉の誕生日をわざと忘れたのでしょうか?理由は何でしょう
丹春は曹雪芹の『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人です。以下、興味歴史編集長が関連内容を詳しく...