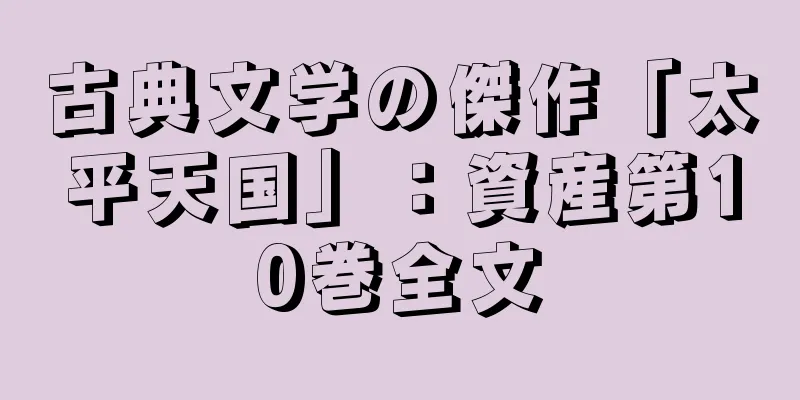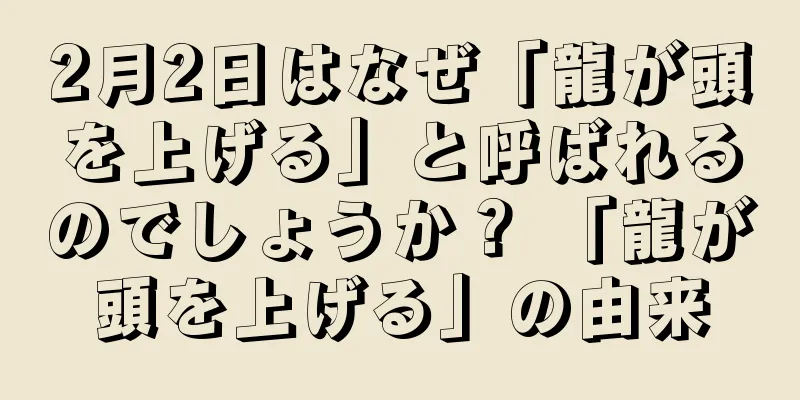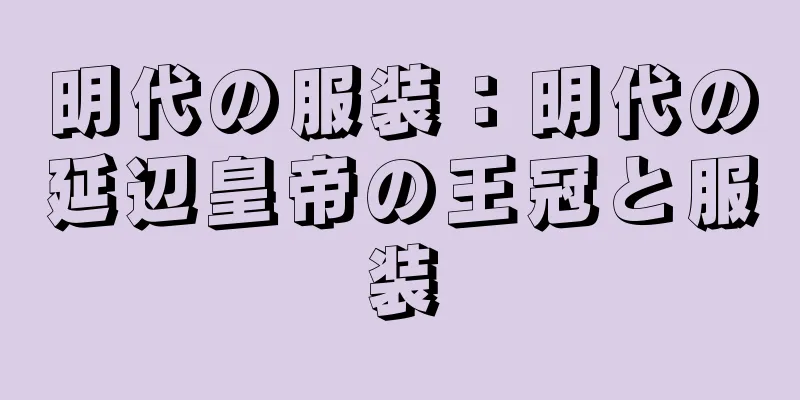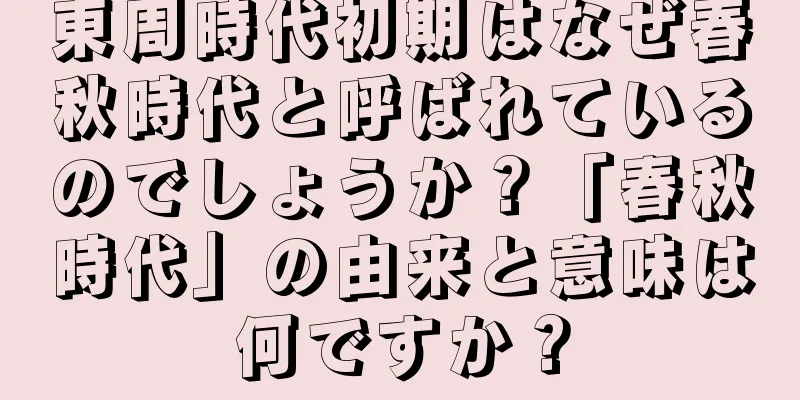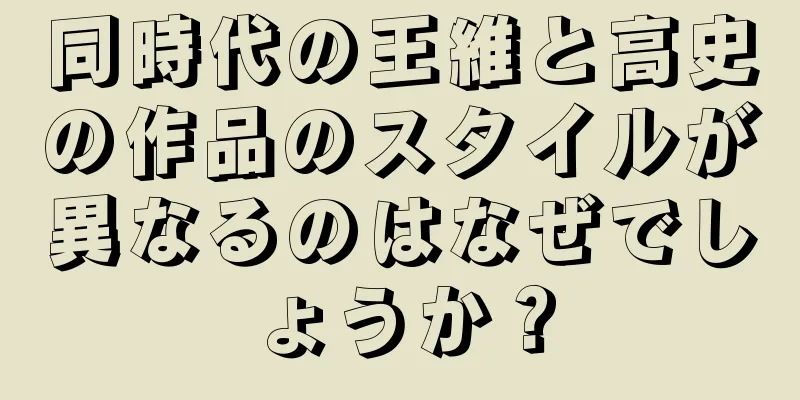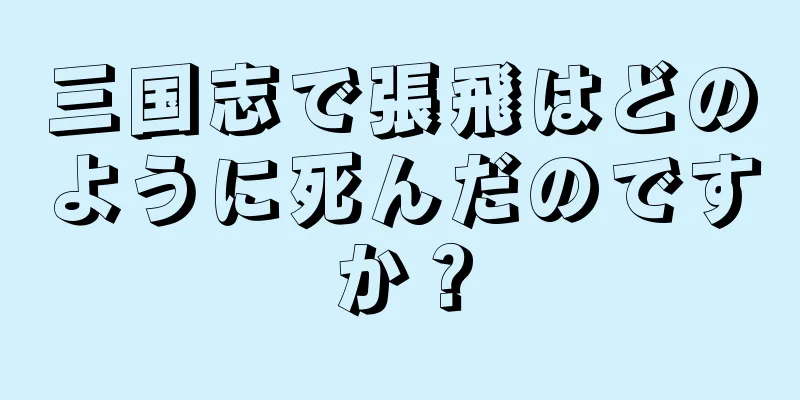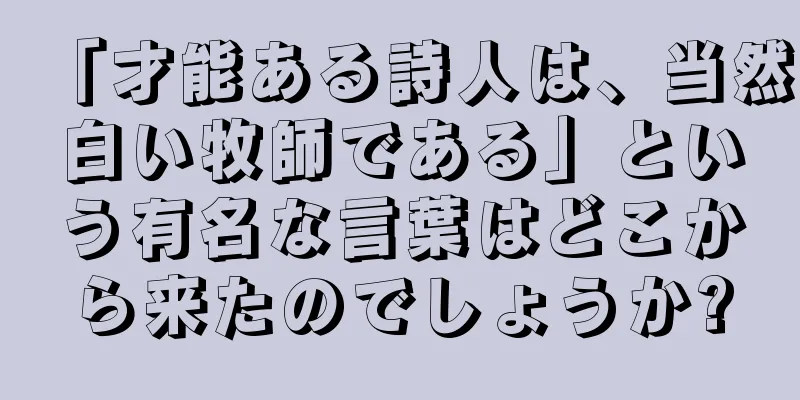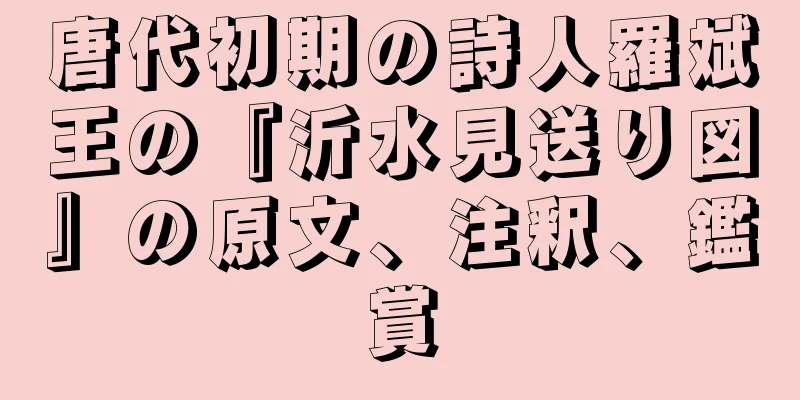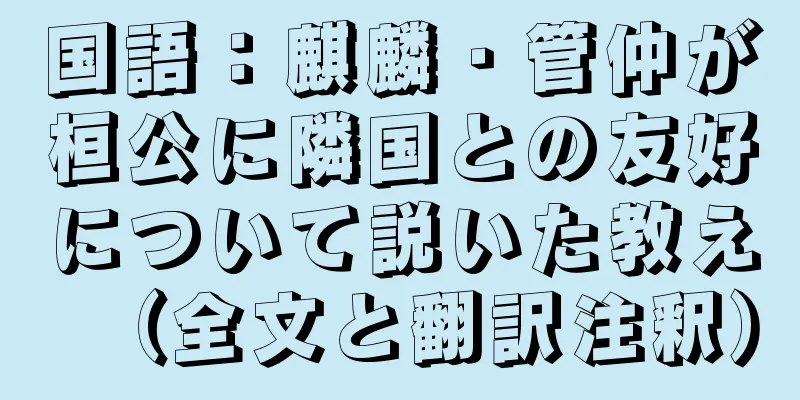楊秀の死因は何でしたか?楊修の死を通して漢から魏への変遷を見つめる!
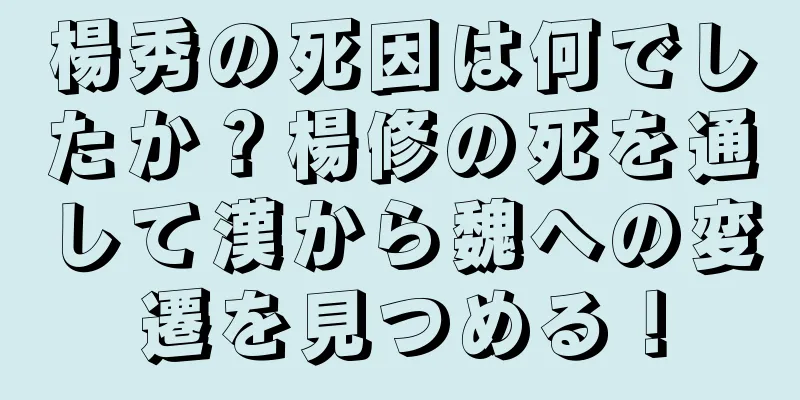
|
今日、『Interesting History』の編集者は楊秀の死についての真実をお伝えし、皆様のお役に立てれば幸いです。 『新説天下一篇』に記された楊秀のイメージは、かなり「軽薄」であり、それは羅貫中によって継承され、発展させられたため、『三国志演義』の楊秀もまた奔放で才能に恵まれていることがわかります。しかし、この小説では、『新世界物語』に述べられている楊秀の死の重要な理由、つまり曹丕と曹植の兄弟の後継者争いに楊秀が関与していたという理由が意図的に隠されている。羅貫中は著作の中で楊秀が「才能ゆえに傲慢」であると大げさに描写したため、曹操は何度も恥をかき、楊秀の死を招き、最終的には曹操の「才能ある者への嫉妬」により楊秀を殺害した。 『三国志演義』のこのアプローチは、もちろん小説のテーマに沿うものであり、歴史の真実ではなく、曹操を「裏切りの英雄」としてイメージする必要性から生まれたものである。 『世碩心于』は歴史的価値が高いが、楊秀の死因は表面的なものである。 歴史上の実在の人物や出来事は、文学作品よりも複雑で奥深い内容を持っていることがよくあります。非常に高い歴史的価値を持つ『新世界物語』でさえ、「楊秀の死」の問題に対する説明はいくぶん平板であるように思われる。楊秀の死は確かに曹家における後継者争いへの関与によるものであったが、楊秀の死は曹家における権力闘争への関与だけにとどまらず、それ以上のものであった。楊秀が曹操の「有能な人材への嫉妬」によって死んだわけではないので、単に「曹操の後継」に関わったというほど単純なことではなかった。それで、楊秀の死の背後にある深い理由は何でしょうか? 私の考えでは、楊秀の死は彼自身の政治的立場と直接関係しているだけでなく、漢から魏への転換の歴史過程における画期的な出来事でもありました。それは貴族階級が支えていた東漢政権の完全な崩壊を意味し、また漢から魏への必然的な転換を予兆するものでもありました。 1. 曹操が楊彪と楊秀を味方につけようとする試み 陳寿は『三国志』の中で曹操について「太祖は計略を立てて天下を荒らし、申商の魔力と韓白の独特な戦略を吸収し、能力に応じて人材を登用し、恨みを持たず、皇帝の権力を掌握し、大きな功績を成し遂げることができたのは、ひとえに彼の知恵と戦略によるもの」と総括評価している。ここで陳寿は曹操の政策レベルが「申商の魔力」であり、それは曹操が「儒教」を特徴とする貴族階級を攻撃する側であると見ていた。陳寿のこの見解が間違っていたとは言えない。しかし、『魏書・陸淵伝』では、孝文帝が陸淵に返した言葉の中に「曹操が袁を破ったのは、おそらく彼の徳と功績によるものであろう。決して兵士の弱さや10万人という少なさによるものではない」とある。孝文帝の曹操の台頭に対する理解は明らかに陳寿よりも高く、すでに社会政治の深淵に触れていた。 曹操は人を雇う際に「道徳」をあまり気にしなかった 田玉清氏によれば、曹操の「徳と功績が内部から認められた」というのは、実際には曹操が東漢以来、政府と国家に大きな影響力を持っていた貴族階級の社会階層を比較的明確かつ客観的に理解していたことを意味しているという。そのため、曹操はこの階級に対して穏健かつ効果的で柔軟な政策を採用した。 田氏の見解と同様に、徐洋傑も著書『中国家制度史』の中で、「後漢政権は大家系と宮廷貴族を擁する政権だった。曹操がこの政権を掌握したとき、彼はこの既成事実を認めざるを得なかった。曹操は統治を強化するために、有力な一族を吸収し、宮廷の要職に就かせなければならなかった」と主張している。 後漢末期の政治において貴族階級は避けられない存在であった。 田と徐は曹操の貴族に対する態度について同様の見解を持っていた。これは、曹操の楊彪とその息子の楊秀に対する態度を調べても確認できます。楊弘農家は東漢以来の名門であり、最も権威のある家系である。後漢末期には、別の名門である汝南袁家とも婚姻関係にあった。楊秀は楊家と袁家の婚姻の子孫である。楊秀の父、楊彪は後漢末期の太将であった。このような状況から、楊秀とその父の社会的影響力は想像に難くない。 楊彪は東漢時代の最も名声ある貴族の出身であり、彼の一族は代々漢王朝に忠誠を誓っていたからです。楊彪の先祖は楊震から始まり、代々宦官と激しい争いを繰り広げ、常に自らを高潔な民とみなしていたため、「宦官の子孫」である曹操を軽蔑し、曹操の統治を心から受け入れることは不可能であった。曹操はずっと前からこのことを知っていた。実は曹操は楊彪を筆頭とする貴族の家を常に警戒しており、楊彪を殺したいとずっと思っていました。 『後漢書 楊真伝と楊彪伝』 「当時、袁術は暴君であり、曹操は彪と袁術の結婚を口実に、袁術が曹操を廃位しようと企んでいると濡れ衣を着せ、投獄され、大逆罪で告発された。」 この史料から、曹操は楊彪を殺害するつもりで長い間過ごしていたが、言い訳の余地はなく、結局袁術と楊彪の関係に頼って仕方なく楊彪に対処するしかなかったことがわかります。しかし、それでも曹操は自軍内部からの強い抵抗に遭遇した。孔容は楊彪の「四代にわたる清廉潔白は全国に尊敬されている」と述べて、楊家の影響力の大きさを曹操に思い起こさせた。また、「罪のない人々を殺せば、全国がそれを見聞きし、皆が引き裂かれるだろう」と警告した。さらに、孔容は曹操が「明日は出て行って、二度と朝廷に出席しない」と脅すことさえ考えた。このような状況では、曹操は諦めるしかなかった。 曹操はついに楊彪を殺す勇気がなかった さらに皮肉なことに、袁紹は楊彪、孔容らとも対立していた。建安3年(198年)に袁紹は曹操に手紙を書き、曹操を利用して彼らを排除しようとした。しかし、曹操はやはり無謀な行動を取る勇気がなかった。 『三国志演義 武帝紀』 「袁紹は、元太守の楊彪、侍従の梁紹、小財務の孔容と長年の確執があり、他の失策に対して彼らを罰したいと考えていました。公は言いました。『今、世は乱れ、英雄が台頭し、君主を補佐する人々は不満で自分の考えを持っています。今は上下が互いに疑念を抱いている時です。疑いがないかのように扱っても、信頼されないのではないかと恐れています。誰かを排除すれば、誰が危険にさらされますか?』」 曹操の袁紹に対する返答は、もちろん、まず第一に彼の偽善を最大限明らかにしたものであったが、それはまた、ある面では楊らが東漢社会に及ぼす大きな影響力を反映しており、曹操が軽率な行動を取ることをためらわせるものでもあった。 漢王朝は衰退していたが、それを支持する人々はまだ多くいた。 曹操は楊彪を殺す勇気はなく、その代わりに、礼部大臣という高位の地位を与えることで楊彪の心を掴もうとした。しかし、楊彪は漢朝を支持するという確固たる政治的立場をとっていたため、曹操と誠実に協力することは不可能であった。この点では楊彪と荀攸は似ているが、楊彪の行動はより極端である。 『三国志 文帝紀』 「彪は漢の滅亡を悟ると、代々三公を継いできた家柄に、魏の丞相であることを恥じ、足を捻挫して十数年も歩けなくなったと語る。皇帝が即位すると、彼を大元帥にしようと思い、側近に勅令を出すよう命じた。彪は『私は漢の三公であったが、世は衰え、混乱しており、何の進歩も遂げられなかった。再び魏の丞相になれば、国が私を選ぶことは名誉ではない』と断った。」 曹操が漢王朝を倒そうとしていることが明らかになると、楊彪は漢王朝への忠誠を貫くことを選び、10年以上も国内に留まり曹操との協力を拒否した。魏の文帝が即位すると、楊彪を魏の太元帥に任命しようとしたが、楊彪は再び拒否した。 同じ状況が楊秀にも起こりました。 『三国志陳氏王志伝』注には『伝録』が引用されている。 「楊秀は、号を徳祖といい、太衛彪の子で、謙虚で才能に恵まれていた。建安年間、孝行で誠実な官吏に選ばれ、医者に任じられた。宰相は彼に倉庫部の主任書記を命じた。当時、軍事と国家の事柄が多く、秀は内政と外政の両方を担当し、すべてに満足していた。魏の皇太子など、皆が彼と親しくなろうと競っていた。当時、臨子侯志はその才能のために寵愛を受けていたため、秀のもとに来て意向を伝え、何度も手紙を書いて「数日あなたに会っていないので、とても寂しいです。あなたも同じ気持ちだと思います」と言った。 ” この記録から、2つの重要な情報を見ることができます。1つ目は、楊秀が曹操に昇進し、評価されたことです。これは曹操が楊秀を味方につけようとする試みの表れであり、楊秀に「内外のすべてを知る」という地位を与えました。2つ目は非常に重要な点です。つまり、これは『新説天下一篇』の楊秀とはまったく異なる楊秀を提示しているということです。『新説天下一篇』では、楊秀は非常に軽薄で、曹操の後継者を立てるために自ら行動を起こしました。彼は「中途半端に賢すぎる」イメージであり、彼の死には少し「自業自得」の色合いがありました。裴のノートに引用されている資料は、楊秀が曹操に近い秘密を持っていたため、曹丕や曹植を含む曹魏のさまざまな貴族が楊秀と親交を深めようと競っていたことを明らかに示している。楊秀が曹植を助けることを選んだ理由は、当然ながら彼の政治的立場と関係があった。この問題については後ほどさらに分析します。 楊秀は実際に漢の立場を支持した 東漢の楊家は社会的に非常に名声があったため、曹操は楊家の支持を得るために全力を尽くさなければなりませんでした。これは曹操が貴族階級に対して柔軟に対応していたことを示しています。しかし、彼らを味方につけようとする度重なる試みが失敗に終わった場合、時が来れば曹操は「古い関係に頼り、信心深くない」者や、漢王朝の交代に協力する意志のない者を殺すことになります。 表面上、楊秀の死は後継者争いに巻き込まれたことによるものだった。しかし、楊秀の悲劇は、本質的には、彼が父親と同様に漢王朝に忠誠を誓い、曹魏が漢王朝に取って代わることを支持しなかったためであり、それが曹操に彼を殺す口実を与えることにつながった。 2. 楊秀の死と曹操の継承 楊秀とその父である楊彪は漢王朝の扶養問題に関しては同じ立場をとっていたと言わざるを得ない。しかし、父と息子のスタイルは若干異なります。楊彪は建安の時代から曹操への協力を拒否したが、楊秀は曹操に仕え続けた。しかし、楊秀は曹操に仕えていたにもかかわらず、曹操を尊敬していなかったことは指摘しておくべきだろう。曹操の前で自分の才能をひけらかすことが多く、曹操の権威に対する軽蔑を示しているようだった。これは実は、孔容や倪亨など、漢の忠臣が過去に見せたさまざまな振る舞いと似ている。 楊秀は自分の知性を誇示したが、傲慢ではなかった。 楊秀の行動については歴史書に多くの記録が残っている。 「世界の物語の新しい説明:素早い啓蒙」: 楊徳祖は衛公主の秘書でした。当時、彼は宰相の門を建てていました。ちょうど梁を組み始めたとき、衛武が見に来ました。彼は誰かに門に「活」の文字を書いてもらい、立ち去りました。ヤンはそれを見て、破壊するよう命じた。話を終えた後、彼はこう言った。「『ドア』の『活発』という言葉と『広い』という言葉は、王正がドアが大きすぎると考えていることを意味しています。」 『後漢書:楊秀伝』: 「曹操が漢中を征服したとき、劉備を攻撃したいと思ったが、前進できず、防御するのが困難でした。衛兵はどのように前進し、どのように止まるべきかを知りませんでした。そこで曹操は命令を出し、「鶏の肋骨」とだけ言いました。曹操以外の誰も理解できず、修だけが言いました。「鶏の肋骨、食べても何も得られませんが、捨てたら残念です。戻って決断してください。」 「そこで彼は外部に厳重な処置を命じ、曹はここで軍に戻った。秀がほぼ決心した時のようなケースはよくある。」 『史記』のいくつかの逸話は基本的に『三国志演義』に取り入れられ、楊秀の「軽薄な」イメージを形作った。『後漢書』のこの「役に立たない」記録は、『三国志演義』の羅貫中によって楊秀の死の直接の原因としても解釈された。 しかし、先に述べたように、楊秀の死因は決して単純なものではなかった。 『三国志』には楊秀に関する個別の伝記がないので、彼の死因については解明し明らかにする必要がある。 "クラシック": 「公(曹操)は教えを漏らし、諸侯と関係を持ったと非難され、逮捕され、殺された。」 「三国志:陳思王志の伝記」: 「芝はかつて車に乗って道中を走り、司馬門を開けて去ろうとした。太祖は激怒し、芝を処刑するよう命じた。それ以来、君主への処罰は強化され、芝の寵愛は次第に衰退した。太祖は始末の変わり目を心配し、楊秀は才能と戦略に優れ、袁の甥でもあったため、処罰され、処刑された。」 これら二つの史料を分析すると、どちらも楊秀が曹植の客人であったと明らかに言及しており、これは楊秀が「志党」の一員となり、後継者争いに巻き込まれたことを意味しており、これが楊秀の死の直接的な原因であると見ることができる。しかし、曹植の党員の中には司馬郁、賈奎、王凌など、曹植の党員だった人がたくさんいた。なぜ楊秀を殺さなければならなかったのか?また、曹植の党員の殺害は、実際にはほとんど曹丕によって行われた。しかし、曹丕自身も楊秀は「甘すぎる」と考えており、死刑に値しないと考えていた。楊秀の死後、曹丕は楊秀をとても恋しく思っていた。結局、建安24年に曹操は楊秀を殺害し、建安22年に曹丕は皇太子に立てられた。後継者争いは2年以上も続いた。楊秀が本当に後継者争いに巻き込まれたために死んだのなら、なぜ曹操は死のわずか100日前に楊秀を殺害することを決めたのだろうか? 以上のことから、曹操が楊秀を殺害したのは、楊秀が後継者争いに巻き込まれたからという単純な理由ではなかったことがわかります。 継承をめぐる争いには多くの人が関わっていたのに、なぜ楊秀だけを殺したのでしょうか? むしろ重要なのは楊修自身の政治的立場であり、曹操が「終始変遷を憂慮」していたのはおそらくそのことだったのだろうと著者は感じている。曹操に仕えることを拒否した父とは異なり、楊秀は実際に曹操に仕え、かつては曹操から深い信頼を受けていました。しかし、楊秀の曹魏グループでの活躍と前回の記事での分析から、楊秀が曹操に仕えた当初の意図は荀攸と非常に似ていたことがわかります。二人とも曹操の力を利用して漢王朝を復興したいと考えていました。これは、代々漢王朝に忠誠を尽くしてきた彼の一族の伝統とも一致しています。曹操は死の100日前に楊秀を殺害したが、これは曹操が魏公に叙せられる1年前に荀攸を殺害したのと全く同じである。 『三国志』における荀攸の死因は非常に混乱しており、明確に説明することはほとんど不可能である。陳寿の「(荀攸の死後)翌年、太祖が魏公となった」という一文には、「遂」という語が強いヒントを与えている。 『三国志』にも「秀の死後百日余りして太祖が亡くなり、太子が即位して天下を治めた」とある。このことから、楊秀の死の真の原因は陳寿によってほぼ同じように伝えられていたことがわかる。 楊秀は家系の伝統を受け継ぎ、漢王朝に忠誠を誓い、自分のやり方を変えることを望まなかったため、結局曹操に受け入れられなかった。曹操は「非常に才能があり、機知に富んでいた」ため、背後の政治情勢を懸念し、漢朝に残っていた権力をすべて抑制することを考慮して、最終的に楊修を殺すために刀を振り上げた。 曹操は楊修の政治的立場を懸念していた 楊秀の死は、楊弘農一族の「四代三官」の全盛期の終焉を意味し、貴族階級が支えた東漢王朝の終焉を意味した。 3. 楊秀の死と漢から魏への変遷 楊秀の死は曹植の没落と密接に関係しており、どちらの出来事も親漢勢力の完全な衰退を意味し、当然ながら東漢の完全な敗北と漢から魏への不可逆的な移行を意味した。 楊秀の死は、根本的には彼の親漢の立場によるものであった。しかし、楊秀が漢を支持したことと曹植を支持したこと、また曹植を支持したことと漢から魏への転換との間には、本質的なつながりがあるのだろうか。これは、学界やインターネットではあまり議論されていない問題である。筆者は以前、周一陸氏の『魏晋南北朝史注』を読み、そこから得たものがあるようだ。ここでは、表面的な見解について簡単に述べたいと思う。 楊秀の政治的立場は明らかである。漢王朝の忠実な支持者として、彼は漢から魏への転換に断固として反対したに違いない。しかし、曹植の政治的立場はあまり注目されていない。曹操の息子として、これは議論されるべき問題ではないと思われる。しかし、周一良氏は著書の中でその謎を探り、「曹丕と曹植の争い、そして子堅の失敗は、漢王朝を奪取しようとする曹操の決意に対する彼らの態度にも関係している可能性がある」と指摘した。 清代の学者宋相鋒は著書『国廷録』の中で、曹植の『三好詩』にある「功名を得ることはできず、忠義は我が満足である」という言葉を分析し、曹植は漢王朝に忠誠を尽くし、自分以外の考えを持つべきではないと信じた。また、建安15年に曹操は桓温と自分を比較し、彼を支えたいと思ったとも言われています。曹操の言葉の真偽は当然疑問ですが、曹操が自分と桓温を比較した際に、曹植の考えは自分の考えと一致しているとも言っています。これは事実を誤って表現したものではないかと思います。その後、曹植は失脚し、「状況が許さなかった」。これは曹植が「依然として以前の意図に固執していた」結果であった。言い換えれば、曹植は常に「桓文の仕事」を主張し、漢王朝に取って代わって独自の政権を樹立し、漢魏の転換を遂行するのではなく、漢王朝を支援するために最善を尽くそうとした。その後、曹丕が漢王朝を簒奪した。曹植は兄から決して許されなかった。このような状況下でも曹植は大きなリスクを冒し、「喪服を脱いで激しく泣く」など、漢王朝への強い執着を示した。 『蘇沢伝』には「臨淄侯志は、魏氏が漢王朝に取って代わったと聞いて、喪服を脱ぎ、激しく泣いた」とある。これは特異な事例ではない。『魏歴代』にも同様の記録がある。「志は先帝の寵愛を失ったことを悲しみ、激しく泣いた」 曹操の息子である曹植の政治的立場は予想外のものだった。 北魏の孝文帝は兄の袁懿への信頼を表明した際、「二人の曹は才能と名声で互いに嫉妬しているが、あなたと私は道徳で親しい。自分を抑制して礼節に戻れば、他のことは気にする必要はない」と述べた。曹丕と曹植の争いに対するこれまでの解釈は、主に「才能と名声への嫉妬」の観点から見られており、おそらくその理由の一部しか含まれておらず、兄弟の政治的才能のみを議論し、政治的野心の違いを無視していた。曹操はかつて「第一は子堅、我が子の中では最も重大事を決める能力がある」という訓令を出した。曹操がここで言う「重大事を決める」とは、間違いなく漢の魏継承を指している。これは曹操が魏の皇太子を選ぶ際に、漢王朝の簒奪問題と結び付けていたことを示している。曹操はかつて曹植に大きな期待を寄せていたが、後に曹植は漢王朝への郷愁を露わにし、少なくとも漢王朝を簒奪する考えについては曖昧な態度を取った。曹丕の野心と比較すると、曹操が最終的に考えを変えて曹丕を後継者に選んだ理由は非常に簡単に理解できる。 ここでは曹植の漢王朝に対する態度について論じることに多くのスペースが費やされている。曹植の政治的傾向を理解することは、楊修が曹植を一貫して強く支持していたことを理解する上で非常に重要だからである。実は、楊秀だけではなく、当初曹植を支持した人物は多くいた。後に曹魏の建国の英雄となった賈駁、王凌、司馬馗も曹植の支持者だった。さらに、荀彧の態度も熟考する価値がある。荀彧は曹操の後継者問題について明確な発言をしなかったが、息子の荀雲の選択から荀彧の態度を垣間見ることができる。 曹丕は野心家で、漢王朝を奪取しようと決意していた。 『三国志』における荀雲の伝記: 「最初、文帝と平原侯志は似たような考えを持っていたが、文帝は禹を丁重に扱った。禹が亡くなった後、雲と志は再び仲が良くなった…文帝は雲を深く憎んでいた。」 前述のように、陳寿は『三国志』の中で荀攸の死因をすでに強く示唆していた。ここで陳寿は荀雲も「智と仲が良かった」とも言っており、明らかに深い意味がある。曹魏の時代の荀攸の子孫を見てみると、いずれも著名な人物とは言えない。これは明らかに荀攸とその息子が漢王朝への忠誠の理念を掲げ、曹植を支援したという事実と密接に関係しています。しかし、賈逵や王陵に代表される貴族たちは漢王朝を捨て、漢から魏への移行を支持するようになった。結局、楊秀だけが自分の信念を貫き、頑固に曹植を支え続けた。このような孤独な粘り強さは明らかに不十分だった。楊秀自身が「だから私は死ぬのが遅くなると思う」と言ったのも不思議ではない。彼は実際に自分の最後の悲劇を予期していたのだ。 楊秀は貴族階級の中で漢王朝の最後の、そして最も忠実な支持者であったため、漢から魏への移り変わりの波の中でとても孤独に見えました。楊秀は大きな野望を抱いて曹植に身を委ねたが、曹植の失敗により、結局は一族の栄華を継承し、残された漢王朝を再興することができなかった。これが彼の悲劇の本当の原因かもしれない。 楊秀の悲劇の根源は、漢から魏への転換を支持しなかったことだった。 結論 楊秀が死んだのは、曹操が有能な人材を嫉妬したからではなく、曹操の誘惑を拒み、漢王朝への忠誠を常に主張し、曹操が漢から魏に移ることに反対したためである。しかし楊秀には政治的にも軍事的にも曹操に対抗できるほどの資金がなく、曹操の前で才能を誇示して曹操の権威に逆らうことしかできなかった。彼は、漢王朝を簒奪する意図のない曹植の政治的理想を実現するために、曹植を支持することしか選択できなかった。しかし、曹植が帝位獲得に失敗したため、曹操は楊秀の才能と政治的立場を常に警戒していた。曹操は最終的に、楊秀の死を前に、政治的リスクを排除するために楊秀を排除することを決意した。楊秀の死は画期的な出来事であり、洪農楊家の「四代三官」の全盛期の終焉、貴族階級が支えた東漢の終焉、そして漢から魏への転換の最終的な到来を告げるものであった。 |
<<: 『三国志演義』に出てくる四つの毒泉は本当に存在するのでしょうか?どこですか?
>>: 張覇蛇槍は誰の武器ですか?張八蛇槍の長さはどれくらいですか?
推薦する
歴史考古学によれば、香を焚くための香炉が古代のどの時代に登場したのでしょうか?
古代中国では、香の使用に長い歴史があります。中国に仏教が伝わると、さまざまな香料が登場し、香の芸術が...
唐代の詩人、魏応武の『新秋夜兄弟書』の原文、注釈、翻訳、鑑賞
「新秋夜同胞書」は唐代の魏応武によって書かれたものです。次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けし...
宋代の詩「西江月」を分析して、詩人はどのような感情を表現しているのでしょうか?
西江月·宋代の張小湘の『湖畔春景色』について、以下の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので...
『中級レベルの春節祭』の著者は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
中級春節祭①王安石春のそよ風が花を吹き飛ばし、涼しい日陰を与えてくれます。池への道は静かで暗く、庭園...
『紅楼夢』で王希峰が林黛玉に尋ねた質問は貴族の生活習慣を反映している
周知のように、林黛玉が賈邸に入るシーンは間違いなく『紅楼夢』の中で最も重要なシーンです。その中で、王...
馮小青とは誰ですか?明代の揚州の八大美人の一人、馮小青の簡単な紹介
馮小青、本名は玄、雅号は小青。彼は明代の万暦年間に南直里(現在の江蘇省)揚州に生まれた。杭州の富豪、...
『紅楼夢』では「季」と「気」が共存しています。「季」とは何のことですか?
「紅楼夢」は何度も登場し、「側室」が共存しています。側室はわかりやすいですが、「妾」とはどういう意味...
孫悟空が五本指山の下に閉じ込められていた500年間、誰が彼を訪ねたのでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
「サンセットタワー」の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
サンセットタワー李尚閔(唐代)ご存知のように、滕陽では遂寧の大臣蕭が滕陽を統治していた日に建てられま...
金玄宗の南方への移住がなぜ金王朝にとって重要な転換点となったのでしょうか?
古代中国の歴史では、ほとんどの王朝が都を移しています。有名なものとしては、潘庚の殷への遷都、周の平王...
曹桂の論争とは何ですか?曹桂の論争の主人公は誰ですか?
曹桂は春秋時代の魯の国の医師であり、歴史上有名な軍事理論家である。当時、斉国が魯国を攻撃しており、曹...
水族の建築や食事にはどのような民族習慣があるのでしょうか?
水祖居住区は亜熱帯に位置し、雨が多く湿気が多く、深い森があり、ジャッカル、トラ、ヒョウ、イノシシなど...
『紅楼夢』で宝玉はどのようないじめ行為をしましたか?
賈宝玉は『紅楼夢』の主人公であり、作家曹雪芹が書いた人物です。興味のある読者と『Interestin...
鄧塵の妻は誰ですか?鄧塵の妻、新野公主劉淵の簡単な紹介
劉淵(?-22年)は、漢の光武帝劉秀の姉である。父は南屯主劉欽、母は范献都である。劉淵は若い頃に鄧塵...
太平広記・第1巻・仙人・顔真卿を翻訳するには?原文の内容は何ですか?
『太平広記』は、漢文で書かれた中国古代の記録小説集で、全500巻、目録10巻から成り、漢代から宋代初...