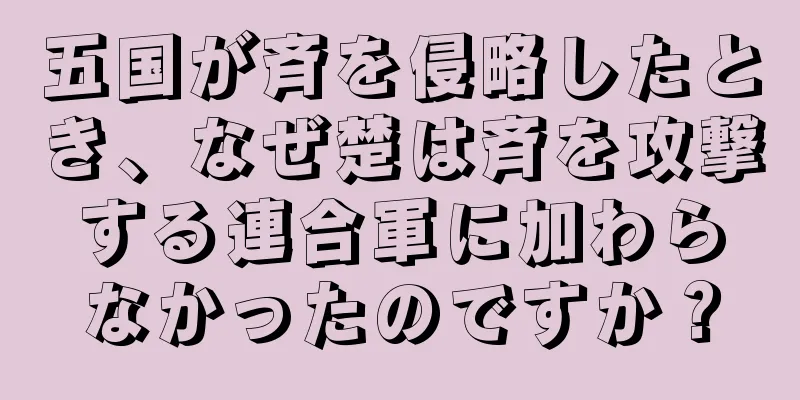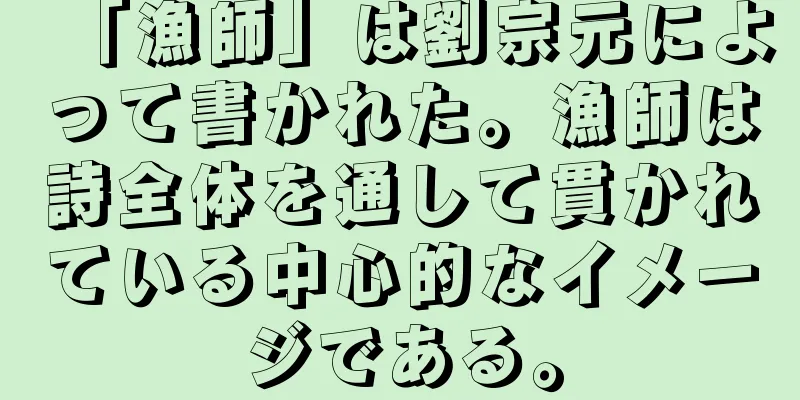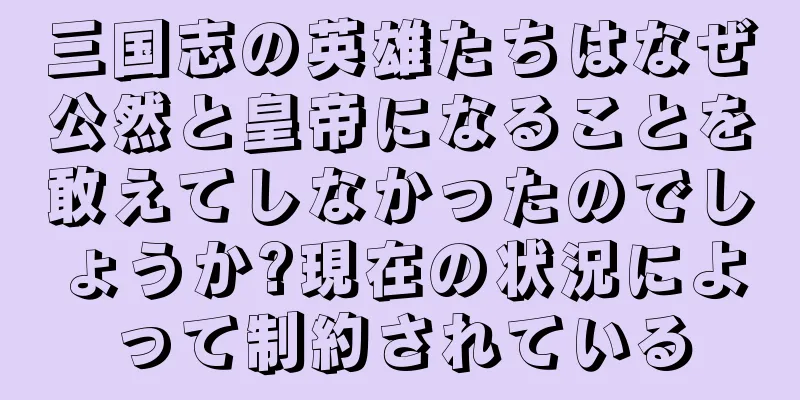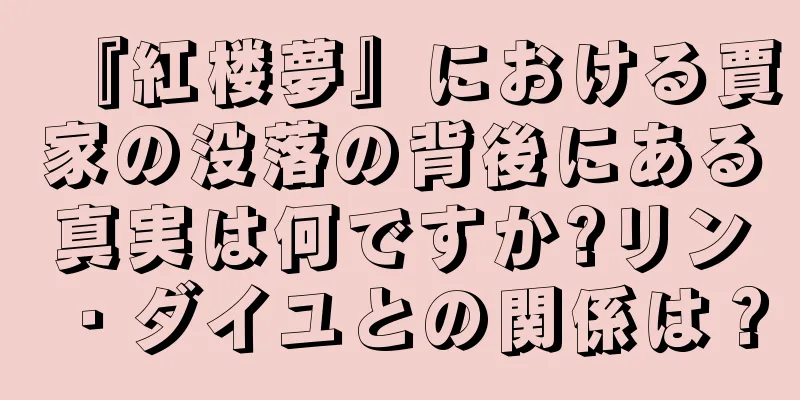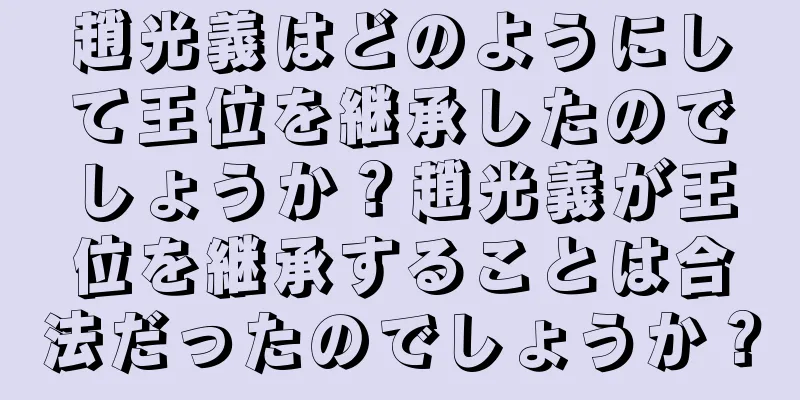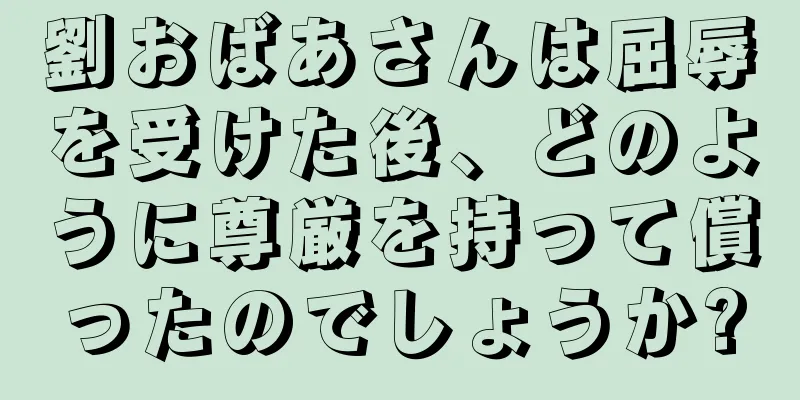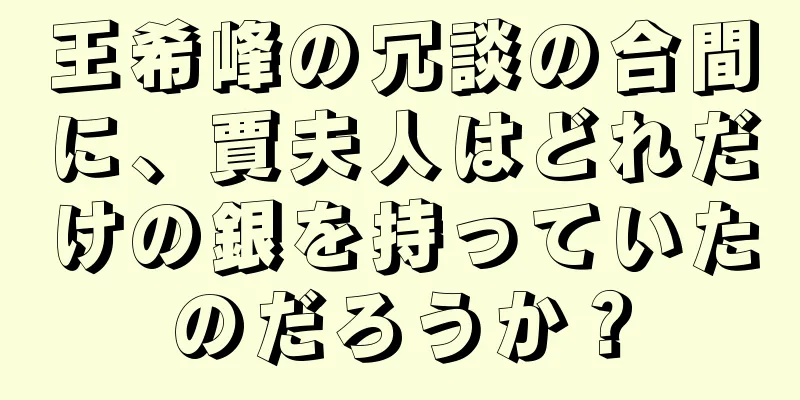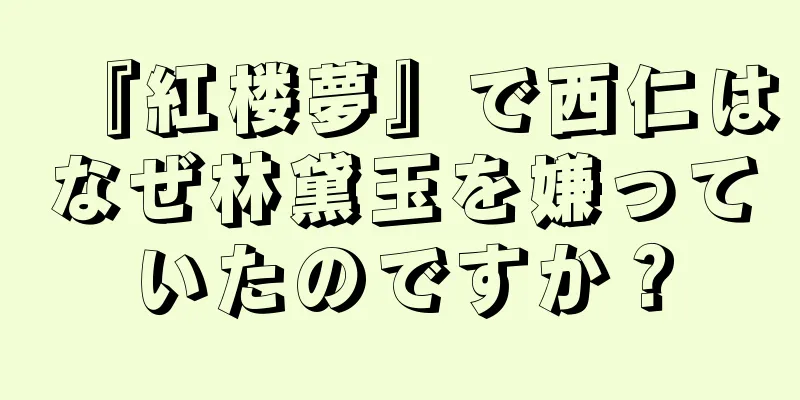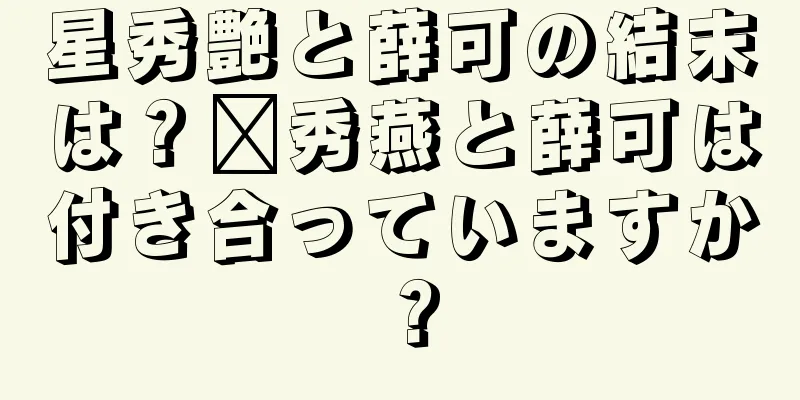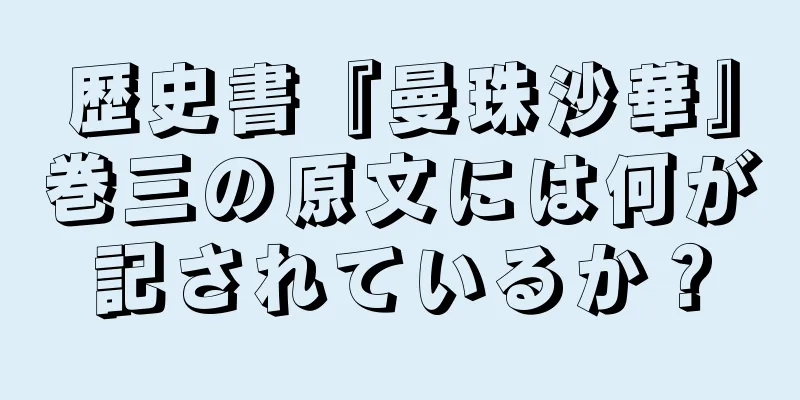古代の戦争では将軍たちは本当に一対一で戦ったのでしょうか? 「戦う将軍」という現象は正史に本当に存在するのでしょうか?
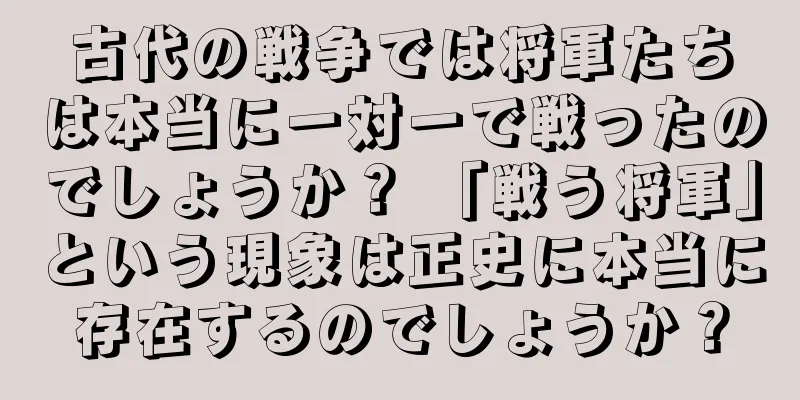
|
今日は、Interesting Historyの編集者が「戦う将軍」についての記事をお届けします。ぜひお読みください〜 中国の歴史を反映した時代劇のテレビドラマでは、非常に興味深いシーンがよく見られます。つまり、両軍が戦闘を始める前に、兵士と馬が戦場に整列し、将軍は馬に乗って出陣し、「私は誰それだ、ここにいる。誰が死ぬまで戦う勇気があるか!」などと大声で叫んだのです。すると敵陣の将軍が駆け寄ってきて決闘を始める。これは歴史上本当でしょうか? この場面は『三国志演義』によく登場します。例えば、関羽が有名になったのは、十八王子が董卓と戦っていたとき、董卓の指揮下にある華雄が軍を率いて戦い、王子の孫堅が敗れたからです。その後、十八王子はそれぞれ潘鋒、于社などの将軍を派遣しましたが、誰も華雄に3ラウンド耐えることができませんでした。 その結果、18人の王子は互いに顔を見合わせて狼狽し、兵士たちの士気も大きく低下しました。この混乱の時に、当時は小さな弓兵と騎兵に過ぎなかった関羽が前に出て、一撃で華雄を倒しました。その結果、董卓に対する連合軍の士気は瞬く間に高まり、関羽の勇猛果敢な名前は世界中に広まりました。 また、『岳飛全伝』や『隋唐志演義』などの歴史小説には、戦前、両軍の将軍が一対一で戦うような古代の戦いが多く登場します。例えば、岳飛は戦前、楊在興の「裏切り」を破り、楊在興に入隊を決意させました。羅成は戦前、竇建徳の娘竇先娘を破り、美しい結婚生活を送りました。 こうした歴史小説が広く普及し、現代の映画やテレビドラマの影響もあって、人々は戦いの前に将軍が一対一で戦うというルールにすっかり慣れてしまい、だんだんとそれが真実かどうか疑問に思うようになりました。結局のところ、これらの本に書かれていることがいかに真実であっても、それは単なる小説であり、必ずしも本当の歴史ではありません。それでは、正史が何を言っているのか見てみましょう。 『漢書』の記録によると、項羽と劉邦が広武で戦っていたとき、劉邦は城壁に隠れて出てこなかった。項羽は劉邦に言った。「我々の出世のために、どうしてこれほど多くの兵士や民間人を巻き込むことができるのか? 我々と戦場で戦って、世界の運命を決めようではないか!」これは、戦場で決闘を仕掛けるという項羽の提案だった。 しかし、劉邦はそれを受け入れなかった。それも無理はない。項羽は劉邦より20歳以上も年下だっただけでなく、幼い頃から三脚を持ち上げることができ、非常に強い個人武術を持っていた。もし劉邦が本当に決闘を挑んできたなら、3手で持ちこたえられれば幸運な方だ。しかし、人前で決闘を拒否するのは恥ずかしい。そこで劉邦はこう答えた。「力で戦うよりも知恵で戦いたい!」これはまるで自分自身で逃げ道を見つけたかのようだった。 この記録から、当時は戦争の際、主将が先に戦うという慣習があったが、相手側が拒否することもできたことがわかります。清代の文献研究者である王時珍は、個人著作『赤北於譚』の中で、この現象を「戦う将軍」という特別な名前で呼んでいます。 古代には、戦闘の際、まず将軍と戦い、次に軍と戦うという現象がありました。しかし、秦漢の時代には、この現象は比較的まれでした。戦争には数十万人が関与することが多く、将軍の個人的な武術が戦争で活用される余地はあまりなかったからです。逆に、三国時代、十六国時代、南北朝時代などの激動の時代には、将軍と戦う傾向が広まりました。これは主に、小規模で突発的な戦争が多くなったため、将軍の武術がより重要になったためです。 |
<<: 古代のお金の名前は何でしたか?古代のお金はどんな感じだったのでしょうか?
>>: 清軍の関への侵入は漢文化にどのような影響を与えたのでしょうか?清朝が中国に与えた影響を美学の観点から見てみましょう!
推薦する
歴史上最も熱狂的な皇帝は実際に棺桶に入り、女王の遺体と性交した
歴史上、熱狂的な皇帝は数多く存在したが、恐ろしいほど熱狂的な皇帝はそう多くはない。慕容家は最も熱狂的...
中国古典『東周紀』第4章:秦の文公は、鄭の荘公が地面を掘って母親の姿を見た夢を見た。
平王が東進して洛陽に到着すると、郝京のものと変わらない賑やかな市場と豪華な宮殿を見て、とても喜んだと...
劉備は増援のため荊州の主力を益州に移したが、この軍の主将は誰だったのか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
羌族の食べ物 羌族の「托九」にはどんな文化があるのでしょうか?
羌族の人々は茶酒を飲むたびに神々を崇拝し、茶酒は神々と人々をつなぐ媒介となる。羌族は酒で神を崇拝しま...
宋江が涼山に行った後、陸俊義はなぜそんなに彼を恐れたのでしょうか?慎重に話すことも?
『水滸伝』では、宋江はあらゆる手段を使って呂俊義を梁山に引き入れただけでなく、呂俊義を梁山の副官に据...
十六国時代の後趙の君主、石賁の略歴。石賁はどのようにして亡くなったのでしょうか?
石頌(339-349)、号は福安、桀族の人。上当武郷(今の山西省)の人。後趙の武帝石虎の息子、母は劉...
古典文学の傑作『淘宝夢』:第8巻:呂兄の全文
『淘安夢』は明代の散文集である。明代の随筆家、張岱によって書かれた。この本は8巻から成り、明朝が滅亡...
古代の皇帝の名前はどのようにして付けられたのでしょうか?皇帝の名前はなぜそんなに奇妙なのでしょうか?
歴史上の皇帝の名前に使われている漢字の多くは奇妙で難解であり、平時にはほとんど見られません。以下は、...
漢代のどの皇帝が建立したのですか?宮殿のレイアウトはどのようなものですか?
中国の古代宮殿建築である建張宮は、太初元年(紀元前104年)に漢の武帝劉徹によって建てられました。武...
『紅楼夢』における秦克清の葬儀は賈家にどのような影響を与えましたか?
秦克清は『紅楼夢』の登場人物であり、金陵十二美女の一人である。次回は、Interesting His...
王維の古詩「王師を蜀に送りて礼を尽くす」の本来の意味を理解する
古代の詩「王先生を蜀に送り返して礼をさせる」時代: 唐代著者: 王偉大洛天からの仙人が来ていて、卓金...
ランタンフェスティバルは他に何と呼ばれていますか?ランタンフェスティバルの起源と意義を探る
元宵節は中国の重要な伝統祭りの一つで、毎年旧暦の1月15日に行われます。元宵節には、「上元節」や「小...
『紅楼夢』では、賈おばあさんはいつも笑っていたのに、なぜ元宵節に西仁を公然と批判したのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
『紅楼夢』で、王希峰がなぜ王山宝に横武源を捜索する許可を求めたのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
中国にとって西域はどのような存在なのでしょうか?西部地域の存在または不在はどのような影響を及ぼしますか?
本日は、Interesting History の編集者が、西域の存在と不在がどのような影響を与える...