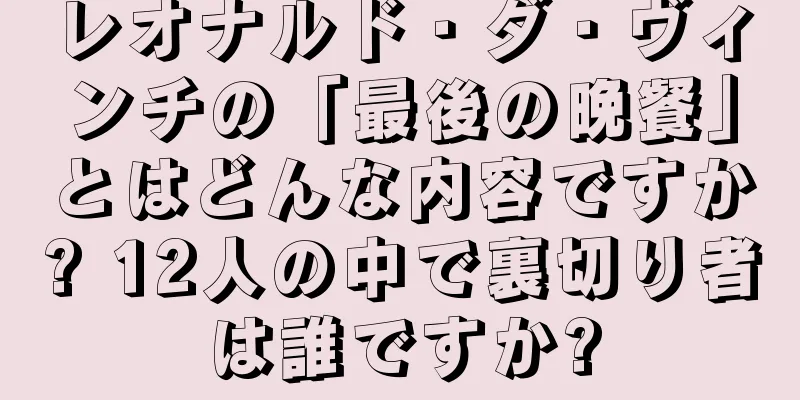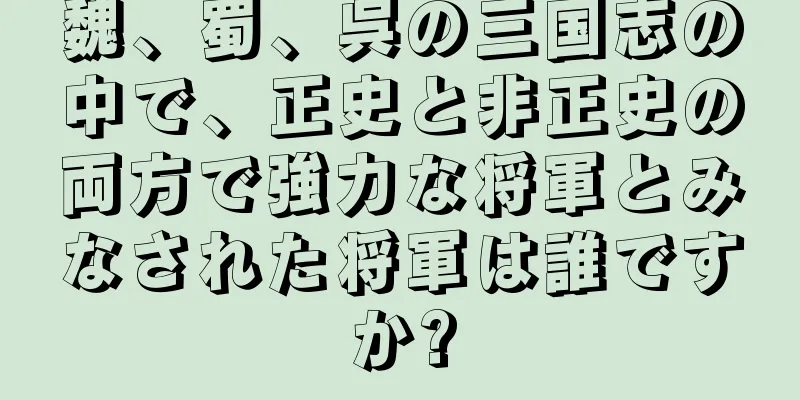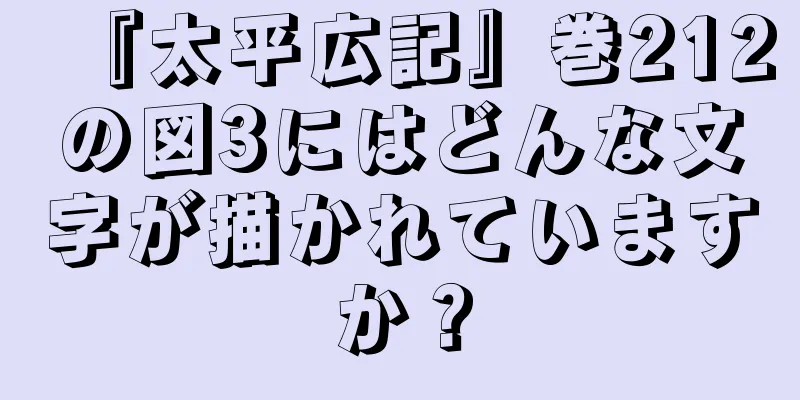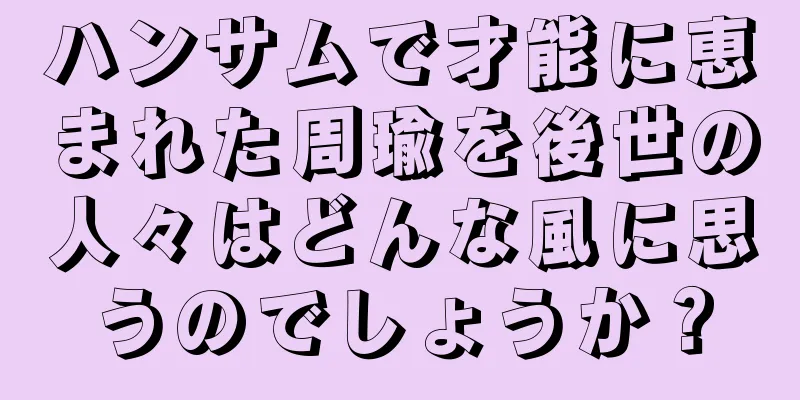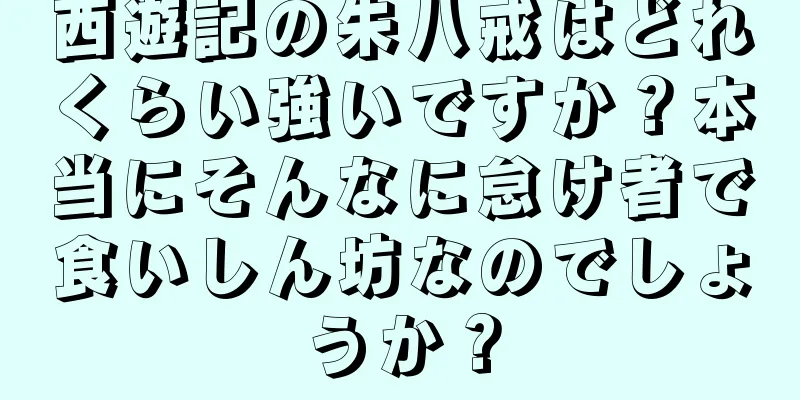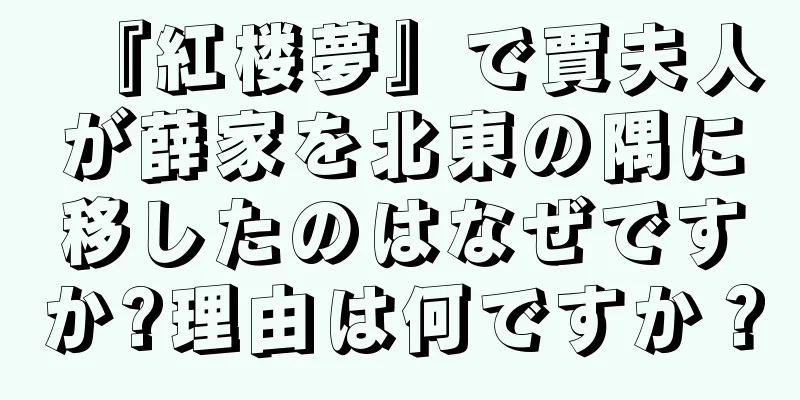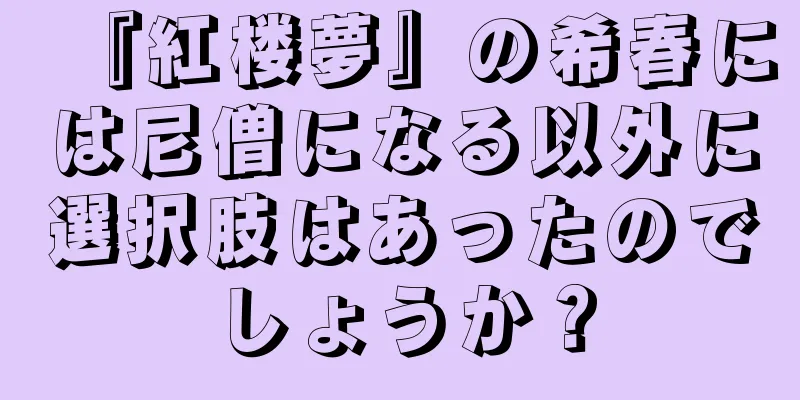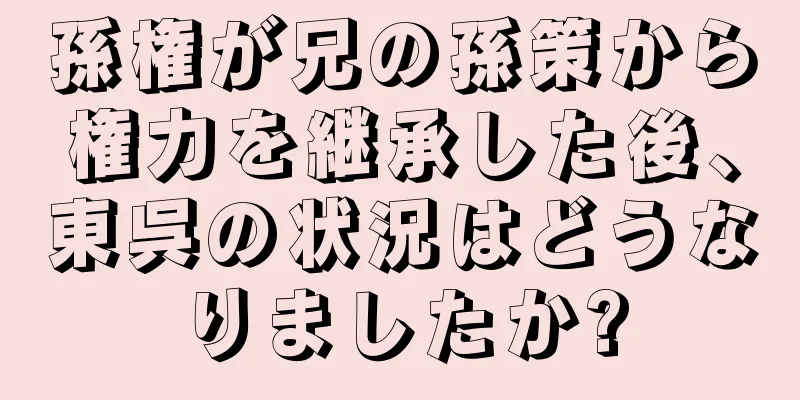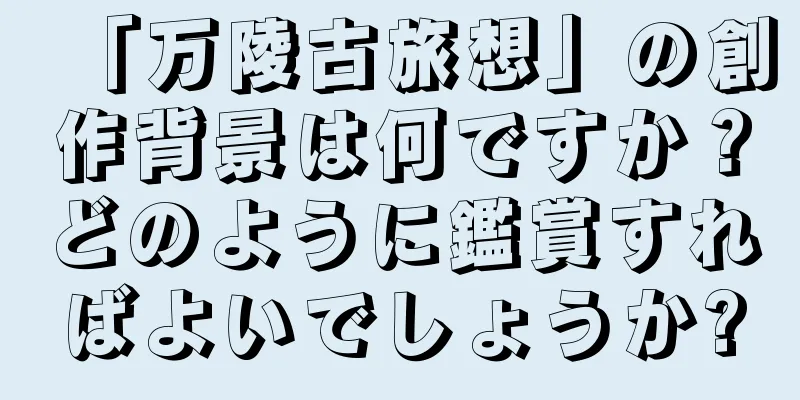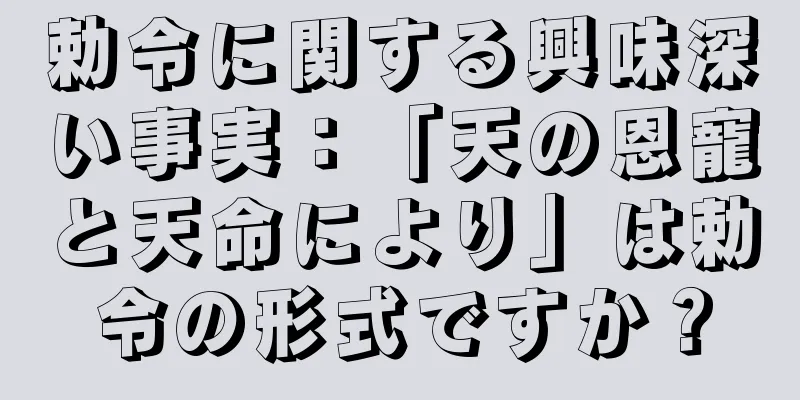元王朝が成立したとき、なぜ「儒教」に抵抗したのでしょうか?儒教の統治制度はどのようにして復活したのでしょうか?
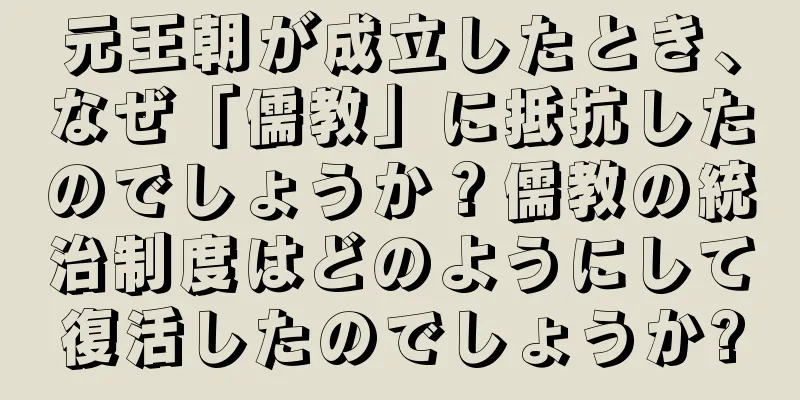
|
儒教の統治体制はいかにして復活したのか。Interesting History編集長が、その内容を詳しく紹介します。 序文:『二十二史記 巻三十』に「元代には儒教は重んじられなかった」と記されており、儒教に対する抵抗が極めて大きく、そのため元代における儒教の社会的地位は非常に低かった。しかし、問題は、「儒教」が封建領主に対して果たした肯定的な役割が誰の目にも明らかであるということです。そのため、明の太祖朱元璋にとって、儒教の統治制度をいかに再建するかが、権力を握った後に解決しなければならない最重要課題となった。最終的に、儒教に対する人々の信頼を回復し、儒教統治体制の復興という最終目標を達成するために、四書五経を科挙の内容とする科挙による官吏選抜方式を採用することが決定されました。 モンゴル帝国の大ハーン、オゴデイの肖像画のイラスト 元朝は儒教の本質に抵抗した 多くの人が不思議に思うかもしれないが、漢の武帝が「諸学を廃し六経を推し進め」て以来、大多数の封建君主が「儒教」を統治の手段とみなし、それを「思想統治のシステム」にまで拡張してきたことは、儒教に確かに長所があることの証明に十分である。元朝がそれを継承しない理由はない。 ——『武帝紀』 実際、元朝は「儒教」をある程度継承していたが、それを「高位の統治思想」とはみなしていなかった。むしろ、それは草の根レベルに限定され、漢民族地域から軍事資金を集めるための統治手段として考えられていた。 それは、モンゴル帝国の大ハーン、オゴデイの治世と全く同じである。イェル・チュツァイが「陛下は南征をなさるでしょうから、軍需品を供給してください。中原の年貢は均等に定めることをおすすめします。毎年、銀50万両、絹8万枚、粟40万石を得ることができます」という申文を提出した後、オゴデイは「周と孔子の教え」を試してみることにした。 ——『新元史・野呂初才伝』 同時に、多くの「儒学者」官吏も設置された。実は、このことからも、オゴデイが「儒学」を推進した目的は軍事資金を得ることにあったことが分かる。 パグパ文字の石彫りのイラスト その後、元朝の創始者フビライ・ハーンの治世中に、「非国家主義」という政治的目標を達成するために、フビライは国師「パグスパ」に「パグスパ文字」の作成を依頼しました。 これは、「脱国家化」を進めれば、必然的に「儒教」の影響を受けた中原の文化体系との明らかな衝突が生じることを意味しており、そのため、元朝の創始者であるフビライ・ハーンにとって、「儒教」に抵抗することが唯一の選択肢となった。そのため、「モンゴル文字を重視し、世界中の人々がモンゴル語を学び、モンゴル語の書き方に習熟できるようにする」という取り組みが行われました。 ——「二十二の歴史的ノート、第30巻」 儒教は元朝の統治の安定を脅かすものとして元朝から抵抗され始めたのはこの頃であり、それは明らかに元朝の統治者たちが望んでいたことではなかった。 中原には儒教が古くから深く根付いていたにもかかわらず、フビライ・カーンの「脱民族化」という政治的目標は、実際には達成されなかった。結局、彼は漢民族の支持を必要とし、遠征の費用を賄うために漢民族から税金を徴収する必要があったのだ。そのため、フビライ・ハーンは原点に立ち返り、「モンゴル教」を基盤として「儒教」の地位を適切に高め続けるしかなかった。 元朝の創始者フビライ・ハーンの肖像画のイラスト フビライ・ハーン以来、元朝の君主たちはみなこのようであり、「元朝では文学が非常に軽視されていた。学者十人のうち九人は乞食だったという言い伝えがあった。科挙制度は何度も新設され、廃止された。風流や洗練といった事柄が些細なことのように放棄されたのは当然であった」という言い伝えがある。 ——「二十二の歴史的ノート、第30巻」 つまり、元朝はある程度儒教を継承していたものの、それは軍事資金を集めることにとどまっており、その本質は「華夷秩序」を「モンゴル秩序」に置き換えることだった。そのため、モンゴルの統治体制のトップレベルではモンゴルの慣習や礼儀作法が保持されていたが、人種や職業の階級制度を利用して、漢民族や知識人を草の根レベルで抑圧したのである。 ——中華夷秩序について これは元朝の統治者が統治の地位を強化した必然的な結果であり、「儒教」と「モンゴル統治秩序」の対立があまりにも明白であったため、完全な「脱国家化」はできなくても、少なくとも社会的身分に対する包括的な統制を達成する必要があった。これにより、元朝が「儒教」に抵抗する状況が生まれた。 その結果、元朝の抑圧的な状況下では、儒学者は効果的に昇進することができず、元朝の統治体制の輪に入ることができませんでした。それでは、「貧しい学者」として「儒教」を学ぶことに何の意味があったのでしょうか? このため、元代に「儒教」を普及させることは極めて困難であった。これが連鎖反応を引き起こし、人々は儒教への信頼を失い、ほぼ 100 年にわたる断絶が生じました。 元朝の肖像画の図 「儒教統治制度」の復活の必要性 まとめると、元朝が「儒教」に抵抗したのは、儒教が存在する必要がなかったからではなく、「儒教の統治体制」と元朝の「モンゴル秩序」が衝突し、共存できなかったからであることは、誰にとっても理解しにくいことではないと思います。 そうでなければ、朝廷の文武官のほとんどは儒教を学んだ「漢人」だった。モンゴル貴族の利益はどうやって保証されるのか? そのため、「儒教」に上限を設けて草の根レベルで制限することしかできず、表面的には「モンゴルと漢人の一族」でありながら、実際は軍事作戦のための軍事資金を集める手段に過ぎない統治の道具となってしまった。 しかし、明朝は違いました。明朝自体が「漢民族の政権」であったため、いわゆる「民族の壁」やそれに伴う「文化の違い」は存在せず、「儒教」に抵抗する理由がなかったのです。 程朱の儒教の図解 宋代に勃興した「程朱新儒教」、すなわち「程浩程易」の「徳のある者は天の理を得て、それを利用する」という命題と、個人の道徳実践に重点を置いた「天の理を保持し、人間の欲望を排除し、厳格な教育を行う」という朱熹の命題と相まって、それは間違いなく人々の「天の理」の理解を効果的に促進することができる。それは人々の「神」への信仰を確立することです。 ——「河南程家手紙 第2巻」 言い換えれば、封建時代の「王権神授説」の考え方をよりよく説明できる。したがって、朱元璋にとって、帝位に就いた後に最初にしなければならなかったことは、彼の「皇帝権」の合理性と正当性を証明する方法を見つけることだった。つまり、国民の承認と支持を得て、皇帝としての地位は神から授けられたものであり、自分は「天」の代弁者であるということを国民に認めさせる必要がある。 朱元璋が即位した時、天に供物を捧げる儀式を行う前に、次のような勅令を出した。「もし私が臣として仕えることができるなら、供物を捧げる日に皇帝が来られ、空が晴れ、風が穏やかであることを願います。もし私が臣として仕えることができなければ、供物を捧げる日に強風や異常気象が起こったら、お知らせします。」 - 『万歴佛編・第1巻』 明朝の初代皇帝朱元璋の肖像画の挿絵 その目的は自明である。それは、朱元璋の「皇帝の座」が確かに「天」の同意を得て獲得されたことを民衆に示すためである。人々が将来、天気が良く、平和で満足した生活と仕事を望むなら、朱元璋を支持しなければならない。 言うまでもなく、儒教は数千年にわたって受け継がれ、すでに人々の意識に痕跡を残しています。元朝時代の儒教への抵抗により、人々は一時的に「儒教」への信頼を失いましたが、その基礎は今も残っています。 そのため、「儒教の統治体制を回復する」ことが太祖朱元璋にとって民衆の支持を得るための最も早い方法となり、また最善の解決策でもあった。朱元璋がしなければならなかったのは、民衆の儒教への信頼を再構築することだけだった。まったく新しいイデオロギーの統治体制を再構築することに比べれば、儒教の統治体制を回復することは明らかにはるかに容易だった。 朱彪の肖像画のイラスト 朱元璋は「儒教統治システム」の思想を再構築した そのため、朱元璋は元代19年(1359年)には「明王朝」を建国しなかったものの、実は儒教の統治体制を「再建」しようと考え、「儒学奨励所を設立し、宋廉を奨励所長に任命し、息子の彪を儒学の経典を学ばせた」。 - 『明史・太祖一』 名前の通り、明王朝がまだ成立していなかったにもかかわらず、「儒教の統治体制」への回帰を意識する必要があったため、自らの息子から始め、皇太子朱彪を明王朝の模範として儒教を推進させた。 つまり、まず「儒教統治システム」の思想を再構築し、「儒教」の社会的地位が元代ほど低くないということを国民に認識させなければならない。元代の「学者十人のうち九人は乞食」という噂のように、彼らの地位は乞食より上というわけではない。 ——「二十二の歴史的ノート、第30巻」 孔子の肖像画のイラスト そして、元の治正26年(1366年)、明の太祖は「官吏に命じて古今東西の書物を探し出し、秘密の書庫に保管して読ませる」とともに、「孔子の言葉はまさに古今東西の教師」であり、まさに「国を治めるための良い規則」であると述べた。これは、明代の太祖、朱元璋が「儒教」を国の統治思想として採用する意図を持っていたことを証明するのに十分です。 ——『明代紀』第14巻 これは、明朝が建国されるずっと前から、「儒教」を標榜する明朝の「思想」がすでに比較的よく構築されていた、つまり「種」はすでに蒔かれており、あとは明朝が正式に建国されるまで待つだけで、その後は「水やりと肥料やり」で「儒教」の種が根付いて芽を出すだけだったということを意味する。 「儒教」を学んだ人々が「支配階級」、つまり明の太祖朱元璋に対する信頼を取り戻すようにしなさい。そうすれば、「民衆」の「儒教」に対する信頼が回復することで、明朝は人材を安定的に獲得し、明の太祖朱元璋の支配的地位を強固にすることができる。 劉基の肖像画のイラスト 朱元璋は官僚を採用するために科挙制度を採用し、四書五経を試験内容としました。 そのため、「明代の太祖が初めて国を統一したとき、他の事柄に時間を割く余裕がなかったので、まず礼楽の二つの部署を設置し、多くの高位の儒学者を招集して各部の問題を議論させた」。彼が最初にしたことは、世界中の儒学者を召集し、「儒教」に対する人々の信頼をどのように促進し回復するかを議論することだった。 ——「明代の歴史・儀式その一」 洪武3年(1370年)には、「中国と外国の官僚は皆、科挙によって昇進し、科挙に合格しない者は役職に就くことができない」という措置が正式に提案され、「科挙」が官僚や人材を選抜する唯一の方法であると明確に位置づけられました。 ——「明代史・選帝侯編 II」 同時に、明代の太祖は「儒教思想統治体制」の円滑な確立をさらに確実にするために、「劉基」の提案を採用し、「四書五経」を科挙の内容とし、「四書に精通しているが経文に精通していない者は、「正易」、「崇志」、「広業」などの「国子書院」の3つの館に留まるように」要求した。そして、1年半待って、「四書五経」をほぼ十分に学んだら、「秀道」や「成心」などの国子書院の2番目の館に入ることができる。 ——「明代史・選挙1」 「国子学」の古代遺跡の図解 さらに1年半後、「経文に堪能で、文理ともに優秀な者は『統治天性』殿に昇格し、『皇学院』の「点数方式」に参加できる。つまり、「1ヶ月目の試験は経文原典、2ヶ月目の試験は随筆、勅旨、紀念、内学、3ヶ月目の試験は経文第一、史学二、審判」である。 - 『明史・選1』 合格とみなされ、正式に卒業して科挙試験を受けるためには、1 年以内に 8 ポイントを取得する必要があることは明らかでした。そうでない場合は、最終的に合格するまで「教室で勉強」を続けることしかできませんでした。 ——「明代史・選挙1」 これらの多くの事例は、疑いもなく、「科挙」と『四書五経』を試験内容とする措置が、太祖朱元璋による「儒教思想統治体制」の復興を推進するための努力であったことを証明するのに十分である。 その目的は、人々の「儒教」への信頼をさらに深め、「儒教統治制度」の復興と発展を促進することです。これだけでは証拠として不十分だと思うなら、明代洪武年間の「宮廷試問」問題を見てみましょう。 明朝の科挙における官吏を選抜する最後の試験であり、また明朝皇帝自らが出題した最も重要な試験でもあったため、明朝の宮廷試験の問題は、間違いなく明朝の統治者の統治思想と明朝の将来の発展方向を最も明確に反映していると言えるでしょう。 例えば、明朝成立後初の科挙であった洪武4年(1371年)の科挙のテーマは「天を敬い民に仕え、社会倫理を明らかにして風俗を重んじた歴代皇帝の王道と統治の理念を問う」というものだった。 - 『中国第1科挙全集(明洪武~正徳期)』 漢の武帝劉徹の像の模式図 封建時代の漢の武帝・劉徹以来、「儒教」は常に封建帝国の「主流の統治思想」であった。実際の統治体制は「公は儒、私は法家」であり、法家が提唱する「法治」制度は多かれ少なかれ存在していたが、儒教が依然として支配的な地位を占めていたことは否定できない。 この試験問題の意味は明らかで、学者や庶民の心に「王権は神から授けられた」という彼の「天命」を定着させることです。科挙の結果が発表される日は、世界中の人々が注目する時です。そのため、朱元璋にとって科挙は人材選抜の必要を満たすだけでなく、「儒教」を推進する最高の機会でもあります。 例えば、洪武18年(1385年)には「問題は人を任命する方法と官吏を統治する方法である」、洪武30年(1397年)には「問題は人民を教育する方法である」とありました。その後の建文帝朱雲文の治世、つまり建文2年では、問題は明らかに「仁政を執る」方法でした。 ——『中国一級試験問題全集(明代洪武帝から正徳帝まで)』 行間には、濃厚な儒教的雰囲気が漂っている。明太祖朱元璋の意識から行動へのほぼ全面的かつ全面的な推進のもと、どうして「儒教」に対する人々の信頼を回復し、数千年にわたり受け継がれてきた「儒教的統治制度」を再現できないだろうか。 明代の科挙の図 結論 つまり、明代における儒教統治体制の復興という問題に関しては、明太子朱元璋は実は明代成立前から準備を始めていたのである。皇太子朱彪に儒教を学ばせ、儒教の書籍を収集することで、明代成立後の儒教統治体制復興に向けた「思想的」枠組みを策定することが第一歩であった。 つまり、その目的は、元代の「学者十人のうち九人は乞食」という噂ほど「儒教」を学ぶことは悪くないということを人々に感じさせること、つまり「儒教」に対する人々の信頼を築くことです。同時に、それは彼の後の「合理的かつ合法的な」王位継承への道を開いた。 ——「二十二歴史ノート、第30巻」 明朝の成立後、「思想」の恵みにより、明太子朱元璋は科挙の政治綱領を定め、「四書五経」を科挙の内容として明朝の人材や官僚を選抜し、「儒教思想統治体制」の再建を順調に開始することができた。 つまり、科挙制度によって「儒学者」の安定した「上向きのルート」が確立され、人々は「儒教」を学ぶことが有益であると感じ、官僚として朝廷に入り、政治的野心を実現できるようになりました。 明朝の統治状態の概念図漫画イラスト このように、民衆の熱心な参加により、明太祖朱元璋が「天与の」統治者としての地位を確立することは、当然のことながらもはや問題ではなくなった。彼は合理的かつ合法的に元朝を打倒し、民衆の支持を得ることができ、つまり「民心を統合」し、長年の戦争によって引き起こされた「民心の分散」の危険を防ぐことができた。彼らの優位性を強化する。 したがって、客観的に見れば、太祖朱元璋が「儒教思想による統治体制」を復興するために講じた一連の措置は、明代初期の統治地位を強固にし、人民の分裂を防ぎ、人材を選抜し、明代の発展と繁栄を促進する上で極めて積極的な意義を持ち、非常に顕著な成果を上げた。 「洪武帝」、「永楽帝の繁栄」、「仁宗・玄宗の繁栄」、「成化新風」、「洪治の維新」、「嘉靖の維新」、「隆清の新政」、「万暦の維新」など、歴史書に記された数多くの繁栄の場面。これらの繁栄の場面が次々と現れたのは、明朝が「儒教の統治制度」を推進したことと全く関係がないと言えるでしょうか? もちろんそうではありません。これらの繁栄した光景は、まさに「明王朝」が「儒教思想の統治システム」を復興した功績を真に反映したものです。 |
<<: 朱其珍はなぜ「西遊」活動をやめたのか? 「西に行く」ことのメリットとデメリットを分析!
>>: オイラト・イェセンは明朝を脅かすために朱其珍を捕らえたのに、なぜ後に釈放したのでしょうか?
推薦する
楊家の伝説第28章:焦瓚は怒りで謝金武を殺し、八王子は知恵で楊俊馬を救う
『北宋実録』(『楊将軍伝』『楊将軍物語』『楊将軍志』とも呼ばれる)は、楊家の将軍が遼に抵抗した功績を...
世界最大の恐竜の化石はどこにありますか?恐竜の化石の大きさはどれくらいですか?
恐竜映画を見るのが好きな人は多く、そのリアルな視覚効果は病みつきになります。それらはすべてジュラ紀の...
陳襄の「秋夜の山閣の恵師の贈り物に対する返事」:この詩は、始まり、展開、移行、結論が自然で穏やかです。
陳子昂(659-700、議論の余地あり)は、法名伯有で、淄州舒洪(現在の四川省)の出身であった。 唐...
南宋代奇談詩集第9巻『易軒志全文』
『易軒志』は、南宋時代の洪邁が漢文で書いた奇談集である。本のタイトルは『列子唐文』から来ている。『山...
王玉燕の母親は誰ですか?王玉燕の母、李清洛のプロフィール
李青洛は金庸の武侠小説『半神半魔』の登場人物。愛称は阿洛。李秋水と五耶子の娘。改訂版では丁春秋が養父...
作曲家シューベルトの音楽スタイルはいつ成熟したのでしょうか?
シューベルトは18世紀オーストリアで生まれたロマン派の作曲家です。有名な作曲家ベートーベンと同じ時代...
赤壁の戦いの後、黄蓋は突然姿を消したようです。どこへ行ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
古代ではなぜ荒れ地の開拓を選んだ人が少なかったのでしょうか?私にはそれを買う余裕がありません。
古代ではなぜ荒れ地の開拓を選ぶ人が少なかったのでしょうか? 根本的な理由は生産コストが高かったからで...
星堂伝第11章:二仙荘には良い友達がいて、仁丘県はBMWを失う
小説『大唐興隆』は『大隋唐』『大唐興隆全物語』とも呼ばれています。関連する古典小説には、清代乾隆年間...
東周書紀第71章:顔平忠が桃2個で3人の男を殺し、楚の平王が義理の娘と結婚し、皇太子を追い払う
『戦国志』は、明代末期の小説家馮夢龍が執筆し、清代に蔡元芳が脚色した長編歴史恋愛小説で、清代の乾隆年...
『太平広記』第18巻「十八神仙」の原文は何ですか?
劉貴順源の楊伯州と劉先生のテキスト集劉貴順隋の開皇20年、呉興の劉貴順が長江の南から巴陵に到着した。...
もし趙雲が荊州の守備を担当していたら、関羽と同じ道を辿って捕らえられていたでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
唐代の詩の名句を鑑賞する:雁が飛んでいるのを見るだけで悲しくなる
高史(704-765)、号は大夫、滄州渤海県(現在の河北省荊県)に生まれた。唐代の大臣、辺境の詩人で...
水滸伝の血まみれの元陽塔で一体何が起こったのでしょうか?武松は何をしたのですか?
「元陽楼血痕」の物語は、元代末期から明代初期にかけて史乃安が著した『水滸伝』第31章に由来しています...
『紅楼夢』で、賈おばあさんは林黛玉が何を考えているのか知っていますか?林黛玉はなぜ彼女に言わなかったのか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...