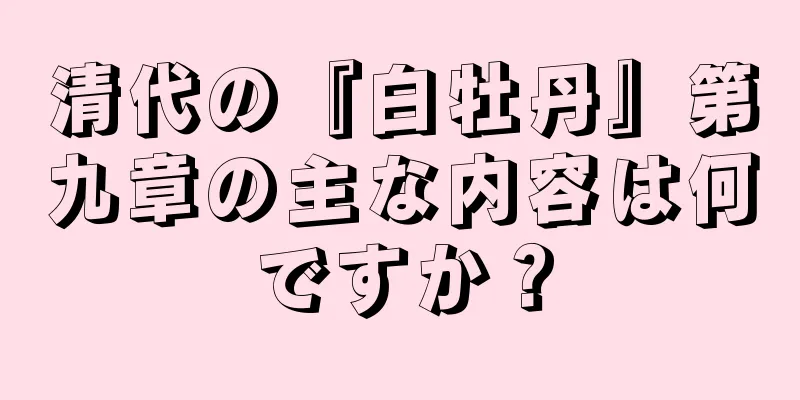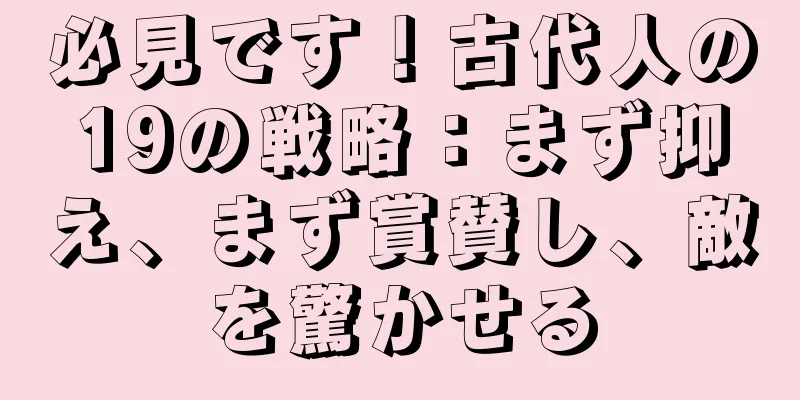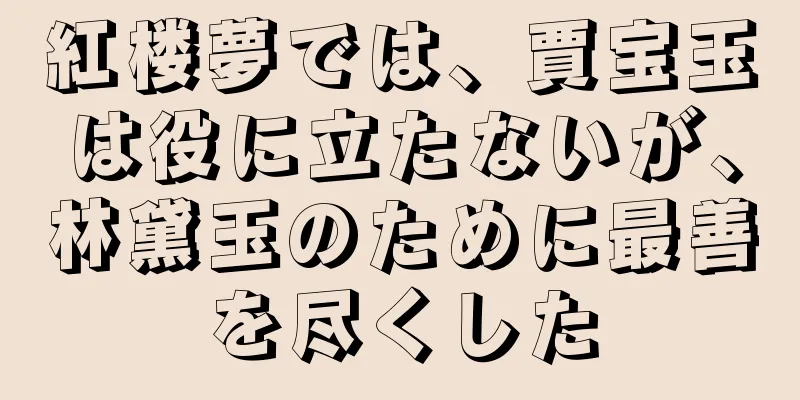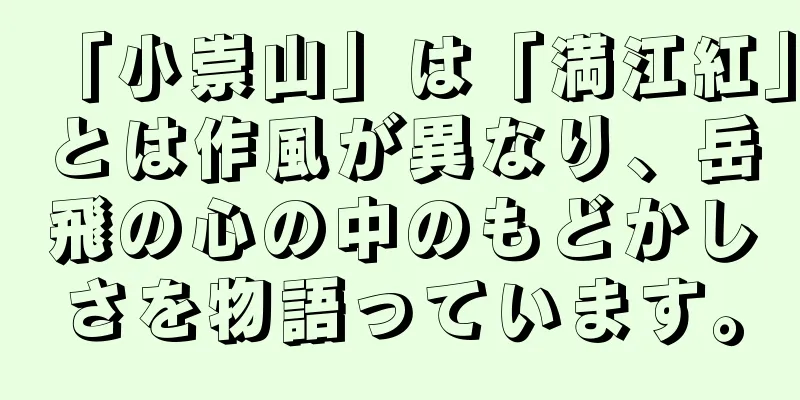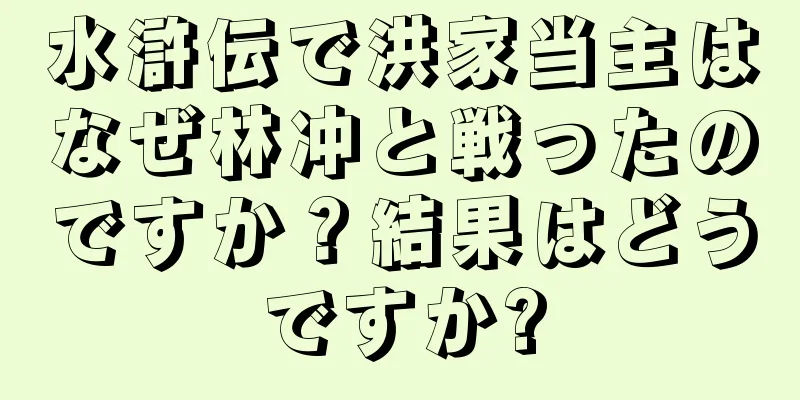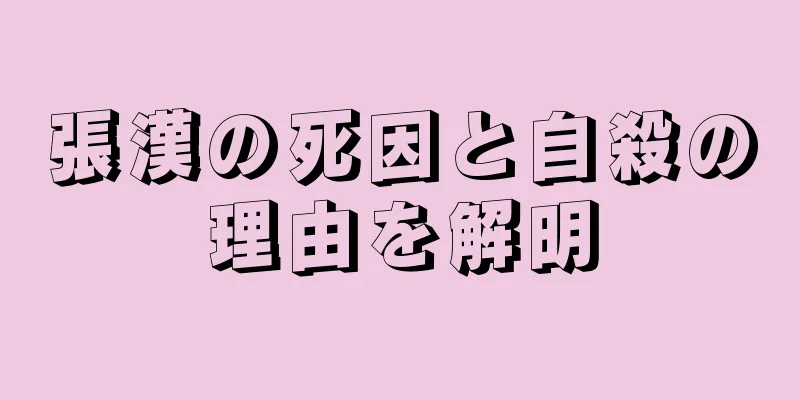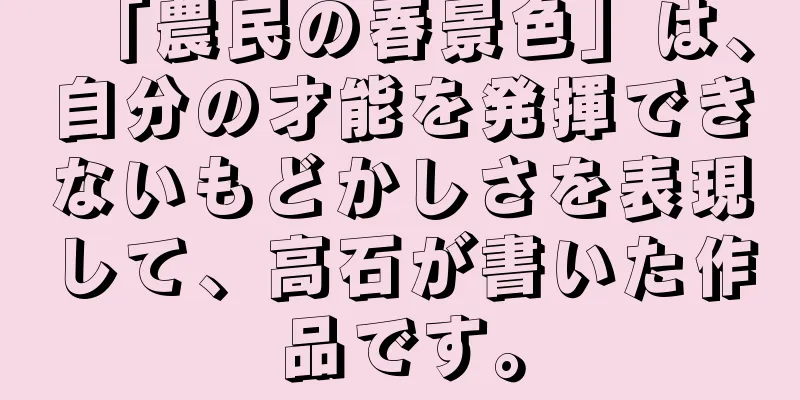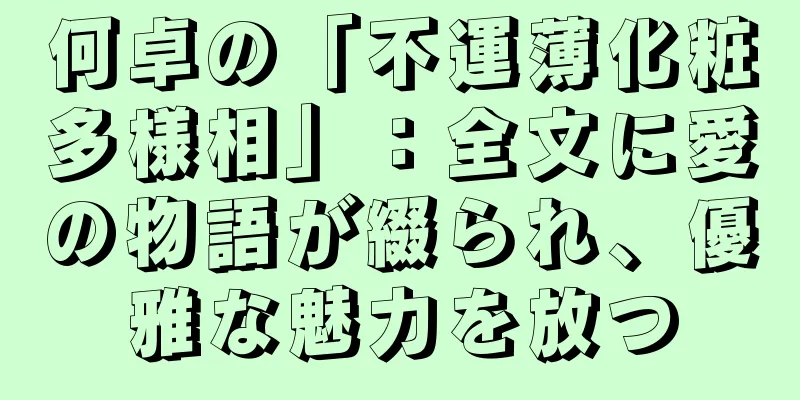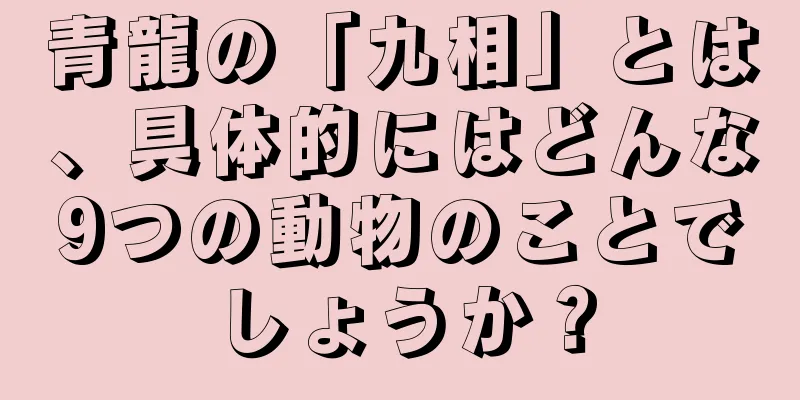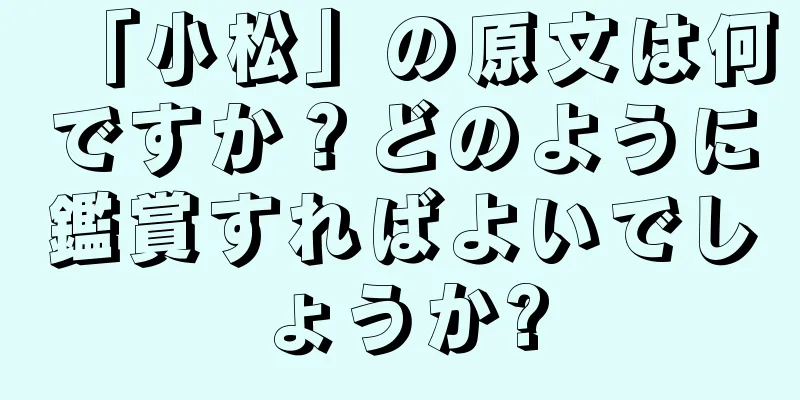東漢時代には民間の軍隊が盛んに存在していました。東漢時代にはどのような「民間の軍隊」が存在したのでしょうか。
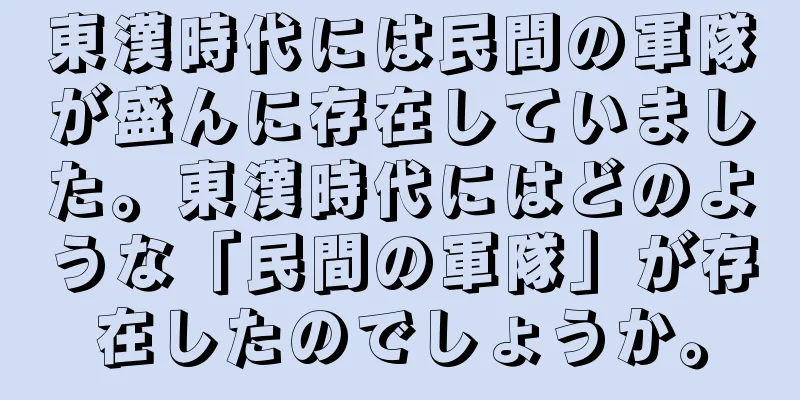
|
本日は、おもしろ歴史編集長が、東漢時代にはどのような「私兵」が存在したのかをお伝えします。皆様のお役に立てれば幸いです。 私兵は東漢時代の典型的な歴史現象であり、地主・有力者の私兵と官僚・軍閥の私兵の2種類がある。地主・有力者の私兵は官僚・軍閥の私兵よりも早く出現した。 1. 民間軍隊設立の背景 秦王朝の成立後、全国的に土地の私有制が確立されました。しかし、秦代から前漢代にかけては「土地賜与制度」がまだ存在していたため、土地のほとんどは軍事功績のある将校や貴族官僚によって所有されており、土地の所有権は比較的安定しており、土地の売買は一般的ではありませんでした。しかし、社会経済の急速な発展に伴い、土地は徐々に商品化され、土地の売買や土地の合併は社会の一般的な現象となり、土地はますます少数の人々の手に集中し、大多数の自耕農民は徐々に土地の所有権を失っていった。土地を失った農民たちは地主の土地に頼らざるを得ず、地主の小作人となるしかなかった。 大土地所有の発展とともに、土地を失った小作人と地主との間の封建的な依存関係は強化され続け、地主が従属民を武装させて独自の権力を形成する基盤が築かれました。 漢代は、中国の氏族活動と氏族構造の再構築の時代でした。自然の経済環境の中で、人々はリスクに抵抗するために、主に親戚や氏族を中心に一緒に暮らし、血縁関係を利用して地元の氏族勢力を構築しました。社会の発展に伴い、氏族人口も増加し、その経済力と社会的影響力も向上し続け、地方の有力地主が私兵を結成する条件も整った。 前漢末期には土地の併合がますます深刻になり、土地を失う農民がますます増え、地主階級と農民の間の矛盾は深まり続けました。支配者たちは極めて贅沢をし、重い税金を課し、農民を残酷に抑圧し、搾取したため、ますます多くの農民が地主階級に反抗するようになりました。この階級的矛盾は、最終的に緑の森蜂起と赤眉蜂起につながり、地主階級の傲慢さに深刻な打撃を与えました。この闘争状況下で、多くの有力地主は自らを守るために私兵を組織した。 地主階級内にも和解不可能な矛盾が存在する。地主や有力者の権力の増大は必然的に権力の集中を危険にさらすので、権力の集中は必然的に地主や有力者に打撃を与えざるを得なくなる。特に、前漢末期の王莽の改革では、土地の売買を禁止し、通貨制度を恣意的に変え、「王田制度」を実施し、地主や有力者の利益を深刻に損ないました。これらの有力地主たちは自らの利益のために軍隊を組織し、王莽を打倒する闘争に参加した。以上が東漢時代に私兵が出現した背景と理由である。 2. 東漢時代の私兵の種類 私兵は地主や軍閥が利権を争うための道具であるが、組織形態や機能、依存度などに違いがあり、氏族軍、家族軍、義勇軍などの種類に分けられる。 クラン武装 氏族軍とは、有力な地主が氏族の血縁関係を利用して設立した私兵組織である。東漢の時代は、中国の氏族組織が急速に発展した時代でした。氏族はその厳格さと安定性により、重要な社会組織となりました。藩軍の構成員は、地主に従属する土地を持たない農民ばかりではなく、藩内の自耕農民も多数含まれていた。個人的な依存関係という点では、家族兵士や志願兵よりも依存関係は弱く、主に血縁関係に基づいて組織された私兵部隊である。 時代的に見ると、藩軍は固定した武装組織ばかりではなく、ある程度の緩さを持っていた。氏族の構成員は平時には生産活動を行い、戦時には氏族長の指導と組織のもと、軍の部族組織に従って動員される。戦争が終われば、構成員は自由な身分に戻る。必ずしも強い政治目的があるわけではなく、氏族の自衛や政府の徴兵に対する抵抗が主な目的である。使用する武器は統一されておらず、各氏族構成員が自ら購入または用意する。「困ったときに集まり、困ったことがないときは解散する」という比較的緩やかな私兵組織である。 家庭兵士 近衛兵は主君に対して強い個人的な依存心を持つ一種の私兵である。 『日直録』には「それは戦国時代の武士から始まり、漢代の李陵のような荊楚の剣士も同じ類であった」とある。 東漢末期には、政治情勢が混乱し、社会矛盾が激化し、多くの有力地主が独自の兵士を抱えていた。 『三国志』には、「曹洪は太祖の従兄弟であった。洪は千人以上の家族の兵士を率いて龍康で太祖と会見した」と記されている。この記録は、当時の多くの有力地主が独自の兵士を所有し、自らの政治的目的を達成するために戦争に参加させていたことを示しています。 家臣の主な供給源は奴隷、召使、従者、客人であった。 『後漢書 鍾昌同伝』には、「裕福な人の家は数百棟の建物が連なり、肥沃な田畑が田んぼを埋め尽くし、奴隷や召使は数千人、従者は数万人に上る」と記されており、『三国志』にも、劉備の義理の兄弟である米祝が自宅に「数万人の召使や客」を抱えていたと記録されている。これら数千万人の奴隷はすべて有力な地主の家族に依存しており、彼ら自身の兵士を組織するための有利な選抜条件を提供していた。使用人から構成される「家兵」は、当時最も安価な兵力源であった。漢末期には土地が集中し、小農が次々と破産し、社会には失業者の浮浪者が大量に存在した。こうした浮浪者はしばしば採用されます。 地主や豪族の兵士たちは、普段は生産活動に従事し、軍事訓練も受け、戦争時には「部隊」として戦った。 「ブク」はもともと軍事組織単位であり、ブク組織に従って家族兵士を組織することは、軍事訓練と戦闘効率の向上に役立ちました。軍閥の私兵は主に徴兵制度を通じて採用された。 後漢末期には兵士の募集が軍隊を集める主な方法であった。当時、袁紹や曹操などの多くの軍閥が兵士を募集していました。 当時、東漢の中央権力は弱まり、州知事や地方知事の権力が強まったため、中央政府は地方に対する統制力を失っていました。地方の軍閥はしばしば国軍を私兵化して軍事力を拡大し、一方を支配しました。 吉継 易宗は、東漢時代に朝廷に服従した少数民族に与えられた名称であり、特に胡族や羌族などの少数民族の健常者で構成された軍隊を指す言葉でもあった。軍閥に従って自ら進んで軍隊に入った者も「義臣」と呼ばれる。 「易宗」は強力な軍閥の一族でもなければ、その小作人でもなかった。彼らは、ある程度の自発性と自発性を持った私兵であった。これらの人々は、少数民族地域から逃げてきた胡人か、あるいは、わずかな恩恵で有力な軍閥に取り込まれ、喜んでこれらの有力な軍閥に仕えるようになった若者や中年の人々であった。彼らは生産活動には従事しないが、主人に対して強い個人的な依存心を持ち、特定の有力な軍閥に従属する特別な私兵集団である。 富裕層の勢力拡大に伴い、上記私兵組織の境界はますます曖昧になり、私兵組織は形式化、部族化へと発展を続け、最終的にはプロの私兵組織を形成した。 東漢末期には、数百、数千の私兵を所有する地主が多くいたが、有力な軍閥に比べると力も規模も小さく、結局は有力な軍閥に飲み込まれてしまった。併合後、これらの私兵はもはや元の主人の私兵ではなく、強力な軍閥の配下となった。ブクゥは次第に、強力な軍閥の私兵部隊の代名詞となっていった。 III. 民間軍隊と国軍の関係 東漢は徴兵制度を導入した。東漢初期には、小作農も国家の税金と賦役を負担しなければならなかったため、兵士の供給は比較的十分であった。しかし、有力な一族が自分たちに依存していた小作農に対する支配力を強めるにつれ、小作農は自分たちの既得権益を守るために政府の労働に非常に抵抗するようになった。彼らにとって、自分たちを頼りにする小作農は、政府の統制から自由な私有財産であり、私有地主であった。これらの有力者たちは、政府の徴兵に強く抵抗し、反対した。 先に述べたように、権力者が私兵を組織する目的の一つは、政府の徴兵制度に抵抗することであった。実際、こうした対立は後漢末期には非常に一般的であった。権力者の抵抗により、政府の兵力はますます不足し、大量の犯罪者や少数民族の兵士しか使えなくなった。これが後漢末期の民間武装勢力と国軍の増減関係であった。 国軍の機能は国家体制を守ることであり、一方、民間の軍隊は主人の利益を守るためであり、両者の間には和解不可能な矛盾があることは周知の事実です。しかし、多くの場合、支配階級内部のこの内部矛盾は主要な矛盾ではありません。農民蜂起を鎮圧する際、国家軍と民間武装勢力は実際には協力的かつ補完的な関係にあります。 後漢末期の黄巾の乱は大規模なものであり、後漢の統治に極めて深刻な打撃を与えた。黄巾の乱は朝廷の統治を危険にさらしただけでなく、大多数の有力者の利益にも脅威を与えた。したがって、双方は対立を脇に置き、統一戦線を形成し、主な矛盾である農民反乱を鎮圧することができる。 国軍と有力軍閥の私兵組織との間の変革の可能性もある。東漢中期以降、大規模な私有地所有が発達し、有力地主が社会の強力な勢力となったため、政府は彼らを全面的に抑制することができなくなり、寛容と協力の態度しかとれなくなった。特に後漢末期には、皇帝の親族や宦官による独裁が交代し、中央の権力は絶えず弱体化し、政府は崩壊しつつありました。政権を存続させるために、政府は軍閥の私兵に頼って統治秩序を維持しなければなりませんでした。これら軍閥の傘下にある私兵は国家軍としての性格を持ち、政権維持のための重要な手段となっている。 IV. 民間兵器の歴史への影響 東漢の地方政権が樹立されると、地方の有力な氏族に大きく依存するようになり、多くの氏族の指導者が地方官の主補佐や補佐官に任命された。しかし、この頃はまだ東漢の中央権力は弱まっておらず、これらの豪族をある程度統制することができた。しかし、桓帝と霊帝の時代以降、地方に州知事が置かれるようになり、地方の軍閥や有力者の権力がさらに拡大し、中央の権力は弱体化の一途をたどった。地方知事や州知事も地元の有力者と結託して、強力な軍事力を持つ軍閥集団を形成した。 後漢末期の名将、袁紹は早くから私兵を組織していた。「当時、多くの英雄が袁紹に加わり、国や郡が興り、すべて袁家の名を冠していた。」袁紹が4つの州を占領し、強力な軍閥集団となったのは、地方の有力者たちの武力を味方につけたからである。曹操の権力の台頭は、有力地主たちの私兵力と切り離せないものであった。曹操が軍隊を立ち上げたとき、曹洪、陸謙、許褚らが1000人以上の私兵と合流した。曹操はこれらの私兵の力で最終的に北方を統一した。 後漢末期から三国時代にかけて、軍閥は分割され、各軍閥は独自の私兵を有していました。分離独立の過程で、地方の軍閥は私兵を擁する有力地主を積極的に誘致し、これらの有力地主も軍閥の保護を必要としていたため、両者は意気投合した。このような協力により、地方の分裂と軍閥間の抗争の状況がさらに拡大し、中央権力がさらに弱体化し、最終的に東漢の滅亡につながった。 「一等兵」は後の「世襲制軍事制度」の起源となった。固定された軍人としての身分を持つ独立した世襲の軍家は、実際には東漢末期の私兵から始まった。 西暦220年に曹魏が漢王朝に取って代わって東漢王朝が滅亡したことから、魏、蜀、呉の3つの分離政権が形成されました。これら3つの家の前身は、私兵と家臣を頼りに政権を確立した3つの大規模な軍閥グループでした。その後、これらの一等兵の身分は変わり、彼らは国の正規軍となった。しかし、彼らは元の主人に対する個人的な依存から一気に脱却したわけではありません。 実際、三国時代初期には多くの将軍が自らの軍隊を指揮していました。この「本部部隊」は、実は彼らの私兵である。 『三国志』の記録によると、曹魏の将軍李典には3,000人以上の部下がおり、蜀の将軍孟達には4,000人以上の部下がいた。これらの部下は基本的に父から息子へと継承され、それぞれの主君に依存していた。彼らには兵役期間の制限はなく、国軍に編入された後は歴史上に登場したことのない「終身兵士」となる。元の主人に対する個人的な依存を断ち切ったにもかかわらず、「代々兵士として仕える」という特徴は依然として保持されていました。 このため、曹魏は貴族の家が私兵を管理する方法を利用して国軍を管理する「士家制度」を実施し、この点で最も顕著であったのは東呉であった。東呉では、常に世襲制の軍事指導体制が敷かれていた。将軍が亡くなった後、その指揮下にある軍は息子が率いることになった。これは東呉の成熟した制度であった。東呉の「世襲軍制」は、兵士の家族が軍隊に従うことを認めるという独創的な措置も考案し、後の世襲軍家の出現に確固たる基盤を築いた。 V. 結論 東漢時代は、封建的地主経済が完全に確立された時代であり、また地主経済が完成に向かっていた時代でもありました。彼らは新興の封建領主階級として、非常に短期間で歴史の舞台の中心に登場し、必然的にそれまでに存在しなかった多くの矛盾を生み出しました。これらの矛盾には、地主階級と農民階級の間の矛盾、および地主階級と中央政府の間の矛盾が含まれます。地主や権力者は、より大きな利益を得るために、軍隊を統制し、暴力を使ってより大きな権力を争わなければならない。これが民間軍隊が出現する根本的な理由である。 東漢中期に形成され始めた地主の私兵は、地主経済の発展とともに発展し、東漢の中央集権を弱め、地方と中央の間に遠心力を生み出し、魏晋の貴族の台頭につながった。この頃から、軍の世襲制が形を整え、徐々に成熟していった。兵士の専門化と世襲制、兵士の家族の駐屯地への集中居住も、兵士の安定した供給源を確保し、軍に対する統制を強化するのに役立った。世襲制の軍事制度は、東漢の並行する募集・徴兵制度の重要な改革であり、徐々に前者に取って代わり、新たな戦闘力となっていった。 |
<<: 清朝の衛兵はどのように選ばれたのでしょうか?なぜ皇帝は護衛兵に暗殺されることを恐れなかったのでしょうか?
>>: 清朝は中国の発展にどのような影響を与えましたか?なぜ「清朝が国を滅ぼした」と言われるのでしょうか?
推薦する
「扶瑪」はもともと「扶瑪」を意味し、南北朝以前は副馬車の責任者であった。
もともと「太子妃」は王女の夫でもなければ、皇帝の婿でもありませんでした。漢の武帝の時代には、副馬車の...
林相如はかつて首相を務めたことがありますか?将軍や首相と調和するというのはどういう意味ですか?
有名な伝統京劇に「将軍と宰相の和解」というものがあります。ここでの「将軍」は連攫を指し、「宰相」は当...
誓い合った兄弟愛から心のこもった友情まで:古代の17種類の美しい友情
友情は人間が持つ最も美しい感情の一つです。古代には美しい友情が17種類ありました。あなたにはいくつあ...
唐代の劉蘭田に捧げられた詩をどのように鑑賞すればよいでしょうか?王維はどのような感情を表現したのでしょうか?
劉藍田(唐代)王維については、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しているので、見てみましょう!犬がフ...
漢代の服装:漢代の柳仙スカートはどのようなものだったのでしょうか?柳仙スカートの写真
漢王朝では、女性はズボンではなくスカートを履いていました。その中で最も有名なのは柳仙スカートです。柳...
小李飛道の名人トップ6のランキング:荊無明はリストに載っていなかったが、リストに載っている誰かによって一撃で殺された
6番目は、驚異的な仙女楊厳。楊厳は優れた隠し武器の達人です。一対の毒流星矢は稲妻のように速く、彼女の...
古代の詩から名前を抽出!素敵で詩的な女の子の名前のセレクション!
今日は、Interesting History の編集者が、美しく詩的な女の子の名前をいくつかご紹介...
「夜の旅に思いを綴る」を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
【オリジナル】穏やかな風が吹く岸辺の薄い草、夜にマストが危険にさらされている船。星は広大な平原の上に...
呉起の改革は楚の国の歴史的流れにどれほど大きな影響を与えたのでしょうか?
紀元前480年代の呉起の改革は、楚の歴史における大きな政治的出来事であり、楚の歴史の進路に大きな影響...
袁梅のビジネス感覚はどれほど優れているのでしょうか?彼は清朝最高の商業宣伝の達人だった
袁梅は清朝最高の商業宣伝の専門家とみなされる。彼は段階的に事業を計画した。まず、多額の資金を投じて隋...
【梁州慈】原文注釈・コメント、著者薛鋒
「梁州慈」は、西暦851年に薛鋒が書いた七字の四行詩です。この詩は、祖国の軍隊が失われた領土を回復し...
結局、喬潔は売却されたのでしょうか?なぜ賈憐は気にしないのか?
タイトル: 『紅楼夢』で賈廉が喬潔が売られたことを気にしなかった理由 - 歴史的背景の解釈段落1: ...
水滸伝に登場する108人の英雄のうち、裏切り者は誰ですか?結末は?
四大古典の一つ『水滸伝』には108人の英雄が登場しますが、その中でも最も古典的なのは10人です。以下...
『紅楼夢』における大観園の捜索と押収の影響はどれほど大きかったのでしょうか?勝者は誰でしょうか?
大観園の探索は、賈一族の繁栄から衰退の過程における重要な節目として一般的に認識されています。ご存知で...
王山宝が大観園を捜索することを提案したとき、なぜ事前に嗣斉に知らせなかったのか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...