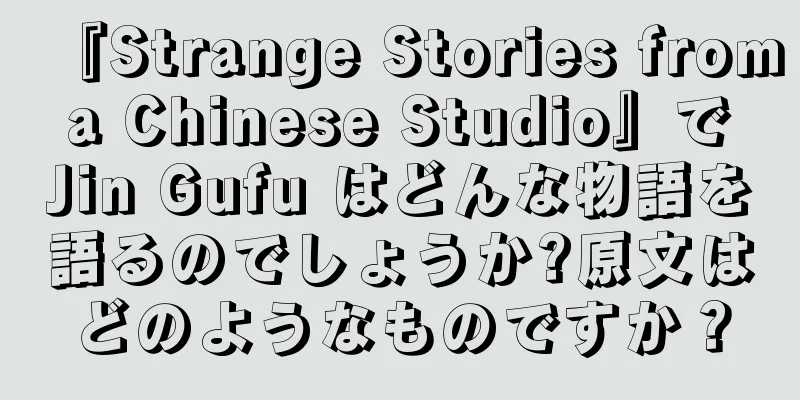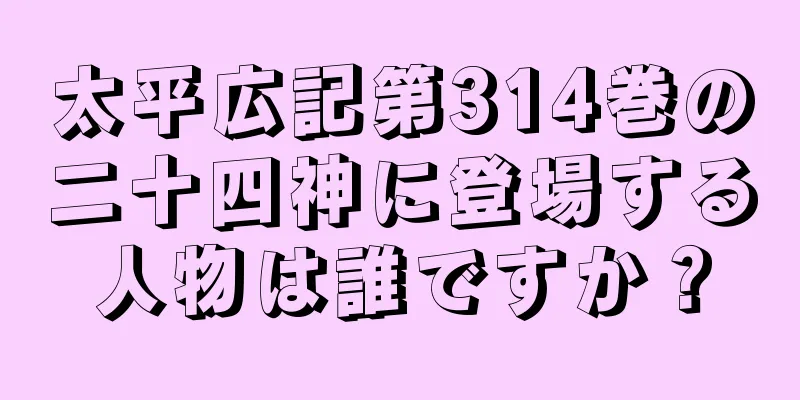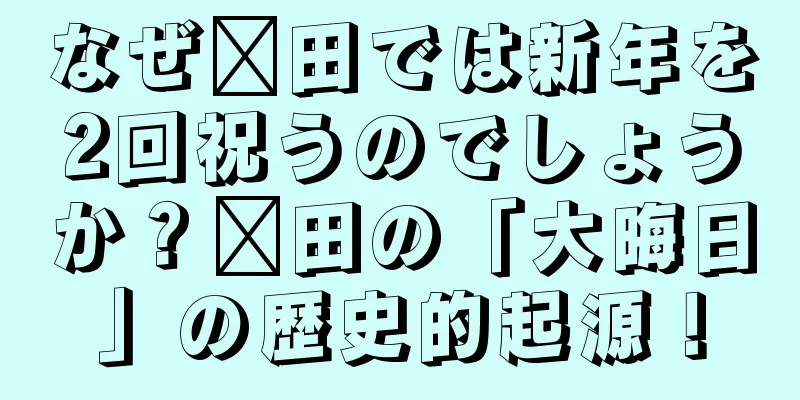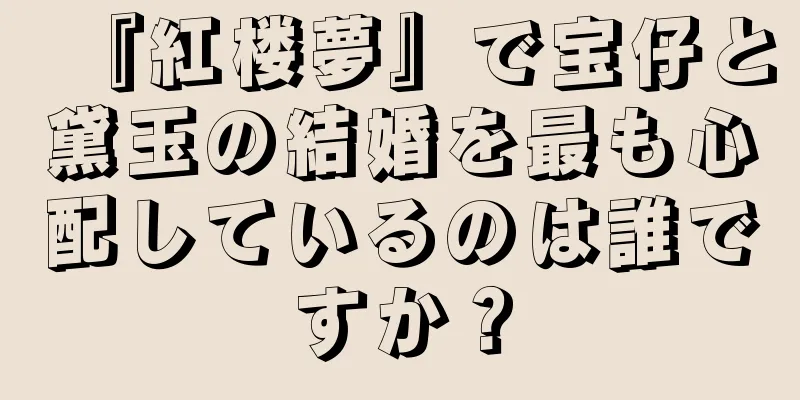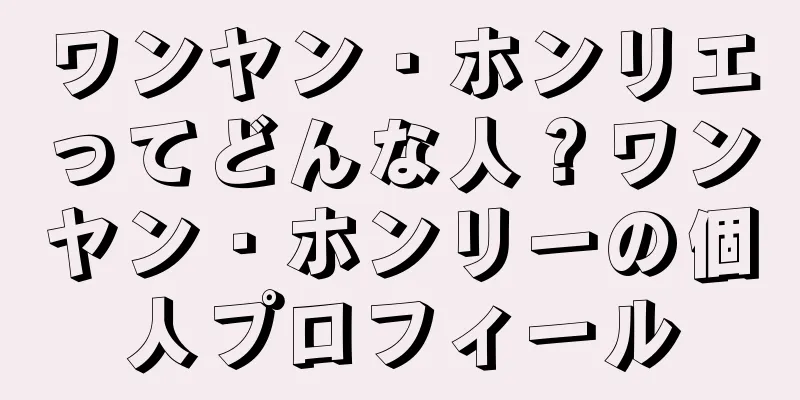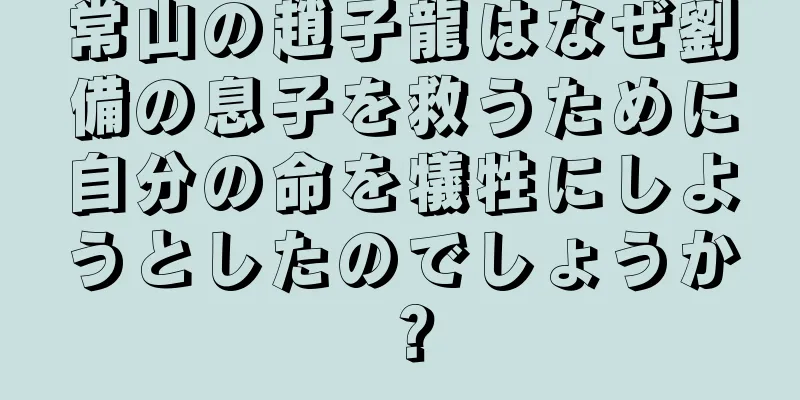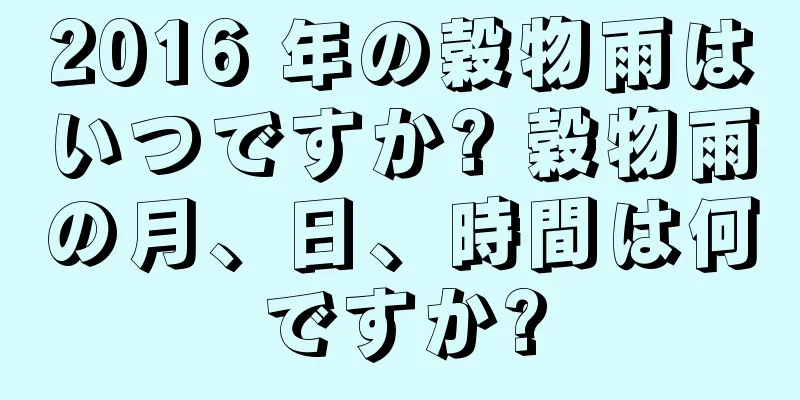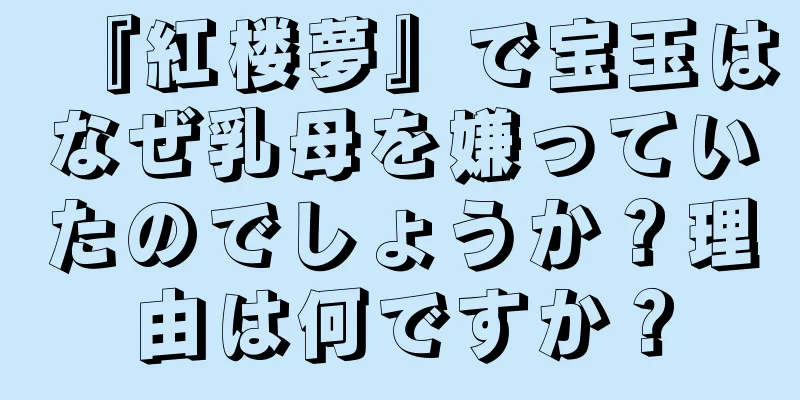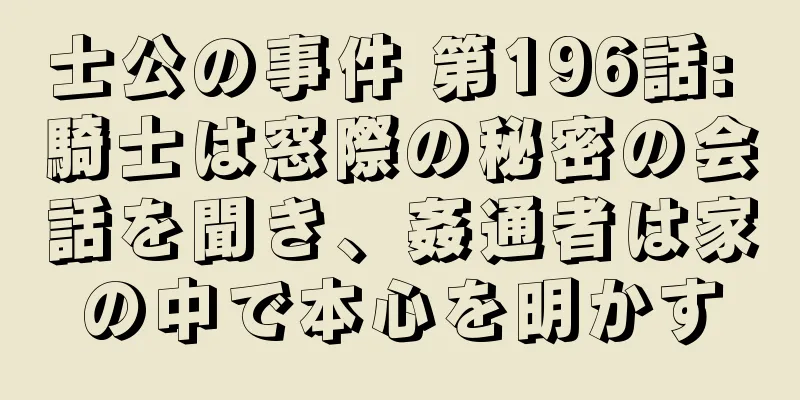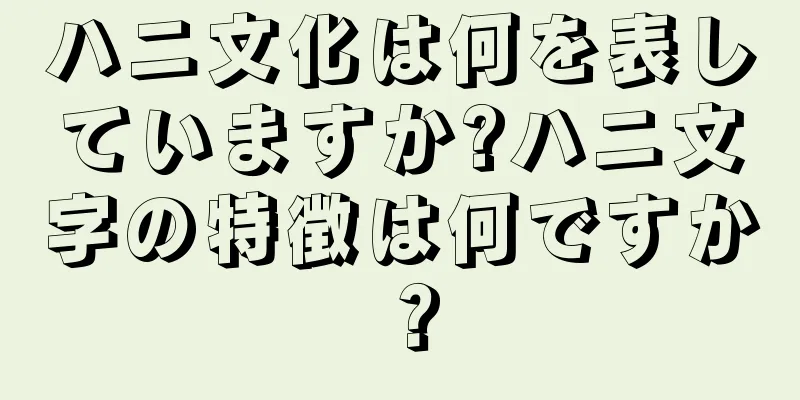トゥムの戦いにおけるオイラートと明王朝の目的は何でしたか?結局、どちらの側も幸せにはなれません!
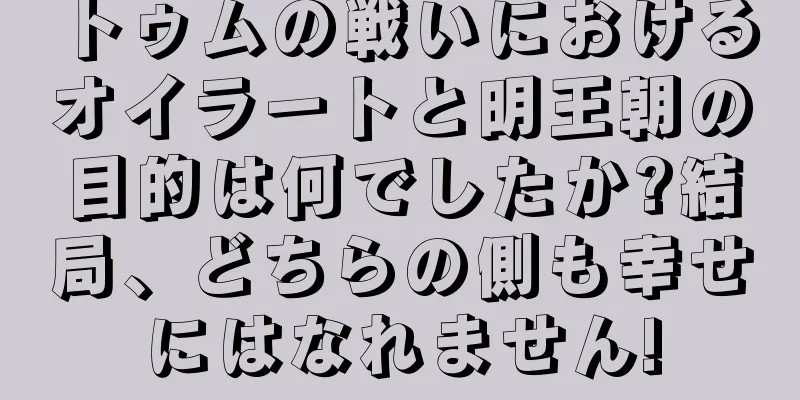
|
本日、Interesting History の編集者は、オイラトと明王朝の両方が大きな損失を被ったトゥムの戦いについてお伝えします。ご興味のある読者は、編集者をフォローしてご覧ください。 トゥムの戦いにおける二人の敵、オイラトと明朝は、気力と生命力に満ちた若者と、生まれたばかりの子牛のように恐れを知らない少年でした。これは中年の男と少年の正面衝突であり、明の若き皇帝英宗は血まみれになるまで殴打された。しかし、中年のイェセン大師は一瞬だけ大笑いしただけで、すぐに北京の戦いで悲惨な敗北を喫した。 この戦争の原因は金銭なので、生死に関わる問題とは程遠い。だから、戦争が終わっても、明王朝は依然として明王朝であり、オイラートは依然としてオイラートのままだったのです。しかし、戦いがあまりにも残酷だったため、オイラートと明王朝の双方が負ける結果となった。彼らは互いに戦っていたが、どちらが勝つかは分からないものの、両者とも間違いなく敗北した。 01. トゥムの戦いの敵対者2人:オイラトとミン オイラートを説明するには、まず元代以降の草原について話さなければなりません。結局、元朝とモンゴルが中原を支配していた。彼らは中原を変え、中原も彼らを変えた。最も大きな変化は、モンゴルの草原に住む部族が法的正当性を感じ始めたことだ。簡単に言えば、誰が草原の大ハーンになるかについては合意があったということです。元朝以降、草原帝国の大ハーンは黄金一族しかあり得なかった。他の部族の支部については考えないでください。しかし、ゴールデンファミリーは結局人数が少なく、その後に英雄が出てくることもあまりありませんでした。そのため、他のモンゴル支部もさらに大きく成長する必要がありました。 自らをウェイウエルと称したオイラート人は、広い意味ではモンゴル人の一派であった。したがって、オイラートはモンゴルの支族とさえみなすことはできません。しかし、それはさらに大きく強くなり、草原帝国を築きました。しかし、オイラートのリーダーであるイェセンは、大ハーンや草原の皇帝と呼ばれることはできなかった。大ハーンや皇帝は黄金一族からしか生まれなかったからだ。そのため、イェセンはオイラト帝国の大教師であったが、実際には最高指導者であった。イェセンは野心家で戦略に富んでいた。彼は北方の草原を統一しただけでなく、北東部の女真族も征服した。したがって、オイラートの時代の草原帝国は、その発展の絶頂期にあった。 明王朝が最初に建国されたとき、その軍事的功績は傑出していたと考えられていました。しかし、第6代皇帝英宗朱祁鎮の時代には、明朝の軍事的功績は目立ったものはありませんでした。自慢したくても、自慢できるようなことは何もない。 1427年に交趾が反乱を起こし、明朝は交趾を放棄したため、それまで14あった省級行政委員会は13に削減され、こうして十三省が誕生した。 1439年から1448年にかけて、明朝は雲南省洛川の玄威族の首長である司仁法とその息子の司継法の反乱を鎮圧するために4回の遠征を行った。我々は勝利したが、それはピュロスの勝利であり、国の力は無駄になった。三楊内閣時代、明代の官僚制度は非常に強力でした。その理由は、楊容、楊普、楊世奇という3人の代表的な学者官僚が永楽、洪熙、宣徳、正統の各朝に仕えたからである。十分な時間と、十分な弟子たち、そして十分に強いコネクションがあれば、公務員制度は飛躍的に成長するでしょう。 1449年、明朝の23歳の英宗皇帝朱其真が権力を握り、すぐに大宦官の王震を朝廷の統治者に任命しました。朱其珍の目的は、もちろん、急激に拡大する官僚制度を抑制することであった。官僚制度は絶対に反抗しないし、理屈で言えば天皇を支える絶対的な柱だ。しかし、人々はしばしば感情、直感、感情に基づいて行動します。あなた方官僚はあまりにも権力が強いので、皇帝である私は隅に隠れることしかできないのです。そのため、明代の英宗皇帝は皇帝の権威を示すために宦官を利用しなければなりませんでした。しかし、皇帝が権威を確立したいのであれば、権力を掌握するだけでは不十分で、驚くべき武術のスキルも必要です。したがって、この若く精力的な皇帝は、戦争を通じて騒動を起こさなければなりません。 一つは野心的なオイラト、もう一つは若く英雄的な明王朝。この二つの敵対者の間には必ず衝突が起こります。しかし、この火事は本当に大きすぎます。 02. トゥムの戦いの2つの目的:金銭を得ることと軍事力を誇示すること トゥムの戦いの原因は金銭問題だった。 タイ・シ・イェセンはオイラートを統治していたが、それでも明王朝に貢物を納めなければならなかった。貢物や敬意を払うことは二次的なものであり、貢物と貿易が主要なものでした。その理由は、中原と草原の間の文明の格差にあります。草原では鉄鍋さえも贅沢品であり、草原の騎兵がいかに猛々しくても、明朝の前では頭を下げることしかできない。オイラート人は、明朝の宮廷からさまざまな褒賞を得るために、軍馬を貢馬と呼んで利用したいと考えていました。 毎年冬になると、オイラートは使節を派遣して明朝に馬を貢ぎました。当初、使節の数は50人ほどで、明朝は使節の数に応じて褒美を与えていました。明朝の観点からすれば、これはワラの降伏であったが、ワラの観点からすれば、一方は政治に関するものであり、他方は金銭に関するものであったため、これは有利な取引であった。そのため、利益志向のオイラト・モンゴル人は、貢物の規模を50人から2000人以上に拡大するためにあらゆる手段を講じたに違いありません。さらに、貢物は多く支払われるほど良いとされていました。ワラは可能な限り毎日貢物を支払いました。明朝もオイラートの目的を知っていたが、政治意識の高い明朝はそれに目をつぶらざるを得なかった。なぜなら、金が鍵ではなく、政治が中心であり、国境地帯の安定を維持することが何よりも重要だったからだ。 しかし、明朝の英宗皇帝が権力を握ると、この状況はもはや機能しなくなりました。若い皇帝は見て見ぬふりをするつもりはなかった。その年の2月、オイラートは再び貢物を送った。実際の人数は2,000人以上だったが、オイラートは3,000人であると虚偽の主張をした。宦官の王震は新任の官吏であり、就任直後にやるべきことが3つあった。当然、彼はオイラトが主君である皇帝を露骨に騙すことを許さなかった。そのため、この朝貢の際、明朝は黙っていることを拒み、実際の人数に応じて褒賞を与え、馬の価格を5分の4にまで引き下げました。 これがトゥム事件の背景と原因です。明朝は混乱しておらず、オイラートには儲けるお金がなかった。明朝は非常に強く、オイラートはさらに強かった。そうなると、明王朝とオイラート・モンゴルは戦争をせざるを得なくなる。こうしてトゥムの戦いが起こった。 トゥムの戦いで、オイラト・モンゴル軍は明朝の精鋭兵士20万人以上と高官50人以上を殺害し、明朝の英宗皇帝を捕らえて北京に向かって進軍した。結果は深刻です。しかし、上記の背景から判断すると、オイラートも明王朝も互いに殺し合うことを望んでいなかった。 まず第一に、オイラト・モンゴルの目的は金を得ることでした。 確かにタイ・シ・イェセンはチンギス・ハーンとモンゴル帝国を尊敬していたが、それは単なる感情に過ぎなかった。強力なリーダーとしての彼の合理的な分析は、それが不可能であることを告げていた。理由の 1 つは、モンゴルの部族が太師である彼よりも黄金一族に忠誠を誓っていたため、草原を統合する必要があったことです。もう 1 つの理由は、明王朝が非常に強力で、人口が多く、資金が豊富で、領土が広大だったため、イェセンはそれを飲み込む気がまったくなかったことです。さらにもう 1 つの理由は、変化が速すぎたことです。年初には敬意と貢物を捧げていたのに、年末には北京に挑戦しようとしていました。イェセンは心の準備がまったくできていませんでした。 したがって、イェセンにとっての最優先事項はお金でした。彼にはお金が必要だったのです。明の皇帝を捕らえた後、彼は明帝国が手を振っているのを見ず、代わりに明の銀が手を振っているのを見ました。そのため、イェセンは明の英宗皇帝を人質に取り、必死になって明朝に身代金を要求した。 2つ目は、朱其珍の目的、つまり自分の力を誇示することです。 彼は一度も戦争に参加したことはなかったが、戦争に参加することを主張し、最も手強い敵であるオイラートと戦いたいと考えていた。宮廷の役人たちは次々と反対したが、若い皇帝は頑固で無関心だった。 それを扇動したのは宦官の王震だけだったのでしょうか?主たる者と従属者の関係を明確にしなければなりません。宦官は皇帝の奴隷であり、彼らの個人的な奴隷であり、皇帝が主人でした。皇帝が間違いを犯した場合、大臣は皇帝を批判できるが、宦官は批判できない。たとえ皇帝が間違っていたとしても、皇帝は命令を実行しなければならない。これが奴隷と臣民の違いです。したがって、朱其珍が戦争を望んだからこそ、宦官の王震が火に油を注いだのである。 では、なぜ朱其珍は戦いたかったのでしょうか? 三楊の後、明朝の官僚制度は急速に発展し、すでに宮廷から宮殿へと拡大していました。当時、明朝の皇帝には立つ場所がなかった。若い皇帝は、生まれつき衝動的なホルモンに支配されていますが、合理的な分析もできます。朱其珍は、自分の権威を確立し、大勝利を収めて、自分がどんな皇帝であるかを宮廷の役人たちに示したいと考えていました。そのため、自ら軍を率いた朱其珍は、戦場で自分の武勇を誇示するために観衆を必要としていたため、朝廷の半分の者を連れて行った。 したがって、朱其珍の目的は草原で自らの力を誇示し、皇帝の権威を強化することであった。明の皇帝はオイラート・モンゴルや草原に対して何もするつもりはなかった。彼らを打ち負かして降伏させれば、我々は貢物と交換を続けるだろう。明朝が政治を欲しければ、オイラートは貢物を納めるだろうし、オイラートが銀を欲しければ、明朝は金を与えれば、両国の外交関係は非常に緊密になるだろう。 03. トゥムの戦いと同じ結末:シギとハマグリの戦い トゥムの戦いの後は北京防衛戦が続き、オイラト・モンゴル軍は資金獲得に失敗しただけでなく、中原の大砲の威力を痛感した。そのため、それ以降、彼らはモンゴルの草原に隠れて自らの力を誇示することしかできなくなりました。 元朝が中原に侵入した後、草原帝国は法的正当性に関する合意を確立しました。しかし、草原の根底にある論理は、強い者がルールを作るというものです。支配的なリーダー、戦いに勝てる者、そしてより多くを略奪できる者が最終決定権を持ちます。北京防衛戦ではオイラートが大きな損失を被り、草原の英雄的指導者イェセンは頭を下げるしかなかった。 草原のすべての部族の支持を完全に得るためには、まず戦場で武勇を身につけ、その後、自身の威信を頼りに黄金家の正当性に関する総意を覆し、最終的にそれを置き換える必要があります。しかし、トゥムの戦いと北京の戦いの後、明朝とオイラート・モンゴルは完全に敵対するようになりました。一見和解したように見えても、あなたは私を警戒し、私もあなたを警戒していました。英雄的なリーダーであるイェセンにとって、他の何かをすることは難しいだろう。 1453年、イェセンは黄金家の代宗ハーンとトクトブカを破り、「大元の天聖大ハーン」を名乗り、「天元」という君主号を確立した。しかし、イェセンはそれほどの威信を持っていなかったため、すぐに様々な部族の反乱や部下による暗殺に遭遇し、その後イェセンのオイラト帝国は分裂した。 トゥムの戦いの後、明代に再びブルッヘの戦いが勃発し、明の英宗皇帝が復位した。 20万人の精鋭部隊の損失と朝廷の浮き沈みの連続により、明王朝は深刻な打撃を受けたに違いありません。 土木の戦いでは、荊南の乱の老臣たちが多数戦死した。宮廷にはこの貴族の力が欠けていた。しかし、非合法に権力を握り、不名誉な経歴を持つ明朝の英宗皇帝朱其真と官僚制度との間の疑惑はますます深刻になっていった。こうして宦官勢力は急速な成長の春を迎えた。明朝の権力構造は、皇帝、宦官、大臣の間での地主争いでした。簡単に言えば、皇帝と宦官が力を合わせて大臣と戦ったのです。君主と臣民の関係が非常に疑わしく、権力構造が非常に混乱していたため、明帝国は衰退を止めることができませんでした。 したがって、トゥムの戦いの結果は、明王朝とオイラート・モンゴルが互いに戦うこととなり、結果は同じ負け負けの状況となった。 |
<<: 昔は、このようなものがあれば、まず実行して後で報告することができました。 「皇剣」以外に何を知っていますか?
>>: 朱元璋は元代末期から明代初期にかけてモンゴル人に対してどのように接したのでしょうか? 「ソフト政策」をどう実施するか?
推薦する
起源を遡ってみると、「武林」という言葉はどこから来たのでしょうか?
今、武術小説を読むと、本の中によく出てくる「武術の達人」「武術の指導者」「武術会議」「武術界の有名人...
『紅楼夢』の子娟とは誰ですか?彼女は師匠の林黛玉に対してどう思っているのでしょうか?
『紅楼夢』には多くの女性キャラクターが登場し、女性だけでなく、数え切れないほど多くのメイドも登場しま...
諸葛亮はどのようにして自ら軍隊を率いて戦い、最終的に南部の反乱を鎮圧したのでしょうか?
東漢末期、全国各地の英雄たちが立ち上がり、3つの非常に強力な勢力を形成しました。東漢の滅亡後、これら...
特殊な形のクルミブレスレットの価格はいくらですか?特殊な形のクルミの選び方は?
変わった形のクルミにとても興味がある人のために、Interesting History の編集者が詳...
南北朝時代は並列散文の全盛期でした。その主な特徴は何ですか?
並列散文は後漢時代に始まり、南北朝時代に形成され、普及した文体です。 4文字と6文字を交互に使用する...
『紅楼夢』では、劉香蓮は幽三姐に騙された愚か者です。なぜそう言うのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
嘉靖帝の長女である長安公主と長安公主の母である曹端妃公主の簡単な紹介
長安公主(1536年-1549年)は、本名を朱寿安[1]といい、明代の公主であり、明代の世宗皇帝の長...
なぜ王希峰は、下品な老婆である劉老婆に娘の名前をつけさせたのでしょうか?
王希峰の物語は好きですか?今日は、興味深い歴史の編集者が詳しく説明します〜本当に「二狗子」のような名...
李米順の『十種花道風景』には早咲きの梅に対する無限の賛美が込められている。
李米淳(1085-1153)、字は思志、別名は雲熙翁、雲熙居士、普賢居士など。祖先の故郷は福建省連江...
『南京郷愁』の執筆背景を教えてください。これをどう理解すべきでしょうか?
金陵の過去への郷愁劉玉熙鄴城島の潮は満ち、正魯閣に太陽が沈んでいます。蔡州の新草は青く、幕府の古い煙...
麗陽公主は誰の娘ですか?溧陽の英江公主はどのようにして亡くなったのでしょうか?
ドラマ「秦の始皇帝」の衣装を着た麗陽公主は、秦の恵文王英思の従妹である英江です。歴史上麗陽公主という...
鍾離梅と韓信:韓信の死は正当だったのか、不当だったのか?
韓信(?~紀元前196年)は秦漢時代の有名な軍事戦略家であった。韓信はもともと項羽の配下の将軍であっ...
諺にもあるように、「皇帝に仕えることは虎に仕えるようなものだ」。なぜ、高名な大臣である張廷宇の財産は乾隆帝に没収されたのでしょうか?
諺にもあるように、「王様と一緒に暮らすのは虎と一緒に暮らすようなものだ」。乾隆15年(1750年)8...
「旧友の農場を訪ねて」をどのように理解すべきでしょうか?創作の背景は何ですか?
旧友の村を通り過ぎる孟浩然(唐代)昔の友人が鶏肉とご飯を用意して、私を彼の農場に招待してくれました。...
諸葛亮の北伐の際、張郃と魏延のどちらがより強かったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...