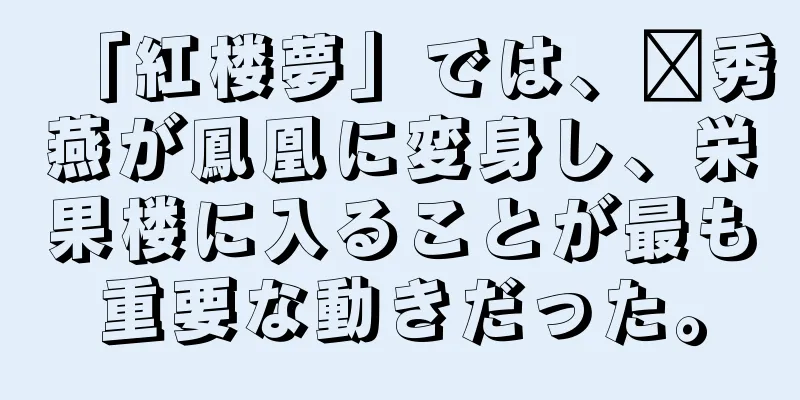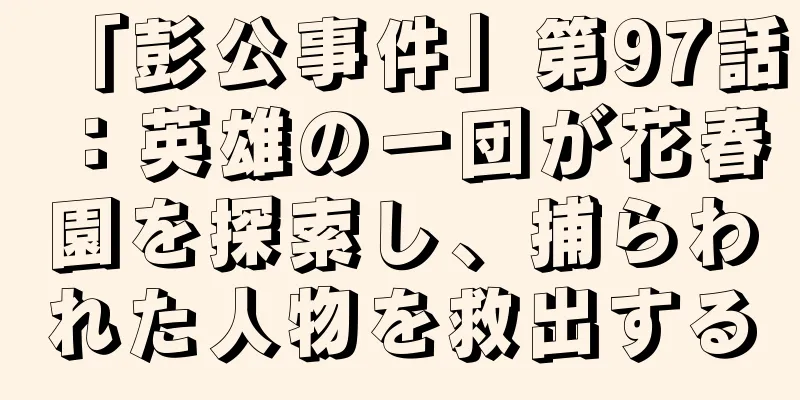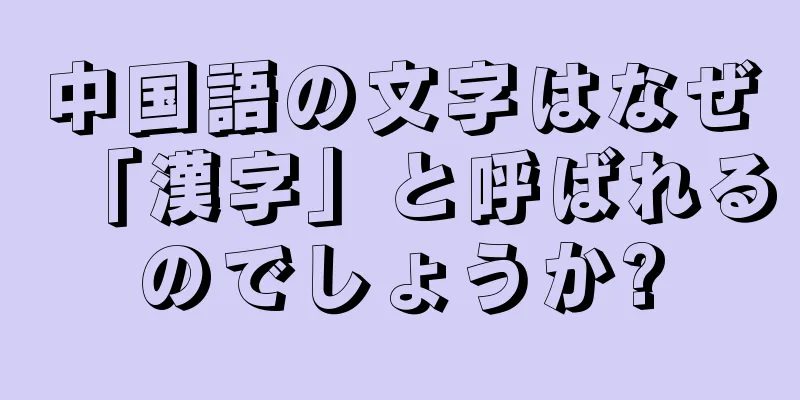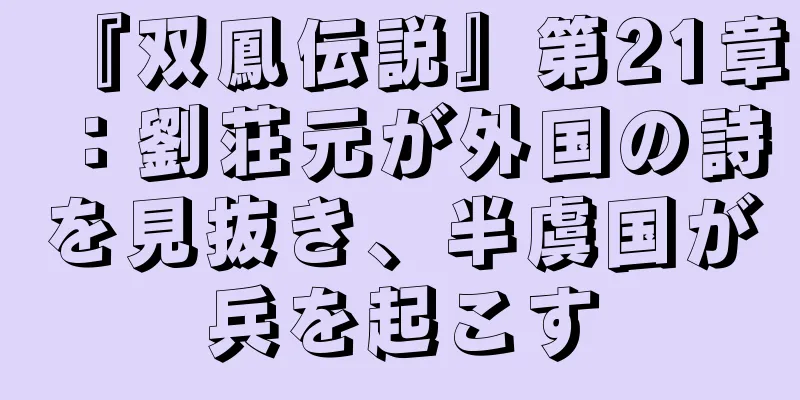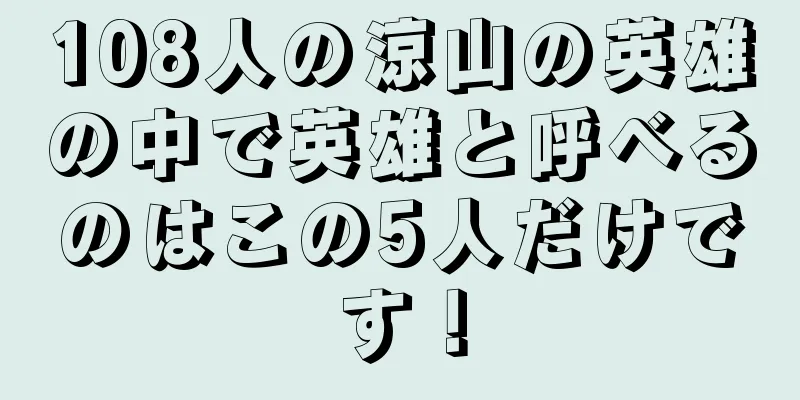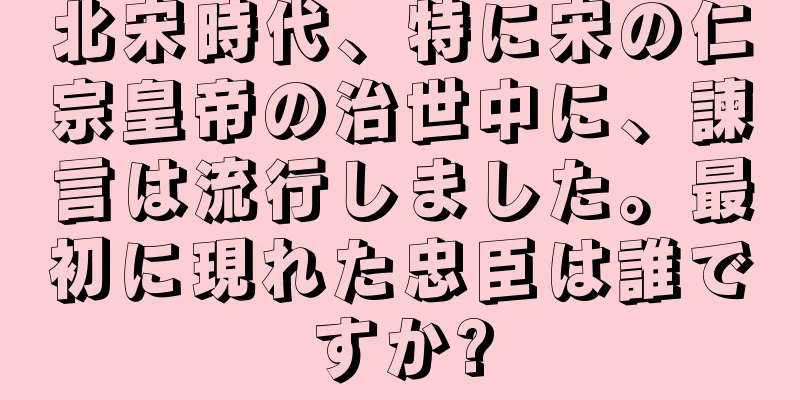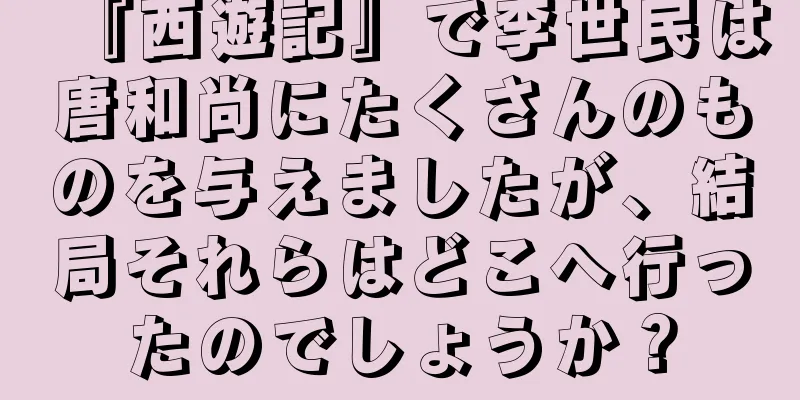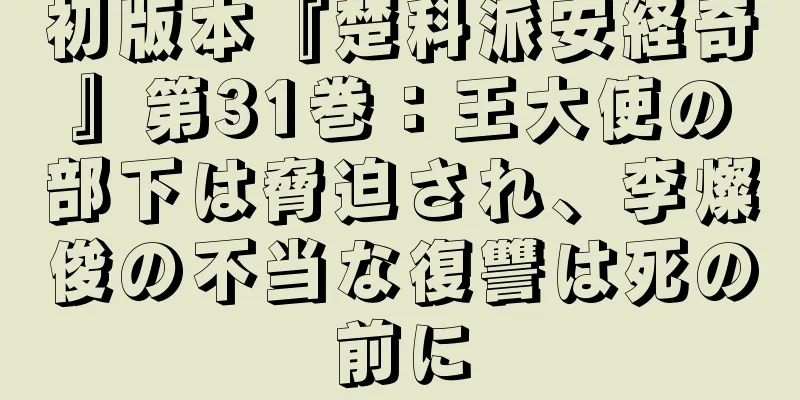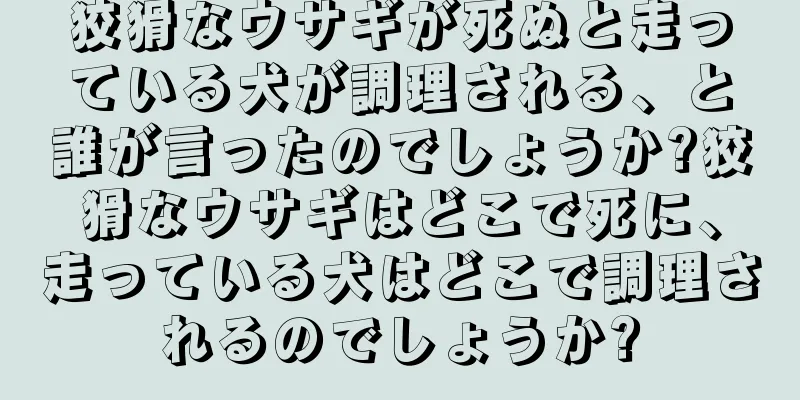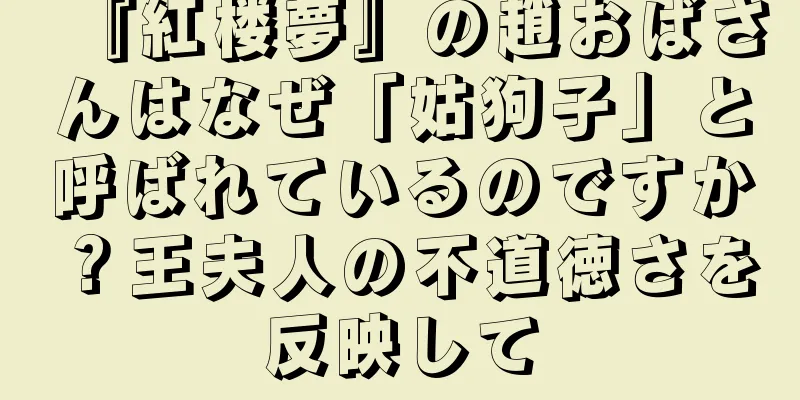諸葛亮の北伐の際、張郃と魏延のどちらがより強かったのでしょうか?
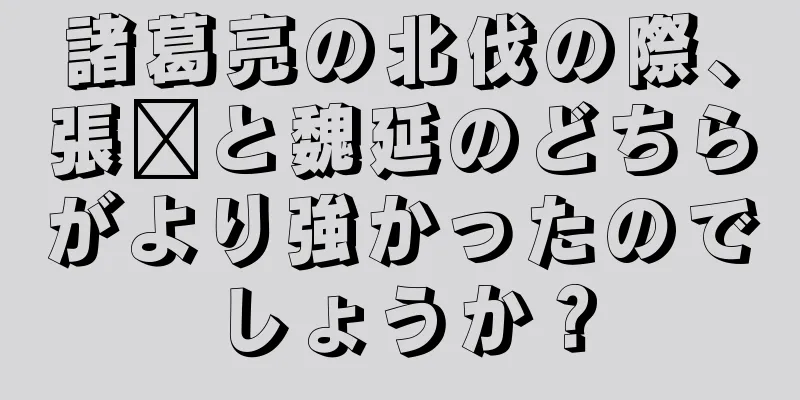
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、五大将軍の一人である張郃と諸葛亮の先鋒である魏延について詳しく紹介します。彼らのうち、どちらが優れた武術を持っているでしょうか? 見てみましょう! 諸葛亮の治世中、魏延は蜀漢で最も有能な将軍でした。諸葛亮と対峙した魏軍の中で、リーダーを務めたのは五大将軍の中で唯一生き残った張郃であった。この二人は諸葛亮の北伐の際にそれぞれの主君に仕え、戦場で血みどろの戦いを繰り広げた。では、張郃と魏延のどちらがより強いのでしょうか? 1. 張郃と魏延の戦闘記録。 張郃はもともと袁紹の配下の「河北四柱」の一人であった。官渡の戦いでは張遼と40、50ラウンドにわたって戦い、勝敗は決せず、曹操に深い印象を残した。張郃は戦いに失敗し、裏切り者の役人たちに陥れられた後、曹操に決然と降伏した。曹操は張郃の降伏を非常に喜び、すぐに彼を将軍と獨亭侯に任命した。張郃は曹操の感謝に深く感謝し、それ以来曹操に忠実に仕えた。 張郃は曹操のもとで多くの戦いに参加し、多くの功績を残した。積極的かつ積極的な戦闘スタイルのため、劉備陣営の最大の敵にもなった。劉備陣営の五虎将軍のうち四人が劉備と戦った。張郃は多くの戦いで敗北したにもかかわらず、劉備に依然として印象を残しました。定軍山の戦いの際、劉備は夏侯淵の首を指差して「人を殺したいなら張郃を殺せ。夏侯淵のような将軍を殺しても何の自慢にもならない」と言った。 諸葛亮が北伐に軍を率いたとき、彼が受けた最大の敗北は街亭の戦いであった。街亭の戦いにおける魏軍の主将は張郃であった。張郃は馬謖が守る南山に水源がないことを利用し、蜀軍の水供給を遮断した。蜀軍が水不足で混乱したとき、張郃はそれを機に攻撃を開始し、一撃で蜀軍を破った。街亭での敗北により諸葛亮は蜀へ撤退しなければならなくなり、第一次北伐は失敗に終わった。 その後、張郃は関龍の戦場に留まり、諸葛亮の主敵となった。諸葛亮も張郃の能力を高く評価し、彼を排除することを誓った。最終的に、諸葛亮の第四次北伐の際、諸葛亮は好機を捉えて木門路で張郃を待ち伏せした。張郃は太ももを矢で撃たれ、その傷が原因で死亡した。 魏延は劉備に選ばれた将軍で、劉備に従って四川に入り、益州の戦いや漢中の戦いで活躍した。劉備が漢中の守護者を選ぶとき、意外にも魏延を選んだ。魏延は劉備の任命を受け入れたとき、曹操が全国の軍を率いて来たら阻止し、他の将軍が10万の軍を率いて来たら滅ぼし、漢中の安全を絶対に保証すると劉備に約束した。 諸葛亮が北伐を開始すると、漢中に拠点を置いた。魏延は諸葛亮の軍に転属し、先鋒となった。しかし、魏延と諸葛亮の戦術思想の相違により、衝突が頻繁に発生しました。魏延は、諸葛亮が臆病で才能を十分に発揮できないとよく嘲笑した。 楊西の戦いでは、魏延は単独で軍を率いて戦いに臨んだ。この戦いで、魏延は軍事的才能を存分に発揮した。彼は軍を率いて曹魏の領土の奥深くまで侵入した。張郃、郭淮らは魏延の意図を理解できず、拠点を守ることしかできなかった。魏延は好機を捉えて西の羌の領土に進軍した。魏軍はもはや彼を止めることができないと悟った。 魏延は羌の現地部族と友好関係を築き、すぐに1万人以上の騎兵隊を結成した。魏延は蜀中への帰還命令を受けて軍を率いて戻ったが、途中で費瑶と郭淮の率いる魏軍に阻止された。楊西方面では、魏軍が魏延を包囲し、勝利は確実だと考え、魏延の陣地に近づいて障害物を設置した。両者が戦ったとき、魏軍が魏延に敗れたことを誰が知っていただろうか。この戦いでの勝利により、魏延は元軍顧問、西伐将軍に任命され、臨時に権力を与えられ、南鄭侯に叙せられた。 しかし、諸葛亮の死後、魏延は楊毅と軍事力を争い、敗れて殺害され、彼の家族も楊毅によって滅ぼされた。しかし、魏延の軍事的才能は誰の目にも明らかで、蜀軍において諸葛亮に次ぐ地位にある将軍であるだけでなく、諸葛亮の後継者としても誰もが認める人物でした。 2. 張郃と魏延の武術の腕前の違い。 魏延は蜀軍にとって重要な存在であったため、諸葛亮は当然ながら彼を使うことに非常に慎重でした。蜀漢には才能が不足していたため、諸葛亮は魏延に危険を冒させることは決してなかった。諸葛亮が魏延の「紫木谷の策」を採用しなかったのはまさにこのためであり、それは魏延が考えていたような臆病さではなかった。諸葛亮の慎重さのせいで、魏延は張郃と戦う機会を得られなかった。 しかし、魏延と張郃はそれぞれ街亭の戦いと木門路の戦いで二度戦った。興味深いことに、この 2 つの遭遇では両者の役割が逆転しました。街亭の戦いでは、敵を誘い出すために敗北を装った将軍は張郃であり、木門道の戦いでは、敵を誘い出すために敗北を装った将軍は魏延であった。 街亭の戦いでは、魏延は諸葛亮の命令に従い、軍を率いて街亭の背後に陣取り、街亭を支援した。馬素は街亭で惨敗を喫した後、張郃に追われた。魏延は張郃の追撃を途中で止め、まっすぐに張郃に向かって突進した。張郃は魏延と戦うことなく方向転換して去っていった。魏延は追撃中に司馬懿に待ち伏せされ包囲された。王平の救出のおかげで、魏延は脱出することができた。 木門路の戦いになると、魏延と関平は敗北を装って張郃をおびき寄せた。この誘引作戦の間、魏延と張郃は3回戦い、そのたびに魏延は10ラウンドも戦わずに負けたふりをして逃げていった。最後の戦いでは、魏延は10ラウンドも戦わなかった後、衣服、鎧、兜を捨て、敗北した軍隊を率いて馬に乗って木門道へ逃げました。張郃も意気揚々としており、魏延が敗れたのを見て、木門路まで追いかけた。その結果、張郃は諸葛亮の罠に陥り、射殺された。 魏延と張郃の二度の戦いを見ると、どちらも相手に納得していないことが感じられます。最初の遭遇では、張郃は負けたふりをして逃げたが、魏延はそれを全く疑わなかったため、司馬懿の待ち伏せに遭い、包囲を突破するのを危うく失敗しそうになった。二度目の対決でも、張郃は魏延が何度も見せかけた敗北を疑わなかった。 この戦いでは、魏延は毎回10ラウンド以内に敗北した。前回は、彼は大げさに言い過ぎて、服や鎧、兜を投げ捨てて逃げた。張郃はためらうことなく、木門路の危険な地域まで彼を追った。張郃の行動から、彼は心の中で魏延が自分の相手ではないと信じていたことがわかります。これは長期にわたる戦闘で得た経験に基づいた判断でした。 諸葛亮が魏延をどのように利用したかを見れば、いくつかの手がかりも見えてきます。もし魏延が張郃を直接倒すことができたなら、わざわざ待ち伏せ作戦を練ることはなかっただろう。諸葛亮が魏延に敵をおびき寄せるよう命じたのは、魏延の武術を使って張郃を誘い、追撃させるためだった。なぜなら、蜀軍の中で、張郃と決闘して自分の安全を確保できるのは魏延だけだったからだ。さらに、魏延の地位と立場は張郃の注意を引き、敵をおびき寄せる目的を達成するだろう。 そのため、魏延と張郃の間では、張郃の武術がわずかに優れていたものの、魏延を簡単に倒すことはできなかった。まさにこの隙間があったからこそ、魏延は張郃を罠にかけ、軍隊を誘き出す計画を完遂することができたのである。両者が公平な決闘を行えば、張郃は魏延を倒すことができるだろうが、おそらく50~60ラウンドかかるだろう。 結論: 魏延と張郃は北伐の際の諸葛亮の敵対者であり、それぞれの陣営で重要な将軍であった。そのため、諸葛亮は魏延と直接対決することを避けるために、魏延を利用することに非常に慎重でした。しかし、彼らは街亭の戦いと木門道の戦いという戦場で二度対戦していた。 この二つの戦いにおいて、二人は互いに囮と追跡者として行動した。しかし、この二つの出会いから、張郃は戦いで勝利するという自信に満ちており、魏延が自分の敵ではないと心から信じていたことがわかります。諸葛亮はこれをよく知っていたので、それを利用し、魏延に命じて張郃を木門の中に誘い込み、射殺させた。もし二人が公平な決闘をしていたなら、張郃は50~60ラウンドで魏延を倒すことができたはずだ。 |
<<: 蜀滅亡に多大な貢献をした鄧艾だが、良い最後を迎えられなかった。一体何が起こったのか?
>>: 諸葛亮の生涯において、どの北伐が最も大きな成果をあげたでしょうか?
推薦する
「十二塔」:夏一楼 · 蓮池で水浴び、美しい顔のいたずらっ子と遠くまで見通す美しい男
『十二塔』は、明代末期から清代初期の作家・劇作家である李毓が章立てで書いた中国語の短編集です。12巻...
大鵬を征服できるのは如来だけなのに、獅子駱駝嶺で義兄弟となったのに、なぜ彼は三番目の兄弟になったのでしょうか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
関羽はどのような過ちを犯して失敗のどん底に陥ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
孟浩然の古詩「謝祚世の越境行の別れ」の本来の意味を理解する
古代詩「謝禄之越行の別れ」時代: 唐代著者: 孟浩然夜明けには川と空が広く広がり、北西から涼しい風が...
明代に朱棣によって設立された神金営の目的は何だったのでしょうか?
明代の神雍英は中国および世界で最初に設立された銃器部隊であり、「内部から首都を守り、外部の戦争に備え...
紅楼夢の金陵十二美人三巻のうち最初の一巻は、8月15日の中秋節に枯れてしまった。
『紅楼夢』の金陵十二美人三巻のうち、最初の巻が8月15日の中秋節頃に枯れてしまったのはなぜでしょうか...
三国志に登場する24人の有名な将軍のうち、曹操陣営に属するのは誰でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』では、秦克清は中秋節の後に病気になりました。なぜでしょうか?
秦克清は『紅楼夢』の登場人物で、賈容の妻であり、金陵十二美女の一人である。これに非常に興味がある人の...
西遊記に出てくる鉄背狼はどんな怪物ですか?彼はどうやって孫悟空を二度騙したのでしょうか?
鉄背狼の怪物は西遊記の登場人物です。西遊記に登場する機知に富んだ小悪魔とも言えます。今日は、おもしろ...
『皇血の剣』で夏雪怡はなぜ文怡をそんなに好きなのでしょうか?
私は2007年版の「皇帝の血に染まった剣」を観ましたが、ウェン・イーとシア・シュエイーのコンビが本当...
朱其玉の死は謎であるが、なぜその答えはすでに私たちの心の中にあると言えるのだろうか?
今日は、景泰帝の朱其禹がどのようにして亡くなったのかというテーマについてお話しします。皆さんも注目し...
古代の科目はテストしやすいですか?歴代で科挙に合格した人は何人いたでしょうか?
古代の科挙に合格するのは容易だったのでしょうか?歴代科挙に合格した人は何人いたのでしょうか?Inte...
古典文学の傑作『前漢演義』第45章:辛斉が虎を殺し、韓信と出会う
『西漢志演義』と『東漢志演義』は、もともと『江暁閣批判東西漢通志演義』というタイトルで、明代の中山の...
端平の洛陽侵攻とは何ですか?なぜそれが蒙宋戦争の本格勃発の導火線となったのか?
端平の洛陽攻めとは、端平の元年(1234年)に南宋がモンゴルと連合して金朝を滅ぼした後、河南にあった...
神龍の政変で武則天が退位を余儀なくされた後、彼女にはまだどんな権利があったのでしょうか?
唐王朝の中頃に武周王朝が出現した。短命ではあったが、数千年続いた中国の家父長制を揺るがした。これらす...