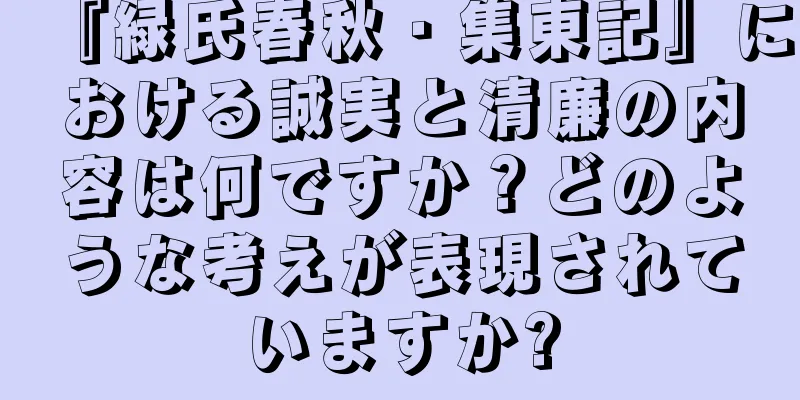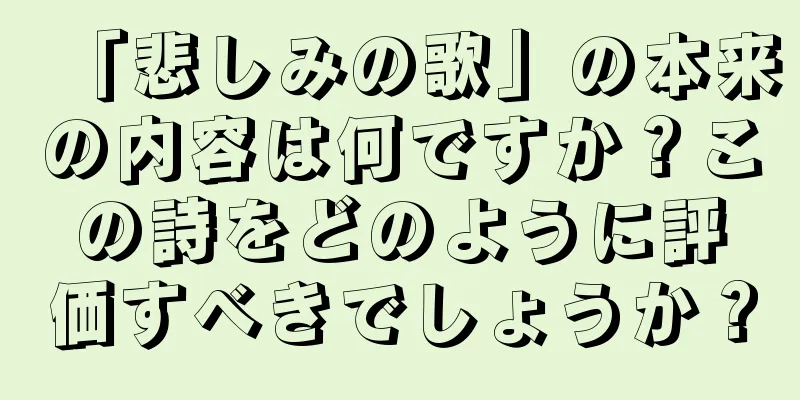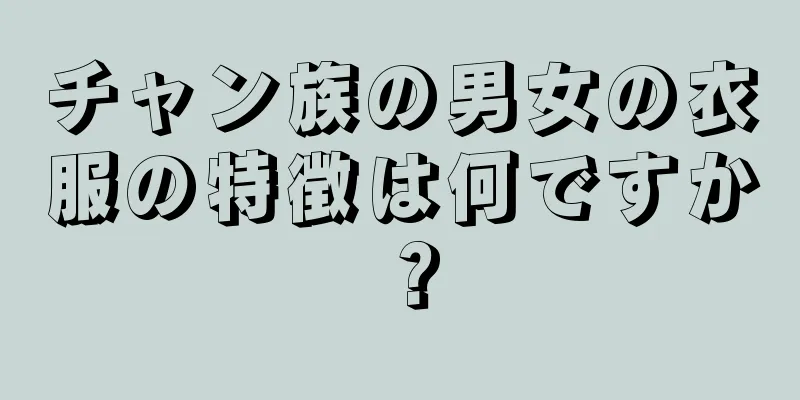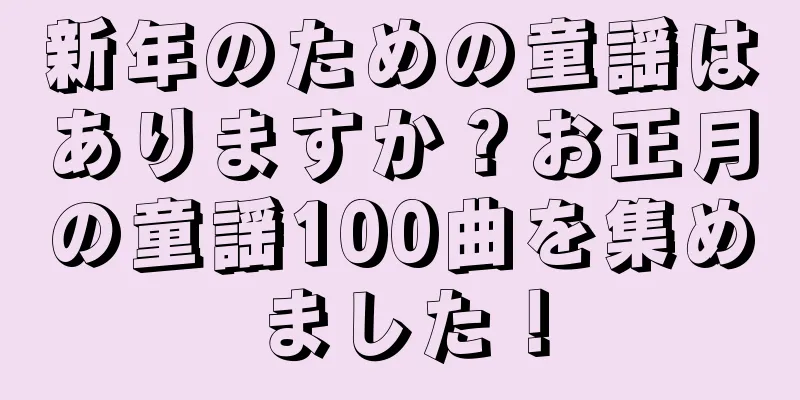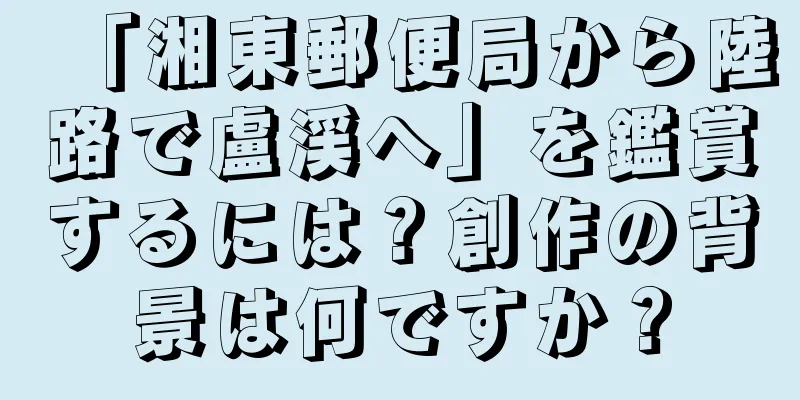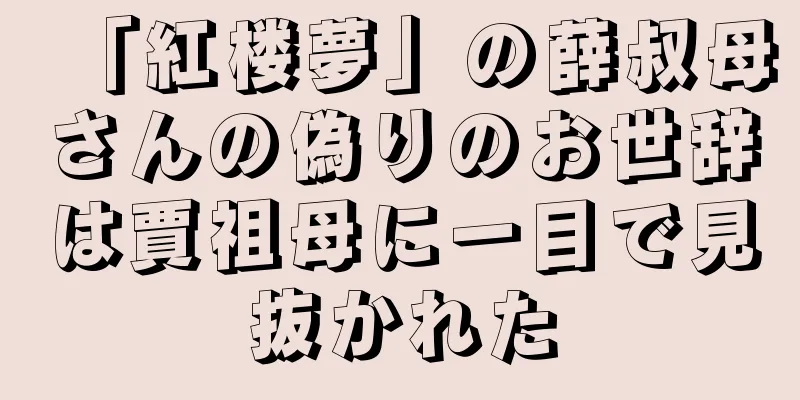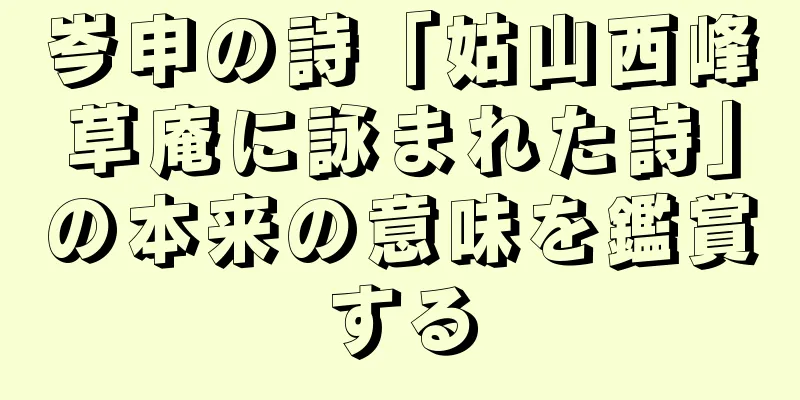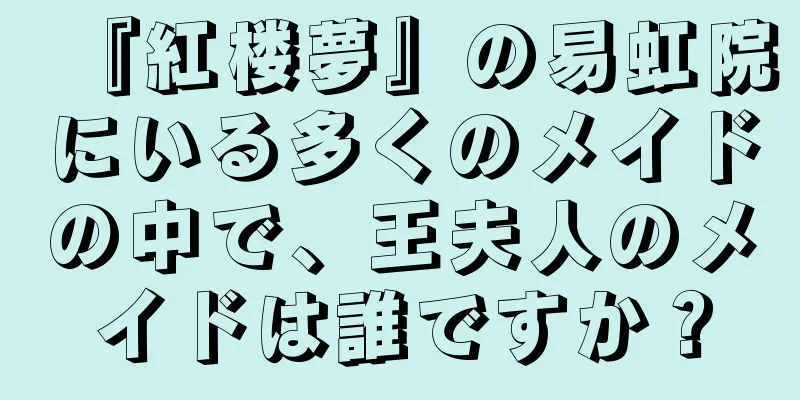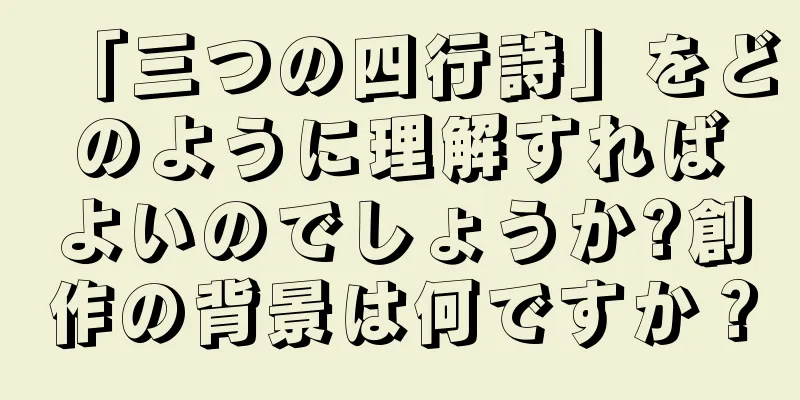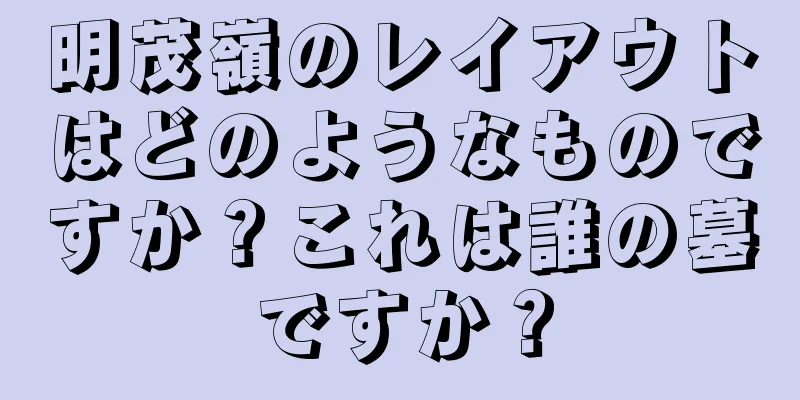諸葛亮の生涯において、どの北伐が最も大きな成果をあげたでしょうか?
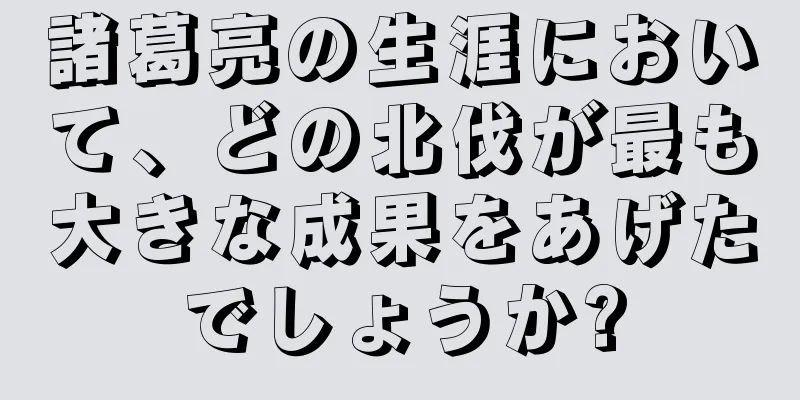
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、諸葛亮が行った5回の北伐について詳しく紹介します。これらの北伐のうち、最も大きな成果をあげたのはどれでしょうか?見てみましょう! 諸葛亮は白帝城の孤児の世話を引き受けた後、劉備の遺言も受け入れて漢王朝を支援した。諸葛亮は経済を発展させ、軍隊を再編し、内政を改善し、孫権と同盟を結んだ後、まず南中の反乱を鎮圧した。その後、諸葛亮は漢中に入り、曹魏に対して北伐を開始した。諸葛亮は生涯に渡り曹魏に対して計5回の北伐を行った。では、諸葛亮の北伐で最も大きな成果をあげたのはどの作戦だったのでしょうか? 1. 諸葛亮の五回の北伐。 諸葛亮の第一次北伐は二つのルートに分かれていた。一つは趙雲が薛谷から率いて魏軍を長安方面に足止めする囮の役目をしたルートであった。諸葛亮は主力を率いて旗山から出撃した。曹魏は備えがなかったため、諸葛亮の奇襲を受けた。曹魏の南竿、安定、天水の三県は諸葛亮に反応して蜀軍に降伏し、竜游に大きな衝撃を与えた。 しかし、曹魏が派遣した援軍が竜游に到着したため、幸福な時代は長くは続かなかった。長い旅の末、張郃率いる曹魏中央機動部隊5万人以上が街亭に到着した。諸葛亮は誤って馬謖を街亭の守護に任命したため、張郃に敗れた。諸葛亮はその地域に拠点がなかったため、漢中へ撤退しなければならなかった。趙雲の軍も曹真に敗れ、漢中へ撤退した。 諸葛亮の第二次北伐は東呉との戦争に協力するためであった。彼は蜀軍を率いて三官から脱出し、陳倉を攻撃した。曹魏が事前に準備を整えており、守備の将軍である郝昭が勇敢で戦闘に優れていたため、諸葛亮は城塞都市で足止めされた。魏の援軍が到着し、諸葛亮の食糧が尽きたため、蜀軍は撤退を余儀なくされた。 諸葛亮の第三次北伐の際、彼は陳世を派遣して曹魏から五都県と銀平県を奪取させた。 諸葛亮の4回目の北伐は竜游から始まり、今度は最大のライバルである司馬懿と遭遇した。この戦いで両陣営は互いに試し合い、将来の戦争の方向性を決定づけた。この戦いで、諸葛亮は退却中に木門路で待ち伏せし、追撃してきた魏の将軍張郃を射殺した。 諸葛亮の第五次北伐は最大のものであった。この戦いの最中、諸葛亮は東呉と連絡を取り、10万人の蜀軍を率いて下鼓から脱出し、渭南に陣を敷いた。この戦いでは、司馬懿は定められた戦略に従い、地上に留まりました。諸葛亮と司馬懿は100日以上戦い、最終的に諸葛亮は五丈原陣営で病死した。その後蜀軍は撤退し、諸葛亮の北伐は終結した。 2. 諸葛亮は北伐において最大の成果をあげた。 諸葛亮の5回の北伐のうち、街亭で惨敗した最初の遠征を除いて、他の4回の遠征では基本的に大きな損失はなかった。これら4回の戦いの間、戦争が続くにつれて諸葛亮とその軍隊の戦闘能力は徐々に向上していきました。結局、諸葛亮は敵に前進時に戦うことを恐れさせ、後退時に追撃することを恐れさせた。 諸葛亮の最も成功した北伐は第一次北伐であったと言えるでしょう。この北伐では、曹魏が準備していなかったため、諸葛亮の攻撃は奇襲のような効果をもたらした。諸葛亮は短期間で南竿、天水、安定の3県の広大な地域を支配し、現地の人々の支持を獲得した。 しかし、諸葛亮が最大の損失を被ったのは第一次北伐のときであった。この北伐では、馬謖が街亭を失ったことで蜀軍は壊滅的な敗北を喫した。当時、馬謖の率いる軍は張郃に敗れ、兵士たちは散り散りになって完全に統率力を失った。諸葛亮はそれまでの拠点がなかったため、漢中に撤退し、獲得した3つの郡を放棄せざるを得なくなり、西城の千戸余りだけを戻した。最終結果から判断すると、戦い全体はコストに見合うものではなかった。 諸葛亮の北伐のうち、領土を獲得したのは第三次北伐のみである。この北伐の際、諸葛亮は陳世を派遣して蜀軍を率い、曹魏の五都県と銀平県を占領させた。これら二つの郡は人口も駐屯兵も少なく、規模も小さかったが、守備にあたる魏軍は合計で数百人しかいなかった。しかし、この二つの郡は地理的に重要な位置にあるため、これを占領することは蜀漢にとって大きな意義を持つことになる。その後、鄧艾はここから700マイルの銀平道を抜け、蜀漢の中心部に直接侵入し、蜀漢を滅ぼした。 戦場では諸葛亮も多くの勝利を収めました。中でも有名なものとしては、第二次北伐の王双の戦い、首陽の戦い、第四次北伐の鹿城の戦い、木門道の戦いなどが挙げられます。戦闘結果から言えば、鹿城の戦いが最大の成果を上げたはずだ。 『漢進春秋』には諸葛亮と司馬懿が鹿城で激戦を繰り広げたと記録されている。司馬懿は張郃を諸葛亮の背後に派遣し、自らは主力を率いて蜀軍の陣地を攻撃した。諸葛亮は魏延、高湘、呉班を派遣して戦い、魏軍を破った。張郃も王平が守る陣地を占領することができず、撤退を余儀なくされた。 この戦いで蜀軍は3,000段の鎧、5,000組の黒鎧、3,100本の角弩を手に入れた。蜀軍の戦利品から、魏軍が少なくとも数万人の死傷者を出し、極めて大きな損失を被ったことがわかります。しかし、この戦いは『三国志』には記録されていない。『晋書・宣帝紀』には司馬懿が勝利したと記録されている。また、蜀軍はこの戦いに対して何の褒賞も与えなかったため、この戦いの真相は依然として疑問のままである。 残りの戦いで諸葛亮が捕らえた敵チームの最高位の将軍は張郃であるはずです。張郃は曹魏の五大将軍の中で唯一生き残り、関龍戦場で活躍し、諸葛亮の強力なライバルとなった。街亭の戦いで馬謖を破ったのは彼だった。諸葛亮の第四次北伐の際、諸葛亮は張郃を木門の中に誘い込み、撤退中に射殺した。 呂城の戦いが実際に起こったことが確認できないのであれば、諸葛亮が最も多くの敵を排除した首陽の戦いこそが首陽の戦いであるべきである。この戦いの最中、魏延率いる蜀軍が羌から帰還し、魏軍に迎え撃たれた。魏軍の費瑶と郭淮は幹線道路を封鎖し、谷底に陣を張り、夜間に歩兵を派遣して魏延の陣地を馬で包囲した。その結果、魏軍は諸葛亮の援軍と魏延の内外からの攻撃を受け、大敗を喫した。この功績により、魏延は元軍顧問、西伐将軍の称号を与えられ、臨時の権力と南鄭侯の爵位を与えられた。この戦いは『三国志』に明確に記録されている勝利である。 結論: 諸葛亮の北伐は曹魏に大きな打撃を与えた。諸葛亮の北伐を総括すると、第一次北伐は最大の成果をあげたが、最大の損失も被った。成果と損失は相殺し合い、損失は利益を上回らなかった。諸葛亮の戦術は魏軍の主力を倒すことであり、都市や場所の損得にはこだわらなかったため、武都郡と銀平郡の2つの郡のみを占領した。 戦闘の戦果について言えば、『韓進春秋』の記録が真実であれば、それは第四次北伐の際の鹿城の戦いであるはずだ。そうでなければ、諸葛亮の最大の勝利は首陽の戦いとなるでしょう。この戦いは第三次北伐と第四次北伐の間に起こった。諸葛亮が敵の最高位の将軍を捕らえた戦いは、第四次北伐の際の木門路の戦いで、張郃を射殺した時であった。以上の分析から、蜀漢政権の利益という点では、諸葛亮の最も成功した北伐は、武都郡と銀平郡を占領した第3次北伐であったことがわかります。 |
<<: 諸葛亮の北伐の際、張郃と魏延のどちらがより強かったのでしょうか?
>>: なぜ関羽は60歳のベテラン、黄忠と引き分けになったのでしょうか?
推薦する
宋代の女流詩人、李清昭:「汝孟玲:昨夜は雨がまばらで風が強かった」の原文と鑑賞
「汝孟玲:昨夜は雨がまばらで風が強かった」は宋代の女流詩人、李清昭の初期の詩です。この詩は、酔い覚め...
済公第110章: 姚子厳は男を殺し、その首を贈り物として与えた。張知事は分隊長を派遣して彼を逮捕させた。
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
金庸の小説『射雁英雄伝』に登場する鉄掌団のリーダー、尚官剣南の簡単な紹介
尚官剣南は金庸の小説『射雁英雄伝』の登場人物です。尚官剣南はもともと南宋の名将、韓時忠の配下の将軍で...
金、遼、宋と比べて、西夏はなぜ長寿だったのでしょうか?
中国二十四史には、金史、遼史、宋史がありますが、西夏史はありません。これは、現在の王朝が前王朝の歴史...
青旗:清朝の八旗の一つ。青い地に赤い縁取りが施されていることからこの名がついた。
現在の内モンゴル自治区ウランチャブ市東部に位置する青旗は、清朝の八旗の一つであった。明の万暦43年(...
『蔡連慈』の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
蓮の花張超(唐代)朝は砂州の上の太陽が真っ赤に輝き、夕方には川の真ん中に雲が立ち上がる。幸運にも、以...
唐の皇帝睿宗李丹の娘、良果公主の簡単な紹介。良果公主の配偶者は誰ですか?
唐代の公主、良果公主(687-724)は、李(紹門)、雅号は華荘(『新唐書公主伝』では華荘)と称され...
明顕宗朱建神には何人の娘がいましたか?実の母親は誰ですか?
明献宗朱建神には何人の娘がいましたか?彼女たちの実の母親は誰でしたか?朱建真(1447年12月9日 ...
「言論の自由に関する5つの詩、第3号」の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
自由談義の詩 5 篇 第 3 節白居易(唐代)亀の甲羅やノコギリソウの茎を使わずに疑問を解決する方法...
どちらの色がより高貴でしょうか?古代人の「色の階層」という概念!
今日は、Interesting Historyの編集者が、皆さんのお役に立てればと願って、古代の「カ...
「势如破竹」という慣用句はどういう意味ですか?その裏にある物語は何ですか?
「势如破竹」という慣用句をどう説明すればいいのでしょうか?その裏にはどんな物語があるのでしょうか?次...
海公大紅報全集第41章:エンシティでの毒殺と私的目的の陰謀
『海公大紅袍全伝』は、清代の中国語で書かれた全60章からなる長編歴史ロマンス小説です。題名は「金一寨...
法律顧問の職業は何ですか?彼は朝廷の役人ですか?
多くの時代劇には特別な職業が登場します。衙門で事件を扱う際、郡長官の計画立案を補佐することが多いので...
「端午節詩三首」の作者は誰ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
端午節の詩3編趙範(宋代)汨羅河に詩を投げると言ったが、今は幸せなので、彼に何ができるだろうか?在家...
司馬遷はどうやって亡くなったのですか?司馬遷の子孫に関する論争とは何ですか?
『司馬遷自伝』には、「司馬遷は龍門に生まれ、川と山の南側で農業と牧畜を営んだ」とある。龍門の場所につ...