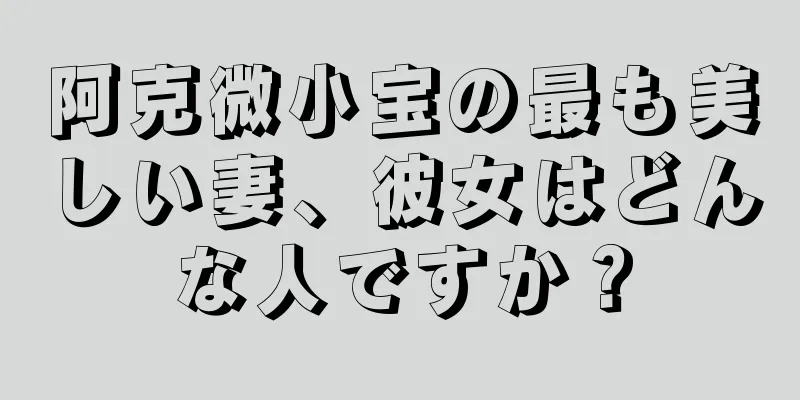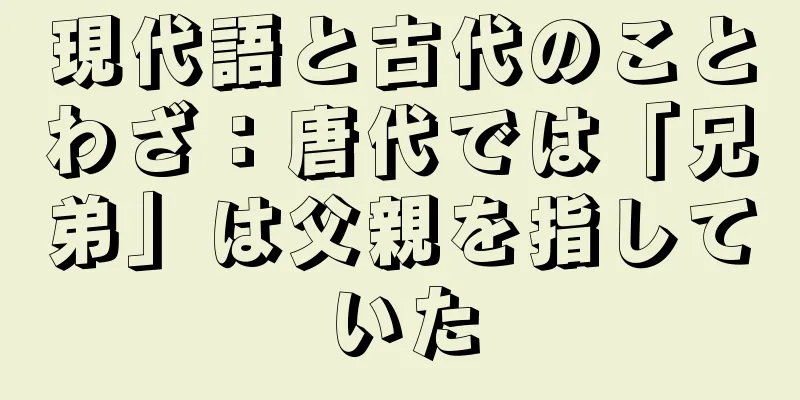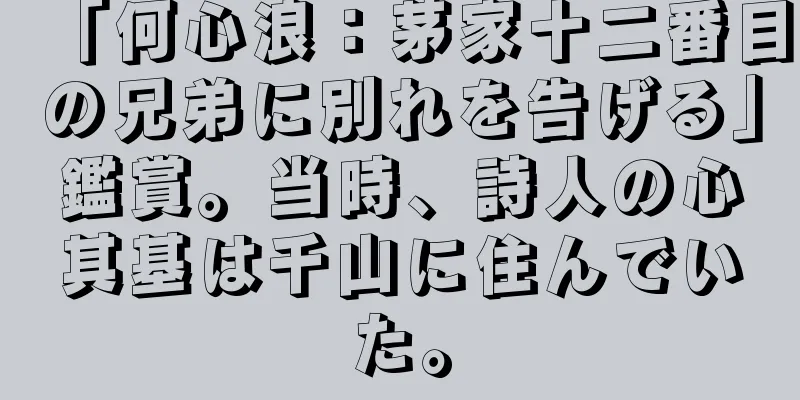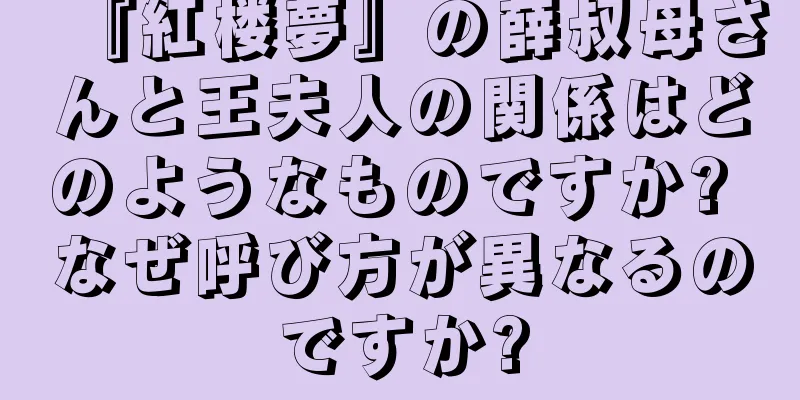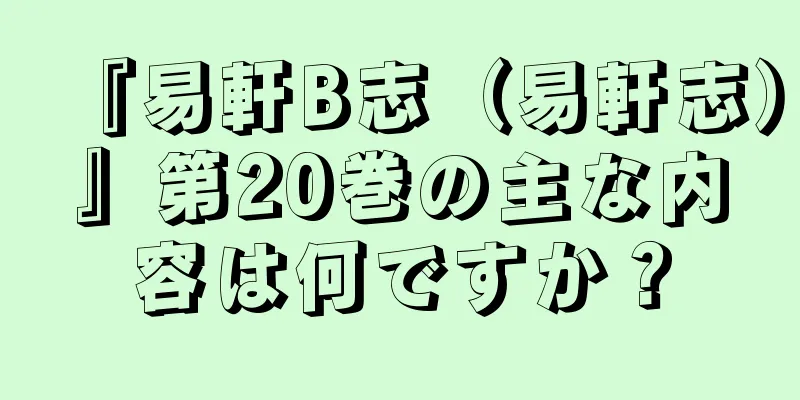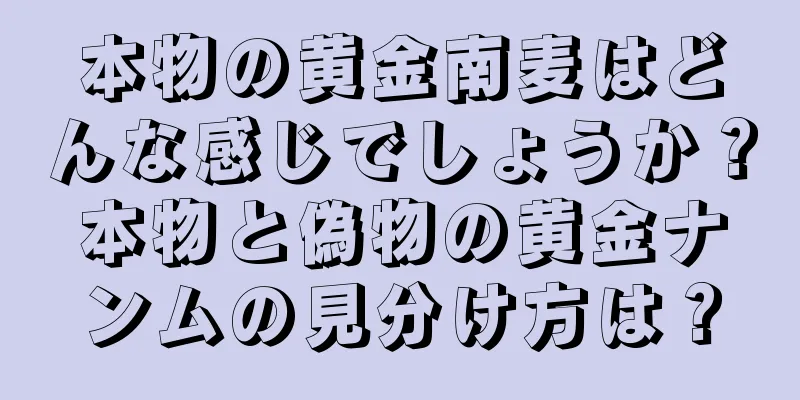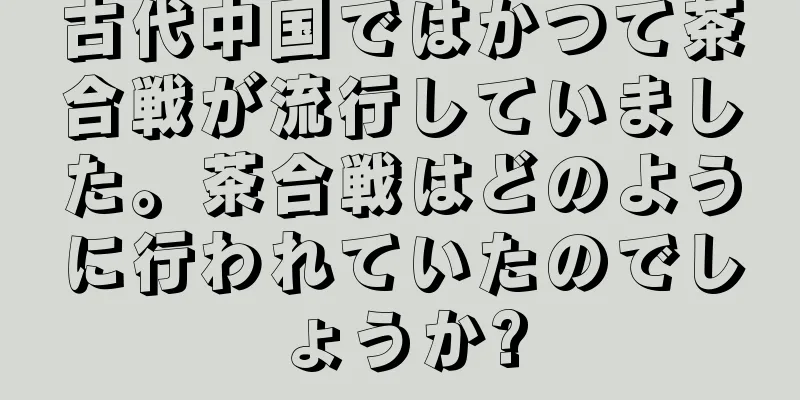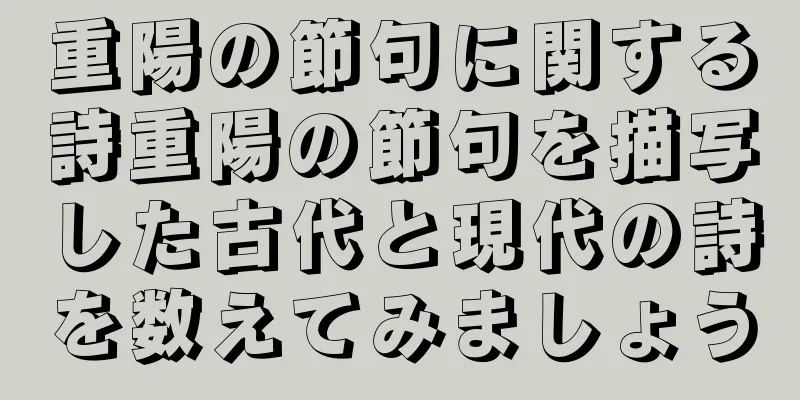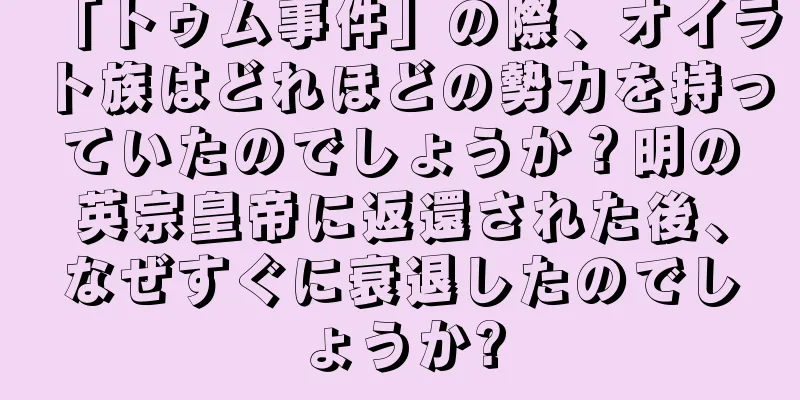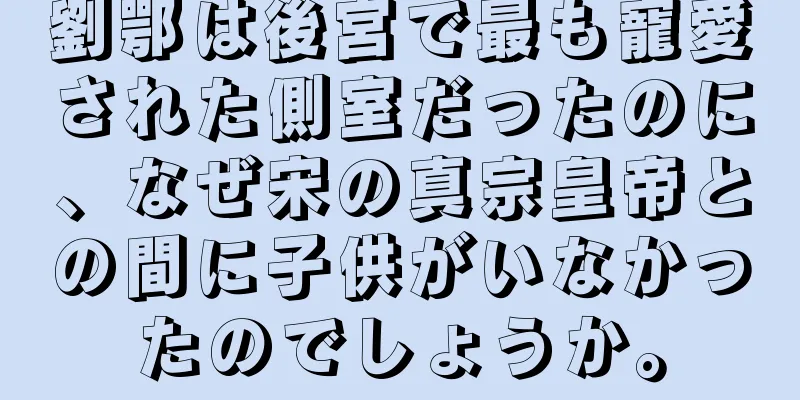なぜ関羽は60歳のベテラン、黄忠と引き分けになったのでしょうか?
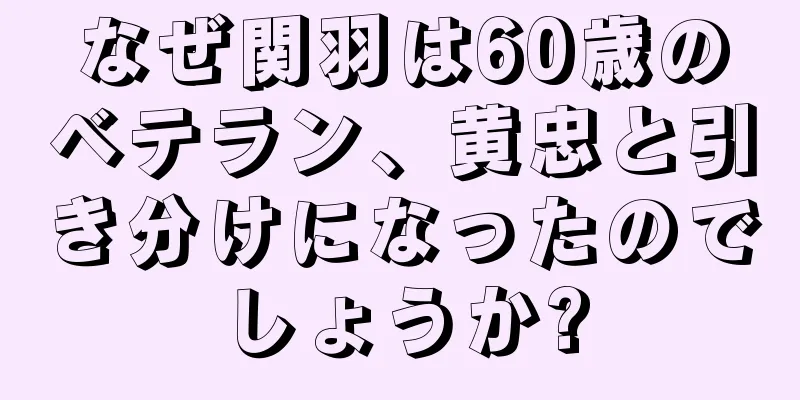
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、武術の達人であった関羽が、長沙で3日連続でベテランの黄忠と一戦も勝てなかった理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 関羽は武術の達人でした。白馬坂で顔良と文周を殺し、また五つの峠を越え六人の将軍を殺したため、中国全土でその名が知られていました。しかし、彼は生涯、長沙で悲痛な戦いを繰り広げた。彼と黄忠は3日連続で一騎打ちを繰り広げ、引き分けに終わった。 60歳近いベテランである黄忠を前にして、この記録は関羽を本当に恥ずかしくさせた。では、なぜ関羽は黄忠を倒せなかったのでしょうか? 1. 関羽と黄忠の決闘。 関羽の長沙の戦いは、赤壁の戦いの後に劉備が軍を率いて揚子江の南にある荊州の4つの郡を攻撃したときに起こりました。霊陵、貴陽、武陵の3県は劉備軍に次々と占領された。後方に陣取っていた関羽は黙っていられなくなり、自ら率先して劉備に長沙攻撃を命じた。彼は自分の勇敢さを示すために、わざと500人の剣を持った兵士を率いて長沙を占領した。諸葛亮は関羽に、長沙に黄忠という歴戦の将軍がいることを特に思い出させ、それがかえって関羽の闘志をかき立てた。 長沙を占領する戦いで、関羽はまず長沙軍の隊長である楊玲を殺し、次に黄忠と戦った。初日の決闘では、両者は100ラウンド以上戦いましたが、勝者は出ませんでした。翌日、関羽は剣引きの術を使って黄忠を殺す準備をした。両者は50ラウンドか60ラウンド戦いましたが、明確な勝者は出ませんでした。すると関羽は負けたふりをして黄忠を誘い、追いかけさせたが、関羽が剣を引きずる技を使う前に黄忠はつまずいてしまった。関羽は黄忠を殺すのは不当だと考え、黄忠を解放した。 3日目の決闘では、黄忠は関羽に対して、100歩離れたところから矢を的に向けて射抜くという独特の技を使った。関羽が自分を殺さなかったことへの報いとして、彼は最初に弓弦を二度引いたが無駄で、三度目に関羽の兜の房の根元に矢を射た。関羽は衝撃を受け、矢を持って戻らなければなりませんでした。魏延は太守を殺し、長沙を差し出したが、関羽と黄忠は3日間戦い、勝ったり負けたりを繰り返し、結局引き分けに終わった。 関羽はこの結果に非常に不満だった。数年後、黄忠は劉備に従って四川に入り、大きな貢献を果たした。特に定軍山の戦いでは、黄忠は曹操の指揮官である夏侯淵を殺害し、漢中の戦いでの勝利の基礎を築きました。劉備は大臣たちに褒賞を与える際、黄忠を後将に任命した。関羽はこれに強い不満を抱き、男なら老兵と付き合うべきではないと言った。関羽は黄忠を非常に軽蔑していたことがわかります。もしそうだとしたら、なぜ関羽は長沙で黄忠を倒せなかったのか? 2. 関羽はなぜ黄忠を倒せなかったのか? 実際、関羽と黄忠の戦いはさまざまな要素に富んでおり、これらの要素が関羽と黄忠の引き分けにつながったのです。両者の戦いの初日、関羽は長い距離を旅し、途中で再び戦いを繰り広げた。関羽は、十分に休息を取り、相手が疲れるのを待っていた黄忠と対峙したとき、有利な立場になかった。それでも関羽は疲労を無視してまっすぐに戦場へと向かった。 関羽はもともと諸葛亮の言葉に憤慨し、黄忠に対して怒りを抱きました。黄忠との戦いの後、彼は成功を熱望しているように見えた。彼は自分の勇敢さを示すために、いつもの動きで黄忠と戦い、自分の武術で黄忠を威嚇して簡単に勝つことを望みました。関羽が驚いたことに、黄忠は年老いていたにもかかわらず、武術の腕は衰えていなかった。一方は勝利を熱望し、もう一方は十分に休息を取っていたため、両チームは100ラウンド以上も戦いましたが、明確な勝者が出ることはありませんでした。 戦いの初日、両者は引き分けに終わったが、その主な理由は関羽が敵を過小評価していたことであった。そこで、関羽は軍を撤退させた後、初日の経験を総括し、剣引きの術を使って黄忠を殺すことを決意した。三国志演義では、引き刀戦法は数回しか登場しません。しかし、関羽には2回しか登場しません。一つは黄忠に対するものであり、もう一つは龐徳に対するものでした。龐徳が関羽を攻撃したとき、相手が剣を引きずる戦法を使うだろうと考えたため、わざと相手に向かって叫んだ。関羽は剣を引きずる技にかなり熟練していることがわかります。 もし関羽が初日に剣引き戦法を使うことを決めていたら、結果はずっと前に決まっていたかもしれない。その結果、翌日、関羽が剣引き戦法を使おうとしたとき、事故が起こりました。黄忠の馬が関羽を追いかけている間につまずいたのです。黄忠はやはり年老いており、馬から落とされてしまいました。しばらく動けず、関羽に追い詰められてしまいました。しかし、関羽は心が広い人だったので、黄忠の不運に乗じることを望まず、剣引き戦法を使って彼を逃がし、勝利の機会を失いました。 戦いの3日目、黄忠は独特の弓矢の技を使って、関羽を100歩離れたところから射抜き、関羽の勝利の可能性をさらに低くしました。 30ラウンド以上戦った後、黄忠は負けたふりをして関羽を誘い出し、関羽の兜の房の根元を矢で射た。関羽はこの時点で戦う気があったとしても恥ずかしいので撤退しなければならなかった。 二日目と三日目の戦いでは、黄忠の馬が不意につまずき、黄忠も恩返しに矢を放ったにもかかわらず、関羽が黄忠を倒せなかったのは彼の性格によるものであった。関羽は黄忠のつまずきを利用して彼を殺すこともできたが、自分の面子のために、彼を逃がす前に公正に黄忠を倒さなければならなかった。黄忠が矢で恩返しをすると、関羽も黄忠の優しさに感動し、もう戦うことができなくなった。 3. 関羽が黄忠を倒せるかどうか。 関羽と黄忠は長沙での3日間の決闘で引き分けに終わったが、公平に言えば、関羽は黄忠を倒すことができた。黄忠の武術も非常に強いものの、比較的若い関羽と対峙すると依然として不利になるからです。 3日間の対決の間に、いくつかの詳細から手がかりも明らかになった。 例えば、戦いの初日、関羽はまず長沙城から50マイル離れたところで楊令を殺し、その後長沙城の麓まで行って休むことなく黄忠と戦った。この戦いでは、両者は100ラウンド以上も戦いましたが、明確な勝敗は出ませんでした。関羽の夜の総括では、黄忠が百回以上も戦っても何の欠点もなかったと関羽が言ったことがわかります。これは、両者の戦いにおいて、関羽が攻撃側であり、黄忠が防御側であったことを示しています。この観点から見ると、誰が強くて、誰が弱いかは明らかです。 2日目に戦ったとき、関羽は剣を引きずり、背後から攻撃して勝利しようとしました。関羽が剣を引きずる戦法を使ったのは、黄忠の堅固な防御を突破するためだった。もし関羽の計画が成功すれば、黄忠は大きな危険にさらされるだろう。しかし、関羽は黄忠の失策により敗北した。その後、黄忠は韓玄に、この間違いは彼の馬が長い間戦闘に参加していなかったために起こったと説明した。この点から、長沙における黄忠の立場が分かります。長年何もせずにいた黄忠は、当然、長年戦い続けてきた関羽より劣っています。 3日目の戦いで関羽はさらに落ち込んだ。二日連続で黄忠を倒せなかった関羽は、当初は良い戦いをしたいと思っていたが、結局黄忠の弓の腕前に敗れた。実は、黄忠の弓術の腕は衰えていました。高齢と体力の衰えにより、弓術の精度は依然として保たれていますが、強さは失われていました。 『三国志演義』全体を通して、百歩先から矢を射抜く能力で知られた黄忠は、関羽の兜の房の根元を射抜いたほかは、定軍山の夏侯尚に向けて矢を射ただけだった。黄忠が夏侯尚に放った矢は正確で背中に命中したが、夏侯尚を馬から落とすことはできず、矢を持って戻らなければならなかった。ここから黄忠の弓術の真髄が分かります。 黄忠は百歩先の的を射抜く弓術で名高い将軍であったが、その弓術で功績を挙げることはほとんどなかった。これもまたベテラン将軍の悲しみである。もし関羽が黄忠の挨拶の返事に感謝せず、黄忠を追いかけて戦い続けていたら、黄忠の弓の腕は優れていたものの、その殺傷力の低さが関羽に見破られ、戦いの結末はわからなかっただろう。 以上の分析から、関羽の武術の力は黄忠の武術の力よりはるかに優れていることがわかります。しかし、黄忠は武術に長けていたため、関羽を倒すことはできなかったものの、自分自身を守ることは十分にできました。両者が公平に戦えば、関羽は黄忠を倒すチャンスがあっただろう。関羽が黄忠に不満を抱いていたのもこの理由による。 結論: 関羽は長沙で黄忠を倒すことができたが、敵を過小評価したことと性格のせいで失敗した。戦いの初日、関羽は疲労にもかかわらず、十分に休息を取っていた黄忠と戦い、敗北を喫した。二日目と三日目の戦いでは、関羽は自分の面子を考え、相手の不運に乗じて勝つことを望まず、また相手の報復を受けて再び戦うことも望まなかったため、機会を逃した。 実際、もし彼が黄忠を真剣に受け止め、戦いの初日に慎重に行動し、勝てないときには思い切って剣引き戦法をとっていたら、黄忠を倒せたかもしれない。二日目と三日目の戦いでは、関羽が最後まで黄忠を追い続けていれば、黄忠を倒すことができただろう。残念ながら、その機会はつかの間であり、魏延が城を明け渡した後、関羽は勝利のチャンスを失いました。関羽はこれに憤慨し、劉備が漢中王に昇格して褒美を与えるまで怒りをぶちまけなかった。 |
<<: 諸葛亮の生涯において、どの北伐が最も大きな成果をあげたでしょうか?
>>: 夏侯淵が亡くなった後、曹操に従った老将軍は誰でしたか?
推薦する
朱淑珍の「魅力的な目:春の日は優しくて柔らかい」:歌詞には言い表せない悲しみが込められている
生没年不明の朱淑珍は、有奇居師として知られている。朱淑珍の出身地や経歴については諸説ある。銭塘(現在...
大禹が世界を9つの国に分けたことと、大禹が洪水を治めたこととの間には何か関係があるのでしょうか?
洪水を治めるために、禹は知恵を絞って苦労を恐れず、13年間の苦労の末、無数の山を切り開き、無数の川を...
張慧燕の有名な詩句を鑑賞する:柳は柔らかく揺れ、短い草はなかなか緑にならない
張慧延(1761-1802)は清代の詩人、随筆家であった。彼の本名は怡明、雅号は高文、別名高文、明科...
唐代の重要な軍事書『太白印経』全文:戦争装備カテゴリ·都市防衛装備
『神機滅敵』は『太白陰経』とも呼ばれ、道教の著作です。古代中国では太白星は殺生の達人であると信じられ...
「安史の乱」は世界情勢にどのような影響を与えたのでしょうか? 「安史の乱」はなぜ世界大戦と呼ばれているのでしょうか?
「安史の乱」はなぜ世界大戦と呼ばれているのでしょうか?Interesting Historyの編集者...
宋金海上同盟の簡単な紹介:宋金海上同盟は遼を滅ぼすために軍隊を派遣することを協議している
北宋末期に宋と金が共同で遼国を攻撃するために結んだ軍事協力同盟。この名前は、両国が遼王国によって地理...
劉炳義の息子のうち誰が皇帝になるのでしょうか?劉炳義の息子は皇帝ですか?
劉炳義の息子の中で皇帝は誰ですか?劉炳義の息子が皇帝ですか?劉炳義の息子が皇帝となった。劉炳義の息...
呂智深が枝垂れ柳を引き抜いた物語の紹介
柳を引き抜くというのは、古典小説『水滸伝』に出てくる話です。悪党の集団を制圧するために、魯智深は左手...
曹植の『仙人伝』はどのように書かれていますか? 「不滅の者」の文学的評価
曹植の『仙人』はどのように書かれていますか?『仙人』は仙界への旅を描いた詩です。曹植が仙界の向こう側...
ペーパートークとはどういう意味ですか? 「アームチェア・トーク」の主人公は誰ですか?
ペーパートークとは、紙の上で戦争を戦うことについて話すことです。それは、実際の問題を解決できない空虚...
前漢の有名な官僚、公孫洪の略歴 公孫洪はどのようにして亡くなったのでしょうか?
公孫洪(紀元前200年 - 紀元前121年)は、本名は洪、字は季、別名は慈青(『西京雑録』に記録)で...
陶淵明と陶寛の関係は?陶寛の孫は誰ですか?
陶寛(259年 - 334年7月30日)、雅号は世興(世衡とも呼ばれる)。彼はもともと鄱陽県小陽県(...
本草綱目第 7 巻冶金および石碑銘の項硫酸ナトリウムの具体的な内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
『紅楼夢』の劉おばあさんが語る雪の中で薪を集める話と宝釵にはどのような関係があるのでしょうか?
宝仔は『紅楼夢』のヒロインの一人です。林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。今日は『...
中国の天才騎兵将軍、魏青将軍の詳しい解説
魏青将軍は平陽県の出身で、父の鄭基は平陽県の下級官吏で、平陽侯曹寿の家に仕えていた。彼は平陽侯曹寿の...