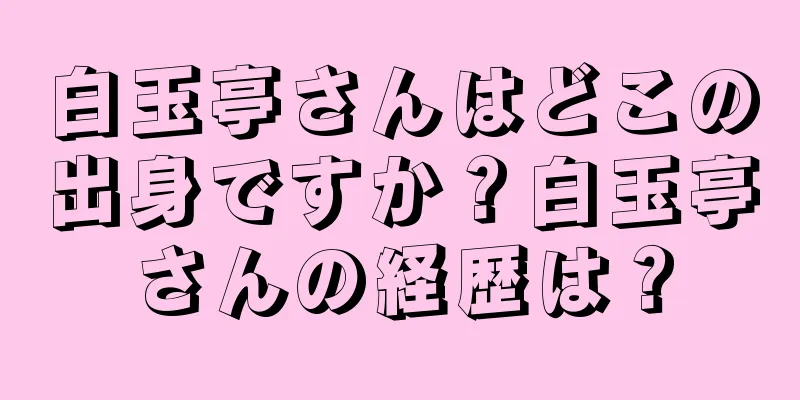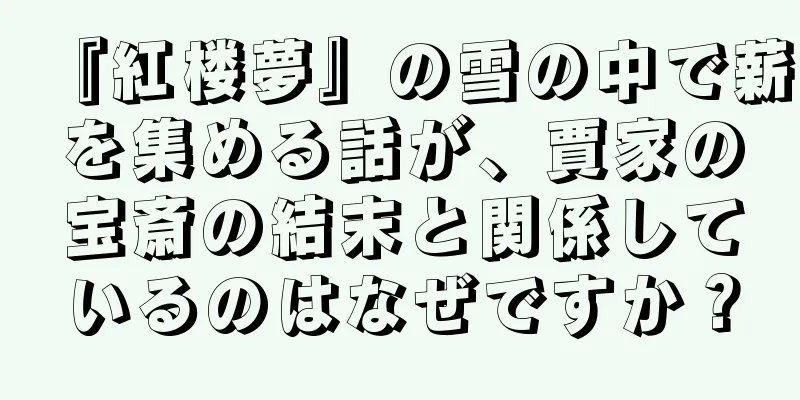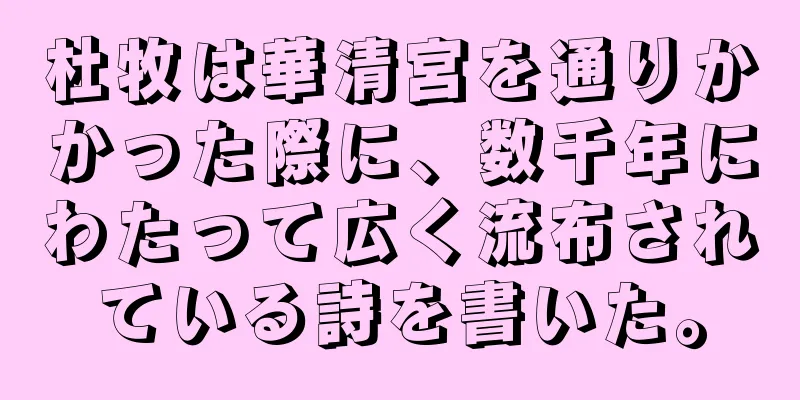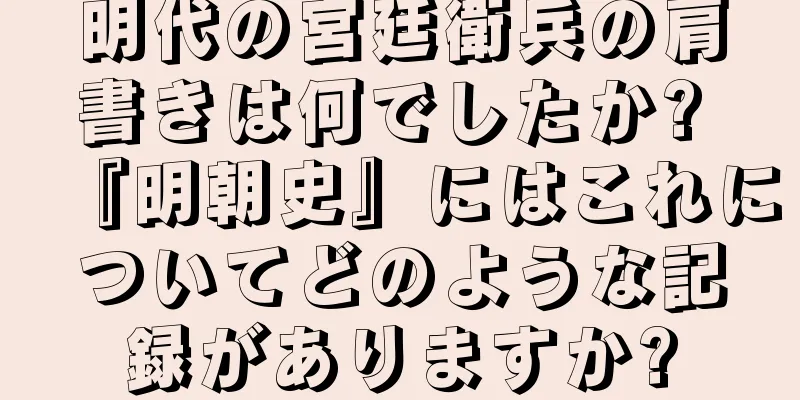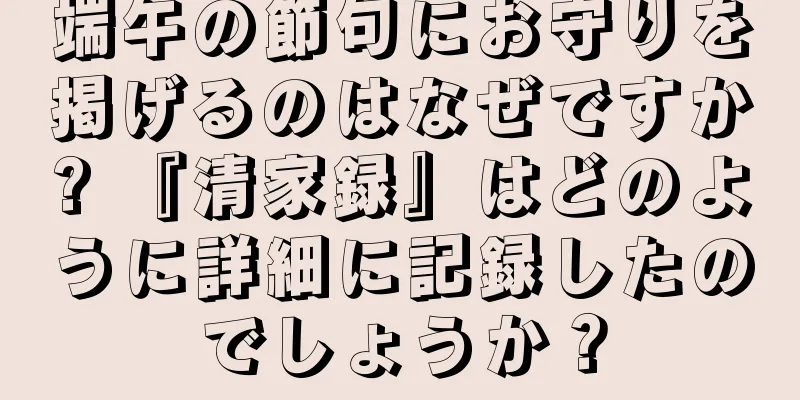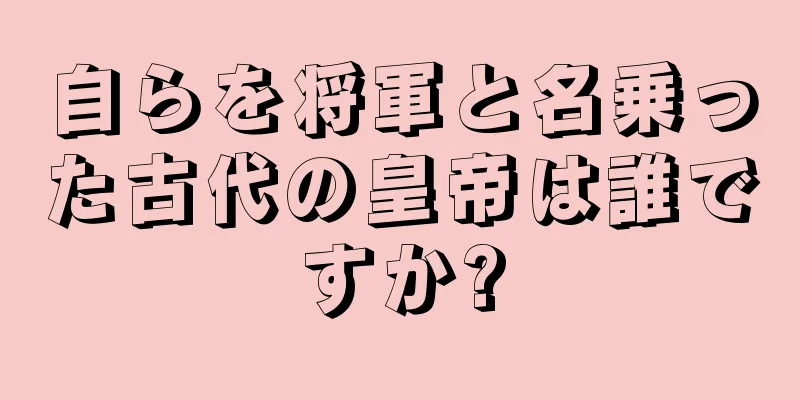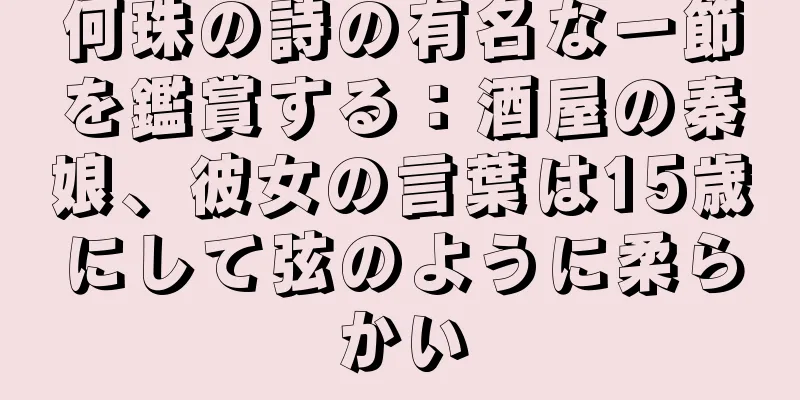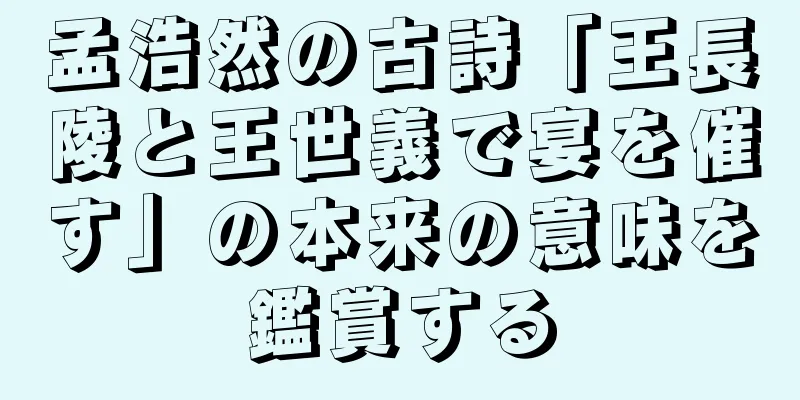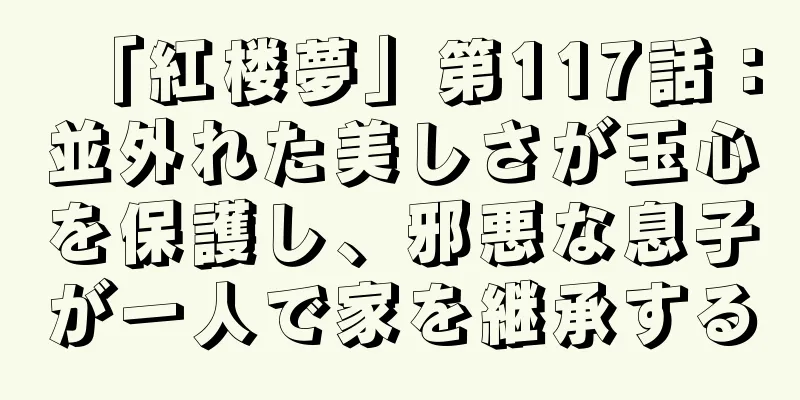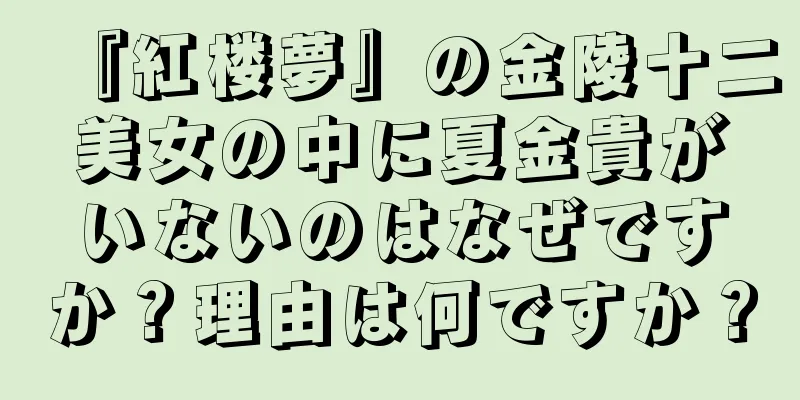清朝における教育長の地位はどうだったのでしょうか?なぜ五位の官吏が二位の知事と対立できたのか?
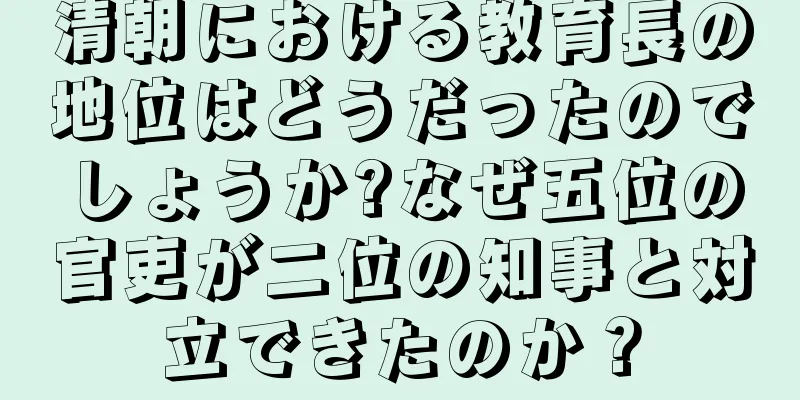
|
清朝の教育長の地位はどのようなものだったのでしょうか? Interesting History の編集者が関連コンテンツをお届けします。ご興味のある方はぜひご覧ください。 清代、省知事は省行政単位の最高軍事・政治責任者として、省の民政、司法、監督、軍事力の指揮を担当し、強大な権力を持つ高官であった。清朝では、知事の階級は当初二等であったが、雍正元年に知事に爵位を付ける制度が確立され、知事が陸軍部副大臣を兼務した後、その階級は二等に昇格した。これは基本的に、現在の省級および部級の官職に相当する。 清朝の知事官邸のロビー 『清代史稿・官録』の記録によれば、州知事は総督に次ぐ重要な官職であり、州内で絶対的な地位と権力を持っていた。清代の地方行政単位の設定では、省の指導者として、州知事のほかに「省の財政と民政」を担当する州知事と「省の司法」を担当する州司法監がおり、彼らは州知事の部下として州知事の省政を補佐していました。 さらに、知事、省知事、省裁判官の間には、地位が定かで権力も大きくはないが、絶対に無視できない省レベルの副リーダー、教育監察総監がいる。つまり、清朝の省行政単位において、省指導部は扶台、学台、範台、内台の4人の高官で構成されていた。 清朝の官僚のイメージ 『清代史草稿 官録』には教育長の階級と権限が次のように記録されている。 各州には教育長が 1 人ずついます。 (壬氏卒業生の中から、副大臣、朝廷官吏、翰林、瞻、柯、道、その他の官吏などから候補者を募集する。各人は元の称号と階級を保持する。)学校の政策を担当し、年次試験と科挙を実施する。彼はどこへ行っても教師や学者の質、学生の勤勉さを観察し、徳が高く有能な者を昇進させ、教えるのが下手な者を降格させた。改革があるときはいつでも、知事と知事がそれを実行します。 つまり、清代の教育監督は、省の教育と科挙を担当する副省級の官吏であり、その階級は転勤先の官吏の階級によって決定された。教育部第5位の郎中(現在の部局の行政レベルにほぼ相当)から六部第2位の士郎(現在の副省または部級の行政レベルにほぼ相当)まで、誰でもこの職に就くことができた。唯一の共通点は、教育長は2つのリストの進士である役人でなければならないということです。 しかし、地位も権力も定かでないこの高官級副省長は「あらゆる改革を監督し、実施する」という絶大な権力を有しており、教育や科挙などの具体的な問題では「最高指導者」の知事と直接対立することさえ可能であり、朝廷に提出された陳情書の中には、総督の署名が総督の署名よりも先に記されているものもあった。 清朝の教育長はなぜそのような権力と地位を持っていたのでしょうか? 1. 背景が強すぎる まず、教育長は北京の官僚で科挙に合格した上位2名の中から任命された。階級は固定されていなかったが、彼らは朝廷から任命された勅使であり、地方官僚とは根本的に異なっていた。つまり、天皇自らが任命し、天皇に直接責任を負うこの「勅使」は、基本的には省庁から地方に派遣される出向官に相当し、その経歴はあまりにも強力であった。 2. 未来は無限だ いわゆる「二つの壬氏名簿」とは、獣錬試験に合格した者の名簿がB名簿、壬氏試験に合格した者の名簿がA名簿であることを意味します。壬氏は両方の名簿に載っているため、この名前が付けられています。清朝の一般的な官僚選抜方法であったため、進士二名簿出身の官僚には無限の発展の余地があり、太書記などの国家級の官僚になる可能性が非常に高かった。清朝の教育長を務めた著名人の中では、張之洞が国家級官僚の鉄仁閣大書記に昇進し、冀小蘭が副国家級官僚の副書記に昇進した。 つまり、朝廷から地方に派遣されたこの官吏は、いつでも天皇によって都に呼び戻され、重要な仕事を任され、すぐに昇進する可能性があり、その権力と地位は国司を凌ぐ可能性が非常に高かったのです。この観点から見ると、教育長が知事と直接対決することを敢えてしたのは、「将来再び会うことができるように道を残す」という官僚の常套手段でもあった。 清朝の教育総監は省レベルの副指導者として省の教育と科挙を担当し、行政レベルでは五位下であったが、皇帝の使節であり、二科挙の合格者という身分が省レベルの行政単位における地位と影響力を直接決定づけた。まさにこの地方官僚間の相互抑制と監視のシステムこそが、清朝の300年近くにわたる実効的な統治を保証したのである。 |
<<: 「自国の奴隷よりも外国と友好関係を築きたい」と言ったのは誰ですか?私たちは皆、西太后を誤解していました!
>>: 樊遂と白起の間の対立はどのようにして起こったのでしょうか?歴史書に記された「復讐説」は信憑性があるか?
推薦する
邱楚基は何人殺したのですか?彼はなぜそんなことをしたのですか?
中国の長い歴史の中で、後世にその功績が讃えられ、その精神が尊敬される英雄は数多く存在します。しかし、...
『紅楼夢』で賈家の全員が先祖に供物を捧げていたのに、なぜ宝琴は参加したのですか?
「紅楼夢」の薛宝琴は誰もが好きな女の子です。今日は、面白い歴史の編集者が詳しく説明します〜 『紅楼夢...
五虎将軍の中で最も弱い武術家は誰ですか?諸葛亮はそれをどう評価したのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
水滸伝 第十九章 涼山沼の英雄が趙蓋を尊敬し、月夜の運城県で劉唐が逃げる
『水滸伝』は、元代末期から明代初期にかけて書かれた章立ての小説である。作者あるいは編者は、一般に施乃...
古代中国で漆器の工芸はいつ登場したのでしょうか?
様々な物の表面に漆を塗って作られた日用品や工芸品、美術品などを総称して「漆器」と呼びます。生漆は漆の...
何卓は亡き妻を懐かしみ、「江澄子」に匹敵する詩を書いた。
本日は、『Interesting History』の編集者が何朱の物語をお届けします。ご興味のある読...
「夏の夜の溜息」を鑑賞するには?著者は誰ですか?
夏の夜の溜息杜甫(唐代)一日が終わらない、暑さで腸が毒されている。何千マイルも離れたところから風が吹...
孟浩然の詩「呂少夫を秦に送る」の本来の意味を理解する
古代詩「呂少夫を秦に送る」時代: 唐代著者: 孟浩然楚関は、千マイル以上離れた秦国と面しています。県...
春秋時代の強大な国、晋はなぜ分裂したのか?主な理由は何ですか?
春秋時代の強大な晋はなぜ分裂したのか?その主な理由は何だったのか?興味のある読者は編集者をフォローし...
『紅楼夢』では、西仁は江玉漢と結婚し、とても幸せな結末を迎えます。
『紅楼夢』の華希仁は、王夫人に認められ、側室のような待遇を受けた最初の人物である。しかし、結局彼女は...
司馬炎の太康の繁栄の時代の背後には、西晋のどのような二つの大きな社会悪が隠されていたのでしょうか。
西晋初期には経済が急速に発展した。司馬炎の治世の号は太康であったため、この時代は太康繁栄と呼ばれた。...
古典文学の傑作「劉公安」第72章:汚れた寺院の力を探り、ロマンチックな売春婦を借りる
『劉公庵』は清代末期の劉雍の原型に基づく民間説話作品で、全106章から成っている。原作者は不明ですが...
『紅楼夢』の賈雲は何も持っていなかったが、なぜ最終的に恋愛でも仕事でも成功を収めたのだろうか?
「紅楼夢」の賈雲が何もなかったのに、なぜ仕事も恋愛も成功したのか知りたいですか?これはすべて彼の高い...
沼地の無法者たち(パート 1)の第 134 章: 政府軍を水上輸送するカタツムリ船、峠で石を投げるウォグア ハンマー
『水滸伝』は清代の作家于完春が口語で書いた長編英雄小説である。道光帝の治世6年(1826年)に起草さ...
水滸伝の歩兵十人のリーダーは誰ですか?彼らはどれくらい強いですか?
『水滸伝』は中国文学の四大傑作の一つで、英雄伝説を章立てで描いた長編小説です。多くの読者が気になる疑...