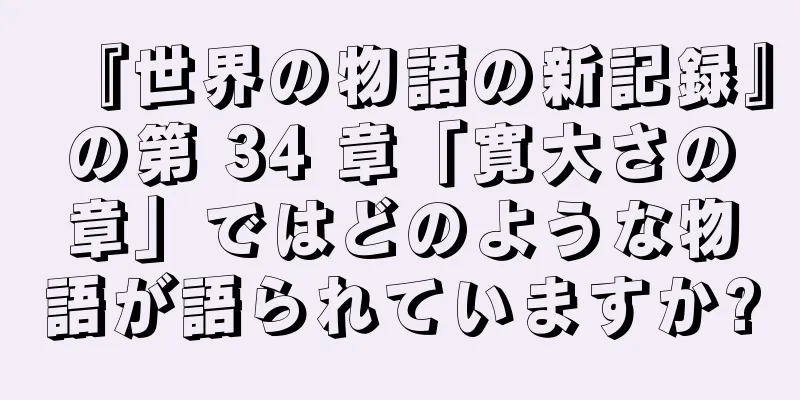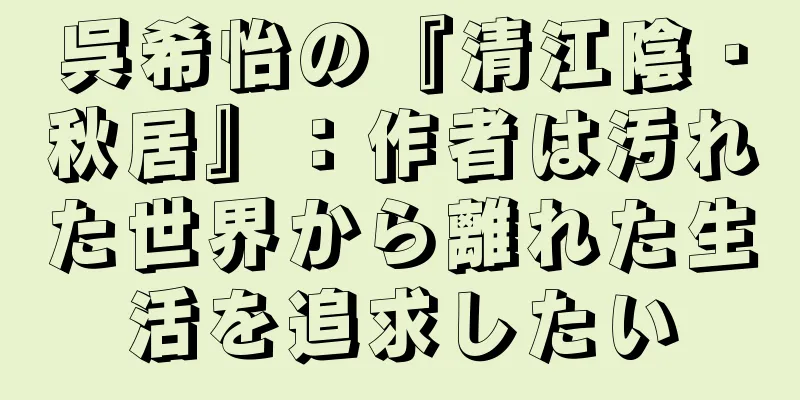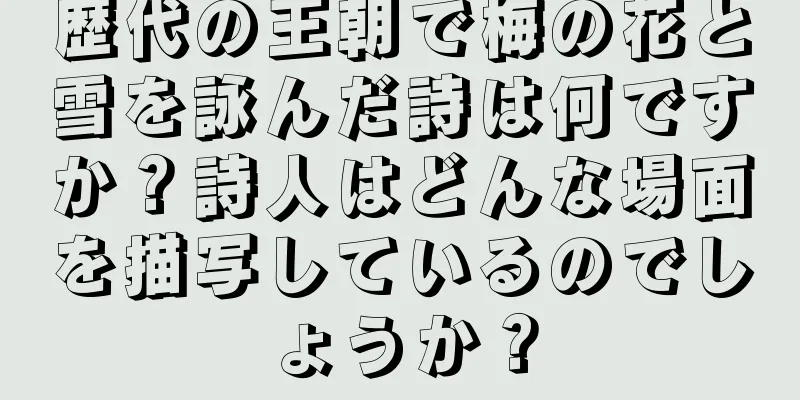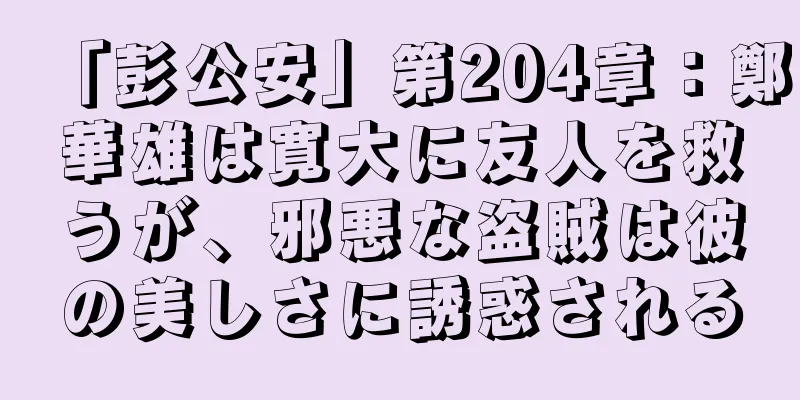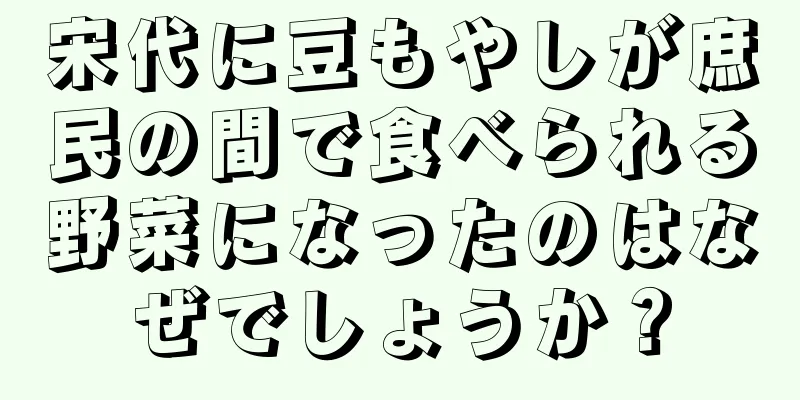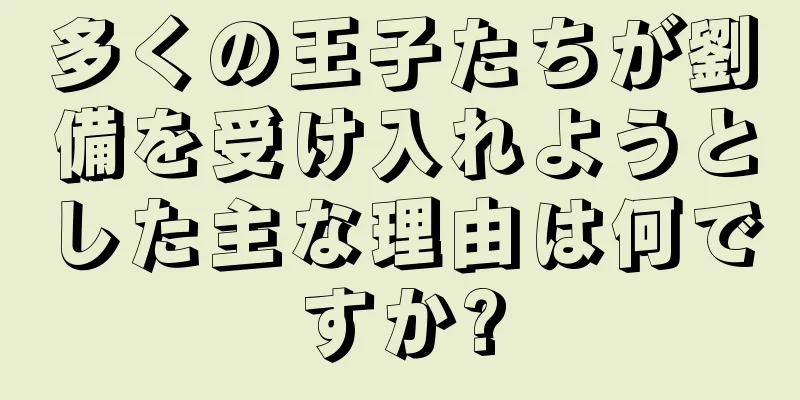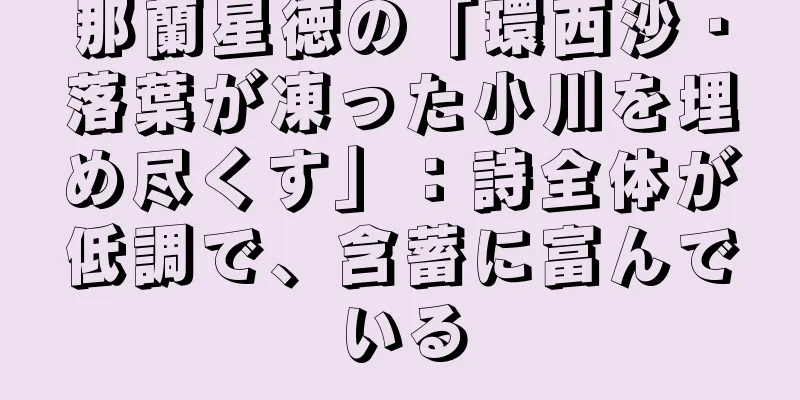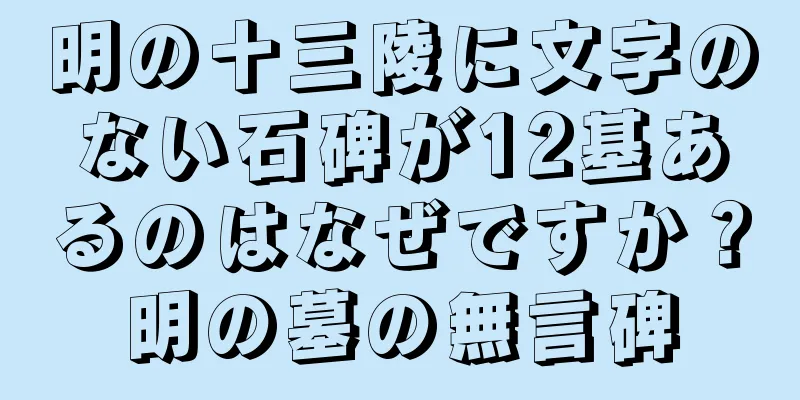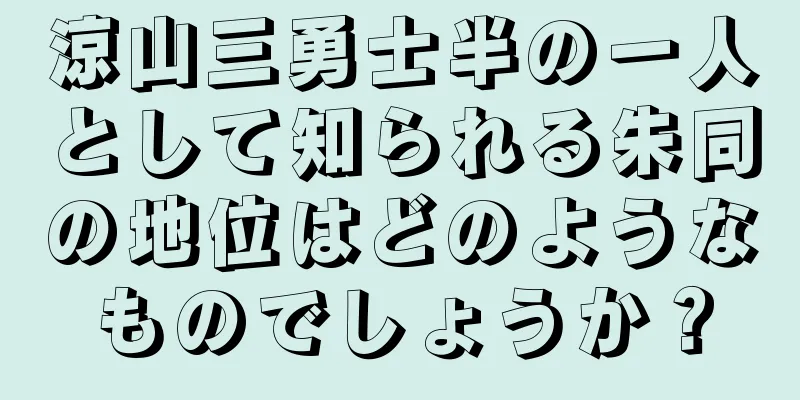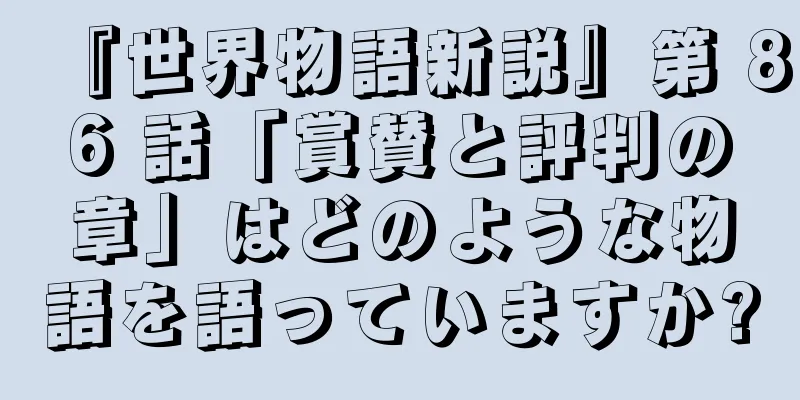古代の役人が「引退」した後、何が起こったのでしょうか?どのような人が退職して故郷に帰ることができるのでしょうか?
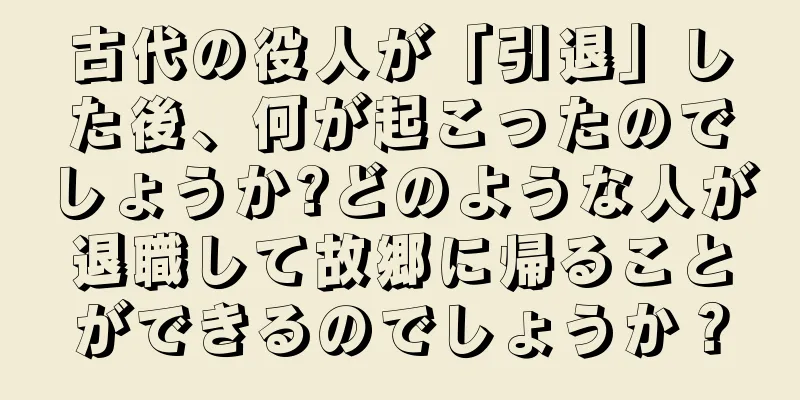
|
今日、Interesting History の編集者が古代の退職制度について紹介します。興味のある読者は編集者をフォローして見てください。 時代劇を見ていると、「隠居して帰る」という言葉をよく耳にします。 昔の役人は年老いたら「引退して家に帰る」ことができたのでしょうか?必ずしもそうではありませんでした。 さらに言えば、「引退して故郷に戻る」ということは、平穏に余生を送れるということなのでしょうか。必ずしもそうではなく、むしろ危険のほうが大きいかもしれません。 その理由について、ここでは「退職制度」としても知られる古代の退職制度について学んでみましょう。 「辞世」は、特に役人の退職を指す古い用語です。中国人は古来から「帰郷」を重視してきた。古代の官僚は健康上の理由から、一定の年齢に達すると自ら辞職し、故郷に戻って余生を楽しむのが一般的だった。 しかし、法定定年を迎えれば自然に退職する現代とは異なり、古代の官吏の退職条件は非常に厳しく、誰もが希望通りに帰国できるわけではありませんでした。 まず古代における「退職」の条件を見てみましょう。 (I)年齢要件 古代では、年齢は役人が引退するための主な条件でした。古代では、役人の定年に関する規定も同様で、一般的には70歳前後でした。 例えば、封建社会の最盛期であった隋・唐・宋の時代には、朝廷は官吏の定年を70歳と定めていたため、「官吏は70歳で定年退職すべきである」という諺がありました。 科学的な観点から見ると、現代においても、ほとんどの人は70歳までにすでにエネルギー、知性、体力を失っており、これでは公務の正常な遂行に支障が出るのは確実です。ましてや、平均寿命が70歳をはるかに下回っていた古代においてはなおさらです。 2. 身体の状態 古代では、70歳は「古希の老齢」であり、ほとんどの人はそれに達することができませんでした。「定年」まで生きるのは容易なことではなかったため、古代の官吏は定年退職すると自らを「骨乞い」と称しました。 古代では、さまざまな理由により、70歳未満で高齢になる人が多かった。そのため、「早期退職」という言葉があり、病気や体調不良により現在の職務を遂行できない役人は、70歳未満であっても早期退職を申請することができた。 例えば、明朝では「70歳未満で、公職に就くには高齢で体力が衰えている者も引退できる」と規定されていました。 古代、官吏と朝廷の関係は個人的な依存関係に近いものでした。朝廷が官吏の早期退職を認めたのは、官吏への配慮だけでなく、官吏のポストを空けて新鮮な人材を補充するためでもありました。 3. 強制退職 最初の 2 つの退職方法と比較すると、強制退職は間違いなく最も悲惨な方法です。 汚職や重大な失策で弾劾された役人もいたが、彼らの罪は刑事罰に値するほど重大ではなかった。このケースでは、彼らは退職して帰国するよう命じられた。 しかし、これはまともな退職方法ではないため、通常の退職に伴うさまざまなメリットを享受することはできません。 退職の3つの条件についてお話しした後で、「退職すべきなのに退職できない」という特殊な状況についてお話しします。 一般的に言えば、朝廷が頼りにする重要な役人や特別な才能を持つ大臣に対しては、皇帝は彼らの経験、資格、さらには権力さえも使って、統治のために朝廷に仕え続けなければならない。 したがって、歴史を振り返ると、次のような場面がよく見られます。一部の大臣が、年齢や健康などの理由で天皇に引退を申し出ましたが、天皇は彼らを留めようと懸命に努力し、引退の申し出を却下し、最終的にこれらの老大臣は在任中に老齢または病気で亡くなりました。 したがって、皇帝は古代の官吏が引退できるかどうかに関して「拒否権」を持っていました。 さて、次にお話ししたいのは、古代の官吏が無事に引退できたのであれば、「故郷に帰って」余生を穏やかに過ごすことができたのかということです。それは難しいですね。 古代の官吏は引退後どこへ行ったのでしょうか? 1. 首都に滞在する 古代では、役人が引退しても、それが一般人になったことを意味しませんでした。定年制度の円滑な実施を促すため、朝廷は通常、定年退職した官吏に「光禄大夫」や「建一大夫」などの名誉官職を与えたり、皇帝の顧問として引き続き務め、朝廷の意思決定に参加することを認めるなど、一連の奨励政策を実施している。 唐代の玄宗皇帝の治世中には、退役した官吏が軍事や国家の事柄に引き続き参加できるよう、月に2回朝廷に出廷することが許可されていたほどであった。 何人かの古い大臣は、その才能により皇帝に再雇用され、再び重要な地位に就くことになる。 例えば、唐代初期、名将李靖が退役した後、国境の緊急事態のため、李世民は彼を西北に派遣して国のために働かせました。北宋の名官、文延博は77歳で引退した。宋の哲宗の時代に再び引退から復帰し、要職に就いた。84歳で2度目の引退。 都に留まる必要のある他の役人については、朝廷が何らかの手配をしなければならなかった。例えば、宋代には道教の特別な「宮」という機関があり、そこでは引退した役人が宮廷や寺院の使者、副使、その他の役職を務めていた。 2. 出身地への帰還 昔は、定年後も引き続き役職に就くことができた役人はほんのわずかでした。役人の多くは定年後に故郷に戻らなければならず、故郷に戻りたくない場合は特別に申請しなければならない。しかし、故郷に帰れたとしても、すべてがうまくいくというわけではありません。彼らを待ち受けているものはまだ不明かもしれない。 なぜなら、退職官僚はもともと特権階級であり、彼らが喜んで権力を手放すためには、裁判所が退職後の経済的、政治的待遇を保証しなければならないからである。 都の皇帝にとって最も恐れられたのは、引退した官僚たちが、かつての人脈と朝廷から与えられた権力を利用して、別の精神で「余力」を発揮し続け、地方の政務に影響力を及ぼし、私利私欲のために不正行為を行い、朝廷の統治秩序を乱すことだった。 その結果、退職公務員に対する監督措置は、主に以下のような内容を含めて厳格化が進んでいます。 まず、退職した公務員は帰郷後、必ず地方自治体に登録しなければならないと規定されている。これは名目上は弔問のためだが、実際は地方の監督を容易にするためである。 第二に、地方政府は退職した公務員を厳しく管理する義務を負い、彼らの日常の通信や交友関係を記録し、違法行為があった場合には速やかに裁判所に報告して処罰しなければならないとされた。 3つ目は、朝廷使節の「特別な配慮」です。朝廷は、退職官僚が地方当局と結託し、政府に実態が伝えられないと懸念する場合は、特使を派遣して監視や査察を行う。 例えば、明代初期、人事大臣の武林が引退した後、朱元璋はわざわざ使節を派遣して彼の故郷を秘密裏に訪問した。武林が少しも傲慢ではなく、畑の老農民に名前で呼ばれることさえあると聞いて、朱元璋は安心し、武林の善良な性格を褒めた。 「天下の物はすべて王のものであり、四方の海中の物はすべて王の臣下である。」封建時代、役人は引退しても、依然として王の意志の下で生きなければならなかったことがわかります。 |
<<: 時代劇における「宮中の三人の妾」とは何ですか? 「宮中の三人の女官」の地位はどのようなものでしょうか?
>>: モンゴルは明朝の国境を絶えず侵略していました。清朝が成立した後、侵略が止まったのはなぜですか?
推薦する
『王江南:三日月頌』の原文は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
王江南:三日月への頌歌那蘭興徳(清朝)八月八日には鏡の半分が青空に上がります。彼女は何も言わずに絵の...
古典文学の傑作『前漢演義』第82章:張子芳の悲しい歌
『西漢志演義』と『東漢志演義』は、もともと『江暁閣批判東西漢通志演義』というタイトルで、明代の中山の...
古代の二重姓は現在でもどれだけ受け継がれているのでしょうか?なぜそのほとんどが消えてしまったのでしょうか?
古代の二重姓は現在でもどれだけ伝承されているのでしょうか。なぜその多くが消滅してしまったのでしょうか...
『西遊記』の初期の唐代の守護者、劉伯珍とは誰ですか?
『西遊記』には知られていない小さな登場人物がたくさんいます。読者は彼らがいつ登場したのかさえ知りませ...
葉孟徳の「水の旋律・秋の色は徐々に遅く近づいている」:詩全体に愛国心と人民への思いやりが溢れている
葉孟徳(1077年 - 1148年8月17日)は、雅号邵雲としても知られ、蘇州常熟の出身である。彼の...
明代の読書本『遊学瓊林』:第2巻:老若男女の誕生日、全文と翻訳と注釈付き
『遊学瓊林』は、程雲生が書いた古代中国の子供向けの啓蒙書です。 『遊学瓊林』は、明代に西昌の程登基(...
『紅楼夢』で、賈おばあさんは林黛玉を賈邸に連れてきたことを後悔していましたか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
杜甫の最もシンプルな詩:「再び武朗に贈る」の鑑賞
以下、Interesting History の編集者が、杜甫の「再び武朗に贈る」の原文と評価をお届...
尹坑の「雪中梅」:冷たい風に立ち向かい、誇らしげに雪を舞う梅の姿を歌う
尹坑(511年頃 - 563年頃)、号は子建、武威郡古蔵(現在の甘粛省武威市)の出身。南北朝時代の梁...
七剣十三英雄第60章:徐明高が二度目に寧王の邸宅を訪問、朱晨昊が反乱を起こし戦争に訴える
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
古代の皇帝は後継者がいなかったとき、どうやって次の皇帝を選んだのでしょうか?
秦の始皇帝が六国を統一し皇帝を名乗って以来、中国には83の王朝があり、408人の皇帝がいました。今日...
もし孫権が生きた関羽を曹操に渡したらどうなるでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『楽山堂コレクション』には何が書いてあるのですか?洪礼はなぜ雍正8年にこの本を出版しようとしたのでしょうか?
「楽山堂コレクション」とは何かご存知ですか?次は、Interesting Historyの編集者が解...
「12階建て」:3階と2階:巣でも強盗でもない、突然奇妙な略奪品が見つかり、家族が元の持ち主に返還されることを望む
『十二塔』は、明代末期から清代初期の作家・劇作家である李毓が章立てで書いた中国語の短編集です。12巻...
「どんなに素晴らしい料理でも、肉は繊細である」唐代の多様な食文化はどのようにして生まれたのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、唐代の多様な食文化を皆さんにご紹介し、皆さ...