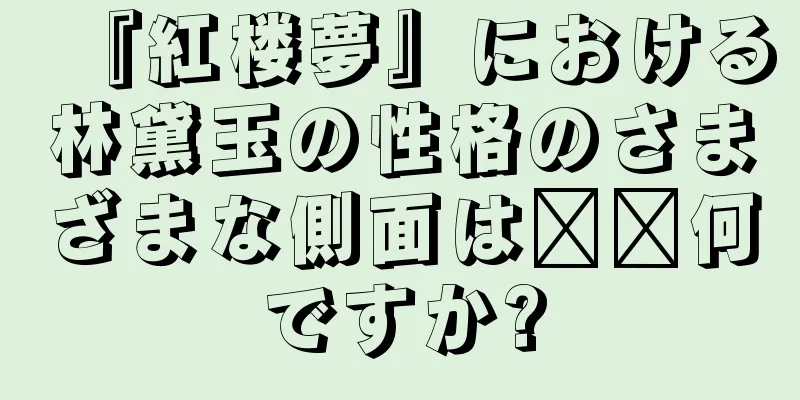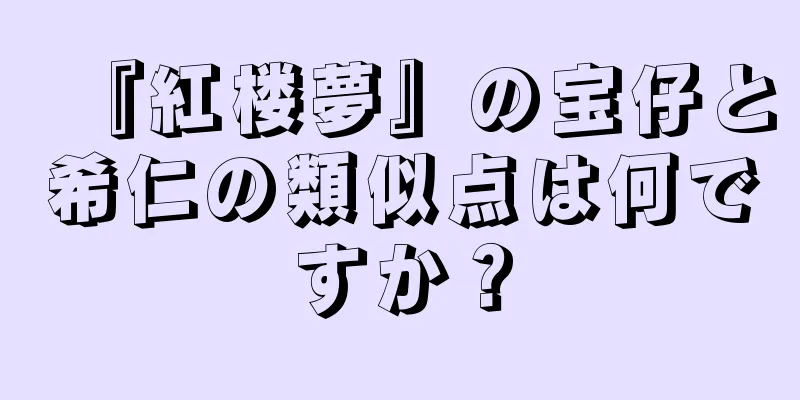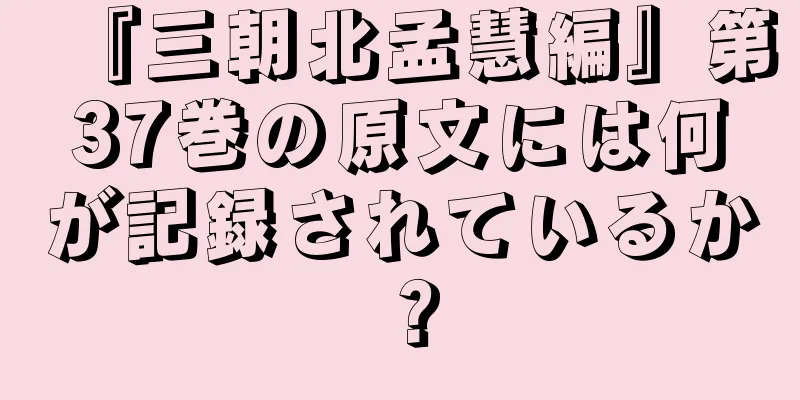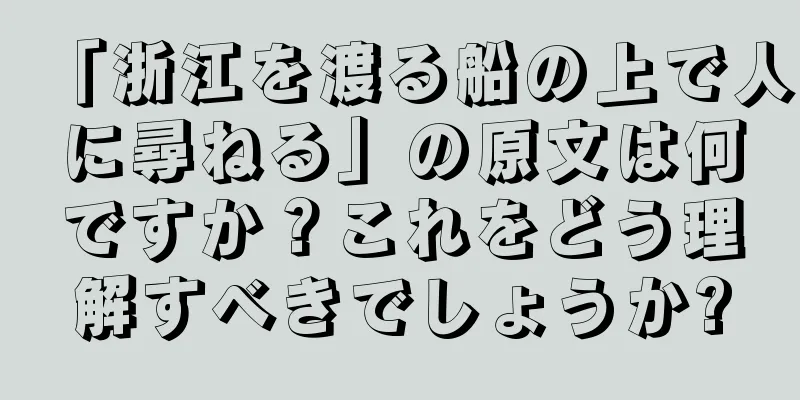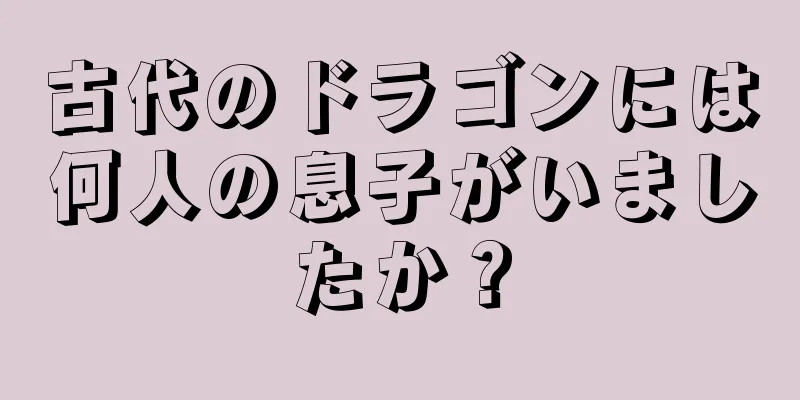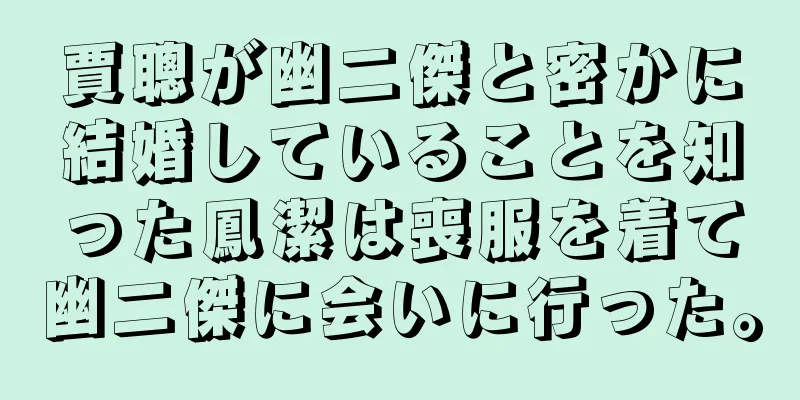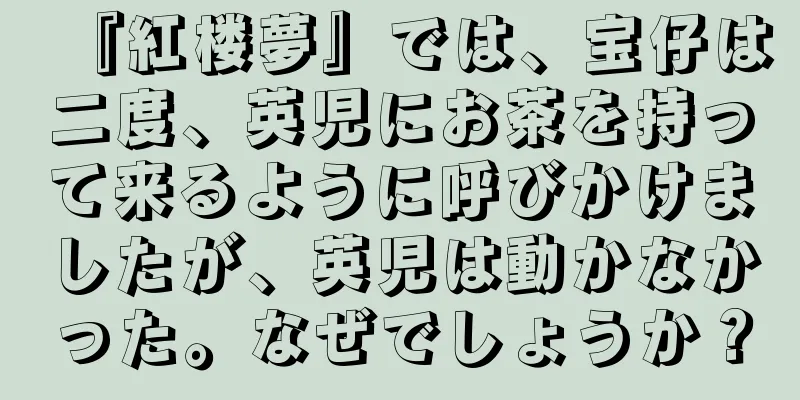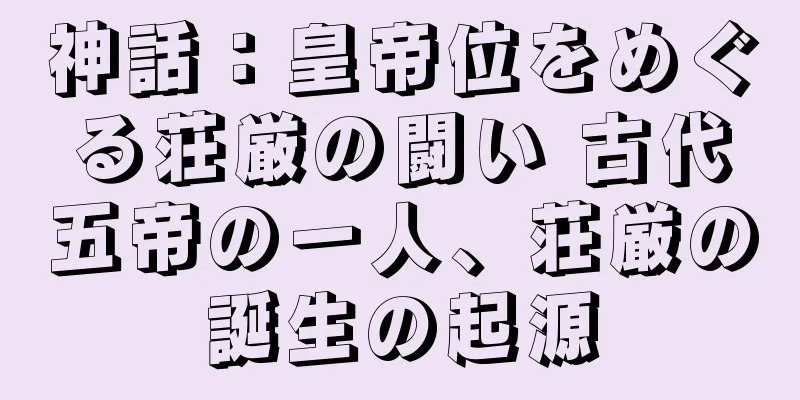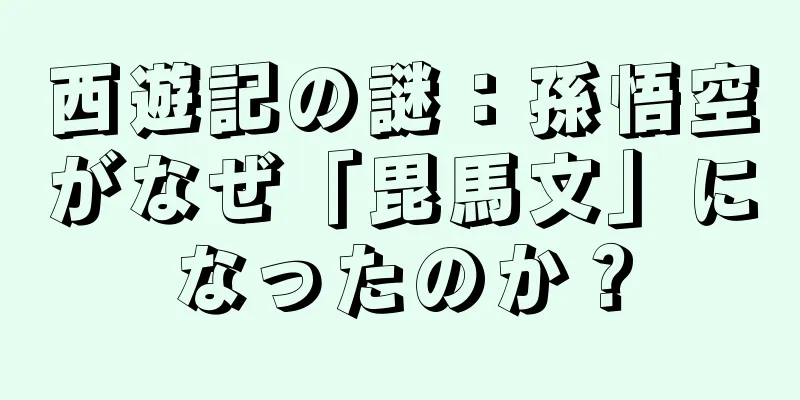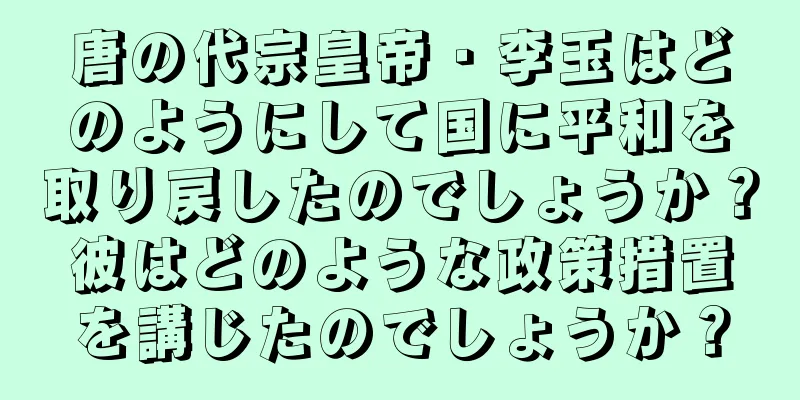黄河の名前の由来は何ですか?黄河に関する民間伝説にはどのようなものがありますか?
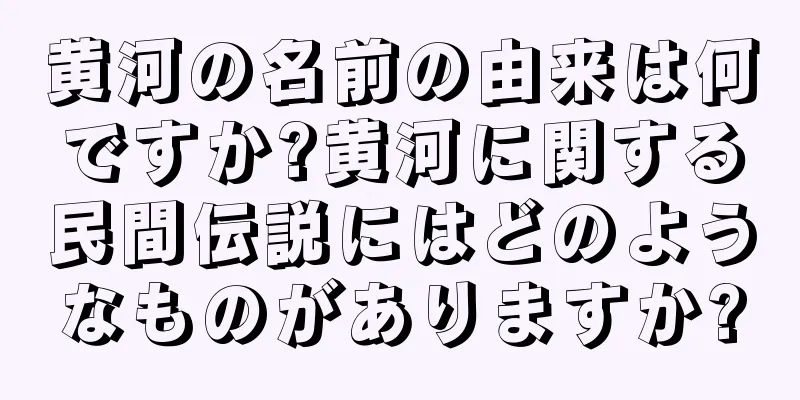
|
黄河に関する民間伝説をご存知ですか? 知らなくても大丈夫です。Interesting History の編集者がお教えします。 昔々、黄和という名の若者がいました。彼は非常にハンサムで、獰猛な馬に乗り、強い弓を引き、百歩離れたところから的を射抜くことができました。 黄和は毎朝馬に乗って狩りに出かけました。彼は裕福な家庭の庭の前を通り過ぎた。 その日、狩りから戻って来た彼は、再び庭の前を通りかかり、壁に座って微笑みながら彼を見ている18歳か19歳くらいの少女を見ました。少女はブレスレットを投げ捨てて壁の後ろに隠れた。 黄和は馬から飛び降りてブレスレットを拾い上げ、まさに妖精に会ったのだと思った。 それ以来、彼は庭を通るたびに上を見上げるようになった。しかし、壁の花の枝以外、少女の姿は見えなかった。 半月後のある日、黄和は狩りから遅く帰ってきました。私たちが庭に近づいたとき、突然、道端から男が現れました。黄和はそれが少女だと知って、とても喜びました。少女は父親に内緒で彼に会いに来たと話した。二人は長い間話をした後、しぶしぶ別れを告げた。 翌日、デートの日が来たが、その女の子は現れなかった。 10日以上もの間、黄和は再びその少女に会うことはなかった。調べてみると、金持ちの男はその件を知っていて、娘を監禁していたことが判明した。これを聞いた黄和は、「たとえ世界がひっくり返っても、娘を救い出す」と誓った。役人は黄和を怒らせることを恐れ、難題を出した。人々に、門の前に棚を設け、銅貨を掛け、あらゆるところに張り紙を貼らせた。百歩先からその銅貨の目に矢を射込めた者は、自分の娘と結婚できるというのだ。その知らせが広まると、人々は次々とやって来た。しかし、誰もお金の目に矢を射ることはできなかった。 黄和は出てきて弓を引き、矢を放ち、貨幣の穴を正確に射抜いた。役人はまた、黄和の2番目の矢が前の矢を押し出すことを要求し、黄和はそれを実行しました。すると役人はもう一つの難問を出し、百歩先の黄河から銅貨を射落とすだけでなく、地面に落とさずにその銅貨をキャッチするようにと命じた。 この時、傍観者でさえも審判が故意に不正行為をしていたことを知っていた。黄河は怒りに満ち、矢が官吏に向かって飛んでいった。 官吏は若い頃に武術を習っていたので、首を回して矢を避けました。そして、官吏が捕まえに来たら黄何は逃げてしまうのではないかと恐れ、部下に黄何の捕獲を命じました。彼は少女を救出に行く前に、深い山や森で武術の練習をすることにした。 1年後、黄和は剣の技を習得し、少女を救出するために出発しました。 昼にお腹が空いたので、一本の矢で大きな鳥を撃ち落としました。 大鳥は黄和に、金持ちの男が自分の娘を金持ちの男と結婚させるよう強要したので、娘は怒りのあまりビルから飛び降りたのだと話しました。 飛び降りる前に、彼女は「黄河!黄河!黄河…」と叫んだ。黄河はこれを聞いて、まるで山が崩れ落ちたような衝撃を受け、地面に座り込み、涙が泉のように流れ出た。 大鳥は驚いて空に飛び立ちました。下を見ると、黄河の涙が東へ流れる大河に変わっていました。黄河は「黄河」になりました!黄河の水は常に波立っています。 人々は黄河が恨みに満ちていて、少女を救うためにいつも村に近づきたいと言っていました。 |
<<: 西湖龍井に関する伝説は何ですか?西湖龍井はどの皇帝と関係があるのでしょうか?
>>: 宝公の奇怪な事件とは何ですか?結局、バオゴンは事件を解決したのでしょうか?
推薦する
王覇の伝記:東漢の有名な将軍、王覇の生涯
王覇(?-59年)、愛称は袁伯、殷川県殷陽(現在の河南省許昌の西)出身の漢人。東漢の将軍であり、雲台...
『神授説』で神を授ける大義は、なぜ人間関係と世俗的な知恵の問題であると言われているのでしょうか。
『冊封』の冊封の大業はなぜ人間関係や世俗の駆け引きだと言われているのでしょうか?冊封の戦いを見ると、...
『二科派安経記』には何が書いてあるのですか?市場の法則は古代から存在していたのです!
今日、Interesting History の編集者は、皆さんのお役に立てればと願いながら、古代の...
ファン・ユンの「文学に別れを告げる別れの詩」
范靼(451-503)、号は延龍、南郷武隠(現在の河南省碧陽県の北西)の出身で、南朝時代の作家である...
軍事著作「百戦百策」第2巻:全文と翻訳注
『百戦奇略』(原題『百戦奇法』)は、主に戦闘の原理と方法について論じた古代の軍事理論書であり、宋代以...
白露節気中にはどんな習慣がありますか?白鹿の「三つの兆し」とは何を意味するのでしょうか?
白鹿は二十四節気のうち15番目の節気であり、自然界の寒気が増すことを反映する重要な節気です。次の I...
明代志農(選集):言語と知恵、魏徴、全文と翻訳注釈
『シンクタンク全集』は、明の天啓6年(1626年)に初めて編纂された。この本には、秦以前の時代から明...
太子婿の官職について言えば、それは郭堅が傅宰に降伏したこととどのような関係があるのでしょうか?
太子西馬という官職の本来の意味は「西馬王子」であり、正しくは「仙馬」と発音する。しかし、馬を洗う役人...
沼地の無法者(パート1)第136章:万子城の副盗賊が捕らえられ、中義殿の司令官が盗賊を調査する
『水滸伝』は清代の作家于完春が口語で書いた長編英雄小説である。道光帝の治世6年(1826年)に起草さ...
七人の剣士と十三人の英雄 第101話: 三度の計画と傲慢な兵士の敗北、そして一つの命令で戦いに勝つ
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...
『紅楼夢』で賈蘭の存在感が低いのはなぜですか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
宋代の名詩を鑑賞する:寒い春に酒を飲み、朝の夢にオリオールの鳴き声を聞く
呉文英(1200年頃 - 1260年頃)は、雅号を君特、号を孟荘といい、晩年は妓翁とも呼ばれた。思明...
水滸伝で桓真はどのように亡くなりましたか?彼の歴史的評価はどのようなものですか?
杰珍はどうやって死んだのですか?彼らが道路上で待ち伏せしていた2人の兵士に遭遇したのは、ちょうど最初...
馬超と張飛はかつて戦ったことがある。二人が死ぬまで戦ったら、どちらが勝つだろうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
西遊記で孫悟空が生まれたときの不思議な現象とは何ですか?玉皇大帝はなぜ最後に彼を解放したのでしょうか?
孫悟空は中国の有名な神話上の人物の一人で、四大古典の一つである『西遊記』に登場します。 Intere...