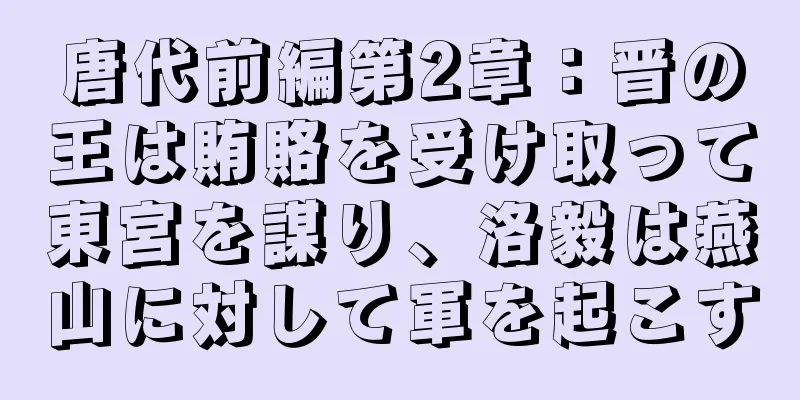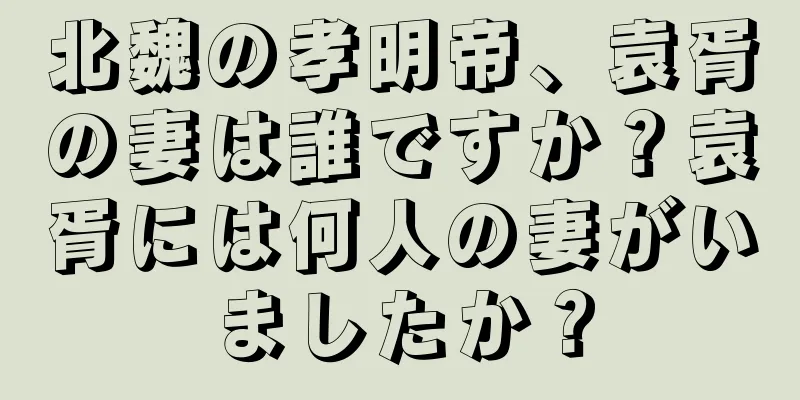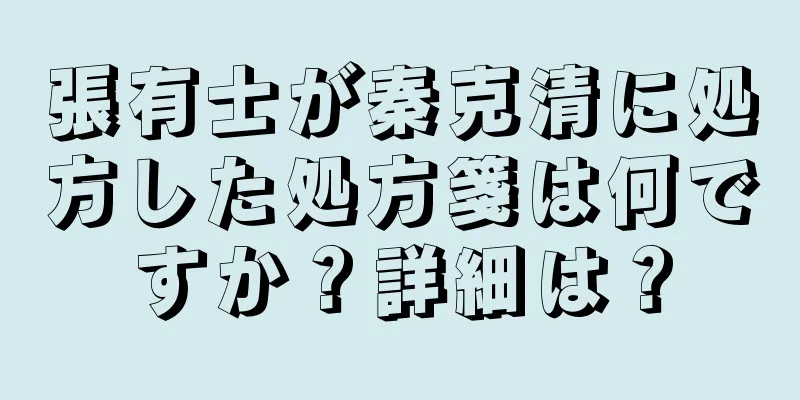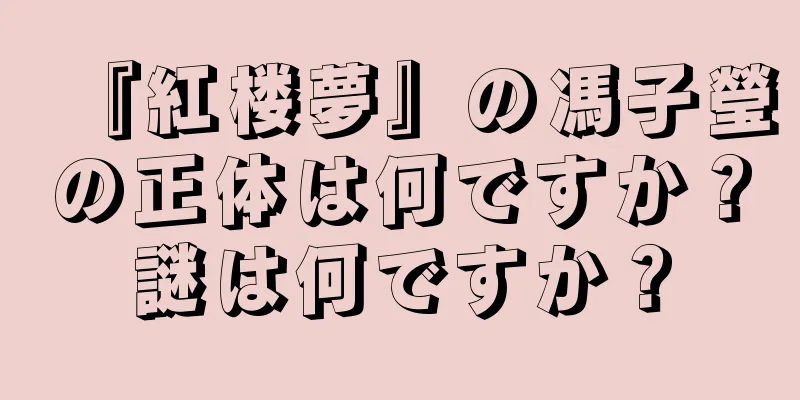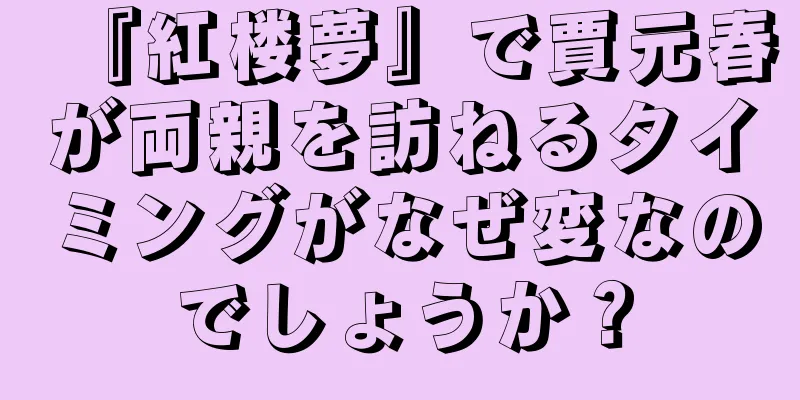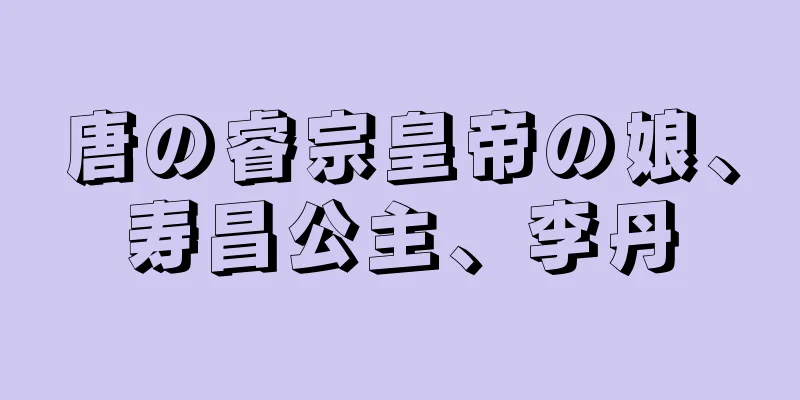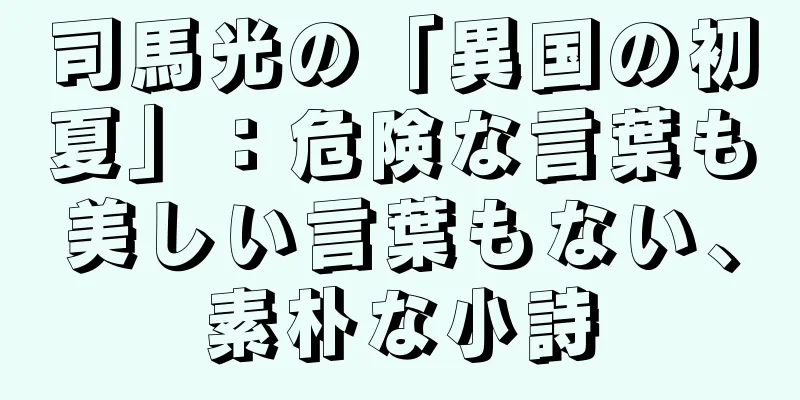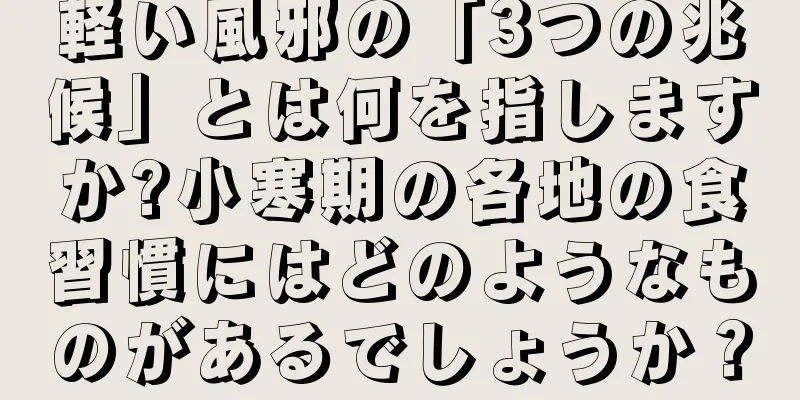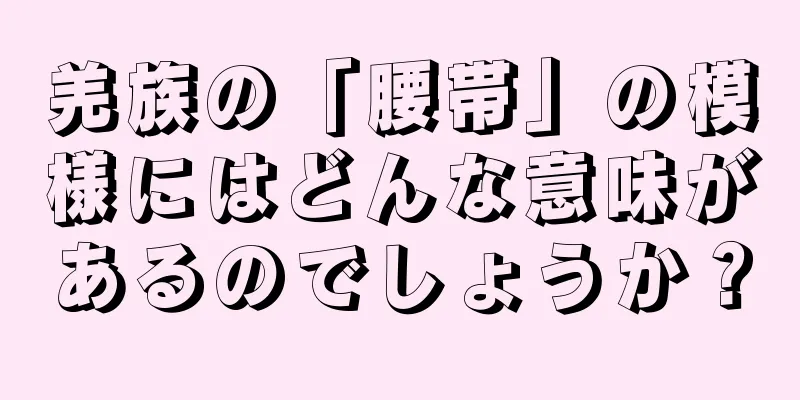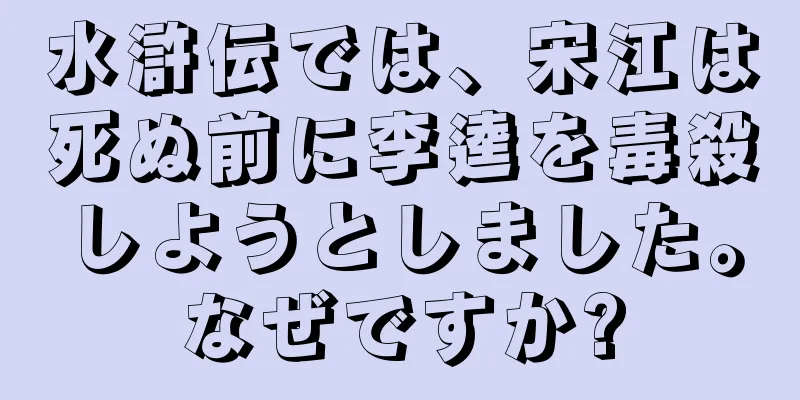戌亥は戦国時代から漢・三国時代にかけてどのように発展し、変化したのでしょうか?
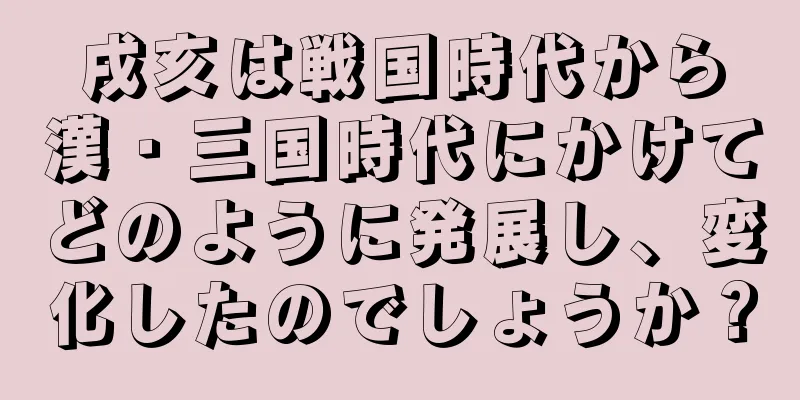
|
蹴球は「大蹴球」「蹴球」「蹴院」「竹球」「鉄院」とも呼ばれ、現代のサッカーと同様に、古代人が足でボールを蹴ったり、踏んだり、蹴ったりする動作を指します。托鉢の発展は長い過程を経ており、黄帝の時代に始まり、漢・唐の時代に発展し、宋代に栄え、明・清の時代に衰退したと言われています。次に、戦国時代、漢代、三国時代における托鉢の発展と変化についてお話しします。 中国の枷の起源についてはさまざまな意見があります。伝説によると、枷は黄帝によって作られたと言われています。黄帝は蚩尤の部族を倒した後、蚩尤を捕らえ、その腹を取り出し、髪の毛を詰めて、兵士たちにボールとして蹴らせたと言われています。それ以来、彼らは戦争に勝利すると、敵の腹を取り出し、ボールのように蹴り飛ばして部族の戦闘力を示すようになった。しかし、黄帝と蚩尤は古代の伝説上の人物であり、現在ではその出来事の信憑性を検証することは不可能である。 蹴球の最も古い歴史記録は戦国時代ですが、当時古代蹴球は「大蹴球」と呼ばれていました。 『戦国兵法 斉兵法』には斉の首都臨淄の人々の暮らしが次のように記されている。「臨淄には7万戸あり…非常に裕福で繁栄しており、人々はみな竽、琴、鼓を弾き、鶏を闘わせ、犬を走らせ、六伯、蹋球を遊ぶことができる。」この一節は後の『史記 蘇秦伝』にも登場している。このことから、当時の斉ではすでに蹴球というスポーツが発達していたことがわかります。当時のボールの構造は非常にシンプルで、主に動物の毛を丸めてボールにし、その外側に革を縫い付けてボールの形にしていました。特別な技術や機会を必要としないため、人々の参加度が高く、斉の人々の夕食後の娯楽となっています。 「蹴鞠」という言葉が初めて登場したのは『史記 扁鵲・蒼公伝』である。この本には、西漢の項楚が「蹴鞠」に執着し、重病の時も密かに蹴鞠を弾いていたと書かれている。彼は最後に血を吐いて死んだ。その後、「沐居」は『漢書』に何度も登場する。 秦以前の時代には、枡菊は一部の地域の人々の間でのみ愛されていましたが、漢、魏、晋の時代には枡菊は広く普及し始めました。漢の時代は枡菊の発展の最初のピークでした。国境付近の異民族による長期にわたる嫌がらせと「強きがゆえに漢が滅ぶ」という好戦的な文化のため、漢代の歴代皇帝は兵士の軍事訓練を非常に重視し、兵士の体力、スピード、持久力、柔軟性に対する新たな要求を提唱した。蹴鞠は手足の運動スポーツとしても利用されており、現在では軍隊でも効果的な軍事訓練法として広く利用されています。 『漢書・霍去兵伝』には、名将霍去兵が兵の訓練に蹴鞠を使ったという記録もある。「蹴鞠が万里の長城の外にいた時、兵士たちは食糧が不足し、前進できない者もいたが、蹴鞠はそれでも野原で蹴鞠をしていた。」『漢書』の中で、班固は蹴鞠を兵の訓練法として挙げ、「軍事技術」とみなしていた。 三国時代、『淮集典録』によると、「三国は常に戦乱が続いており、毎年戦争が激化していた。皇帝は弓術と乗馬を重視し、各家庭で弓術を学んでいた」と記されている。三国時代は戦争が絶えず、弓術と乗馬が最優先され、各家庭で弓術が学ばれていたことから、弓術がいかに人気があったかがわかる。魏の曹操は楔居を非常に愛していました。その息子の曹植は楔居に関する傑作『明度篇』を著し、後世にとって重要な意義を持っています。 |
<<: 景勝期には気候はどのように変化するのでしょうか?啓蟄の三つの兆候は何を意味しますか?
>>: 唐代に托鉢はどれほど人気があったのでしょうか?唐代の托鉢文化の特徴は何ですか?
推薦する
唐の玄宗皇帝の皇后李塵は誰ですか?唐の玄宗皇帝の皇后袁昭の簡単な紹介
袁昭皇后(姓は超)は、唐の玄宗皇帝李懿の側室であり、唐の懿宗皇帝李毓の生母であった。彼は若い頃、光麗...
杜甫の最もシンプルな詩:「再び武朗に贈る」の鑑賞
以下、Interesting History の編集者が、杜甫の「再び武朗に贈る」の原文と評価をお届...
前秦の隻眼の暴君、傅勝とはどんな人物だったのか?歴史は傅勝をどのように評価しているのだろうか?
傅勝(335-357)、号は長勝、洛陽臨衛(現在の甘粛秦安)の出身。ディ族に属し、前秦の景明帝傅堅の...
鏡の中の花 第51話: 孝行娘は食べ物がなくなり、生き残る方法を見つけました。妖精は彼女に米を差し出しました
『鏡花』は清代の学者、李如真が書いた長編小説で、全100章からなり、『西遊記』『冊封』『唐人奇譚』な...
唐代の官僚はどのようにして階級に分かれていたのでしょうか?給料はいくらですか?
今日は、興味深い歴史の編集者が唐代の官僚の階級と給料についての記事をお届けします。ぜひお読みください...
秦観の最も古典的なエロティックな詩を読んだことがありますか?
唐代末期から五代にかけて、戯は次第に料亭や歌宴の娯楽となり、その多くは遊女や歌姫によって歌われ、必然...
三国志に登場する24人の有名な将軍のうち、曹操陣営に属するのは誰でしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 財務省の役人』はどんな物語を語るのでしょうか?原文はどのようなものですか?
中国のスタジオからの奇妙な物語の「会計係」の原文鄒平の張華東[1]は南越山に供物を捧げるよう命じられ...
サラール地方の慣習 サラール地方の人々の特別な結婚の慣習は何ですか?
サラール族は一夫一婦制を実践しています。解放以前の結婚にはいくつかの特徴がありました。第一に、男性に...
『紅楼夢』で賈容は秦克青に対してどのような感情を抱いているのでしょうか?
賈容と秦克清という若いカップルは、『紅楼夢』の中で最も奇妙なカップルであるはずです。これは今日、In...
宝玉が黛玉の部屋で洗濯したり着替えたりしているのを見たとき、希仁の態度はどうだったでしょうか?なぜ怒っているのですか?
みなさんこんにちは。Interesting Historyの編集者です。今日はXirenの物語をお話...
酔僧の正体は何ですか?天龍八卦のどこに登場しますか?
この記事では、金庸の作品に登場する非常に謎めいたキャラクター、「酔僧」についてお話します。酔僧に関し...
劉邦が西漢を建国した後、六国の老貴族たちはなぜ沈黙していたのか?
項羽は関中に入った後、18人の王子を封建制にしました。しかし、1年も経たないうちに、世は混乱し、英雄...
なぜ阮小武は「短命の武郎」ではなく「短命の二郎」と呼ばれているのでしょうか?
なぜ阮小武は「短命の武郎」ではなく「短命の二郎」と呼ばれているのでしょうか?短命の二郎阮小武、これは...
『中国のスタジオからの奇妙な物語 - 不当な投獄の章』はどんな物語を語っていますか?原文はどのようなものですか?
「不当な監禁」の原文(中国のスタジオからの奇妙な物語より)朱氏は楊谷[1]出身である。その若者は軽薄...