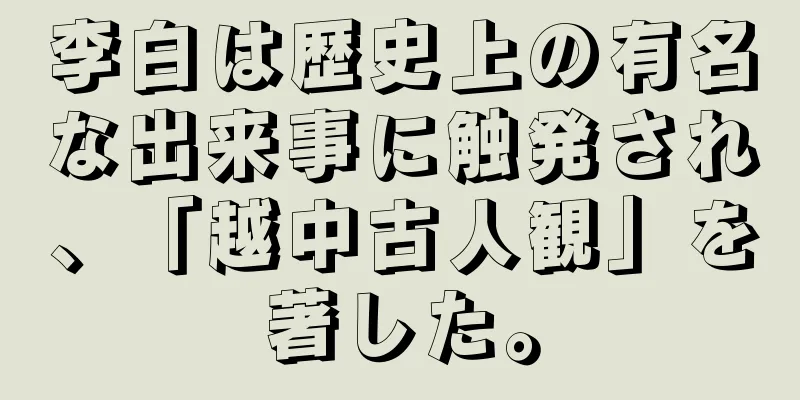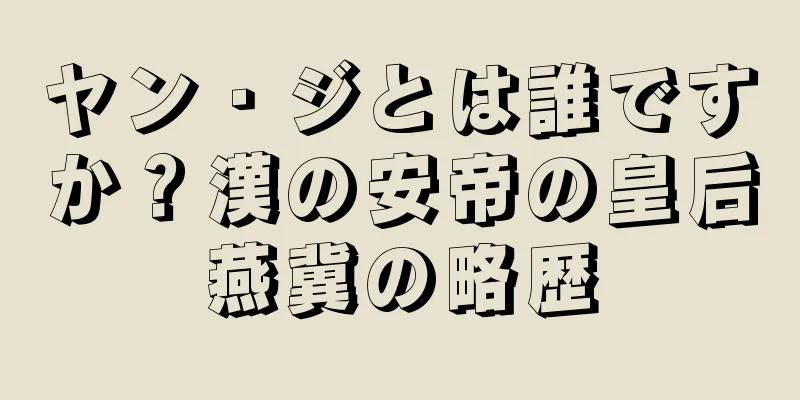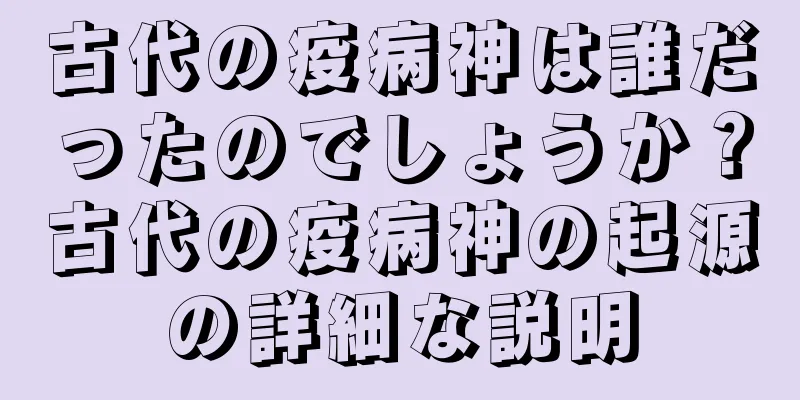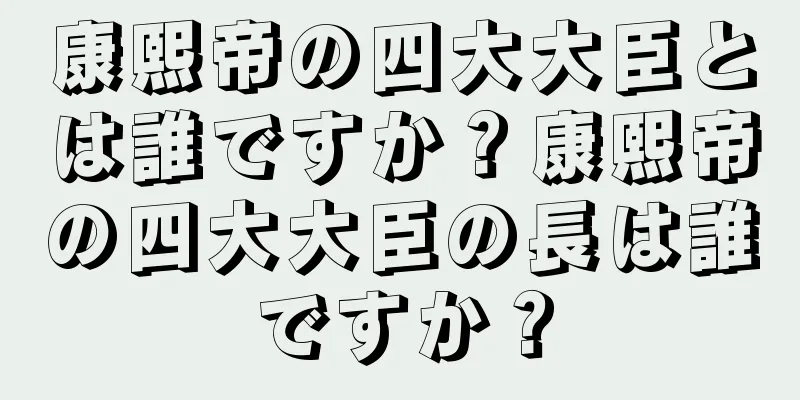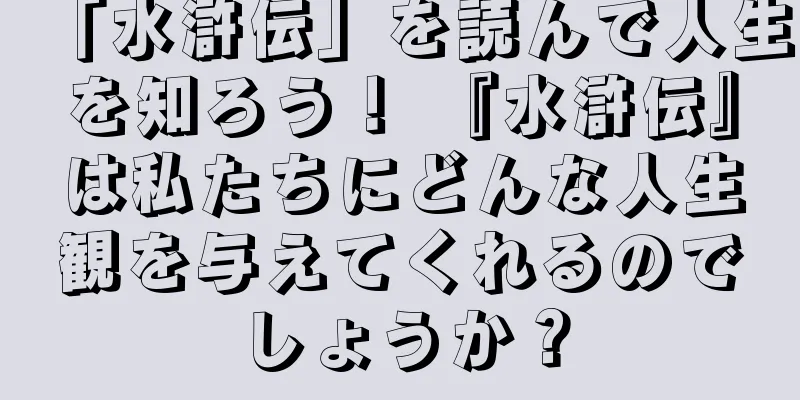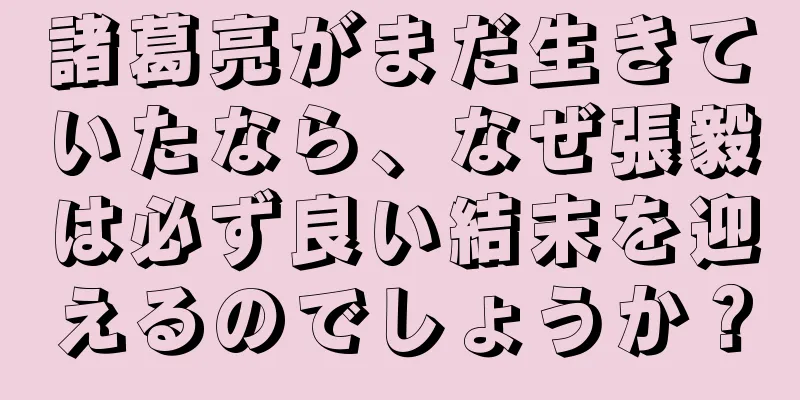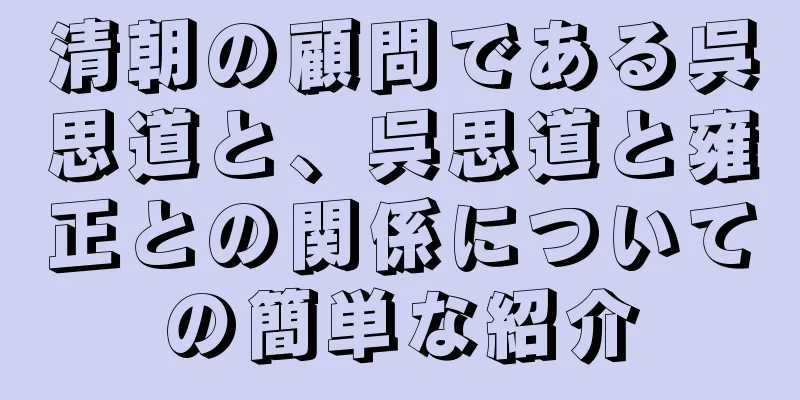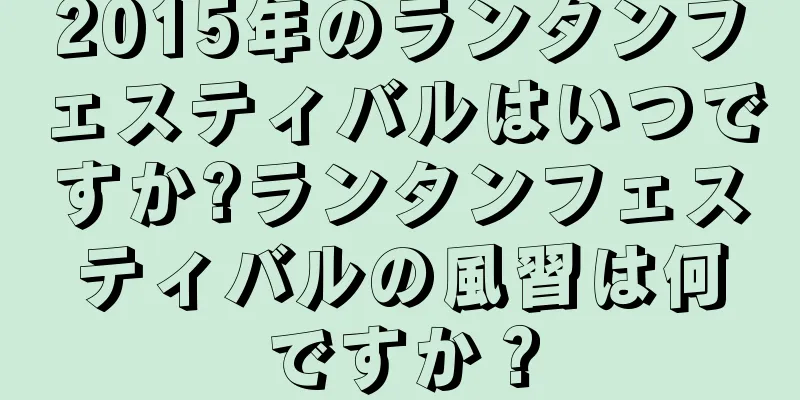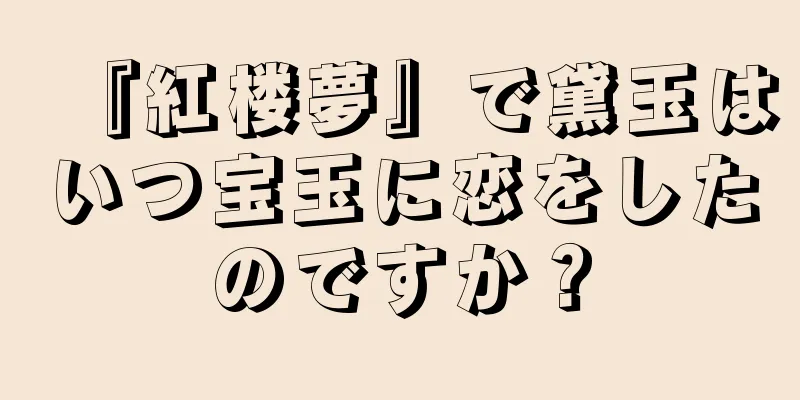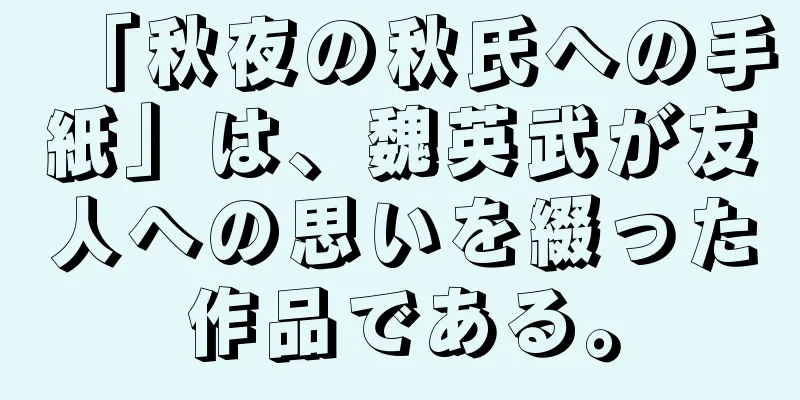美しかった西施の最後はどうなったのでしょうか?西施に関する6つの主な伝説は何ですか?
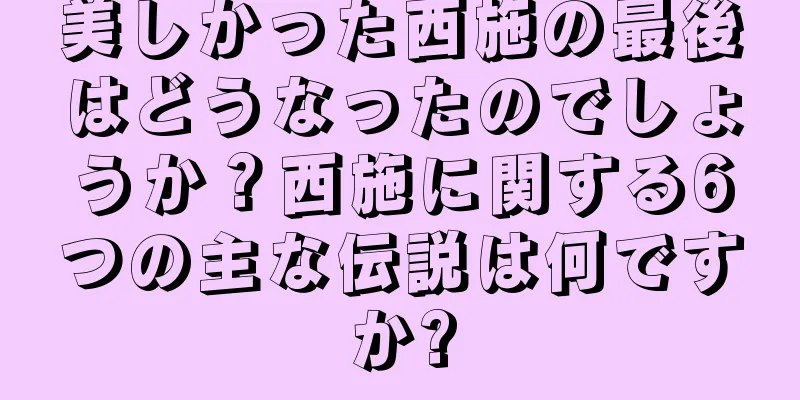
|
呉越紛争の煙が晴れた後、後世には美女西施の最期について様々な伝説が残されています。まとめると、主に以下の6種類があります。次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けします。見てみましょう! 1. 罪悪感から自殺したという説 いくつかの脚本やドラマで演じられた筋書きでは、西施が越国を助けて呉国を滅ぼした後、満足感を覚え、使命を果たしたとされています。その一方で、呉の夫差王に対して罪悪感と同情心も抱いており、極めて矛盾した心理状態に陥り、そこから抜け出すことができず、ついには官娃宮で首を吊って自殺した。 2. ファン・リーに連れ去られる この見解は非常に人気があり、古代の書物にも記録されています。東漢の人々が書いた『越境書』には、「呉が滅んだ後、西施は范蠡に戻り、二人は一緒に五湖を航海した」と記されている。ほとんどの文学作品や演劇作品では、このように描写されている。呉が滅亡した日、范蠡は二つのことをしたと言われています。一つは、同じ苦難を共にした親友の文忠を説得して、できるだけ早く郭堅を離れるようにしたことです。もう一つは、姑蘇台地の下の花陰の奥深くで、疲れ果てた元恋人の西施を発見し、慌てて太湖に逃げ、二人とも小舟に乗って広大な海に消えていったことだった。蘇東坡はかつてこう記している。「私は道を求めて五つの湖を巡り、西施を乗せたまま小船で帰ってきた。」山東省肥城市淘山には范蠡と西施の墓があると言われている。 3. 湖で溺死した范蠡の物語 越が呉を征服した後の西施の運命については、別のバージョンがあります。呉が滅ぼされた後、越王は西施の美しさのために彼女を側に置いておきたいと考えましたが、范蠡は断固として反対しました。彼は越王が呉王の教訓から学び、美しさに誘惑されないように望んでいました。彼は計画を練り、人を遣わして西施を越王の馬車に乗せて太湖に誘い込み、船に乗せた。湖の中央に着くと、西施の不注意に乗じて残酷にも船から突き落とした。こうして西施は太湖で溺死した。 4. 呉族に溺死させられた話 呉王国が滅亡した後、呉の民衆は西施に怒りをぶつけ、錦の布で彼女を包み、揚子江の真ん中で溺死させたという民間伝説があります。東坡易武誌には、「揚子江には人魚がおり、西施魚とも呼ばれる。一日に何度も色が変わる。肉は上質で美味しい。これを食べた女性はより魅力的になる。西施が川で溺死した後に生まれたと言われている」と記されている。 唐代の洛隠は詩を書いた。「国の興亡は時勢によって決まる。呉の民はなぜ西施を責めなければならないのか。西施が呉を倒すのに役立ったのなら、越を滅ぼしたのは誰の責任か」。唐代の人物が書いたこの詩から、「呉の民が西施を川に沈めた」という話には一定の市場があることがわかります。 5. 郭建に溺死させられた話 越の王、郭堅はかつてこう言った。「呉の滅亡の功績は西施のおかげだ」。伝説によると、郭堅は呉の滅亡は傅差王が西施の美しさに溺れたためだと信じていた。西施の美しさが越に害を及ぼすのを防ぐため、郭堅は恩を仇で返し、西施を川に沈めるよう命じた。この発言は、「呉の民によって川で溺死させられた」説や「范蠡によって湖で溺死させられた」説と似ており、どちらも西施を「災いをもたらす美女」とみなしている。 6. 越後川で沈没した話 伝説によれば、越国が呉国を征服した後、郭堅は西施を自分の後宮に迎え入れようとした。越後は西施を「国に災いをもたらす女」と信じ、彼女が越国に災いをもたらすことを心配し、部下に命じて彼女を牛皮袋に包み、川の底に沈めさせた。 この発言は、王の好色な精神と女王の嫉妬深い精神に一致しているため、より人気があります。 『東周戦国記』にはこう記されている。 「川に沈む説」は、古くから古書に記録されている。呉の滅亡から100年も経たないうちに(紀元前475年頃)、墨子は『墨子 士友論』の中でこう述べています。「畢干の死は彼の抵抗によるものであり、孟本が殺害されたのは彼の勇敢さによるものであり、西施が溺死したのは彼女の美しさによるものであり、呉起が分裂したのは彼の悪行によるものである。」彼が言いたかったのは、これらの人々は皆「自分の強さのために死んだ」ということ、つまり自分の強さのために同じ災難に遭ったということである。西施はその美貌ゆえに川で溺死した。彼ははっきりと「西施は美貌のゆえに溺死した」と述べ、西施が川で溺死したことを明確に指摘した。 もう一つの古典『呉越春秋』にも、「呉王の死後、越は西施を川に流し、赤夷と共に死ぬよう命じた」と明確に記録されている。范離がかつて「姓と名を変えて斉に行き、赤夷子皮となった」という事実に基づいて、ここでの「赤夷」は范離を指していると解釈する人もいる(『史記・商人伝』)。筆者は、ここでの「鸱夷」を「牛皮」と解釈する方が合理的であると考えている。牛皮で西石を包み、川に流すという意味です。范蠡は友人でありライバルでもあった伍子胥を記念して、名前を「其一子皮」に変更した。伍子胥は夫差王によって死刑を宣告された後、彼の遺体も牛皮で包まれた。唐代の学者、司馬鎮は『史記目録』の中で次のように記している。「范離は自らを赤易子弼と名乗った。おそらく、呉王が子胥を殺し、赤易を権力のある者にしたためだろう。范離は自分が罪を犯したと思い、自らこの名を名乗ったのだ。」 もう一つの証拠があります。浙江省の沿岸地域の名物料理「西施舌」(一種のハマグリ肉)は、西施が川で溺死したことを記念して作られたと言われており、いわゆる美しくておいしい食べ物です。 つまり、西施の魂は故郷に戻ったということだ。どこに埋葬されたのか、遺体なのか衣服なのか、さらなる検証が必要だ。 |
<<: 春秋戦国時代に、魚を水底に沈めるほど美しかった西施の称号はどのようにして生まれたのでしょうか。
>>: 春秋時代後期の越国の美女:西施とともに「絹を洗う二人の美女」と呼ばれた鄭丹の略歴
推薦する
「楊家将軍物語」第27章:枢密院が武寧邸の転覆を計画し、金武が天宝塔を破壊する
『北宋実録』(『楊将軍伝』『楊将軍物語』『楊将軍志』とも呼ばれる)は、楊家の将軍が遼に抵抗した功績を...
なぜ、多くの登場人物の中で、施夫人と賈夫人が最大の勝者とみなされるのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、施夫人と賈夫人についての記事をお届けします...
『紅楼夢』で薛宝才は宝玉と結婚した後、どのような生活を送りましたか?
薛宝柴は『紅楼夢』のヒロインで、林黛玉と肩を並べる存在です。これは多くの読者が気になる問題です。一緒...
なぜ袁術は自らを皇帝であると公言したのでしょうか?皇帝の璽を持つ彼は、それを運命だと思ったのだろうか?
東漢末期には皇帝の権力が衰え、多くの英雄たちが覇権を競い合いました。多くの王子たちの中でも、袁術は非...
宋代以降、簒奪があまり行われなくなったのはなぜでしょうか?君主と臣下の倫理は正統な儒教となる
秦・漢の時代から隋・唐の時代にかけては、強権政治が頻繁に出現し、中には王位を簒奪して新しい王朝を樹立...
『紅楼夢』で甄世銀が太虚を訪れた際に突然起こった災難の目的は何だったのでしょうか?
長い時間の流れは止まらず、歴史は発展し続けます。『Interesting History』の編集者が...
『太平光記 八妖怪』第366巻の登場人物は誰ですか?
杜元英、朱道士、鄭勝、趙世宗、曹朗、李月、張震、馬居、魏塵、張慕孫、李煌、宋勲、張世子、僧侶世鵬、宜...
『紅楼夢』の四大家の一つである薛家はいつから衰退し始めたのでしょうか?
『紅楼夢』の四大家とは、『紅楼夢』に登場する封建的な官僚集団を指します。今日は、Interestin...
王安石はなぜ解任されたのか?事件の全過程はどうだったのですか?
西寧七年(1074年)の春、全国に大干ばつが起こり、飢えた民が避難した。大臣たちは旅費免除の弊害を訴...
なぜ唐の時代は外国人が官僚になることを許可したのでしょうか?唐王朝はどれほど強大だったのでしょうか?
今日は、Interesting History の編集者が唐王朝がいかに強大だったかをお話しします。...
唐詩の鑑賞:『放浪息子の歌』、孟嬌は詩の中でどのような比喩を表現したのでしょうか?
唐代の孟嬌の『放浪記』について、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介しますので、見てみましょう!愛情深...
清朝の四大回班集団とは何ですか?恵班の起源の紹介
清朝の四大徽班劇団とは何でしょうか? 実は、四大徽班劇団とは、中国の清朝の乾隆時代に北京の劇場にあっ...
『紅楼夢』で秦克清が亡くなった後、薛潘はなぜ彼女に棺を送ったのですか?
『紅楼夢』で秦克清が亡くなった後、薛潘はなぜ棺板を送ったのでしょうか?これは多くの読者が気になる疑問...
涼山の英雄たちのリーダーとして、宋江はどのような人々を恐れていましたか?
宋代末期の統治者は無能であったため、多くの人々が様々な理由で涼山に集まり、山を占領して王となり、宋代...
紅楼夢第97話(1):林黛玉は恋心を終わらせるために原稿を燃やし、薛宝柴は寝室から出てくる
『紅楼夢』は、中国の四大古典小説の一つで、清代の章立て形式の長編小説です。通俗版は全部で120章から...