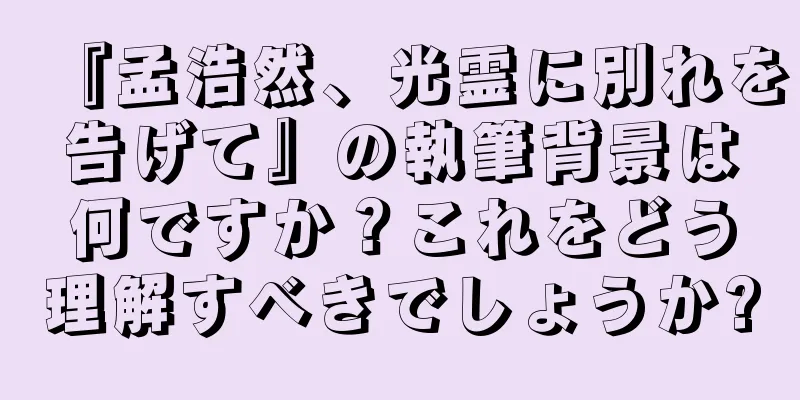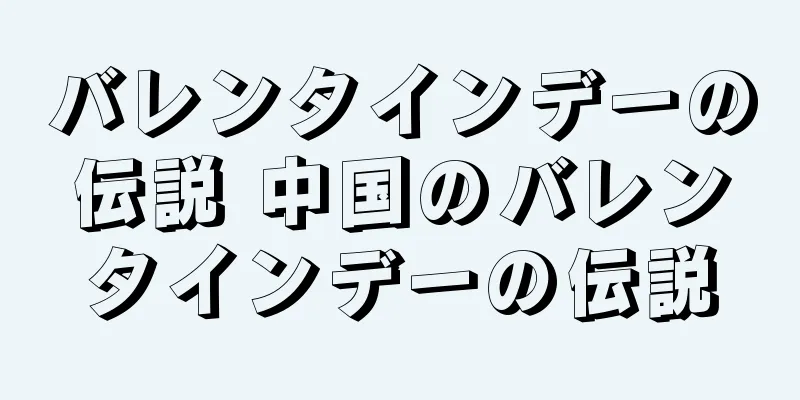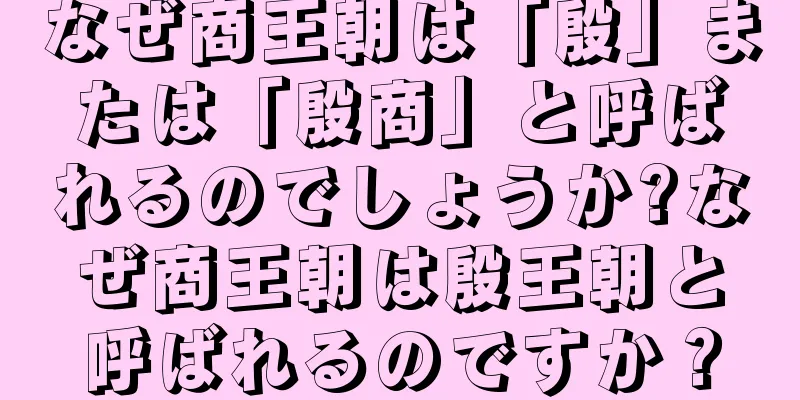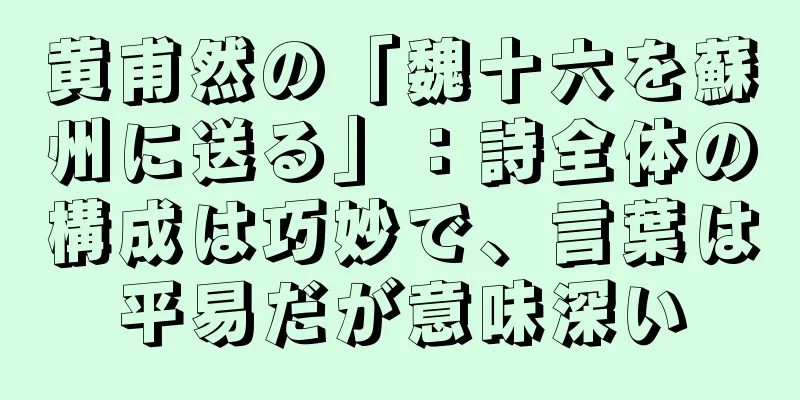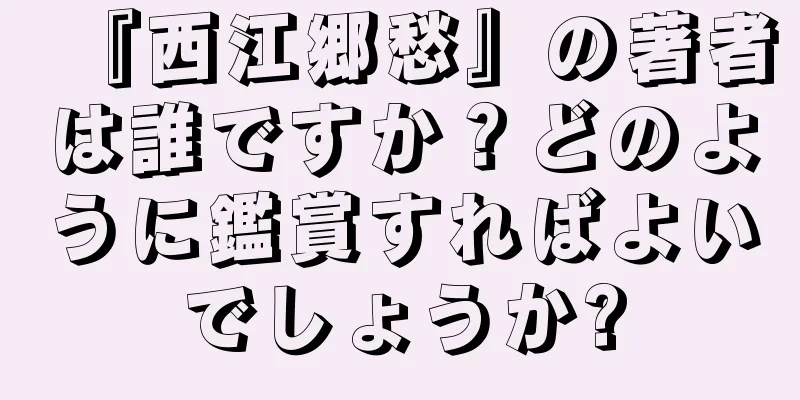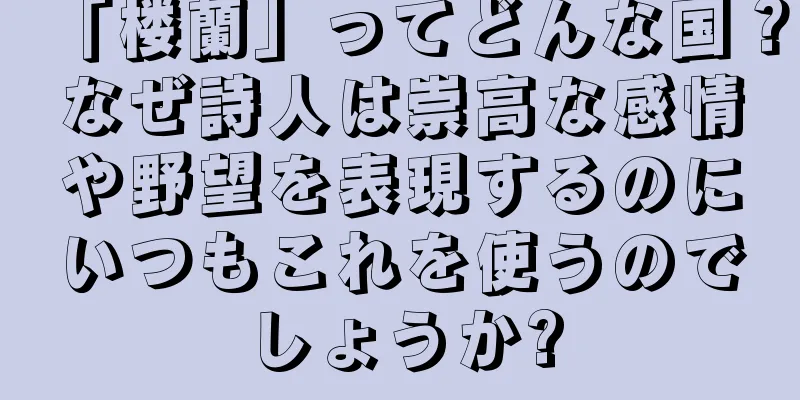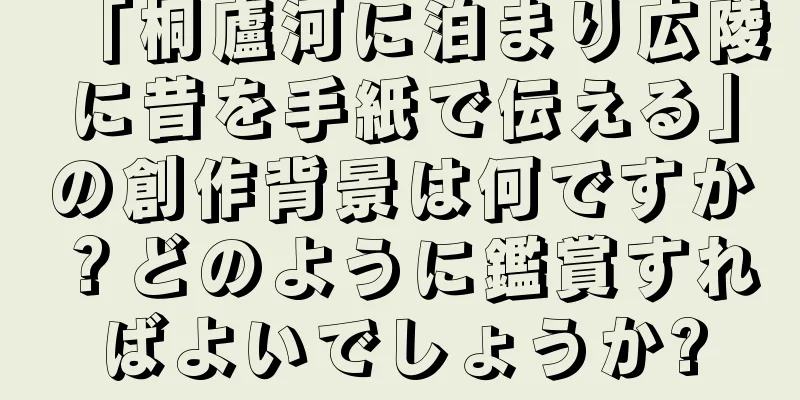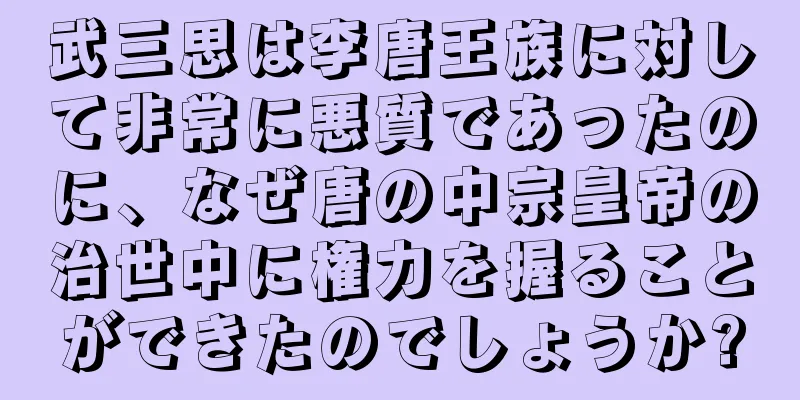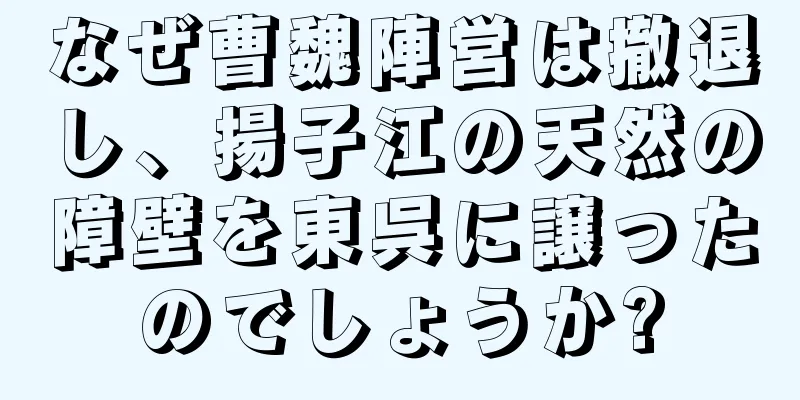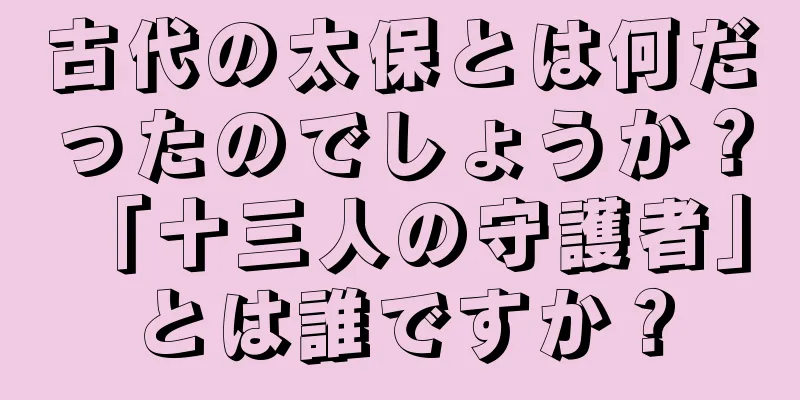国営の塩と鉄の産業はいつ始まったのですか?国営の塩と鉄の産業が歴史的に与えた影響は何でしょうか?
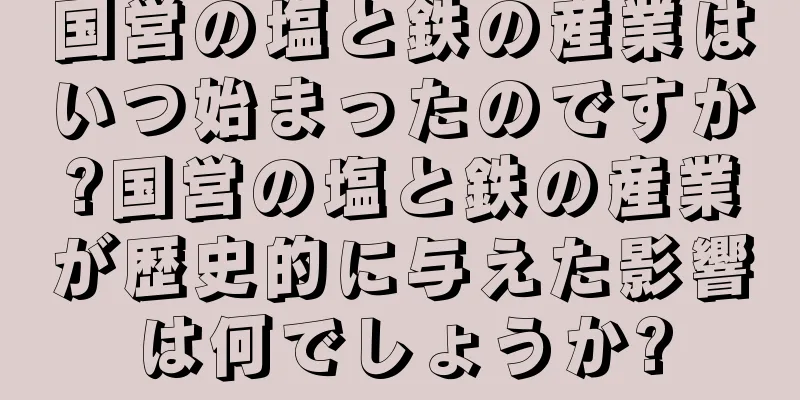
|
塩鉄専売は「国営塩鉄」とも呼ばれる。旧政府は、産業と商業の発展を制限し、財政収入を増やすために、塩と鉄の独占を実施しました。伝説によると、春秋時代の斉国で始まったとされ、『管子』に記された「官山海」とは、山海の産物を政府が独占的に管理していたことを指す。当時、山海の主産物は鉄と塩であり、政府は塩と鉄を管理し、物品の価格に税金を含めていたため、人々は税金を逃れることも感じることもできませんでした。漢王朝初期の統治者は不干渉を主張し、塩と鉄に対して自由放任主義の政策を採用し、塩と鉄を扱う商人を王や王子と同じくらい裕福にした。 次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 起源と発展 これは、春秋時代に斉の管仲が提唱した、塩と鉄の独占を実現するという「官山海」政策に由来しています。秦の商鞅は山と湖の恵みを統制する改革を行い、塩と鉄の独占も実施した。当時の山海の主力産物は塩と鉄であり、これらは政府によって独占されており、税金は商品の価格に含まれていたため、人々は課税を免れながらもそれを感じずにはいられませんでした。漢代初期に民間企業に開放されたことで、塩や鉄を扱う商人は王や王子と同じくらい裕福になった。財政的圧力と「非常時に民を助けない」商人に対する嫌悪感から、漢の武帝は桑鴻陽の指導のもと、「塩と鉄の囲い込み」事業を政府の管理下に置き、独占を実施した。 塩や鉄が生産される地域では、それらを管理するために塩官や鉄官が設置されています。塩の独占は政府の監督下で行われ、塩は塩農家によって生産され、政府の価格で購入され、政府によって輸送および販売されました。鉄の専売公社は、鉄鉱石の採掘、製鋼、鉄器の鋳造、販売など、事業のあらゆる側面を政府が管理する政策を採用した。東漢時代には塩と鉄の独占が廃止され、課税制度が実施されました。三国時代と晋時代には独占的な購入が重視され、南北朝時代には課税制度が復活しました。 隋代から唐代初期にかけて、塩に対する特別税は廃止され、他の商品と同様に市場税が課せられました。唐代の安史の乱の後、国は財政難に直面し、塩の独占が再び実施されました。それ以来、歴代の王朝は塩の独占を強化し、鉄に税金を課し、鉄はもはや塩と同じように扱われなくなりました。塩と鉄の独占により、封建国家は相当の利益を得た。特に塩は歴代の封建政府によってしっかりと管理された最も重要な独占商品であり、その収入は歴代の政府にとって重要な収入源となっていた。 歴史的影響 単純な恐喝と重税は簡単に民衆の不安を誘発する可能性があります。表面的には、「官山海」は直接税を課さず、人民の不満を招くこともなく、「与える形は見ても、奪う原理は見ない」という国家財政の非常に巧妙な方法である。 管山海は管仲以降のすべての王朝で高く評価され、特に宋、元、明、清の時代には塩税収入が地租に次ぐ朝廷の第二の収入源となった。 管仲の塩と鉄の専売の思想は今日まで受け継がれ、広範囲な影響を与え、春秋時代以降2000年以上続いた中国の塩の専売制度の起源となった。そのため、後世の人々は管仲を「塩の達人」として尊敬している。 その他の紹介 漢の武帝の治世中、匈奴を攻撃するために、桑鴻陽の助言を受け入れ、塩、鉄、酒の国家独占制度を実施しました。漢の武帝は晩年、「倫台罪人令」を発布し、匈奴への反撃の範囲を超えた過剰な軍事征服を悔い、より平和的な政策に転換した。 しかし、漢の昭帝の時代まで廃止されなかった塩と鉄の専売制度は、広範囲にわたる不満を引き起こし、「塩鉄論」に記録されている大論争につながりました。これは「国」が撤退すべきか否かをめぐる議論である。塩鉄会議において、塩と鉄の独占を擁護する人々は、それが匈奴に対抗するための軍事資金を集めるためであると主張したが、塩と鉄の独占に反対する人々は、「利益のために民衆と競争しない」という古典的な儒教の原則を強調した。 塩鉄会議はすぐに政府による酒類産業の独占を廃止し、塩と鉄の独占も部分的に取り消した。しかし、塩鉄会議の最も重要な貢献は、今日でも非常に当てはまる憲法原則を提唱したことです。つまり、政府は、一般的な事業を運営するのではなく、適切な税率で税金を徴収することによってのみ、公共財を提供するための資源を獲得できるというものです。 おそらく桑鴻陽らが塩と鉄の独占を確立した当初は誠意があったのだろうが、当時の匈奴への大規模な攻撃は一時的に彼らの資金力を超えたものだったのかもしれない。しかし、いったん独占の利益を得ると、それを手放すことを躊躇する。 漢の昭帝は塩鉄会議の後に酒類専売制度を廃止し、塩と鉄の専売制度を部分的に解除し、常に高く評価されてきた。 |
<<: 歴史上、漢の武帝は本当に魏子夫を愛したのでしょうか?劉澈は魏子夫をどのように扱いましたか?
>>: 封土令の独自性は何ですか?封建制や封建社会主義との違いは何でしょうか?
推薦する
「朝の5時には葉はまばらで、木は青々としていて無情だ」という有名な言葉はどこから来たのでしょうか?
「五時葉散り、樹木青し心なし」という有名な一節はどこから来たのでしょうか。実はこの一節は唐代の李商胤...
『西山秋涼図に詠まれた水の旋律』の作者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
水の旋律の歌:西山秋の絵に刻まれたもの那蘭興徳(清朝)空っぽの山の中では仏の祈りの声が静まり、月と水...
宋代の劉勇の詩「晩天荒儒」を鑑賞する、この詩をどのように理解すべきか?
双声·晩天荒宋[宋代]劉勇、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょう...
欧陽秀の「木蘭花:別れた後、あなたがどこまで行ったか分からない」:ロマンチックなセリフと荒涼とした情景
欧陽秀(おうようしゅう、1007年8月1日 - 1072年9月22日)、字は永叔、晩年は随翁、劉義居...
『紅楼夢』で王夫人が担当していた頃の状況はどうでしたか? Tanchunと比べて何が違うのでしょうか?
タンチュンは『紅楼夢』に登場する意外なキャラクターです。今日は『おもしろ歴史』の編集者が詳しく説明し...
李奇の「古辺の歌」:曲全体を見ると、少し悲しく、少し壮大である。
李斉(690-751)は漢族で、昭君(現在の河北省昭県)と河南省毓陽(現在の河南省登封市)の出身。唐...
『済公全伝』第187章:劉妙通は英雄を救いたい。済公老は英雄を招待する手紙を書く
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
『紅楼夢』の賈宝玉の前世は何でしたか?これにはどんな意味があるのでしょうか?
賈宝玉は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公です。本日は、Interesting History編集長が...
女媧の原型は実は裸だった?紅山の女神は女媧ですか?
紅山の女神は女媧ですか? 1982年、加須県東山嘴で比較的完全な女神立像2体が発掘されました。円形の...
哲学の名著『荘子』雑集:耿桑抄(3)原文と口語訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...
明王朝は国の北半分を保持するために首都を北京に移さなければならなかったのでしょうか?
明代の偉人、王陽明はかつて、明代の国防について独自の戦略構想を提唱した。彼の見解は、「明代は大きいが...
唐代の宗教建築はどのようなものだったのでしょうか?
唐王朝は、中国史上、文化が栄え、国力が強く、各国から貢物を集め、過去と未来を繋ぐ繁栄した帝国でした。...
古代の人々はどうやって魚を捕まえたのでしょうか?高度な釣り道具はありますか?
最近では、市場には多種多様な釣り道具が存在します。では、古代の人々はこれらの高度な漁具なしでどのよう...
『紅楼夢』の小湘妃の称号はどういう意味ですか?秘密は何ですか?
『紅楼夢』では、小湘閣は林黛玉が住んでいる場所です。本日は、Interesting History編...
『紅楼夢』では、賈正は王夫人を20年間溺愛していましたが、なぜ二人は疎遠になってしまったのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...