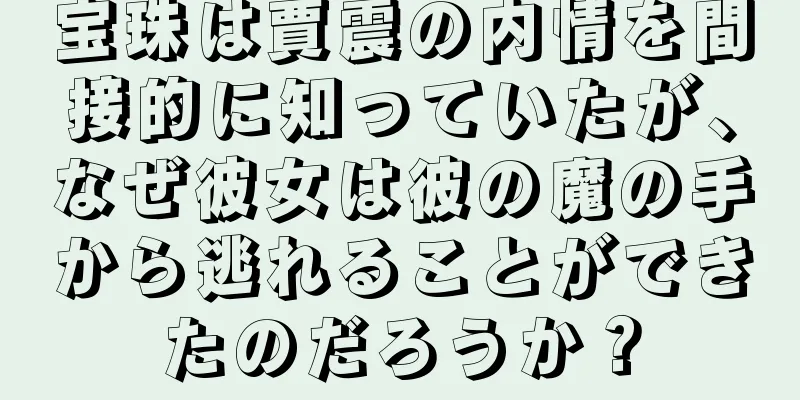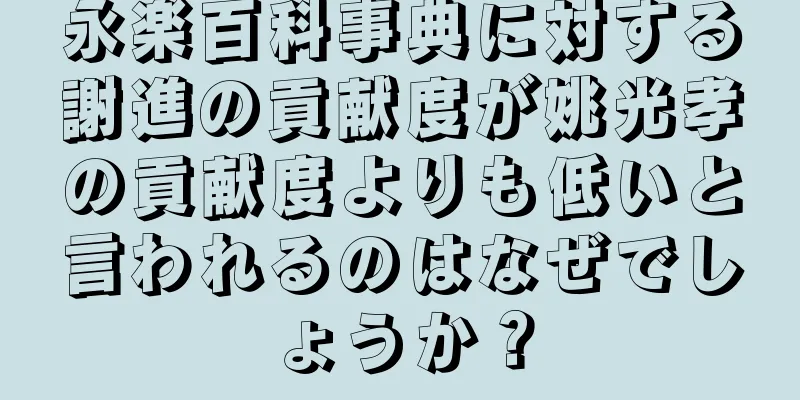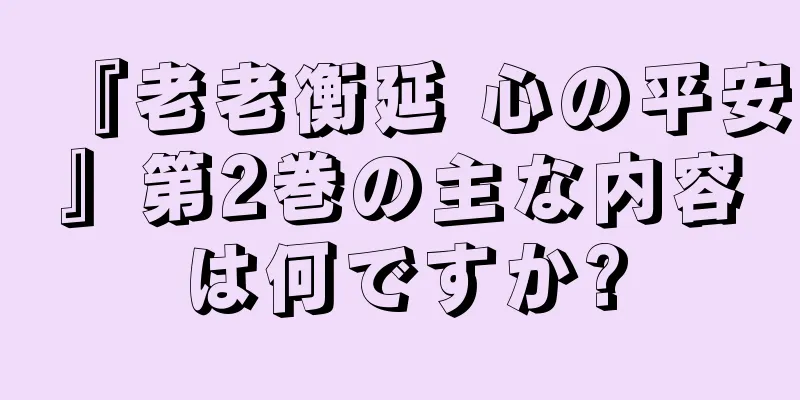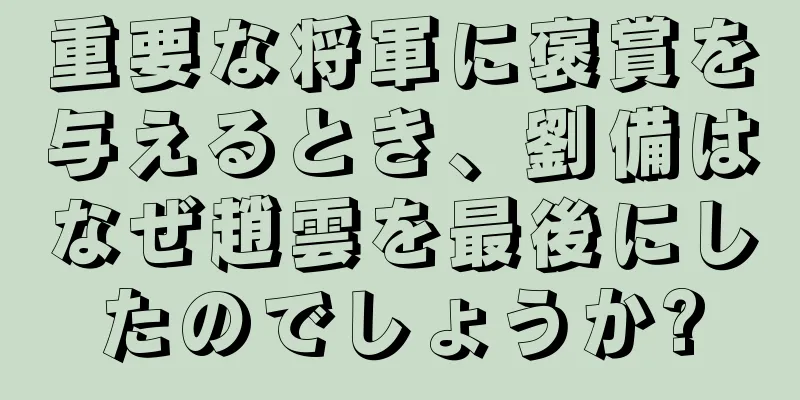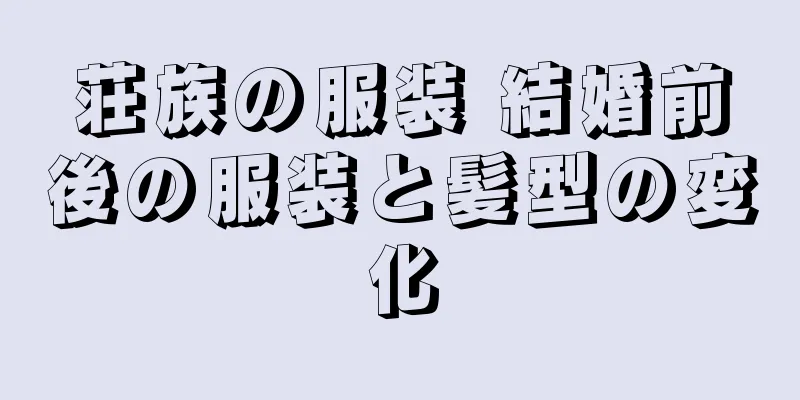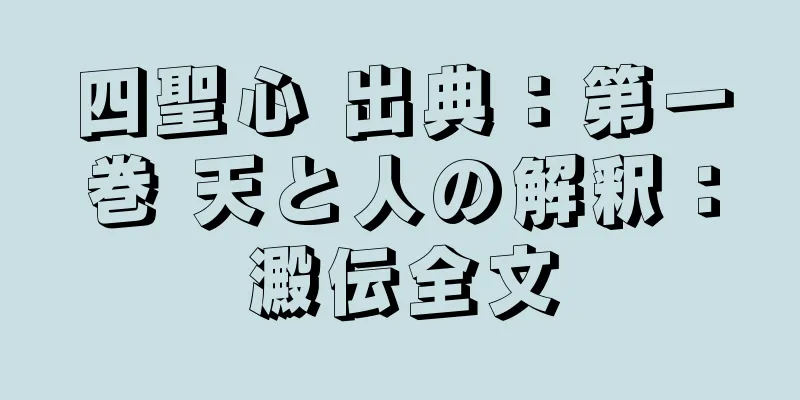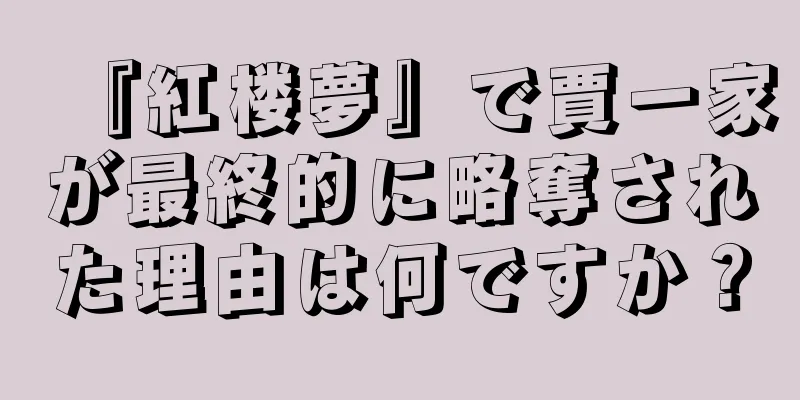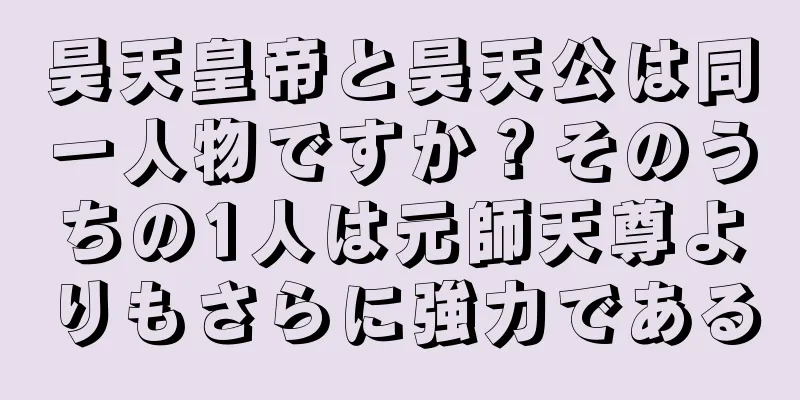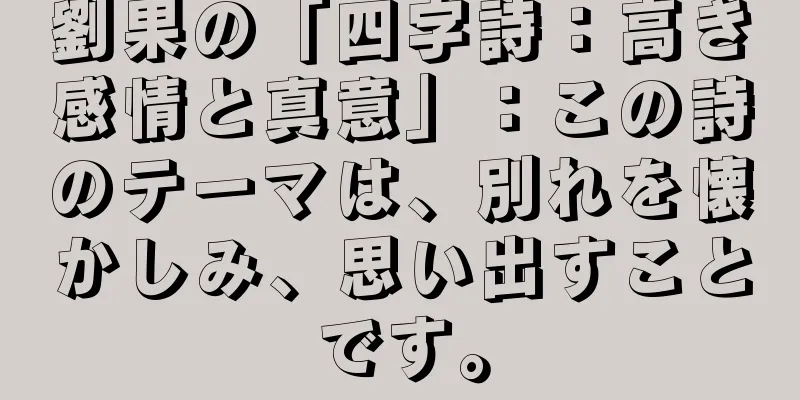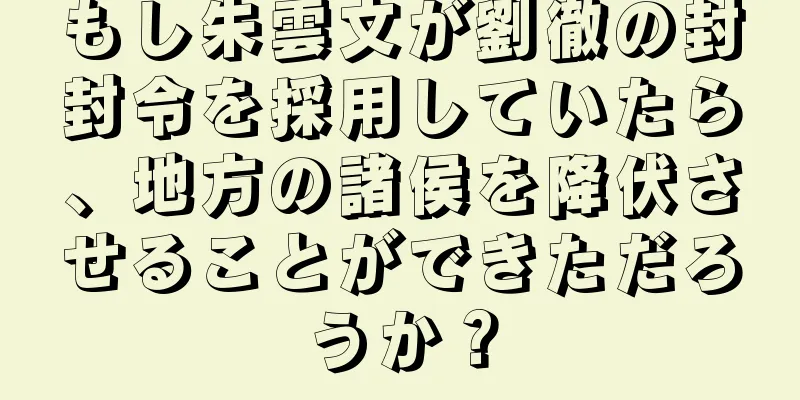楊雄さんの代表作は何ですか?楊雄の主な業績は何ですか?
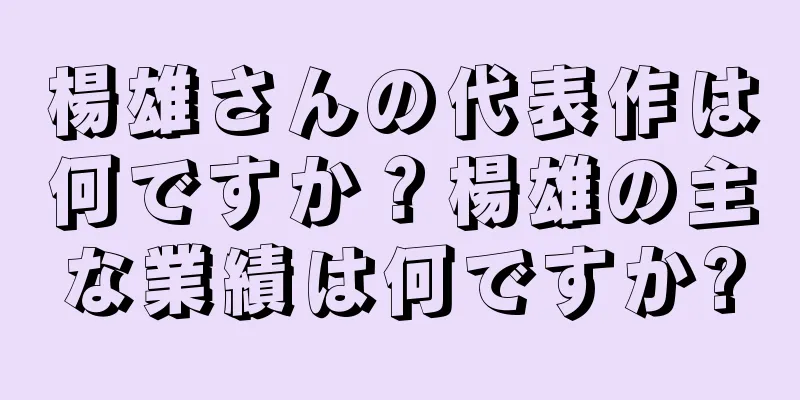
|
楊雄(紀元前53年 - 紀元18年):「楊雄」とも呼ばれる。前漢時代の作家、哲学者、言語学者。姓は紫雲、成都市蜀県(現在の四川省)の出身。漢の成帝の治世中に黄門郎として仕えた。王莽は皇帝を称した後、太中大夫に任命された。彼は若い頃の詩作で有名で、『甘泉譜』や『長陽譜』などの有名な作品がある。晩年は哲学を学び、『論語』や『易経』を模倣して『法眼』や『太玄』を著した。言語学を研究した『方言』や王莽を讃えた『莽琴美心』などもあります。明代の人々は『楊十朗全集』を編纂した。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! チフ 楊雄は若い頃、司馬相如を非常に尊敬しており、司馬相如の『子胥賦』や『上林賦』を模倣し、『甘泉賦』『玉烈賦』『長陽賦』を著して、平和を装い、崩壊寸前の漢王朝を讃美した。そのため、後世では「ヤンマ」と呼ばれるようになりました。楊雄は晩年、賦に対する新たな認識を持つようになった。『法眼無字』の中で、賦を書くことは「子供が虫を彫ったり印章を刻んだりするようなもの」であり、「能力の高い人はそんなことはしない」と考えていた。また、楊雄は、自分の初期の賦が司馬相如の賦と同じであると信じていた。どちらも風刺的であるように見えて、実際には説得力があった。この理解は、後の『賦』の文学批評に一定の影響を与えた。 楊雄の賦の中で最も特徴的な作品は、『戀超』『祝品賦』『九瑾』など、楊雄自身の感情を表現した作品である。 『傑超』では、彼が権力者に取り入って官僚になることを望まず、その代わりに質素な生活を送り『太玄』を書くことに満足していたことが描かれている。記事は、権力を濫用し、圧制が横行していた当時の朝廷の暗い状況を暴露し、「権力者は天に昇り、道に迷った者は溝に落ちる。朝に権力を握った者は大臣となり、夕方に権力を失った者は庶民となる」と述べ、朝廷が凡庸な人々で満ち、並外れた才能や振る舞いを持つ者が容認されない状況に深い憤りを表明し、「今日、郡守は学者を招かず、郡知事は教師を迎えず、大臣は客を迎えず、将軍は頭を下げない。奇妙な話し方をする者は疑われ、振る舞いが違う者は解雇される。そのため、話したい者は舌を巻いて同じ声で話し、歩きたい者は足を制御された方法で動かす」と述べた。この賦は、著者の社会の現実に対する強い不満を表現していることがわかる。この賦は東方碩の『応客論』の影響を受けていますが、その思想は自由奔放で、修辞は鋭く、思想と芸術の面で独自の特徴を示しています。 「貧困を追い払う」は、彼の憂鬱と欲求不満を描写したユニークな短編小説であり、その中で彼は「貧困を呼び、それに話しかける」ことで、なぜ貧困が常に彼を追いかけるのかを問いかけている。この傀は、彼の貧しい生活に対する不満を吐露したもので、四字熟語が多く、斬新な発想とユーモラスな文体だが、深い憤りが込められている。 「九壬」は物に関する詩で、その内容は、水瓶はシンプルで便利だが壊れやすい、酒瓶は鈍くて重いが「国の道具としてよく使われる」というもので、主な目的は内面の不満を表現することでもある。彼はまた、屈原の『楚辞』を模倣し、『范里索』、『光索』、『潘老周』などの作品を書いた。 「反李索」は屈原を偲んで書かれた詩である。詩は詩人の体験に対する共感に満ちているが、老子と荘子の思想を用いて、屈原が「幽丹が大切にしていたものを捨て、彭仙が残したものを拾い上げた」と非難しており、作者の自己保存の考えを反映しており、屈原を正しく評価していない。現在残っているのは「広堯」と「潘老周」の称号だけです。 楊雄は若い頃は詩と散文で有名であったが、晩年は詩と散文に対する考え方が変わった。彼は詩と散文の創作について、風刺的であると同時に説得力のあるものであるべきであり、詩を書くことは「子供が昆虫を彫ったり印章を刻んだりするのと同じ」であり、「強い男がするようなことではない」と述べた。また、彼は「詩人の賦は美しく整然としており、修辞家の賦は美しく淫らである」という見解も提唱し、楚辞と漢辞の長所と短所を区別した(法眼無字)。楊雄の賦に関する発言は、後世の賦の発展と賦の評価に一定の影響を与えた。それは劉協や韓愈の後の文学理論に大きな影響を与えた。 楊雄は散文においても一定の業績を残した。たとえば、「陳有の朝廷文書の受理に対する抗議」は、力強い文章、平易な言葉遣い、流暢な勢い、徹底した推論を備えた優れた政治論文です。彼の『法眼』は意図的に『論語』を模倣し、秦以前の哲学者の文学技法の長所を継承しており、言葉は簡潔で意味は豊かで、唐代の古代散文作家、例えば韓愈の「尊敬する司馬遷と楊雄」(劉宗元の「魏衡の韓愈への書文の件に対する返書」)に良い影響を与えた。また、彼は「連竹流」の創始者であり、彼以降、多くの後継者が生まれました。 散文 散文の面では、楊雄は模倣の達人と言えるでしょう。例えば、『易経』を真似て「太宣」と書いたり、『論語』を真似て「法閻」と書いたりしました。その後、楊雄は「修辞学や散文は、君子の詩や散文の正しい形式ではない」と考え、すべての言葉は「五経」に基づくべきだと主張した。彼は修辞学や散文を「虫を彫ったり印を刻んだりするようなもので、勇士のすることではない」と蔑み、形而上学の研究に転向した。例えば、『法眼』では文学は古典に従い、聖人を求め、儒教の著作を範とすべきだと唱え、劉謝の『文心謠論』に大きな影響を与えた。楊雄は言語学の著作『方言』も著しており、これは前漢時代の言語を研究する上で重要な資料となっている。 『隋書経篇』には、現在失われている『楊雄全集』5巻が収録されている。明代には張普が『楊十朗集』を編纂し、『漢魏六代百三人集』に収録された。現代の学者である張振沢は、『楊雄全集』を編集し、注釈を付けた。 楊雄は著書『太玄』の中で、「玄」は宇宙の根源であるという説を唱え、自然現象を真に理解する必要性を強調し、「すべての生き物は必ず死に、すべての死んだものは必ず終わりを迎える」と信じ、仙人や魔法の迷信を論駁した。社会倫理の面では、老子や荘子の「仁義を捨てる」という考え方を批判し、儒教を重視した。「人間の本性には善と悪が混在している。善を修めれば善人となり、悪を修めれば悪人となる」(『法眼修志』)と信じた。 儒教 楊雄は孔子の正統な儒教を復活させるために神学の古典を批判した。楊雄の考えでは、孔子は最も偉大な聖人であり、孔子の経典は最も重要な経典である。彼は言った。「船を放棄して溝を渡ろうとする者は、結局失敗するだろう。」五経を捨てて道を求める者は終わりである。またこうも言われている。「山への道は無数にあり、入るべき門は無数にある。」彼は言った。「悪は内側から生じる。」名前: 孔家。コング家は家庭です。したがって、本が好きでも孔子に学ばない人は書店のようであり、講義が好きでも孔子に学ばない人は講義の鐘のようである。孔子の道は四つの川のようで、中国を流れて最後には海に流れ込む。他人の道は西北の流れのようで、蛮族と貳を治め、時には沱河に流れ込み、時には漢江に沈む。しかし、楊雄は、孔子の死後、孔子の教えの発展と普及は「妨害者」の妨害によって妨げられたと信じていた。 古代には楊貴妃と墨賽禄がいた。当時、孟子は彼らを拒絶し、避けていた。将来、道を塞ぐ人々が現れるだろう、私は密かに自分を孟子と比較する。ここで言う「後世の儒教」とは、漢代の偽善的で煩雑で不条理な官儒教正統経典を指し、偽物を売りながら本物のふりをし、羊の質は五虎の皮で、利益のために学ぶことを目的としていた。そのため、楊雄は孟子のように道を阻む者を排除し、漢代における孔子の儒教の健全な発展への道を切り開こうとしたのです。 |
<<: 歴代の著名人は楊雄をどのように評価したのでしょうか?レビューは肯定的なものですか、それとも否定的なものですか?
>>: バン・グは人生で何を経験したのでしょうか?バン・グは若い頃はどんな人でしたか?
推薦する
『隋唐代記』第5章:楊玄干の軍が溧陽で蜂起する
『隋唐代志』は、元代末期から明代初期にかけて羅貫中が書いた章立ての小説である。 『隋唐書紀』は瓦岡寨...
乾隆帝は89歳まで生きたが、在位わずか60年で自ら退位を申し出たのはなぜだろうか。
清朝の皇帝の中で、乾隆帝が最も長生きし、90歳近くまで生きたことは知られています。彼の治世中、国は平...
唐代の洪文観の歴史的影響はどのような側面に反映されていますか?
唐代の洪文観の歴史的影響はどのような側面に反映されているのでしょうか。これは多くの読者が関心を持って...
李游の詩「河を渡って石城を見て泣く」は、国と故郷を失った後の荒涼とした光景と悲しい気持ちを描いています。
李郁は五代十国時代の南唐最後の君主であり、唐の元宗皇帝李靖の6番目の息子でした。李毓は皇帝の座に就く...
観音菩薩の乗るところとは何ですか?なぜ金色の毛の虎は太上老君の金色の首輪をつけているのでしょうか?
観音菩薩の山とは何でしょうか?金色の髪の虎がなぜ太上老君の金色の首輪をつけているのでしょうか?ご興味...
曹操が兗州太守になった後、父の曹宋は本当に徐州太守の陶謙に殺されたのでしょうか?
曹操が兗州太守になった後、大きな事件が起こりました。父の曹宋が途中で捕らえられ、殺されたのです。そこ...
「十二階」:三勇楼・三人の老騎士が貪欲な人々に徳を積ませ、疑わしい事件に注意を向けさせる場所を設計しました 全文
『十二塔』は、明代末期から清代初期の作家・劇作家である李毓が章立てで書いた中国語の短編集です。12巻...
曹植の『孔后音』:この詩は「優雅、寛大」の時代のスタイルを示している
曹植は三国時代の著名な文人であり、建安文学の代表者および巨匠の一人として、晋や南北朝時代の文芸の模範...
『西遊記』の沙僧はなぜ九生にわたって金色の蝉を食べ続けても罰せられなかったのか?
周知のように、『西遊記』の金蝉は、唐僧に転生する前に、すでに仏典を手に入れる計画を立てていました。で...
『紅楼夢』で宝仔が唯一怒ったのはなぜですか?
宝仔は『紅楼夢』のヒロインの一人です。林黛玉とともに金陵十二美女の第一位に数えられています。今日は、...
ミャオ族の魔術は本当にそんなに怖いのでしょうか?苗古書の秘密
伝説によると、グシュは人工的に栽培された一種の有毒昆虫です。毒殺は古代中国から受け継がれた神秘的な魔...
後漢書第30巻の西湘楷の伝記の原文
郎熙は雅光といい、北海安丘の出身であった。父の宗は、字を鍾綽といい、『経世易経』を学び、風角、占星術...
恵文王と米八子の息子、英基の生涯
秦の始皇帝:嬰児の伝説 登場人物紹介役: 秦の昭襄王 俳優: 張波秦の恵文王と米八子の息子で、幼い頃...
古典文学の名作「夜船」:四霊・獣(2)全文
『夜船』は、明代末期から清代初期の作家・歴史家である張岱が著した百科事典である。この本は、あらゆる職...
司馬懿は曹魏の君主三代よりも長生きしました。なぜ権力を握った後、皇帝にならなかったのでしょうか?
三国志におけるさまざまな戦略家について言えば、最も印象に残るのは「死ぬまで大義に身を捧げた」諸葛亮で...