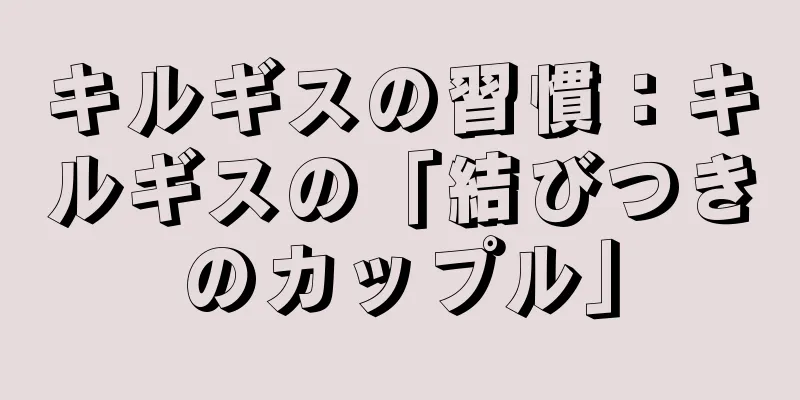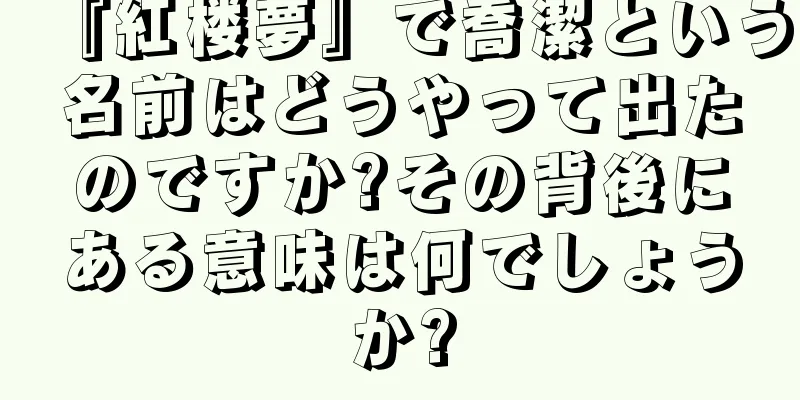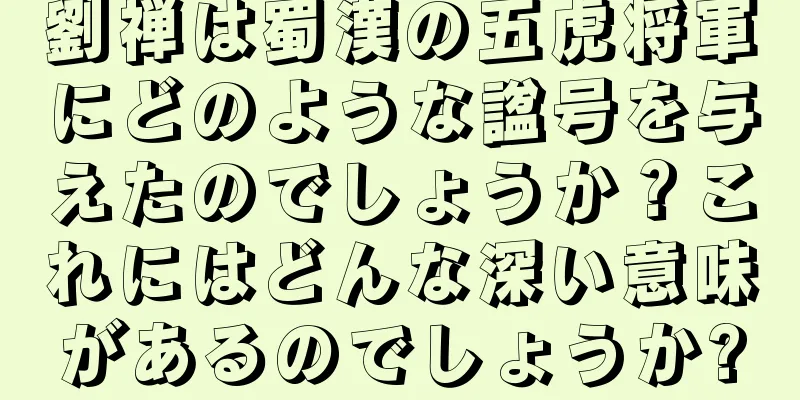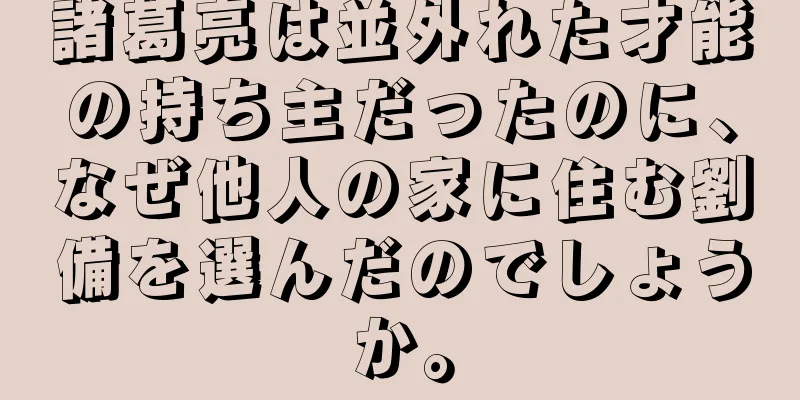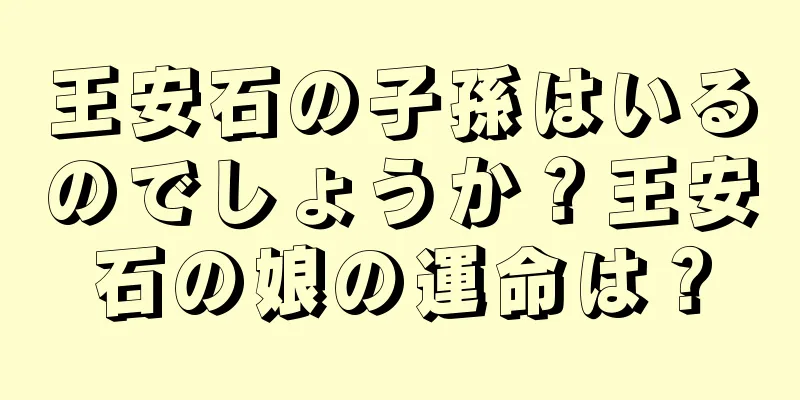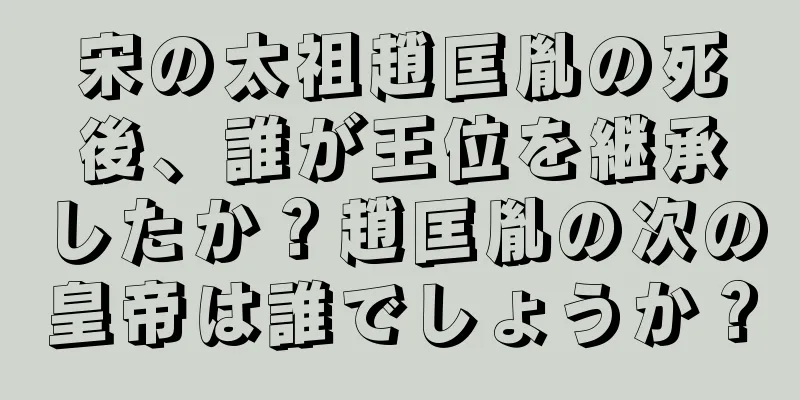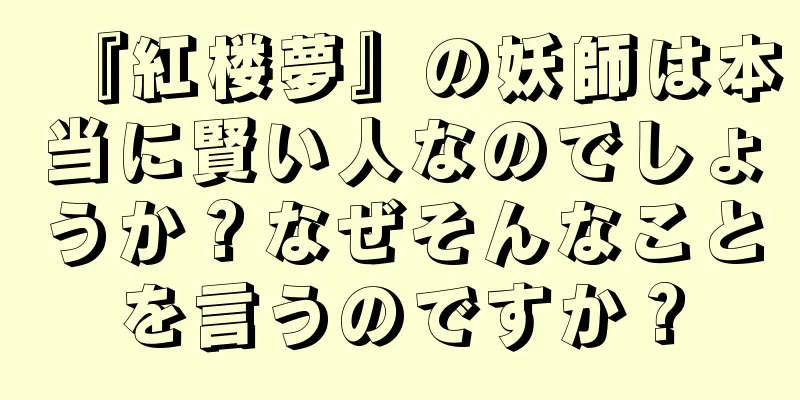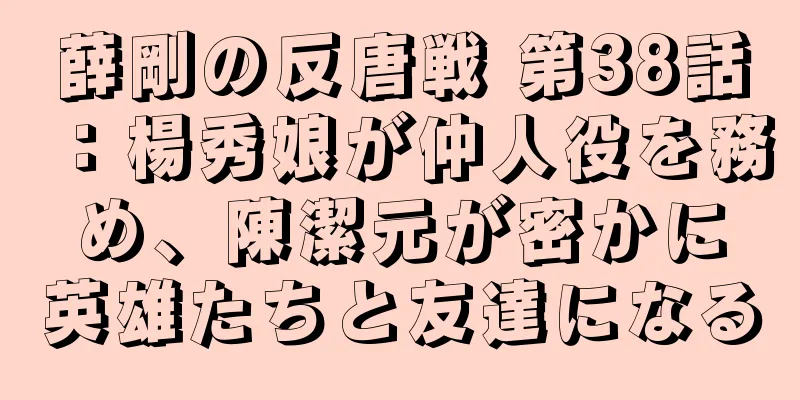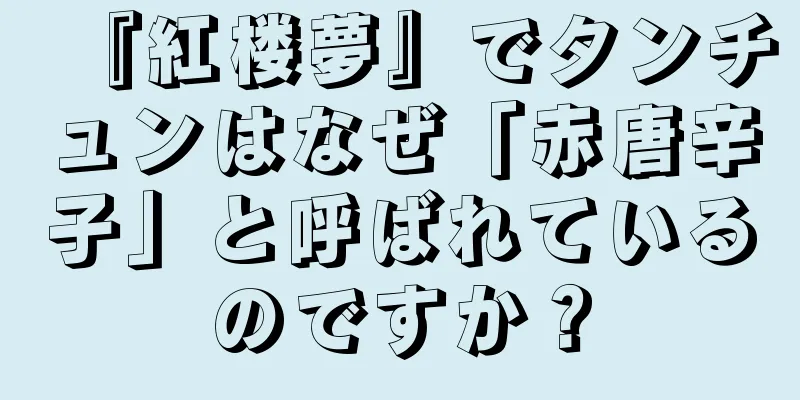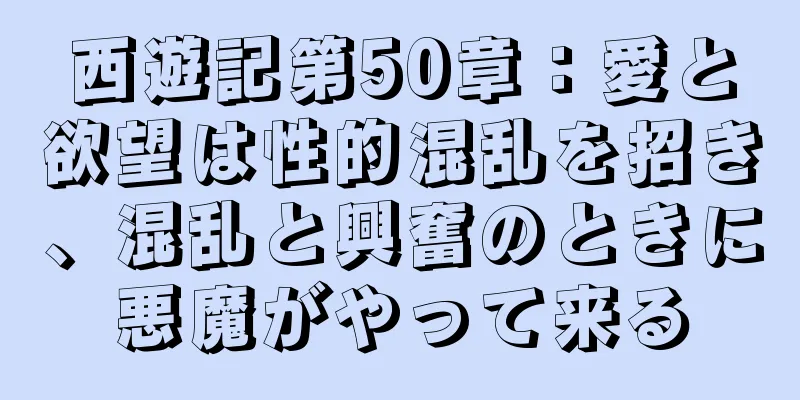「皇妾の誉れを持つ女性」の給料はいくらですか?このタイトルに付随する特権は何ですか?
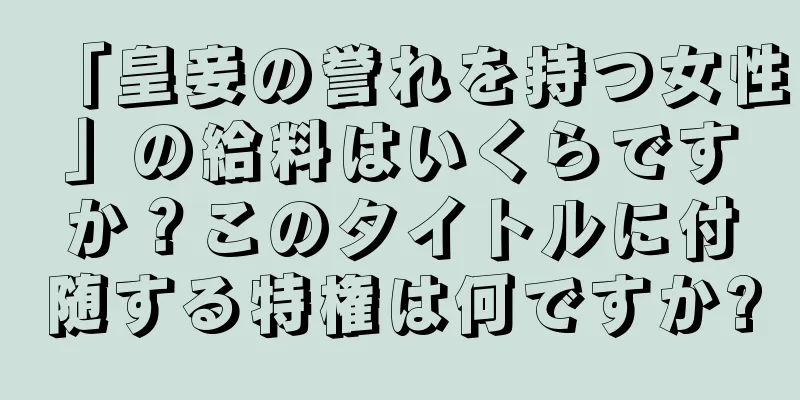
|
「皇后夫人」は、明・清時代に皇帝から爵位を与えられた二位以上の高官の母または妻に付けられた称号である。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 官僚の妻や母親に爵位を与える制度は唐の時代に始まった。 『新唐書官傳上』には「一級の文武官または公爵の母と妻を官夫人といい、三級以上の官僚の母と妻を郡夫人といい、四級の官僚の母と妻を郡夫人といい、五級の官僚の母と妻を郡夫人といい、四級の爵位のある官僚の母と妻を郷夫人といい」とある。 すなわち、一位官吏の母または妻には州夫人の称号が与えられ、三位以上の官吏の母または妻には郡夫人の称号が与えられ、四位官吏の母または妻には郡夫人の称号が与えられ、五位官吏の母または妻には郡夫人の称号が与えられ、栄誉ある四位官吏の母または妻には郷夫人の称号が与えられた。 もちろん、唐代の即位制度は比較的不完全で、五位以上の官吏の母または妻のみが即位し、五位以下の官吏の即位は認められなかった。 宋代には即位の範囲が第八位まで拡大された。 『宋史 官職官号 巻三』には、「宮廷内外の女性には、太公主、公主、公主、郡公主、郡公主、国夫人、郡夫人、徳夫人、大夫人、仁寧夫人、敬夫人、易人、安人、汝人という14の称号がある」と記されている。 当時、宰相、使節、三公、三師、国王、宮中大臣、宮内大臣の妻には「女官」の称号が与えられることがありました。光禄大夫、太子少豫、街道師など二級以上の官吏で権力を握っていない(宰相ではない)人の母または妻には、「県夫人」の称号が与えられる。尚書や中城有氏など、権力を握っていない三位以上の官吏の母や妻には、「叔人」や「叔人」の称号が与えられる。太中大夫、中大夫など四位以上の官吏の母や妻には「仁仁」の称号が与えられることもあった。中三大夫や団連師など五位以上の官吏の母や妻には「公人」の称号が与えられることがあった。超鋒大夫、鳳之大夫など六位以上の官吏の母や妻には「夷人」の称号が与えられることもあった。超風郎、扶宝郎など七位以上の官吏の母や妻には「安人」の称号が与えられることもあった。同之郎、宣一郎など八位以上の官吏の母や妻には「如人」の称号が与えられることもあった。 唐代に比べると宋代の叙爵制度は複雑で、どの階級の官吏が妻や母にどのような爵位を授けることができるかについて明確な規定はなかった。宋代の即位制度は唐代に比べると比較的完成していたと言えますが、あまりにも複雑で標準的な設定がなく、人々には理解しにくいものでした。 明代になって初めて、封土制度は完全に完成し、厳格な階層区分が確立されました。 『明代史・官記一』には、「一位を夫人といい、後に一位夫人といい、二位を夫人といい、三位を叔仁といい、四位を公仁といい、五位を易仁といい、六位を安仁といい、七位を如仁という。」と記されている。つまり、一位の妻には「一位夫人」、二位の妻には「夫人」、三位の妻には「叔仁」、四位の妻には「公仁」、五位の妻には「易仁」、六位の妻には「安仁」、七位の妻には「如仁」、八位の妻には「八位如仁」、九位の妻には「九位如仁」という称号が与えられるのである。 同時に、明代は各階級の母親や妻が取得できる称号を規定しただけでなく、称号を授与する回数や条件も規定した。詳細は以下の通りです。 1. 「子孫の名義で女性が爵位を授かる場合、爵位に「太」の字を加える。夫が存命の場合は、爵位に「太」の字を加えない。」女性が子孫の名義で爵位を授かる場合、例えば、その息子が二等官吏である場合、朝廷がその女性に爵位を授ける場合、その女性に与えられる爵位は「太夫人」となる。もちろん、夫が生きていれば「太」という文字は付けられないだろう。 2. 「爵位を授与する順序は、七位から六位までが1回、五位が1回、三位、二位、各1回とする。」これは、各位がその家族に爵位を授与できる回数を規定している。例えば、ある人が第七位にいるときに、その母親または妻が一度列聖されていた場合、その人は第五位に昇格するまで、家族を列聖させる機会をもう 1 回は得られません。その後、その人は第 3 位、第 2 位、第 1 位に昇格したときに、家族を列聖または昇格させる機会をそれぞれ 1 回ずつ得ることになります。 3. 「3人の母親を同時に列聖することはできない。そのうち2人は上位の位に従って列聖される。」 法的な母親、継母、実の母親は同時に列聖されることはない。一方、長男が三位、次男が二位の場合は、二位の皇嗣が優先される。 4. 「父親の官位が息子の官位よりも高い場合、母親は1階級昇格する。」母親が列聖されたとき、父親の官位が息子の官位よりも高い場合、母親は直接1階級昇格します。元々は第四位の「公人」だったが、第三位の「叔人」に昇格する。 5. 「もし父親の保護がこの世代で終了するか、その息子が他の誰かの養子になった場合、この女性の称号は取り消されます。 6. 「嫡出の母親が存命の場合、実の母親は列聖されない。実の母親が列聖されていない場合、妻は列聖されない。」嫡出の母親が存命の場合、実の母親は列聖されない。実の母親が列聖されていない場合、妻は列聖されない。 7. 「妻に与えられる称号は、正妻 1 名と継妻 1 名に限られる。」妻に称号を与えたい場合、それは正妻と継妻のみに与えられます。 さらに、明朝は即位の際に使用する文書の種類も規定しました。一位から五位までの官人の妻や母に爵位を授ける勅旨を叙位宣旨といい、六位から九位までの官人の妻や母に爵位を授ける勅旨を叙位宣旨という。 前述のように、「公明婦人」は明・清時代の一級・二級官吏の妻や母に付けられた名前でした。 また、ここで注目すべきは、「公明府人」は一級と二級の官吏の妻だけが取得できる称号であるということです。他の階級の妻はこれを取得できませんでした。たとえば、3 級官吏の妻は「高明叔人」としか呼ばれず、6 級官吏の妻は「赤明安人」としか呼ばれませんでした。 もちろん、「公明夫人」の意味を説明した後、その機能を紹介しましょう。実際、「皇后妃」の唯一の役割は、皇帝が官吏に好意を示し、官吏を味方につけ、皇帝に忠誠を誓わせることです。 「妻や息子に爵位を与える」というのは、古代の学者にとって常に最高の夢ではなかったでしょうか。自分の母親や妻に爵位が与えられるのは、何と名誉なことでしょう。 例えば、清朝の康熙帝の治世中、周佩公が康熙帝に協力して王福塵を降伏させた後、康熙帝は周佩公に何の褒賞が欲しいかと尋ねました。周佩公が唯一要求したのは、康熙帝が彼の母親に爵位を授けてくれることだけでした。結局、彼の母親は真礼公人の爵位を授けられました。このことから、「皇后妃」という称号が文武両道の官僚にとって非常に魅力的であることがわかります。 もちろん、「高明皇后の妃」は、給料が支払われるだけで実権はないが、それでも特権はある。結局のところ、皇帝が官僚たちを味方につけるために使うものなので、あまり卑屈にはなれない。そのため、「皇后貴人」には、他の一般人が享受できない特権がいくつか残っています。 例えば、皇后が蚕蚕の儀式を主宰する時、皇后の妃は祭祀に同行することができた。同時に、蚕蚕の儀式の後に宴会が開かれる時、皇后の妃は宮殿の石段で食事をすることができ、一方、皇后の妃など三位以下の女性は石段のふもとでしか食事をすることができない。例えば、皇帝が皇后を立てたり、皇太子を立てたり、皇帝の称号を授けたりするときには、勅許女官が出席することができ、また、請願書を提出する権利も有する。 服装面では、一級の女性の正装は、山松で作られた特別な饅頭で、5本の緑の松、8羽の金色のキジ、口に真珠の結び目があります。二位の女性の正装は、髪に金色の鳳凰を七羽飾り、口に真珠の結び目をつけることです。 |
<<: 清朝の最盛期の人口はどれくらいでしたか?急速な人口増加の理由は何ですか?
>>: 古代の人々は高齢者の世話をする際にどのような配慮をしたのでしょうか。老人ホームは古代に存在したのでしょうか?
推薦する
『紅楼夢』では、邢秀燕と賈歓はどちらも困難な状況にありました。しかし、二人の人気度は正反対でした。
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
『紅楼夢』で宝玉と金伝児の間に何が起こったのですか?なぜ王夫人はそれを止めなかったのですか?
賈宝玉は、中国の有名な古典『紅楼夢』の男性主人公で、賈徴と王傅仁の次男です。 Interesting...
中国の雨前茶とは何ですか?雨の前のお茶の中の雨は何を意味していますか?
今は春なので、たくさんの新しいお茶が市場に出回っています。最近、「雨前茶」という言葉をよく耳にします...
「胡曉草氏への返答」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
何虎熙曹は顧澤草に陶淵明(魏晋) 5月中旬、清朝は瑞浜で南雄を開始した。前進も減速もせず、風が私の服...
『紅楼夢』に出てくる召使たちは本当に主人よりも尊敬されるのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
真偽の孫悟空の物語で、六耳の猿の武器がなぜ「遂心鉄剛ビン」と呼ばれるのですか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
三国時代、関羽はなぜ東呉の将軍を「江東のネズミ」とみなしたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「世界の物語の新記録」第 38 章の教訓は何ですか?
『十碩心于』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。それでは、『十碩心於・讃・第38話』に表現...
古代に「スパイ」は存在したのでしょうか?歴史上有名なスパイ機関にはどのようなものがありますか?
歴史上有名なスパイ機関とは?Interesting History編集部が関連内容を詳しく紹介します...
三国志演義 第18章:賈文和が敵の勝利を予言し、夏侯惇が矢を抜いて目玉を食べる
『三国志演義』は、『三国志演義』とも呼ばれ、正式名称は『三国志演義』で、元代末期から明代初期にかけて...
全体的に見ると、朱棣の反乱は「反乱」のように見えますが、なぜそれが朱元璋によって仕組まれた効果であったと言われるのでしょうか。
朱元璋は息子の朱彪に明朝の一流の軍事集団を残し、それが息子が王位を継承し北元の主力を徹底的に排除する...
なぜ張孫無忌と朱遂良は劉礼を厄介者とみなしたのでしょうか?
唐王朝(618-907)は、隋王朝に続く中原の統一王朝であり、289年間続き、21人の皇帝がいました...
米芾の有名な詩句を鑑賞する:濃雲の中の双鳳、金玉を突き破る
米芾(1051-1107)、元の名は傅、後に傅と改め、号は元章、号は米または銭。祖先の故郷は太原で、...
「優しいカラスは夜に泣く」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
優しいカラスは夜に鳴く白居易(唐代)優しいカラスは母親を失い、しわがれた声で悲しげな鳴き声を上げまし...
魏定果は水滸伝でどのような経験をしましたか?彼はどうやって死んだのですか?
魏定果は『水滸伝』の登場人物で、神火将軍の異名を持つ。彼は霊州の出身で、もともと霊州の民兵の指揮...