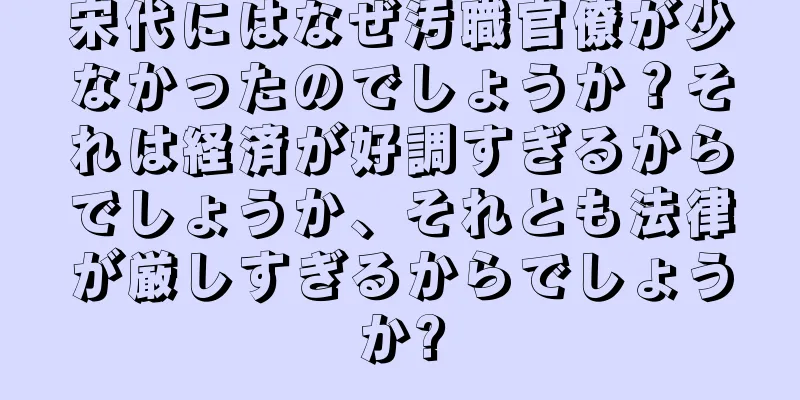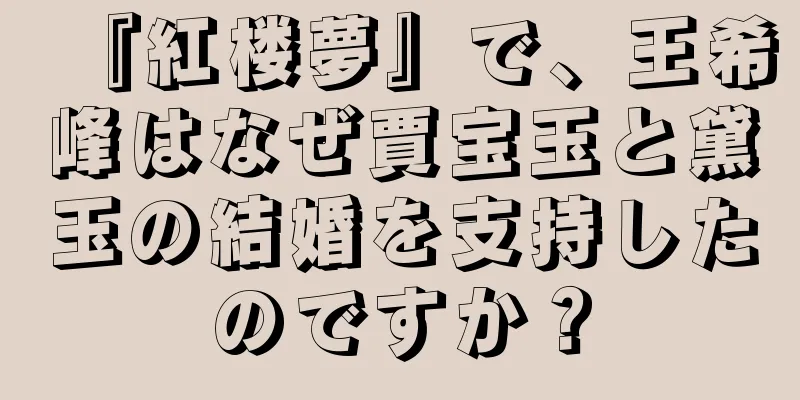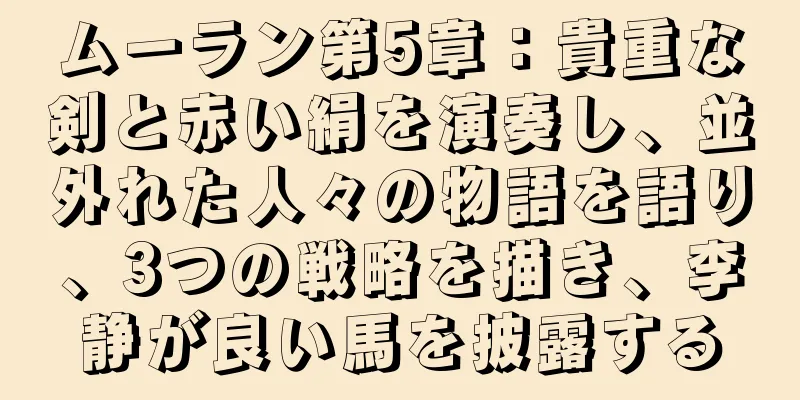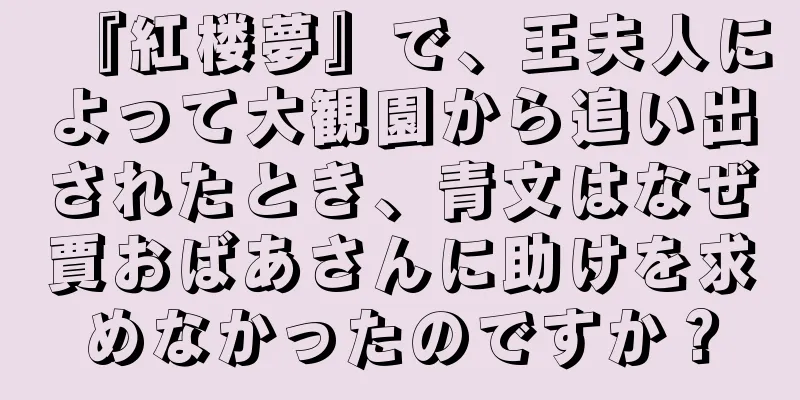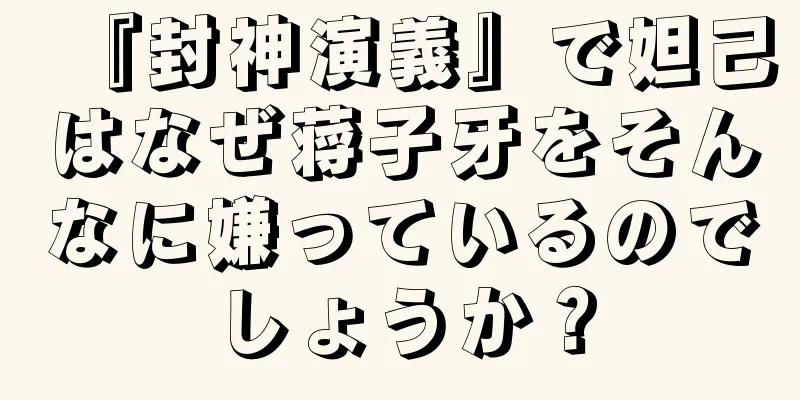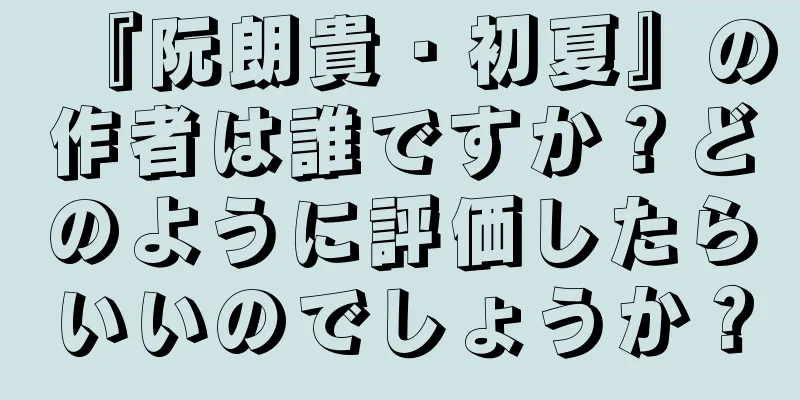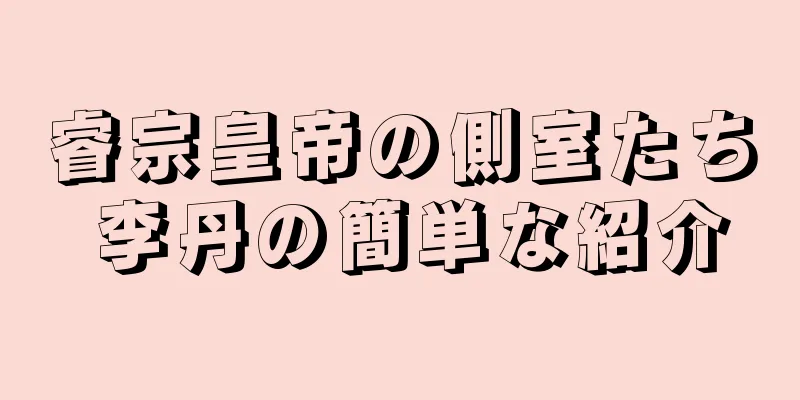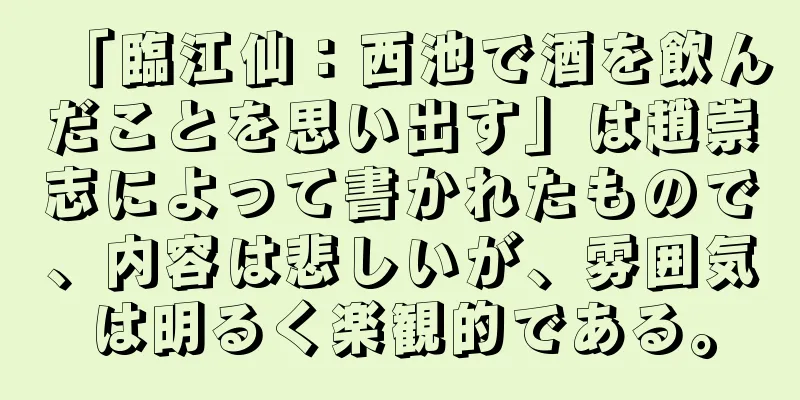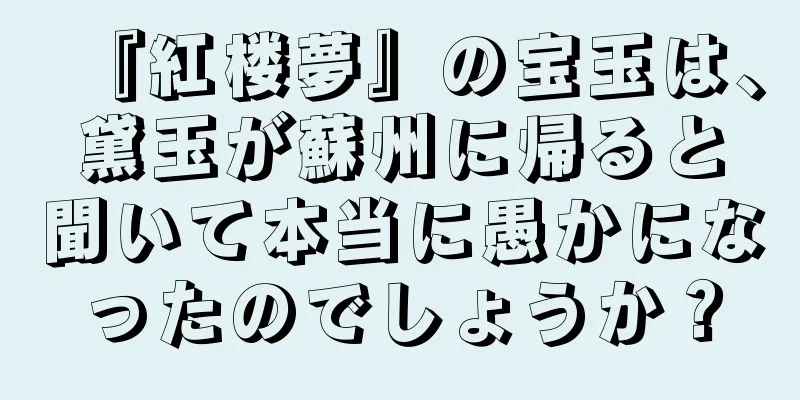呂布の武術は比類のないものと賞賛されていたが、趙雲との決闘の結果はどうなるのだろうか?
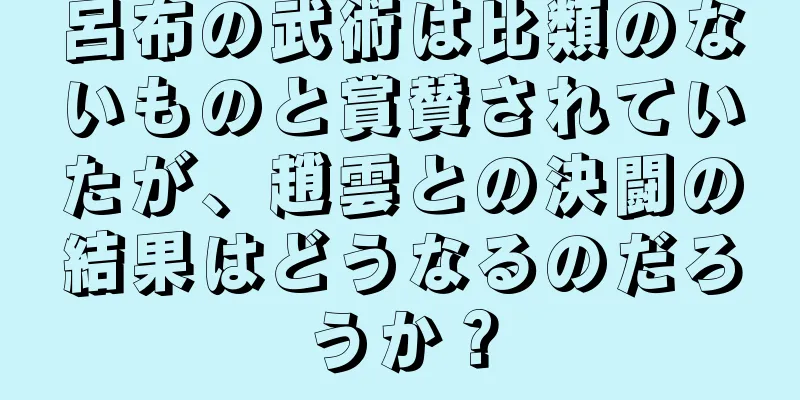
|
周知のとおり、三国時代には多くの英雄たちが覇権をめぐって戦いました。黄巾の乱以外にも各地で反乱が起こり、諸侯も脱出の糸口を見つけるために兵を募り、勢力を集める機会をうかがっていた。最も有名な王子は曹操、劉備、孫権です。しかし、たとえこの三人が並外れた能力を持っていたとしても、賢明な顧問と強力な将軍の支援がなければ、彼らは何も偉大なことを成し遂げることはできないでしょう。つまり、彼がリーダーになれるためには、当然、彼の指揮下にある賢明な顧問や将軍たちが大きな貢献をしたのです。例えば、曹操の配下には張遼、徐晃といった強力な将軍がおり、劉備の配下には「臥龍」諸葛亮がいます。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 今日お話ししたいのは、王子たちの指揮下にある強力な将軍たちに関することです。古来より戦争には勇敢な将軍が多く存在してきましたが、このことは三国時代にも十分に証明されました。当時は、「人中の呂布、馬中の赤兎馬」と言われる三国志最強の将軍・呂布だけでなく、典韋、許褚、関羽、張飛など数え切れないほどの有力な大臣がいた。それだけでなく、『三国志演義』では呂布の強さは誰にも敵わないほどと称賛されました。劉備配下の五虎将軍の中には、有名な関羽や張飛の他に、「常勝将軍」と呼ばれる趙雲という将軍もいます。この二人が一対一で戦ったら、どうなるのでしょうか? 下記、面白い歴史編集者が詳しく紹介するので、見てみましょう! まず呂布の強さを分析する 前述のように、趙雲と呂布の決闘の結果を三国志演義の観点から分析すると、三国志演義の観点からのみ分析することになります。まず呂布は、号を奉賢といい、婺源県九源県の出身であった。ストーリー全体から見ると、呂布の強さは三国志の中でもトップクラスです。そうでなければ、「人の中では呂布、馬の中では赤兎馬」ということわざは生まれなかったでしょう。このような評価を受けられるかどうかは、自分自身のパフォーマンスと密接に関係しています。呂布について語るとき、彼の最高潮の戦いである虎牢関での三英雄との戦いに触れなければなりません。当時、18人の王子が董卓を包囲し、董卓は呂布を派遣して戦いを挑んだが、しばらくの間、誰も彼と戦う勇気がなかった。 その後、張飛は劉備の指揮下にあり、耐えられなくなり戦いに出陣した。呂布と50ラウンド以上戦った後、関羽は再び到着し、張飛とともに呂布と戦いました。小説によると、「費は奮起して呂布と激しく戦った。彼らは50ラウンド以上戦ったが、勝者はいなかった。関羽はそれを見て、馬を叩き、82斤の青龍延月剣を振りかざし、一緒に呂布を攻撃した。3頭の馬はジグザグに戦った。30ラウンド戦った後も、呂布はまだ負けていなかった。」これだけで、呂布の強さをある程度理解できると思います。結局のところ、すべての将軍が関羽と張飛に対して無敗で戦えるわけではない。 しかし、後に劉備が加わったことで呂布はそれを利用する機会を得た。三国志演義によれば、「呂布は攻撃をどう防げばよいか分からなかった。呂布は玄徳の顔を見て、戟で突こうとしたが、玄徳はかわした。呂布は陣形を脇に振り、戟を後ろに引きずり、馬に乗って戻った。」呂布が曹操の将軍6人と対決した濮陽城の戦いは、呂布の強さをさらに物語っている。三国志演義によれば、「許褚が出てきて、20ラウンド戦ったが勝敗は決まらなかった。曹操は言った。「呂布は一人では倒せない。 「呂布は典韋を援軍に派遣し、両将軍が両側から攻撃した。左には夏侯惇と夏侯淵、右には李典と楽進、6人の将軍が一緒に呂布を攻撃した。」6人の強力な将軍を相手に無敗を維持できたことから、呂布の強さが想像できる。 第二に、趙雲の強さを分析する 趙雲は、字を子龍といい、常山鎮(現在の河北省鎮定)の出身である。趙子龍は多くの武将が集まる常山に生まれ、自身の力も非常に強力です。まずは彼が若い頃の戦場での活躍を見てみましょう。 『三国志演義』には、「突然、草の斜面の左側に若い将軍が現れ、馬に乗り、槍を持ち、一直線に文周に向かっていった。公孫瓚が斜面を登ってその若者を見た。身長は8フィート、眉毛は太く、目は大きく、顔は広く、顎は重く、非常に威厳があった。彼は文周と50、60ラウンド戦ったが、勝敗は未だ不明であった。」とある。趙雲が初めて戦場に出たとき、彼は全盛期の文周と対峙し、戦いは50、60ラウンド続き、勝敗ははっきりしなかった。これは彼がかなり強大であったことを示している。 趙雲は開幕戦以外にも多くの功績を残した。結局のところ、「常勝将軍」という称号は不当なものではない。例えば、長盤浦の七つの出入り口。これも彼の人生における大きな功績です。 『三国志演義』によると、「この戦いで、趙雲は皇帝を抱きかかえ、包囲を突破し、大旗を二本切り落とし、三本を奪い、槍と剣で曹陣営の名将五十人以上を殺した」とある。もし心にそれほどの決意を持っていない他の将軍であれば、曹軍の勢いに怯えていただろう。趙雲の演技は彼の内なる決意をさらに表している。 3番目に、二人の戦いの状況と結果を分析する 以上、呂布と趙雲それぞれの強さを分析しました。二人とも三国志の中でも稀有かつ強力な武将であることは容易に想像がつくでしょう。しかし、二人が一対一で戦った場合、呂布が勝つ可能性が高いと個人的には思います。結局、呂布は関羽と張飛とそれぞれ数十ラウンド戦ったのです。しかし、趙雲の強さは関羽や張飛に比べるとはるかに劣っています。 劉備配下の五虎将軍におけるこの三人の順位だけを見ても、何かが分かるだろう。呂布と趙雲が戦えば、百回以内で互角になるかもしれないが、戦いが長く続くと趙雲が弱まり、呂布に敗れるかもしれない。このことから、「三国志演義」によれば、趙雲が単独で呂布と戦った場合、趙雲が負ける可能性が高くなることがわかります。 |
<<: 荀攸は曹操から「我が子芳」と呼ばれていたが、なぜ張良のように幸せな結末を迎えなかったのだろうか?
>>: 甄嬛は曹丕の寵愛を10年間独占していたのに、なぜ郭王后に取って代わられたのでしょうか?
推薦する
デアン民族の歴史 デアン民族の名前と起源の簡単な紹介
「デアン」はこの民族の自称です。 「Ang」はデアン語で「洞窟」を意味します。「De」は敬称の追加語...
「風と雨」の原文、翻訳、鑑賞
風雨李尚閔(唐代)剣の悲しい章、私は何年も立ち往生するでしょう。黄色い葉はまだ風雨に覆われ、売春宿で...
沙陀族はどこから来たのですか?沙陀族はどのようにして唐王朝の一部になったのでしょうか?
沙沐族はどこから来たのか?沙沐族はどのようにして唐朝に組み込まれたのか?興味深い歴史の編集者と一緒に...
チャオガイが奪った誕生日プレゼントは価値のあるものなのでしょうか?今、いくらぐらいの価値があるのでしょうか?
趙蓋が奪った誕生日プレゼントは価値あるものだったのか?今ならいくらになるのか?次のInteresti...
秦以前の学術書『管子書演』は何を表現しているのでしょうか?
秦以前の学術書『管子』に書かれた思想は、当時の政治家が国を治め、世界を平定するために用いた偉大な原則...
『禅真史』第 30 章: 沈蘭は陣地を略奪し、全軍を捕らえた。牛金は悪人を罰するために街へ出た。
本日は、Interesting History編集部が『禅真史』第30章の全文をお届けします。明代の...
『紅楼夢』には、生涯を通じて一人の女性に忠実であり続ける男性はいますか?彼は誰ですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
水滸伝第76章:呉嘉良が四分割五角旗を配し、宋公明が九方八図の陣形を配する
『水滸伝』は、元代末期から明代初期にかけて書かれた章立ての小説である。作者あるいは編者は、一般に施乃...
「江徳河に泊まる」は孟浩然が呉越を旅していたときに書いたものである。
孟浩然(689-740)は、浩然、孟山人としても知られ、襄州襄陽(現在の湖北省襄陽市)の出身です。唐...
晋の詩人蔡松年の詩集「山葵空 蓮華を鑑賞する」
以下に、Interesting History の編集者が、蔡松年の『山葵天・蓮華観』の原文と評価を...
晋の廃帝、司馬懿の物語。司馬懿に関する逸話や物語は何ですか?
司馬懿(342年 - 386年)は、雅号を延陵といい、晋の成帝司馬炎の次男で、晋の哀帝司馬丙の弟であ...
「春秋双葉」第六話の主なストーリーは何ですか?
駆け落ちした乳母は殺され川に流され、秋娘は難を逃れた。侯尚官はもともと落ち着きのない人物だったと言わ...
なぜ劉備は漢王朝を支持するのではなく、「鳳山勇利」を究極の追求としたのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
荀攸は曹操に助言を与えて常に助けていたのに、なぜ年老いてから曹操を裏切ったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
哲学の名著『荘子』雑集と寓話集(3)原文と方言訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...