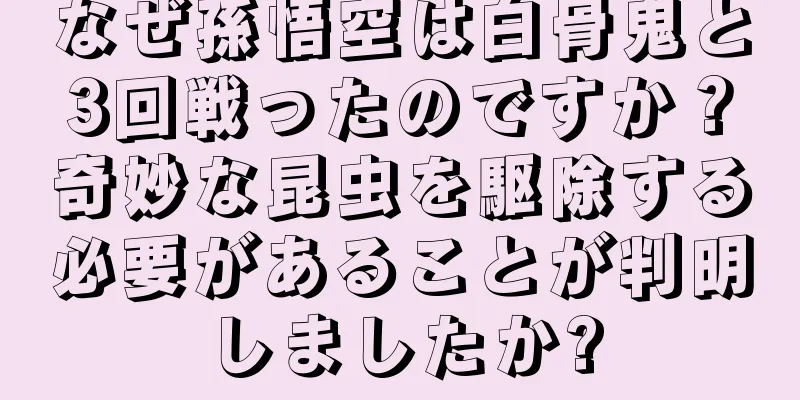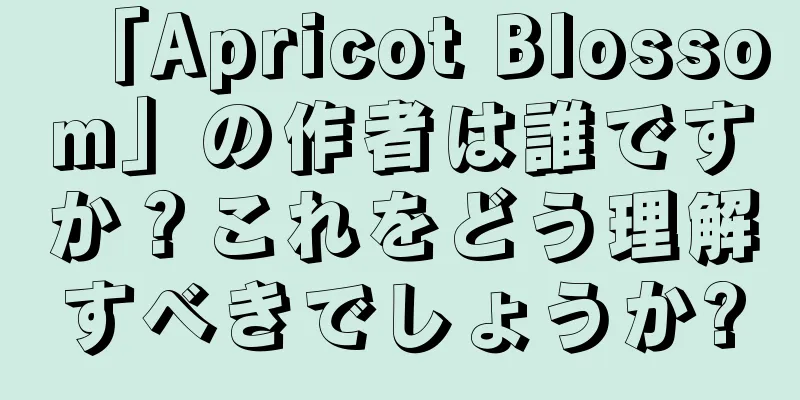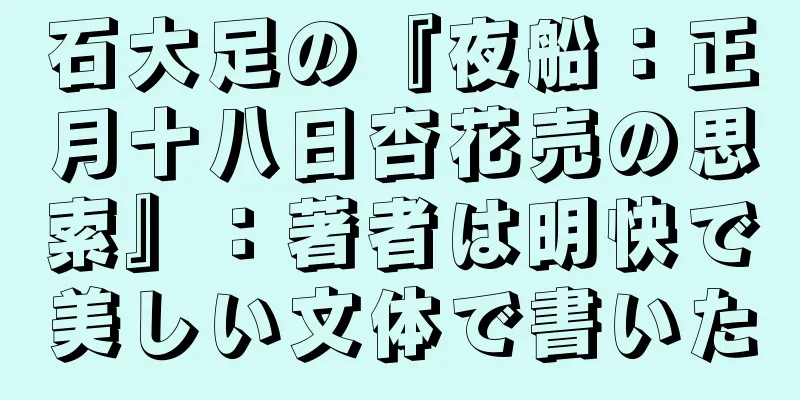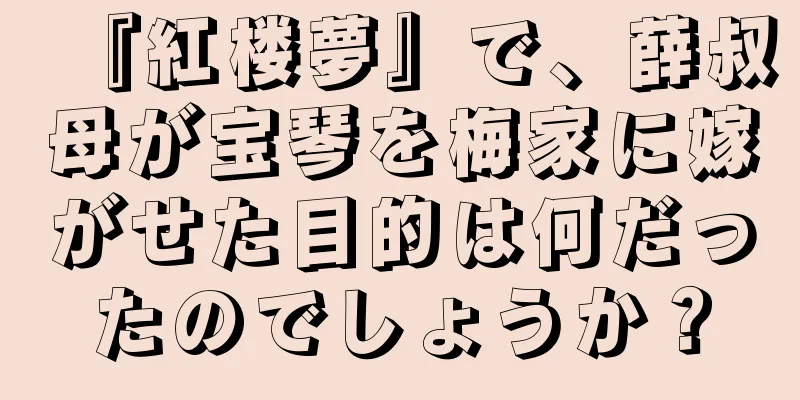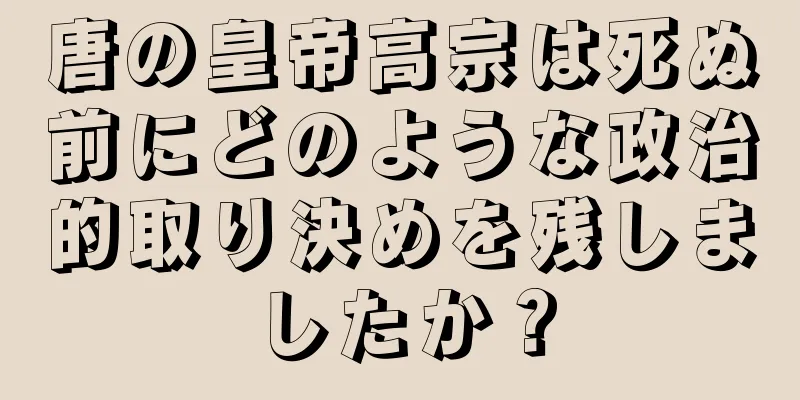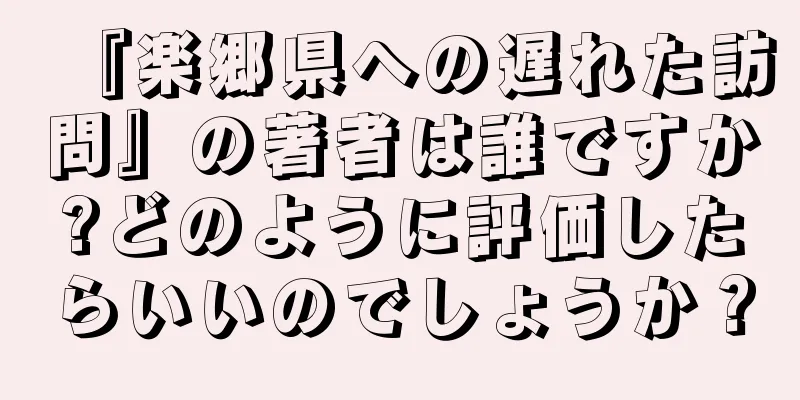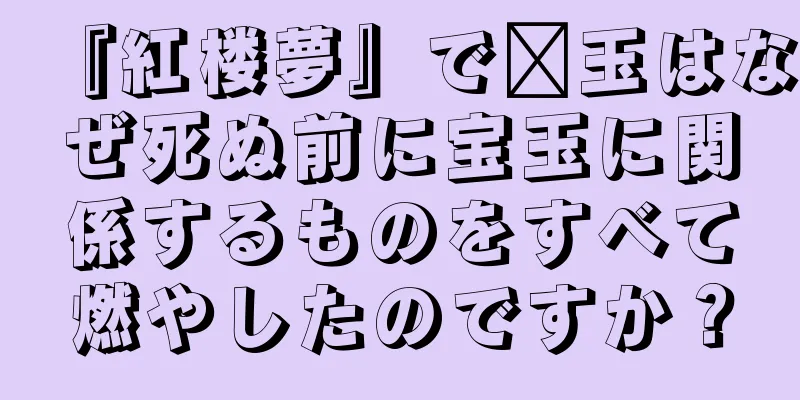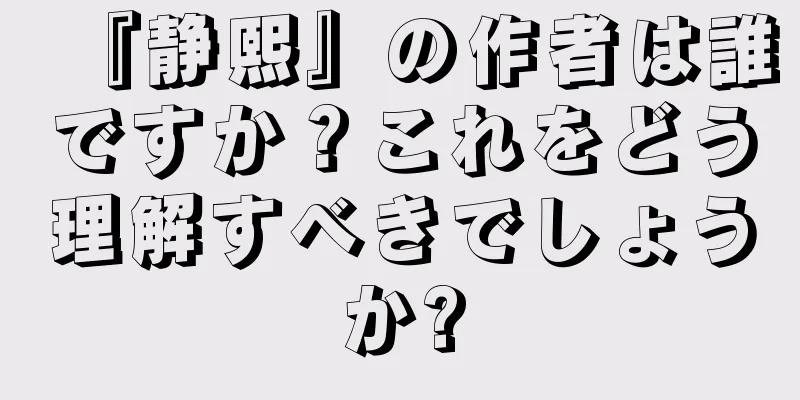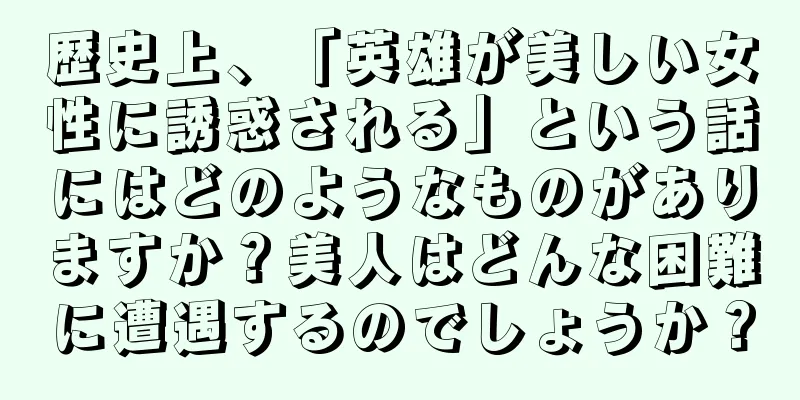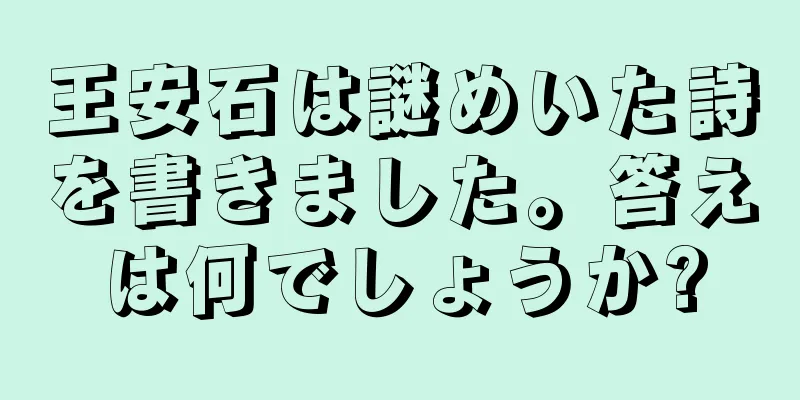古代漢服の袖はどれくらいの長さまで入るのでしょうか?そこに物を入れると、なぜ落ちないのでしょうか?
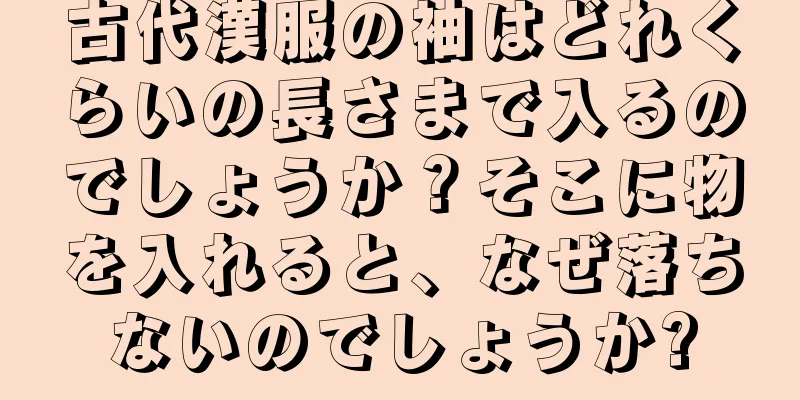
|
時代劇では、漢服を着た人が袖に物を入れたり、袖から物を取り出したりするシーンがよく登場します。では、漢服の袖にはどれくらいの量が入るのでしょうか?袖の中に物を入れても落ちないのはなぜでしょうか?今日は、Interesting History の編集者が関連コンテンツをお届けしました。 漢服は全体的に華やかですが、現代の服のようにポケットがたくさんついているわけではありません。しかし、問題は、古代の人たちが外出するときにどのように物を保管していたかということです。彼らは当然、大きな物を手に持ちますが、小さな物もすべて手に持ち運ぶことはできませんよね。それは便利でも美しくもありません。そこで古代人は、それらの小さなものを広い袖の中に入れるという解決策を思いつきました。 もちろん、袖の中に物を直接入れることは不可能です。そうしないと、手を離すとすぐに物が落ちてしまいます。そこで古代人は、体にポケットがないので、袖にポケットを縫い付ければよいと考えました。袖のポケットは肘の近くに縫い付けられていることが多く、一般的に口が小さく底が大きく、開口部が上向きに傾斜し、留め具が台形になっているため、中に入れたものが落ちにくい構造になっています。こうすることで、外出時に軽いものを収納する場所が確保され、外出時に簡単に盗まれることがなくなります。また、服全体の見た目にまったく影響しないのもポイントです。 私たちは皆、「両袖清風」という慣用句を聞いたことがあるでしょう。これは、両袖の中には清風以外に何も入っていないという意味です。これは主に、正直な役人を表すときに使われます。この諺の由来は、昔、袖の内ポケットは主に金銀を収納するために使われ、正直な役人は当然余分なお金を持っていなかったため、袖の内ポケットは当然空っぽだったため、「袖二つに清風」ということわざがありました。 金銀のほか、手紙やハンカチなどの軽い物を保管するのにも使われます。官吏であれば記念品などの保管にも使われます。保管や取り出しに便利で、自分の行動に影響を与えません。 重い金銀をたくさん持ち歩く必要があり、袖に入れるのが少々面倒だったり、保管したい物が重要で袖に入れるのが安全でなかったりしたら、古代人はどうしたらいいのだろうと疑問に思う人もいるかもしれません。実は、袖の内ポケットに加えて、古代人は財布、鞍袋、胸の襟など、物を保管する他の場所を持っていました。これらの保管方法は、袖の内ポケットと比較して、それぞれ長所と短所があります。なぜ小さな物は胸ではなく袖の中に入れることが多いのでしょうか? 古代人は礼儀作法を重視し、公共の場で胸から物を取り出すのは野蛮なことだと考えていたため、自然に袖の内ポケットに物を入れる傾向があったのです。 しかし、古代では誰もが内側の縫い目にポケットがあり、袖が広い服を着ていたわけではありません。このような袖の広い衣服を着るのは、役人や貴族、裕福な家庭、あるいは文人だけであり、行商人や農民などの一般の人々に、そのような豪華な衣服を買う余裕はなかった。第二に、彼らは一年中働く必要があり、袖口がゆるい服を着ていると仕事に非常に不便です。たとえば、農夫が袖の広い服を着て畑仕事に出かけたら、「動きが鈍くてだるい」と思いませんか。 そのため、昔の人が袖の中に物を入れても落ちなかったのは、袖の内側に内ポケットが縫い付けられていたからなのです。また、現代のテレビドラマのストーリーは、古代の実際の状況とは必然的に異なることも知っておく必要があります。例えば、内ポケットの深さ。現代の映画やテレビドラマでは、撮影の都合上、内ポケットは浅めに作られていますが、昔は、肘の近くに縫い付けられていることが多かったのです。 |
<<: 古代の妻は側室を意のままに罰することができたのでしょうか?妾は単なる生殖の道具なのでしょうか?
>>: なぜ古代人は中国語で書かなかったのでしょうか?理由を説明する
推薦する
歴史上最も原始的な毒:古代の「毒」は毒薬を意味しない
はじめに: 「謝管子」を読んでいると、とても興味深い箇所を見つけました。魏王は扁鵲に、医術に長けた三...
李青昭の『星香子・七夕』:詩人の心の悲しみと別れを表現している
李清昭(1084年3月13日 - 1155年)は、易安居士とも呼ばれ、宋代の斉州章丘(現在の山東省章...
『紅楼夢』では、西仁は江玉漢と結婚し、とても幸せな結末を迎えます。
『紅楼夢』の華希仁は、王夫人に認められ、側室のような待遇を受けた最初の人物である。しかし、結局彼女は...
庚始皇帝劉玄とはどんな人物だったのでしょうか?庚始皇帝劉玄はどのようにして亡くなったのでしょうか?
劉玄さんはどんな人ですか?劉玄は歴史上有名な更始皇帝です。彼は緑林軍に加わり、皇帝に即位しました。後...
宋高宗趙狗には何人の王妃がいましたか?趙狗の皇后と側室のリスト
はじめに:趙狗(1107-1187)、号は徳済、南宋の初代皇帝、すなわち宋の高宗皇帝である。宋の徽宗...
唐代の重要な軍事書『太白陰経』全文:人略第一部:心を探る章
『神機滅敵』は『太白陰経』とも呼ばれ、道教の著作です。古代中国では太白星は殺生の達人であると信じられ...
王希峰の「一人は服従、二人は命令、三人は木偶の坊」という判決の深い意味は何でしょうか?
『紅楼夢』第五章で、賈宝玉が太虚の幻界で金陵十二美女の「生涯帳」を見ているとき、王希峰を暗示する「氷...
『紅楼夢』では、賈家の称号は何世代にわたって受け継がれてきたのでしょうか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
杜遜和の『自伝』では、詩人は自身の感情を通して現在の政治情勢に対する不満を表現している。
杜遜和は、字を延芝、号を九花山人といい、唐代末期の官僚詩人であり、写実主義の詩人である。彼は詩が優雅...
南北朝時代の衣服:古代中国の衣服史における大きな変化の時代
南北朝時代は古代中国の服装史において大きな変化があった時期であり、この時期に大量の胡人が中原に移住し...
孤独な指揮官である霊済菩薩が、八菩薩の中で上中位に位置する資格があるのはなぜでしょうか?
『西遊記』では、八大菩薩を横に並べて比較すると、非常に興味深い状況が見つかります。他の菩薩には乗り物...
紅楼夢の刺繍入り小袋は誰のものですか?宝仔と平児はすでに知っていた
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
『紅楼夢』にはたくさんのお金持ちが登場しますが、最高の生活を送るお金持ちの女性は誰でしょうか?
『紅楼夢』にはたくさんのお金持ちが登場しますが、最も良い生活を送っているお金持ちの女性は誰でしょうか...
「ドアの外には何千エーカーもの緑の木陰があり、オリオールのつがいが一斉に歌っている」という有名な一節はどこから来たのでしょうか?
「門外千畝の緑陰、コウライウグイスはつがいになって鳴く」という有名な一節がどこから来たのか知りたいで...
イ族の習慣 イ族衣装コンテストフェスティバルはどのようにして始まったのでしょうか?その特徴は何ですか?
長い歴史と豊かで素朴な民族文化を体現するイ族の「衣装コンテスト祭り」は、古代の祭祀や「料理の引き継ぎ...