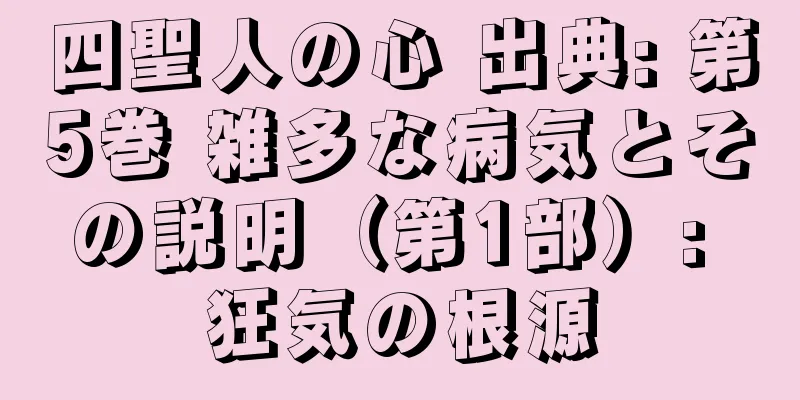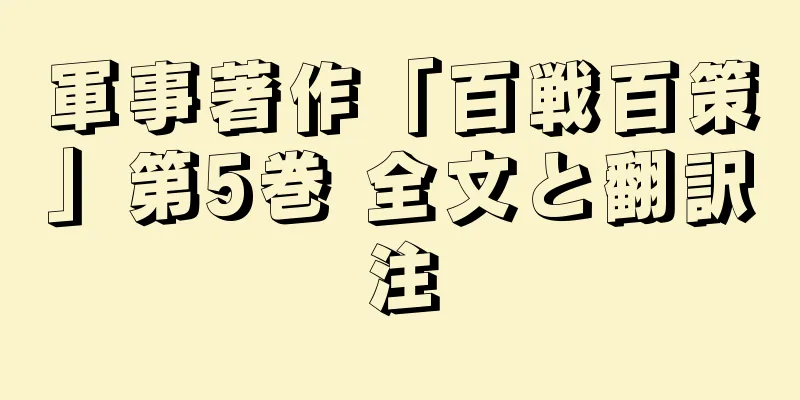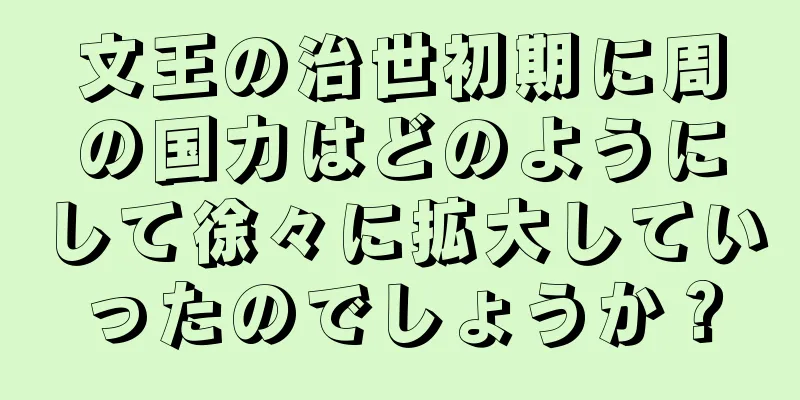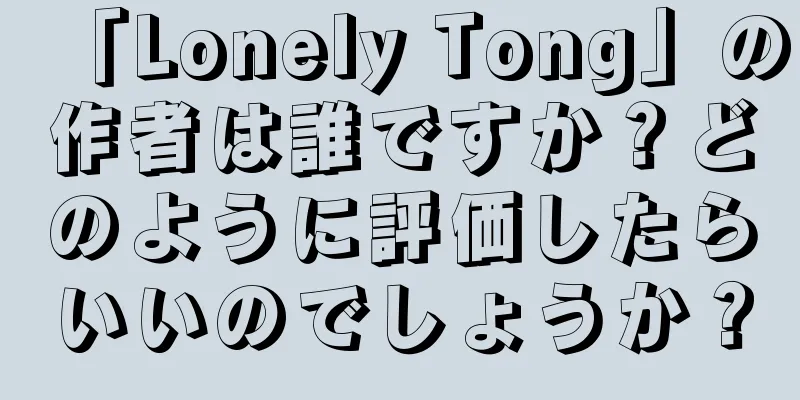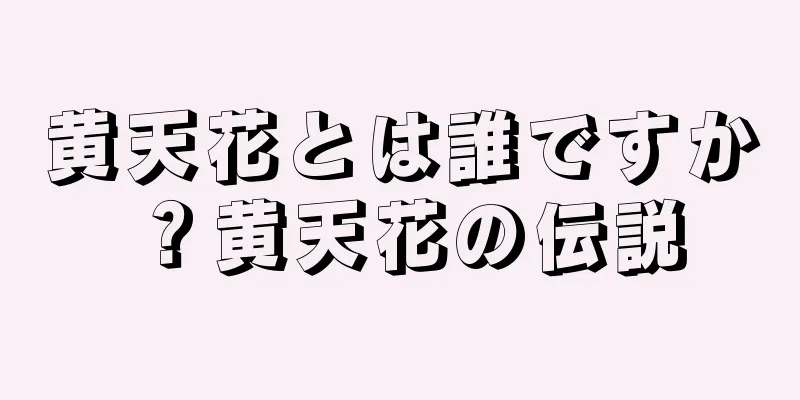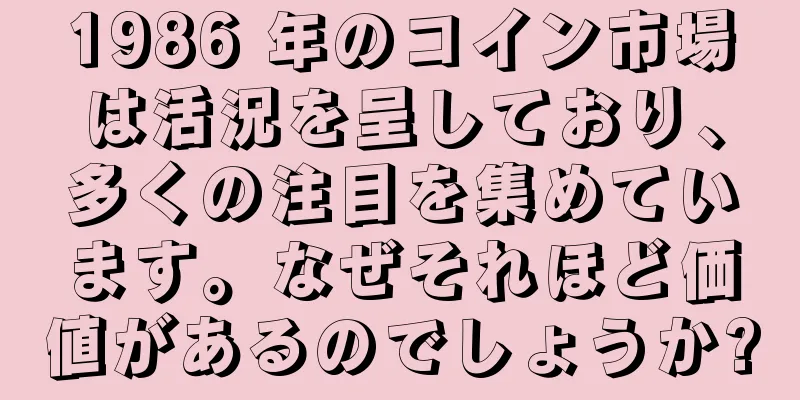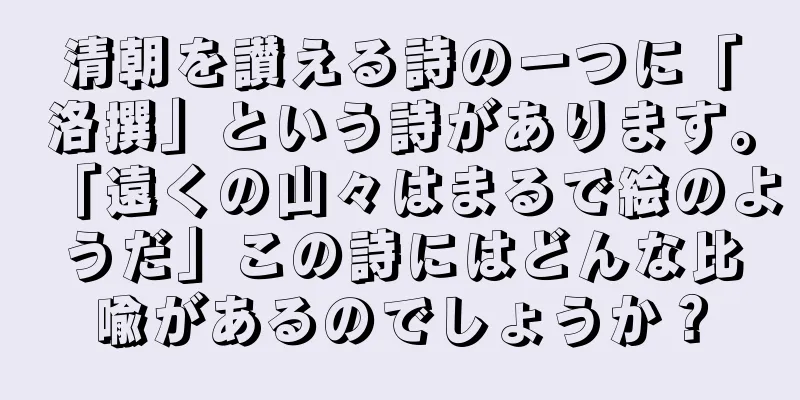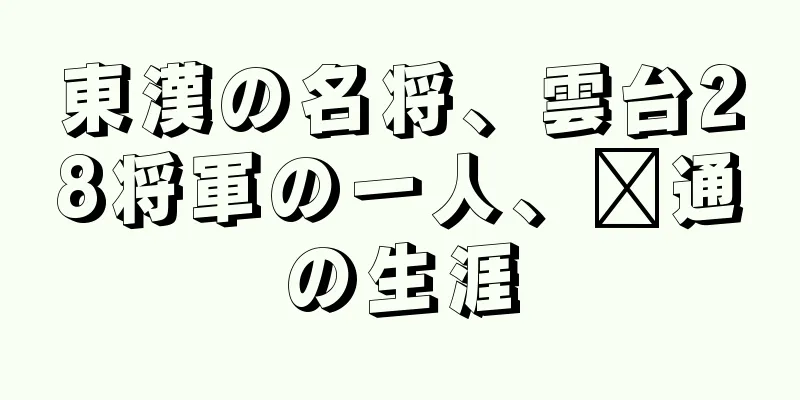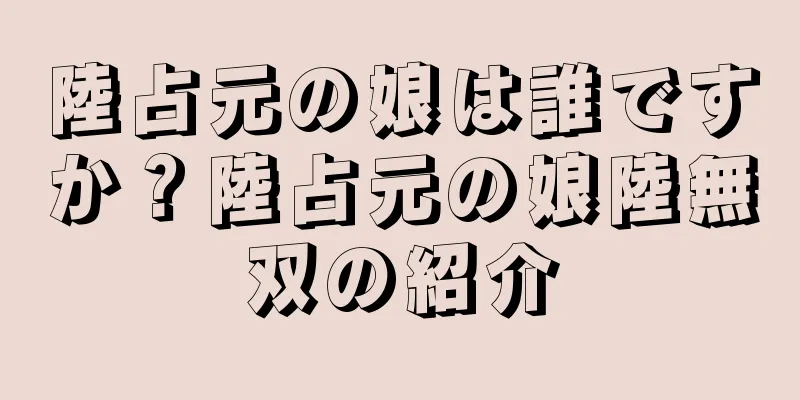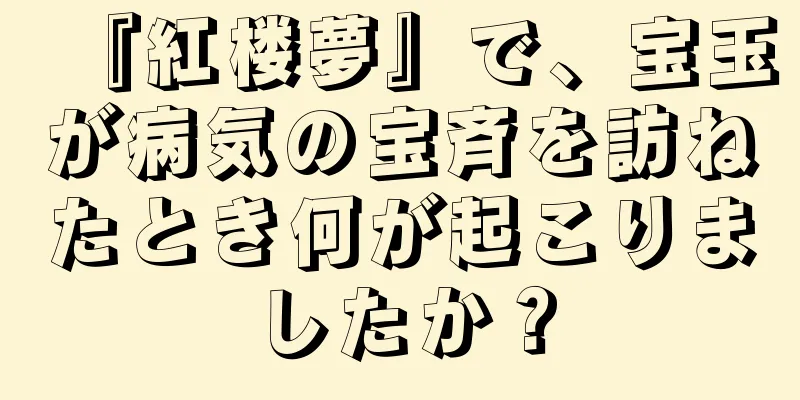諸葛亮は漢王朝を旧都に戻すよう求めたのに、なぜ長安を遠征の目標にしなかったのか?
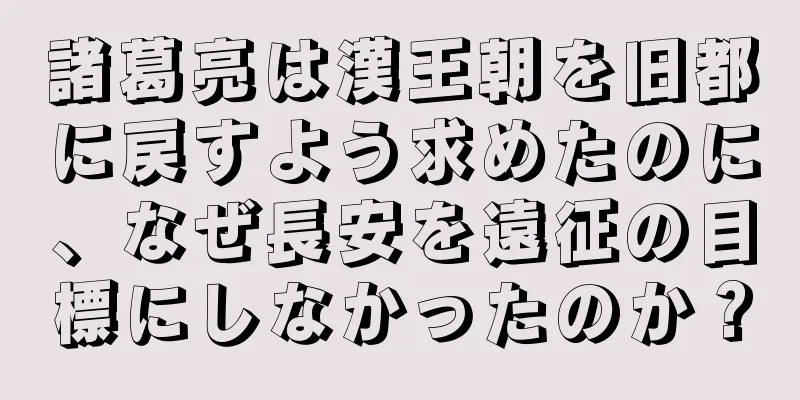
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、諸葛亮が漢王朝を古都に戻そうとしたが、北伐の目標として長安を取らなかった理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 諸葛亮は蜀漢政権を掌握した後、漢王朝を支えるという理想を実現するために、曹魏に対して5回の北伐を行なった。これらの北伐はさまざまな理由で失敗に終わったが、死ぬまでその目的に身を捧げた諸葛亮の精神は世界中から賞賛されている。これらの北伐を見ると、諸葛亮のスローガンは漢王朝を古都に戻すことであったにもかかわらず、長安を遠征の目標としなかったことがわかります。それはなぜでしょうか。 1. 諸葛亮は戦争を通じて戦争を学んだ。 諸葛亮は管仲や岳毅と自分を比べていたが、実際に戦争を指揮していた期間は長くはなかった。諸葛亮の先祖は漢代に近衛軍の監察官を務めていたため、当然ながら彼の家族には軍事の知識が受け継がれていました。諸葛亮はそのような家庭で育ったため、当然ながら軍事面での深い知識を身につけ、それが将来の戦争指揮の理論的基礎となった。 しかし、劉備には関羽、張飛、馬超といった一流の武将がいたにもかかわらず、国を治める才能が欠けていた。そのため、劉備は蕭何のように諸葛亮を利用し、彼の才能を国を治める上で十分に発揮させようとし、彼自身が戦いを指揮することはさせなかった。諸葛亮は地方を治め、軍隊を組織して訓練し、兵站資源を配置し、劉備が安心して戦えるだけの十分な食料と兵士を確保し、すぐに形勢を逆転させて荊と益を征服するという成果を収めた。 しかし、夷陵の戦いの後、蜀軍は連敗し壊滅的な打撃を受けた。あらゆるレベルのエリート部隊と指揮官が多数死亡した。諸葛亮は白帝城の孤児の信頼を受け入れた後、軍の再編成という重責を担うことになった。彼の努力により、10万人の蜀軍が再建され、諸葛亮自らが彼らを率いて北伐に赴いた。 諸葛亮の5回の北伐を見れば、彼の指揮能力がいくらか分かるだろう。諸葛亮は軍事的に優れた才能を持ち、理論的には当時の将軍たちを凌駕していました。彼は軍隊の訓練に長けており、彼が訓練した軍隊は戦闘隊形がよく組織化されており、厳格な命令に従っていた。しかし、戦争の初期段階では、諸葛亮とその軍隊には大きな問題がありました。それは、豊富な実践経験が欠けていたことです。この種の実践的な経験は戦闘を通じてのみ得られ、理論的な経験は信頼できません。 そのため、最初の3回の北伐では諸葛亮は挫折を味わった。しかし、これらの挫折は諸葛亮の実践経験を豊かにし、彼の軍事指揮術の質的な飛躍を可能にした。諸葛亮の第四次北伐から、彼の優れた指揮の下、実戦訓練を受けた蜀軍は魏軍を段階的に打ち破りました。魏軍は前進するときには敢えて戦わず、後退するときには敢えて追撃しませんでした。残念ながら、諸葛亮は若くして亡くなり、理想を実現することができませんでした。 2. 長安を攻撃しなかった理由は、客観的な条件がそれを許さなかったためである。 諸葛亮の五度の北伐では長安は戦闘の目標とされなかったが、これは自然条件と蜀軍の能力の両面から見て非現実的であったためである。歴史上、魏延はかつて諸葛亮に「紫霧谷の計」を提示し、紫霧谷から長安に奇襲を仕掛けようとしたが、諸葛亮に拒否された。諸葛亮は長安を攻撃することは無意味でも現実的でもないことをはっきりと知っていたからだ。 まず、長期にわたる戦争により、長安は関中での戦略的地位を失っていました。東漢の時代には、朝廷は洛陽に首都を置きました。長安は政治の中心地としての地位を失い、経済発展にも影響が出ました。董卓の時代、東漢の朝廷は長安に移りましたが、長安に繁栄をもたらすどころか、次々と戦争を引き起こしました。 これらの戦争で長安は大きな被害を受けた。関中一帯はイバラに覆われ、荒れ果てていた。巨大な都市長安は住民を失い、死の都市となった。巨大な都市があるが、城壁は崩壊し、防御はどこも空っぽで、防御は不可能となっている。これに加えて補給の困難もあって、防衛側は大きな困難に直面した。 長安は守備側にとって悪夢とも言える。攻撃するのは簡単だが守るのは困難な巨大な負担だ。諸葛亮はこれをはっきりと理解しており、この重荷を引き受けることは絶対にできないと考えていた。なぜなら、たとえ蜀軍が長安を占領したとしても、その兵力はわずか10万人であり、その大半を長安の防衛に投入しなければならなかったからである。さらに、関中の数千里に及ぶ平原のため、蜀軍は騎兵を主体とする魏軍の動きを抑えることができず、孤立し、窮地に陥った。諸葛亮は損失を補えないような行動は決して取らないだろう。 第二に、諸葛亮は実際の戦闘経験に基づいて、曹魏とともに城攻めと防衛を行う戦闘方法を採用しなかった。長安のような巨大な都市を攻撃するには、長期にわたる市街地攻撃と防衛の戦いが必要であった。こうした戦闘能力こそが蜀軍に欠けているものである。第二次北伐の際、諸葛亮は蜀軍の力量を試すために陳倉への攻撃を開始した。 実際のパフォーマンスから判断すると、結論は残念です。数万の蜀軍が、千人余りの魏軍が占領していた陳倉を攻撃した。彼らはあらゆる手段を講じたが、20日余りの激戦の末、陳倉を陥落させることはできなかった。この戦いで諸葛亮は蜀軍の強さと長安をすぐに占領できないことをはっきりと認識した。もし戦争が長期化すれば、前に長安、後ろに魏軍の援軍がいて、蜀軍は勝てなくなるだろう。そのため、諸葛亮の北伐では、第二次北伐で陳倉を包囲しただけで、それ以外の包囲作戦は行われなかった。 3つ目は、諸葛亮の実際の戦闘戦略です。諸葛亮は関中平原と蜀・魏軍の特性を考慮して、多くの戦闘試行を経て、野戦に重点を置き、魏軍の主力を排除してから関龍を制圧するという最終的な戦闘戦略を決定しました。魏軍の主力が破壊されれば、長安も容易に手が届くようになるだろう。 蜀軍には実践的な経験と戦闘で鍛えられた体力がなかったため、諸葛亮は彼らのために防御的な反撃という戦闘方法を考案しました。戦闘では、諸葛亮の「八図」で訓練された蜀軍は、まず粘り強い防御で敵の攻撃を打ち破り、次に敵の弱点を突いて反撃しました。この戦術により、魏軍は防衛が困難となり、度重なる敗北を喫した。王爽や張郃のような勇敢な将軍でさえも蜀軍に殺された。 第四次北伐以降、諸葛亮の戦い方は成熟した。ますます強力になる蜀軍に直面して、魏軍は持ちこたえて戦わない戦略を採用するしかなかった。曹魏の君主や大臣たちは、まず蜀軍の食糧や草を食い尽くし、蜀軍の兵站補給の困難につけ込み、蜀軍の食糧や草が尽きて撤退したときに追撃して敵を倒すという綿密な計画を立てたと自慢していた。 この計画は諸葛亮の第四次北伐において一定の役割を果たしたが、諸葛亮を追撃する間に魏軍は壊滅的な敗北を喫し、名将張郃は戦場で死亡した。諸葛亮が第五次北伐を開始したとき、魏軍はもはや戦う勇気がなく、諸葛亮が陣地の前で農耕を行うことを許可した。もし諸葛亮が病死していなかったら、戦争の結果はどうなっていたか分からない。 そのため、諸葛亮の第五次北伐の際、司馬懿が諸葛亮を勇敢な男ではなく、長安を背後から攻撃する勇気もなかったと嘲笑したことは、全く根拠のないものであった。諸葛亮は野戦で敵を倒すという戦術をとっており、長安は諸葛亮の戦闘目標には全く入っていなかった。 結論: 諸葛亮の五度の北伐の際、長安は一度も作戦目標とされなかった。これは、長安が長年の戦争に苦しみ、戦略的な地位を失っていたためである。諸葛亮の長安占領は無意味であったばかりか、蜀軍の大半を投入する必要があり、彼自身に大きな負担を課した。さらに、関中の数千里の平原を利用して、騎兵を主体とした魏軍が国中を縦横に動き回り、長安を包囲状態に陥れ、蜀軍の不利な状況をさらに悪化させた。 さらに、蜀軍には攻撃力と征服力が欠けていたため、長安を速やかに占領することは困難でした。膠着状態になれば蜀軍にとって非常に不利となるだろう。そこで諸葛亮は蜀軍に防御的な反撃戦闘法を編み出し、野戦で敵の主力を撃破するという戦闘戦略を採用した。魏軍の主力が壊滅すれば、関龍は当然我々の手に入るだろう。残念ながら、魏軍は抵抗して戦うことを拒否し、諸葛亮は若くして亡くなったため、彼の作戦は実行できませんでした。 |
<<: 曹爽が処刑されたとき、なぜ誰も助けに来なかったのですか?
>>: 公孫瓚は劉備を大いに助けたのに、なぜ劉備は独自の派閥を設立したのでしょうか?
推薦する
石公の事件第435章:大明城で奇妙な風に遭遇し、淫らな僧侶を訪ね、密かに観王寺を探索する
『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...
ジ・カンはシャン・タオを長い間知っていたのに、なぜ友情を断つ手紙を書いたのでしょうか?
魏晋の時代はとても自由奔放な時代だったと誰もが言います。文人は酒を飲み、笑い、叱り、気ままで、文章に...
「Re-Gift」が誕生した背景は何でしょうか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
再贈与袁真(唐代)リンロンに私の詩を歌わせないでください。私の詩のほとんどはあなたへの別れの言葉です...
旧暦1月2日の習慣は何ですか?なぜ「婿の日」と呼ばれるのでしょうか?
旧暦の正月2日はどんな風習があるのでしょうか?なぜ「婿を迎える日」と呼ばれるのでしょうか?旧暦の正月...
古典文学作品『東遊記』第19章:蔡和が板を持ち踊る
『東遊記』は、『山東八仙伝』や『山東八仙伝』としても知られ、全2巻、全56章から構成されています。作...
「王朗送」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
王朗を送る黄庭堅(宋代)私はあなたに浦城の桑の葉で作った酒を出し、湘怡の秋菊のエッセンスを添えて航海...
なぜ作家の王公は蘇軾の五台詩事件に関与したのか?
王公は宋代の詩人で、優れた画家でもありました。蘇軾が徐州の官吏だったとき、王公は蘇軾を山河遊覧に誘い...
孔子に供物を捧げた最初の皇帝は誰ですか?
劉邦は、本名を劉基といい、沛県豊義(現在の江蘇省豊県)の人です。周の南王59年(紀元前256年)に生...
明軍はモンゴルの騎兵隊を打ち破ることができたのに、なぜ清軍を打ち破ることができなかったのでしょうか?
冷兵器の時代にモンゴル軍が非常に強かったことはよく知られています。では、なぜ明軍はモンゴル騎兵隊を倒...
北宋時代の軍事著作『武経宗要』第二巻全文:北宋時代の軍事著作『武経宗要』第二巻全文
『武経宗瑶』は北宋の政府が編纂した軍事書である。著者は宋の仁宗の治世中の文官、曾公良と丁度である。二...
拓跋洪には何人の妻がいましたか?北魏の献文帝拓跋洪の妻は誰でしたか?
北魏の献文帝拓跋洪(454年 - 476年)は、文成帝拓跋鈞の長男で、南北朝時代の北魏の第6代皇帝で...
古今奇蹟第20巻:荘子は盆を打つのをやめて偉大な道になる
『今昔奇談』は、明代の鮑翁老人によって書かれた、中国語の俗語による短編小説集です。馮夢龍の『三語』と...
白骨魔との3回目の戦いで、孫悟空はなぜ唐僧に追い払われたのですか?
『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...
魏索制度はなぜ明朝の繁栄の基盤を築いたとも、明朝を滅ぼしたとも言われているのでしょうか。
魏索の概念を最初に提唱したのは、元代の歳入大臣である張昌であった。明の洪武17年(1384年)、全国...
『西遊記』で、なぜ真元子は如来を恐れず、観音に頭を下げるのでしょうか?
周知のように、『西遊記』の真元子はずっと傲慢な人物ですが、なぜ真元子は如来を恐れず、観音に頭を下げる...