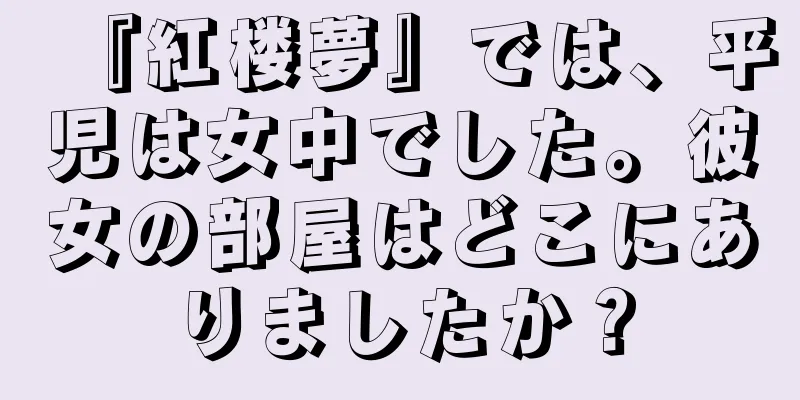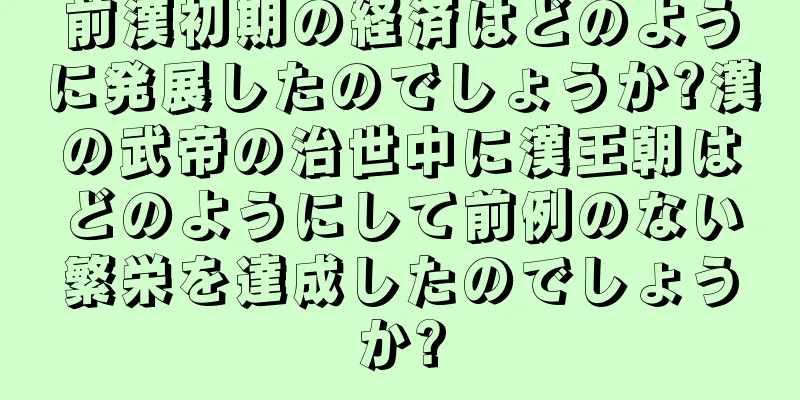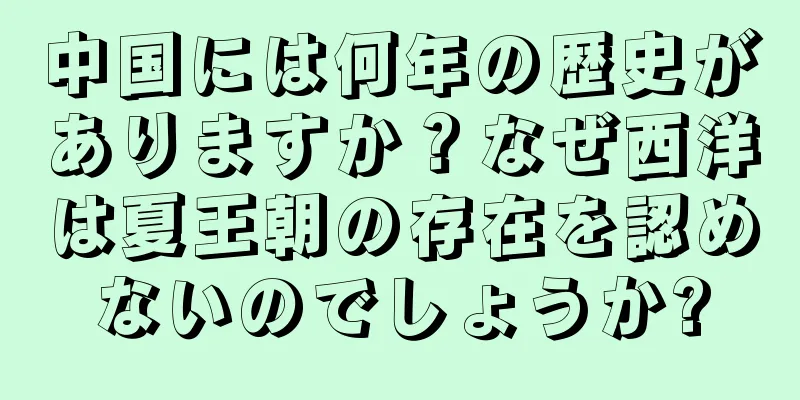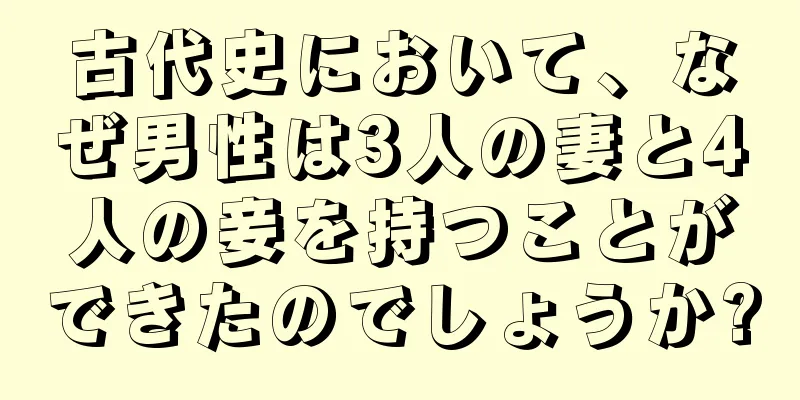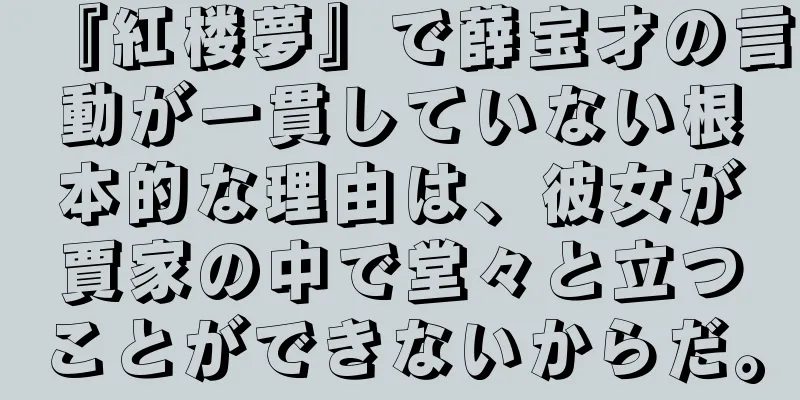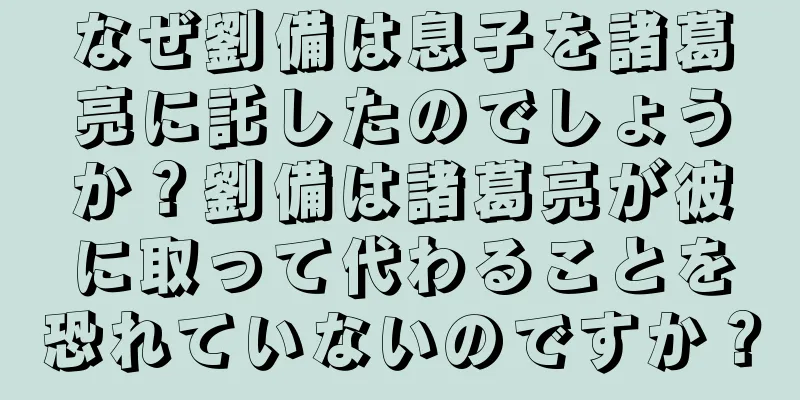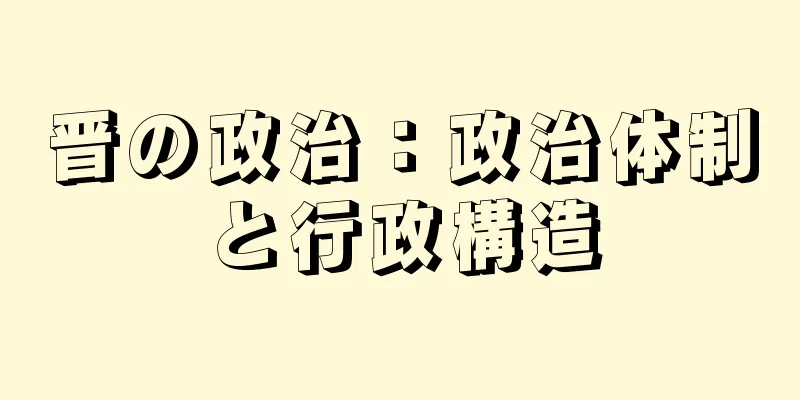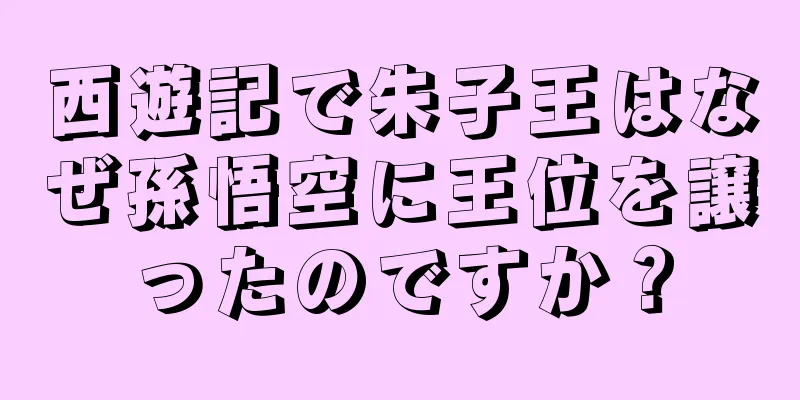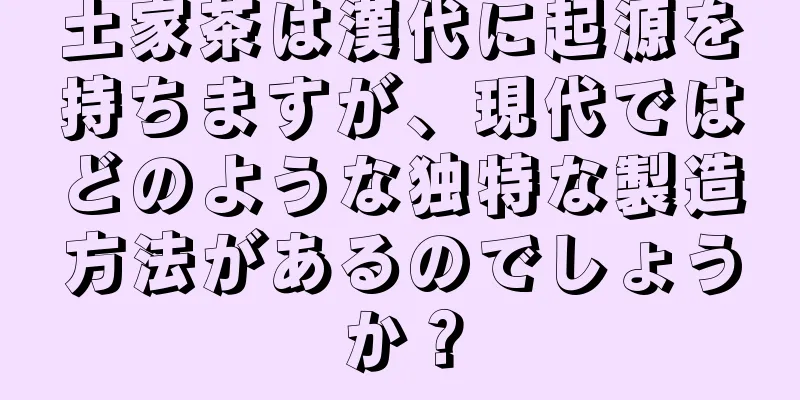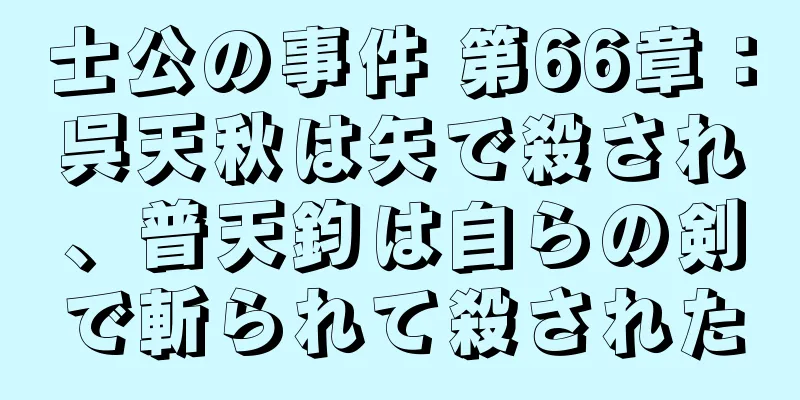諸葛亮が権力を握った後、蜀漢はなぜ再び東呉と同盟を結んだのでしょうか?
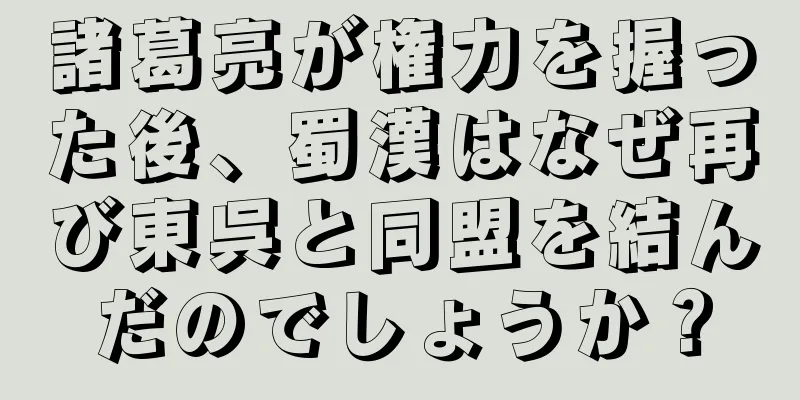
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、孫権がなぜ同盟を破棄し蜀漢に大きな損害を与えたのか、そしてなぜ諸葛亮が依然として孫権との同盟を結びたかったのかについて詳しく紹介します。それでは見てみましょう! 劉備と孫権は互いに愛し合いながら憎み合うライバル同士だったが、二人は力を合わせて赤壁の戦いに勝利し、荊州を分割した。しかし、すぐに彼らは互いに敵対し、戦い始めました。孫権は荊州を攻撃し、関羽を捕らえて殺した。その後、夷陵の戦いで劉備率いる蜀軍は東呉に敗れ、ほぼ壊滅した。両者の憎しみはそれほど深かったのに、諸葛亮が権力を握った後、なぜ再び蘇州と同盟を結んだのでしょうか。 1. 魏に抵抗するために両者が同盟を結ぶことが唯一の正しい戦略的選択である。 赤壁の戦いは三国志の基礎を築きました。この戦いの後、曹操は防御に転じ、孫権と劉備は攻撃に転じました。長い闘争の末、荊州は三つの勢力に分割された。曹操は荊州の北部を占領し、襄樊と合肥の2つの主要拠点を利用して劉備と孫権の攻撃を防御した。 孫権は南軍を劉備に貸与し、軍勢を集中させて淮南で攻勢を開始し、北の徐州へ進軍しようとした。劉備は南君を手に入れた後、益州に目を向けた。彼は劉璋の要請を利用し、軍を率いて四川に侵入し、益州を占領する作戦を開始した。長い戦いの末、劉備は成都を占領し、益州に支配権を確立し、安定した基盤を獲得した。 その後、劉備の勢力拡大に脅威を感じた孫権は、劉備に荊州の返還を要求し始めた。その後数年間、孫権は湘江の戦い、荊州の戦いを相次いで起こし、最終的に荊州を奪還して比較的安定した基盤を確立した。その後の夷陵の戦いでは、東呉は劉備の軍を破り、自国の領土の安全を守った。 この闘争の期間を経て、3つの勢力はそれぞれ成長と衰退を経験しましたが、一つの基本的な状況は変わっていません。つまり、曹魏の国力は蜀漢や東呉をはるかに上回っていたのです。当時、中国北部の大部分は曹魏の支配下にあり、これらの地域は経済発展が進んだ地域でもありました。 当時、蜀漢と東呉は広大な地域を占めていたものの、そのほとんどは未開発の荒野で、人口もまばらでした。人的資源も物的資源も曹魏に匹敵するものではない。国力の大きな差により、双方の軍事力も大きく異なります。東呉が長江を障壁とし、蜀漢が山を支えとしていたからこそ、曹魏は彼らを滅ぼすことができなかったのだ。 このような状況下では、弱い蜀漢と東呉にとって唯一の正しい戦略的選択は、団結して曹魏と戦うことだった。事実は、赤壁の戦い以来、孫家と劉家が共に戦い、常に戦場で主導権を握ってきたことを証明しています。曹操は優れた能力を持っていたが、長い戦線の中で一つのことに集中できず、何度も敗北し、常に消極的な防御姿勢をとっていた。 しかし、荊州の戦いの後、孫劉同盟が崩壊したため、曹魏はすぐに戦略的な主導権を握りました。劉備の軍は攻撃することができず、東呉は曹魏に服従するしかなかった。歴史の事実は、蜀漢と東呉にとって唯一の戦略的な道は、二つの弱い国が協力して一つの強い国と戦うことであることを証明しています。 2. 夷陵の戦いの後、孫家と劉家は新たな同盟の基礎を築いた。 赤壁の戦いの前に、劉備と孫権は曹操と戦うために同盟を結成しました。これは当時の状況によるもので、双方とも生き残るために対策を講じる必要がありました。この後、劉備と孫権は共に戦い、それぞれ大きな発展を遂げました。しかし、双方の力が増すにつれて、両者の間の矛盾はますます深刻になっていった。 これは主に両者間の戦略的対立によって引き起こされた。劉備と諸葛亮の「隆中議」における戦略目標は、第一段階として荊と宜を征服し、最終段階として軍を二手に分け北進することであった。これらの戦略目標を達成するために、劉備の一団は荊州を制圧しなければなりません。そのため、劉備は揚子江以南の荊州四郡を占領した後、孫権から南軍を借り受けた。 孫権の戦略目標は、揚子江全体を支配し、皇帝としての地位を確立し、北から世界のために戦うことだった。この戦略目標を達成するためには、長江上流に位置する荊州を支配することが重要です。劉備の力が弱く、脅威を与えなかったときは、孫権は劉備の荊州占領を容認していた。しかし、劉備が益州を占領した後、孫権の考えは変わった。 劉備が荊州と益州の二国を制圧した後、彼の勢力は大幅に増強され、孫権は脅威を感じた。彼は自身の戦略的安全のために荊州を奪還することを決意した。関羽の傲慢さも相まって、孫権はついに荊州を奪還し、関羽を捕らえて殺害し、長江全土を支配するという戦略目標を達成するために荊州の戦いを開始した。もちろん、これは劉備の復讐にもつながりました。 夷陵の戦いの後、劉備の蜀軍はほぼ壊滅した。その後、東呉は曹丕に反旗を翻し、互いに攻撃し合った。当時、東武は長江と三峡という自然の防壁を防衛手段としており、安定した安全な拠点を築いていた。蜀漢は弱体化し、東呉に対する報復攻撃を仕掛けることができなかった。しかし、東呉は曹魏と蜀漢と同時に敵対するなど、戦略的状況は非常に不利であった。これは東呉の能力を超えていたので、この窮地から脱出するためには、東呉と蜀漢が再び同盟を結ぶことが共通の必要でした。 3. 魏に対抗するために両者が同盟を結ぶことは諸葛亮の一貫した戦略政策であった。 劉備も死ぬ前にこれを見た。そこで、蜀漢の将来のために、劉備は自ら蜀と呉の国境にある白堤城に駐屯した。孫権はこれを知り、劉備が両側から攻撃してくるのではないかと恐れて恐怖した。そこで孫権は劉備に和平を求めるために人を派遣した。劉備は孫権の要請を受け入れ、報告のために使者を蘇州に派遣した。劉備の死の前の最後の努力は、諸葛亮が東呉と再び同盟を結ぶための基盤を築いた。 劉備は死ぬと、蜀漢の国を諸葛亮に託した。諸葛亮は権力を掌握した後、自らが定めた指針に従って統治を始めました。外交においては、東呉との再同盟を主な目標とした。東呉と連合して曹魏と戦うことが諸葛亮の一貫した戦略方針だったからです。 『龍中の策』では、諸葛亮は劉備に東呉を援軍として、曹操を主敵として使うよう提案した。これは実際には曹操と戦うために劉備と東呉が結んだ同盟でした。長阪坡の戦いで敗北した後、諸葛亮は自ら進んで蘇州に行き、孫権と連絡を取って曹操と共闘することを提案した。諸葛亮の仲介により、孫権と劉備は同盟を組み、赤壁の戦いに勝利した。 以後、諸葛亮は孫劉同盟の方針を堅持して曹操と戦った。諸葛亮が荊州に滞在していた期間中、劉備一派と東呉は常に良好な同盟関係を維持していた。このような好条件のもと、双方の勢力は急速に発展し、北方の曹操の勢力を制圧した。 孫劉同盟の崩壊後も、諸葛亮は東呉との戦いを続けることに反対した。夷陵の戦いの前に、諸葛亮は劉備の呉攻撃の決定を支持しなかった。諸葛亮の曖昧な態度はすでに反対を表明している。さらに、諸葛亮と親交の深かった黄権、趙雲、秦密らは、劉備に呉を攻撃しないよう公然と進言し、諸葛亮の姿勢を表明した。 そのため、劉備の死後、諸葛亮は東呉との再同盟を模索し始めた。同じ頃、蜀と呉の同盟を緊急に必要としていた孫権は、諸葛亮と意気投合した。こうして、諸葛亮の努力により、蜀と呉の同盟はすぐに再建された。この同盟は非常に安定しており、蜀漢の滅亡まで続いた。 結論: 蜀漢と東呉がともに弱く、曹魏が唯一の強国であったとき、双方にとって唯一の正しい戦略的選択は、蜀漢と東呉が同盟を組んで曹魏と戦うことだった。劉備一派の勢力が強まるにつれ、孫権は恐怖を覚えるようになった。孫権は自らの戦略的安全のために荊州の戦いを開始し、長江全域を支配し安定した基盤を確立するのに有利な状況を作り出した。 夷陵の戦いの後、蜀漢は戦力に大きな打撃を受け、東呉を攻撃する能力を失った。東呉は蜀漢と曹魏の両方と同時に敵となるというジレンマにも直面した。蜀漢政権を継承した諸葛亮は、常に東呉と同盟を組んで曹操と戦うという戦略方針を採用した。諸葛亮と孫権はあらゆる要因の影響を受けて意気投合し、再び同盟を結び、曹魏に共同で抵抗するという正しい道を再び歩み始めた。 |
<<: 諸葛亮が籐甲軍を滅ぼした後、なぜ自分のために再編成しなかったのでしょうか?
>>: 孫策は「小覇王」として知られていましたが、なぜ3人の正体不明の人物の手によって殺されたのでしょうか?
推薦する
『新世界物語集』第 38 話「美徳の章」はどのような物語を語っていますか?
周知のように、『新世界物語』は魏晋時代の逸話小説の集大成です。では、『新世界物語・徳』第38篇はどん...
『紅楼夢』でなぜ丹春と趙叔母の関係は悪かったのでしょうか?
丹春は曹雪芹の『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人です。以下の興味深い歴史編集者が詳しい記事の...
『紅楼夢』で賈正はなぜ妻の王傅仁に不満を抱いているのか?
なぜ賈正は妻の王福仁に不満を抱いているのでしょうか?賈正が妻の王夫人に不満を抱いているのは、実は理解...
宋代の文人蘇軾の『水歌・明月はいつ現れるか』鑑賞
蘇軾の『水の旋律・明月はいつ現れるか』について、次の『興味歴史』編集者が関連内容を詳しく紹介します。...
仏教で言われている八つの邪教徒の区分とは何ですか?
仏教でよく言われる八部天龍は、「八部龍神」や「八部天」とも呼ばれ、仏教の守護神8柱のことであり、その...
堯、舜、禹の時代の継承制度はどのようなものだったのでしょうか? 「退位制度」もその一つです!
今日は、おもしろ歴史編集長が堯・舜・禹時代の継承制度についてお伝えします。皆さんのお役に立てれば幸い...
詩や随筆の名句鑑賞:『別れの詩五篇』第4節、最も有名な詩句はどれでしょうか?
海を見たら、他の水はすべて水たまりにしか見えず、武山を見たら、他の山はすべて水たまりにしか見えず唐代...
ピラミッドの未解決の謎。ピラミッドの未解決の謎を解明?
ピラミッドの未解決の謎:神秘的で魅力的な首都エジプトには、海と同じくらい広大な砂漠があります。4 つ...
『紅楼夢』で、薛宝才と夏金貴はなぜ賈宝玉にふさわしくないのでしょうか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
秦克清の葬儀はどれほど盛大だったのでしょうか?このような盛大な葬儀の真髄は何でしょうか?
みなさんこんにちは。Interesting Historyの編集者です。今日は秦克清の葬儀の話をした...
劉宗元の散文の特徴:「文学と道徳の統一」、「文明を使って教える」、「言葉は独創的でなければならない」
劉宗元の散文は韓愈の散文と並んで有名です。韓愈と劉宗元は、宋代の欧陽秀、蘇軾とともに「唐宋八大散文家...
「台州海陵県郡書記徐氏の墓誌」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
台州海陵県の郡書記長徐氏の墓碑銘王安石(宋代)その紳士の名前は平、雅号は炳志、姓は徐といった。私はか...
『済公全伝』第19章:秦宰相は夢の中で幽霊を見て、済公は夜に仏教を教えに来た
『済公全伝』は清代の学者郭暁廷が書いた神と悪魔についての長編小説である。主に済公僧侶が世界中を旅しな...
李承謙皇太子の人生が悲劇に終わった原因はいったい何だったのでしょうか?
唐王朝(618-907)は、隋王朝に続く中原の統一王朝であり、289年間続き、21人の皇帝がいました...
古代詩の鑑賞:詩集:黒い服:黒い服は似合うが、擦り切れたので着替えた
『詩経』は中国古代詩の始まりであり、最古の詩集である。西周初期から春秋中期(紀元前11世紀から6世紀...