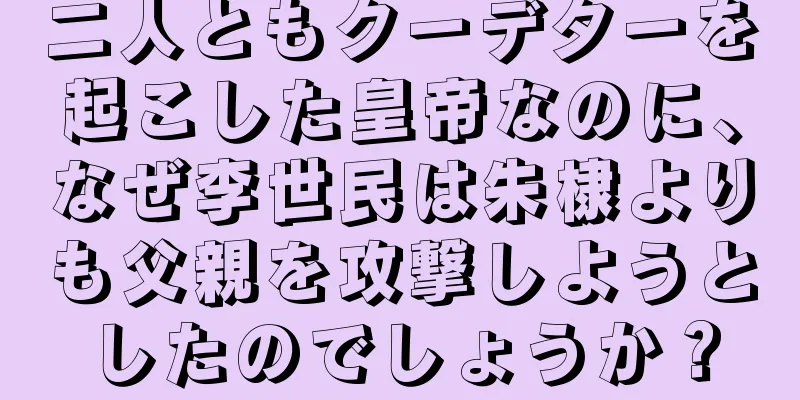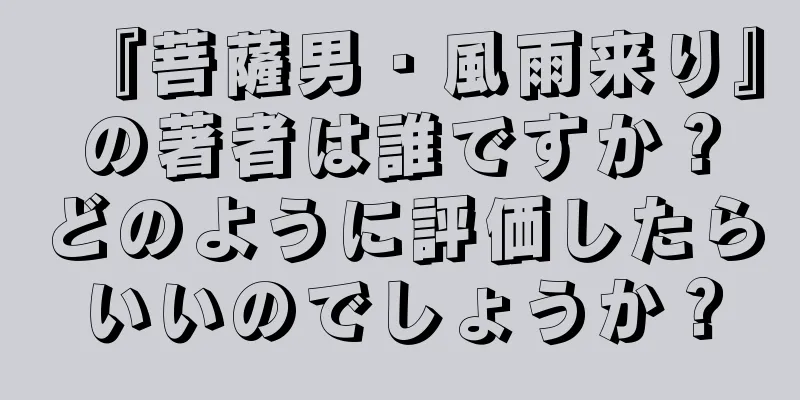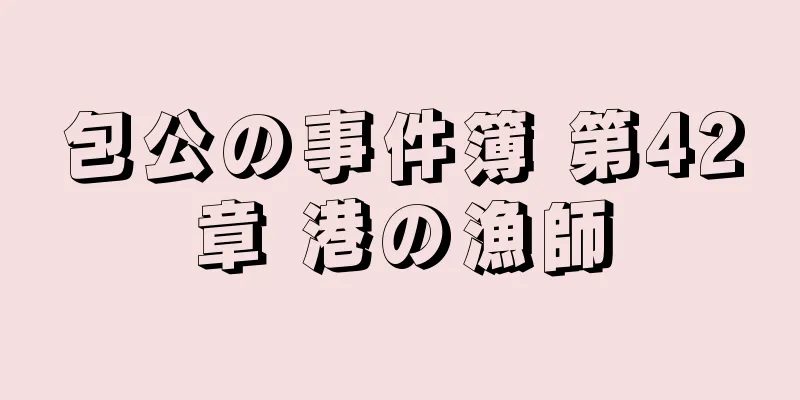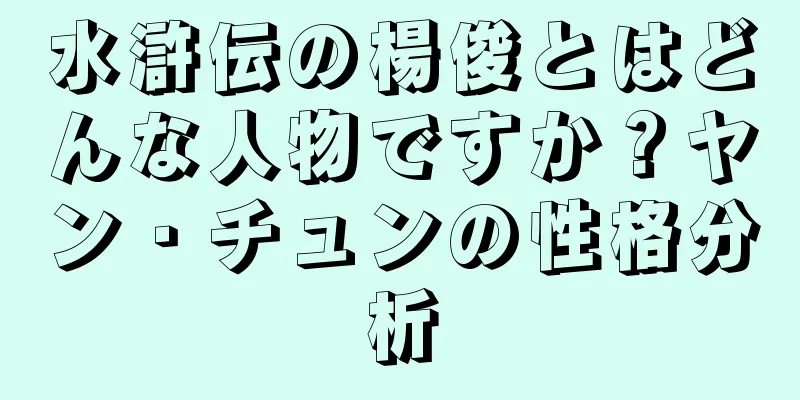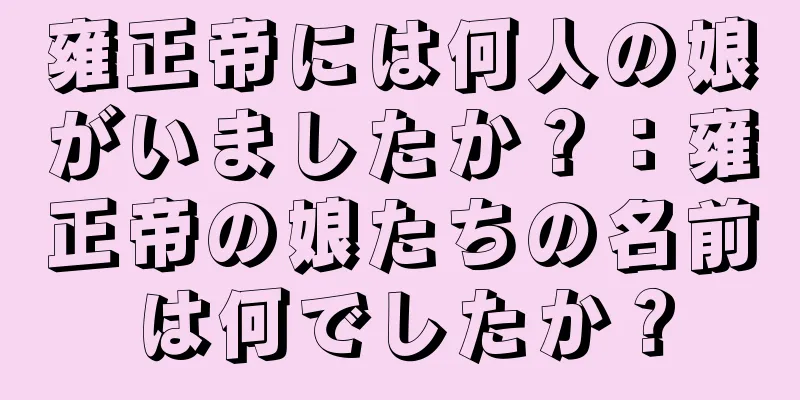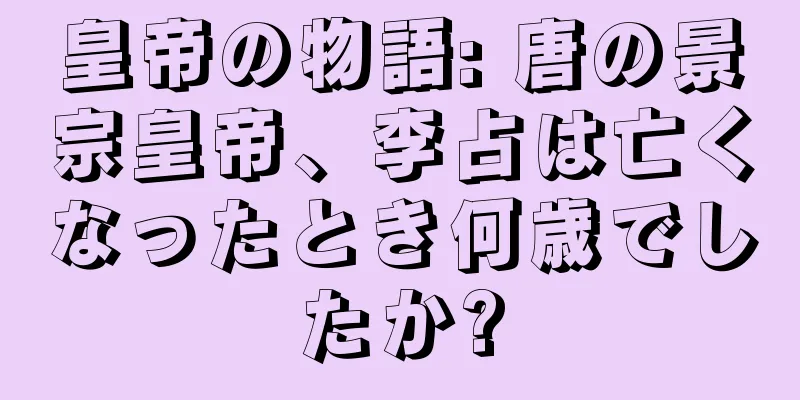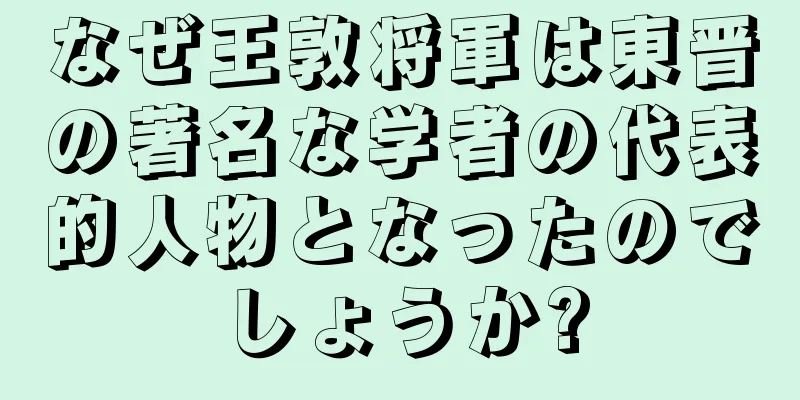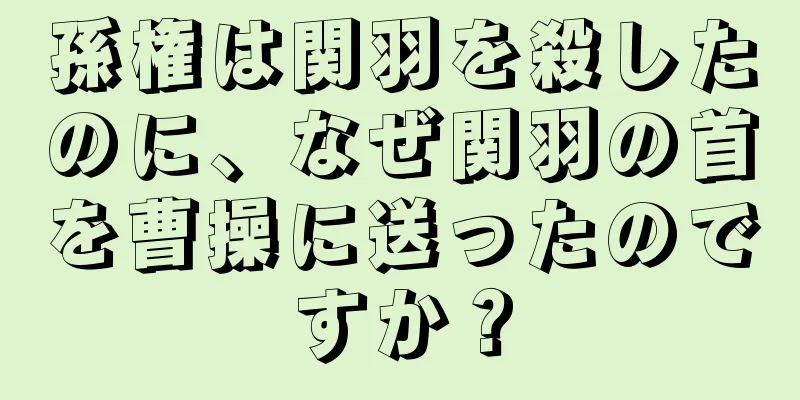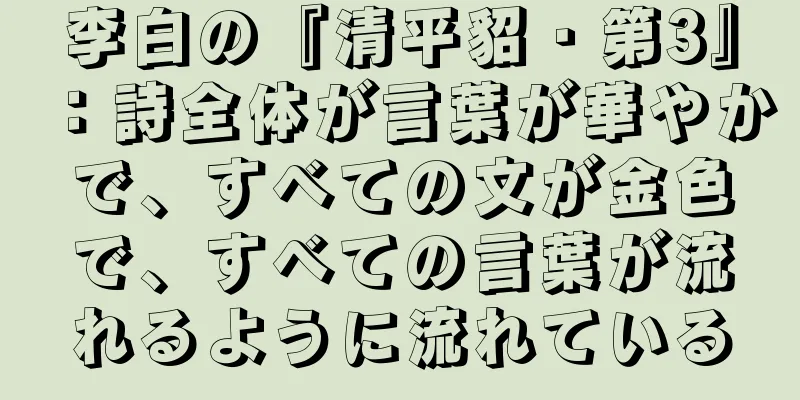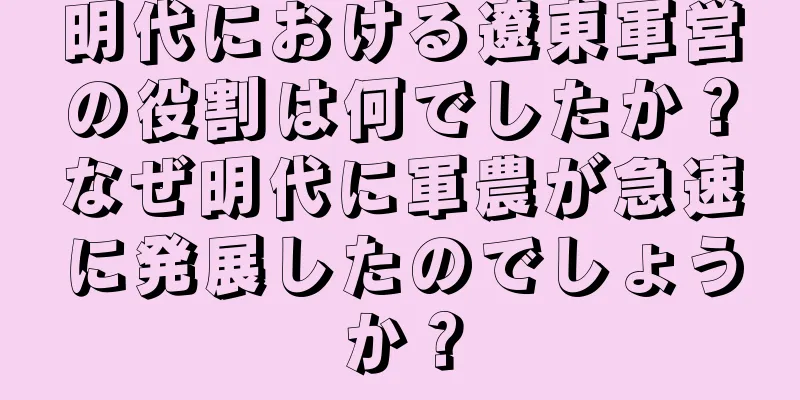司馬懿はなぜそんなに慎重だったのでしょうか?諸葛亮の軍事的才能を恐れたから
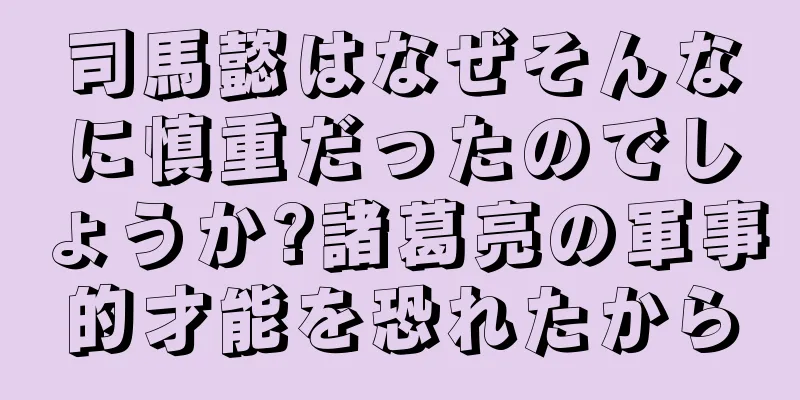
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、諸葛亮と司馬懿が慎重だった理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 三国時代には諸葛亮と司馬懿という完璧なライバルがいました。 『三国志演義』では、二人の知恵のぶつかり合いを強調するために、街亭の戦いから戦いが始まりました。もちろん、司馬懿は諸葛亮の前では常に不利な立場にあり、戦うたびにほぼ敗北していました。しかし、現実には諸葛亮と司馬懿の対立は第四次北伐から始まった。諸葛亮の最後の二度の北伐では、司馬懿は曹魏の支柱となり、諸葛亮の攻勢に抵抗した。結局、諸葛亮の野望は達成されず、彼は五丈原で軍の中で病死し、後悔した。しかし、諸葛亮と司馬懿にはいくつかの共通点があり、それも非常に興味深いものです。 1. 部下から尋問を受ける指揮官。 諸葛亮と司馬懿はともに文民の地位から昇進して指揮官となった。そのうちの一人は劉備に従い、宰相として軍事権を握り北伐を開始した。一人は曹操の部下であり、曹操、曹丕、曹叡の三代の君主の下で関龍軍の総司令官となった。その結果、部下から軍事力に疑問を持たれ、同様の光景を目にすることとなった。 諸葛亮に対して最も不満を抱いていたのは、最強の武将である魏延であった。魏延は劉備自ら漢中守護に任命されており、豊富な戦闘経験を持っています。彼は勇敢で戦闘に優れ、兵士の世話も上手で、諸葛亮の北伐に大きな貢献をした。しかし、諸葛亮は魏延の能力を十分に認めず、彼をその地位に留めた。 北伐の際、魏延は諸葛亮に何度も、自ら軍を率いて潼関を攻撃し占領したいと提案した。こうすれば、諸葛亮の主力軍が到着すれば、一気に潼関以西の地域は平定されることになる。しかし、諸葛亮は魏延の提案はあまりにも危険だと考え、採用しなかった。街亭の戦いでは、諸葛亮は皆の忠告を受け入れられず、魏延を街亭の守備に使わず、口は達者だが実力のない馬蘇を派遣した。これにより街亭の戦いで惨敗し、諸葛亮の第一次北伐も失敗に終わった。 そのため、魏延は諸葛亮に対して非常に不満を抱いていた。諸葛亮は魏延を非常に厚く扱い、魏延は諸葛亮の下で先鋒の将軍として仕えていたが、劉延と魏延が対立したとき、諸葛亮は魏延に味方し、劉延を罰した。しかし、魏延は常に自分が評価されていないと感じていました。彼は、主に諸葛亮があまりにも臆病で、リスクを冒すことを敢えてしなかったために、彼の才能が十分に生かされていなかったと信じていました。 司馬懿に対して最も不満を抱いていたのは、彼の配下の重要な将軍であり、曹魏の五大将軍の一人である張郃であった。張郃は曹魏の関龍軍の重要な将軍であった。曹操に従い、曹魏のさまざまな戦場で活躍した歴戦の武将。曹魏成立後は五大将軍の唯一の生き残りとしてますます重要な役割を果たすようになる。 諸葛亮が北伐を開始した後、張郃は関龍戦場に移動し、諸葛亮の強敵となった。街亭の戦いでは、極めて不利な状況下で数千里も駆けつけて救援し、馬蘇を破って隴溪を危機から救った。陳倉の戦いでは、彼は素早く援軍を率いて諸葛亮を撤退に追い込んだ。 しかし、張郃のような優れた将軍の目には、司馬懿も臆病な人物として映った。諸葛亮の第四次北伐の際、張郃と司馬懿の間では一連の衝突が起こった。彼は司馬懿の指揮を批判し、不満を表明した。彼は、司馬懿が常に諸葛亮に従い、諸葛亮が挑戦したときに戦うことを拒否したため、慎重すぎると考え、そうすれば軍の士気に影響を与えるだろうと考えました。 しかし、諸葛亮と同様に、司馬懿も部下の影響を受けず、独自のやり方を貫きました。このため、司馬懿の部下たちは、張郃が戦死した後も、司馬懿は臆病すぎると考え続けた。諸葛亮の絶え間ない挑発に直面した司馬懿は、戦争を起こして皇帝の意志を利用して部下たちの不穏を鎮圧することを要求する嘆願書を提出するために何千マイルも旅するしかなかった。諸葛亮が亡くなり軍が撤退すると、蜀軍の陽動攻撃に司馬懿は怯え、「死んだ諸葛が生きている鍾馗を怖がらせる」というジョークを残した。 諸葛亮と司馬懿の両者が部下から臆病者とみなされていたというのは興味深い偶然である。部下から嘲笑されるほど慎重なのは、優秀な指揮官に共通する特徴だというのは本当だろうか。しかし、諸葛亮や司馬懿の軍歴を見ると、彼らの慎重さは異なっていた。 2. 諸葛亮の慎重さは条件によって制限された。 諸葛亮は奇襲作戦をとらず、軍勢を分散させてさまざまな方向に攻撃したため、魏延からは臆病者とみなされた。しかし、諸葛亮が指揮した戦いを見ると、彼は軍隊を分割して戦うことを恐れていなかったことがわかります。諸葛亮は張飛と趙雲を率いて四川に入城すると、軍をいくつかのルートに分け、それぞれ内水、外水などから進軍し、成都で合流して劉備の益州攻略を支援した。 諸葛亮が南方を征服していたとき、敵を分断して包囲するために軍隊を3つのグループに分けました。敵は頑強に抵抗したが、諸葛亮の指揮の下、蜀軍は止められなかった。孟獲は7回捕らえられ、解放された後、誠実に降伏した。こうして諸葛亮は南中の反乱を鎮圧し、北伐の基盤を築いた。 しかし、北伐に関しては、諸葛亮は第一次北伐のときのみ、軍を分割する戦術を採用した。彼は趙雲と鄧芝に蜀軍を率いて蜀谷から出向させ、梅県を占領したいと言い張り、魏軍を混乱させるための囮軍とした。さらに、諸葛亮は常に蜀軍を集中させ、魏延の奇襲戦術はおろか、軍を分割する戦術も採用しなくなった。 これは諸葛亮がリスクを取ることを恐れていたからでしょうか?入川の戦いや南伐の戦いから、諸葛亮は状況が有利なときにはリスクを取ることをいとわなかったことがわかります。四川に入る戦いの際、諸葛亮は張飛と趙雲という将軍を指揮下に置き、彼らに戦わせ、少しの挫折も許容した。南征の際、武器、装備、組織が自分より劣る敵に直面した彼は、あえて部隊を分割し、一緒に敵を攻撃した。 しかし、北伐の際、諸葛亮は突然リスクを取ることを恐れるようになったのでしょうか? 理由は実は非常に単純で、彼にはリスクを取るための資金が本当になかったからです。諸葛亮が蜀漢の軍事力を掌握した当時、蜀漢は荊州の戦いと夷陵の戦いで連続して敗北を喫していた。一連の悲惨な敗北の後、蜀漢の軍事力は壊滅的な打撃を受けた。 劉備、関羽、張飛など多くの名将が失われ、また曹魏に対する北伐の主力二軍もすべて失われた。諸葛亮は成都に大規模な駐屯地を設置し、軍隊を再編成し訓練するしかなかった。諸葛亮の懸命な努力のおかげで、蜀漢はついに10万人の軍隊を取り戻した。蜀漢は小さくて弱かったため、蜀漢が滅亡するまで蜀軍の強さは増加しませんでした。 これにより、諸葛亮は危険を冒すことが不可能になった。しかし、漢王朝を支えるという理想を実現するために、諸葛亮は曹魏に対して北伐を発動し、最大の冒険に出た。蜀漢と曹魏の間には秦嶺山脈という自然の障壁がある。この自然の障壁はかつて曹操を怖がらせた。漢中を失った後、曹操は「解谷道は500マイルの長さの石の洞窟だ」と嘆いた。曹魏が蜀漢を容易に攻撃しようとしなかったのは、まさにこの理由による。しかし、諸葛亮は5回連続で北伐を行なったが、そのたびに秦嶺山脈の障壁を乗り越えなければならなかった。 これにより、諸葛亮の軍事作戦は変動の多いものとなった。彼は敵地の奥深くまで進まなければならなかっただけでなく、自らの兵站補給の困難も解決しなければならなかった。対応が間違っていたら蜀軍は壊滅的な被害を受けるかもしれない。蜀漢に残された唯一の主力は諸葛亮率いる蜀軍であった。この蜀軍が失われれば、蜀漢は壊滅的な打撃を受けるであろう。このような状況下では、諸葛亮は戦場の指揮において簡単に危険を冒すことをせず、何事にも慎重に慎重に行動せざるを得なかった。 3. 司馬懿の警戒心は諸葛亮の軍事力に対する恐怖から生じたものであった。 同様に、司馬懿の冒険的な行動は彼の性質にそぐわなかった。司馬懿の軍歴を見ると、彼の大胆かつ冒険的な行動が分かります。彼は孟達の反乱を鎮圧する際に、断固たる行動を取った。司馬懿は皇帝に許可を求めることもなく、昼夜を問わず部下を率いて上庸の城に向かった。司馬懿はその後、城を四方から包囲し、昼夜を問わず攻撃するという戦術を採用した。上庸を占領し、孟達を殺すのに、わずか十数日しかかからなかった。 司馬懿の予想外の攻撃は孟達の希望的観測を打ち砕いた。孟達は当初、司馬懿が皇帝に指示を仰ぎ、段階的に商勇を攻撃し、孟達に準備の時間を与えられると考えていた。しかし、司馬懿は軍事戦略家のタブーを無視して危険な攻撃戦術を採用し、一挙に上庸を征服した。 司馬懿は遼東を攻撃した際にも、比較的危険な戦術を採用した。敵がすぐ近くにあり、都市が強固で食料も豊富であったにもかかわらず、彼は敵の目の前で陣を張った。彼はその地域の自然条件の悪さを無視し、数ヶ月にわたって公孫淵と戦い、ついに遼東を平定した。司馬懿のこれらの軍事行動から、司馬懿はあえてリスクを負う将軍であったことがわかります。しかし、司馬懿は諸葛亮の北伐を阻止する作戦において非常に慎重だったため、部下から嘲笑された。これは主に以下の理由により発生します。 まず、司馬懿と諸葛亮が対峙したとき、彼は負けるわけにはいかない男だった。これは彼が若い頃に曹操に見出され、曹丕に司馬懿に注意するよう遺言を残したためである。これは、諸葛亮の第四次北伐まで司馬懿が真の軍事力を持っていなかったことを意味している。これは曹叡の信頼と曹真が重病だったからこそ可能となり、司馬懿にその機会を与えたのである。 曹叡が曹真に代わって司馬懿を任命したちょうどその時、ある人が曹叡に、司馬懿に関龍軍団を率いさせたくないと忠告した。司馬懿がこの機会をどれほど大切にしていたかは想像に難くない。そのため、失敗によって軍事力や将来の出世の機会を失わないように、あらゆることに注意を払った。 第二に、司馬懿は諸葛亮の軍事的才能を非常に恐れていたため、予期せぬ挫折を恐れて、簡単に危険を冒すことを敢えてしなかった。司馬懿が関龍軍を率いたころには、諸葛亮の軍事指揮能力は三度にわたる北伐を経て成熟しており、戦闘組織も完璧であった。さらに、諸葛亮の訓練により、蜀軍は八卦陣の戦術を習得し、戦場で無敵の力を発揮できるようになりました。蜀軍の戦闘力はこの時頂点に達したと言える。 諸葛亮の第四次北伐の際、司馬懿と諸葛亮は長い間交渉し、双方は互いのやり方を理解し、その後の戦闘計画を立てた。この戦役で、司馬懿は呂城の戦いと木門道の戦いで連続して敗北し、蜀軍の戦闘力と諸葛亮の軍事的才能を深く理解した。彼は戦場で諸葛亮を倒すことはできないと考え、戦わずに陣地を守り、地の利を生かして膠着状態を長引かせ、蜀軍を弱らせて諸葛亮に軍を撤退させようとする戦術を採用した。 すると、司馬懿の部下たちが司馬懿を嘲笑する場面がありました。しかし、双方の警戒心の裏には、強い殺意が隠されていた。それはまるで、敵に致命的な打撃を与えるために互いの弱点を待ち構えている、比類のない二人の剣士のようです。結局、どちらの側も敵に抜け穴を残さず、諸葛亮は健康上の理由により五丈原で病死した。戦争後、司馬懿は蜀軍の陣地を視察し、諸葛亮を天下の天才と讃え、心からの尊敬の念を表した。 結論: 諸葛亮も司馬懿も、慎重すぎるとして部下から嘲笑された。しかし、彼らが用心深かったのは諸葛亮の北伐の時だけで、他の戦場では、彼らはまだ危険を冒すことを敢えてした。これは、彼らの用心深さが彼らの性質によるものではなく、外的要因によって引き起こされていることを示しています。 諸葛亮が北伐の際に慎重だったのは、彼が統率する軍事力が弱すぎて、簡単に危険を冒すことができなかったからである。客観的な観点から見れば、彼の北方探検は冒険的な行動だった。そのため、諸葛亮は蜀漢の生死にかかわる軍隊を失わないように、軍事作戦には細心の注意を払った。 司馬懿は苦労して獲得した軍事力を維持し、将来の出世に備えたいと考えていた。諸葛亮と戦った後、戦場で勝つことは難しく、失敗する可能性があることがわかりました。そこで彼は安全な方法を取り、自分の立場を守りながら諸葛亮と対峙し、諸葛亮を降伏させました。これは実は司馬懿が諸葛亮の軍事的才能を恐れていたことを示しています。司馬懿が慎重にならざるを得なかったのは諸葛亮の軍事的圧力によるものでした。 |
<<: 関羽の傲慢さは傲慢ではありませんでした。彼の目には、どの軍将が尊敬されていたのでしょうか?
>>: 劉表が劉備に荊州を譲るよう提案したとき、劉備はなぜ拒否したのですか?
推薦する
白居易の古詩「江楼を振り返って月中に帰依」の本来の意味を鑑賞
古代詩:「河楼から振り返り、月中に避難する」時代: 唐代著者: 白居易目には雲と水が満ち、明るい月の...
「リトルファイブヒーローズ」第123章:若い英雄は、泥棒同盟に対する黒狐の陰謀を盗み聞きする
『五人の勇士』は、古典小説『三人の勇士と五人の勇士』の続編の一つです。正式名称は『忠勇五人の勇士の物...
『紅楼夢』の最後で袁春が死刑判決を受けたのは、賈一家に関与したためですか?
元春は『紅楼夢』の登場人物で、金陵十二美女の一人であり、賈家の四人の娘の第一人者です。興味深い歴史の...
唐代の詩人賈道の「夕山里を過ぎる」の原文、翻訳、注釈、題名の説明
賈島の『夕暮れの山村を通り過ぎる』に興味がある読者は、Interesting History の編集...
清朝の皇帝と皇后の一覧 清朝には何人の皇帝と皇后がいましたか?
清朝の皇帝と皇后の一覧 - 清朝の十二皇帝と二十八皇后の一覧清朝は我が国の長い封建社会の最後のページ...
呉菊の「柳はカラスを隠す」:この詩は平易な言葉と誠実な気持ちで書かれている
呉儒(1189年頃生きた)は南宋時代の書家。号は聚福、号は雲和。汴景(現在の河南省開封市)の出身。 ...
張郃と徐晃の戦闘記録から判断すると、張遼と徐晃は趙雲を倒せるでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
諸葛亮が曹操に降伏しなかったとしても、曹操は諸葛亮を引き離すことができなかったと言われるのはなぜですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』で、王希峰が賈邸で泣いた2つの場面は何ですか?
今日、「おもしろ歴史」編集者は、鳳潔が泣いた2つの場面をお伝えします。賈おばあさんの態度はなぜこんな...
『紅楼夢』の嘉慧とは誰ですか?彼女は結局どこへ行ったのでしょうか?
『紅楼夢』では、賈宝玉の易宏院には彼に仕える侍女が最も多く、それぞれに名前と物語がある。次回は、In...
周史第五巻原文の鑑賞
武帝(第1部)高祖武帝の本名は雍、字は尼洛傳。太祖の四番目の息子。彼の母親はチ・ヌ王母であった。彼は...
張慧燕の「つがいのツバメ、都会の雨」は、ツバメに関する古代の詩の文化遺産を描いている。
張慧延(1761-1802)は清代の詩人、随筆家であった。彼の本名は怡明、雅号は高文、別名高文、明科...
秘密を明かす:商鞅の改革がなぜこれほどの成果を上げたのか?
商鞅の改革は、法的責任の追及に関する彼の考えを実行するために確かに厳しい刑罰を規定しましたが、実際に...
賈芬の晩年の生活はどのようなものだったのでしょうか?有名な東漢の将軍、賈芬はどのようにして亡くなったのでしょうか?
賈芬(9-55)、号は君文、南陽の関邑(現在の河南省鄧県の北西)出身の漢人。東漢の有名な将軍で、雲台...
『紅楼夢』の側室である趙叔母に対する王夫人の態度はどのようなものですか?
夫人は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公の一人です。Interesting History の編集者が...