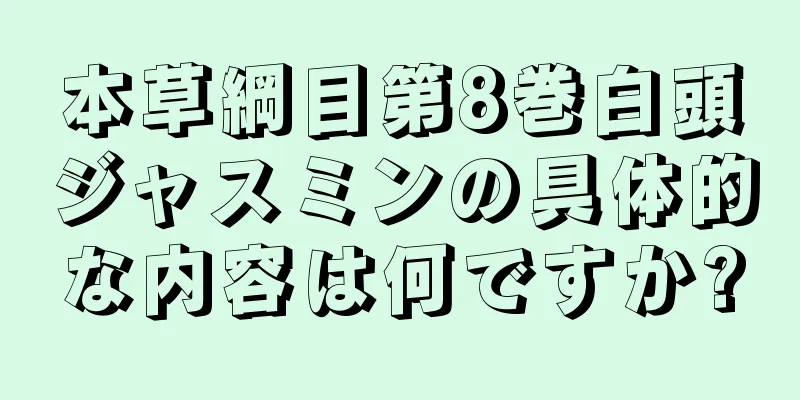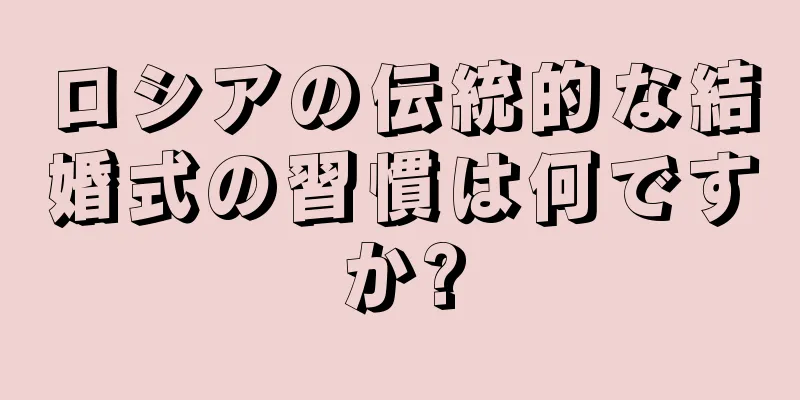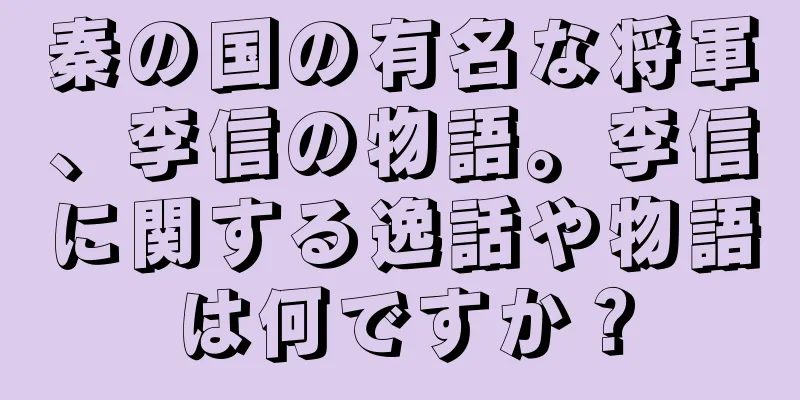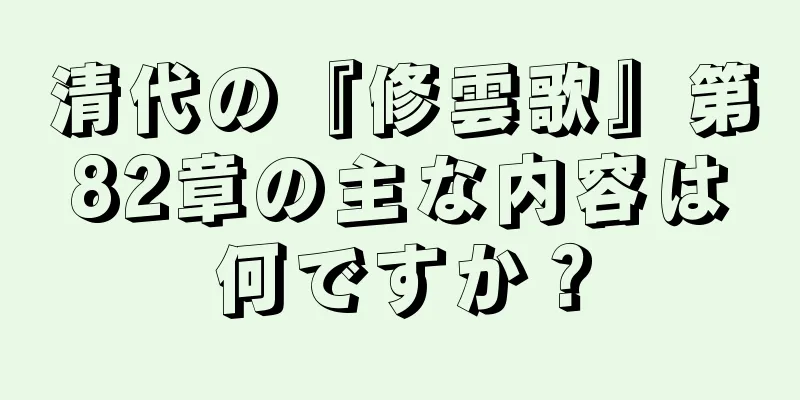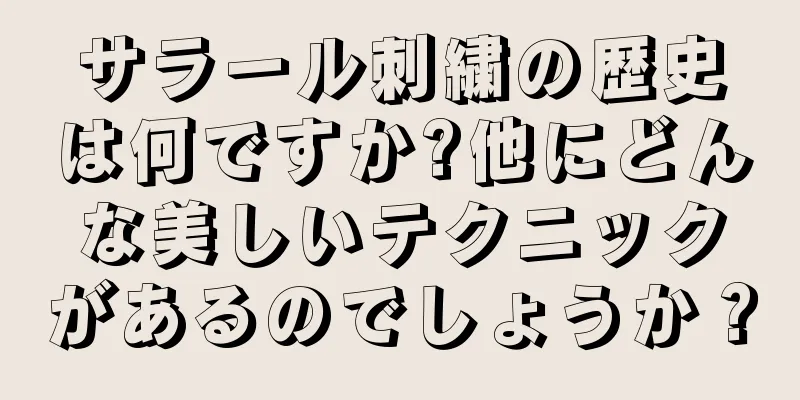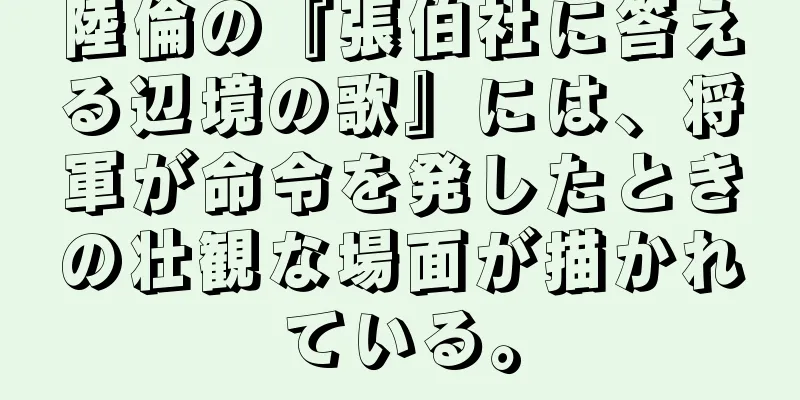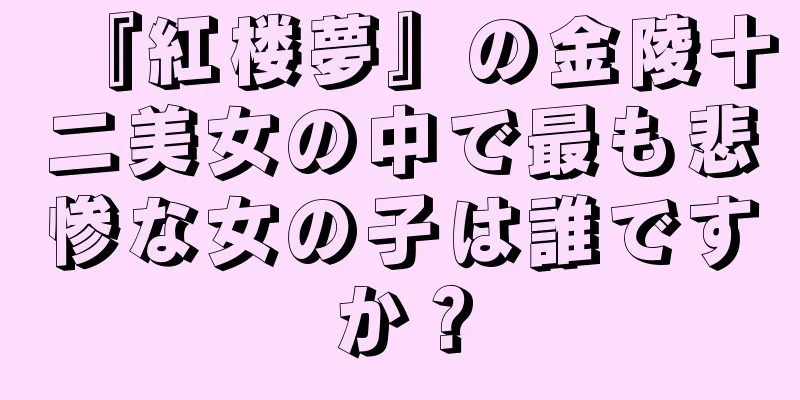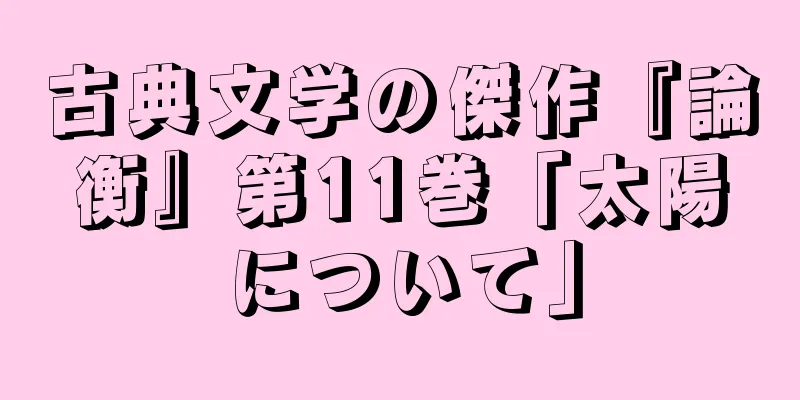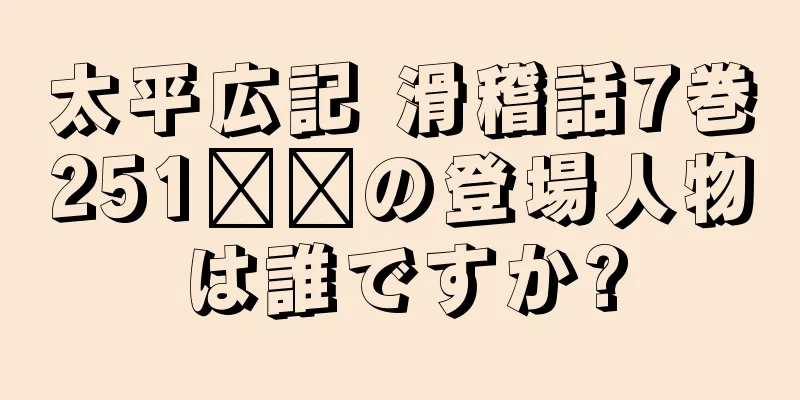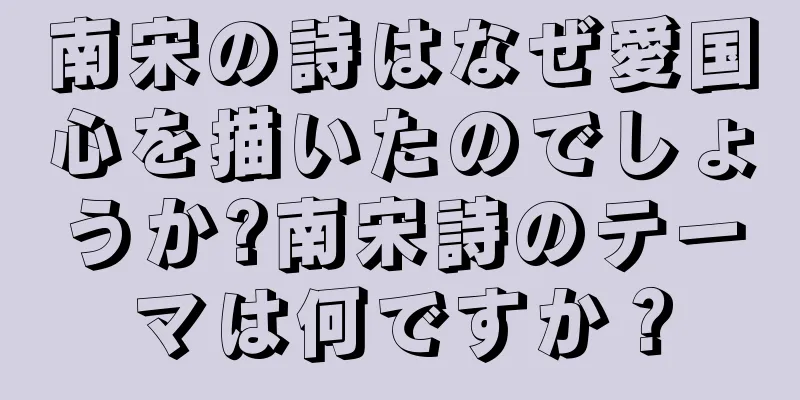張郃は諸葛亮が非常に恐れていた人物なのに、なぜ矢雨に打たれて死んだのでしょうか?

|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、張郃がなぜ死んだのかについて詳しく紹介します。司馬懿がナイフを借りて人を殺すためだったのか、それとも一石二鳥の計画だったのか?見てみましょう! 張郃は曹操軍の五人の将軍の中で最も長生きしたが、戦闘で亡くなった唯一の将軍であった。彼は北伐の際の諸葛亮の主な敵の一人であり、何度も諸葛亮の攻勢を阻止した。しかし、諸葛亮が非常に恐れていたこの人物は、諸葛亮の矢に当たって死んでしまいました。途中でどんな話があったんですか? 1. 諸葛亮に恐れられた張郃。 諸葛亮の時代、張郃は曹操軍の五人の最高の将軍のうち唯一生き残った人物であった。彼には諸葛亮に抵抗する任務を引き受けるしか選択肢がなかった。諸葛亮の第一次北伐以来、張郃と諸葛亮の間には切っても切れない絆があった。張郃は戦場で亡くなるまで、諸葛亮率いる蜀軍と戦い、関龍戦場で活躍した。 諸葛亮の第一次北伐の際、曹魏は諸葛亮に対して全く備えがなかったため、彼の攻撃は奇襲のような効果をもたらした。曹魏の天水・安定・南竿の三県はいずれも諸葛亮に降伏し、曹魏の関中の支配地域は大きく動揺した。当時、曹魏の役人たちは皆、このことを話し、どうしたらよいか困惑していました。 曹叡は状況を総合的に考慮した後、すぐに援軍を派遣して龍尚を救出することに決めた。彼が派遣した援軍は張郃率いる中央機動軍で、騎兵と歩兵5万人以上で構成されていた。張郃はこの軍を率いて長く困難な旅をし、危険な関龍路を抜け、ついに街亭の諸葛亮の防衛陣地に到着した。 当時、張郃の状況は非常に危険でした。前方に諸葛亮の軍勢、後方に関龍路が立ちはだかっていたためである。彼の軍隊は長い旅の後で疲れ果てていた。兵站補給も非常に困難で、蜀軍との長期戦になれば補給難で必ず敗れるだろう。 張郃に残された唯一の方法は、街亭の蜀軍を完全に打ち破り、できるだけ短時間で彼らを倒すことだった。この作業の難しさは極めて大きいです。しかし、張郃は南山に駐屯していた馬謖の蜀軍の弱点を突き止め、一挙に蜀軍を破った。歴史の記録によれば、蜀軍は「兵士たちは散り散りになり」、「群衆は星のように散り散りになった」という悲惨な敗北を喫した。 この戦いで惨敗したため、諸葛亮は前進する拠点を失い、漢中へ撤退せざるを得なくなり、第一次北伐は失敗に終わった。この失敗の後、諸葛亮は張郃の軍事的才能に深く感銘を受けた。その後、諸葛亮の第二次北伐の際、張郃は陳倉を援軍し、諸葛亮を撤退させた。曹魏の名将である曹真のもと、関龍軍の総大将である張郃が諸葛亮の最大の敵となった。 2. 張郃の死。 張郃は諸葛亮の第四次北伐の戦場で亡くなった。この北伐では、すでに八卦陣の訓練に成功していた蜀軍を率いて諸葛亮が新たな戦術の実験を始めました。この時、曹真は病気のため軍事力を放棄し、司馬懿が関龍軍団の新世代指揮官となり歴史の舞台に立った。 しかし、この戦役中、司馬懿は諸葛亮の北伐に抵抗する目的で張郃と対立していた。論理的に言えば、張郃は関龍軍の総大将として諸葛亮との戦いにおいて豊富な経験を持っていた。司馬懿はちょうど到着したばかりであり、張郃の意見を尊重すべきだった。司馬懿が関龍軍の新しい司令官であったため、張郃も彼に仕えるはずであった。しかし、この二人の対立は戦闘中ずっと続いた。 今度は諸葛亮が軍を率いて北へ向かい、やはり岐山から出撃し、魏軍が保持する岐山砦を包囲した。戦いが始まったとき、曹真は諸葛亮に別の計画があるのではないかと恐れ、各地に持ちこたえて戦わないように命じた。司馬懿が到着すると、曹真は戦略を変えて旗山に軍隊を派遣した。このとき、張郃と司馬懿の間に初めての衝突が起こった。 張郃は、諸葛亮がまだ漢中に軍を残していると信じており、諸葛亮が他のルートから攻撃し、背後を襲撃するのではないかと恐れていた。そのため、司馬懿は部隊の一部を後方防衛の準備に割り当てるよう提案された。司馬懿は、諸葛亮に次々と打ち負かされるのを防ぐために軍隊を分散させるべきではないという理由で張郃の提案を拒否した。 岐山を救出する際、諸葛亮は強者を避け弱者を攻撃する戦略を採用し、軍を分けて上桂を攻撃し、郭淮と費瑶を破った。司馬懿は知らせを聞いて救出に急いだが、諸葛亮と会ってからは立ち去ることを拒否した。諸葛亮は司馬懿への挑戦に失敗した後、上桂で小麦を収穫し、軍を南に導いた。この時、司馬懿は魏軍を率いて諸葛亮を追撃した。 この時、張郃は再び司馬懿に、主力部隊は諸葛亮の追撃をやめてここに留まり、奇襲部隊を派遣して諸葛亮の背後を攻撃するよう進言した。諸葛亮を追って進軍せず、民を失望させるべきではなかった。現在、諸葛亮の軍隊は食糧が不足しており、すぐに撤退するでしょう。しかし、司馬懿は張郃の忠告を受け入れず、依然として軍を率いて諸葛亮を追跡した。 彼らが鹿城に到着すると、そこは張郃が予想した通りだった。諸葛亮は司馬懿と戦うために引き返したが、司馬懿は軍を率いて山に登り、防御のために陣地を掘った。この時点で、魏軍の将軍たちは皆そうすることを望んでいませんでした。彼らは司馬懿が諸葛亮を虎のように恐れていると非難し、世界中から嘲笑を浴びた。絶望した司馬懿は諸葛亮を攻撃し、大敗を喫した。これは歴史上、呂城の戦いとして知られている。 この悲惨な敗北の後、司馬懿は二度と戦うことはなかった。諸葛亮は兵站支援の不足により軍隊を撤退させなければならなかった。このとき、司馬懿は張郃と最後の戦いを繰り広げた。つまり、司馬懿は張郃に軍を率いて諸葛亮の軍を追撃するよう命じたが、張郃は異議を唱えた。張郃は言った。「軍法では城を包囲する際には必ず脱出口を見つけ、退却する軍を追撃してはならないと定められている。ではなぜ今、諸葛亮を追撃しているのだ?」 司馬懿は、諸葛亮が撤退したのは食糧と草が途絶えたためであり、民衆はきっとパニックに陥るだろうと考えていた。このとき、諸葛亮を追撃すれば、きっと輝かしい成果が得られるだろう。そのため、司馬懿は張郃に諸葛亮を追撃するよう主張した。張郃は仕方なく兵を派遣したが、木門路で諸葛亮に待ち伏せされた。戦闘中、張郃は右膝を撃たれて死亡した。 3. 張郃は本当に司馬懿が人を殺すためにナイフを借りたために死んだのでしょうか? 後世の人々は、張郃の戦死前後のさまざまな状況から、張郃の死は司馬懿の陰謀と関係があると推測した。張郃の死は司馬懿が張郃を殺そうとしたためだと彼らは信じ、借り物の刀で殺すという方法を使い、諸葛亮の手で張郃を殺した。それで、これは本当に現実なのでしょうか? 現代の受益者理論を採用すれば、この見解は理にかなっているように思われます。司馬懿が曹真の後を継ぐ前に、曹叡の周囲には彼を妨害する勢力が存在した。その時、諸葛亮の軍には荷物がなく、食料や飼料も不足しているに違いないと曹叡に助言する者がいた。諸葛亮のこの弱点を突いて正面から対峙する限り、軍を派遣する必要はなく、諸葛亮は自ら退却するだろう。上桂の小麦が収穫され続ける限り、諸葛亮は撤退するしか選択肢がなかった。曹叡はこの提案を採用せず、司馬懿を派遣して関龍軍を指揮させた。 当時、張郃は関龍軍の総大将であり、軍内で最高の威信を誇っていました。論理的に言えば、曹真が病気のために軍を指揮できなくなったとき、張郃が彼の後継者として唯一の選択肢でした。予想外に、曹叡は曹真に代わって司馬懿を派遣し、張郃は司馬懿の部下となった。曹叡の前で司馬懿を妨害した人々は、実は朝廷で張郃を支持していた人々であったと想像できます。 もちろん、狡猾な司馬懿はこれらすべてをはっきりと見抜いていました。そのため、戦いの最中、彼は張郃の提案を繰り返し拒否し、その逆のことをした。この意図は、諸葛亮を追撃するために軍隊を派遣したときにさらに明らかになりました。諸葛亮を追撃する際に待ち伏せがあり、将軍の王爽が殺された。司馬懿はこれをすべて知っていたが、それでも張郃に追撃を強要し、最終的に張郃の死を招いた。 張郃が戦闘で戦死した後、司馬懿は関龍軍を真に掌握することができた。軍の最大の敵である張郃を排除した後、他の将軍たちは司馬懿に不満を抱いていたものの、再び公然と司馬懿に反論する勇気はなかった。司馬懿は長期にわたる統治を経て、関龍軍団を自らのキャリアを築く軍隊とした。 曹爽の時代にも、関龍軍は一時的に夏侯玄によって指揮されていた。しかし、軍隊は夏侯玄とその部下に対して敬意を払わず、軍規が緩むさまざまな現象が頻繁に発生しました。この状況は、高平陵の変後すぐに司馬家が権力を握ると一変し、関龍軍団は直ちに厳格な軍規を備えた軍隊となった。この変化から、関龍軍における司馬一族の影響力を見ることができます。 司馬の天下統一戦争において、関龍軍は欠かせない役割を果たした。関龍軍の中で、司馬家に反対していた夏侯覇や鍾会などは、関龍軍を利用して自らの目的を達成することができず、逃亡するか死亡しました。関龍軍は司馬家の忠実な部下となった。その起源は司馬懿にあり、張郃の死とともに始まった。この観点から見ると、張郃の死はまさに司馬懿の裏工作の結果であった。 司馬家が権力を握る過程から、司馬懿が曹真の後を継いだとき、すでに関龍軍団を統制する考えを心に抱いていたことが分かります。もし司馬懿が曹魏に心から忠誠を誓う張郃に影響を与えたり説得したりすることができなかったら、司馬懿は間違いなくできるだけ早く張郃を排除するだろう。そのため、司馬懿は張郃が諸葛亮に待ち伏せされる可能性があることを知っていたにもかかわらず、張郃を追撃に派遣することを主張した。実際のところ、張郃のような重要な将軍をそのような任務に派遣する必要はありません。これはまさに司馬懿が借りた刀で人を殺そうとしている意図を明らかにした。 4. 張郃の死は、実は司馬懿の一石二鳥の戦略だった。 しかし、司馬懿が張郃を利用したことを、借りた刀で人を殺すという観点からのみ判断するのは、司馬懿を過小評価することになるでしょう。諸葛亮に匹敵する人物として、張郃の戦死だけでは満足しなかった。彼はまた、張郃の死を諸葛亮の戦術を判断する機会として利用し、諸葛亮との次の対決に備えた。 歴史から、司馬懿は張郃の死を気にしていなかったことがわかります。彼がもっと気にしていたのは、諸葛亮が次にいつ攻撃してくるかということだった。彼は、諸葛亮が来年も攻撃してくるかもしれないという部下の判断を否定し、むしろ諸葛亮は食料と物資を蓄え、3年後まで軍隊を派遣しないだろうと信じた。そこで彼は次の戦いに備えて、荒れ地を開拓し、関中平原の土地を耕作した。 司馬懿と諸葛亮のこの対決を見ると、司馬懿が諸葛亮の行動を試し、自身の戦闘戦略を試すために、あらゆる段階で慎重に行動していたことがわかります。この戦闘戦略は、後に司馬懿が諸葛亮の第五次北伐から守るために使用した戦略でした。つまり、 「しかし、しっかりと地盤を固めれば、敵の進撃を鈍らせることができます。前進すれば、無力になります。後退すれば、戦う機会はありません。あまり長くじっとしていると、食料が尽きてしまいます。略奪しても、何も得られません。そして、逃げることになります。逃げた後に追いかければ、完全な勝利への道が開けます。」 この政策は諸葛亮の第四次北伐に抵抗した教訓から生まれたものである。諸葛亮に抵抗する第四次北伐の際、司馬懿は何度も諸葛亮を追ったが、共に戦うことはなかった。このため諸葛亮は司馬懿に対処するために主力を集中せざるを得ず、食糧と牧草の問題を解決するために軍を分散させることはできなかった。 諸葛亮との鹿城の戦いで、司馬懿は諸葛亮の蜀軍の戦闘力の高さを目の当たりにした。この失敗により、彼は諸葛亮の主力軍と遭遇した際に戦わずに持ちこたえるという決意をさらに強めた。諸葛亮の食料と草が尽きると、彼は必然的に撤退する。彼らは諸葛亮の撤退を利用して、再び彼を追いかけるだろう。この経験は張郃の命を犠牲にして得られたものである。 司馬懿が張郃を追撃に派遣することを主張したことで、司馬懿は諸葛亮の撤退の背後にある謎を理解することができた。司馬懿は諸葛亮の第五次北伐に抵抗していたとき、撤退する諸葛亮の軍を慎重に追撃した。蜀軍が反撃を装うと、司馬懿は張郃と同じ運命を辿ることを恐れてすぐに撤退した。 そのため、張郃の死は司馬懿の借り物の刃物だったという疑惑もあるが、むしろ司馬懿が戦術の実験のために張郃を犠牲にしていた可能性の方が高い。司馬懿は張郃の死を利用して貴重な戦闘経験を得ることで、一石二鳥の効果を達成した。これらの業績から判断すると、司馬懿は間違いなく三国時代で最も狡猾な将軍である。 |
<<: 唐代には食事のシステム、座り方、食習慣にどのような変化が起こったのでしょうか?
>>: もし馬超の対戦相手が関羽に代わったら、最終的に誰が勝つでしょうか?
推薦する
「双鳳伝説」第31章:大小が魏陸を侮辱させる 蘇武が雪山で羊を飼う
今日、興味深い歴史の編集者は「双鳳物語」の第31章の全内容をお届けします。この本は清朝の薛喬珠人によ...
荊州には多くの兵士が守備にいました。呂蒙はどうやって彼らを騙したのでしょうか?
呂蒙と陸遜がいかに巧妙に荊州を占領したかは、常に語り継がれてきた話である。知られざる裏話とは?陸遜は...
世界で最も奴隷が多い国!モーリタニアはなぜ奴隷制度を廃止しなかったのですか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、世界で奴隷が最も多い国をご紹介します!皆さ...
歴史上不当に殺害された 6 人の有名な将軍を振り返ります。最初の不当な行為は永遠に残るでしょう。
古代、英雄たちが覇権を争っていた時代には、当然ながら優れた功績を残した将軍も数多く存在しました。しか...
秀雲閣第26章:西の毒竜と戦い、水の怪物を倒すよう仏に頼み、東の海で軍を起こす
『秀雲歌』は清代の魏文忠が書いた神と悪魔を扱った長編民俗小説である。 「秀雲仙閣」とも呼ばれる。この...
ヤオ族の文化 ヤオ族の茶にはどのような民族文化があるのでしょうか?
お茶は国民的飲み物です。数千年の歴史を経て、中国茶文化は中国の地に根付き、地元の風習や習慣とシームレ...
神農の妻は誰でしたか?燕迪神農の妻の名前は何ですか?
炎帝とその妻(亭軒、赤水氏の娘) 『山海経』第18巻『山海経』には次のように記されている。「炎帝の妻...
「コートビーズ」とは何でしょうか? Chaozhuは何でできていますか?
宮廷の数珠は、清朝時代に宮廷の衣服につけられた数珠の紐です。宮廷の数珠は、清朝の儀式用の衣装の一部と...
なぜ冬の初めに餃子を食べるのでしょうか?冬の初めに餃子を食べる話
はじめに:冬の初めになり、天気はますます寒くなります。冬の初めには風習だけでなく、食べ物の風習もあり...
「白牡丹」第7章:呉芳は処罰を恐れて劉金に真実を隠し、文桂は母親を歓迎して李通に敬意を表す
『白牡丹』は清代の洪綬が書いた小説です。その主な内容は、正徳帝が夢に見た美しい女性、白牡丹と紅牡丹を...
子路はどのようにして孔子の弟子になったのでしょうか?
子路(紀元前542年 - 紀元前480年)、名は仲有、字は子路、また吉路とも呼ばれ、春秋時代後期の魯...
劉禅はこんなに愚かで無能なのに、なぜ誰も彼の王位を奪いに来なかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
「双鳳伝説」第40章:黄河を渡り、邪悪な風が軍艦を首都の周りで吹き飛ばし、奇妙な岩が漢の兵士を襲う
今日、興味深い歴史の編集者は「双鳳物語」第40章の全内容をお届けします。この本は清朝の薛喬珠人によっ...
古代では男性と女性の服装に違いはありましたか?洞窟人は何を着ていたのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が古代の衣服についての記事をお届けします。ぜひ...
アルボラン海は地中海のどこにありますか?アルボラン海では事故が何件起きているのでしょうか?
ジブラルタル海峡とアルメリア海峡の間に位置する地中海のアルボラン海は、古くから重要な海上輸送ルートで...