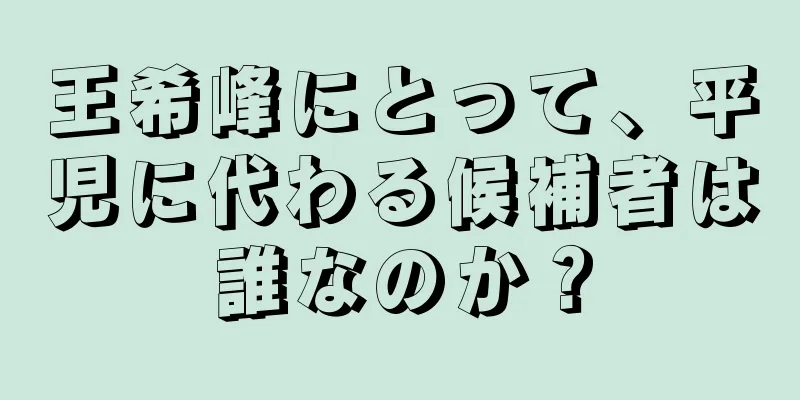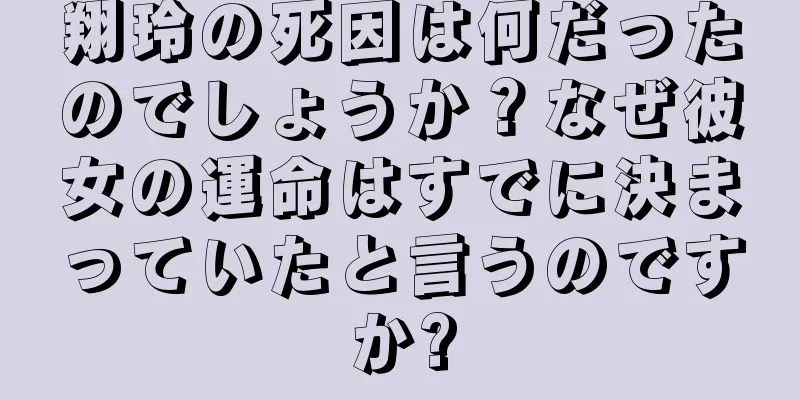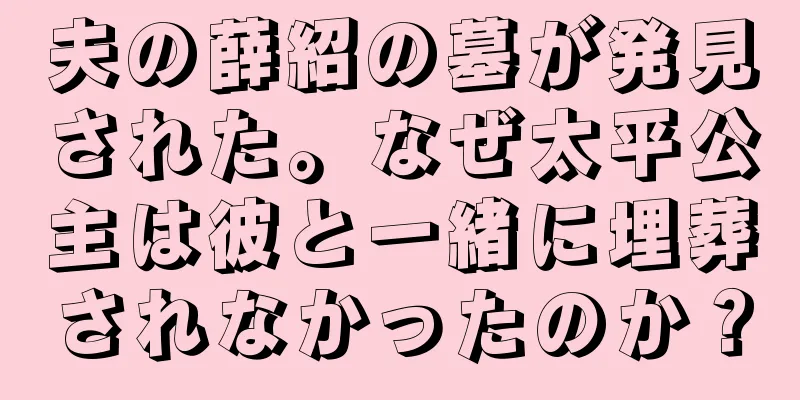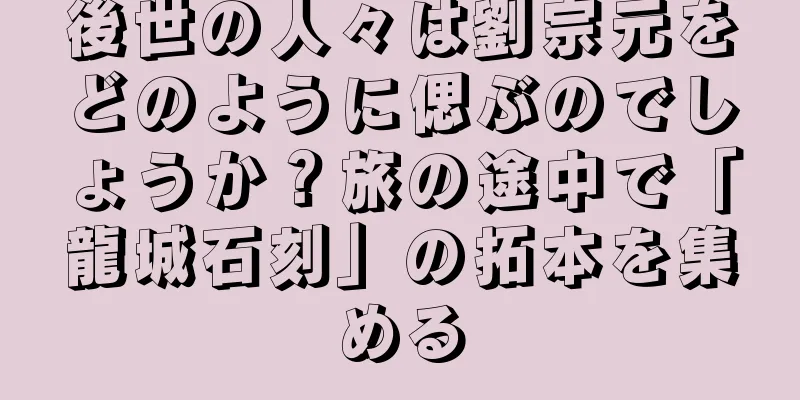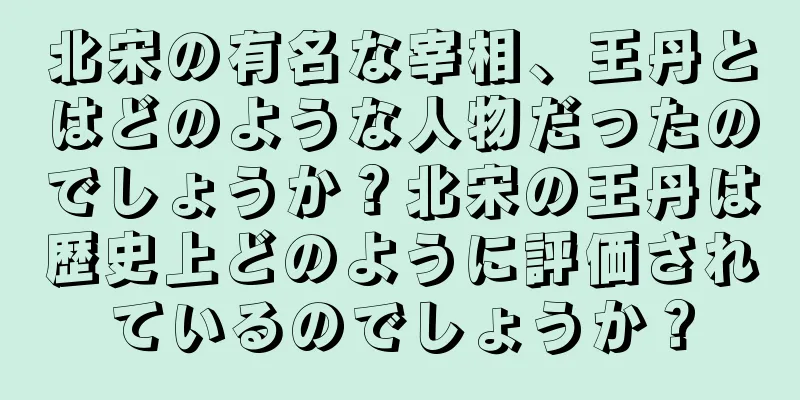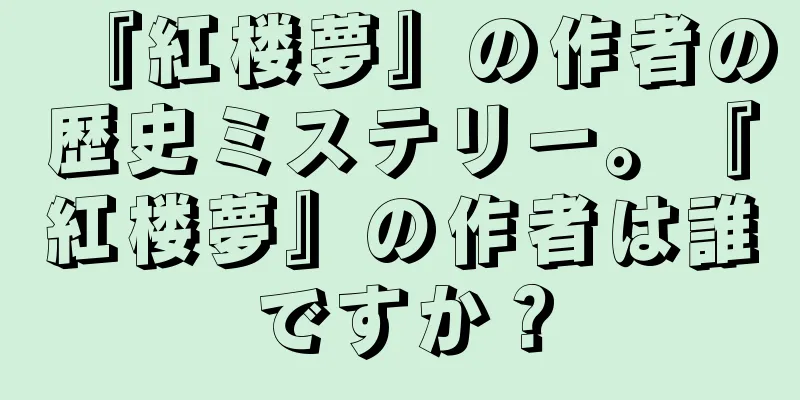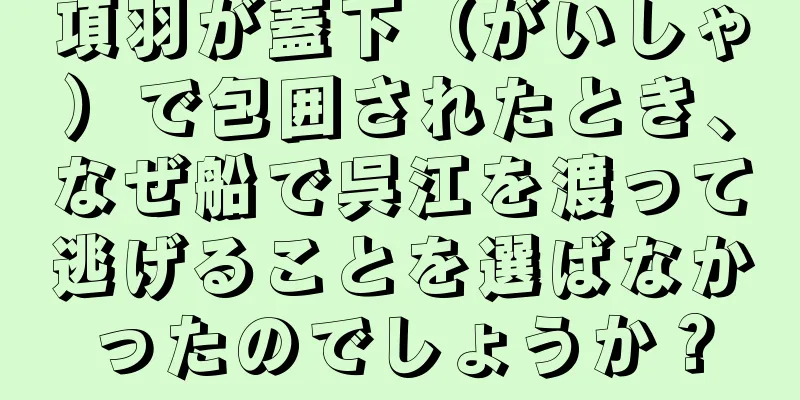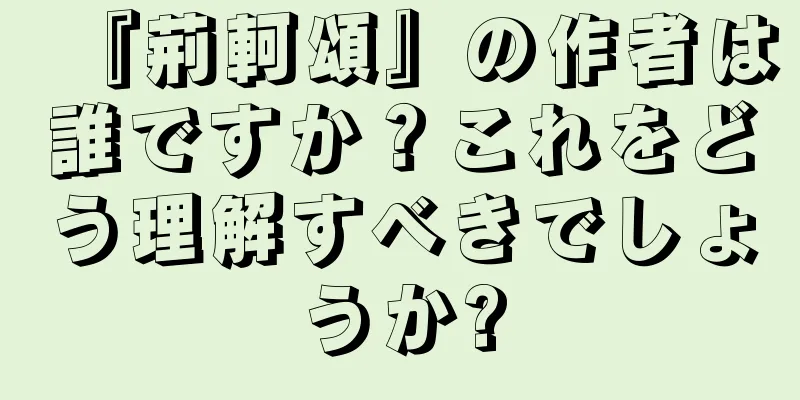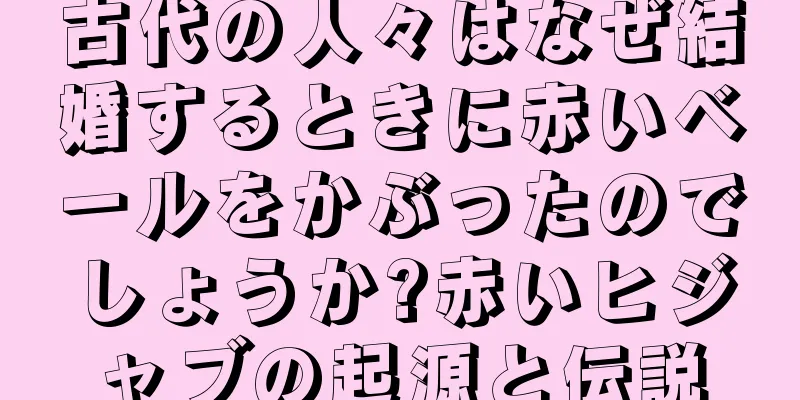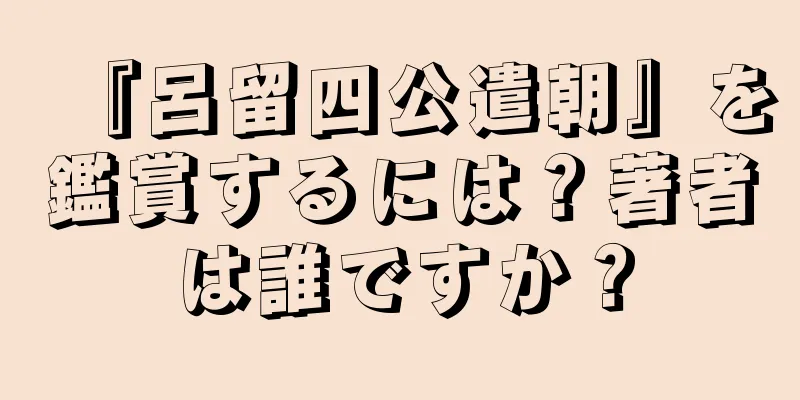諸葛亮は抜け穴の多い空城計画を採用した。なぜ司馬懿は攻撃を主張しなかったのか?
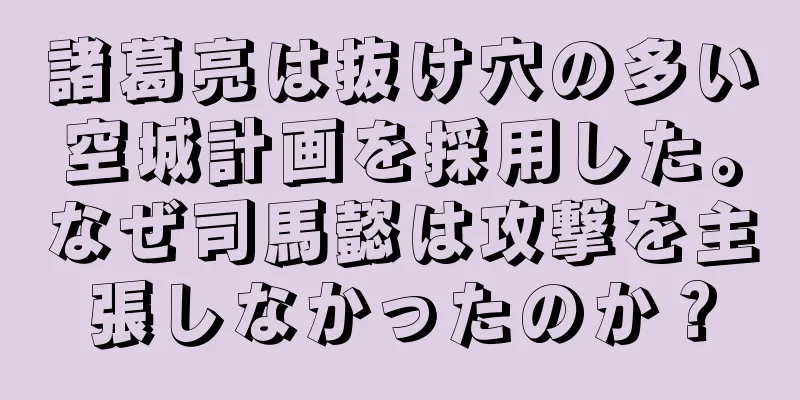
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、司馬懿が空城計画で最初に敵を偵察する兵士を派遣しなかった理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 多くの人は司馬懿が空城計画を見抜いていたとは思っていないので、司馬懿の反応を分析して、ここで何が起こっているのかを見てみましょう。 空城の陰謀は主に三国志演義における諸葛亮の第一次北伐の際に起こった。当時、諸葛亮は曹魏が東呉と争っていることを利用し、軍を率いて竜游を攻撃し、竜游の3つの郡を占領することに成功し、曹魏に衝撃を与えた。諸葛亮の考えは、この機会を利用して竜游全体を占領し、蜀漢の力を拡大し、将来の北伐への道を開くことでした。曹魏は当然、竜游を放棄したくなかったので、司馬懿を救出に派遣しました! 魏軍が救援に来ると聞いて、諸葛亮は魏軍の救援を遅らせるために、あらゆる困難を乗り越えて馬謖に街亭の警備を命じた。しかし、馬謖は才能に恵まれていたが、口先だけで実際の状況に応じた行動をしなかった。道中に陣取る代わりに、山に逃げて陣取り、結局司馬懿にあっさりと打ち負かされた。街亭を失ったことで諸葛亮は孤立の危機に陥り、仕方なく全員撤退を宣言するしかなかった。その結果、彼らが西城県に撤退するとすぐに、司馬懿が彼らを攻撃した。当時の状況は非常に危機的でした。司馬懿は15万人の軍隊を率いていましたが、諸葛亮はわずか2,500人でした。戦っても逃げても、諸葛亮は負ける運命でした。絶望した諸葛亮は空城作戦を採用し、これが後に古典となりました。 孔明は命令を下した。「旗や幟を隠せ。兵士は皆城門を警備せよ。許可なく出入りしたり、大声で話したりする者は処刑する。四つの門を開け、各門に兵士20人ずつを派遣し、民間人のふりをして通りを掃除させよ。魏の兵士が到着したら、無謀な行動をしないように。私には計画がある。」孔明は鶴の外套と絹のスカーフを身に着け、琴を持った二人の少年を連れて城内の敵の塔の前の欄干に座り、香を焚き、琴を弾いた。 司馬懿の軍が近づいていると聞いて、諸葛亮は戦い続けるしかないと悟った。そこで彼は空城計画を立案した。この計画は、軍隊を城内に隠して、旗をすべて降ろし、各家の戸を閉め、人々の移動を禁止して、空っぽの城のイメージを作り出すというものだった。そして、各城門に20人の兵士を配置して通りを掃除させ、自ら城の塔に行ってピアノを弾くというものである。実は、一般人から見れば、諸葛亮の空城計画には多くの抜け穴があったが、この計画は最終的に司馬懿を騙して逃亡させたので衝撃的だった。 空城計画は最終的に司馬懿の敗北で終わり、多くの人々に衝撃を与え、諸葛亮への尊敬の念がさらに高まりました。誰もが、このような奇跡的な考えを思いつくことができるのは、諸葛亮が神のような人物であると信じていました。しかし、現代ではインターネットが普及し、コミュニケーションが増加するにつれて、空城計画に対する疑問がますます世間の注目を集めています。その中でも、最も注目を集めているのが、空城計画の章で、なぜ司馬懿は兵士を派遣して敵を調査させなかったのか、という疑問です。司馬懿が何気なく1万人や2万人を派遣して攻撃したら、諸葛亮は暴露されてしまうのではないでしょうか。 実は、司馬懿がそうしなかったのは、諸葛亮の策略に騙されたからではありません。それどころか、司馬懿は諸葛亮の策略を見抜いて、ここが空城だと知っていたので、積極的に撤退することを選んだのです! 多くの人が疑問に思ったのは、司馬懿はどうしてここが空城だと知ったのか?空城だと知っていたのに、なぜ撤退したのか? 司馬懿は「笑ったが信じなかった」 司馬懿が西城が空城であると知っていた理由を説明するには、司馬懿の反応から推測することができます。 諸葛亮が空城作戦を展開した後、司馬懿の先鋒軍はすでに城に到着していました。門が大きく開いていて、城内には誰もおらず、諸葛亮が門に座っているのを見て、司馬懿の先鋒軍は恐れをなしました。彼らはこれが諸葛亮の計画であるかどうか確信が持てなかったため、敢えて中に入ることができませんでした。彼らにできることは、誰かを派遣して司馬懿に知らせ、司馬懿に決定を任せることだけでした!司馬懿はこの状況を聞いてまったく信じられず、自ら来て調査することにしました! 原文: しかし、司馬懿の先鋒軍の斥候たちが城に到着したとき、彼らはこのような状況を見て、敢えて前進することができず、すぐに司馬懿に報告した。易は笑って信じなかったので、3つの軍隊を止め、馬に乗って遠くから見守った。 司馬懿の先鋒軍の反応は極めて普通だった。このような異常な状況に遭遇したとき、彼らはまず司令官の司馬懿に指示を求めなければならなかった。そうしなければ、何か問題が起きても自分たちの責任になってしまうからだ。司馬懿の次の反応は非常に混乱を招きました。なぜなら、彼の反応は「懿は笑ったが、信じなかった」だったからです。司馬懿は何を笑っていたのでしょうか?なぜ信じなかったのでしょうか?ここで、諸葛亮の空城計画を見なければなりません! 三国志演義では、2つの軍隊の戦いで待ち伏せがよく使われていました。諸葛亮は曹操の軍隊に対処するためにこの方法を使用しました。新野を焼き払うことは、城を空っぽにして曹操の軍隊が突入できるようにし、最終的に曹操の軍隊を待ち伏せするという目的を達成するようなものでした。普通に考えれば、もし諸葛亮がこの時に司馬懿を待ち伏せしたいなら、城門を開けて武器や防具を捨てる場面を作り、司馬懿の軍を城内に誘い込み、その後城門を閉めて敵と戦うのが最善の戦略だろう。しかし、実際の状況は、諸葛亮が城壁の上に座っていたということです。城内には誰もいないように見えましたが、門を掃除している人がいました。これは単に真実を隠そうとした試みでした! こうすることで、諸葛亮は司馬懿に「ここに待ち伏せがあるのに、なぜ攻めに来たのか。どうしてこんな軍隊を使うのか」と言っているのではないですか。中国には「吠える犬は噛まず、噛む犬は吠えない」という諺があります。これは、犬が本当に噛みたいと思ったら、ずっと吠えることはないという意味です。噛みつくのにちょうどいい機会をじかに見つけるのです。本当に吠え続ける犬は、実はブラフをしているだけです。本質的には、あなたをとても恐れているのです。このことわざの派生的な意味は、本当にあなたを殴りたいと思っている人は、あなたと議論することなく直接それを実行するが、あなたと議論し続ける人は通常、行動を起こさない人であるということです。 諸葛亮の空城計画は諺に似ています!もし本当に司馬懿を待ち伏せするつもりなら、塔に現れるはずがありません。塔に現れたことは、それがブラフだったことを示しています。諸葛亮は地上に待ち伏せがあると人々に思わせましたが、実際には、当時の彼の力は敵を食い尽くすのに十分ではありませんでした。そうでなければ、彼はあなたと話す時間を無駄にせず、ただ行動を起こしたでしょう! 諸葛亮の空城計画があまりにも異常だったからこそ、司馬懿は「笑って信じなかった」のです!司馬懿が笑ったのは、この計画があまりにも偽物だったからです。明らかに、城内の軍隊は司馬懿を待ち伏せして倒すほど強力ではなかったのではないでしょうか?司馬懿がそれを信じなかったのは、諸葛亮はとても賢いのに、どうしてこんな下手な計画を使うことができるのかと思ったからです。だから、先鋒軍が人々を騙しているのか、それとも諸葛亮がまた策略を弄しているのか、自分で確かめに行こうと思いました。結果、それを見た後、すぐに軍隊を撤退させることに決めました! どうしてわかるんですか? 司馬懿は自ら敵の状況を調べに行き、先鋒軍が言った通りの状況であることを知った。諸葛亮は城の頂上に座ってピアノを弾いており、城内には待ち伏せがあるようだった。 原文: 案の定、孔明は城壁に座って微笑み、線香を焚き、ピアノを弾いているのが見られました。左側には剣を手に持った少年がいます。右側には泡立て器を手に持った少年がいます。城門の内外には20人以上の民がいて、頭を下げて地面を掃き、まるで誰もいないかのようだった。 易はこれを見て非常に不審に思い、中央軍に行き、後軍を前軍として、前軍を後軍として行動させ、北の山道に向かって撤退するよう命じた。 司馬懿はこれを見て非常に困惑したが、彼の次の行動は人々をさらに困惑させた。彼は直接、後軍を前軍として、前軍を後軍として働かせ、撤退を開始したのである。司馬懿の息子である司馬昭もこの問題に気づき、諸葛亮が策略を巡らせていると考えました。司馬昭は司馬懿に簡単に撤退せず、誰かを派遣して状況を調べるよう助言しました。 原文: 次男の司馬昭は言った。「諸葛亮の五軍がわざとこのような行動をとったのだろうか。なぜ父は軍を撤退させたのか?」 司馬昭の意見は実は我々と同じで、この件に何か怪しいところがあると思っているが、司馬懿は軍の撤退を主張し、こう言った。 原文: 易は言った。「梁は常に用心深く、決して危険を冒さなかった。城門が大きく開いている今、待ち伏せがあるに違いない。我々の軍隊が前進すれば、彼らは罠に陥るだろう。どうしてそれが分かるというのか? すぐに撤退すべきだ。」 実は、司馬懿の言葉の中の「どうして知ることができたのか」という4つの言葉が重要なポイントです。なぜなら、司馬懿は司馬昭よりも先を見通すことができ、諸葛亮の意図をすでに理解していたからです。諸葛亮が欠陥の多いこの空虚な城郭計画を掲げたのは、実は、この城の軍事力は確かに司馬懿を倒すには十分ではないが、もし司馬懿が攻撃を主張して諸葛亮を捕らえたら、司馬懿にどんな利益があるのか、司馬懿に伝えるためでした。以前、曹叡があなたをどのように扱ったかを忘れたのですか? もし諸葛亮が正常な考えに従って、自ら城壁に座るのではなく、空の城計画を立てていたなら、司馬懿は罠に陥り、それが本当の待ち伏せ計画だと思い、司馬懿は間違いなく人を派遣して試しに攻撃を仕掛けていただろうと言える。しかし、諸葛亮が自ら城壁に座ると状況は異なり、それは司馬懿に向かい側に空の城があることを直接告げることに等しく、司馬懿を非常に困惑させた。諸葛亮はこんなにも賢いのに、なぜこの時にこんな愚かな決断をしたのでしょうか?司馬懿は知恵を絞ってようやく諸葛亮の言っている意味を理解しました。鳥が消えたら良い弓は隠される、狡猾なウサギが死ねば走り回る犬は調理される!これは司馬懿に身を守るよう思い出させるためでした!曹叡は以前から司馬懿を疑っていたことと相まって、永涼の太守としての司馬懿の権力を否定し、司馬懿は背後で冷たく感じていました!そこで司馬懿はついに軍を撤退させることを決意しました! |
>>: 壮族の食べ物:壮族の日常の食べ物や祭りの食べ物の特徴は何ですか?
推薦する
宋代の詩「高楊台・西湖の春情」の鑑賞。この詩の作者はどのような感情を表現しているのでしょうか。
高楊台・西湖春情[宋代]張炎、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょ...
二次資本とは何ですか?古代中国の歴史において、伴侶を選ぶための条件は何でしょうか?
漢王朝は劉姓を持つ王朝で、劉邦が建てた前漢と劉秀が建てた後漢に分かれた。後世の歴史家は、首都の場所が...
『紅楼夢』では、禿げ頭の僧侶と足の不自由な道士はどのような役割を果たしていますか?
紅楼夢で禿げ頭の僧侶と足の不自由な道士がどんな役割を演じているか知っていますか?次は興味深い歴史編集...
杜甫は詩「岳陽楼登り」でどのような芸術技法を使用しましたか?
杜甫は『岳陽楼に登る』でどのような芸術技法を使ったのでしょうか。この詩は意味が豊かです。歌詞は低くて...
千奇の「春の夜竹閣の王維の辞世の詩に答える」:詩全体が新鮮で奥深く、余韻がたっぷりである。
銭麒(722?-780)、号は中文、呉興(現在の浙江省湖州市)出身の漢人で、唐代の詩人。偉大な書家懐...
陳玉毅の『清明節二詩・第1』:流暢な音節、簡潔で明確な意味表現
陳毓宜(1090年 - 1139年1月1日)は、字を曲飛、号を建寨といい、漢民族である。彼の先祖は荊...
戴樹倫の『大晦日に石頭駅に泊まる』:唐代の五字律詩の中でも常に名作とされている。
戴叔倫(732年頃 - 789年頃)は唐代の詩人で、字は有公(慈公ともいう)で、潤州金壇(現在の江蘇...
『紅楼夢』で、金婚式は薛叔母と宝仔にどんな利益をもたらしますか?
『紅楼夢』で言及されている「金婚」の象徴は、薛宝才の「金の鍵」と賈宝玉の「魔玉」である。今日は、In...
「通関里」をどう理解するか?創作の背景は何ですか?
トンガン・リー杜甫(唐代)兵士たちは潼関路沿いの都市建設に非常に不注意だった。大都市は鉄ほど良くなく...
劉宗元の「孟徳への別れ」:この詩は別れの気持ちを直接表現し、誠実で感動的な芸術的構想を生み出している。
劉宗元(773年 - 819年11月28日)は、字を子侯といい、河東(現在の山西省運城市永済)出身の...
形而上学の発展の歴史は何ですか?魏晋時代の形而上学の特徴は何ですか?
形而上学とは何を意味しますか?形而上学の歴史は何ですか?形而上学の特徴は何ですか?次の興味深い歴史編...
曹操の『昊麗歌』の原文は何ですか?どのように翻訳しますか?
曹操の『草原の歌』の原文は何ですか?どう翻訳しますか?この詩は、岳府という古い題名を使って時事問題を...
『西遊記続』第7章:法を護ることに専念する大僧正、唐三蔵が神通力を現し経典を封印する
明代の神話小説『続西遊記』は、『西遊記』の3大続編のうちの1つです。 (他の2冊は『続西遊記』と『補...
「富春から延嶺までの景色はとても美しい」の原文は何ですか?どのように理解すればよいのでしょうか?
富春から燕嶺までの景色はとても美しいです季雲(清朝)春の雲のように厚く、煙のように軽く、川岸までずっ...
古代人はなぜ「六人仲良くしないと、七人仲良くならない」と言ったのでしょうか。
昔の人はこう言っていました。「六人仲良くしない、七人一緒にしない!」今日:友達を作るときは注意してく...