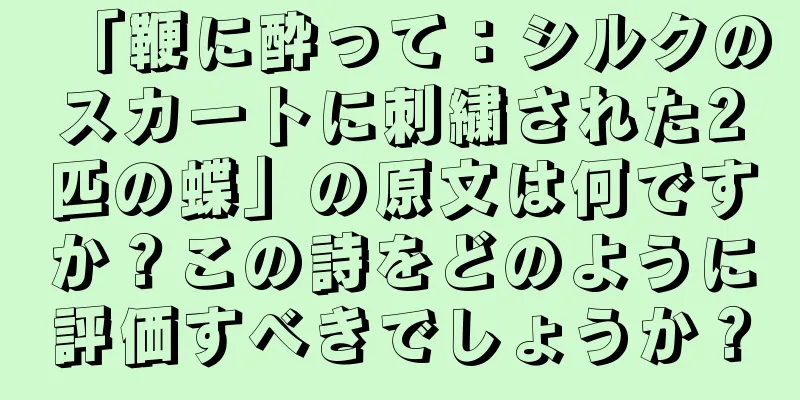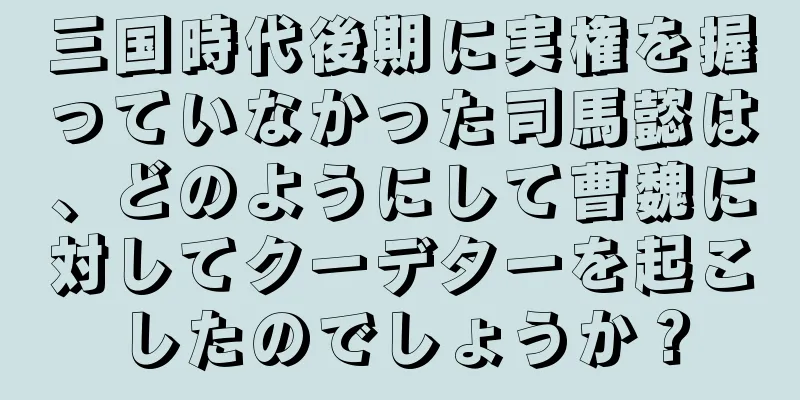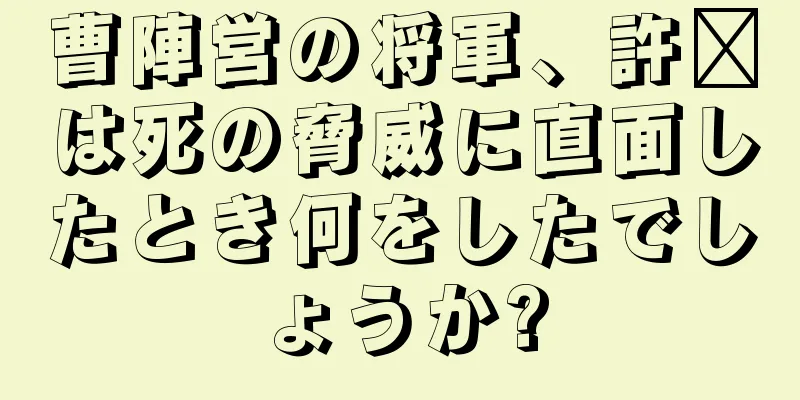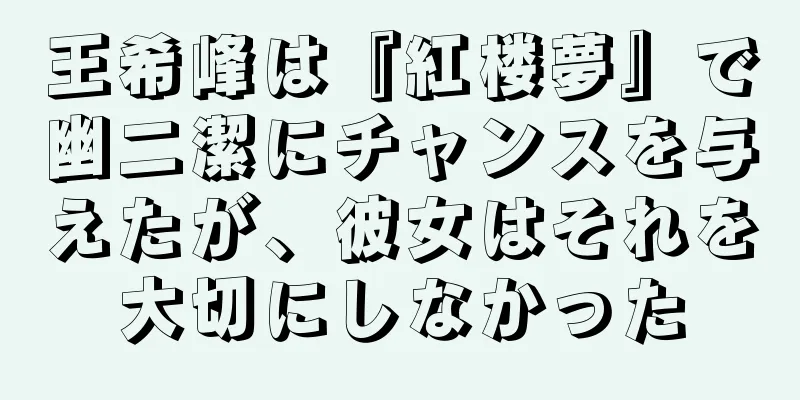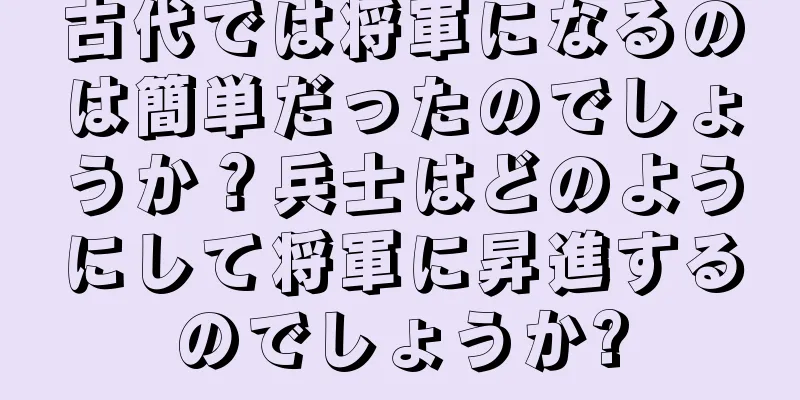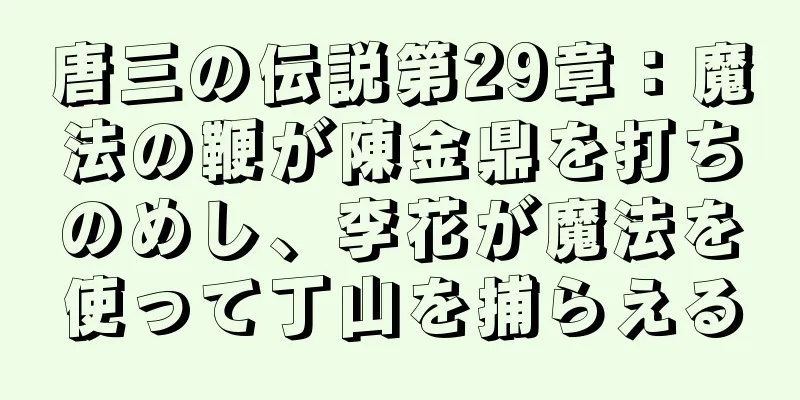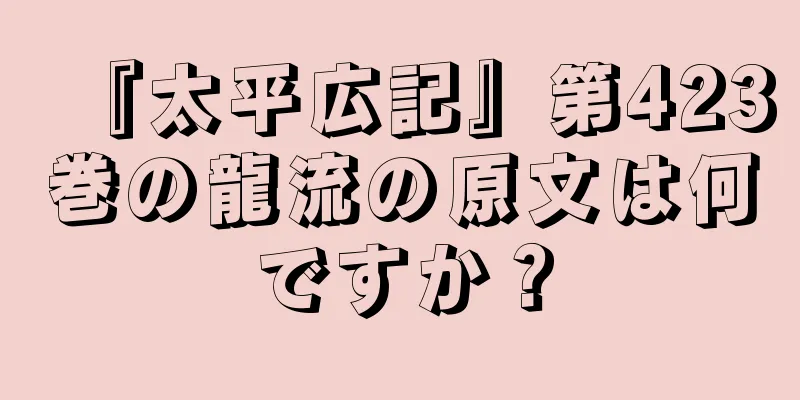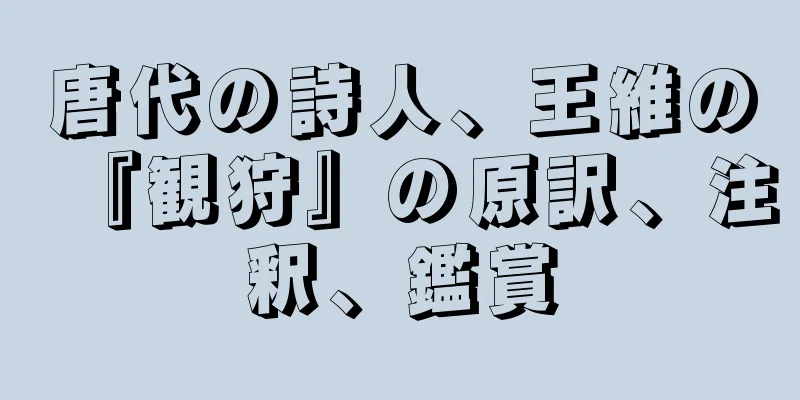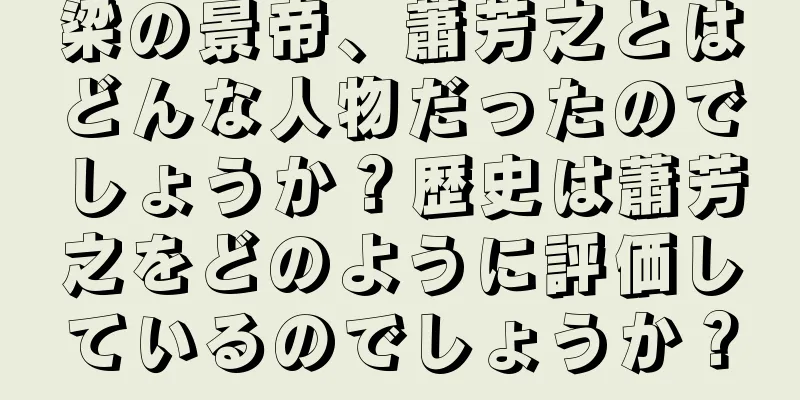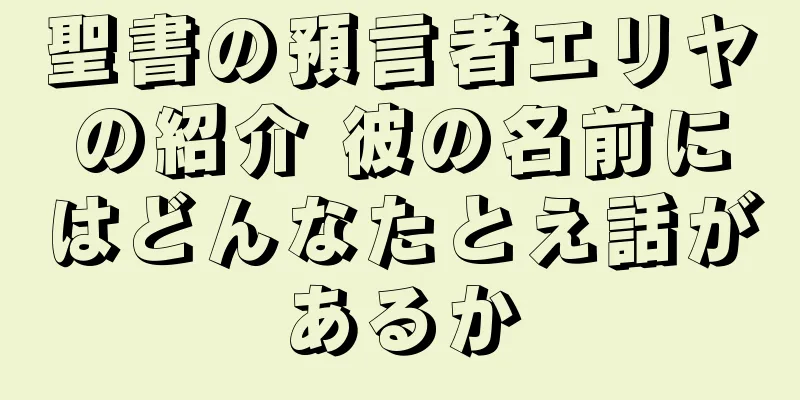形而上学の発展の歴史は何ですか?魏晋時代の形而上学の特徴は何ですか?
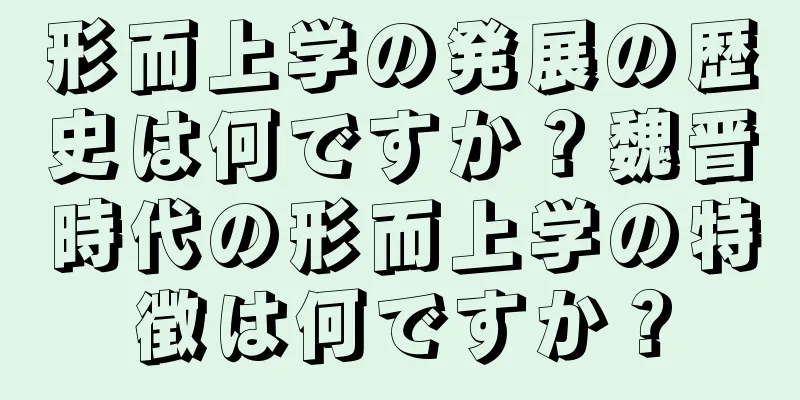
|
形而上学とは何を意味しますか?形而上学の歴史は何ですか?形而上学の特徴は何ですか?次の興味深い歴史編集者が詳細な紹介をお届けしますので、見てみましょう! 形而上学入門 形而上学。ここでの「玄」という言葉は老子の一文「神秘で神秘、すべての驚異への扉」に由来しています。形而上学はもともと道教哲学で使われていた用語で、老子を中核研究として魏晋の時代に出現した哲学的潮流を指していました。 形而上学は、新道教としても知られ、老子、荘子、易経の研究と解釈であり、魏晋の時代に始まりました。形而上学は、中国で魏晋時代から宋代中期にかけて出現し、老子や荘子を擁護した思想潮流である。道教の教えを新しい形で表現したものとも言えるため、新道教とも呼ばれています。この思想の潮流は漢末期から宋中期まで続いた。 形而上学は、漢王朝の儒教の古典に取って代わった、魏晋王朝の主流思想でした。 形而上学は「神秘の学問」であり、「老荘子に遡る」という理論を基礎とし、「老子」「荘子」「周易」を「三神秘」と呼んでいます。道教の形而上学は、儒教以外では公式の学問として指定されている唯一の学問でもあります。 形而上学の目的 魏晋の時代、形而上学は言葉と行為の二つの側面を指し、神秘的な言葉と優雅な行為を指す、深遠で寛大なものとみなされることが多かった。 「玄元」とは、特定の物事から離れ、「言葉やイメージを超越する」という存在論的な問題を具体的に議論することを指します。したがって、表面的なもの、神秘的なもの、深遠なものの研究は、一般的に形而上学と呼ばれることがあります。神秘主義者のほとんどは当時の有名人でした。主な代表者としては、何厳、王弼、阮済、季康、項秀、郭翔などが挙げられます。それは漢代における儒教(古典学)の衰退を基盤として発展し、漢代の道教思想と黄老学派の思想から発展しました。これは後漢時代から魏時代初期の青壇の直接的な発展である。 魏晋形而上学とは、老子と荘子(または三秘)の思想に基づき、漢代の複雑な儒教の古典から解放され、「自然」と「正統」を調和させようとする、魏晋時代の特定の哲学的潮流を指します。中心となるのは「根源と果ての有無」、つまり思索的な手法で宇宙の存在の根拠を論じるという問題です。つまり、「物」や「事」から離れた形で、事の存在の根拠という存在論的・形而上学的問題を論じているのです。老子と荘子の思想を基礎に中国哲学を構築し、儒教と道教を融合させようとする試みは、中国哲学史上初めてのことであり、非常に意義深い哲学的試みであった。 哲学では、存在と非存在の問題に主な焦点が当てられており、非存在を重視する形而上学と存在を重視する形而上学の 2 つの学派が生まれました。 形而上学とはどういう意味ですか? 形而上学は、中国の魏晋時代に生まれた老子と荘子を擁護する思想潮流であり、一般的には特に魏晋時代の形而上学を指します。 「玄」という概念は『老子』に初めて登場します。「神秘で神秘、すべての不思議への扉」。王弼は『老子之略』で「玄は深いという意味だ」と述べています。形而上学は深遠かつ神秘的な問題の研究です。 形而上学は、新道教としても知られ、老子、荘子、易経の研究と解釈であり、魏晋の時代に始まりました。形而上学は、中国で魏晋時代から宋代中期にかけて出現し、老子や荘子を擁護した思想潮流です。道教を新しい形で表現したものともいえるため、新道教とも呼ばれています。この思想の潮流は漢末期から宋中期まで続いた。それは、世間で形而上学や神秘と呼ばれているものとは異なります。 「玄」という概念は老子に初めて登場しました。「神秘的で神秘的、すべての驚異への扉」 楊雄も玄について語った。『太玄玄志』の中で彼は「玄とは、漠然として万物を覆い、目に見えないもの」と述べている。王弼は『老子之略』の中で「玄とは深いという意味」と述べている。形而上学とは、深遠で広範囲にわたる問題を研究する学問である。魏晋の人々は『老子』『荘子』『易経』を「三玄」と呼んで重視し、『老子』と『荘子』は「玄宗」とみなされた。衛晋学の主な代表者としては、何厳、王弼、阮済、季康、項秀、郭湘などが挙げられます。 形而上学における「玄」は老子の思想に由来する。『老子・第一章』には「神秘とは、逆にすべての驚異への扉である」とある。玄とは、宇宙の万物の普遍的な法則、「道」であり、万物の無限かつ神秘的な変化を体現したものです。神秘主義者たちは老子や荘子の思想を儒教の『論語』や『易経』に注釈を加え、人々の心を保つ機能を失っていた漢代の儒教の経典を改造し、「無を根源とする」哲学的存在論を確立した。形而上学では「儀式と法律」「道徳」「人間性」といった儒教の思想も議論されるが、その主なテーマは道教であり、崇高なものは「無」「自然」「無為」であると強調する。 形而上学の進化 東漢末期から晋に至るまで、200年以上の混乱期が続いた。統一された東漢の崩壊とともに、400年近く思想界を支配してきた儒教は魅力を失い始めた。文人は漢代経典の煩雑な学風、神学の奇怪で浅薄な予言、三縁五常の決まり文句に飽き飽きし、新たな「落ち着く」場所を求めて、形而上学的な哲学論争に耽溺した。このような議論は、後世のサロンのようなもので、優雅で有名な学者(紀康と阮済に代表される有名な「竹林の七賢」は、魏晋のスタイルを体現した人物でした)が集まって深遠な真理を議論し、当時の人々はそれを「清壇」または「玄壇」と呼んでいました。 東晋以降、形而上学の人気は衰えるどころか、むしろ高まった。王弼の『易経』は南朝に成立した。宋・斉の南朝の四官学には形而上学が含まれていた。梁・陳の時代は『三秘』の議論が盛んだった。したがって、東晋・南朝は形而上学が盛んだった時代であるはずである。昔、唐代の学問は儒教、仏教、道教が融合したものだったと言われていました。今では、唐代の官学と民間学は違うようです。官学には儒教の経典と道教が含まれます。儒教の経典とは、五経、論語、孝経の研究を指します。その中で、易経は王弼の注釈を使用し、論語は賀厳の評論を使用しており、これは形而上学における易経の完全な継続です。唐代の道教と道教は、老子、列子、文子、荘子の4冊の本を尊重していました。4冊とも経典と呼ばれていました。この種の道教は、老子と荘子の形而上学の発展または増幅であると言えます。宋代中期に形而上学は新儒教に取って代わられた。 清代の学者趙毅の『二十二史記』によると、純談の流行は魏斉王曹芳の正史時代に始まった。何厳と王弼がその創始者と言える。二人とも当時の貴族界の有名人であり、彼らの影響力は時代の流行となった。 『晋書』に出てくる「正式の音」とは、魏晋全時代における形而上学的な議論の動向を指しています。 東晋の時代には仏教が栄え、形而上学と仏教は互いに影響し合いました。仏教学者が形而上学について語り、形而上学者が仏教について議論することが流行しました。両者の収斂は、確かに当時の学問の発展の一般的な傾向であったが、形而上学を用いて仏教を論じる者は、究極的には仏教徒であり、仏教を用いて形而上学を論じる者は、究極的には形而上学者であった。したがって、形而上学であろうと仏教であろうと、両者の間に明確な区別がなかったとは言えない。さらに、一部の形而上学者は正始時代以来の形而上学の潮流を継承しましたが、仏教と融合したり、仏教を利用して形而上学を論じたりしませんでした。 形而上学の特徴 主な研究対象は「三秘」であり、『易経』には『老子』と『荘子』の注釈が付けられている。 「存在と非存在」という弁証法的な問題を中心に据える。何厳や王弼に代表される無を重視する形而上学派は、「無」を世界の根源、世界の統一の基礎とみなす。一方、裴薇や楊全など存在論を唱える人々は、存在は自己生成であり、自己生成したものは存在を本質とすると考えている。 その哲学の基本的な内容は、世界の存在論を探求することです。無を重んじる学派は、「無」を「有」の存在の根拠とみなし、「無を根拠とする」という存在論的思想を提唱する。郭翔は独立論を唱え、「有」は独立して存在し、それ自体の存在論として「無」を必要としないと考えている。 |
<<: 古代の通信手段である鳩の運搬は戦場で効果を発揮できるのか?
>>: 王莽はどのようにして漢王朝を簒奪したのでしょうか? 王莽はなぜ最終的に失敗したのでしょうか?
推薦する
花果山の猿は力強いだけでなく、非常に強い。
孫悟空が捕らえられた後、二郎神はなぜ花果山を攻撃しなかったのでしょうか?今日は、Interestin...
『紅楼夢』の黛玉の「五人の美女」と丹春の遠国への嫁入りにはどんな関係があるのでしょうか?
丹春の遠方への嫁入りは『紅楼夢』の筋書きである。興味のある読者とInteresting Histor...
蔡大先生の誕生日プレゼントが二度も盗まれました!前回は誰が撮ったんですか?
蔡太史の誕生日プレゼントが二度も盗まれた!もう一回盗んだのは誰?『Interesting Histo...
陸倫の「李端への別れ」は感動的な別れの詩である
陸倫は、号を雲艶といい、科挙に合格して進士となったが、安史の乱が勃発したため官吏を務めることができな...
チャン・ジャオの妻は誰ですか?チャン・チャオの妻、ディン・ユエホアのプロフィール
丁月華丁月花は、中国の古典小説『三勇五勇士』の登場人物です。丁朝の二人の英雄の妹であり、武術の決闘で...
「初春に農夫と出会う」の著者は誰ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
春最初の農夫劉宗元(唐代)楚南部では春が早く訪れ、残寒はすでに繁栄をもたらしています。畑は油で覆われ...
雲津の文化的美学とは何ですか?雲錦は中華民族のどのような理念を体現しているのでしょうか?
雲錦は「一寸の錦は一寸の金に値する」と言われる中国の伝統的な絹工芸品であり、中国独特の文化的美学を体...
赤潮は赤潮とも呼ばれます。現代の科学技術は赤潮の原因を説明できますか?
赤潮は赤潮とも呼ばれます。海中のプランクトンの爆発的かつ急速な増殖により海水が異常な色に変化する現象...
趙雲は評価されていないのですか?いいえ、『三国志演義』では他の五大将軍と並んでランク付けされています。
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
熙公29年の儒教経典『古梁伝』の原文は何ですか?
顧良池が著した儒教の著作『春秋古梁伝』は、君主の権威は尊重しなければならないが、王権を制限してはなら...
呉璋の「金鹿曲・聖本清廉街」:大胆さと哀愁が融合した芸術スタイル
呉璋(1799-1862)は、清朝の有名な女性作詞家、作詞家である。彼女の芸名は萍祥、号は玉允子。彼...
金が南方へと大規模な侵攻を開始したとき、なぜ南宋の経済生産は北宋を上回ることができたのでしょうか。
当時の世界貿易圏の二大軸は、インド洋北岸の南宋とアラブ帝国であった。この観点から、アメリカの学者馬潤...
張飛は歴史上実際にどんな武器を使ったのでしょうか?張八蛇槍は本物ですか?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が張飛について...
魏英武の「秋夜秋氏宛書簡」:詩全体は強い言葉やフレーズで読者を惹きつけるものではない
魏英武(生没年不詳)、号は易博、荊昭県都陵(現在の陝西省西安市)の出身。魏蘇州、魏左司、魏江州として...
『漢書』:中国初の年代記と伝記の形式で書かれた歴史書。『二十四史』の一つ。
『漢書』は『前漢書』とも呼ばれ、中国初の伝記形式の年代順歴史書であり、『二十四史』の一つです。後漢時...