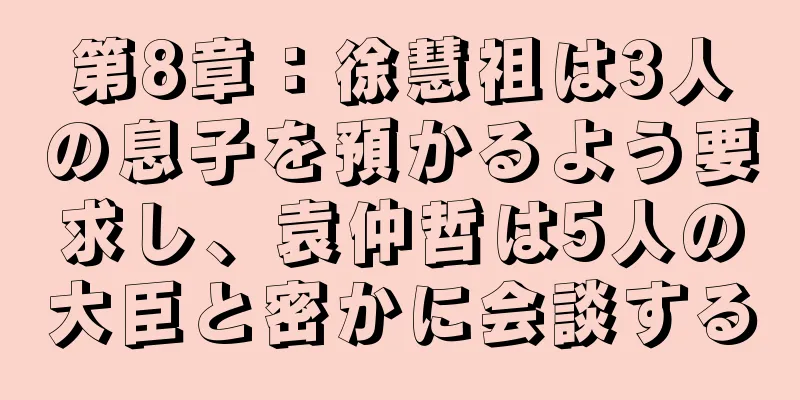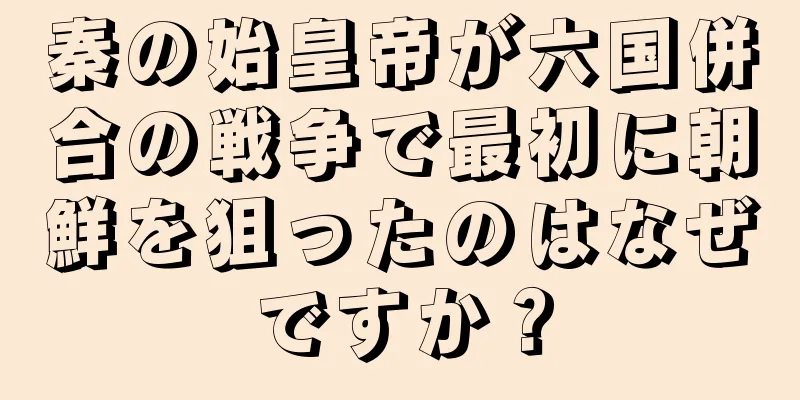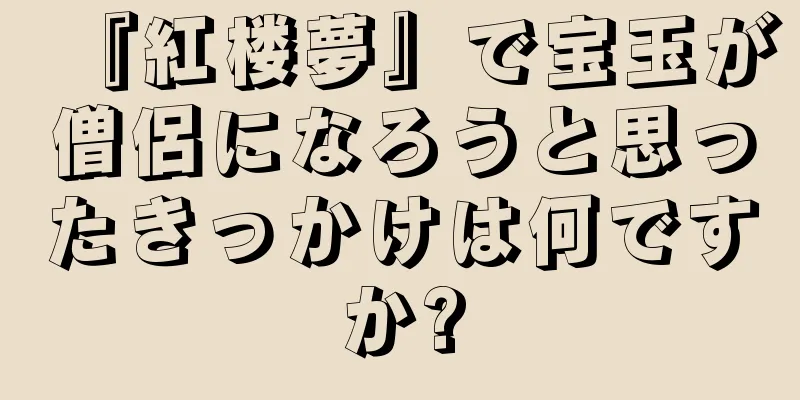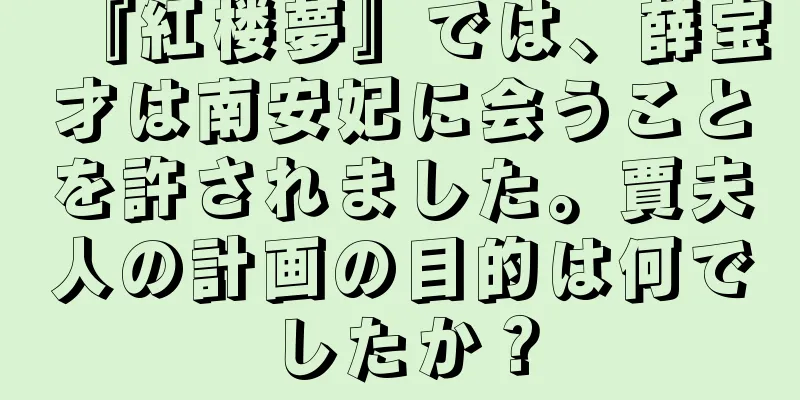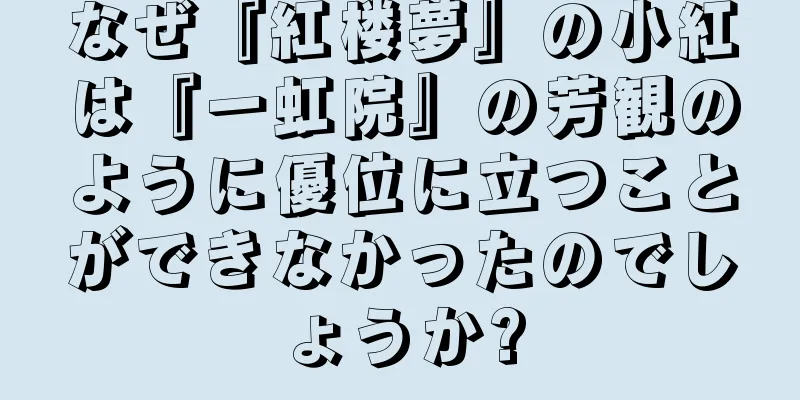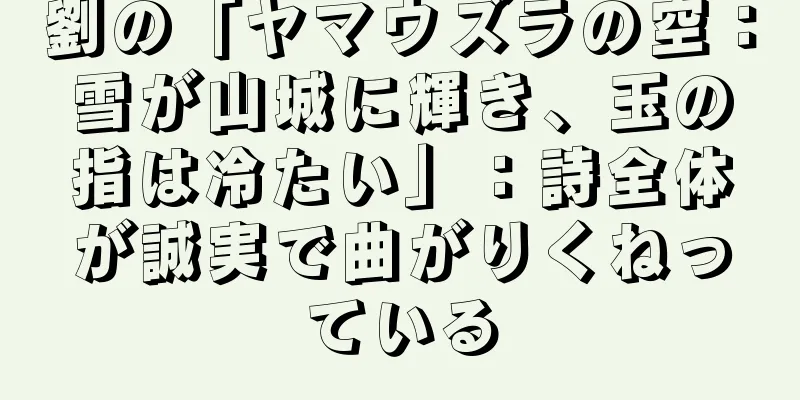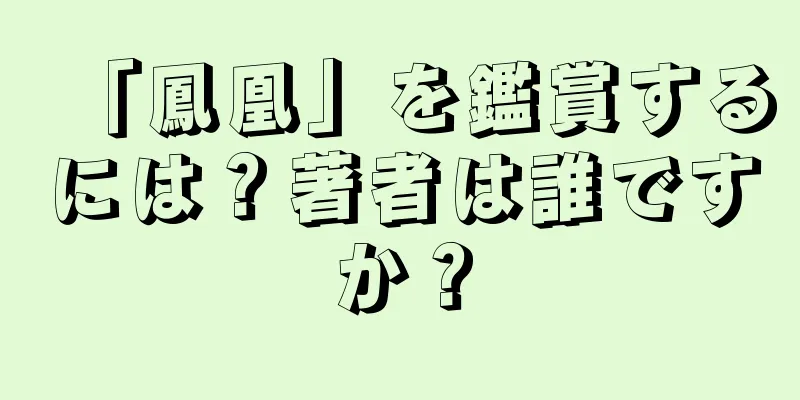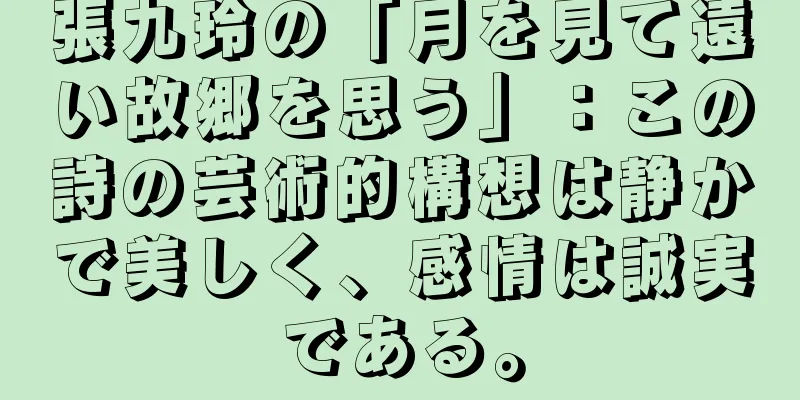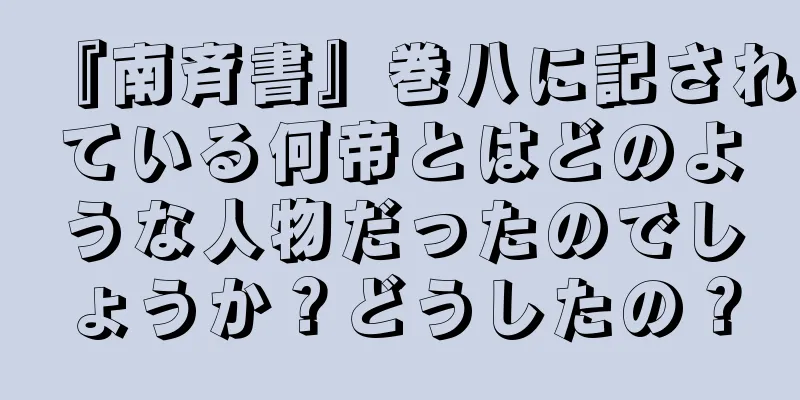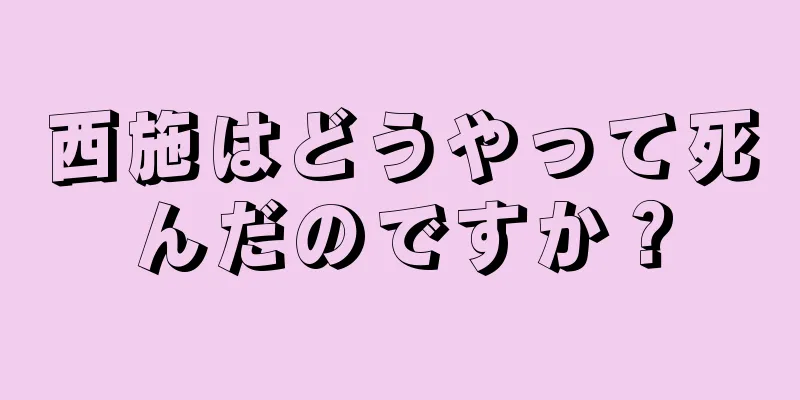于禁は曹操が最も信頼していた人物だったが、なぜ敵意を抱かれたのか?
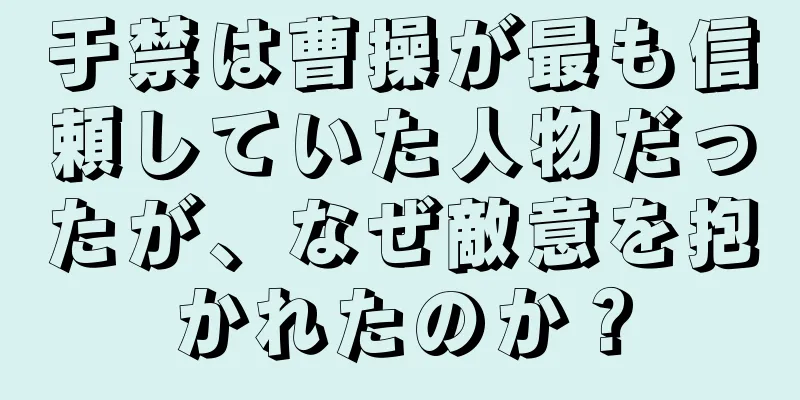
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。次に、興味深い歴史編集者が、張遼、楽進、于進、徐晃、張郃がどのように亡くなったかを詳しく紹介します。見てみましょう! 張遼は後世の五大将軍の筆頭と評価されたが、曹操の時代に曹操が最も尊敬し信頼していたのは張遼ではなく于禁であった。しかし、その後、于禁は大きな過ちを犯し、曹家から許されなかったため、于禁の地位は弱まりました。張遼の話に戻ると、張遼は子供の頃から東漢の国境に住んでいて、胡族から頻繁に嫌がらせを受けていました。しかし、この一連の騒動は張遼の優れた才能を引き出しました。彼はまだ十代の頃、すでに雁門県の県官になっていました。その後、丁元、何進、董卓、呂布の跡を継ぎ、紆余曲折を経て、呂布が敗れた後、曹操に降伏し、曹操のために働くようになった。 張遼の軍事的才能は曹操の下で十分に発揮され、袁紹を攻撃し、常熙を破り、五環を滅ぼした。張遼は多くの偉大な功績を残し、曹操から高く評価された。その後、張遼は合肥の守備を命じられました。合肥で張遼は生涯最高の戦績を収め、この戦績で武廟に入りました。後世からは古今東西の名将64人の一人と評価されました。もちろん、この最高の戦績とは、800騎の孫権率いる10万の軍を破ったことです。張遼の生涯を通じて、東呉は合肥を占領することができず、呉の主君である孫権は何度も張遼に敗れました。人々は冗談で、張遼に経験を与え、張遼を生け捕りにして武廟に入れたと言いました。 正史では張遼は最終的に病気で亡くなり、それは良い結末だったと言える。しかし、小説では、張遼の死は羅貫中氏の価値観に合わないことは明らかです。そのため、小説では、張遼が東呉の将軍徐鋒の矢で腰を撃たれ、陣営に戻った後に死亡したことがわかります。正直に言うと、この記事では、三国志演義における張遼の結末は良くなく、正史における結末の方が明らかにずっと良いと考えています。 楽進と比べると、張遼は比較的幸運です。少なくとも三国志演義では、張遼はまだ非常に強力な戦闘力を持つ一流の将軍です。しかし、五大将軍の一人として、楽進は正史では非常に強力な人物であったが、三国志演義ではその力は大きく弱まった。 正史では、楽進は常に真っ先に戦場に出ていました。それはどういう意味ですか?彼は常に戦いの最前線にいました!そのような状況下で、彼は生き残ることができ、何度も軍事的功績を挙げて大将軍になりました。これは、楽進の個人的な戦闘力がいかに強かったかを示しています!正史では、楽進はかつて袁紹の将軍である淳于瓊と燕静を殺し、1万人の敵である関羽を撃退しました。楽進は超タフガイと言えますが、三国志演義では一流の将軍にもランクされないほど弱体化しており、本当に恥ずかしいです。 建安23年(218年)、楽進は亡くなり、魏侯と諡された。楽進がどのように亡くなったのかは歴史書には記載されていないが、詳細な記録が残っていないことから自然死であり、他人の手で亡くなったのではないと推測されている。このことから、Le Jin の最終的な結果は非常に良好であったことがわかります。もちろん、これは羅冠中氏が見たかったものではありません。そのため、小説では楽進は東呉の将軍甘寧の冷矢に当たって負傷し引退し、その後小説には二度と登場しません。五大将軍の一人である楽進は結局何も得られなかった。それはとても不公平だ。 前述のように、于禁はもともと曹操から五将軍の中で最も尊敬されていた将軍でしたが、やがて失敗を犯し、曹一族に嫌われ、地位が下がってしまいました。では、なぜ于禁は敵対するようになったのでしょうか?実は、それは彼が関羽に降伏したからでした! 襄樊の戦いでは、関羽が軍隊を率いて曹仁を打ち破り、曹仁を市内に撤退させ、戦闘に参加する勇気をなくした。樊城は曹魏の戦略的な軍事拠点であったため、曹操は当然関羽がそこに触れることを許さず、于禁に七つの軍を率いて敵と戦うよう命じた。この戦いでは、于禁も不運だった。彼の軍事的才能からすると、関羽に簡単に負けるはずはなかった。しかし、その時は大雨が降り、地面は数フィートの高さになっていたため、于禁の七つの軍隊が普通の地面に留まることは不可能だった。彼らは高台に移動せざるを得なかった。この移動中に、多くの荷物が失われ、外部からの補給が追いつかなくなることは間違いありません。最も重要なことは、関羽の軍隊が洪水をまったく恐れていなかったことです。 于禁の七軍は北からやって来たが、大きな船はなかった。しかし、関羽自身は海軍を持ち、大きな船を持っていた。水位は数フィート高くなっており、金にとっては不利であったが、関羽にとっては朗報であった。結局、関羽は軍艦から曹の軍を攻撃するよう部隊に命じ、曹の軍を完全に打ち破った。曹操軍は外に援軍がなく、内部では関羽の猛攻撃を受けていたため、抵抗できず、ついに降伏せざるを得ませんでした。しかし、最も不幸なことは于禁に起こりました。彼らは全員降伏しましたが、龐徳は死ぬまで降伏を拒否しました。二人を比較すると、于禁は非常に耐え難いものに見えたので、曹操でさえ次のようにため息をつきました。 『三国志演義』:太祖はこれを聞いて、長い間ため息をついて言った。「私は彼と30年知り合いだが、なぜ彼は龐徳ほど危険や困難に対処できないのか?」 于禁は本当に不運だった。戦い自体は彼のせいではなかった。関羽の味方をしたのは神だった。その時代、降伏はそれほど耐え難いことではなかった。関羽は曹操に降伏したのではないだろうか?しかし、人々は比較を恐れている。決して降伏しないと誓った龐徳と比べて、于禁は非常に目立っていた。だから曹丕は于禁を嫌っていた。最終的に、于禁が東呉によって追い返されたとき、曹丕は表面上は于禁を慰めながら、密かに于禁が関羽に降伏する場面を利用して于禁を挑発し、最終的に于禁を恥と怒りで死に至らしめた。おそらく羅貫中氏も于禁の結末は悲劇的で変えられないと感じたのでしょう。そのため、小説の中での于禁の結末は、実は正史の結末と似ています。 張郃はもともと袁紹の将軍であったが、官渡の戦いで曹操に降伏した。曹操は張郃が降伏したことを聞くと、張郃を韓信と直接比較し、張郃を将軍に任命し、杜亭侯の爵位を与えた。張郃の活躍は曹操の期待を裏切らなかった。張郃は曹操に随伴して何度も戦い、多くの軍事的功績を挙げた。夏侯淵の死後、張郃は漢中の曹操軍を安定させ、総敗北を免れた。そこで曹操は張郃に臨時太守の権限を与え、漢中の全軍を指揮した。 時が経つにつれ、多くの名将が次々と亡くなり、張郃は天下一の名将となり、諸葛亮も彼を警戒するようになった。諸葛亮の第一次北伐の際、馬素に街亭を守らせ、魏軍の援軍を阻止させた。その結果、張郃の軍が到着すると、馬素はすぐに張郃を打ち破り、諸葛亮の背後を脅かした。結局、諸葛亮はこれまでの功績を捨てて撤退せざるを得なかったが、その後の戦いでは張郃も何度も蜀軍と戦い、蜀軍を悩ませた名将となった。 太和5年(231年)、諸葛亮は第4次北伐を開始した。李厳が穀物を輸送できなかったため、蜀軍は食糧が尽きて撤退を余儀なくされた。諸葛亮が退却するのを見て、司馬懿は張郃に追撃するよう促したが、張郃は長年の軍事経験から、追撃するのは適切ではないと考えた。残念ながら、司馬懿は張郃を強引に追い詰め、木門路で彼を死なせてしまった。 「衛略」:梁の軍が撤退すると、司馬宣王は賀を派遣して追撃させた。賀は言った。「軍法によれば、城を包囲するときは必ず逃げ道を残しておかなければならない。撤退する軍を追撃してはならない。」宣王は聞き入れなかった。彼には前進するしか選択肢がなかった。蜀軍は高地を利用して待ち伏せし、弓や弩を思いのままに放ち、矢が何の太腿に命中した。 張郃は戦場で死んだ将軍です。この死に方は羅貫中氏の価値観に合っています。ですから、物語の中では、張郃は結局木門路で亡くなります。しかし、張郃が敵を追った理由は、正史とは少し異なります。 正史では、司馬懿は張郃に諸葛亮を追い詰めるよう強制したが、『三国志演義』では張郃が率先して諸葛亮を追い詰めたとされている。司馬懿は張郃を思いとどまらせようとしたが、張郃は言うことを聞かず、結局待ち伏せされて殺された。小説では、羅管中氏が意図的に司馬懿を高めたことは明らかです。もともと諸葛亮の最初の数回の北伐では、曹魏側の総司令官は曹真でしたが、小説では司馬懿になりました。羅管中氏は司馬懿を高める方法を使って諸葛亮の最高の知恵を強調したかったのです。張郃は生前は英雄だったのに、小説では忠告を聞かなかったために敗北し、殺されてしまったのだから残念だ。 正史では、徐晃は実は五大将軍の中で最も地位が低いのですが、『三国志演義』では徐晃の活躍は非常に目立っています。小説の中で、徐晃は一流の武術の達人として描かれています。彼はかつて一流の達人である徐褚と50ラウンドで引き分けたことがあります。彼は非常に強いです。後期には、作者は徐晃が関羽を一撃で倒す場面まで作りました。これは徐晃に大きな面目を与えたと言えます。しかし、徐晃の死の問題になると、羅貫中氏は相変わらず自分の価値観を貫き、徐晃が戦場で死ぬという結末を演出した。 正史では徐晃の死因については何も説明されていないが、これは徐晃が自然死したことを意味し、比較的良い死であったと言える。しかし、『三国志演義』では、徐晃が上雁で孟達を攻撃していたとき、城壁に近づきすぎたため、孟達の矢が額を射抜かれ、陣地に戻った後に死亡した。正直に言うと、徐晃の結末は小説での彼の役割と完全に矛盾しています。なぜなら、小説では徐晃と張郃はどちらも命を大切にする人であり、一般的に危険を冒さないからです。しかし、徐晃の最後の結末は、城壁に近づきすぎて矢に射殺されたことでした。これは彼のスタイルとはまったく思えません。私たちに言えることは、羅貫中氏が自分の価値観を満たすために『徐晃』に無理やりシーンを追加し、結局『徐晃』を死ぬほど書き上げたということだけです。 |
>>: 楚雄一雨祈雨祭はいつ行われ、どのような特徴がありますか?
推薦する
燕芝山はどこですか?匈奴らはなぜ燕芝山を失った後、悲しみのあまり叫んだのか?
匈奴はなぜ燕子山を失った後、激しく泣いたのでしょうか? Interesting History の編...
張燕の「阮朗帰・北巡回回想」:曲調が美しい「リズムの流れ」を形作る
張炎(1248年 - 1320年頃)は、字を叔霞といい、玉田、楽暁翁とも呼ばれた。彼は臨安(現在の浙...
古代のドラゴンには何人の息子がいましたか?
古代の龍には数人の息子がいました。龍は自分の姿を形成する過程で、さまざまな奇妙な動物の像を集めました...
『晋書』巻75の伝記45の原文は何ですか?
◎王占(息子 程成、息子 舒淑、息子 譚志易、譚志、息子 開宇、郭宝、陳宇、息子 遂成祖、息子 焦元...
漢王朝の官吏が引退するにはどのような条件を満たす必要がありましたか?退職後はどのような給付金が受け取れますか?
古代の定年制度は春秋戦国時代から存在していました。しかし、当時の社会はあまりにも混乱しており、就任し...
王師父の「十二月告別歌」はどのような感情を表現しているのでしょうか?
元代の王師父の『姚十二月送別歌』にはどんな感情が表現されているか知りたいですか?実はこの詩は、女主人...
岑申の古詩「裴将軍邸の笛の歌」の本来の意味を鑑賞する
古詩「裴将軍邸の笛の歌」時代: 唐代著者: セン・シェン遼東省では9月になると葦の葉が落ち、遼東省の...
李逵がいつも想っている「姉さん」龐秋霞は原作には存在しない。
説明する必要はないと思います。1998年版の『水滸伝』は、ネットユーザーからも史上最高のバージョンと...
唐の玄宗皇帝の娘、宜春公主の紹介。宜春公主の夫は誰だったのでしょうか?
宜春公主(?-?)、唐の玄宗皇帝李龍基の娘。母親は不明。王女は若くして亡くなりました。関連歴史資料新...
三峡の神秘的な八卦陣の謎:八卦陣はどこにあるのか?
重慶から船に乗って揚子江に沿って下流へ向かいます。三峡への航海中は、数え切れないほどの素晴らしい景色...
張九玲の「帰燕」:この詩は作者の「鳥に対する風刺」である。
張九齢(673-740)は、雅号は子首、通称は伯武で、韶州曲江(現在の広東省韶関市)の出身である。唐...
趙匡胤が亡くなったとき、なぜ彼は息子を皇帝にさせなかったのですか?
宋の太祖皇帝趙匡胤には何人の息子がいましたか?なぜ趙匡胤は息子に王位を譲らなかったのですか?趙匡...
隋の文帝と煬帝の科挙制度がなぜ重要な革新だったのでしょうか?
魏晋南北朝時代、全国に「九階制」が浸透していた。世界の学者は9つの階級に分けられ、官職が与えられてい...
西遊記で朱子王はなぜ孫悟空に王位を譲ったのですか?
『西遊記』の朱子王は、テレビシリーズでは非常に愛情深い王として描かれています。本日はInterest...
『紅楼夢』で金容はなぜ賈家で不当な扱いを受けたのですか?黄おばあちゃんはなぜ口論する相手を探しに行かなかったのですか?
『紅楼夢』を読んだ人のほとんどは、この物語に黄おばあちゃんが登場したことを覚えていないかもしれません...