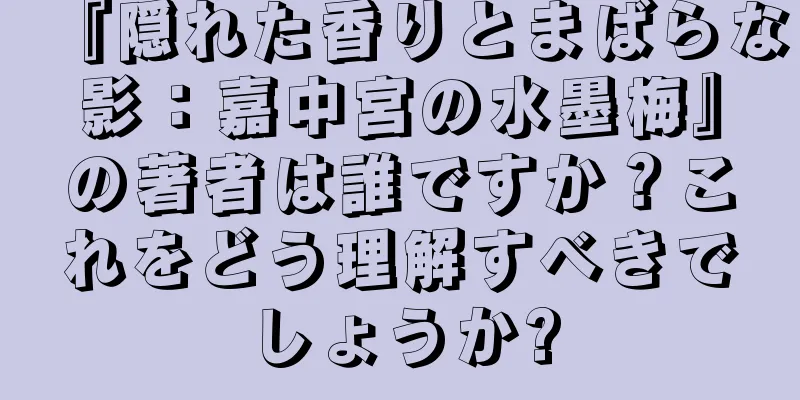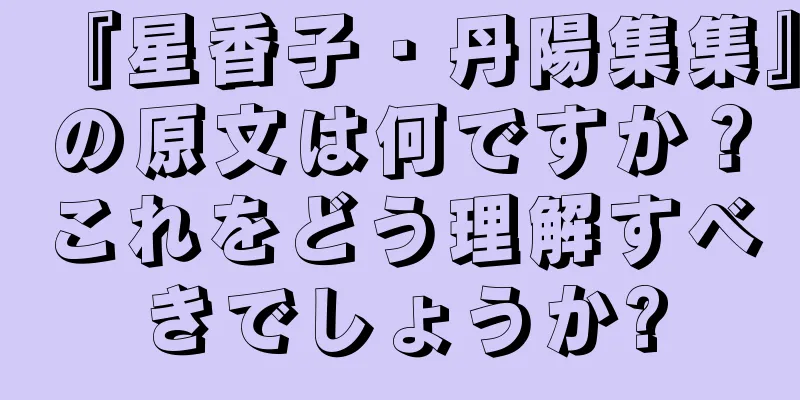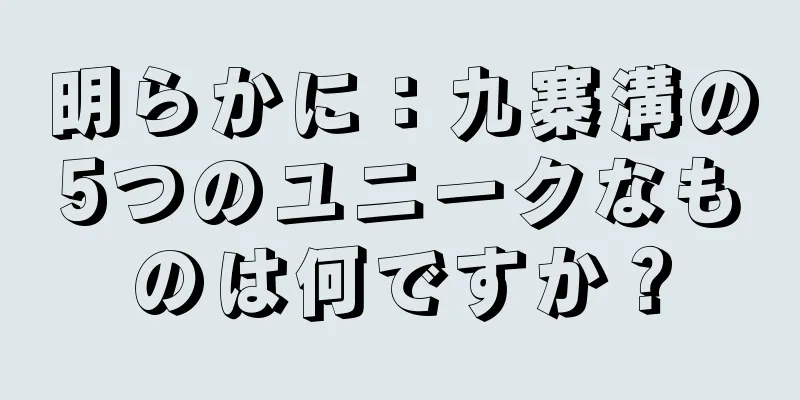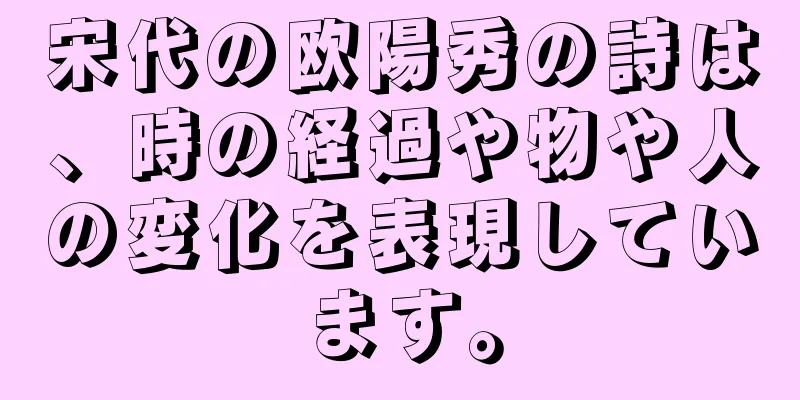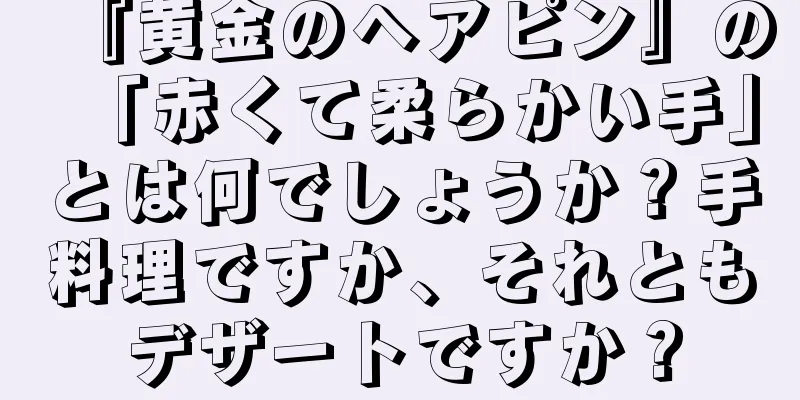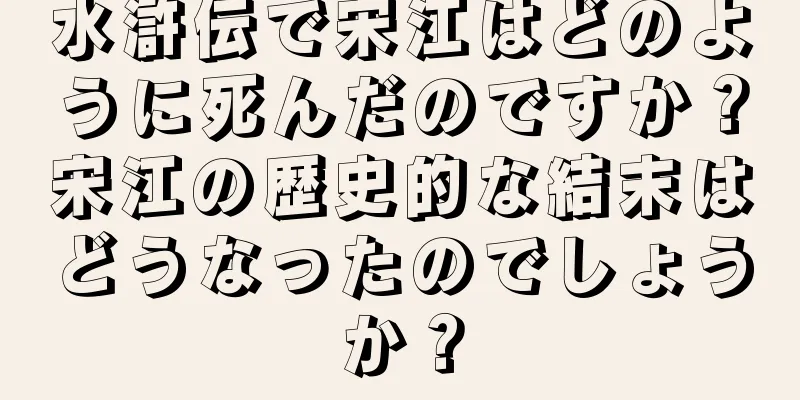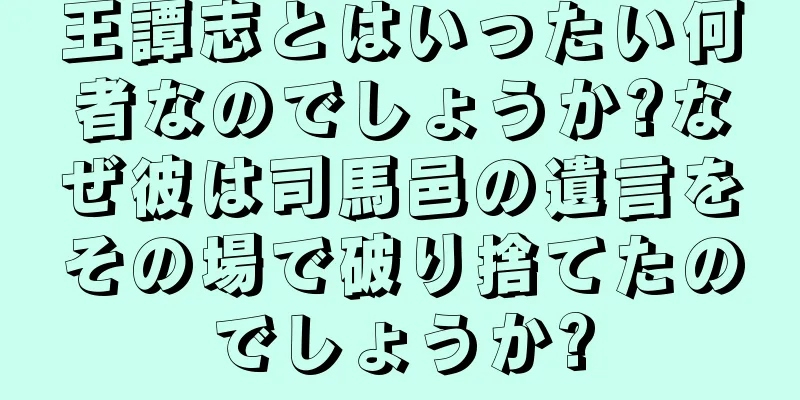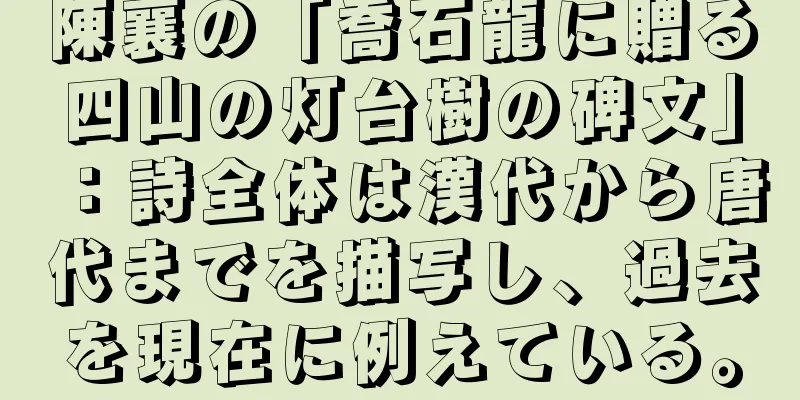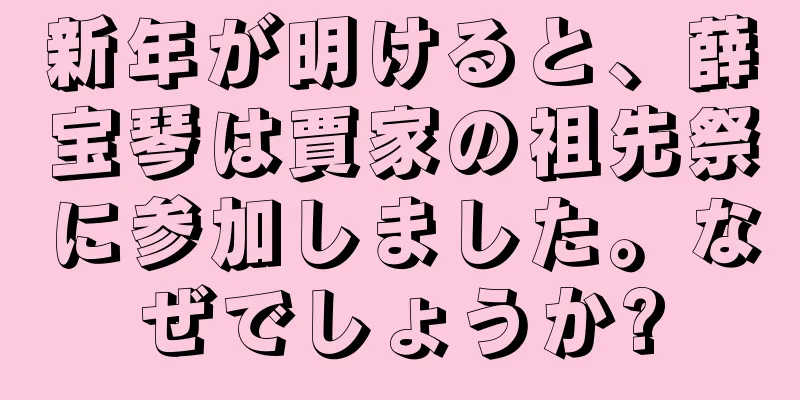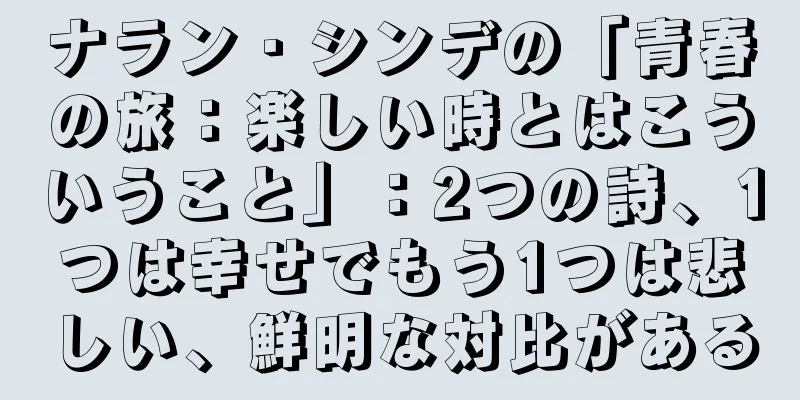曹操が3人の娘を漢の献帝と結婚させた理由は何ですか?
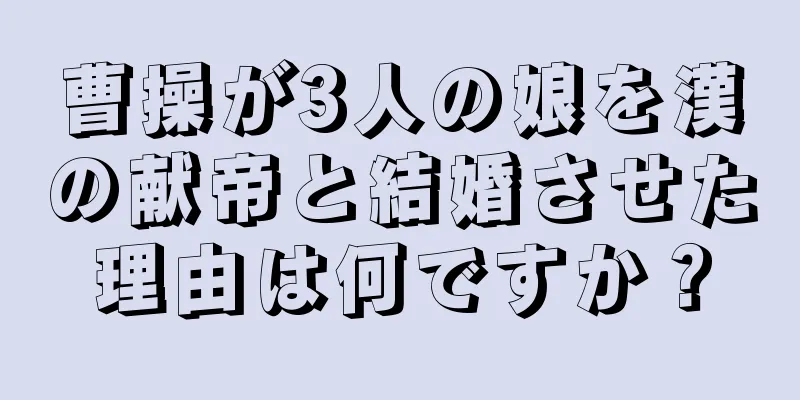
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、曹操が漢の献帝を支配し、娘を一人だけ送ったのに、なぜ3人の娘と結婚したのかを詳しく紹介します。見てみましょう! 曹操が3人の娘を漢の献帝に嫁がせたという記述は、主に『後漢書』に記されている。 『後漢書』:建安18年、曹操は3人の娘、仙、桀、華を妻として迎え、絹5万枚と黒紫で婚約させた。妹の娘は大きくなるまで国に留まることにした。 19歳で彼女は高貴な女性として崇拝されました。皇后宋傅が殺害されると、翌年李潔が皇后に即位した。 曹操が娘を漢の献帝に嫁がせた当時、皇后宋福はまだ権力を握っており、曹操暗殺のことは未だ漏れていなかったことがわかります。したがって、曹操が娘を妃にするために宮殿に嫁がせたという主張は、実際には成り立たない。傅皇后が大きな過ちを犯さない限り、彼女を王妃の地位から排除することは不可能だろう。 漢の献帝を監視し統制することに関して言えば、曹操は長年にわたりこれをすべて行ってきたのだから、本当に監視したかったのなら、一度に3人の娘を送り込む必要などなかったはずだ。それに、古代では女の子は社交的だったし、もし本当に娘たちに漢の献帝を監視させれば、得るものよりも失うものの方が多いかもしれないし、自分の情報が漢の献帝に奪われるかもしれない。曹桀は結局漢の献帝に反抗して献帝側に立ったのではないですか? そこで曹操は別の理由で3人の娘をそこに送りました。 1. 曹操は漢の献帝に友情を示した 曹操が娘を漢の献帝に嫁がせる前に、漢の献帝は曹操に大きな贈り物を与えた。まず、曹操に「名を名乗らずに敬意を表し、剣と靴を履いて宮殿に入る」ことを許した。その後、曹操に魏公の称号を与え、九つの贈り物を授け、魏を建国した。この作戦で曹操は気分がすっきりしてとても幸せになりました。もちろん曹操は恩返しとして、自分の3人の娘を漢の献帝に嫁がせることにしました。 曹操の行動は、本質的には、漢の献帝に報いる善意の行為だった! 彼が言いたかったのは、漢の献帝に慌てるなということだった。私は権力が欲しいが、あなたの命を奪うつもりはない。私の3人の娘をあなたに嫁がせたし、あなたの安全は絶対に保証する。私、曹操がどんなに残酷でも、娘たちを見捨てたりはしない。 2.曹操は天下の民衆に善意を示した 曹操は当初、漢王朝を支えることを使命としていましたが、権力が増し、魏公に任命されるにつれて、世界中の人々は曹操についてもっと考えなければなりませんでした。いったい何をしたいのでしょうか?もちろん、曹操は非常に賢く、人々が何を考えているかを知っていたに違いありません。曹操は権力がありましたが、民意に逆らうことはできず、民を黙らせるために自分の3人の娘を漢の献帝に嫁がせることを選びました。 いいかい、曹操は皇帝にたくさんの娘を嫁がせた。私は皇帝の義父だ。公爵や王様になるのは普通のことじゃないのか? 皇帝と私は一つの家族だ。想像力を働かせすぎないでくれ! 曹操が皇帝にたくさんの娘を嫁がせたということは、皇帝に危害を加えるつもりはないということだ。娘が未亡人になることを望む人はいないだろう? せいぜい、曹操が欲しがっているのは権力だけだ。それで何が悪い? もちろん、曹操のこの行動は庶民を黙らせるだけだった。高位のエリートたちは、曹操が漢王朝を奪取しようとする野望をすでに見抜いていた。しかし、曹操は恐れていなかった。なぜなら、曹操が3人の娘を漢の献帝にすぐに嫁がせたのは、皆に逃げ道を残すためだったからだ。 3. 娘にもっと子供を産ませる 曹操が漢の献帝に次々と娘を嫁がせたのは、実は娘たちの妊娠の可能性を高め、曹家と劉家の血を継がせるためだった。この血こそが曹操が自らに残した逃げ道だったのだ! 曹操は、漢王朝を簒奪する道が必ず波乱に満ちたものになることを知っていた。外には劉備、孫権、張魯、劉璋といった敵対勢力がおり、内部にも漢王朝に忠誠を誓う者が多かった。表面上は誰もが曹操に忠誠を誓っているように見えますが、人の心は予測しにくいものです。曹操と共に戦った良き友人の荀彧は、曹操が九つの賜物を与えられ、魏公と呼ばれたことに不満を抱いたのではないでしょうか。荀彧のような人はたくさんいるので、曹操は最終的に漢王朝を奪取することに本当に成功できるかどうか確信が持てなかったのです。 曹操の考えはおそらくこれだった。自分の娘に漢の献帝の血を引く子を産ませ、曹操が皇帝の正当な義父となり、物事をより正当に行えるようにする、というものだ。さらに、生まれた子供は曹家と劉家の血を引く者となるため、両家間の憎悪が軽減され、殺人も最小限に抑えられるだろう。 もし曹一族が最終的に勝利したとしても、曹操の三人の娘が周囲にいたため、曹一族が漢の献帝を殺すことはあり得なかっただろう。事実は漢の献帝が良い最後を迎えたことを証明している。 そして、もし漢の献帝が最終的に勝利して権力を取り戻したとしても、彼は子供と妻のために曹一族を殺すことはないだろう! この時点で、多くの人は、漢の献帝が権力を奪還した後、曹一族を必ず虐殺するだろうと考えるでしょう。実は、この考えは間違っています。漢の献帝は常に奥宮にいましたが、政治の達人でもありました。曹一族が殺されれば、必然的に別の勢力が台頭し、漢の献帝はそれらに対処する方法を見つけなければなりません。しかし、曹丕のような曹家の当主だけが死刑や投獄の判決を受ければ、漢の献帝と曹操の娘の間に生まれた息子の存在により、曹家が漢の献帝に対して大規模に反乱を起こすことはないだろう。なぜなら、この若主も曹家の血筋だからである。漢の献帝はやがて老齢で亡くなり、若主が権力を握ったとき、曹家の利益は依然として保証されるだろう。 したがって、曹操の娘と漢の献帝の間に男子が生まれれば、双方にとって保証となる。曹操が3人の娘を漢の献帝に嫁がせたのはこのためであった。もしこれらの娘たちが息子を産んでいなかったら、曹操はさらに多くの娘を漢の献帝と結婚させていたでしょう。では、曹操が漢の献帝に6人か7人の娘を嫁がせた理由を改めて分析する必要があるでしょう... |
推薦する
宋代の詩「昭君元・告別」を鑑賞します。この詩はどのような場面を描いていますか?
昭君元·告別[宋代]蘇軾、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょう!...
白古瑶族の独特な葬儀の習慣は何ですか? 「牛を切る」理由
白姑ヤオ族はヤオ族の一派で、南単県の八尾ヤオ郷と立湖ヤオ郷に住んでいます。ここの人々は素朴で誠実であ...
『王九が私に会う幸せな春の日』の著者は誰ですか?どのように評価したらいいのでしょうか?
王九と過ごす幸せな春の日々孟浩然(唐代) 2月には湖は澄み渡り、どの家でも鳥のさえずりが聞こえます。...
『紅楼夢』で、役人の仲人が栄果屋敷にプロポーズに来たのはいつですか?
『紅楼夢』は古代中国の四大傑作の一つで、章立ての長編小説です。 Interesting Histor...
善良な大臣、殷初に関する中国の寓話。この寓話はどのような教訓を明らかにしているでしょうか。
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting History の編集者が、善良な大...
『紅楼夢』で南安公主が賈邸に到着したとき、賈祖母はどのように反応しましたか?
南安妃は『紅楼夢』の登場人物ですが、あまり登場しません。今日は、Interesting Histor...
宋代の呉文英の詩の一つ『清春宮・秋情』をどのように鑑賞すればよいでしょうか?
清春宮・秋の情[宋代]呉文英、次の興味深い歴史編集者があなたに詳細な紹介を持ってきます、見てみましょ...
『紅楼夢』の賈丹春はどんなキャラクターですか?利点は何ですか?
「紅楼夢」のコピーは人生の夢です。 Interesting History の編集者は、以下のテキス...
『紅楼夢』で賈舍が爵位を継承した裏にはどんな真実が隠されているのか?
賈祖母は、石老夫人としても知られ、賈家で最も権力のある人物です。本日は、Interesting Hi...
明楊吉州(吉師)は『鍼灸学論集』第3巻「白内障の歌全文」を著した。
『鍼灸学事典』とも呼ばれる『鍼灸事典』全10巻。明代の楊其左によって書かれ、万暦29年(1601年)...
水族の人々は客人に対してどのような習慣を持っていますか?
素朴で誠実なシュイ族には、おもてなしの素晴らしい伝統があります。彼らは、親戚や友人、さらには一度も会...
『紅楼夢』に登場する12個の金の簪はすべて花の化身です。賈丹春は何の花を表していますか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
崔図の詩「武山寺」全文鑑賞
武山寺時代: 唐代 著者: 崔図二重の眉毛はしかめっ面のようで、故郷の春を悲しく思わせるはずです。国...
科挙制度への盲目的批判の時代を終わらせる:科挙制度の価値と意義
科挙制度の歴史的役割プリンストン大学教授:科挙制度は多くの人材を育成してきたこの制度は多くの人材を育...
帰古子:この古典にある陰伏の七つの技法と聖神法の五つの龍の完全なテキストと翻訳
「魏愚子」は「毗と何の計略」としても知られています。これは、ギグジ氏の発言をもとに、後代の弟子たちが...