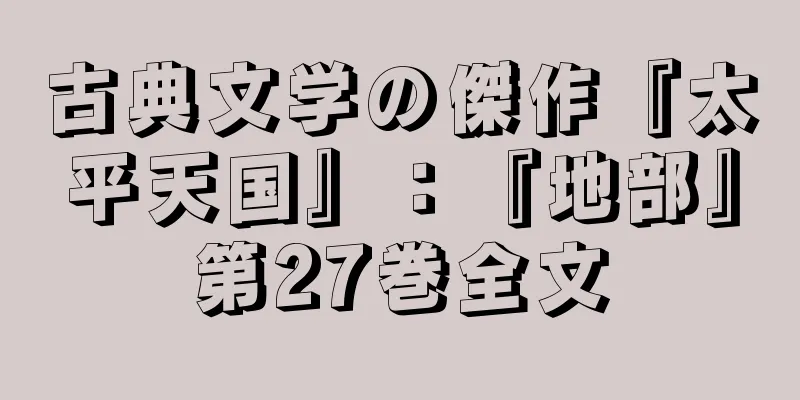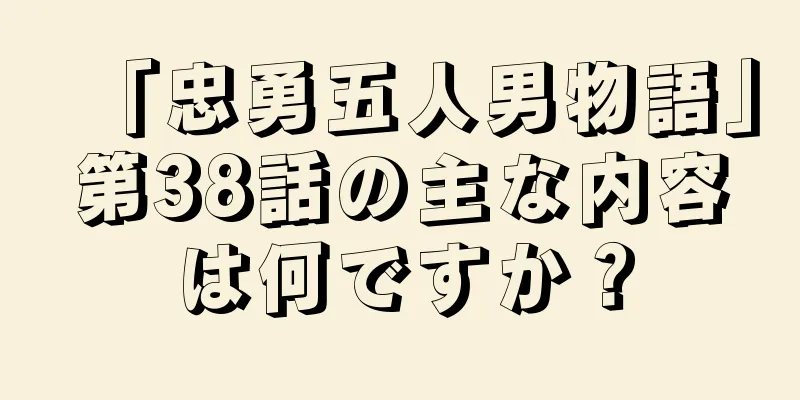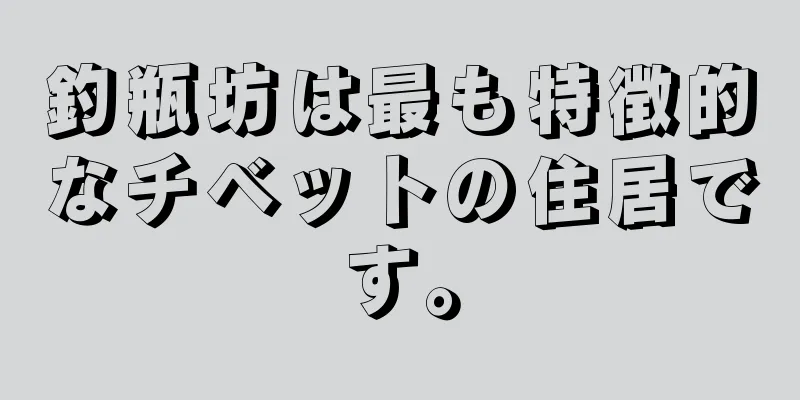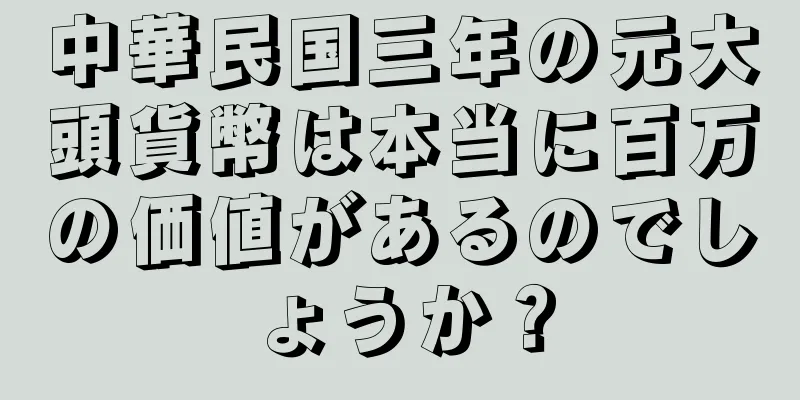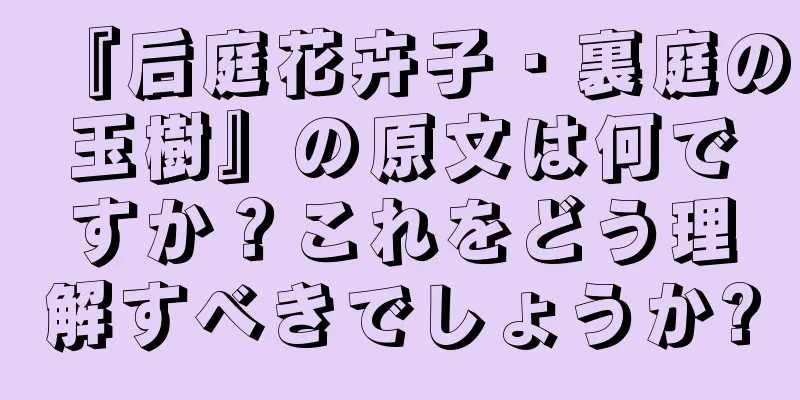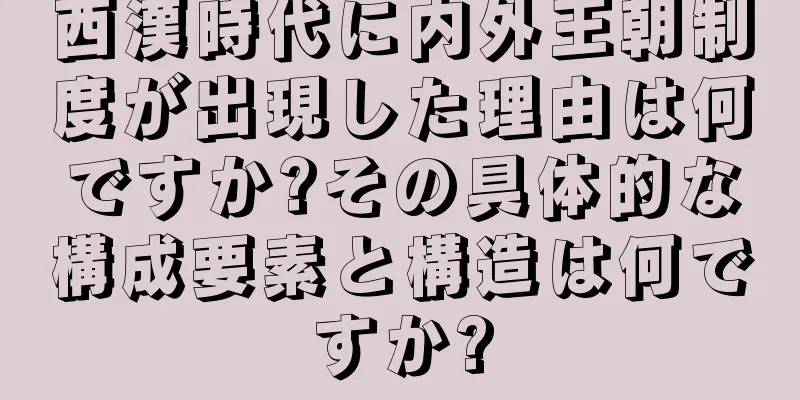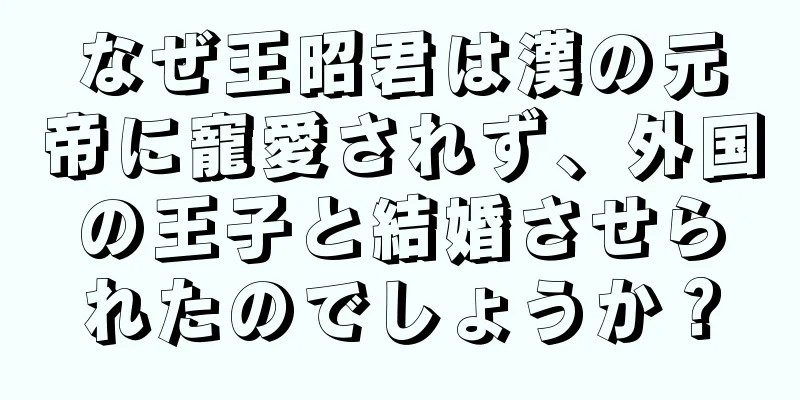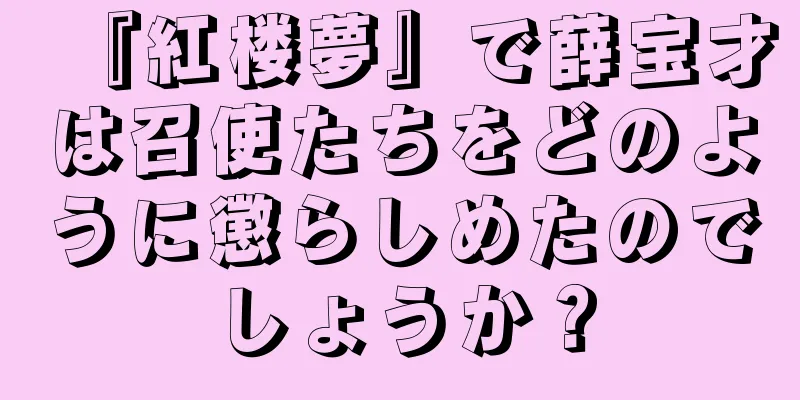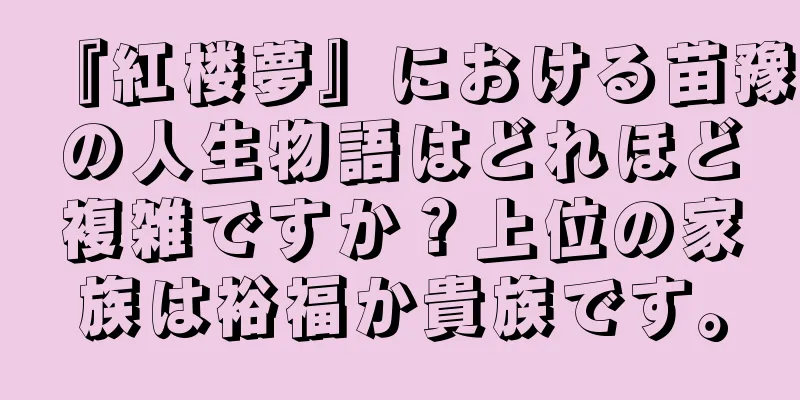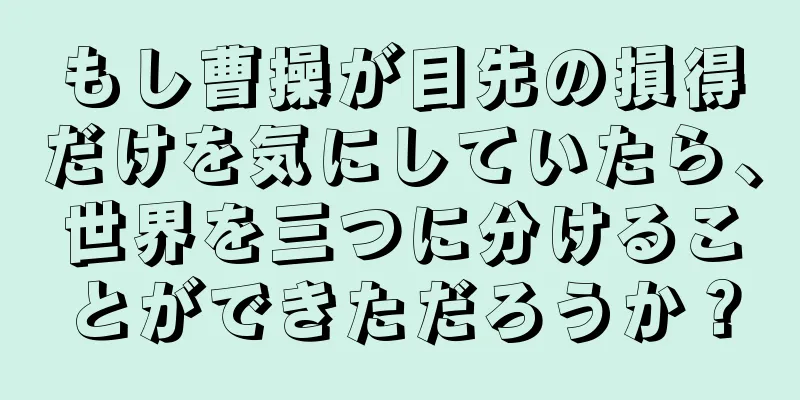なぜ関羽は額に矢を撃たれても生き残ったのに、張郃は膝に矢を撃たれて死んだのでしょうか?
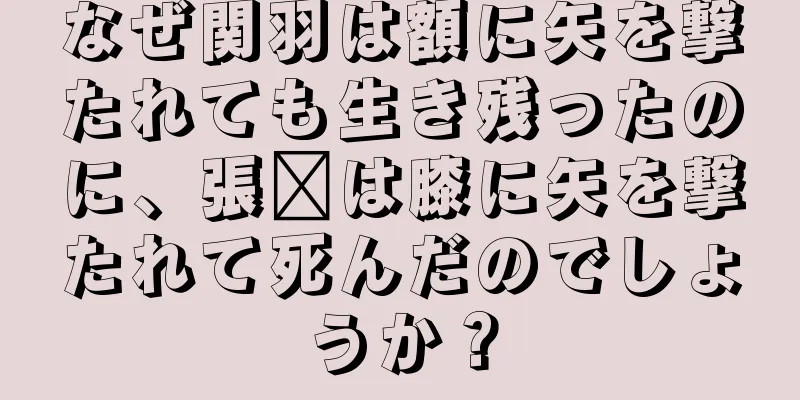
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、関羽が額を撃たれても死ななかったのに、張郃が膝を撃たれて死んだ理由について詳しく紹介します。見てみましょう! 一般的に考えれば、頭部は人体の中でも非常に脆弱な部分であり、頭部が負傷すると死に至る可能性が高いといえます。膝も体の重要な部分ですが、膝を負傷しても実際には命にかかわるわけではありません。例えば、事故により足を切断する人も多くいますが、最終的には生き残ります。では、なぜ関羽と張郃の状況は大きく異なっていたのでしょうか? 関羽は額を撃たれても生き残ったのに、張郃は膝を撃たれて死んだのはなぜでしょうか? 実は、この驚くべき効果には主に 2 つの理由があります。 1. 異なる保護 関羽は龐徳との戦いで額を撃たれた。しかし、古代人は実は頭部をかなりしっかり守っていました。戦場は混沌としていて、矢が飛び交っていました。矢に撃たれて死ぬのを避けるために、ほとんどの古代の将軍はヘルメットをかぶっていましたが、これは弓矢の威力を大幅に弱めるものでした。実際、現代の戦場でも、多くの軍隊はヘルメットの開発を依然として非常に重視しています。ヘルメットは兵士の命を大きく救うことができるからです。 『三国志演義』:徳昌は言った。「私は国の恩恵を受けている。そのために死ぬのは私の義務だ。私は自分で羽を殺したい。今年中に羽を殺さなければ、羽は私を殺すだろう。」その後、彼は自ら羽と戦い、羽の額を撃った。 『三国志演義』の記録によると、関羽との戦いで龐徳は関羽の額に矢を放った。しかし、関羽のその後の行動から判断すると、龐徳は関羽の兜に当たっただけで、矢の衝撃は兜に遮られ、関羽の頭部を傷つけなかった可能性が高い。そのため、外部から見ると関羽が撃たれたように見えましたが、実際には関羽は負傷していませんでした。 関羽とは異なり、張郃の負傷部分は十分に保護されていませんでした。古代の技術と生産性の限界により、すべての兵士が戦闘時に鎧を着用できるわけではありませんでした。一般的に、上級将軍と特別部隊のみが鎧を着用していました。さらに、これらの鎧は、頭部、胸部、腹部など、人体の重要な部分のみを保護し、人体の下肢に対しては、鎧の保護強度はそれほど強くありません。 古代の西洋世界では、全身を覆う全身鎧があり、矢による負傷は少なくなっていました。しかし、これは人の柔軟性を低下させることにもなりました。古代中国の王朝が直面した敵のほとんどは、大規模な鎧を装備する能力がなかったため、古代中国の鎧のほとんどは完全に覆われておらず、主に上半身を保護していました。 この場合、矢が張郃の膝に当たった理由は、防御力が弱かったためだと理解しやすいです。論理的に言えば、たとえ膝を撃たれても、適切な処置を受けていれば死ぬことはありません。しかし、当時曹操軍は待ち伏せされており、張郃は適切な助けを得ることができず、結局矢傷で亡くなりました。 『三国志』:諸葛亮は岐山に戻り、何に将軍を率いて西の洛陽へ向かうよう命じた。梁は岐山を守るために戻った。彼は木門まで追いかけ、梁の軍と戦った。彼は飛んできた矢に右膝を撃たれて死んだ。彼は諡号を荘侯と名付けられた。 2. さまざまな弓と矢 防御力の違いに加えて、関羽と張郃を襲った矢も大きく異なっている可能性があります。 ご存知のように、諸葛亮は発明が得意です。北伐の指揮中に、多くの先進的な武器を発明・作成し、曹魏に多大な損失をもたらしました。ここで最も強力な武器の1つは連射クロスボウです! これまで、クロスボウは強力な武器でしたが、連続して発射することはできませんでした。 しかし、諸葛亮によって改良されたクロスボウは実際に連続して発射することができ、戦場で大きな貢献をしました。諸葛亮は弩を改良できたので、当然矢も改良したはずです。ですから、張郃を撃った矢は、関羽を撃った矢とは全く違うものだった可能性が高いのです。 『三国志』:梁は創意工夫に長けていた。連射式弩や木製の牛馬はすべて彼の考案だった。 その時、張郃は諸葛亮に待ち伏せされ、膝を矢で撃たれました。通常であれば、出血が間に合う限り、張郃は戦場からの撤退を主張できたはずですが、結局張郃はこれが原因で亡くなりました。おそらく、その時は出血が止まらなかったのでしょう!諸葛亮は出血専用の弓矢を発明したのかもしれません。一度人体に矢じりを刺し、一度引き抜いたら、単なる包帯では役に立たなくなります。結局、張郃は過度の失血で亡くなったのかもしれません! |
<<: モンゴルの習慣 モンゴルのアオバオの習慣は何ですか?
>>: モンゴルのゴールデンファミリーとは何ですか?その背後にある物語は何ですか?
推薦する
この人は食べるだけの力はあるのに、哪吒を怖がらせてしまったのか?この人は結局どうなったのでしょうか?
この人は食べるだけの力があったのに、哪吒を怖がらせてしまった?結局この人はどうなったの?次の興味深い...
前趙の昭文帝劉瑶には何人の妻がいましたか?劉瑶の妻は誰でしたか?
前趙の昭文帝劉瑶(?-329年)は匈奴で、号は永明。前漢の光文帝劉淵の養子で、前趙最後の皇帝。筆記に...
トゥチャ族の文化 トゥチャ族の娯楽文化とは何ですか?
トゥチャ族の人々は、農業で忙しくないときは、スポーツやレクリエーション活動にも参加します。これらの活...
「小五英雄」第42章:江沢昌が八宝巷への道を探検し、霍珍老人が自宅で秘密を明かす
『五人の勇士』は、古典小説『三人の勇士と五人の勇士』の続編の一つです。正式名称は『忠勇五人の勇士の物...
歴史上の実際のオボイはどのような人物だったのでしょうか?なぜ多くの皇帝が彼に対して異なる意見を持っていたのでしょうか?
オボイは清朝の宮廷劇によく登場する人物で、武士出身で、性格が乱暴で、力が強くて制御が難しく、政府を牛...
『紅楼夢』で、平児はなぜ賈玉村を決して餓死することのない野蛮な野郎だと呪ったのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
「洞庭湖を眺め張首相に贈る」ではどのような芸術技法が使われているのでしょうか?
孟浩然は「洞庭湖を見て張宰相に贈る」という詩の中でどのような芸術技法を使ったのでしょうか。これは多く...
李時珍は『本草綱目』を著した後、40年間に3回改訂しました。
数十年にわたる医療活動と古典医学書の読書の中で、李時珍は古代の本草書に多くの誤りがあることを発見し、...
覚醒世界物語第12章:李観茶が苦情を収集し、朱推観が考えを変えて法律を施行する
『婚姻天下開闢』は、明代末期から清代初期にかけて習周生が書いた長編社会小説である。この小説は、二人の...
『紅楼夢』で賈家には何人の支援者がいるのでしょうか?結局なぜ家が襲撃されたのですか?
『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...
「彭公安」第153話:英雄が夜に府城寺を訪れ、3人の英雄が小義村で騒動を起こす
『彭公安』は、譚孟道士が書いた清代末期の長編事件小説である。 「彭氏」とは、清朝の康熙帝の治世中の誠...
史書 歌集 第二十三巻 第十三章 天文学 1 原文
天について論じる学派は三つあり、一つは玄野、二つ目が蓋天、三つ目が渾天である。しかし、古典には天の本...
李游の『漁夫 春風に浮かぶ船』は、災難を避けたいという作者の願いと、世間から逃れたいという思いを表現している。
李郁は五代十国時代の南唐最後の君主であり、唐の元宗皇帝李靖の6番目の息子でした。李毓は皇帝の座に就く...
『西遊記』では、二郎神が孫悟空を倒したことはないのに、なぜ孫悟空は二郎神に屈したのでしょうか?
周知のように、「西遊記」の孫悟空は傲慢で乱暴な性格で、横柄な振る舞いを好みます。それでは、二郎神が孫...
古代の人々は夏に厄介な蚊にどう対処したのでしょうか?
古代の人々は、夏に悩まされる蚊とどのように対処したのでしょうか。これは多くの読者が気になる疑問です。...