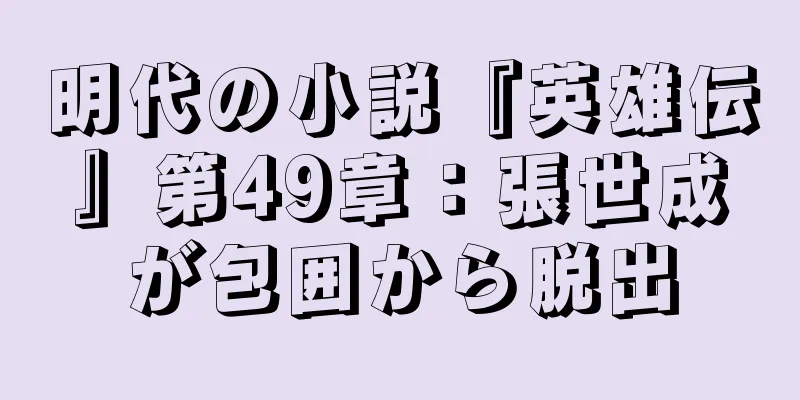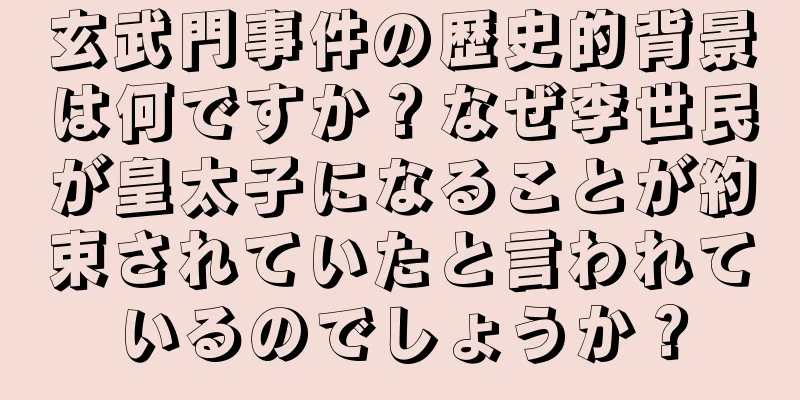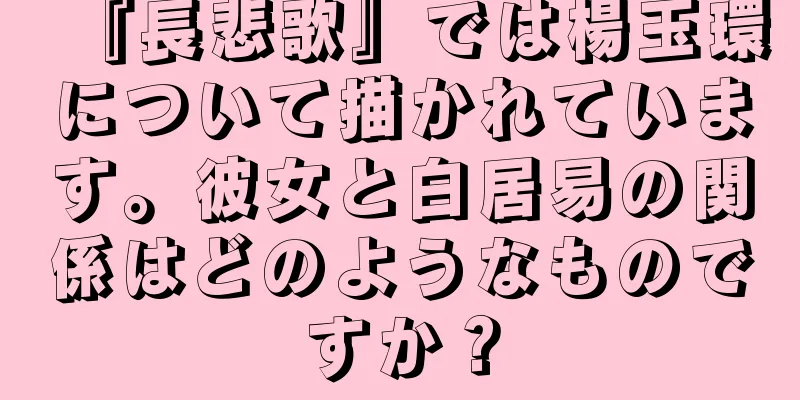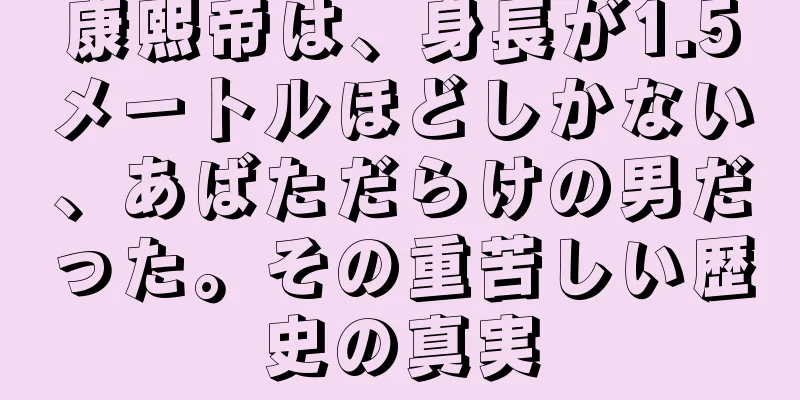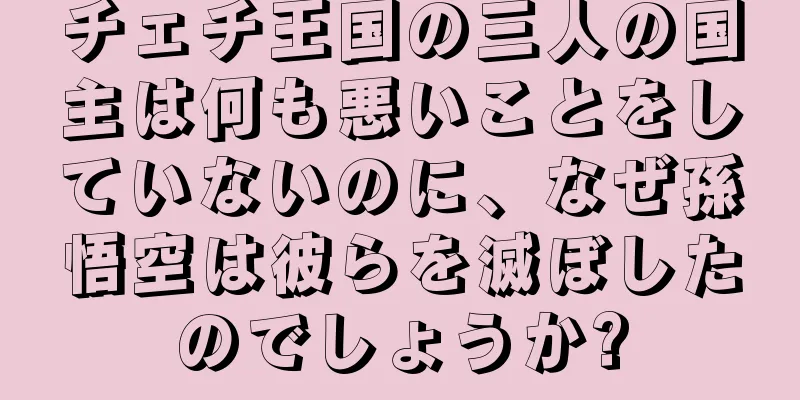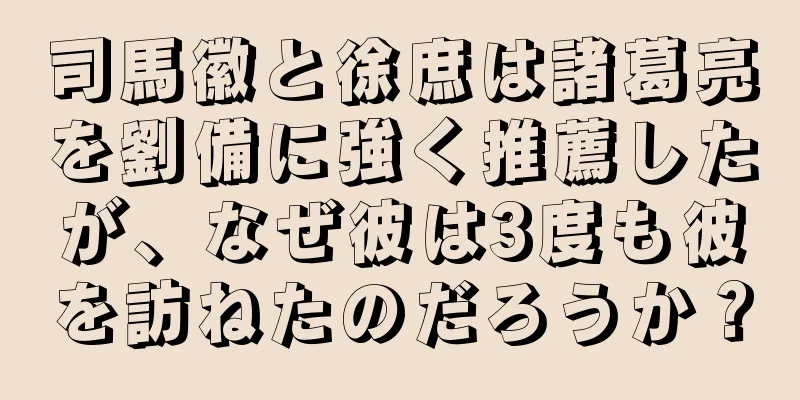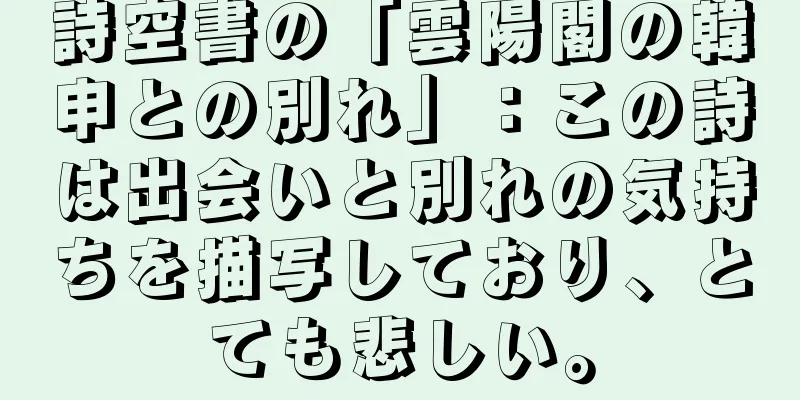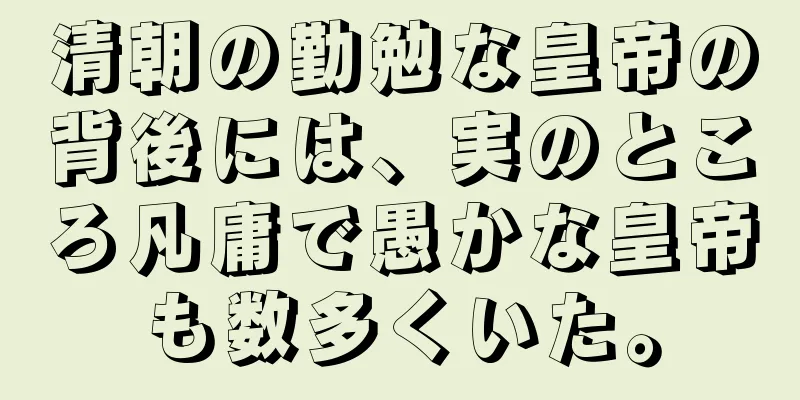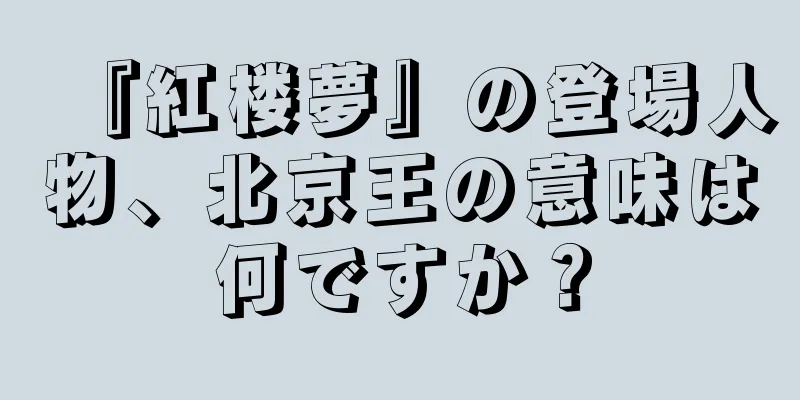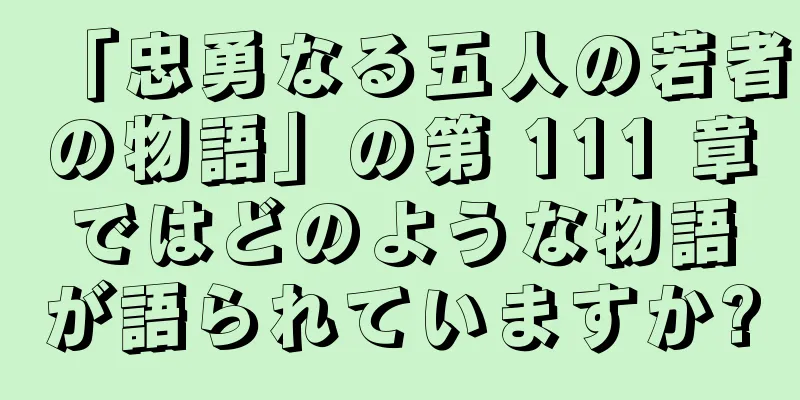チベットの習慣 チベットの葬儀の習慣の特徴は何ですか?
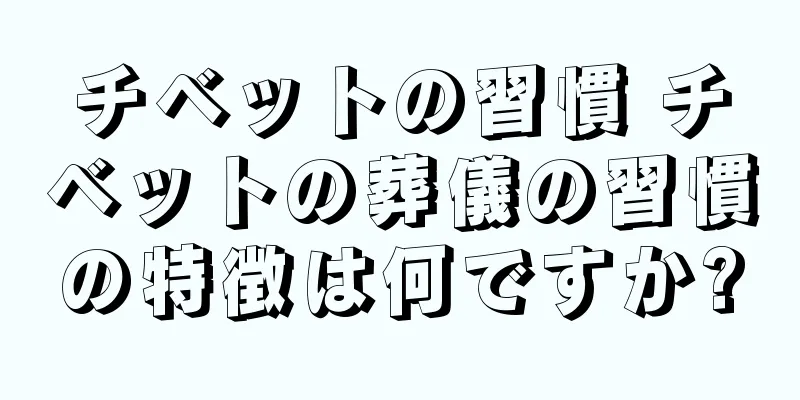
|
チベットの葬儀の習慣は非常に特殊で、仏塔葬、火葬、天葬、土葬、水葬の5つの種類に分かれており、厳格に階層化され、明確に定義されています。どのような葬儀の儀式を採用するかは、主にラマ僧の占いによって決まります。 塔に埋葬することは、死後、徳の高い人々のために行われる崇高な葬儀の儀式です。有名な活仏が亡くなった後、大々的な読経や儀式のほか、胃腸を水銀や「サラダ」の香辛料水、樟脳水、サフラン水などで洗浄、遺体の表面を樟脳水、サフラン水などで拭いた後、絹で包み、袈裟を着せて仏塔に安置し、遺体を保存する。毎日、当番のラマ僧たちはバターランプに火を灯し、昼夜を問わずそれを捧げます。塔には金塔、銀塔、木塔、泥塔など多くの種類があります。仏塔の階数は、生き仏の地位に応じて決まります。ダライ・ラマとパンチェン・ラマが亡くなった後、金の仏塔が使われるようになりましたが、他の生き仏は銀、木、泥の仏塔しか使えませんでした。 伝統的なチベットの観点から見ると、火葬も比較的高貴な埋葬方法である。具体的な方法は、ギーを薪にかけ、遺体を火葬し、灰を集めて木箱や土鍋に入れて、自宅の階下や山の頂上など清潔な場所に埋葬するというものです。墓は塔のような形をしています。遺灰を拾って山の頂上に運び、風や川に撒く人もいます。非常に尊敬されている生きた仏陀とラマ僧の火葬の後。遺灰は金や銀で作られた小さな塔に納められます。遺骨を古典籍、仏像、祭具、金、銀、その他の宝物と一緒に塔に納める人もいます。人々が崇拝するためのこの種の塔は、一般的に仏塔または納骨堂と呼ばれます。 天葬はチベット人の間で一般的な埋葬の習慣であり、「鳥葬」としても知られています。一般農民、遊牧民、庶民が使用します。チベット仏教徒は、天葬は「天国」へ昇りたいという願望を表すと信じている。各地域には天空葬地(天空墓地とも呼ばれる)があり、この業に従事する専門家(天空葬師)がいます。人が亡くなった後、その遺体は頭を膝の上に曲げて座った状態で丸まり、白いチベット毛布で包まれ、ドアの後ろの右側にある土の台の上に置かれ、ラマ僧が招かれて魂を解放するための経文を唱えます。縁起の良い日には、遺体運搬人が遺体を天葬台まで運び、まずハゲワシを引き寄せるために「桑の実」の香を焚きます。ラマ僧が詠唱を終えると、天葬師が遺体を扱います。すると、ハゲワシの群れがそれに応えて飛んできて、餌をついばもうと競い合います。餌をすべて食べることは、死者に罪がなく、魂が安らかに天国に昇ったことを意味するため、最も縁起が良いとされています。食べきれなかった食べ物は、魂の解放を祈って経文を唱えながら、残った部分を拾い集めて燃やします。チベット人は、天葬台を囲む山々にいるハゲワシは人間の死体を食べる以外は小動物に危害を加えないため、「聖なる鳥」であると信じている。天葬の儀式は通常、早朝に行われます。遺族は夜明け前に遺体を天葬台に送ります。太陽がゆっくりと昇るとともに、天葬の儀式が始まります。許可なく視聴しない方がよいでしょう。 水葬は通常、経済的に困窮している家庭がラマ僧を雇う余裕がない場合や、故人が未亡人や幼い子供である場合に行われます。水葬では、遺体は川岸まで運ばれ、バラバラにされて川に投げ込まれます。地域によっては、遺体を白い布や毛布で包み、大きな岩の上に投げ込んで「川の神」への供物として川に捨てることもある。 チベット人にとって、埋葬は葬儀の最も低い形式です。一般的に、ハンセン病、天然痘、炭疽などの伝染病にかかった人や、強盗や殺人犯は死後埋葬されました。埋葬にはおそらく二つの意味がある。一つは疫病の蔓延を根絶すること、もう一つは罪を罰して地獄に送ることである。 葬儀のマナーとタブー チベット地域ではどのような葬儀が行われる場合でも、葬儀の前に僧侶を招いて故人の魂を解放するための経文を唱えてもらいます。葬儀の後、49日以内の7日間ごとに仏教の儀式を行う必要があり、これは一般に「七回忌」として知られています。初七日には、親族や友人が故人の家を訪れ、老若男女を問わず故人の親族が髪を洗うのを手伝い、喪が終わったことを示します。それ以来、僧侶は七日目ごとに経文を唱えるよう招かれ、寺院ではランプが灯され、油が添えられて死者のために祈るようになりました。最後の7日間には盛大な供養が行われ、親族や友人らが「救済像」にハダを捧げ、故人の家族を慰めます。 チベットの葬儀の儀式やタブーは、地域や埋葬のスタイルによって異なります。甘孜州徳格県や雅江地域の墓地では、高齢者は高い位置に埋葬され、若い人は低い位置に埋葬されている。丹巴地区では、遺体を埋葬する際、埋葬後に遺体が圧迫される恐れがあるため、その上に石を置くことは固く禁じられており、また、遺体が蘇る恐れがあるため、保管期間中は犬や猫が埋葬地に入ることは固く禁じられている。 甘孜地区での水葬の際、遺体を運ぶ人は1年間、いかなる活発な活動に参加することが禁じられ、赤い服を着ることもできない。親族は1年間お祝い事を避ける必要がありますが、会葬者は何も避ける必要はありません。デルゲのゴンヤ地区では、葬儀に出席することは功徳を積む方法と考えられており、村人たちは葬儀に出席するために競い合います。甘粛省や青海省のチベット地域では、人が亡くなった後、家族は帽子を逆さまにかぶり、三つ編みに白い毛糸を結び、ベルトの両端をお腹の前で結び、哀悼の意を表します。哀悼の意を表すため、49日間はいかなる娯楽活動にも参加しないでください。 チベット人は死者を名前で呼ぶことを嫌い、ただ「故人」と呼ぶだけだ。誰かが理由もなく故人の名前を呼ぶことは、故人の親族に対する最大の侮辱と挑発とみなされます。 ここでは天葬を例に、ウーツァン地方の葬儀の儀式とタブーについて概説します。 人が亡くなると、まず遺体は家の片隅に置かれます。遺体は白い布で覆い、日干しレンガでクッションを敷きます。ベッドやその他の物品は使用できません。死体が運び去られたからです。すると十字路にレンガが投げ込まれ、人間の魂はもはやその家に留まることができなくなった。人が亡くなった後、家族は髪をとかしたり顔を洗ったりすることは許されず、装飾品をすべて外すことも許されません。また、笑ったり、大声で話したり、歌ったり踊ったりすることも許されません。故人の家の玄関に赤い陶器の壺を掛け、壺の口を白い毛糸かハダで覆います。ツァンパを3種類の非菜食食品(血、肉、脂肪)と3種類の菜食食品(牛乳、チーズ、バター)と混ぜたものを壺に入れます。火をつけて煙を出し、死者の霊への贈り物として毎日壺に注ぎます。 遺体は通常3日間安置され、特定の日に葬儀が行われます。葬列は夜明け前に始まり、死者は前日に衣服を剥ぎ取られます。手足はボール状に縛られ、白いフェルトで覆われていました。葬儀の朝、遺体が置かれた部屋の角から家の玄関までツァンパで線が引かれます。その後、故人の子孫は親孝行のしるしとして、遺体を白い線に沿って玄関まで運びます。門に到着すると、葬儀屋が遺体を天空埋葬地まで運びます。死者が背負われて上がられると、死者と同い年の人が片手に箒を持ち、もう片手に壊れた四角い籠を持って後ろからついてくる。彼はツァンパの白い糸を払い落とし、箒と遺体を包んでいたレンガを籠に入れる。そして死体を十字路まで追いかけ、死体を交差点の真ん中に投げて幽霊を追い払う。その朝、親族や友人らが故人を見送りにやって来て、それぞれ線香を手に持ち、街を出ていった。 遺族は天葬地に行くことは許されません。遺体を運ぶ人や会葬者は後ろを振り返ることも許されません。この2日間、葬儀屋や会葬者は故人の家に行くことが許されません。故人の魂が家に帰って家族に災いをもたらすのを防ぐためです。 葬儀場に到着すると、まず埋葬台の近くで線香が焚かれます。ハゲワシは煙を見慣れているため、餌を求めて飛び回っています。それから葬儀屋は遺体を解体し始める。故人が僧侶だった場合、まず背中に宗教的な意味を持つ模様を彫り、次に腹部を切り開き、内臓を取り出し、肉を切り分け、頭皮を剥ぎ、頭を切り落とし、最後に肉を切り分けて骨を叩き、ツァンパと混ぜてハゲワシの餌にする。十分に食べられなかった骨や肉があれば、一片も残さず拾い上げ、灰になるまで燃やし、四方八方に散らばらせた。つまり、死体は痕跡を残さずに処分されなければならないのです。この時点で天葬の儀式は終了しました。 |
<<: なぜ司馬昭は劉禅を殺さなかったばかりか、彼を安楽県公にしたのでしょうか?
>>: 曹操の25人の息子のうち、楚王曹彪はどのようにして司馬懿に反乱を起こしたのでしょうか?
推薦する
李秋水の息子は誰ですか?李秋水の息子、李千順のプロフィール
西夏の崇宗としても知られる李千順(1083-1139)は、西夏の第4代皇帝であり、夏の徽宗皇帝李炳昌...
『三国志演義』では孔明が東風を借りる様子をどのように描写していますか? 「風を借りる」の謎を解くには?
三国志演義の諸葛亮が東風を借りる話は諸葛亮の知恵を完璧に表現しており、この話は今でも広く流布され、誰...
袁震の「再贈与」:詩の言語はシンプルだが、長く残るリズムがある
袁震(779-831)は、衛之、衛明としても知られ、河南省洛陽(現在の河南省)の出身です。唐代の大臣...
『本草綱目第8巻 ローズマリー』の本来の内容は何ですか?
『本草綱目』は、明代の優れた医学者、李時珍によって著された全52巻からなる中国医学の古典書です。次の...
『事件を裁く亀鏡』の著者は誰ですか?主な内容は何ですか?
『判例亀鏡』は『判例亀鏡』とも呼ばれ、南宋時代の鄭柯が編纂した古事記集である。宋末から元初期にかけて...
「王大長嶺を江寧に送る」の制作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
王大長玲を江寧に派遣岑神(唐代)私は黙って飲み、悲しみとともにあなたに別れを告げます。私は明代に就職...
『紅楼夢』の宝仔はなぜ黛玉のように本が詰まった本棚を持っていないのでしょうか?
黛玉は中国の有名な古典『紅楼夢』のヒロインであり、金陵十二美女の第一人者です。Interesting...
賈憐の実の妹は誰ですか?なぜ彼は賈英春のことを何も気にしないのか?
以下は、Interesting Historyの編集者による、賈聰の実の妹についての紹介です。興味の...
沈月は『報玄城条』でどのような芸術技法を使用しましたか?
沈月が『宣城彪に報いる』でどんな芸術技法を使ったか知りたいですか?この感謝の詩は物語と抒情を融合し、...
古典文学の傑作『論衡』:第3巻:事物と情況の章の全文
『論衡』は、後漢の王充(27-97年)によって書かれ、漢の章帝の元和3年(86年)に完成したと考えら...
漢代の十大将軍の一人:鄧愈は漢の光武帝の名将である。
鄧愈(2-58年)、愛称は中華、南陽の新野の出身。彼は東漢初期の軍事戦略家であり、雲台二十八将軍の第...
西洋諸国が賞賛する古代中国の発明トップ10
西洋から賞賛された古代中国の十大発明。いわゆる四大発明の全てが含まれているわけではありません。列植え...
『福平侯子』の創作背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
富平少侯李尚閔(唐代)七国三辺に憂いはなく、十三自身も福平侯の位を継承した。金の弾丸を集めて森の外に...
王維の古詩「劉藍田に贈る」の本来の意味を理解する
古代詩「劉藍田に贈る」時代: 唐代著者 王維犬たちは柵に向かって吠えた。家の外に出てドアを待ちます。...
三国志演義の張郃についてはなぜこれほどまでに意見が分かれているのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...