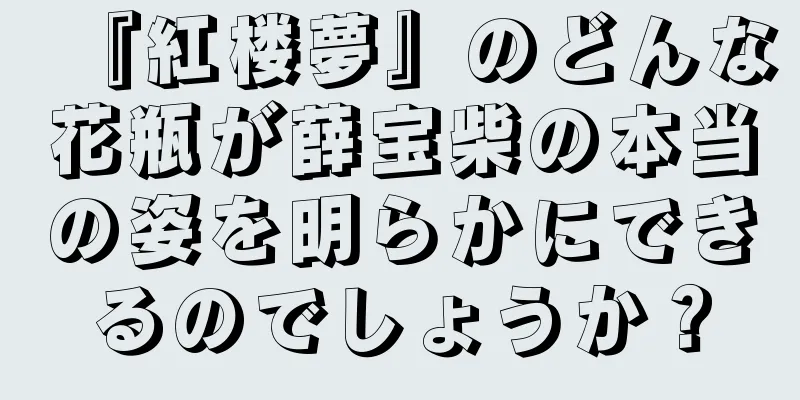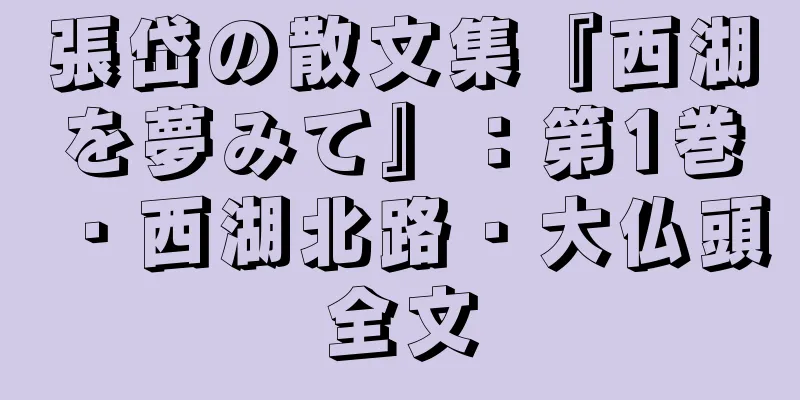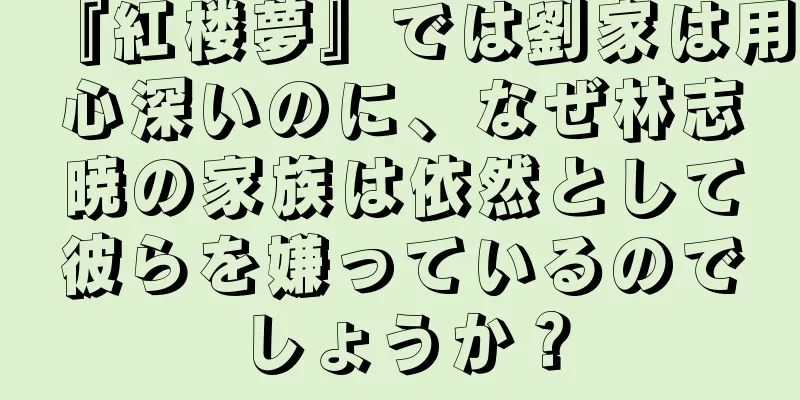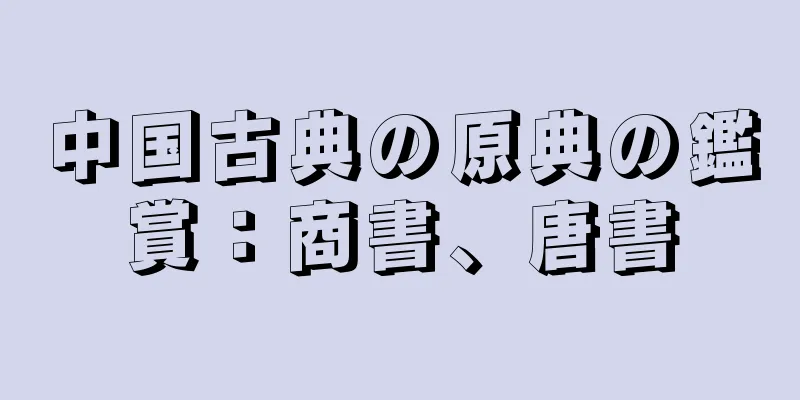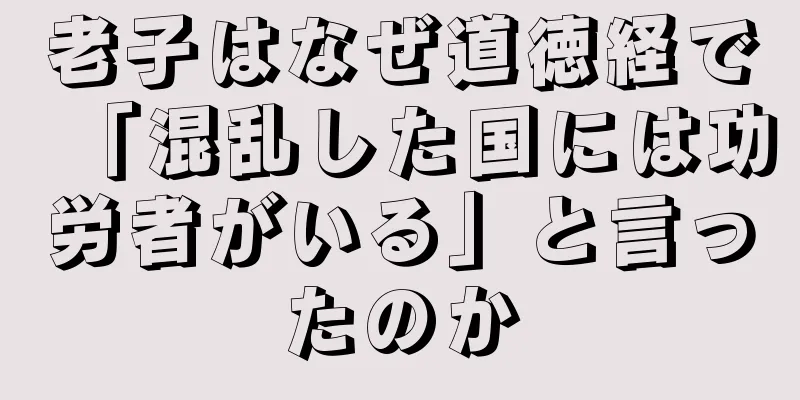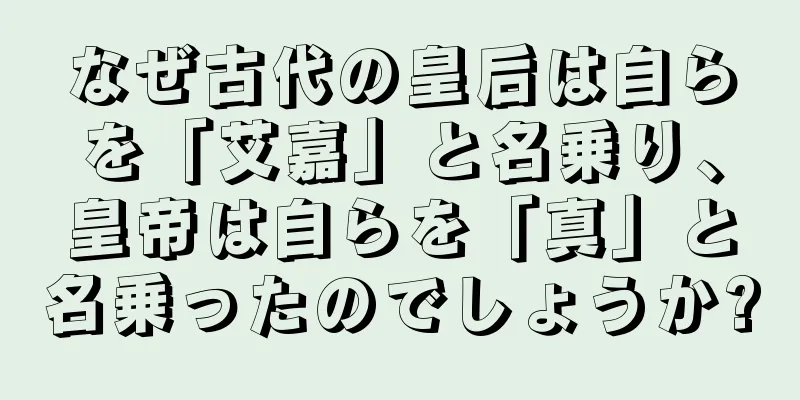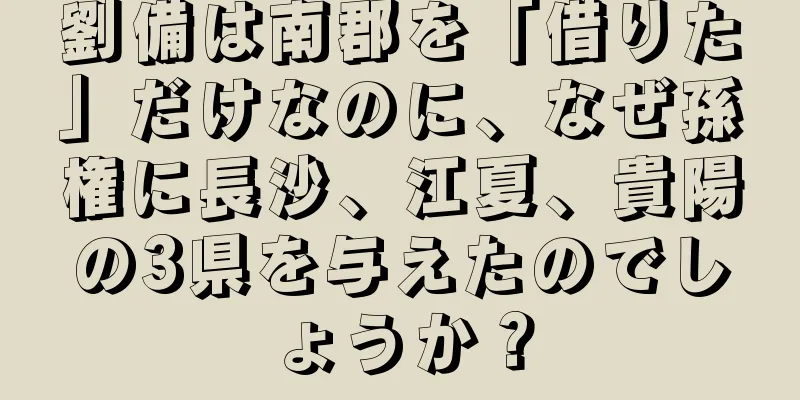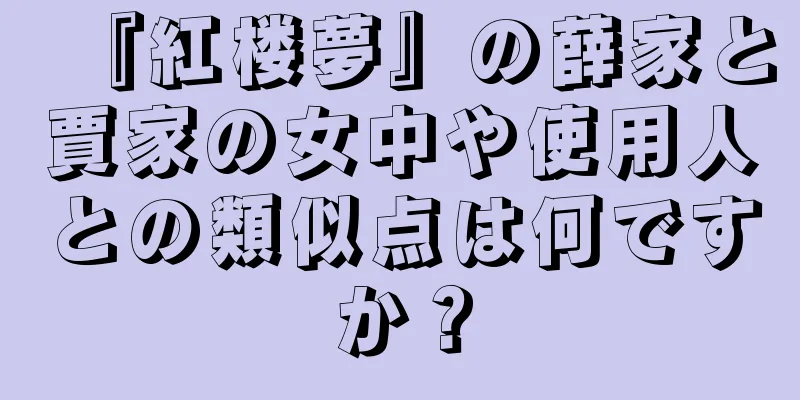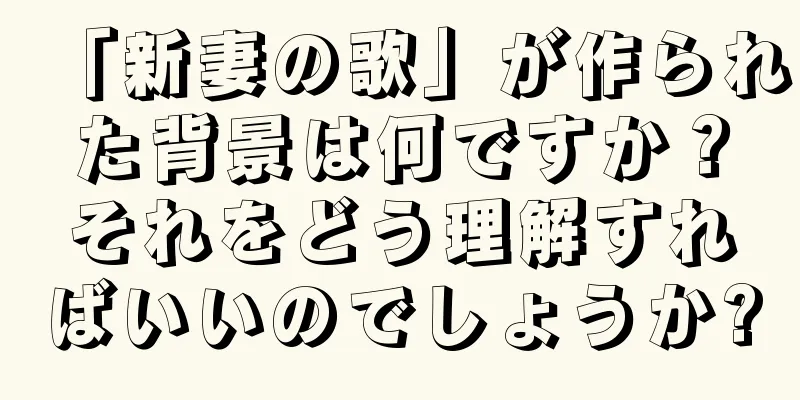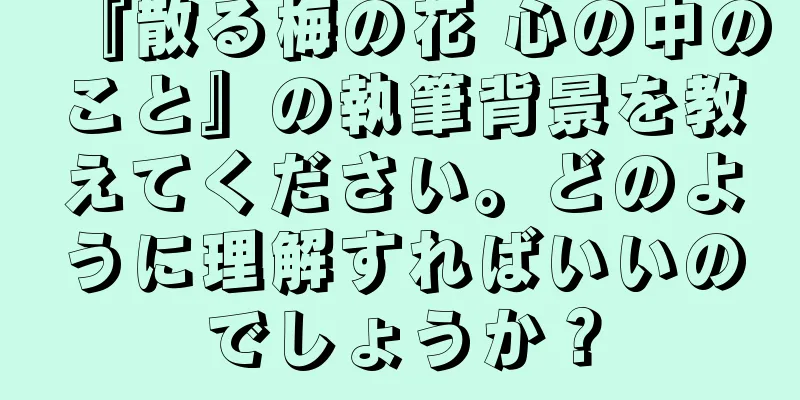三国時代は歴史上有名な混乱の時代ですが、なぜほとんどの戦争は少数勢力が大勢力を倒して終わったのでしょうか?
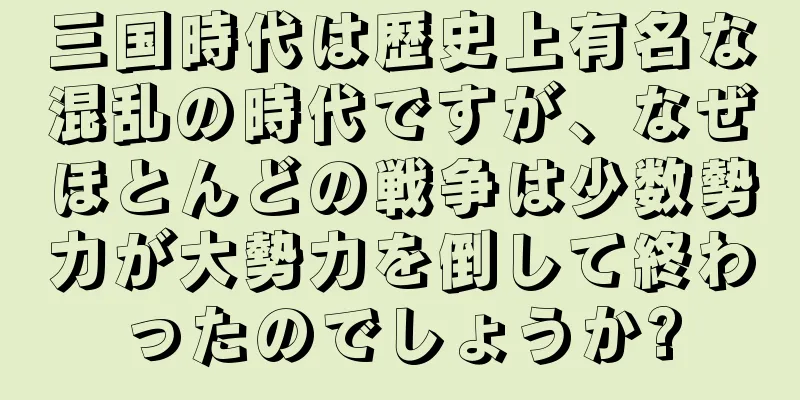
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、三国時代に少数派が多数派を倒す戦いがなぜこれほど多くあったのか、次の興味深い歴史編集者が詳しく紹介します。見てみましょう! まず、三国時代の生産力では、あまりに大規模な軍隊を支えることができませんでした。三国時代の中国は、まだ封建社会の初期段階にあり、四大発明のうち、印刷術、羅針盤、火薬はまだ登場していませんでした。製紙術だけは登場していましたが、まだ広く普及していませんでした。当時の主な媒体は、紙ではなく、竹簡でした。これらはすべて、当時の社会の生産性の後進性を反映しており、生産性の後進性は軍隊に深い影響を与えました。 例えば、農業技術が遅れていたら、大規模な軍隊を支えるために、より多くの食糧を収穫するために、より多くの人を使ってより広い土地を耕作しなければなりません。しかし、ある期間の総人口は基本的に一定です。農業をする人が増えれば、戦う人は減り、戦う人が増えれば、農業をする人は減ります。何十万、何百万人もの軍隊を編成することにこだわるなら、誰も耕作しない広大な土地が必ず存在し、食糧生産は必然的に低下します。時間が経つにつれて、大規模な軍隊は簡単に食糧不足に直面し、戦闘効果が急激に低下します!これが、三国志演義で曹操、袁紹、諸葛亮など当時の英雄たちがしばしば食糧問題に悩まされた根本的な理由です。 例えば、製錬技術が遅れていたため、前線の兵士に十分な武器を供給することができませんでした。当時の名将は、方天華器、青龍延月刀、張巴蛇槍など、さまざまな武器を手にしていましたが、それらは将軍の特権に過ぎませんでした。下級兵士のほとんどは、粗雑に作った武器、または鍬と棒さえ持っていたかもしれません。特に人数が多いときは、武器の需給問題がより顕著でした。このため、孫と劉が曹と戦っていたとき、東武という国は、わずか10万本の矢さえ生産できず、「藁船から矢を借りる」などの機会主義的な方法で武器を補充するしかありませんでした。 例えば、通信方法は後進的で、軍隊の規模が大きいほど、切り離せない尻尾の効果を生み出しやすくなります。特に、前線部隊が撤退すると、指揮部でさえ何が起こったのかわからず、中央軍と後方軍はさらに混乱します。そのため、撤退行動が制御不能になると、取り返しのつかない自己蹂躙現象が発生します。人数が多いほど、死は悲惨です。このような現象は、袁紹と曹操の間の官渡の戦いで発生しました。70万人の軍隊は敗北しました。歴史上の有名な沛水の戦いでも同様の現象がありました。 つまり、生産性が後退している状況では、軍隊が大きすぎると戦闘力が弱いだけでなく、悲惨な敗北を招く可能性もあります。適度な規模の軍隊は管理、訓練、指揮が容易です。諺にあるように、「渡る川の大きさに合った靴を脱ぎ、お尻の大きさに合ったズボンを履く」というのはまさに真実です。実際、魏、蜀、呉の三国は数十万、数百万人の軍隊を持っていると主張していましたが、それぞれの手にある切り札は数万人の精鋭部隊に過ぎませんでした。 第二に、三国時代の戦争の総数は膨大であったため、数で劣る側が勝つ戦いの数も自然と増加しました。周知のように、三国時代は中国史上、戦争が頻発した混乱の時代として有名です。最も驚くべき統計の一つは、中国の総人口が東漢の6000万人から三国時代には1000万人以下に減少したことです。これは、当時の戦争がいかに頻繁で残酷であったかを一面から反映しています。不完全な統計によると、三国時代の三大戦闘のほか、漢中の戦い、徐州の戦い、潼関の戦い、諸葛亮の六次北伐、姜維の九次北伐など、61のよく知られた大規模な戦闘があり、それらのあまり知られていない戦いを加えると、三国時代の歴史全体は戦争の歴史と言えます。分母となる戦争の総数がこのように膨大であるため、分子となる少数が多数を倒した古典的な戦いがいくつかあるのも不思議ではありません。 第三に、「生存者バイアス」現象の存在は、「三国時代には、数の少ない側が数の大きい側に勝つ戦いが多かった」という概念をさらに強固なものにしている。 「生存者バイアス」に関しては、典型的な事例がある。かつて米国は、航空機のどの部分に最も防御が必要かを調査し、損傷した航空機の弾丸位置の分布図を作成した。当初の見解は、弾丸の分布が多いほど、補強が必要であるというものだった。しかし、後に一部の専門家が反対の見解を唱えた。彼らは、統計データ上の航空機の大部分は被弾後も無事帰還できており、データに欠けている航空機の部分は、まさに被弾後に墜落した航空機であるため、これらの戦闘機は被弾していない部分を補強する必要があると考えた。実践により、これらの専門家の見解が正しいことが証明された。 「生存者バイアス」の概念を理解した後は、「なぜ三国時代に少数が多数に勝つことが多かったのか」を理解するのは難しくありません。ある意味では、魏の強大な力の前で、東呉と蜀漢は典型的な「生存者」でした。「生存者」の存在が歴史的事実になったとき、私たちは「少数が多数に勝つ可能性」という問題を疑問視します。論理的に見ると、それ自体が本末転倒です。正しい論理は、「なぜ三国時代に少数が多数に勝つことが多かったのか」ではなく、「三国時代に少数が多数に勝つことが多かったからこそ、混乱した三国時代が生まれた」というべきでしょう。 |
推薦する
白居易の古詩「魏志の情詩に答える」の本来の意味を鑑賞する
古代詩「魏志の情詩に答える」時代: 唐代著者: 白居易みんなで一緒に過去の春の出来事を思い出し、船上...
なぜ林黛玉は薛叔母さんを自分の母親、薛宝柴を自分の妹として認識したのでしょうか?薛叔母と薛宝才の優しい罠
なぜ林黛玉は薛叔母を母、薛宝才を妹と認識したのでしょうか?その理由は胸が痛むほどです。次の『おもしろ...
「世界の物語の新記録」の第 41 章ではどのような物語が語られていますか?
周知のように、『新世界物語』は魏晋時代の逸話小説の集大成です。では、『新世界物語・讃』第41篇はどん...
何千年もの間、人々を魅了し続けている、最も美しい連句 40 選!
詩の美しさは、何千年経っても本当に不滅です。今日、Interesting History の編集者は...
ラン・デン師匠の強さはどのくらいですか?そしてなぜ趙公明に勝てないのですか?
あなたは鄧然先生について本当に知っていますか?Interesting Historyの編集者が詳細な...
『紅楼夢』で賈宝玉が僧侶になることを選んだ本当の理由は何ですか?
宝玉が出家することは、有名な小説『紅楼夢』の筋書きの一つです。次回はInteresting Hist...
『紅楼夢』の邢秀燕のイメージは?文字の意味は何ですか?
『紅楼夢』の全体的なテーマは、何千もの美女が一緒に泣き、何万もの美女が一緒に嘆き、すべての花が枯れ、...
西遊記の玉兎の仙女の起源は何ですか?彼女はなぜ地球に来たのですか?
テレビドラマ「西遊記」をご覧になった方は、西遊記の最後の妖怪が玉兎だということはご存じでしょう。これ...
宋江が涼山に与えられた恩赦を拒否した場合、反乱は成功できただろうか?
今日は、興味深い歴史の編集者が、宋江が恩赦を拒否したかどうか、そして涼山が世界を征服できたかどうかに...
「中国のスタジオからの奇妙な物語 - 試験局」の原文は何ですか?この記事をどう理解すればいいのでしょうか?
「試験局」の原文(中国のスタジオからの奇妙な物語より)温仁生さんは河南省出身です。数日間病気になった...
『紅楼夢』で賈宝玉が林黛玉に鶺鴒の香数珠を渡したとき、林黛玉は何と言いましたか?
女性に親しみやすい賈宝玉のような少年にとって、彼と北京王子は一目惚れした。以下の記事はInter...
ハシビロコウにはどんな紛らわしい行動があるのでしょうか?なぜ世界では「鳥の中のハスキー」と呼ばれているのでしょうか?
ハシビロコウはコウノトリ科によく似た大型の鳥で、ハシビロコウ科のハシビロコウ属に属する唯一の種です。...
青城山の有名な観光スポットは何ですか?なぜ青城山は道教の聖地なのでしょうか?
今日は、Interesting Historyの編集者が道教の聖地である青城山の有名な観光スポットを...
朱棣の子孫である朱厚崇は永楽帝からどのような伝統を受け継いだのでしょうか?
朱厚崇は明の献宗朱建順の孫であり、興憲王朱有洛の息子である。1507年に生まれ、1567年に亡くなっ...
ナラン・シンデの「青春の旅:楽しい時とはこういうこと」:2つの詩、1つは幸せでもう1つは悲しい、鮮明な対比がある
納藍興徳(1655年1月19日 - 1685年7月1日)は、葉河納藍氏族の一員で、号は容若、号は冷家...