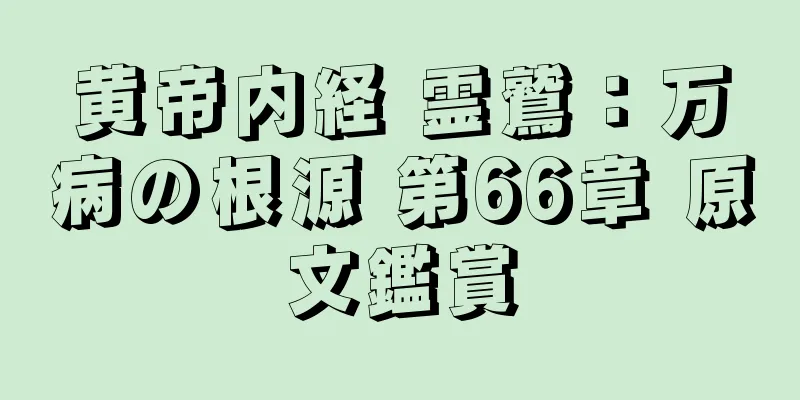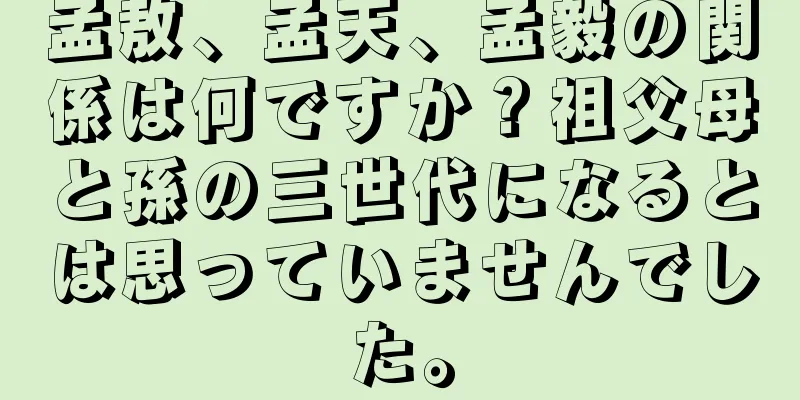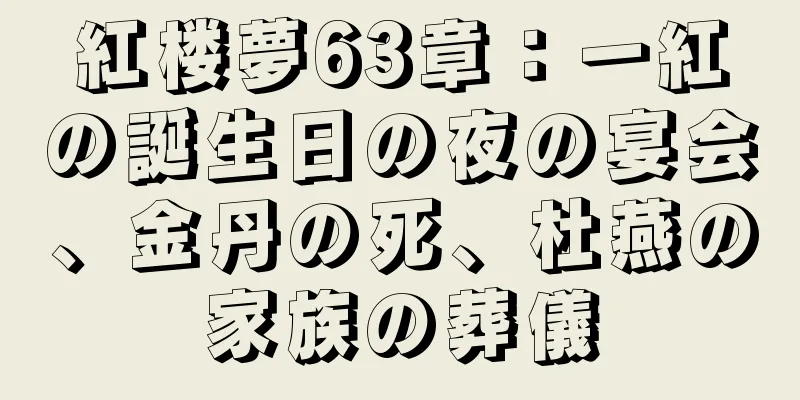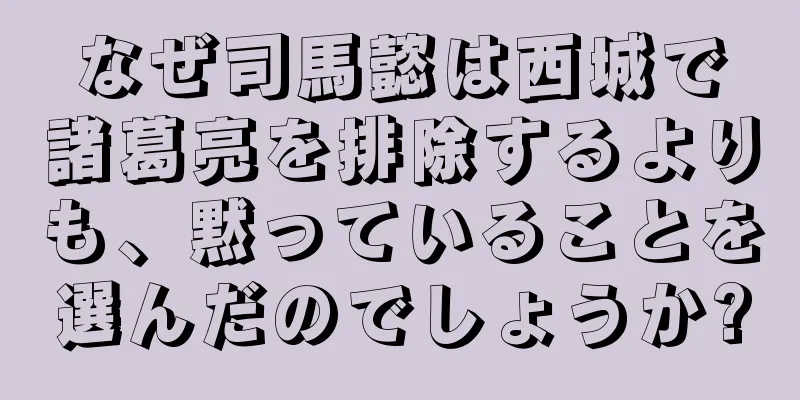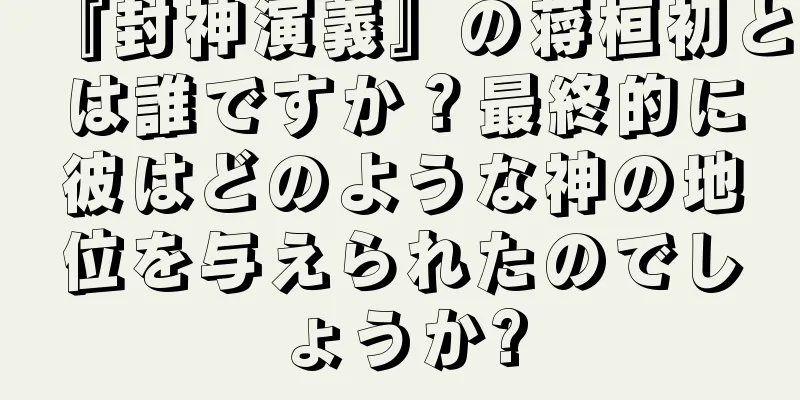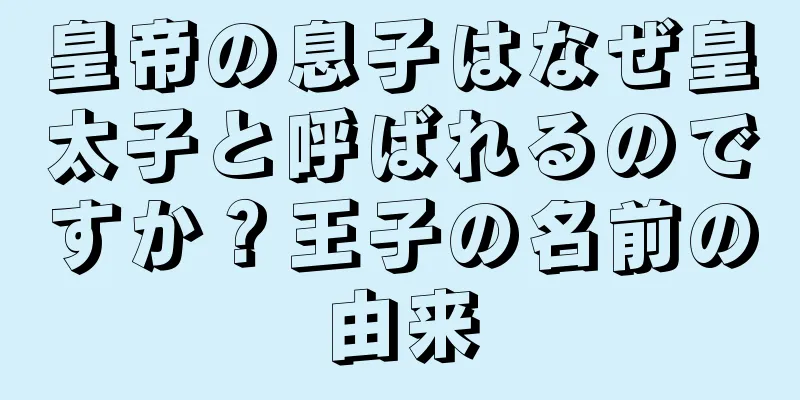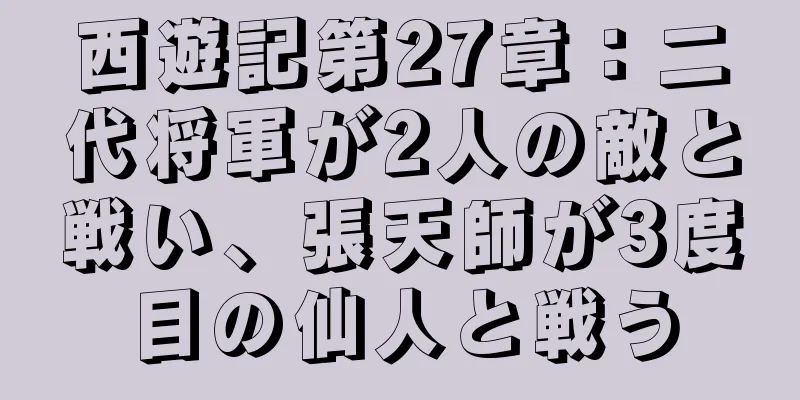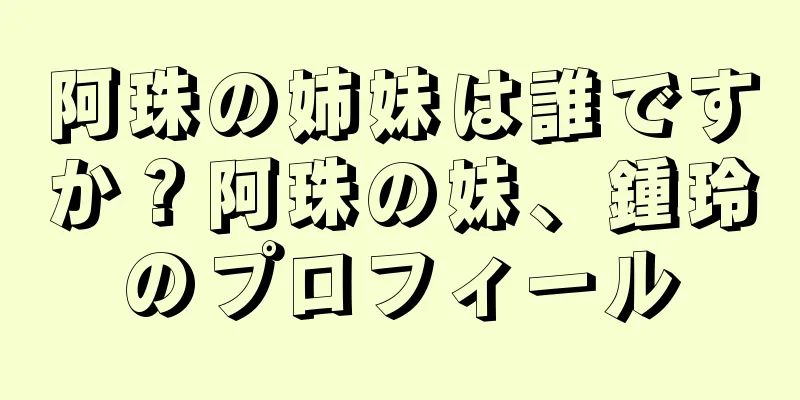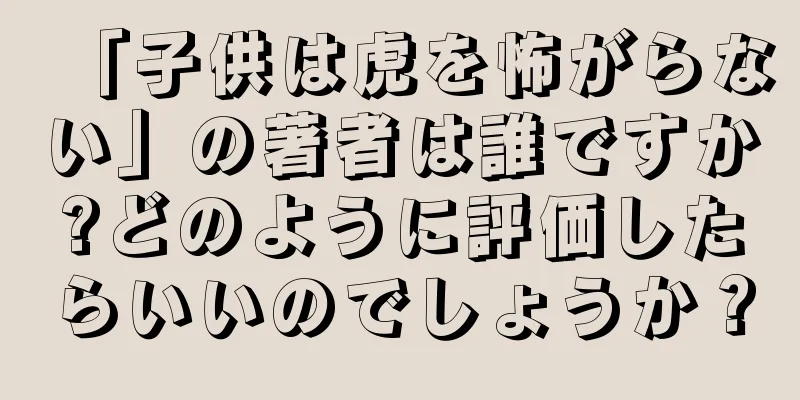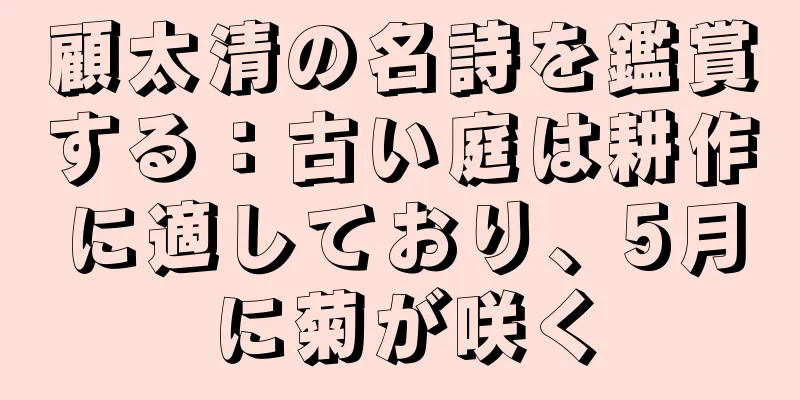詳細から判断すると、なぜ張飛は馬超との夜戦でわずかに劣っていたのでしょうか?
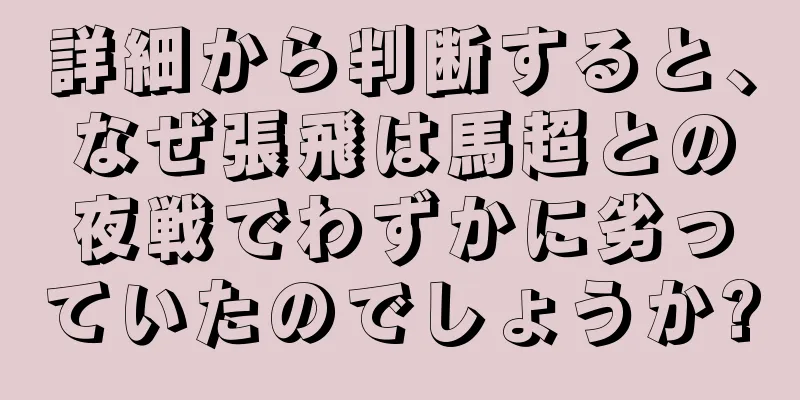
|
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が張飛と馬超の夜の戦いについて詳しく紹介します。どちらが強いでしょうか? 見てみましょう! 若くて強い人こそが戦いに最も適しています。軍の将軍の全盛期は30歳前後です。この年齢層は、将軍の体力がまだ良好で、戦闘技術が最も磨かれ、戦闘経験が最も豊富である時期です。 ピーク期は35歳まで維持でき、一部の将軍はさらに長く維持できるかもしれませんが、40歳を過ぎると、将軍の戦闘力はさまざまな程度に低下します。この年齢になると、戦闘スキルは磨かれ、経験値も増えますが、体力は若い頃ほど良くはないでしょう。 もちろん、より自制心があり、自己管理がしっかりしている将軍は衰えが少なく、黄忠のように老齢になっても強いままでいられるでしょう。しかし、40歳を過ぎてから世界一になりたいと思うのは明らかに非現実的です。 これが、呂布が虎牢関で劉、管、張の包囲に一人で耐えることができた理由でもある。 7、8年後、張飛は呂布に単独で挑むことができました。その理由は呂布が40歳を超えて戦闘力が衰えていたからです。 当時、張飛は40歳未満で、武術の腕前は絶頂期にあった。 同様に、年老いた関羽は龐徳を倒すことができず、30ラウンド後、関平は若者ほど体力がないとして部隊を呼び戻しました。関羽は武術の腕前で戦いを続ければ負けることはなかったかもしれないが、勝つ可能性は低かった。 関羽は年老いているのに、張飛が若いはずがない。馬超と戦ったとき、張飛は50歳を超えていたはずで、彼の武術の腕前はもはや最高ではなかった。この時、馬超は40歳未満で絶頂期にあった。 張飛が誇っていたのは武術であり、彼は武術を比較的よく維持していた(酒は飲んでいたが、他の悪い習慣はなかった)ので、武術の衰えはそれほど深刻ではなかったが、絶頂期の馬超を倒すことは絶対に不可能だった。 このことは、4年後、張飛が張郃と30、50ラウンド戦ったにもかかわらず、彼を倒すことができなかったという事実からもわかります。 一人の将軍が前方から現れ、目を見開いて雷のような声をあげ、行く手を阻んだ。それは張飛だった。彼は槍を高く掲げ、馬に飛び乗って張郃に向かってまっすぐに向かった。二人の将軍は炎の中で30から50ラウンドにわたって戦った。 張郃が絶頂期にあった馬超と対戦したとき、彼はわずか20ラウンドしか持ちこたえられなかった。 張郃は彼を迎え撃ったが、20ラウンド戦った後敗北した。 張飛は馬超と夜戦った。引き分けに終わったが、細部から見て張飛がやや劣勢だったことがわかる。徐褚のように上半身裸で戦いに臨むことはなかったが、帽子も脱いだのだろうか? 張飛は再び陣形に戻り、少し休憩した後、兜をかぶらずにスカーフを巻いて馬に乗り、馬超に戦いを挑んだ。 なぜかって?体力とスピードに影響するから! 張飛は馬超を倒すことができず、関羽と交代しても何も変わらないだろう。 |
>>: キルギス人はどんな服を着ているのか?キルギス人の衣服の紹介
推薦する
なぜ趙雲は矢を簡単に避けて何の害もなかったのに、馬超はそれができなかったのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
『紅楼夢』で西仁はいつ江玉漢と結婚したのですか?真実とは何でしょうか?
希仁は中国の古典小説『紅楼夢』の登場人物。金陵十二美女の一人であり、宝玉の部屋の四人の侍女の筆頭であ...
中国人からは卑怯とみなされている宋王朝が、なぜ海外では高く評価されているのか?
今日は、Interesting Historyの編集者が、宋王朝が外国人から高く評価されている理由を...
『後漢書』第85巻の原文は何ですか?
『礼記』にはこう記されている。「東方の人々は易と呼ばれている。」易は「根」を意味し、慈悲と生命への愛...
米芳の紹介 三国志の将軍、米芳はなぜ反乱を起こしたのか?
米芳(生没年不詳)、法名は子芳、東海曲県(現在の江蘇省連雲港市)の出身。もともと徐州太守の陶謙の部下...
元朝の皇帝は死後どこに埋葬されたのでしょうか?モンゴルの葬儀の習慣は何ですか?
今日は、Interesting Historyの編集者がモンゴルの葬儀の習慣についての記事をお届けし...
白潭の詩の有名な詩句の鑑賞:歌うコウライウグイスと踊るツバメ、小さな橋と流れる水、赤い
白普(1226年 - 1306年頃)、元の名は衡、字は仁福、後に普と改名、字は太素、号は朗古。漢民族...
科挙の受験生はそれほど重要な人物なので、盗賊は命を危険にさらしてまで彼らを襲うでしょうか?
科挙は国家のために人材を選抜するためのものであり、朝廷の最重要課題の一つであった。北京で科挙試験を受...
天皇が記念碑にコメントした内容の秘密を暴露?康熙帝は多くのことを「知っていた」
はじめに:皇帝が記念品を鑑賞した際に何と書いたかご存じですか?最近、南京江寧織物博物館は、康熙帝が鑑...
襄公9年に古梁邁が書いた春秋実録『古梁伝』に何が記録されていますか?
襄公九年に古梁邇が著した『春秋古梁伝』には何が記されているのでしょうか?これは多くの読者が関心を持っ...
八旗制度とは何ですか? 八旗制度を創設したのは誰ですか?
八旗制度は満州人によって確立された社会組織構造です。清朝の前身である後金政権が民族の発展に適応するた...
秦の名将、王離の紹介。王離と王翦の関係は?
王離の紹介:秦の将軍王建の孫、王本(おうぼん)の息子、雅号は明。彼は秦の始皇帝の治世中に武成侯の爵位...
『紅楼夢』で英児が絹の錦織を作ることの意味は何ですか?
英娥(本名:黄金英)は、『紅楼夢』に登場する薛宝齋の侍女である。よく分からない読者は、Interes...
中国の歴史上、人口が最も少なかった王朝はどれですか?
古代を除けば、中国史上最も人口が少なかった時代は五厘の乱であろう。 三国時代には人口は数百万人にまで...
『紅楼夢』ミニチュア切手の真贋はどうやって確認できるのでしょうか?
1980年代初め、わが国の切手発行はより革新的な段階に入りました。まず干支を題材にした切手が発行され...