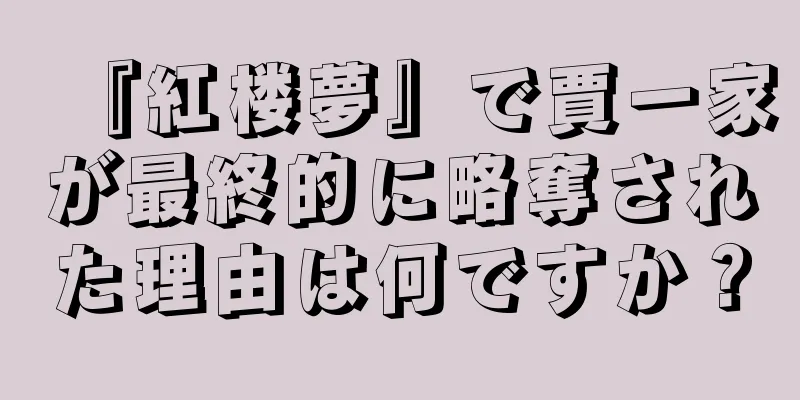日本は唐の文化だけでなく宋の技術も学んだ

|
日本といえば、唐代の文化が大きな影響を与えたと考える人が多いでしょう。実は、日本は唐代の文化だけでなく、宋代の技術も学びました。次の興味深い歴史編集者が詳しい紹介をお届けしますので、見てみましょう! 宋代に生産性が大幅に向上したのは、火力革命(石炭の利用)と鉄鋼の生産によるものでした。火力革命により鉄の生産量が増加しただけでなく、宋代の陶磁器は質・量ともに前例のないほど発展しました。ヨーロッパは18世紀までそれを模倣することができませんでした。 宋代の銅貨は中国本土で流通しただけでなく、外国貿易により日本、東南アジア、ペルシャ、アフリカなどにも流れた。金銀銅貨の価格比率を見ると、日本では金銀の価格が中国よりも安いため、中国の銅貨は日本に大量に輸出され、金銀は中国に輸入されています。この事件は鎌倉時代以降の日本の社会経済に影響を及ぼした。 日本各地の仏教寺院の遺跡からは、宋代の貨幣が詰まった壺や壷が頻繁に発掘されています。これらの貨幣は、ほとんどが宋代に日本に輸入されたものです。火薬 火薬は10世紀初頭の唐代末期に初めて武器として使用されました。火薬の歴史上重要な発展は、発射装置がカタパルトから円筒形の発射装置に改良されたこと(12世紀前半)、そして紙製の容器から鉄製の容器に改良されたこと(13世紀初頭)であり、つまり宋代にはほぼ改良が完了していたことになる。 その後、モンゴル軍が鎌倉幕府を攻撃した際、勇猛果敢で名高い鎌倉武士たちもこの「鉄砲」に恐怖したそうです。印刷技術である活版印刷は北宋中期(11世紀半ば)に発明されました。当時はまだ木版印刷が主流で、活版印刷は一般的ではありませんでした。 活版印刷が高麗に導入されると、印刷技術はより実用的かつ高度なものになりました。その後、豊臣秀吉の軍が朝鮮出兵した際に活版印刷術が日本に持ち帰られ、徳川幕府初期の印刷技術の発展につながりました。しかし、漢字を使用する中国では活版印刷が不便であるため、現在でも木版印刷が使われ続けています。お茶を飲む習慣は三国時代の呉王国で始まりましたが、唐代中期(8世紀半ば)まで中国全土に普及しませんでした。 宋代には流通経路の拡大により茶の独占制度が形成されました。お茶の消費量は中国本土で増加しただけでなく、近隣の民族の間でも需要の増加につながっています。お茶は、中国の唐の時代に相当する奈良時代に日本に伝わりました。しかし、日本でお茶の生産が始まり、お茶を飲む習慣が広まったのは鎌倉時代初期になってからでした。 つまり、日本における茶の栽培は、臨済宗の開祖である栄西(1141-1215)が宋から茶の種子を持ち帰り、高雄の洛西の明恵上人に与え、明恵上人がその種子を植えたことから始まったのです。その後、宇治に茶の木が伝わりました。宇治は茶樹の栽培に最適な場所であるため、宇治茶は銘茶の代名詞となっています。朱熹は禅宗、枯山水、茶道、水墨画などを学んだ。日本の美術は、南宋の画家馬遠(1175-1225)の「一国」様式の影響を受けており、これは線や筆遣いを最小限に抑える日本の画家の「減筆」の伝統と一致しています。絵画においては、精神を重視しすぎたり、精神の重要性を強調しすぎると、形式が軽視されてしまいます。 そのため、「一角ボディ」と「ストロークを少なくしたボディ」の両方が孤立感の効果を実現するのに役立ちます。この不完全さ自体が美しさの形です。日本の芸術のもう一つの注目すべき特徴は「非対称性」であり、これは仏教建築、特に主線の両側に非対称に配置される副次的な建物によく反映されています。 この「非対称性」という概念は、「一は多、多は一」という禅の考え方から着想を得たものだと考える人もいます。東洋の水墨画に体現されている、簡素さ、明晰さ、悟り、完璧さといったさまざまな特徴は、ほとんど例外なく禅と有機的に結びついています。禅の自然観では、川や山、水の音は仏の声であり仏体であると考えられており、自然の美しさを披露する庭園もいわゆる仏土です。 |
<<: チワン族の葬儀:チワン族の葬儀の特別な儀式は何ですか?
>>: 壮族の文化:壮族にはどのような歴史、文化、芸術がありますか?
推薦する
郭墨は裸で対峙した復讐を果たした。なぜ陶寛は郭墨の首を取ることにこだわったのか?
東晋の時代、王道と陶寛は立場が異なり、しばしば争っていました。江州知事の文凌が亡くなった後、二人の対...
「劉公事件」第13章:若い判事が泥棒の家を調査する
『劉公庵』は清代末期の劉雍の原型に基づく民間説話作品で、全106章から成っている。原作者は不明ですが...
「徐道寧画銘」の作者は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
徐道寧の絵画陳玉毅目に映るのは揚子江の水と河県の緑の山々。これまで何千マイルも離れたところにあっ...
李白の古詩「友に贈る詩その2」の本来の意味を鑑賞する
古詩「友に贈る詩その2」時代: 唐代著者: 李白趙の短剣が袖の中にある。徐夫人から購入しました。玉箱...
隋と唐の時代における承天門の役割は何でしたか? 限られた文書記録の中で承天門はどのように記録されていますか?
唐長安城の重要な宮殿として、太極宮の正門も大きな意義を持っています。承天門は、隋唐の都、長安城の太極...
王維の『桃源星』:この詩は散文『桃花春』とともに世界に伝わる
王維(701-761)、字は墨傑、字は墨傑居士。彼は河東省蒲州市(現在の山西省永済市)に生まれ、祖先...
『紅楼夢』における宝玉の地位は何ですか? Jia Cong と比べてどうですか?
賈宝玉は中国の古典小説『紅楼夢』の主人公です。次に、Interesting Historyの編集者が...
後梁の君主呂傅とはどのような人物だったのでしょうか?歴史は呂傅をどのように評価しているのでしょうか?
呂祖(?-401)、号は雍緒、ディ族の人で、洛陽(現在の甘粛天水)の人。後梁の武夷帝呂光の長男、後梁...
二人とも兄弟ですが、賈丹春、賈歓、宝仔、薛潘の違いは何でしょうか?
Interesting History の編集者をフォローして、歴史上の本当の賈湛春を探ってみましょ...
『慕情・南高峰』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
オリジナル:サウスピーク。ノースピーク。北峰と南峰には雲が厚く、また薄い。湖と山の絵です。蔡芙蓉。ハ...
ロマンスと歴史書に記された内容の違いは何でしょうか?なぜ呂不韋の家族の死は不当ではなかったと言われるのでしょうか?
『三国志演義』は我が国の四大傑作の一つです。この本は後漢末期を舞台に、曹操、劉備、孫権の天下をめぐる...
『紅楼夢』では、絹のような瑪瑙の板から何が見えますか?
『紅楼夢』は、中国古代の章立て形式の長編小説で、中国四大古典小説の一つであり、一般に使われているバー...
解釈:西漢王朝の紹介と西漢王朝の歴史の概要
はじめに:前漢王朝とも呼ばれる西漢は、古代中国の王朝です。後漢王朝とも呼ばれる東漢王朝とともに、総称...
実際の歴史では、「一刀両断」の主人公は有名な関羽だったのでしょうか?
「川のそよ風が軽やかな船を前に進ませ、波がうねり、高尚な志と英雄的精神を添える。龍の穴や虎の巣に何を...
古代の人たちは川に飛び込むときになぜ靴を川のそばに残したのでしょうか?
古代の人たちはなぜ川に飛び込んだとき、靴を川のそばに残したのでしょうか。これは多くの読者が特に知りた...