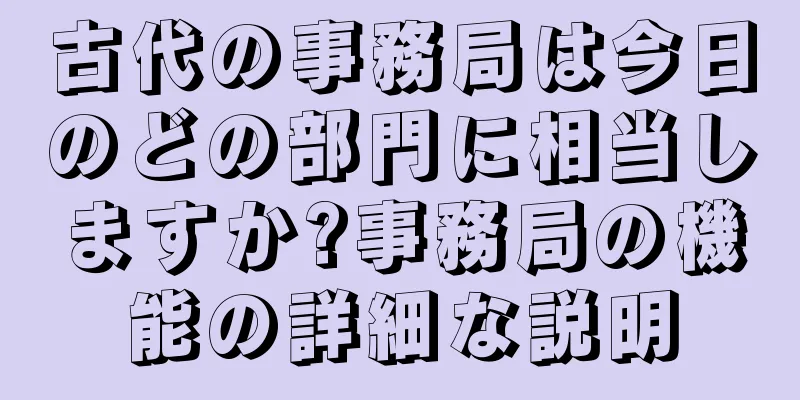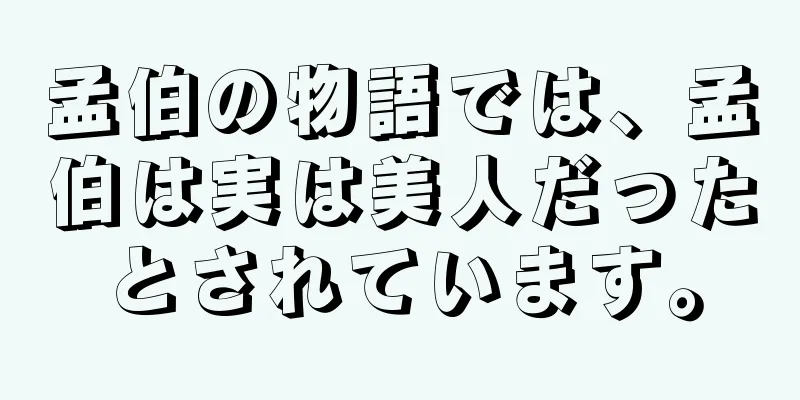後梁の君主呂傅とはどのような人物だったのでしょうか?歴史は呂傅をどのように評価しているのでしょうか?

|
呂祖(?-401)、号は雍緒、ディ族の人で、洛陽(現在の甘粛天水)の人。後梁の武夷帝呂光の長男、後梁の殷王呂紹の異母兄弟。母は趙叔源。十六国時代の後梁の君主。 龍安3年(399年)、父の呂光が重病にかかったため、呂占を太衛に任命し、6つの軍を率いて呂邵を助けた。呂邵が王位を継承して間もなく、呂占が王位を簒奪し、王位を咸寧と改めた。呂闕が王位を継承した後、弟の呂洪が反乱を起こした。呂洪は呂闕が派遣した実力者の康龍に敗れ、殺害された。その後、彼は軍隊を派遣して南涼を攻撃したが、南涼軍に敗れ、急いで撤退した。呂闕の治世中、呂闕は遠慮なく狩りに出かけ、酒と性行為にふけり、大臣たちの忠告を無視した。龍安5年(401年)、呂占は従兄弟の呂隆、呂超らによって殺害された。呂隆が即位すると、呂占を霊帝と名付け、白石廟に埋葬された。 歴史は呂祖をどのように評価しているのでしょうか? 魏寿、『魏書』:「彼は生来疑い深く、殺人をいとわない。」 方玄齢ら『晋書』:①「邵と祖は並の才能があったが、馬に乗って侵略者を率いた」;②「彼らは幼い頃から弓術と乗馬が得意で、鷹と犬が好きだった」;③「残は野を放浪し、酒と女にふける男だった」[26];④「残は愚かで残酷でわがままで、野を放浪し、酒と女にふける男だった」 『春秋十六国史記』:「彼は若い頃、弓術と乗馬が得意だったが、本は好きではなかった。」 |
推薦する
九尾の狐の伝説 九尾の狐の神話の起源と進化
九尾の狐は、中国の春秋戦国時代に編纂された『山海経』に登場する中国の神話上の生き物です。 『南山経』...
隋代における大運河掘削の賛否をどう見るか
大運河は紀元前605年、隋の時代に建設されました。隋の煬帝は当時の経済状況を利用して、南北を貫く運河...
「北西部に高層ビルがある」をどう理解すればよいでしょうか?創作の背景は何ですか?
北西部には高い建物がある匿名(漢代)北西には雲の高さまで届く高い建物があります。窓は絡み合って美しい...
斉の桀玉環王后の物語は何ですか?翡翠の指輪はついに解けたのか? ?
こんにちは、またお会いしました。今日は、Interesting Historyの編集者が斉の桀玉環王...
世界初の馬車を発明したのは誰ですか?
世界初の馬車を発明したのは誰でしょうか? 歴史の記録によると、馬車を発明したのは 4,000 年以上...
『紅楼夢』の薛叔母さんはなぜ北京に来てから賈邸に住むことを選んだのですか?
孤児の薛叔母さんと未亡人の母親は親戚と一緒に北京に来て、数年間、栄果マンションにある義兄の家で暮らし...
唐代の皇帝の皇后と側室の一覧
唐代の皇帝と皇后の一覧 - 唐代は世界的に中国で最も繁栄した時代の一つとして認められていますが、唐代...
劉迅と霍成軍の関係は本当ですか?劉迅は本当に霍成軍が好きなのか?
劉迅と霍成軍の関係は本当ですか? 劉迅は本当に霍成軍が好きですか?それはテレビシリーズで作られたもの...
龍門石窟の歴史的出来事: 龍門石窟ではどんな興味深い出来事が起こったのでしょうか?
石楼:武則天「香山で詩を書き、錦の衣を獲得する」 1300年以上前の唐の時代、武則天は洛陽で皇帝に即...
賈島の「友への遊び心のある贈り物」:この詩は唐代後期と五代詩人たちに大きな影響を与えた。
賈道(779年 - 843年)は、号を朗仙、別名を朗仙といい、唐代に河北省幽州樊陽(現在の河北省涛州...
閻書の「草を踏む:道はまばらに赤い」:この詩は作者の晩春の憂鬱について書かれている。
顔叔(991年 - 1055年2月27日)、号は同叔、福州臨川県江南西路(現在の江西省臨川市)の人。...
「農桑紀要」:養蚕:蚕の性質について(全文と翻訳注釈)
『農桑集要』は、中国の元代初期に農部が編纂した総合的な農業書である。この本は、智遠10年(1273年...
『紅楼夢』における賈歓と迎春の関係は何ですか?
栄果屋敷の三番目の若旦那である賈歓は賈正の庶子で、趙叔母の間に生まれ、賈丹春の同母兄弟である。次はI...
「女仙人の非公式歴史」第9章:正直な役人が飢餓救済の報酬を求めるが、貪欲な夫婦は去勢される
『女仙秘史』は、清代に陸雄が書いた中国語の長編歴史小説です。『石魂』や『明代女仙史』とも呼ばれていま...
袁浩文の名詩を鑑賞する:玄都寺には何千本もの桃の木があり、花は水に落ちて無駄に流れていく
袁浩文(1190年8月10日 - 1257年10月12日)、号は毓之、号は易山、通称は易山氏。彼は太...