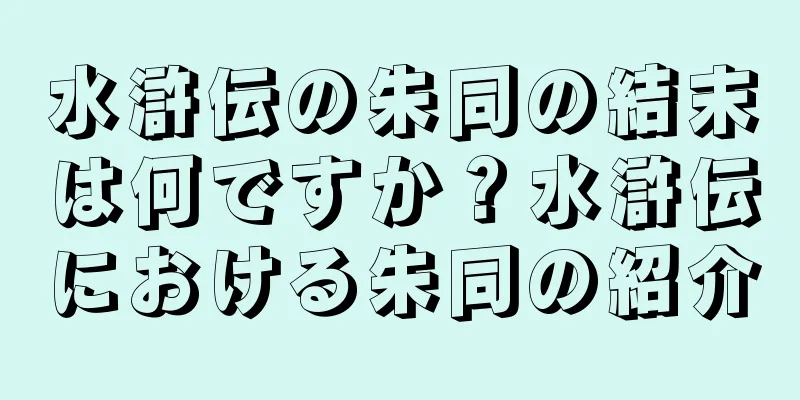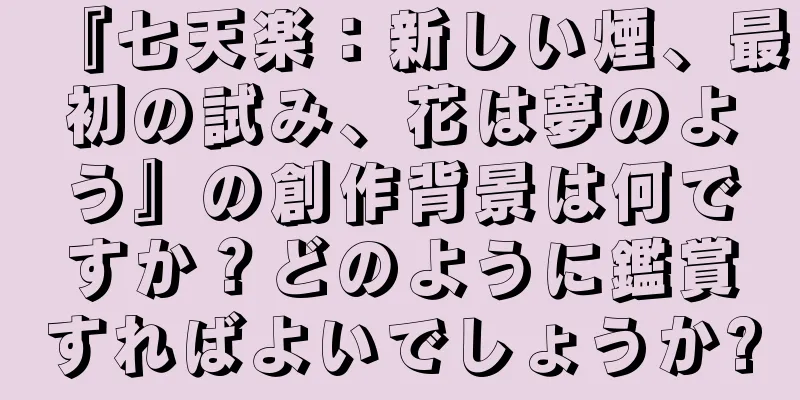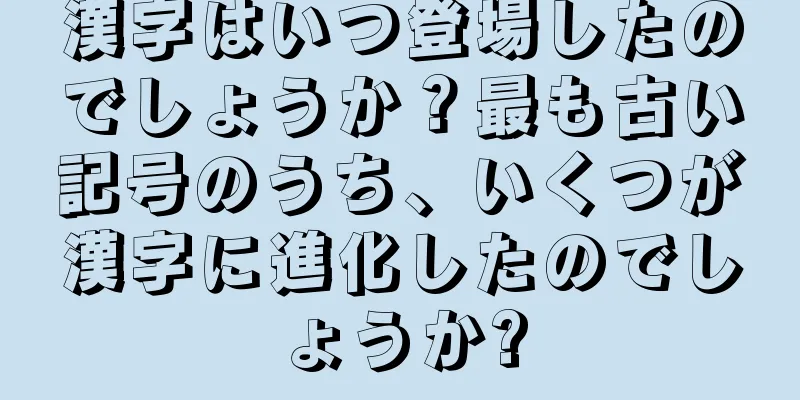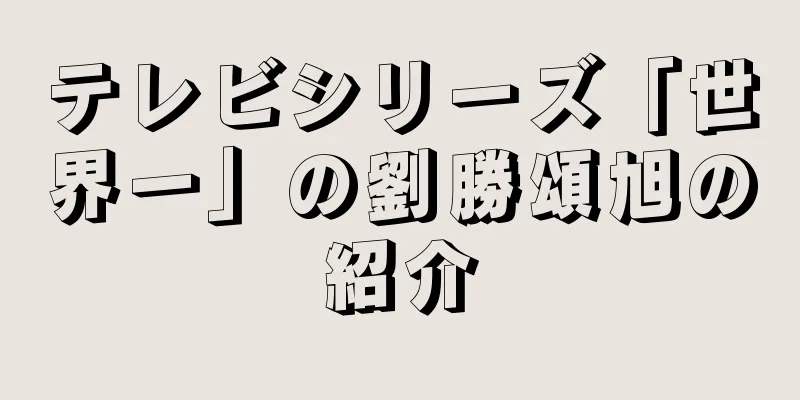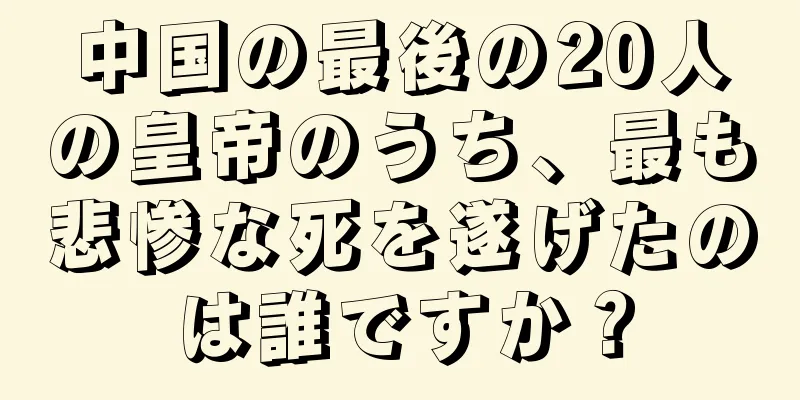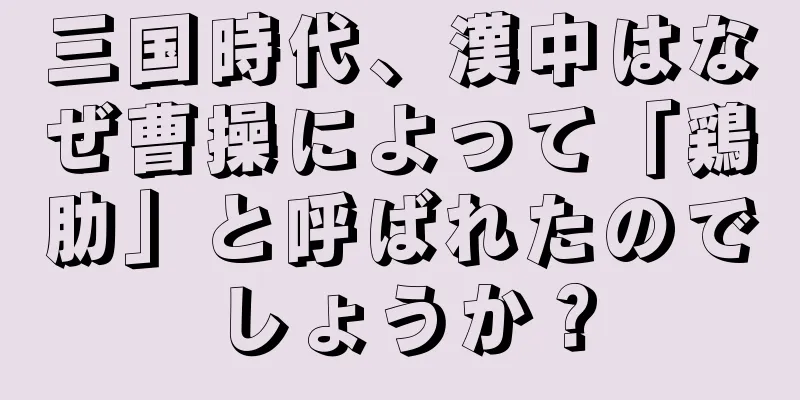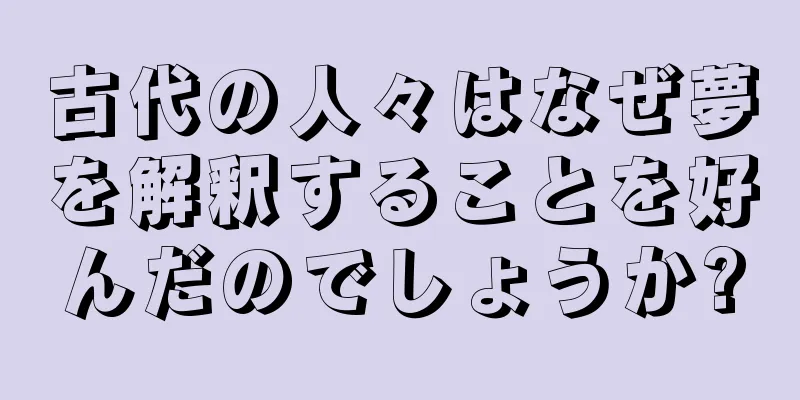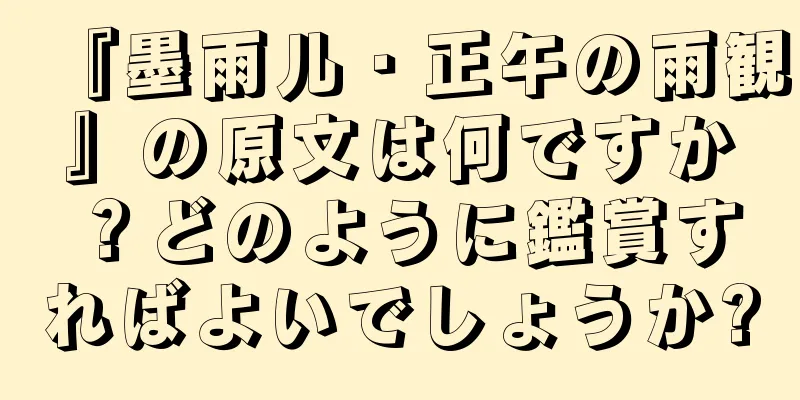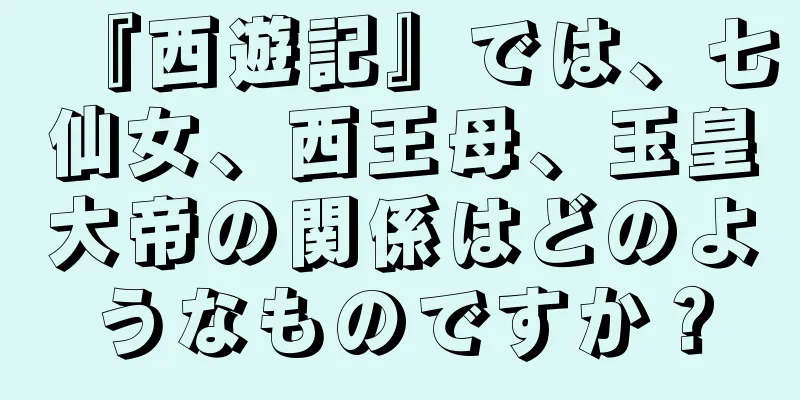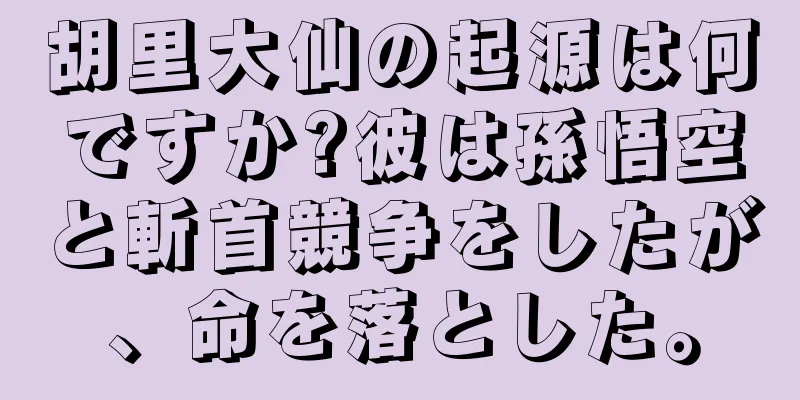詩における「中」の謎:2つの場所は音も意味も異なり、混同してはならない
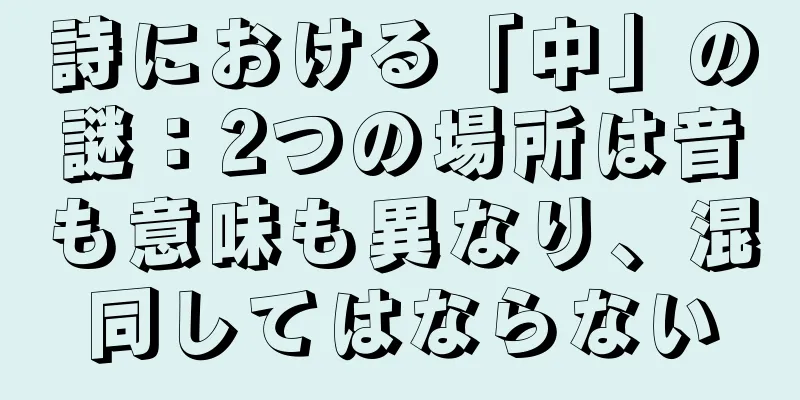
|
「处」には2つの発音があります。1つは「chǔ」で、住む、特定の場所にいる、配置するという意味です。もう1つは「chù」です。 「处」が「chù」と発音される場合、それは通常、方向を示す場所を意味します。しかし、古代の詩では、「chu」は方向だけでなく時間も示すため、「shi」と訳されています。 李白の『秋河歌』:「明鏡に映る秋の霜はどこから来たのか分からない。」 「どこ」は「いつ」を意味し、当然ながら、白い髪がいつ現れたかを意味し、白い髪がどこから来たかを意味するものではありません。 李白の『酒を飲んで何軒を思い出す』:「金亀を酒と交換した所で、ハンカチについた涙を今でも覚えている。」 「金亀を酒と交換した所」とは、金亀を酒と交換した時のことである。 韓愈の『早春』:「一年の春の一番良い時期は、帝都の至る所の柳や煙よりもずっと良い。」 「一年の春の一番良い時期」は明らかに時間、つまり一年の春の一番良い時期を指しています。 王維の『九月九日に山東の兄弟を偲ぶ』:「兄弟たちが山に登っているのは知っているが、ハナミズキの枝を身につけている人が一人少ない。」遠くから知られているのは山でも場所でもない、時間である。 「登高处」は「高く登る時間」と翻訳されるべきであり、「高く登る場所」と翻訳することはできません。 汪婉の『北姑山の隣』:「海の日は昨夜昇り、河の泉は旧年に入る。故郷からの手紙はどこに届くか?帰ってきた雁は洛陽の端にいる。」 「故郷からの手紙はどこに届くか?」とは、故郷からの手紙がどこに届くかではなく、故郷からの手紙がいつ届くかを意味します。 五代の牛希季は『生茶子』の中で「私は緑の絹のスカートを思い出すと、いたるところに香る草が哀れに思う」と書いている。「いたるところに香る草が哀れに思う」とは、よく香る草を哀れに思うという意味であり、いたるところに香る草が哀れに思うという意味ではない。 蘇軾の『江城子・生死十年共に曖昧』には、「私の心が毎年砕ける場所は、月夜の低い松の丘だと私は思う。」とあります。「私の心が毎年砕ける場所」とは、毎年心が砕け散る時期を意味します。 劉勇の『鐘の中の雨』:「蘭の船は、去りがたい時に出発を促す。」 「蘭の船は、去りがたい時に出発を促す」とは、去りがたい時を意味します。 「Chu」は「場所」ではなく「時間」を意味します。 上記の例だけを見ても、古代の詩では「处」は chù と発音され、ほとんどの場合は場所を示していますが、時間を示す場合も多く、一般化することはできません。現代中国語の「chuchu」は「あらゆる場所」を意味し、方向のみを示します。したがって、古代の意味を現代の意味と解釈するのは簡単です。 孟浩然の有名な詩「春暁」には、「春を眠り過ごし、明け方に鳥のさえずりがあちこちから聞こえてくる」とあります。「鳥のさえずりがあちこちから聞こえる」とは、鳥の鳴き声があちこちから聞こえるという意味だと考える人が多いでしょう。実際、正しい説明は、時々鳥のさえずりが聞こえるということでしょう。 詩人は「夜の風と雨の音」が眠りを妨げたため「夜明けを感じなかった」。彼は夜よく眠れず、早めに昼寝をしたかったのですが、至る所で鳥の鳴き声が聞こえたのでできませんでした。鳥の鳴き声のせいで、早くぐっすり眠れなかったのです。 「鳥のさえずりを聞く」は「聞く」という意味です。 「花は何本散っただろうか?」というのは詩人の推測であり、詩人は目覚めたにもかかわらず、外出も起き上がってもいないことを意味している。このとき、窓の外の世界は視覚ではなく聴覚によって認識されます。外に出たことがない人にとって、鳴いている鳥があちこちに散らばっているのか、それとも一本の木に集中しているのかを「匂い」だけで判別するのは難しい。詩人は「鳥の鳴き声」を時々聞いただけで、「鳥の鳴き声」の分布を知らなかったため、「どこでも鳥の鳴き声が聞こえる」の「どこでも」は「どこでも」ではなく「時々」と解釈されるべきである。 「鳥の声がどこでも聞こえる」というのは、実際には鳥の鳴き声が無限にあるという意味です。 春の風景を楽しみたがっていた詩人は、「夜」と「風雨」のせいで春に浸ることができなかった。夜が明け、風も雨も止みましたが、眠気が襲ってきました。昼寝をするべきか、それとも春を見に出かけるべきか?詩人はジレンマに陥っている。 「もう少し寝なさい」と鳥たちは絶え間なくさえずり、「もう少し横になりなさい」とさえずり続けた。 春の音で鳥のさえずりが詩人をからかい、「花は何本散っただろう」と思わせ、彼は我慢できなかった。 「春の夜明け」は、春を眺めたり感謝したりするのではなく、詩人が春に誘惑され、その誘惑に抵抗できない様子を描いています。 その後、孟浩然は外に出て春の懐に身を投じたに違いないが、詩は終わっており、彼はそれ以上詩を書かなかった。春を讃える詩は数多くありますが、そのほとんどは春を直接描写したものです。孟浩然は春を聞き、春を思うことだけを書いたので、他の人より一歩先を進んでいます。 「至る所で鳥のさえずりが聞こえる」を、一般的な理解に従って「至る所で鳥のさえずりが聞こえる」と解釈し、単に聞くという説明を、聞くことと見ることの包括的な組み合わせに変換すると、それは詩人が家の外の泉に入るのと同じであり、一般的な決まり文句に戻り、より直接的になり、繊細さが失われます。 |
推薦する
「心臓の火星」は単なる天文現象ですが、なぜ古代の皇帝たちはそれをそれほど恐れたのでしょうか?
古代中国では、多くの王朝に天文学や占星術を学ぶ場所がありました。皇帝の目には、空の星が幸運や不運を予...
馬千斎の『柳英曲・世を嘆く』:詩人の現実に対する不満を明らかにする
馬千寨と張克久は同時代人で、お互いに知り合いだった。彼の詩の多くは『公三句』『太平楽譜』などの詩集に...
唐の玄宗皇帝は国を統治する上でどのような文化的施策を講じましたか?儒教を広めるために大量の書籍を集める
唐の玄宗皇帝は、少なくとも治世の初期においては、間違いなく唐代における優れた皇帝であった。彼は文化の...
軍事著作「百戦百策」第七巻 火戦 全文と翻訳注
『百戦奇略』(原題『百戦奇法』)は、主に戦闘の原理と方法について論じた古代の軍事理論書であり、宋代以...
印章の彫刻はほんの一部に過ぎません。古代において「印章彫刻」と呼べるものは他に何があるでしょうか?
篆刻(じゅりょう)とは、書道(主に篆書)と彫刻(彫刻や鋳造を含む)を組み合わせて印章を作る芸術であり...
国民の真髄とは何か?中国の真髄とは何でしょうか?
中国文化の真髄とは何でしょうか?中国文化の真髄とは何でしょうか?Interesting Histor...
唐代の農業と養蚕を奨励する政策とは何でしたか?今日の「田舎へ行く三人」は過去を生かして現在に役立てます!
唐代に農民に農業や養蚕を奨励した政策とはどのようなものだったのでしょうか?今日の「三度田舎を訪ねて」...
明朝の孝宗皇帝は生涯でたった一人の女性としか関係がなかった。これは彼の悲惨な幼少時代とどのような関係があるのだろうか?
皇帝といえば、私たち庶民が真っ先に思い浮かべるのは、間違いなく国家の最高権力者であり、最高レベルの享...
『紅楼夢』では、青文は追い出されているのに、なぜまだ銀の腕輪をはめているのでしょうか?
『紅楼夢』では、青文は追い出されているのに、なぜまだ銀の腕輪をはめているのでしょうか。『興史』の編集...
李玉の周皇后追悼文:「新たな恩恵に感謝 秦楼に笛を吹く少女はいない」
以下、Interesting Historyの編集者が、Li Yuの「新恩恵に感謝:秦楼に笛の娘なし...
『新世界物語』第二話「方正篇」はどのような真実を表現しているのでしょうか?
『十碩心于』は南宋時代の作家劉易清が書いた文学小説集です。では、『十碩心於・方正篇・第二』に表現され...
蘇軾が弟に宛てて書いた詩。読むと深い感動を覚える。
古詩が我が国の優れた伝統文化の代表であることは誰もが知っていますが、大学を出て職場に入ると、ほとんど...
清風誌第31章:官営メディアは強を逮捕し、非刑事審査の後に有罪判決を下した
『清風帖』は清代の溥麟が書いた長編民話小説です。この本は32章から成り、物語の展開に応じて3部に分け...
古典文学の傑作『太平楽』:居留部第5巻全文
『太平百科事典』は宋代の有名な百科事典で、北宋の李芳、李牧、徐玄などの学者が皇帝の命を受けて編纂した...
夜華はどうやって白浅が蘇蘇だと知ったのですか?夜華は蘇蘇が好きですか?
これは、夜華の番外編の最後の段落の最後の文で述べられていた。白浅が人に教えるときの口調や仕草は蘇蘇と...