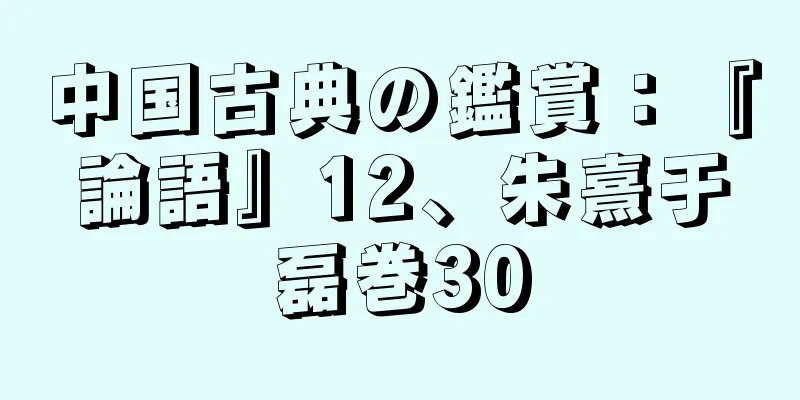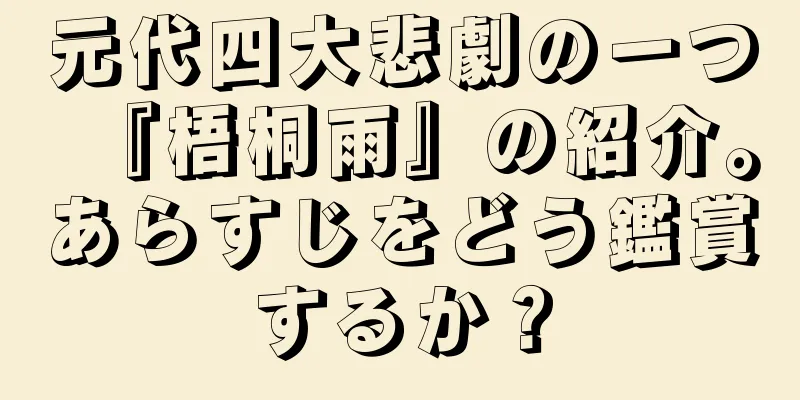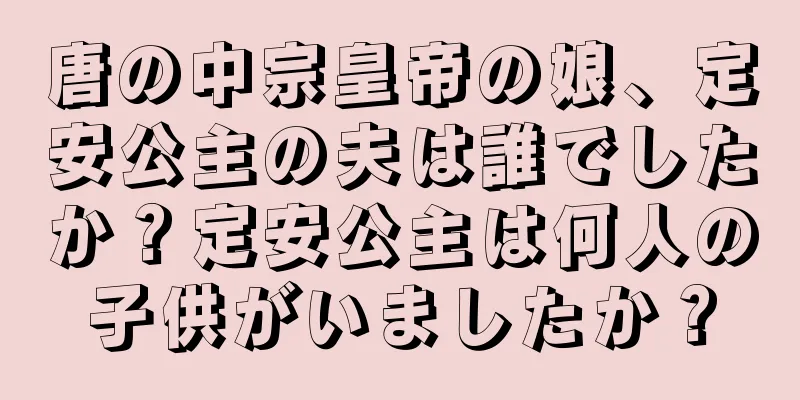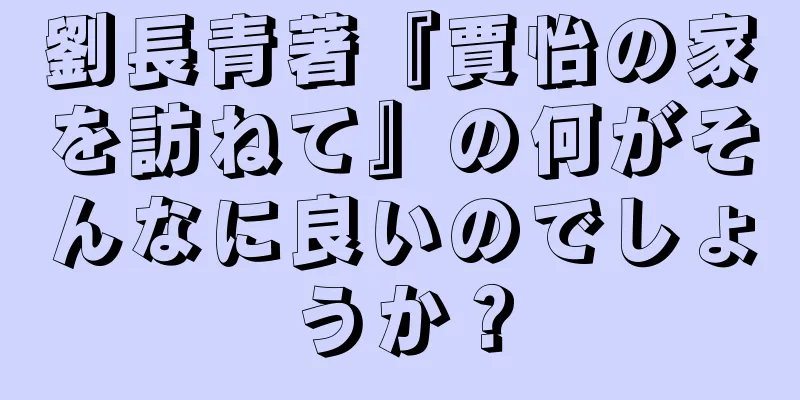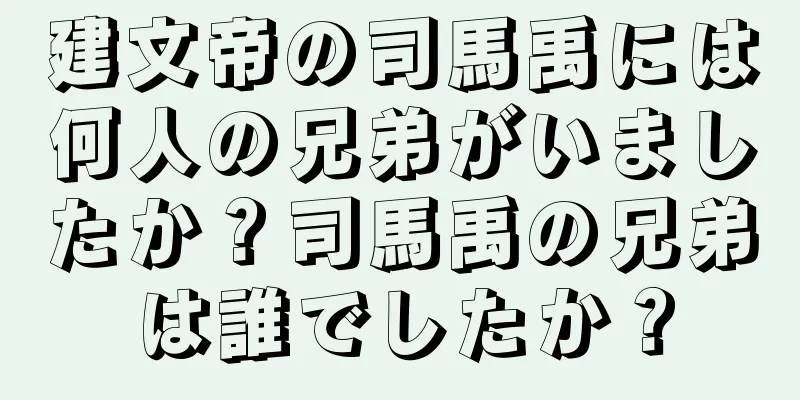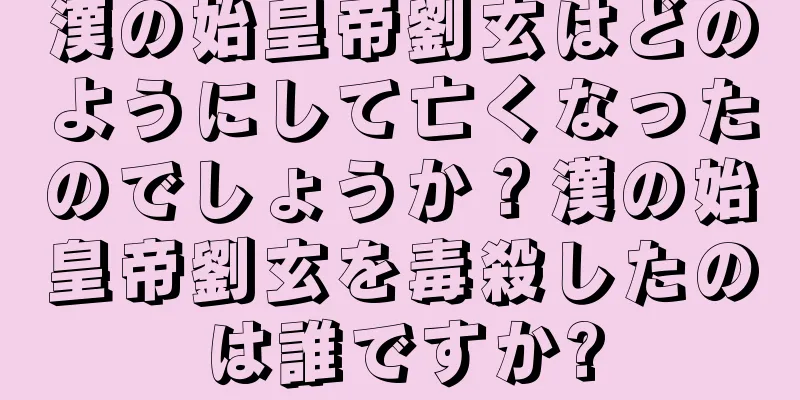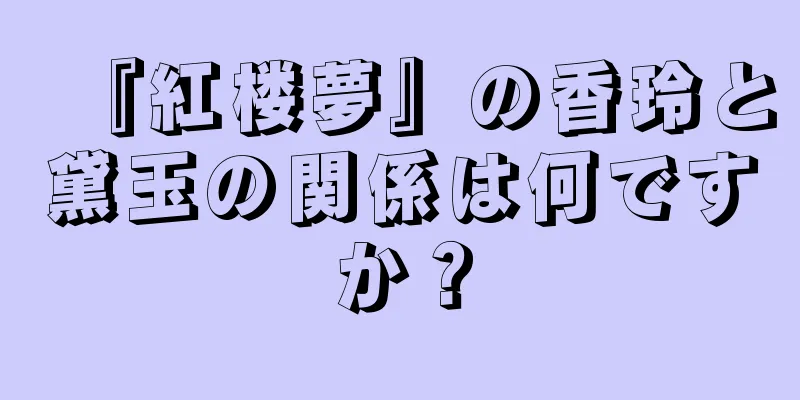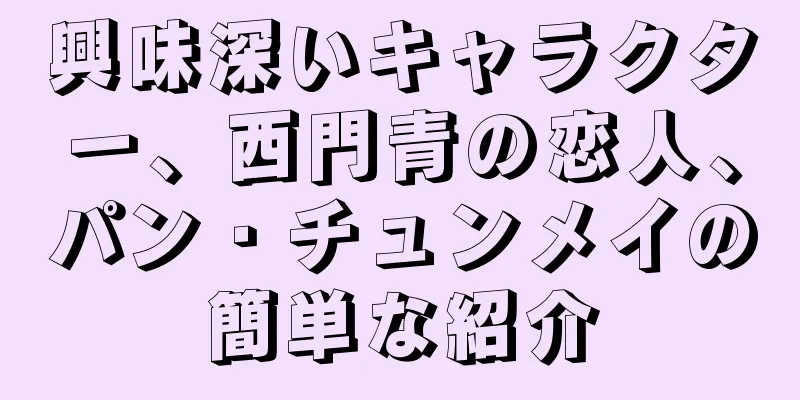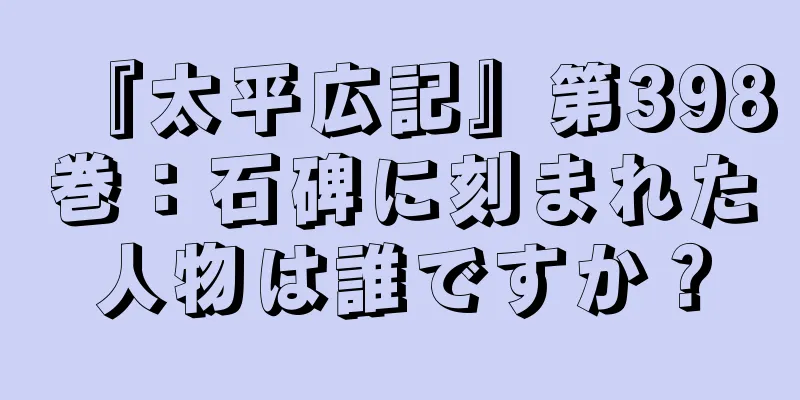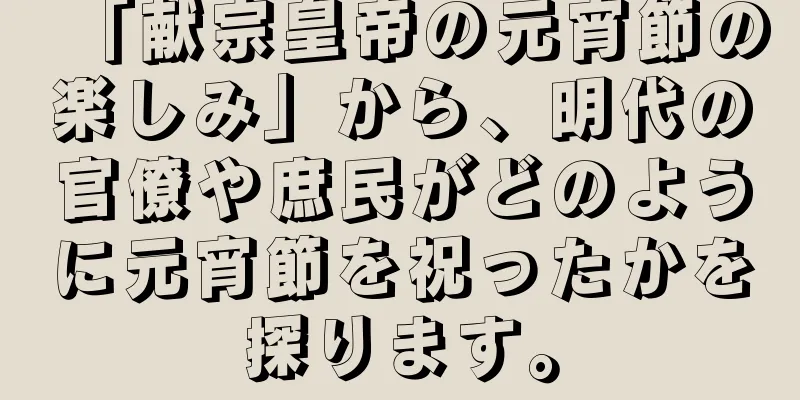タン・シトンの『自殺詩』における二つの大きな歴史的言及
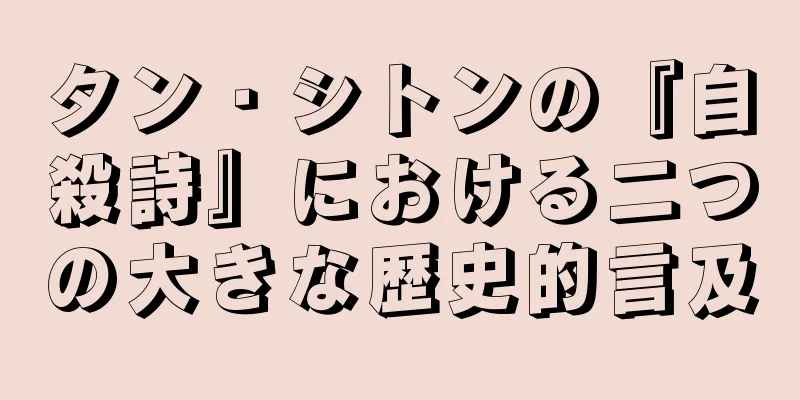
|
タン・シトンの「刑務所の壁に書かれた文字」 泊まる場所を探すとき、私は張堅のことを思い、杜根を待つために一瞬の死を耐えます。 私は剣を手に持ち、空に向かって笑う。私が留まるかどうかにかかわらず、私の忠誠心と勇気は崑崙山脈に残るだろう。 これは、処刑前に譚思童が獄壁に書いた自殺詩だと言われている。また、この詩は梁啓超によって「改ざん」されたとも言われている。 元の詩はこうだ。「門を見ると張建に同情し、陳叔を直接批判した杜根に恥じ入る。西洋刀を投げて天に笑い、後世に自分の罪を裁かせる。」 証拠が不十分であり、受け入れるのが困難です。 「泊まる場所を探してドアを見ると、張建を思い出す」この文章は張建の物語を指しています。 『後漢書』の記録によると、張建は後漢末期の高平の人であり、当初は東山陽郡の監察官であった。彼は宦官の后蘭とその家族の悪行を厳しく弾劾し、学徒たちから尊敬されていた。その後、党派による迫害が再び起こり、彼は逃亡を余儀なくされた。人々は彼の人格を尊敬し、家族や一族を滅ぼす危険を冒して彼を迎え入れた。 「泊まる人を探す」とは、誰かの家に行って一晩泊まるように頼むことです。張建が逃亡中、彼を引き取ったために多くの人が処刑され、「郡は滅びた」ことさえありました。どうして彼はこんなことを我慢できたのでしょう。「私は一瞬死に耐えて杜根を待った」この文章は杜根の物語を指しています。 『後漢書・杜根伝』によると、杜根は清廉な性格で、後漢安帝の時代に医師を務めた。当時は鄧太后が摂政を務め、権力は外戚が握っていた。安帝が年老いたとき、杜根は皇太后に手紙を書いて、権力を返還するよう求めました。皇太后は激怒し、民に彼を袋に入れて叩き殺すよう命じました。警察官は死刑執行人に慈悲を示し、目を覚ますまで彼を街の外に連れ出すよう合図した。太后は人を遣わして調べさせ、杜根は3日間死んだふりをしました。目にウジがわきましたが、幸運にも逃げ出し、15年間隠れていました。鄧太后が亡くなった後、杜根は権力を回復し、皇帝の検閲官に任命されました。譚思童は詩の中でこの二人の歴史上の人物の体験について触れているが、彼自身は彼らのような逃亡の道は選ばず、死を無関心で迎える英雄的な精神を示している。彼は逃亡して他人に迷惑をかけることを望まず、一時的に死を免れるために法執行官の慈悲に頼ることもできなかった。彼は処刑場に行き、「剣を手に持ち、空に向かって笑う」という正義のやり方で処刑されることを望んだ。 「剣を手に持ち、天に向かって笑う」と勇敢に死ぬ覚悟の心意気を示した。 実際、譚思童は監獄車に閉じ込められ、処刑のため北京の菜市口に連行された。彼には剣を天に掲げるしか選択肢がなかった。彼には大きな野望があったが、他に選択肢はなかったのだ。 「留まっても去っても、忠誠と勇気は二つの崑崙山のように残る」という一文については、歴史を通じてさまざまな解釈がなされてきました。梁啓超は『銀冰詩談』の中で、「二つの崑崙」とは康有為と大刀の王武のことだと述べている。後に、康有為を唐才昌と置き換える者もおり、唐才昌は譚思童の親友で、崑崙山のように堅固だと信じていた。また、当時譚思童と親しい関係にあった胡斉と王武という二人の騎士のことだと信じる者もおり、彼らの武術は崑崙流に属していたためだ。また、「崑崙」を「崑崙の奴隷」と理解し、彼らが譚思童の二人の召使だと信じていた者もおり、実は譚思童自身を指しているという者もいる。 「行くか残るか」は生死を意味する。季康の『ピアノ譜』には「運命を天に任せて、留まるか行くか」という一節があり、陶淵明の『帰郷』には「なぜ心を任せて留まるか行くか」という一節がある。生死に関係なく、人は誇り高い中国人である。「行くか残るか」は「行く」と「残る」の対比ではなく、何かを残すことを意味する連体構造であると考える人もいる。…すべての人を殺そうとする敵に直面して、一部の人々は自分自身を犠牲にし、血なまぐさい犠牲を払って大衆に知らせ、生き残った世代と将来の世代に長期的な闘争を続けるよう促す必要がある。 「玄元に我が血を捧げる」(魯迅の詩の一節)譚思童のやり方は、自らの血を使って世界に警告を発しようとしたため、おそらく「血の捧げ物」と呼べるだろう。 「他国の政治改革はすべて流血によって成し遂げられた。しかし、今の中国では政治改革による流血は起きていない。これが我が国が繁栄していない理由だ。もしあるなら、後継者から始めてください」。彼は血をもって誓いを果たした。 タン・シトンと1898年の改革運動 譚思同(1865-1898)は、号を伏生、号を荘非といい、湖南省瀏陽の人であり、北京で生まれた。湖北省知事の三男である。1898年の改革運動以前は、江蘇省の代理知事を務めていた。 12歳の時、北京で大疫病に感染し、3日3晩昏睡状態になったが、ようやく生き返ったため、「傅勝」という名前を名乗ったという。この疫病で、彼の母親、兄、妹は皆亡くなりました。後に台湾で亡くなったのは、彼の次兄である譚思祥であった。タン・シトンが処刑された後、彼の妻は自分自身を「Yusheng」と名付けました。これは「一瞬死を耐え、デュゲンを待つ」ことを意味します。彼女は彼を嘆くために詩を書きました。 Tan Sitongの以前の住居では、Tan Sitowの前で、The Wiepが泣きます。詩「刑務所の壁に書く」。譚思童の内面を解読することは決してできないかもしれないが、この詩「獄中壁の碑文」は何百年もの間、私たちの深い思考を呼び起こし続けている。この詩からは殉教者たちの畏敬の念を起こさせる正義感と冷静さが感じられます。 彼らは信仰と追求した大義のためなら、喜んで命を犠牲にしました。彼らの精神は、まさに未来の世代に刺激を与えることができます。この詩を読むと、自然と譚思童という人物を理解しなければならなくなり、彼が参加した1898年の改革運動の背景に興味を持つようになります。ところで、少し話がそれますが、詩とその作者の背景について語るとき、当然、さまざまな歴史的記録が絡んできます。それが正史であれ、非正史であれ、どれも完全に真実ではないことは明らかです。私たちは、真実に近い、より信憑性が高いと思われる記述を選ぶように努めているとしか言えません。情報のほとんどは、常に二次情報源から来ています。たとえそれが元の歴史資料からコピーされたものであったとしても、実際には、他の人がそれを引用しているのを見て、それを手がかりにして一次歴史書を検証することが多いのです。時には、非常に説得力のあるように聞こえる間接的な情報を見たときに、それに同意するか、面倒になって元の記録を一つ一つ確認しないことがあります。そのため、不明確な「盗作」論争が起こっているのです。 この記事を書く前に、私は李敖の『北京法源寺』を何度も読み、知識と思考の両面で大きな影響を受けました。 1898 年の改革運動は、わずか 103 日間しか続かなかったため、「百日改革」とも呼ばれています。改革運動はグレゴリオ暦の1898年6月11日に正式に始まりました。 この日、光緒帝は「国是を明ずる勅」を発布し、改革自強を宣言し(『清徳宗実録』第418巻)、その後、一連の改革を強力に推進し、古いものを一掃し、新しいものを取り入れました。当時、西太后は名目上は光緒帝に「権力を返還」していたものの、実際には秘密裏に実権を握っていた。わずか4日後の6月14日、西太后は光緒帝の師である翁同和を追い出し、腹心の栄禄を直隷総督と北洋大臣に任命した。その後、「皇帝派」と「皇后派」が公然と、また密かに争い、皇太后がクーデターを起こして光緒帝を追放しようとする気配さえあった。改革派は死活問題に直面していた。 9月18日の夜、譚思同は新設軍を統率していた袁世凱が協力してくれることを期待して、袁世凱と密かに会談した。袁世凱は表面上は譚思同の計画に同意したが、譚思同が去るとすぐにそのことを栄禄に報告した。容禄は西太后の側近であり、頤和園に住んでいた西太后はすぐに真実を知った。 9月20日の早朝、康有為さんは天津行きの列車に乗り込んだ。彼が去った直後、政府軍は南海会館で彼の弟の康光仁を捕らえた。逃げることに成功した康有為はイギリス軍の助けを借りて上海へ逃げた。同時に、梁啓超は日本大使館に保護された。 9月21日、西太后が正式に政権を掌握し、光緒帝は自宅軟禁となり、103日間の改革運動は終結した。五劫八月十日、梁啓超は日本軍に護送されて北京から連れ出され、譚思童は清の官吏と軍隊によって瀏陽会堂に連行された。 3日後の9月28日、旧暦8月13日(中秋節の2日前)、譚思同、楊神秀、楊睿、林旭、劉光迪、康光仁の「六君子」は菜市口の処刑場に連行され、裁判もなしに斬首された。処刑前の譚思童は寛容というよりはむしろ冷静だったと言われている。動揺や恐怖、後悔の念は見せなかった。処刑人に「早く死なせてくれ」と懇願する気さえなかったかもしれない。沈黙を切り裂く声を発しただけだった。「泥棒を殺したいが、状況を救うために何もできない。いい死に方をする。なんて幸せなんだ!」誰も理解できないのは、殺されるはずのこの「泥棒」が誰なのか、そしてなぜ「いい死に方」をしたのかということだ。 鄭士曲編著『中国近代史』の「詩革命」論では、譚思童の詩「獄中壁銘」について次のように評されている。「この詩は、この急進的な改革主義者の自己犠牲の精神と高潔な性格を十分に示している。」この詩に関しては、情熱と寛大さ、悲劇的な静けさ、そして無力感と期待とともに、作者の願望を反映している。暗示は適切で、詩は一気に書かれており、人々の心を動かす力を持っています。命は貴重ですが、信仰はもっと貴重です。この世で最も大切にしているのは死であるが、彼は死を大切にする方法を知らなかった。これはタン・シトンの愚かさを如実に表している。実際、執着心とは、流血や犠牲を恐れないほどの信念への固執の一種です。今日、私たちはそのような悲劇的な方法で命を犠牲にする必要はないかもしれませんが、後悔することなく信仰を貫くこの精神には、畏敬の念を抱かずにはいられません。崑崙の正義が天と地の間に永遠に残りますように。 |
>>: 必ず読むべき唐五代の詩10選:春の花と秋の月はいつ終わるのか?
推薦する
宋代において火薬はどのような軍事用途に使われたのでしょうか?宋代にはどんな火薬兵器がありましたか?
火薬兵器は宋代に急速に発展した。 『宋史記・軍記』によると、西暦970年、軍官の馮継勝がロケット法を...
李白の詩「秋浦桃花の昔を思い出す、夜朗に逃げる時」の本来の意味を理解する
古詩:「野朗にいた頃の秋浦桃花公園への昔の旅を思い出す」時代: 唐代著者: 李白湧き水に桃の花が咲き...
『清代名人逸話』第4巻の主なストーリーは何ですか?
◎添付:唐文正氏から徐世寨氏への偽の手紙の説明唐文正公が呉を平定していたとき、家臣を解散させて、再び...
『淮中都頭泊』の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
淮中夜係留杜頭著者: 蘇順琴春の太陽が緑の草を照らし、時には花の木が鮮やかに咲きます。私は夜、古代寺...
コールドフードフェスティバルとは? 寒食節は歴史的にどこから来たのでしょうか?
寒食節の紹介:寒食節は「禁煙節」「寒節」「百五節」とも呼ばれ、旧暦の冬至の105日後、清明節の1~2...
なぜ朱同は13位の陸智深や14位の武松よりも上位にランクされているのでしょうか?
『水滸伝』は中国史上初の農民反乱をテーマとした章立ての小説である。作者は元代末期から明代初期の史乃安...
劉表が劉備に荊州を譲るよう提案したとき、劉備はなぜ拒否したのですか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
秦と楚の間にはどんな恨みやしがらみがあるのでしょうか? 「楚に三家あっても、楚が秦を滅ぼす」と言われているのはなぜでしょうか?
秦と楚の間にはどんな恨みやもつれがあったのか?「楚に三家あっても、楚が秦を滅ぼす」と言われるのはなぜ...
梁宇勝の武侠小説に登場する有名な人物で、「毒手狂乞食」の異名を持つ金世易の簡単な紹介
梁玉生の武侠小説に登場する有名な人物。通称「毒手狂乞食」。彼が行くところはどこでも、醜い民衆を怖がら...
「農桑紀要」:養蚕:蚕の性質について(全文と翻訳注釈)
『農桑集要』は、中国の元代初期に農部が編纂した総合的な農業書である。この本は、智遠10年(1273年...
王安石が書いた「あなたは信じ難い」は、捨てられた女性についての、分かりやすく、それでいて心に残る詩です。
王安石は、号を潔夫、号を半山といい、北宋時代の政治家、改革者、作家、思想家であった。彼は文学において...
千奇の有名な詩句を鑑賞する:空と海は遠く、死の船は軽い
銭麒(722?-780)、号は中文、呉興(現在の浙江省湖州市)出身の漢人で、唐代の詩人。偉大な書家懐...
『易堅易志』第12巻の主な内容は何ですか?
鎮州僧侶ジアンの2年目は、西田の職員に任命されました僧kは、彼女が彼に見たものをすべて与えていました...
蜀漢にとって、漢中はどのような点で荊州よりもはるかに戦略的に重要なのでしょうか?
「漢中の戦い」といえば、皆さんもよくご存知だと思います。これは、後漢末期から三国時代にかけて、劉備と...
七剣十三英雄第132章:政府軍は火の攻撃で敗北し、邪悪な道士たちは悪の陣形を組んでその力を誇示した
『七剣士十三勇士』は、『七子十三命』とも呼ばれ、清代の作家唐雲州が書いた侠道小説である。清代末期の侠...