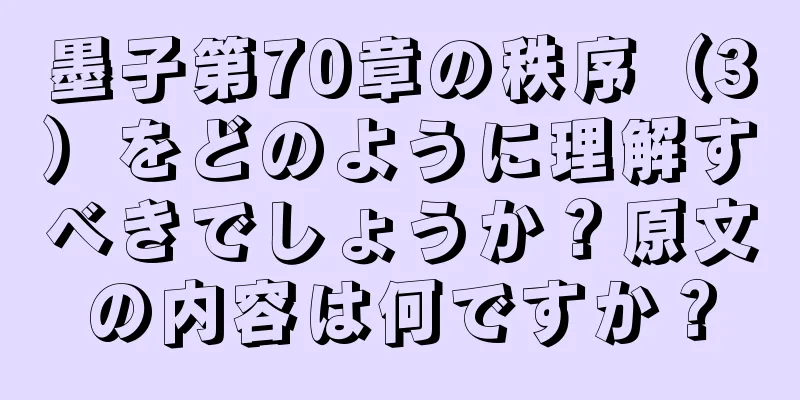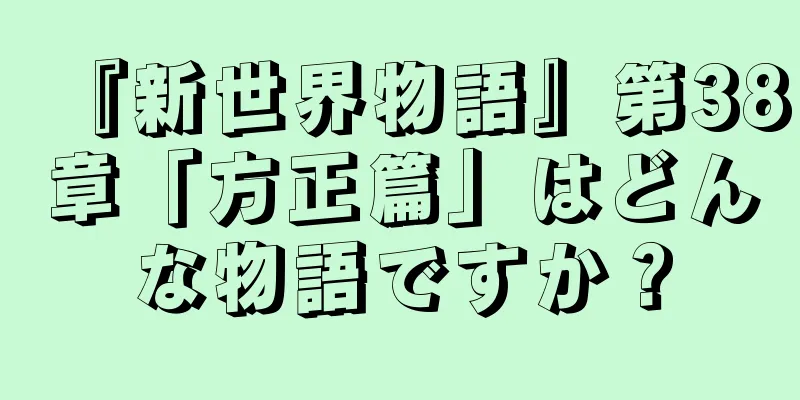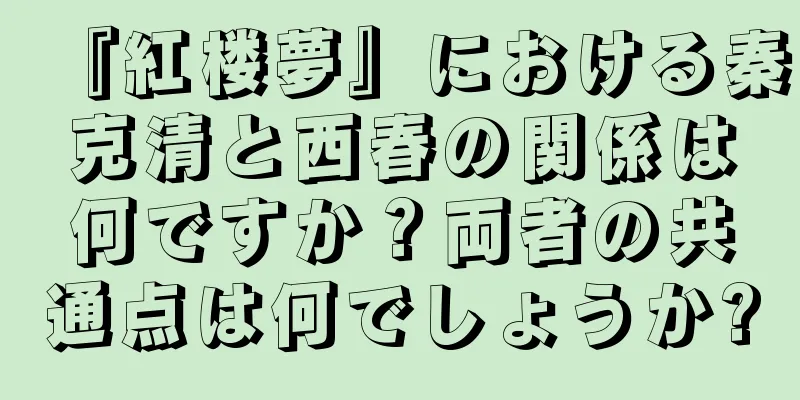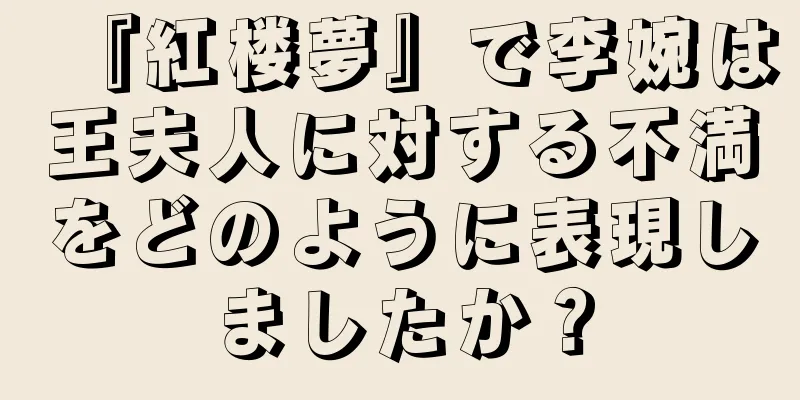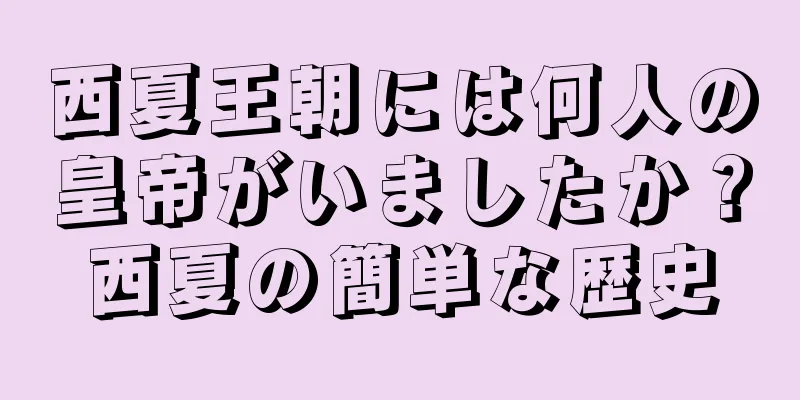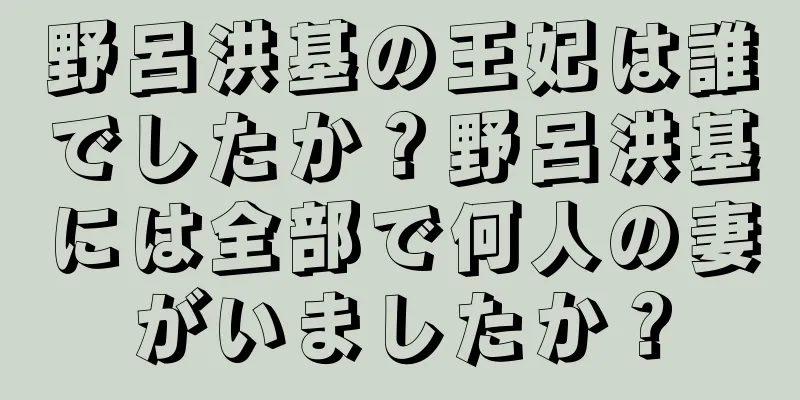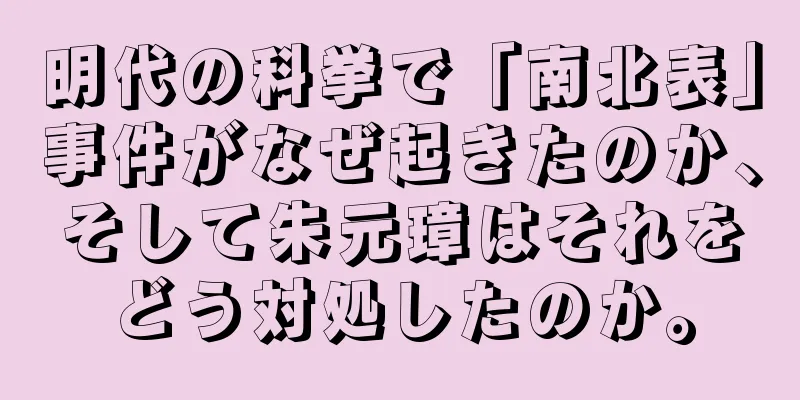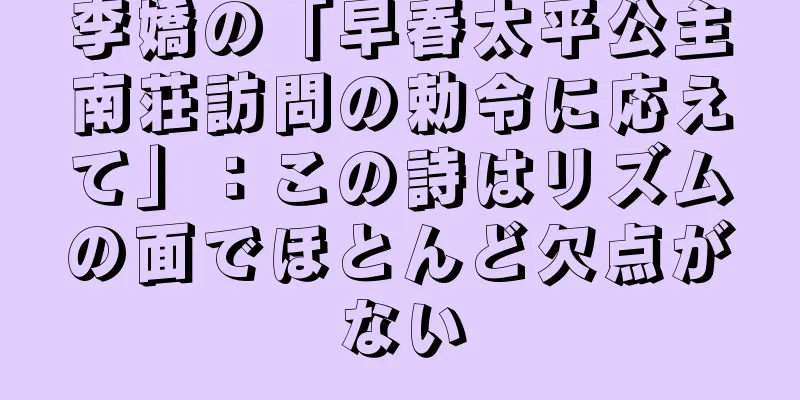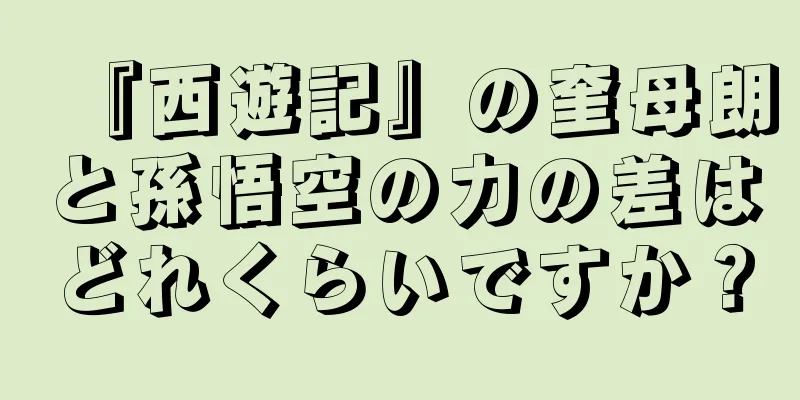「15歳で軍隊に入った」という詩をどのように評価すべきでしょうか?この詩の本来の内容は何ですか?
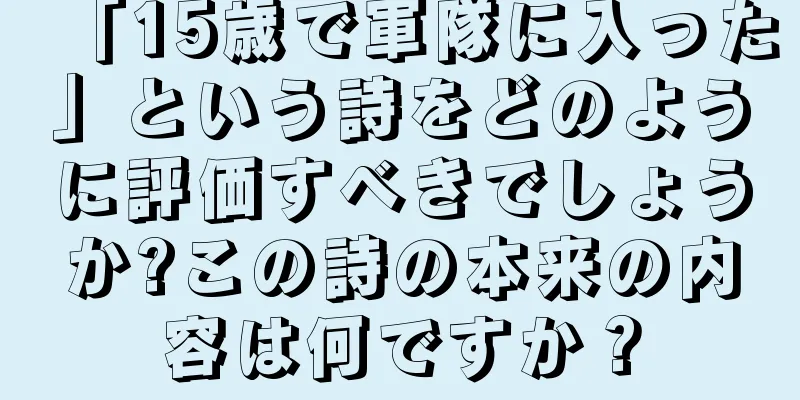
|
15歳で入隊[漢代] 匿名さん、次の興味深い歴史編集者が詳しい紹介を持ってきますので、見てみましょう! 彼は15歳で軍隊に入隊し、80歳で帰国した。 道で村人に会ったとき、彼の家族は誰だったでしょうか? 遠くから見ると、あなたの家が見えます。そこにはたくさんの松やヒノキの木、そして墓があります。 (「Yaokan」の別名は「Yaowan」) ウサギは犬の穴から入り、キジは梁から飛び立ちます。 中庭にはユリが咲いていて、井戸にはヒマワリが咲いています。 穀物を搗いて米を作り、ひまわりを摘んでスープを作ります。 スープとご飯は出来上がりましたが、誰に渡せばいいのか分かりません。 私は外に出て東を眺めると、涙で服が濡れてしまいました。 これは、「若くして家を出て、老いて帰る」老兵の帰郷の道中と帰郷後の情景を描いた物語詩である。老兵の心情を表わすとともに、当時の社会情勢を反映しており、典型的な意義を持っている。冒頭は異例だ。「15歳で軍隊に入り、80歳で帰国した。」この2つの文章は、老兵が「15歳」で軍隊に入り、「80歳」で帰国したことをそのまま述べている。何気なく言ったように平凡で普通に聞こえるが、実は考えさせられる内容で、素晴らしい技巧が光っている。彼は15歳で軍隊に入隊したが、この詩では彼がどこに行ったのかは説明されていない。また、彼の軍隊生活がどのようなものであったか、戦況がどのようなものであったかについても説明されていない。これにより、読者の想像力に大きく余地が残されます。しかし、一つだけはっきりしているのは、彼が戦争のために「軍隊に入隊」し、何十年もの間不在だったということです。「80」と「15」の対比は、彼が「軍隊に入隊」していた期間の長さを強調しています。「ようやく復帰できた」は「軍隊に入隊」と響き、途中で復帰できなかったことを示しています。 「十五歳で入隊」は漢代の民謡で、封建社会の不合理な兵役制度を暴露し、当時の暗黒の兵役制度下における労働者階級の不当性と苦しみを反映している。この作品は、現実的で、深遠で、腹立たしく、そして涙を誘う作品です。 「道で村人に会って、『家には誰がいるの?』と聞いた。」主人公の思考は、65年間の戦争から広大な荒野と長い古い道へと移り変わる。親族の故郷の現状についての彼の考えは、漠然とした想像から不安な探究へと変わり、知りたいと思いながらも、知るのが怖い。詩の最初の2行で広げられた読者の想像力の翼も、主人公の不安な質問で締めくくられている。 「誰が家にいるのか」という質問は、仕事の焦点である家庭を浮き彫りにします。あれから65年が経ちました。家族が無事で、親戚がまだ生きているとどうして期待できるでしょうか。1人か2人の生存者がいれば、それは不幸中の幸いでしょう。そこで彼は、家族の中で他に誰が幸運にも生きているのかと尋ねた。しかし、その「田舎者」の答えは、まるで雪の中に氷水を注いだようなものだった。「遠くからあなたの家が見えます。松や糸杉の木がたくさんあり、墓もあります。」この激動の時代、私の親戚は誰一人生き残れなかったのか。長年心に秘めてきた気持ちを打ち明け、打ち明けられる人は誰なのか。そこにあるのはあの緑の松や糸杉と墓だけなのか。それが私の家なのか。いやいや、そんなわけない! 彼の目の前の現実は、「ウサギは犬の穴から飛び込み、キジは梁から飛び立ち、中庭には野生のガチョウが育ち、井戸にはヒマワリが育っている」というものでした。遠くから見ることから近くから見るまで、彼の目にはさらに荒涼とした悲惨な光景が浮かびました。作者は、部屋が空っぽだとは言わず、人を見て家を見つけたと思って家畜小屋に忍び込む野ウサギや、怖がって飛び去ったキジが安全だと思って家の中の梁に止まる場面を捉えている。作者は、庭が荒れ果てて乱雑だと直接は書いておらず、井戸のそばと中庭に無造作に生えているヒマワリと穀物の2つの「ショット」を捉えているだけだ。空っぽの家と荒れ果てた庭は、さらに生々しく、二重に悲痛である。旅の疲れを癒した老人が、かつては火が燃え、庭もきれいに整えられた「家」の前に立つ。65年間待ち望んでいた家だが、親戚の誰も迎えてくれない。想像していたよりも10倍も100倍も耐え難い状況…。これは一体どんな状況で、読者にどんな感情の波を巻き起こすのだろうか。 「外に出て東を見たら、涙で服が濡れた。」彼は何年も放置されていた荒れ果てたドアから出て、東の方角を見た。おそらくまだ希望を抱いていたのだろう。彼は誰を見たのだろう?何を見たのだろう?長い間会っていなかった親戚を見たのだろうか?あるいは何も見なかったのかもしれない。彼はぼんやりと幻想から抜け出し、静かに泣いた。「涙が服を濡らした」という5つの言葉には、このように豊かで深く、そして痛ましい感情的含意が詰まっている。主人公とその家族の相互反省的な物語は、作品のテーマと芸術的レベルを新たな高みに押し上げた。65年間も兵役に就いた男は、実は家族の中で唯一の生存者だ。兵役に就いていない親族の墓は、青々とした松やヒノキで覆われている。彼らの生前の貧しく惨めな生活は、いつ犠牲になるかわからない兵士たちの生活に及ばないことは想像に難くない。この作品は、65年間国のために戦ったが帰郷できず、帰郷したときには家を失った主人公の不幸な経験と辛い気持ちを具体的に描いている。生きざるを得ず、静かで湿った冷たい墓に入るしかない親族に比べれば、彼の不幸は「幸運」である。この作品は、封建的な兵役制度の暗黒と邪悪を暴露し、80歳の老人の不幸を描いただけではなく、当時の社会実態全体の暗黒を反映し、個人の不幸よりもさらに深く広い、人民全体の不幸、社会の衰退、時代の混乱を描いています。 詩の最後の2行では、老兵の行動を描写することで、老兵の悲しみをさらに表現しています。ここでは、老兵が東方を見に出かける(「東方を見に出かけた」)ことや、涙を流す(「涙が落ちて服を濡らした」)ことなどが強調されており、身寄りもなく孤独な老兵の姿が鮮明に描かれ、悲しみや戸惑いが生々しく表現されている。想像してみてほしい。彼は「15歳で軍隊に入り、80歳で帰国した」。家には親戚は誰も残っておらず、ただ荒涼とした風景があるだけだった。悲しくないわけがない。これからの人生はどうなるのだろう。混乱しないわけがない。遠くを見つめながら、祖国にはこんな家族は自分だけだろうかと考えていた。いや、違う。この詩では誰が彼の悲劇的な運命を引き起こしたのかは明確に述べられていないが、この詩の歴史的背景を考えれば、それがわかるのは難しくない。呉靖の『古月譜要』によれば、この詩は晋代の月譜に収録されており、漢魏の戦乱期に書かれた作品とみなすことができます。当時の好戦的な統治者と終わりのない戦争が、この退役軍人の悲劇的な運命を引き起こした。老兵の悲惨な体験を映し出すと同時に、当時、強制労働という厳しい抑圧を受けていた民間人の悲惨な体験も映し出し、当時の暗い社会実態を深く浮き彫りにしている。 この詩の構成は巧妙かつ自然で、老兵の帰国体験と感情の変化を中心にしています。帰宅時の彼の体験は、ようやく帰宅できる→帰宅途中→帰宅→「外に出て東を見る」であり、感情の変化は、家に帰りたくて不安、「家には誰がいるのか」を知りたくて不安、家族との再会に期待でいっぱい(帰宅途中)→希望が打ち砕かれる→完全に失望(帰宅、景色は荒涼としていて誰もいない)→悲しくて泣く、混乱する(「外に出て東を見る」)である。これらは、暗い社会現実を表現し暴露する詩のテーマに集約されます。詩全体は平易な文体で場面や人物を描写しており、明確な層と平易な言葉で表現されている。悲しい場面で悲しい感情を表現しており、誠実で心のこもった、非常に特徴的な詩である。また、場面に基づいて感情を表現する漢代の民謡の芸術的特徴も反映している。 |
<<: 「山に登り蓬を摘む」という詩をどのように評価すればよいのでしょうか。この詩の本来の内容は何ですか?
>>: 「Yousi」という詩をどのように鑑賞すればよいのでしょうか?この詩の本来の内容は何ですか?
推薦する
『紅楼夢』で宝玉が病気になった後、黛玉に関係する何かが起こったのですか?
林黛玉は、中国の有名な古典『紅楼夢』のヒロインであり、金陵十二美女の第一人者です。これは、今日『興味...
なぜ崇禎が魏忠賢を殺さなかったとしても、明王朝は滅びたと言われるのでしょうか?
1644年、清朝が北京を占領し、明王朝は滅ぼされました。魏忠賢が殺されなければ国は滅びなかったかもし...
長安は西周の首都の設立にどのような影響を与えましたか?西周時代の長安の愛称は何でしたか?
長安は首都として長い歴史を持っています。西周の時代には、周の文王が長安を首都に定めました。ただ、当時...
昔の人も爆竹を鳴らしていたんですね!中国の爆竹は秦以前の時代の「爆竹供儀」の活動に由来する
今年の春節では、PM2.5が大気環境に与える影響を考慮して、花火の打ち上げを減らす、あるいはまったく...
元代の女流詩人、鄭雲端の詩十首を振り返ると、彼女の詩の特徴は何でしょうか。
鄭雲端(ていうんどあん)、号は鄭書(じょうしょ)で、呉中平江の出身で、元代の有名な女性詩人である。彼...
「紅楼夢」の薛叔母さんの偽りのお世辞は賈祖母に一目で見抜かれた
『紅楼夢』の薛おばさんの嘘のお世辞は賈おばあさんに一目で見抜かれ、直接からかわれ、馮お姉さんもじっと...
王維の古詩「春が何遂元外の薬園を通り過ぎる」の本来の意味を鑑賞
古代詩「春が何遂元外の薬園を通り過ぎる」時代: 唐代著者 王維一昨年、ハイビスカスのフェンスが新しい...
高平陵の変の際、10万人の軍勢を率いた夏侯玄はなぜ抵抗を放棄したのか?
嘉平元年(249年)1月、魏の曹芳皇帝は洛陽を出発し、魏の明皇帝高平陵(現在の洛陽市如陽県大安郷公如...
『紅楼夢』の玉川はどんな人物ですか?玉川の性格特性
『紅楼夢』の玉川はどんな人物ですか? 『紅楼夢』の登場人物。姓は白、名は玉川。金川の妹で王夫人の侍女...
唐の玄宗皇帝の娘、楚公主についての簡単な紹介。楚公主の妃は誰だったのでしょうか?
唐の玄宗皇帝李龍基の娘、楚公主(?-?)、母親は不明。王女は最初、寿春公主と名付けられました。王女は...
趙高と呂不韋はどちらもかつては非常に強力でした。呂不韋はなぜ秦の始皇帝を殺せなかったのでしょうか?
歴史上、皇帝に忠誠を誓った少数の者を除いて、権力者のほとんどは悪意を持っていました。たとえ最初は皇帝...
『紅楼夢』で賈夫人はなぜ孫家に迎春をいじめさせるのですか?理由は何でしょう
賈祖母は曹雪芹の『紅楼夢』の登場人物です。多くの人が理解していないので、Interesting Hi...
宋代における社会扶助とはどのようなものだったのでしょうか?宋の太祖はどのようにしてそれを実現したのでしょうか?
人々の生活は今、ますます良くなっています。食べ物、衣服、住居、交通はすべて保証されています。さらに、...
結局、大勝した司馬家以外に諸葛亮の一族はどうなったのでしょうか?
三国時代の歴史には多くの豪族が存在した。三国時代初期には、袁紹の袁家が間違いなく最強だったと言われて...
古代の恋愛物語の一つ:なぜ梁洪と孟光はお互いを対等に扱ったのでしょうか?
中国の古代史には、人々をあこがれる伝説的な恋愛物語が数多くあります。古代の書物や古典の記述では、愛は...