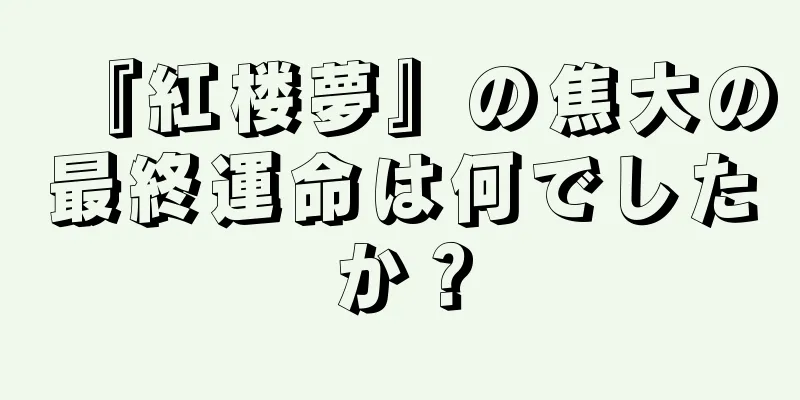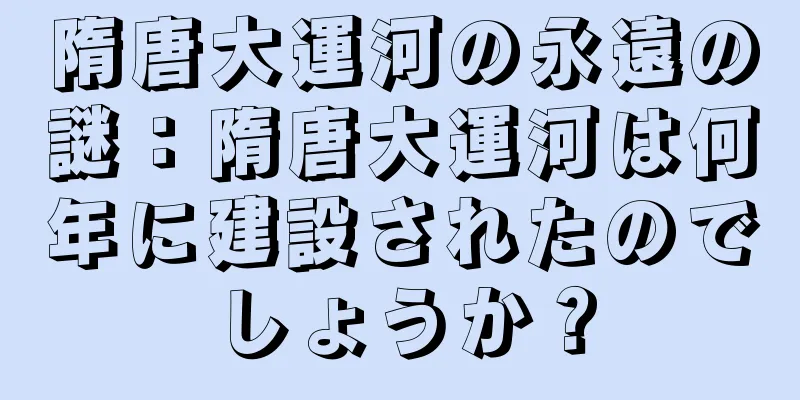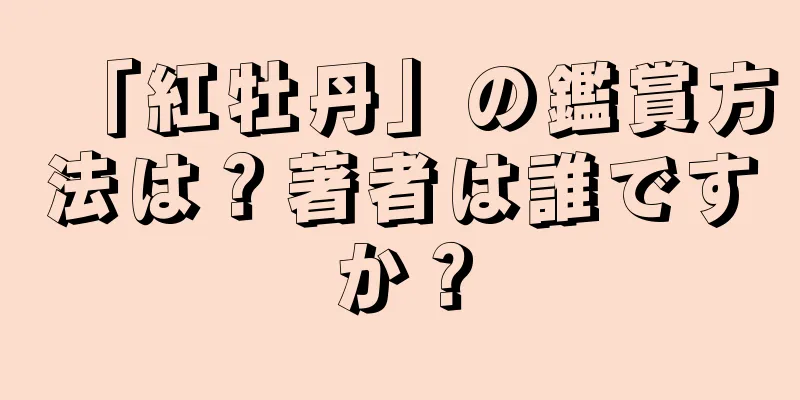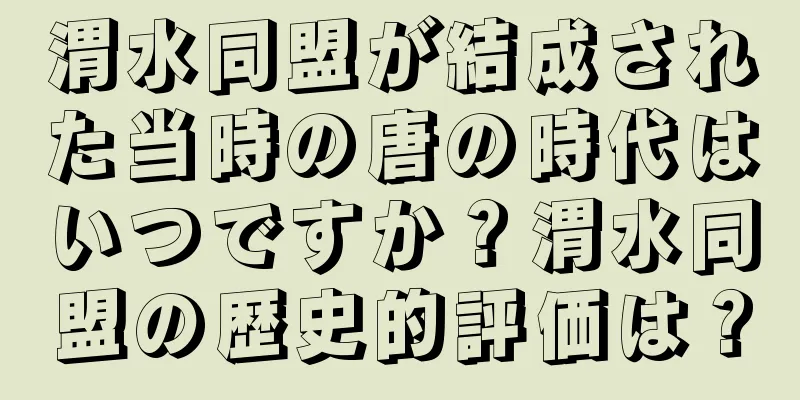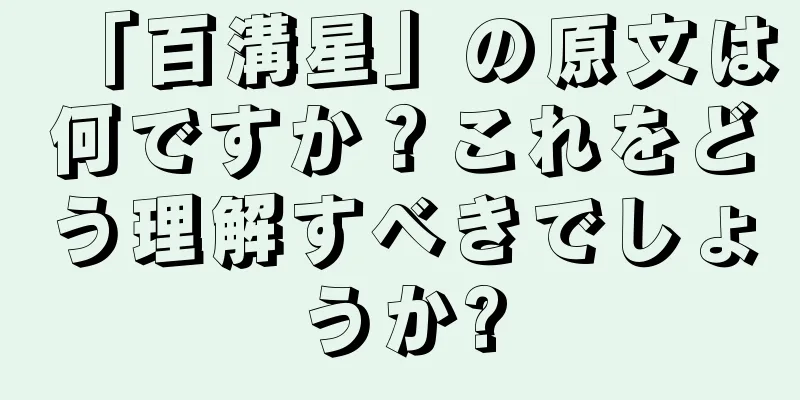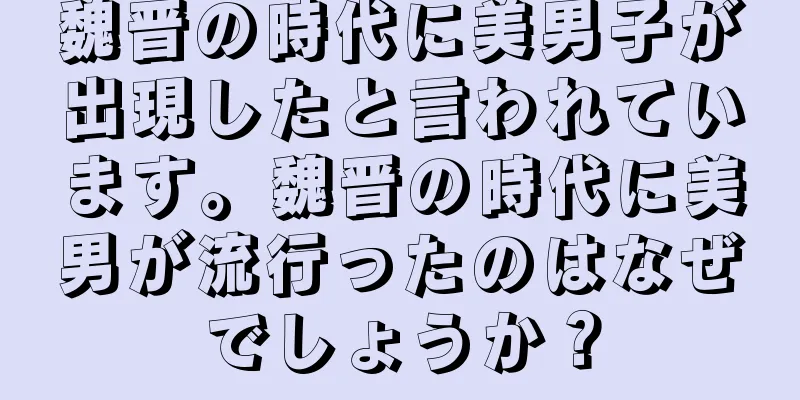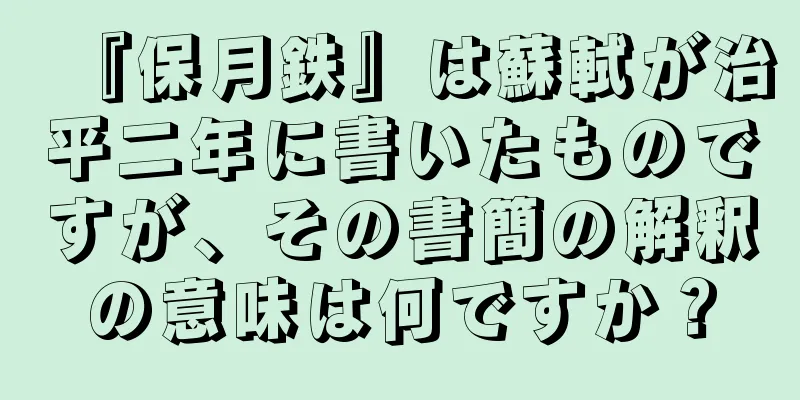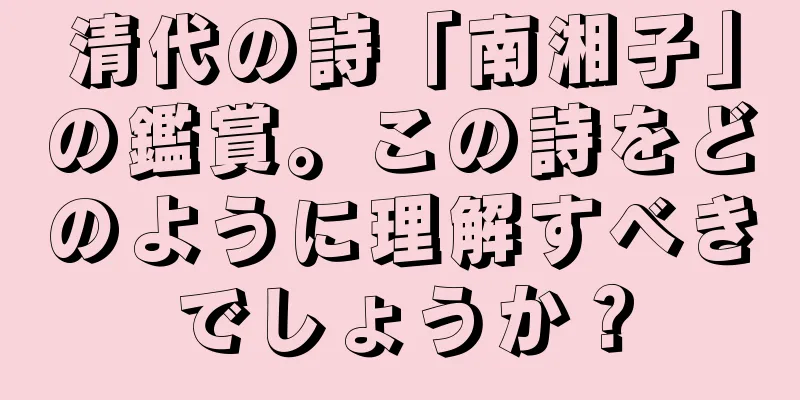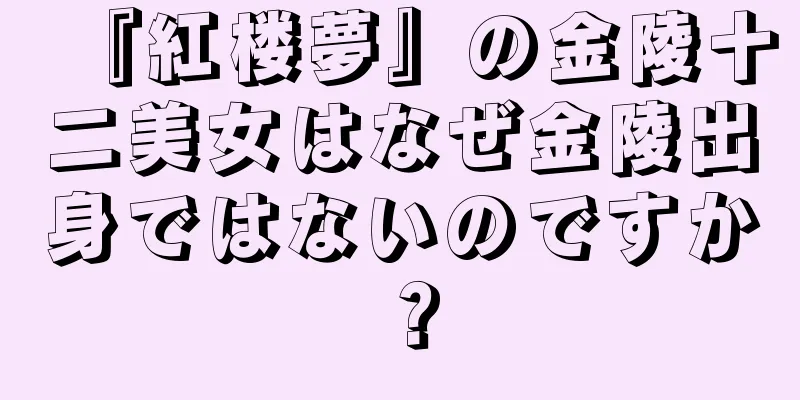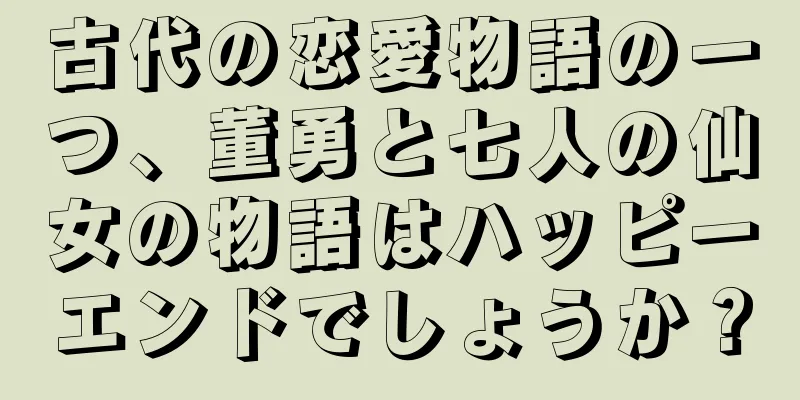「清明」を書いた詩人は誰ですか?この詩の本来の意味は何ですか?
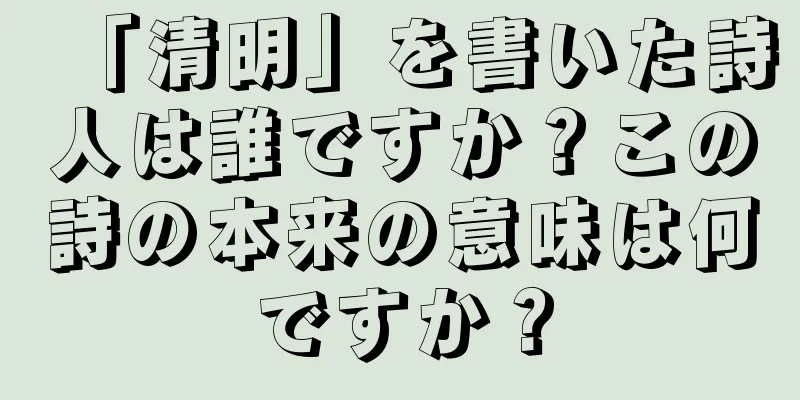
|
清明 【唐代 - 杜牧】 清明節には大雨が降ります。 道を歩いている人々は悲嘆に暮れています。 居酒屋はどこにありますか? 羊飼いの少年は遠くの星華村を指さした。 清明節は二十四節気の5番目の節気です。清明節に祖先を祀り、墓を掃くことは、今日まで受け継がれてきた中国の伝統的な風習です。 古代人は家族や氏族に対する強い意識を持っていました。なぜなら、古代人は、人が家族に溶け込み、家族に受け入れられて初めて本当の人間とみなされると信じていたからです。家族を失った人は、実際には生き残る余地がなく、死後もさまよう幽霊となってしまいます。したがって、古代人にとって家族は非常に重要でした。 このように、清明節に先祖の墓を掃除することは、古代人の生活において非常に重要な部分となりました。 先祖の墓を掃除することは、先祖の記憶を思い出し、大切にする方法であり、人々の過去への感謝の表現です。家族や一族が一緒にこのような活動に参加すると、家族間の感情が高まり、家族の結束が強まります。 しかし、このとき詩人は家から遠く離れた道を一人で旅しており、そのような家族や一族の活動に参加することは許されていませんでした。さらに悪いことに、霧雨まで降ってきました。それで、私はとても気分が落ち込み、機嫌が悪くなり、まるで魂を失っているかのような気分になりました。 どうすればいい?当分の間は酒で悲しみを紛らわすしかない。したがって、この詩の最後の 2 行には、尽きることのない意味が込められています。 杜牧(803年 - 852年頃)は唐代の詩人で、李商隠とともに「小李杜」と呼ばれた。雅号は穆之、号は樊川居士。荊昭萬年(現在の陝西省西安市)の出身。杜牧は七字四行詩の名手であった。この詩は4行28語から成り、濃密で遠慮のない文体で書かれている。しかし、この詩の中の「洪水」、「途中」、「尋ねる」、「羊飼いの少年」という言葉をすべて削除して、5文字の四行詩に変えれば、より簡潔になると言う人もいます。実際、これによって単語数は節約されますが、無限の詩的な感覚も減少します。 「浮遊」は清明の雨の特徴を表し、「路上」は歩行者の切迫感を表し、「借用質問」は質問者の礼儀作法を表し、「羊飼いの少年」は実際の状況を表しています。4つが重なり合って、複数の詩的な意味を生み出します。どのように簡素化できますか? 古代の詩の書き方は、四字熟語から七字熟語へと進化し、一般的に言えば、シンプルで自然なものから優雅で美しいものへと進化しました。ここには芸術の追求が必然的に存在します。杜牧の時代には、七字四行詩は真の傑作となり、杜牧はこの傑作を歌い上げる優れた人物でした。この曲「清明」もこの最高の歌手の最高の曲の一つです。この観点からすると、「清明」を五字詩に変えたほうが良いと考える人は、実は「芸術的共感覚」を欠いている人です。 |
<<: 古代詩「山行」の執筆背景は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
>>: 「田舎の四季雑感」の原文は何ですか?この詩をどのように評価すべきでしょうか?
推薦する
『三朝北孟慧編』第212巻はどんな物語を語っているのでしょうか?
延行第二巻は112巻あります。それは紹興12年庚武8月14日に始まり、嘉寿12月16日に終わります。...
南北朝時代、北方の戦場では、斉火軍のような軍隊が活躍していたのでしょうか?
「乞食」という言葉と「生きる」という言葉から、その時代の難民全員の悲惨さと不幸を読み取ることができま...
「四川に友を送る」の原文は何ですか?どうやって翻訳するのでしょうか?
友人を四川省に送る李白(唐)カンコンへの道は険しくて通行が難しいと聞きました。山は人の顔から立ち上が...
なぜ劉表は英雄の一人としてふさわしくなく、曹操らと天下を争うことはできなかったと言われているのでしょうか?
三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代...
グリーンピオニーの完全な物語第16章:邪悪な西門双瓜頭の不当な殺害
『青牡丹全話』は清代に書かれた長編の侠道小説で、『紅壁元』、『四王亭全話』、『龍潭宝羅奇書』、『青牡...
琉球と沖縄は同じ場所ですか?沖縄と琉球の関係は?
現在の日本の沖縄県は、沖縄島、宮古島、八重山島の3つの島を中心に、大小140以上の島々で構成されてい...
スリングショット:子供の頃に遊んだおもちゃには、こんなに深い由来があったんですね!
スリングは、石を投げるときにその威力と射程距離を増大させるために使われる道具です。パチンコの作り方は...
オーディン:北欧神話の神々の父
神々の父、オーディン(古ノルド語:Óðinn、ドイツ語:Wotan、古英語/アングロサクソン語:Wō...
トゥチャ族の建築には独特のトゥチャ族の家屋がある
トゥ族のほとんどは山岳地帯に住んでおり、自然条件がより良い河川地域に住んでいるのはごくわずかです。ト...
「あなたへの憧れ:山を越える旅」の原文は何ですか?これをどう理解すべきでしょうか?
あなたへの憧れ:山を巡る旅那蘭興徳(清朝)山と川を越え、玉門峠に向かう旅。夜には何千ものテントが灯り...
明代初期の名将、康茂才とはどのような人物だったのでしょうか?歴史は康茂才をどのように評価しているのでしょうか?
康茂才(1313-1370)、号は寿清、斉県(現在の湖北省斉春市)の出身で、明代初期の有名な将軍でし...
トン族の花火と大砲祭りを訪れて、その起源と習慣を探ってみましょう。
ドン族の花火大会は、ドン族の最も賑やかな祭りであり、数百年の歴史があります。トン族には、花火と花火祭...
「歓喜沙・漁師」が作られた背景は何ですか?どのように鑑賞すればよいでしょうか?
環西沙·漁師蘇軾(宋代)西葦山のそばを白鷺が飛び、三花州の外には小さな帆が見える。桃の花、流れる水、...
水滸伝における李俊の功績は何ですか?彼はどのようにして宋江と知り合ったのですか?
水滸伝における李俊の功績は何ですか?李軍は『水滸伝』の登場人物で、渾江龍というあだ名で呼ばれ、瀘州の...
有名な哲学書『荘子』雑集:世界(5)原文と方言訳
『荘子』は『南華経』とも呼ばれ、戦国時代後期に荘子とその弟子たちが著した道教の教義をまとめた書物です...